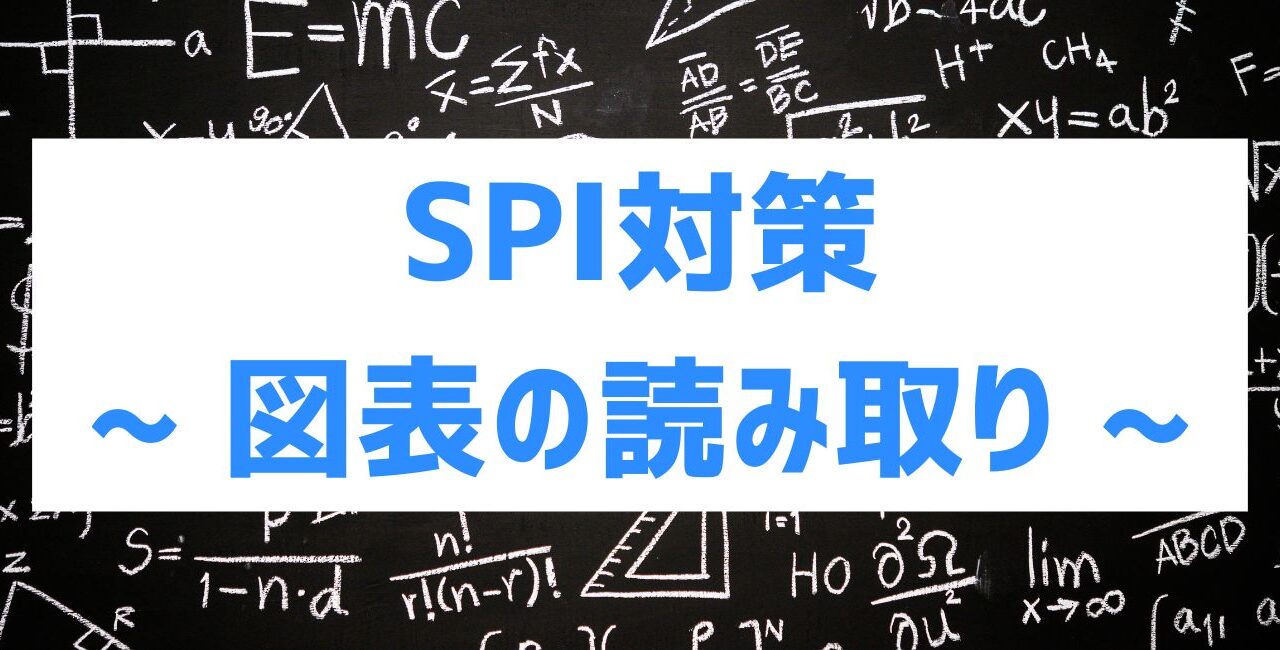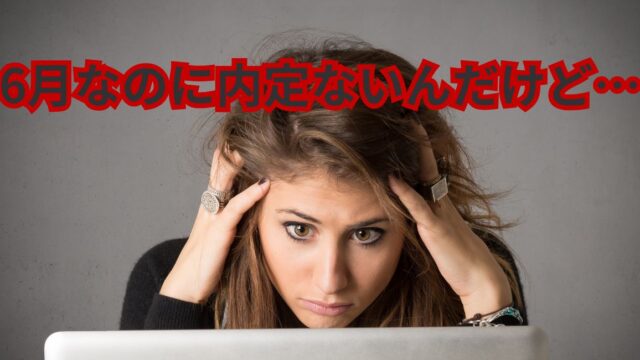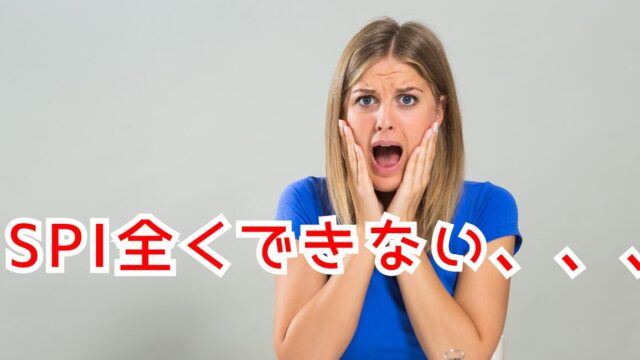【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
SPIの非言語問題の中でも「図表の読み取り」は、見た目のインパクトが大きく、初めて見ると戸惑う学生も多い分野です。グラフや表がずらりと並んでいるだけで「難しそう」「計算が多そう」と苦手意識を持ってしまうかもしれません。
しかし実は図表問題はパターンがあるため、問われる内容にポイントさえ押さえれば得点しやすいお得なジャンルです。
この記事では、SPIの図表問題についてどんな力が求められているのか、よく出る出題形式と読み取りのコツ、本番に向けた対策方法や練習問題といった内容を丁寧に解説します。数字やグラフが苦手な人でも、この記事を読み終えるころには「図表はチャンス問題だ」と思えるようになるはずです。
目次
SPIの図表の読み取りとは
SPIの図表の読み取りとは、棒グラフや折れ線グラフ、表形式のデータなどから、正しい情報を素早く読み取り、それをもとに設問に答える力を測る問題です。一見、計算問題のように見えるかもしれませんが、実際にはいかに効率よく情報を処理できるかが問われています。
グラフ・表・統計を素早く読み取る力が問われる
図表問題では、目の前のデータを見て、次のような力が求められます。
- 変化や比較に注目して、必要な数値をすぐに見つける
- 全体と部分、割合の関係を理解する
- 条件に合うデータを選別し、正しい判断を下す
つまり、単にグラフを“眺める”だけではなく、「読み解いて活用する」力が求められるのです。
SPIの試験は時間との勝負でもあります。図や表に惑わされて時間を使いすぎてしまうと、他の問題を解く余裕がなくなってしまいます。だからこそ、限られた時間で情報を取捨選択するスキルが重要になります。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPI図表の読み取りの出題形式
SPIの図表問題では、大きく分けて3つの形式がよく出題されます。どの形式にもそれぞれの特徴や読み取りのポイントがあります。形式ごとの特性を理解しておけば、初見の問題でも冷静に対処できます。
棒グラフ・折れ線グラフの読み取り
最もオーソドックスな形式が、棒グラフや折れ線グラフから情報を読み取る問題です。売上や来場者数など、数値の「増減」や「比較」が中心です。
・折れ線グラフは、推移(増えている/減っている)に注目
・棒グラフは、どの項目が大きい/小さいかの比較がポイント
・年ごとの変化や前年比を問う問題も多い
視覚的に変化がわかりやすいため、読み取る力とスピードが鍵になります。
例題
以下の折れ線グラフは、あるカフェの売上推移(単位:万円)を1月から6月まで表したものです。
このとき、最も売上が増加した月はどれか。
【選択肢】
A.2月→3月
B.3月→4月
C.4月→5月
D.5月→6月
【答え】
D.5月→6月(+8万円)
【解説】
それぞれの月の増加幅を確認
・2月→3月:+7
・3月→4月:+5
・4月→5月:−3(減少)
・5月→6月:+8(最大)
表形式の売上や人口データ
数値だけが並んだ「表形式」のデータも頻出です。これらは、単純な比較や合計値、差分を計算させる問題が中心です。
・「この年の売上が最も多かったのはどれか?」
・「最も伸び率が高かった年は?」といった設問が定番
・条件によっては一部の列・行だけに注目するのが正解になる
表は情報量が多いため、設問に関係のある部分を素早く特定する力が求められます。
例題
次の表は、3つの支店の第1四半期(1月〜3月)の売上(単位:万円)を示しています。
| 支店 | 1月 | 2月 | 3月 |
| A店 | 120 | 130 | 125 |
| B店 | 110 | 115 | 120 |
| C店 | 100 | 105 | 110 |
このとき、第1四半期(1月〜3月)の累計売上が最も高い店舗はどこか。
【選択肢】
A.A店
B.B店
C.C店
D.3店舗すべて同じ
【答え】
A.A店
【解説】
累計売上を計算:
・A店:120+130+125=375万円
・B店:345万円
・C店:315万円
→A店が最も高い
割合・推移の読み取り問題
割合や比率に関する問題では、全体に対する割合・内訳・割合の変化などが出題されます。
・「前年から何%増えたか」
・「全体に対するAの割合は?」
・「AとBの割合の変化を比較して正しい選択肢を選ぶ」
特にパーセンテージや割合の増減が苦手な人は、あらかじめ計算のやり方に慣れておく必要があります。
例題
ある大学の学生クラブの年度ごとの加入率を以下の円グラフで表した。
このとき、2022年度と2023年度を比較して、クラブ加入率が何ポイント増加したか。
【選択肢】
A.約4ポイント
B.約6ポイント
C.約8ポイント
D.約10ポイント
【答え】
D.約10ポイント
【解説】
・2022年度:180÷300=60%
・2023年度:224÷320=70%
→70%−60%=10ポイント増
※選択肢が「約」とあるため、四捨五入して10ポイントが正確な値
どの形式でも、落ち着いて条件を整理し、数値を的確に読み取ることが求められます。次は、実際に問題を解くときに使える「コツ」を紹介します。
SPI図表の読み取りを解くコツ
図表問題は、正確さとスピードの両方が求められます。ただ眺めていても答えは出ないため、目的を持って読み取る姿勢が重要です。ここでは解くときの実践的なコツを2つ紹介します。
数値の変化に注目しながら、不要な情報を見極める
図表問題には、あえて“不要な情報”が含まれていることがよくあります。全てのデータに目を通す必要はありません。
- 設問に必要な項目だけを確認する
- 変化や極端な値に注目して判断する
- 「増えているか、減っているか」など、ざっくりした傾向を見抜く
例えば、売上グラフなら「どの年が一番多かったか」にだけ注目するなど、目的を絞ってデータを見ることが正解への近道です。
設問の先読みとメモ取りがポイント
問題文を読む前に図表だけをじっくり見るより、先に設問を読んで「何を探せばいいのか」を明確にしてからグラフを見る方が効率的です。
- 設問を読んでから、グラフ・表を見る
- 気づいたポイントはメモする(たとえば「前年比+2%」など)
- 選択肢と照らし合わせながら、矛盾のないものを選ぶ
時間制限があるSPIでは、読み取りスピードとメモの正確さが合否を分けることもあります。これらのコツを日頃から意識し、実戦形式での練習を積むことで、図表問題も得意分野に変わっていきます。
SPI図表の読み取りの対策ポイント
ここでは、SPI本番に向けてどのように図表問題の対策をしていくべきか、実践的なポイントを紹介します。特別な知識がなくても、日々の積み重ねで得点力を伸ばすことができます。
練習で図表慣れしておく
SPIの図表問題においては、問題形式に慣れることが何より重要です。
- 過去問やSPI対策本で繰り返し演習する
- グラフや表を見たときに、自然と「何を聞かれそうか」を予想するクセをつける
- 1問にかける時間の目安(1分〜1分半)を意識する
本番に近い環境で練習することで、時間配分や読み取りのスピード感が身につきます。
読み違えしやすいポイントを知っておく
図表問題では、うっかりミスや読み違いが起きやすい箇所があります。
- 「単位」(千人、億円、%など)を見落とす
- 縦軸・横軸のスケールを正しく把握していない
- 増減の向き(前年比+か−か)を逆に読み取ってしまう
これらはすべて、本番でのミスにつながる要因です。設問に入る前にグラフの単位や軸の意味をしっかり確認するクセをつけておきましょう。
図表問題は、丁寧さと慣れで誰でも得点できるジャンルです。それではここまでの内容を踏まえて、次は実際の練習問題を解いてみましょう。
SPI図表の読み取りの練習問題3つ
このセクションでは、実際に出題される形式に近い図表問題を3問紹介します。読み取りのポイントや解き方の考え方も一緒に解説するので、アウトプットとして挑戦してみてください。
問題1:折れ線グラフからの前年比読み取り
次の折れ線グラフは、ある会社の2019年から2023年までの売上(単位:百万円)の推移を示したものです。
このとき、「前年比で最も売上が増加した年」はどれか。
【解き方】
前年比の増加を計算します。
・2020年:290-320=-30(減少)
・2021年:310-290=+20
・2022年:370-310=+60
・2023年:340-370=-30(減少)
最も増加したのは2022年で、前年度から+60百万円の伸びがありました。
【答え】
2022年
問題2:表の売上データ比較
以下は、3つの店舗(A店・B店・C店)の4月から6月の売上(単位:千円)を表したものです。
| 店舗 | 4月 | 5月 | 6月 |
| A店 | 150 | 160 | 170 |
| B店 | 180 | 175 | 165 |
| C店 | 140 | 145 | 150 |
この表から、「6月に最も売上が高かった店舗」はどれか。
【解き方】
6月の売上に注目します。
・A店:170
・B店:165
・C店:150
最も高いのはA店です。
【答え】
A店
問題3:複数項目の割合比較問題
次の円グラフは、ある企業の社員100人のうち、どの部門に所属しているかを示したものです。
このとき、「営業部と企画部を合わせた割合」は全体の何%か。
【解き方】
営業部(40人)+企画部(25人)=65人
全体が100人なので、65%に相当します。
【答え】
65%
これらの練習問題を通じて、図表の読み方や数値の扱いに慣れておくことが重要です。次は、この記事のまとめとして、図表対策のポイントを振り返ります。
まとめ|図表問題は「慣れ」と「判断力」で差がつく
SPIの図表の読み取り問題は、見た目の情報量に圧倒されがちですが、実は得点しやすい分野です。基本的な計算やグラフの読み方さえ押さえれば、他の受験者に差をつけることができます。
SPIは時間との勝負でもあるため、「情報を読む力」と「無駄を省く判断力」が問われます。この記事で紹介した内容をもとに、図表問題を苦手から得意分野に変えて、就活を有利に進めていきましょう。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。