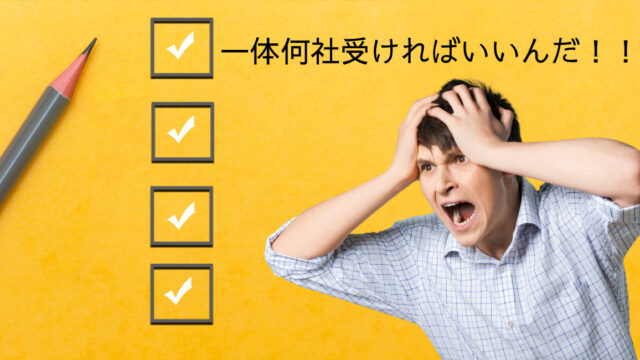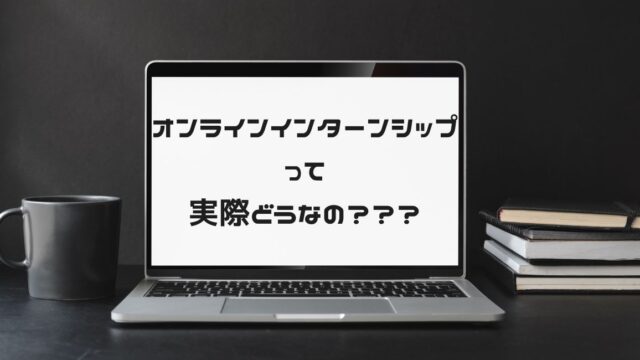【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
就活をしていると、「説明会」や「選考会」という言葉はよく目にしますが、「説明選考会」という聞き慣れないワードに戸惑う学生も少なくありません。「これって説明会なの?選考なの?」「参加したらすぐ落ちたりするの?」といった疑問を抱いたまま、参加をためらってしまう人もいるでしょう。
実はこの「説明選考会」は、企業によっては非常にスピーディーに採用を進める手段として活用されている形式で、参加の仕方次第では効率的に内定へとつなげられるチャンス要素の高いイベントでもあります。しかし、その反面、準備不足で挑んでしまうと、せっかくの機会を活かせずに終わってしまうリスクもあるため、どんなものなのか正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、「説明選考会とはどんなものなのか?」「通常の説明会との違い」「どんな準備が必要なのか」「どんな企業でよく開催されるのか」などをわかりやすく解説していきます。これから就活を本格的に始める学生にとって、必ず役立つ内容となっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
説明選考会とは?
説明選考会とは、会社説明会と選考を一体化させた形式の就活イベントのことを指します。名前の通り「説明」と「選考」がセットになっており、通常の説明会とは異なり、企業情報の説明に加え、簡易的な選考が同時に実施されるのが特徴です。
企業側にとっては、1回のイベントで興味を持った学生にそのままアプローチできるため、人員的にも時間的にも負担を削減できます。学生側も、説明会後に何日も空けて選考を待つ必要がないため、他企業とのスケジュール調整がしやすくなるという利点があります。
とくに、採用スピードを重視しているベンチャー企業や中小企業では、この形式を積極的に取り入れており、なかには説明選考会当日に面接まで終わらせ、1日で内定を出すケースも見られます。
説明会や一次選考との違い
通常の説明会は、企業の事業内容や雰囲気を知るための場であり、基本的には選考には関係ありません。質問の時間はあっても、評価されることはほとんどなく、学生が自由に情報収集できる場です。
また説明会なら企業の情報を聞いた上で、一次選考を受けるまでに志望度を確認したり、他の企業と吟味する時間があります。
一方で説明選考会は、説明会と一次選考が合体して1日で行われるイメージで、説明会の後即選考となるためいかに短い時間で情報を精査したり、事前の情報収集がより重要といえます。
また、説明選考会では複数人が同じタイミングで選考に臨むことも多く、グループ形式になることも珍しくありません。このように、形式や雰囲気も含めて通常の説明会や一次選考とは異なるため、あらかじめ内容を理解して準備しておくことが大切です。
説明選考会の流れ
説明選考会は、名前の通り「説明」と「選考」がセットになっているため、一般的な説明会よりも時間が長くなる傾向があります。企業によって構成や時間配分は異なりますが、基本的には以下のようなステップで進行することが多いです。
①会社説明
最初に行われるのは、通常の説明会と同様の会社説明です。企業の理念や事業内容、今後の展望、募集職種、社員の働き方などについて人事担当者から話があります。ここでは、単なる情報収集の場ではなく、この後の選考に向けた評価の一部として見られている意識を持つことが大切です。
企業によっては「説明会の内容を踏まえて質問してください」と指示がある場合もあります。そのため、ただ話を聞くだけでなく、メモを取りながら内容をしっかり理解しておくことが求められます。
また、説明中に共感したポイントや興味を持った事業などを整理しておくと、後の面接やアンケートで役立つこともあります。
②アンケートやESの提出
会社説明が終わったあとは、その場でアンケートへの記入やエントリーシート(ES)の提出を求められることがあります。内容は企業によって異なりますが、「志望動機」や「学生時代に力を入れたこと」など、基本的な質問が中心です。
ここでの記述内容は、あとの選考や面接で使用される可能性が高いため、ただの形式的なアンケートだと思わず、丁寧に書くことが重要です。時間が限られている中で記入することになるので、事前に志望動機や自己PRのベースを用意しておくと安心です。
企業によっては、紙のESではなく、当日配布されたタブレットやQRコード経由でオンラインフォームに入力するケースもあります。
③適性検査 or グループ面接
書類提出のあとは、続けて適性検査やグループ面接が行われるのが一般的です。内容としては、SPI(総合適性検査)や性格診断テスト、あるいは5~6人でのグループディスカッション(GD)、グループ面接などが挙げられます。
グループ面接では、志望動機や自己PRに加えて、「本日の説明で興味を持った点」など、その場で感じたことを問われるケースもあります。そのため、会社説明を聞いている間に、発言の準備をしておくと良いでしょう。
一方、適性検査の場合は、事前に問題集などで慣れておくことが大切です。特に制限時間内に大量の設問に答えるタイプのテストは、慣れないと実力を発揮しにくい傾向があります。
選考方法は企業次第!個別面接や筆記試験の可能性も
説明選考会で実施される選考内容は、企業によって大きく異なります。たとえば、面接重視の企業であれば、説明会のあとすぐに個別面接に進む場合もありますし、筆記試験に力を入れている企業であれば、テスト中心の構成になることもあります。
そのため、適性検査かグループ面接だと思って参加したら、突然個人面接が始まったなんてことにならないよう、必ず事前にどのような選考形式なのか確認しておきましょう。
説明選考会の参加前にやるべきこと
説明選考会は、通常の説明会とは異なり、選考の場でもあるため、事前の準備がとても重要です。特に「準備不足で評価が下がってしまった」といったケースも少なくありません。ここでは、参加前に確認・準備しておくべきポイントを4つ紹介します。
スケジュール・提出書類・服装の確認
まず大前提として、説明選考会の日程や開始時間、集合場所などはしっかりと確認しておきましょう。オンライン開催であれば、ZoomなどのURLが事前に送られてくるので、接続環境や機材(パソコン・マイク・カメラ)の確認も忘れずに。開始直前にトラブルが発生すると、遅刻扱いになったり、焦って本来のパフォーマンスを出せなくなる恐れもあります。
また、企業によっては当日にエントリーシートや履歴書の提出を求める場合もあります。事前に何が必要かを確認し、プリントアウトやデータの準備を済ませておきましょう。服装に関しては、原則としてリクルートスーツが無難ですが、「私服可」と書かれていても「オフィスカジュアル」を意識した落ち着いた服装が望ましいです。
簡潔な自己紹介の準備(面接がある場合は志望動機や自己PRまで)
説明選考会の中で面接やグループディスカッションが実施される場合、自分のことを短時間で的確に伝える力が求められます。そのため、自己紹介文はあらかじめ準備しておきましょう。
たとえば、「◯◯大学の△△学部に所属している、就活では□□業界に興味がある○○と申します。」というように、1分以内で簡潔にまとめるのが理想です。さらに、志望動機や自己PRも用意しておけば、予想外に面接が始まっても慌てることなく対応できます。
特に説明選考会は想定外の選考が行われる可能性があるため、準備しておいて損はありません。
質問を用意
企業説明のあと、「質問はありますか?」と聞かれることがあります。これは単に疑問解消の場というだけでなく、質問の内容から学生の興味関心や準備度を判断されることもあります。
そのため、何も聞かないのではなく、「企業研究をしてきたことが伝わる質問」や「説明会の内容に対しての感想・疑問」などを用意しておくと好印象です。たとえば、「御社が力を入れている◯◯事業について、入社後どのような関わり方ができるのか知りたいです」といった質問は、前向きな姿勢が伝わります。
時間に余裕を持って行動する
対面での説明選考会に参加する場合、余裕を持って会場に到着するようにしましょう。遅刻は選考以前の問題として、評価に大きく影響する可能性があります。また、ギリギリの到着だと心の準備が整わないまま本番に入ってしまい、緊張から失敗することも。
オンライン開催の場合も同様で、開始5〜10分前にはログインし、カメラやマイクのチェックを終えておくことが理想的です。時間管理も社会人としての基本的な資質として見られるポイントです。
次の章では、説明選考会に参加する際に特に気をつけたい「注意点」について解説します。うっかり見落としがちな点や、選考ならではの落とし穴についても触れていきます。
説明選考会に参加する時の注意点
説明選考会は、説明会でありながら選考の場でもあります。通常の説明会のつもりで油断してしまうと、思わぬところで評価を下げてしまうこともあるため、事前に注意点を理解しておくことが大切です。ここでは、特に気をつけたい3つのポイントを紹介します。
会社説明の感想を聞かれる可能性がある
説明会パートが終わったあとやグループ面接の場で、「本日の説明を聞いて、どの点に魅力を感じましたか?」といった質問をされることがあります。これは学生がただ話を聞いていただけなのか、それとも自分の興味関心と照らし合わせながら積極的に理解しようとしていたのかを見極めるための問いです。
このような質問にスムーズに答えられるようにするためには、説明中にメモを取り、印象に残った点や共感した内容をその場で整理しておくことが大切です。「説明された事業内容の中で特に◯◯に惹かれた」といった具体的な表現ができれば、好印象につながります。
ただ「分かりやすかったです」などの感想で終わってしまうと、浅い理解にとどまっているように見られてしまうため注意が必要です。
質問が評価に影響する可能性がある
説明会後の質疑応答では、学生からの質問が評価一部として見られているケースもあります。特に説明選考会では、通常の説明会以上に学生の関心や主体性を測る材料として質問が重要になります。
そのため事前に企業研究をしておき、自分なりの視点で質問を考えておくことで、「企業の事業内容を理解したうえで、さらに深く知りたいと思っている」という前向きな姿勢をアピールできます。
質問の内容に困った場合は、「入社1年目の社員はどのような業務に携わることが多いか」や「チームでの働き方について」など、働くイメージに関する質問が比較的取り入れやすく、評価にもつながりやすいです。
落ちる可能性があることを忘れない
説明選考会はあくまで「選考」です。つまりESや面接での受け答えが評価され、即日で不採用になるケースもあります。
そのため、「とりあえず行ってみよう」という軽い気持ちで参加すると、準備不足のまま選考に臨んでしまい、結果を残せずに終わるリスクがあります。逆に、きちんと対策をして臨めば、他の就活生よりも一歩先に進める可能性もあるイベントです。
また、選考結果が即日で通知されない場合でも、説明選考会の中でのふるまいや受け答えが次の選考に反映されることが多いため、最後まで気を抜かず、常に選ばれている意識を持つことが重要です。
説明選考会の開催が多い業界・企業の傾向
説明選考会はすべての企業で一般的に実施されているわけではありません。採用スタイルや業界ごとの事情によって、説明会と選考を分ける企業もあれば、一体化して効率的に進める企業もあります。ここでは、説明選考会が多く開催される傾向にある業界や企業の特徴について解説します。
ベンチャー企業や中小企業に多い
説明選考会は、特にベンチャー企業や中小企業で多く採用されている形式です。理由はシンプルで、これらの企業は大手と比べて採用にかけられるリソース(人員・時間・予算)が限られているため、効率的に選考を進める必要があるからです。
1日で説明と選考をまとめて実施することで、学生の関心度をその場で把握し、すぐに採用の意思決定ができます。また、学生にとってもスピード感があるため、早期に内定を獲得したい層との相性が良く、双方にメリットがあるのです。
特に、急成長中のスタートアップ企業や、独自の採用手法を導入している中小企業では、説明選考会を重視しており、場合によってはその1日で内定まで出すというスピード感のある企業もあります。
接客・営業系職種を中心とした業界
もう一つの傾向として、営業職や販売職など、対人スキルを重視する業界でも説明選考会がよく見られます。具体的には、以下のような業界が該当します。
- 人材業界
- 小売・流通業界
- 外食・飲食サービス業界
- 不動産業界
- 保険・金融の営業職
これらの業界では、学生の「話し方」や「態度」「その場の対応力」など、面接を通して感じ取れる人柄や対人スキルを重視する傾向があるため、選考の前段階で行う説明会と合わせて、そのまま面接などの選考に進む形式が取られています。
また、説明会でのリアクションや質問内容などからも、積極性やコミュニケーション能力を判断されやすいため、形式的な書類選考よりも、会って判断したいという意図があります。
大手企業でも一部導入されているケースがある
大手企業では、選考フローが分割されていることが多く、説明選考会のような一体型の形式は少数派です。しかし、早期選考や地方学生の参加を促すための工夫として、一部の大手企業でもこの形式を取り入れている例があります。
たとえば、地方で開催される合同企業説明会の中で、説明と同時に簡単な面談を実施したり、オンライン説明選考会という形で開催されたりすることもあります。
まとめ
説明選考会は、通常の説明会と異なり、企業説明と選考がセットになっている就活イベントです。企業側にとっては採用活動の効率化、学生にとっては選考スケジュールの短縮というメリットがあり、特にベンチャー企業や営業・接客系職種を中心とした業界では頻繁に実施されています。
この形式の特徴は、「説明会だからといって気を抜けない」という点にあります。説明を聞いて終わりではなく、その場でエントリーシートを提出したり、面接や適性検査を受けたりと、明確に選考がスタートしているという意識を持つことが大切です。
また、説明会での感想を問われたり、学生からの質問が評価に影響したりする場面もあるため、しっかりと企業研究を行い、質問や自己紹介の準備をして臨むことが求められます。準備不足で参加すると、選考のチャンスを逃してしまうだけでなく、企業に対して誤った印象を与えるリスクもあるため注意しましょう。
一方で、説明選考会はきちんと準備をしていれば、他の就活生よりも早く内定を得るチャンスでもあります。特に、スピード感を重視する企業では「その日のうちに内定」というケースもあるため、真剣に準備して臨む価値は十分にあります。
就活においては、限られた時間の中でいかに効率よく行動できるかがカギです。説明選考会をうまく活用すれば、志望企業への距離を一気に縮めることができます。これから参加を控えている方は、この記事を参考に、しっかりと準備を整えて臨んでください。
そして何よりも大切なのは、どの形式の選考であっても「自分らしさを伝えること」。説明選考会もその一環であることを忘れず、冷静に、そして前向きに取り組んでいきましょう。