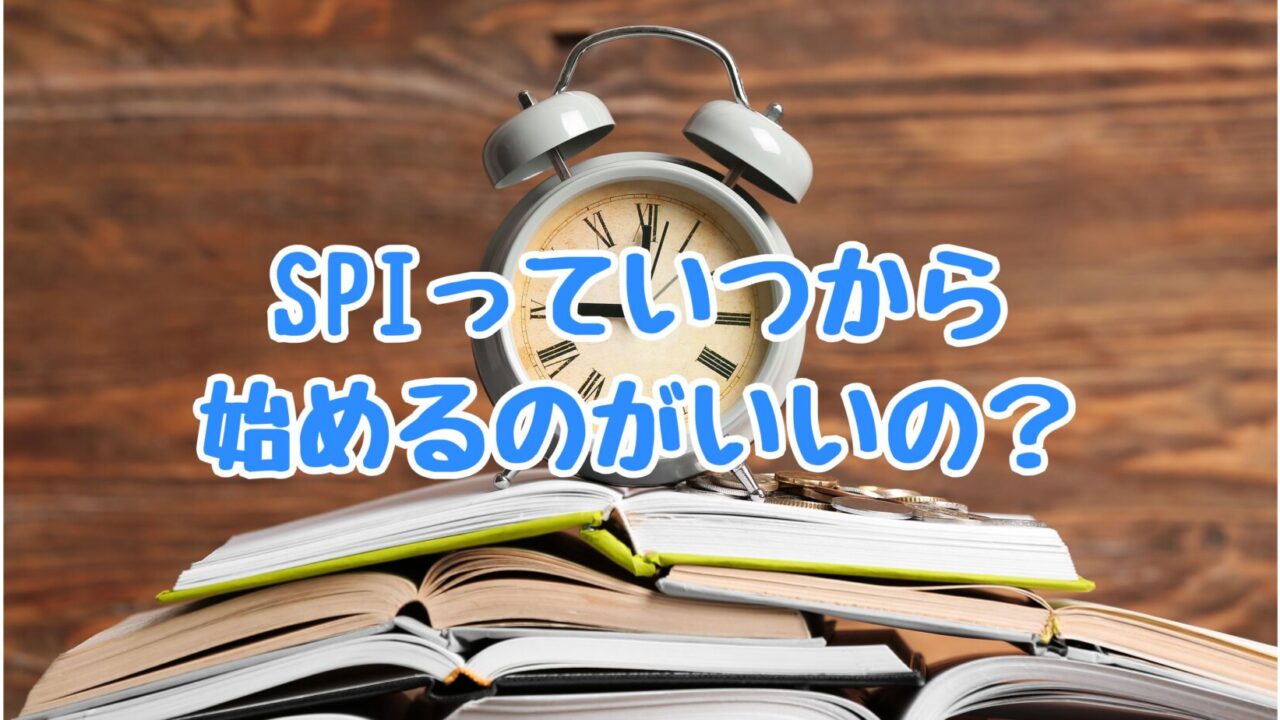【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「そろそろ就活の準備を始めなきゃ」と思っているけれど、SPI対策はまだ手をつけていない……そんな学生も多いのではないでしょうか。実際に、SPIは書類選考や面接と違って、つい後回しにしがちな分野。でも、企業によっては早い時期からSPIの提出を求められることもあるため、出遅れてしまうと「受けたい企業を受けられなかった」という事態になりかねません。
では、SPI対策は一体いつから始めるべきなのでしょうか? また、どれくらいの時間をかけて対策すれば安心なのでしょうか?
この記事では、SPI対策の開始時期や勉強時間の目安、さらに直前からでも間に合う効率的な勉強法までをわかりやすく解説します。あなたに合った対策スケジュールがわかる「診断チャート」や、実際に成功した先輩の体験談も掲載。これからSPI対策を始める方はもちろん、やる気が出ない…と悩む方にも参考になる内容です。
それではさっそく、SPI対策を始めるべきタイミングについて見ていきましょう。
目次
SPI対策はいつから始めるべき?
SPIは選考フローの初期に課されることが多く、早めに対策を始めておくことで他の就活準備もスムーズに進められます。特に学力検査に不安がある場合、早い段階からの取り組みが効果的です。では、実際の就活生たちはいつ頃から始めているのでしょうか。
一般的な開始時期の目安
SPI対策の開始時期は、就活のフェーズによって異なります。以下に、インターン選考と本選考それぞれのタイミングを紹介します。
本選考:大学3年の12月頃〜
一般的に本選考が本格化するのは大学3年の12月〜1月頃。そのため、この時期にSPIの提出を求められることが多く、11月〜12月には対策を始めておくのが理想です。早い企業では11月中にSPIを課すケースもあるので、秋頃から意識し始めると安心です。
インターン:大学3年の夏前〜秋頃
サマーインターンやオータムインターンでもSPIを導入している企業があります。特に大手企業ではSPIがエントリー条件になっている場合もあるため、大学3年の6月〜8月頃にかけて、SPIの準備を始めておくことが望ましいです。
SPI対策タイプ診断チャート
「自分はどのくらい時間をかけるべき?」と悩んでいる人は、以下の簡単な診断チャートを試してみてください。
Q1. SPI受験予定は1ヶ月以内?
┗ YES →「直前集中型」へ
┗ NO → Q2へ
Q2. 数学や文章問題が苦手?
┗ YES →「じっくり長期型」へ
┗ NO →「短期集中型」へ
以下は、タイプ別の特徴と対策スケジュールの目安です。
| タイプ | 対策開始の目安 | 勉強期間 | 特徴 |
| 直前集中型 | 1〜2週間前 | 15〜30時間 | 模試中心の追い込み型 |
| 短期集中型 | 約1ヶ月前 | 30〜40時間 | 苦手潰し+演習反復 |
| 長期型 | 2〜3ヶ月前 | 60時間以上 | 初心者・苦手意識が強い人向け |
SPI対策に必要な勉強時間はどれくらい?
「SPIって、どれくらいの時間をかければ安心なの?」と感じる方も多いと思います。ここでは、全体の目安時間と、分野別にどれくらい時間を割くべきかを解説します。
全体の目安時間(基礎〜本番対応)
一般的な目安としては、30〜60時間ほどの勉強時間が必要です。SPIは範囲が広いわけではありませんが、慣れがものを言う試験です。特に非言語分野に苦手意識がある場合は、+10〜20時間程度を見込んでおくと安心です。
1日1〜2時間の学習を1ヶ月程度続ければ、基本的な問題には対応できるレベルになります。逆に、短期間で一気に仕上げたい場合は、1日3〜4時間程度の集中学習が求められます。
分野別のおすすめ勉強時間
それぞれの分野ごとに、目安の勉強時間と対策のポイントをまとめました。
| 分野 | 目安時間 | ポイント |
| 言語問題 | 10〜15時間 | 語彙力・整序問題・長文読解に慣れる |
| 非言語問題 | 15〜25時間 | 計算・表の読み取り・推論問題への慣れ |
| 英語(SPI英語型) | 10〜15時間 | 短文理解・文法・英単語対策 |
| 構造的把握力 | 約10時間 | 抽象的な文章の構造理解を練習 |
| 性格検査 | 数時間〜 | 自己分析と一貫性を持たせることが重要 |
SPI対策の進め方4STEP
効率よくSPIの対策を進めるためには、なんとなく勉強を始めるのではなく、目的と順序を明確にして取り組むことが重要です。焦って全体を中途半端に勉強するよりも、1つずつ確実に積み上げていく方が、結果的に得点力も自信もついてきます。
ここでは、SPI対策の基本となる4つのステップを紹介します。
STEP1|志望企業の出題形式を調べる
いきなり問題集を開くのではなく、まずは自分が受ける企業でどんな形式の適性検査が使われているかを調べることが先決です。SPIには「SPI-G」「SPI-U」「SPI英語型」のようなバリエーションがあるほか、企業によっては「玉手箱」や「CAB」など異なる形式を採用しているケースもあります。
この形式によって、出題される問題の種類や難易度、時間配分が異なるため、正確に把握しておかないと対策がズレてしまうリスクがあります。たとえば、SPI対策ばかりしていたのに、実際は玉手箱だった…となれば努力が無駄になりかねません。
対策の第一歩は、「敵を知る」こと。企業の採用ページや就活口コミサイト、OB・OG訪問などを活用して、選考で使用される適性検査の種類を早めに確認しておきましょう。
STEP2|まずは1冊問題集をやり切る
形式が分かったら、次は基礎固めです。ここでは市販のSPI対策本を1冊やり切ることを目標にしましょう。
どれを選べばいいかわからない場合は、『これが本当のSPI3だ!』や『史上最強SPI問題集』といった定番の書籍がおすすめです。解説が丁寧で、初心者でも取り組みやすく、多くの就活生が使っています。
この段階で大事なのは、すべての問題を「完璧に解けるようにする」ことではありません。まずは一通り全体を経験し、出題パターンや問題の雰囲気に慣れることが目的です。完璧主義にならず、「まず1周する」「最低限の解説を読む」を意識して進めると、効率よく土台が築けます。
やり切ったあとは、どの分野が得意で、どこが苦手かも見えてくるため、次の対策にもつなげやすくなります。
STEP3|「SPI対策早押しクイズ」でスキマ時間に実力チェック
SPIの勉強は、机に向かって何時間も集中しないと効果が出ない、というものではありません。むしろ毎日のスキマ時間を有効に活用できるかどうかが、SPI対策の明暗を分けます。
通学中、授業と授業の合間、寝る前の10分など、小さな時間を積み重ねることで、大きな差が生まれます。
そこで活用して欲しいのが、**らくらく就活が提供する「SPI対策早押しクイズ」**です。
こちらツールは、LINEに友だち追加するだけで完全無料で使えるSPI対策アプリで、SPI予想問題が2000問以上収録された早押しクイズ形式の問題集になっています。ゲーム感覚でテンポよく問題を解くことができるので、勉強というより「遊びながら慣れる」感覚で続けられるのが特長です。
模試モードもあるため、自分の実力チェックや本番形式の練習にも最適。特に、「問題集に飽きてしまった」「集中力が続かない」という方にとって、モチベーションを維持しながら反復練習できる最強ツールです。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
STEP4|時間制限演習で仕上げる
問題集で基礎を固め、アプリで慣れてきたら、最後の仕上げは**「時間制限つきの本番想定演習」**です。
SPIでは「正答率」だけでなく、「制限時間内に解けるか」も非常に重要です。特に非言語分野は、焦ると計算ミスや読み取りミスを起こしやすく、実力が発揮できないまま終わってしまうこともあります。
ここでは、タイマーを使って本番と同じ時間内で模試や問題集を解くことで、時間感覚と集中力を鍛えることが目的です。
時間を意識した演習を繰り返すことで、「どの問題にどれくらい時間を使うか」「見直し時間をどう確保するか」といった戦略も自然と身につきます。
また、本番形式に慣れておくことで、試験当日の緊張や焦りを最小限に抑えることができます。SPIは“慣れ”がスコアに直結する試験なので、この仕上げステップは決して省略せず、必ず数回はタイマー演習を行うようにしましょう。
以上が、SPI対策を効率よく進めるための4ステップです。段階を踏んで進めていくことで、短期間でもしっかり得点力をつけることができます。特にアプリや時間制限演習を取り入れることで、実践的な力がぐっと伸びますので、ぜひ取り入れてみてください。
今から間に合う?直前対策でできること
「SPIの受検が迫っているけど、全然対策できていない…」
そんな不安を抱えている就活生も多いのではないでしょうか。特に、エントリーシートや面接準備に追われて、SPI対策が後回しになってしまったという声は非常によく聞きます。
しかし、結論から言えば、今からでも十分間に合います。大事なのは“やるべきことを絞る”ことです。限られた時間の中で最大限の成果を出すためには、やみくもに手を広げるのではなく、効果の高い取り組みに集中する必要があります。
ここでは、1週間前からでも実践できる直前対策を3つ紹介します。
1週間前でもやるべき3つの対策
SPIまで残りわずかという状況で焦る気持ちはよくわかりますが、焦りすぎて全範囲に手を出してしまうと、逆に非効率になってしまいます。以下の3つに絞って、重点的に取り組んでください。
1. 苦手分野の重点対策(1日1テーマで集中)
今から全範囲を網羅するのは時間的に厳しいため、苦手な分野に絞って、徹底的に潰すことがポイントです。たとえば、「表の読み取り」「推論」「語句の用法」など、自分が過去に間違えた問題や理解が曖昧だったテーマを1日1単元ペースで絞って対策します。
1つのテーマごとに、「基本問題→応用問題→模試形式で確認」というサイクルを短く回すことで、理解と定着を効率よく進めることができます。
2. 模試を最低2回、解いたら必ず復習する
短期間で成果を出すには、模試形式の演習が非常に効果的です。本番と同じような時間配分・緊張感の中で問題を解くことで、自分の実力や課題が一気に浮き彫りになります。
ただし、模試を受けるだけでは不十分。最も大事なのは復習です。「なぜ間違えたのか」「問題の意図を正しく読み取れていたか」を分析し、同じミスを繰り返さないようにします。模試は少なくとも2回、多ければ3回以上できるとベストです。
SPI対策早押しクイズなどのツールを活用すれば、模試モードで実力を手軽にチェックすることも可能です。
3. 性格検査の整合性チェック
学力検査の対策に気を取られがちですが、性格検査の対策も見落とせません。基本的には“正直に答える”ことが原則ですが、企業がどのように性格検査を見ているかを理解したうえで、自分の回答が自己分析と矛盾していないかを確認しておくと安心です。
特に、「協調性が高い」とESに書いているのに、性格検査では自己中心的な傾向が出てしまうと、選考での評価が下がる可能性があります。ESや面接内容と一貫性を持たせる意識を忘れずに。
実際の短期成功者の声
焦りながらも1週間でSPIを突破した先輩の実例を紹介します。自分と似た状況の人がどのように対策したかを知ることで、希望が持てるはずです。
Bさん(国立大学・研究で多忙)
「2月中旬に志望企業の書類選考が通過し、急遽SPIを受けることに。正直、それまでほとんど対策できておらず焦りましたが、1週間だけ集中して取り組むことを決意しました。
特に非言語が苦手だったので、模試を3回解いて、間違えた問題をすべて解説付きで確認。SPI対策早押しクイズも併用して、スキマ時間に反復演習をしました。
かなり詰め込んだ1週間でしたが、なんとか本番でも冷静に対応でき、無事に通過できました。“やるべきことを絞ってやり切る”ことが何より大事だと実感しました。」
このように、直前でも戦略的に取り組めば、SPIを突破することは十分可能です。「間に合わない」とあきらめるのではなく、限られた時間をどう使うかに集中してみてください。SPIは、短期間でも成果が出やすいテストです。やる気次第でまだ巻き返せます。
SPI対策のスケジュール例
SPI対策は、自分の性格や勉強スタイルに合わせて計画を立てることで、より効率的に取り組むことができます。「計画的に少しずつ進めたい人」「直前の短期集中が向いている人」など、タイプに応じて取り組み方は変わります。
ここでは、代表的な2パターンのスケジュール例を紹介します。自分に合ったスタイルを選んで、無理のない対策を進めていきましょう。
3ヶ月前から始めるじっくり型スケジュール
コツコツ型・苦手意識がある人・SPI未経験者におすすめなのが、3ヶ月かけてじっくり対策するスタイルです。焦らず段階的にステップアップできるので、初めてのSPIでも着実に力を伸ばせます。
| 時期 | 内容 |
| 3ヶ月前 | 問題集1冊を通して演習 |
| 2ヶ月前 | 苦手分野の集中対策+模試 |
| 1ヶ月前 | タイマー演習+復習 |
このスケジュールのメリット:
・無理なく習慣化できる
・理解→反復→実戦のサイクルが定着しやすい
・ESや面接対策との両立がしやすい
1週間で仕上げる直前集中プラン
「SPIが目前に迫っている」「今すぐやらなきゃまずい!」という人に向けた、1週間で一気に仕上げるスピード対策プランです。時間が限られているからこそ、やるべきことを絞って集中的に取り組みます。
| 日数 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| Day1 | SPI全体像をつかむ、出題範囲を確認 | 問題集や解説サイトでSPIの形式・出題分野・難易度を一通り把握する。まず「全体を理解すること」が出発点。 |
| Day2〜Day5 | 分野ごとに日替わりで学習(例:Day2は言語、Day3は非言語など) | 1日1テーマに集中し、「例題→演習→解説」の流れで反復。早押しクイズなども併用して、短時間でも密度の高い対策を。 |
| Day6 | 模試1回+間違えた問題の復習 | 時間を測って模試を解き、結果を見て弱点を分析。間違えた問題は「なぜ解けなかったか」を必ず言語化してから復習。 |
| Day7 | 模試で仕上げ、全体の総点検 | 最終確認として模試をもう一度実施し、スピード・正確性・集中力を総仕上げ。前日の復習効果を体感できる日。 |
このスケジュールのコツ:
・分野別に優先順位を決める(苦手を前半に)
・1日2〜3時間を目安に集中して学習する
・アプリやWeb模試など、手軽にできるツールもフル活用する
どちらのスケジュールでも共通して大切なのは、「やりっぱなしにしないこと」と「模試+復習」のサイクルを取り入れることです。
計画通りに進まない日があっても、焦らずにできる範囲でリカバリーしていきましょう。SPIは努力がスコアに直結しやすい試験なので、短期間でも集中すれば結果につながります。
SPI対策に成功した人の共通点チェックリスト
SPI対策に成功する人には、共通して“やっていること”があります。特別なテクニックや能力ではなく、基本を丁寧に積み重ねているかどうかがポイントです。
以下のチェックリストを読みながら、自分に足りないところ・すでにできていることを見直してみてください。
□ 出題形式を事前に確認している
SPI対策の第一歩は、「敵を知る」こと。受ける企業がどの形式の適性検査(SPI-G/SPI-U/玉手箱など)を課してくるかを事前に調べたうえで、それに合った対策をしています。
口コミサイトや就活体験記、ナビサイトの企業ページなどで確認している人は、ムダな勉強をせず、効率よく進められている傾向があります。逆に、形式が違えば出題内容も時間配分も大きく異なるため、「知らなかった」で落ちるのはもったいないです。
□ 問題集を1冊はやり切っている
SPI対策本は数多くありますが、「とりあえず1冊を最初から最後までやり切る」ことが成功への近道です。あれこれ手を出すよりも、1冊を繰り返す方が理解が深まり、得点力も安定します。
解けなかった問題に付箋をつけたり、解説を読み込んで理解を深めたりと、“ただやる”のではなく“使い倒す”意識がある人ほど、SPI本番に強い傾向があります。
□ SPIアプリを週3回以上使っている
SPI対策は“継続”が鍵です。毎日まとまった時間を取れなくても、スキマ時間を使ってアプリで演習している人は、自然と問題形式に慣れ、スピードも上がっていきます。
例えば「らくらく就活のSPI対策早押しクイズ」など、ゲーム感覚で楽しめるツールを使えば、やる気の波に左右されず習慣化が可能です。週に3回以上取り組んでいれば、それだけで“差がつく就活生”になれているはずです。
□ 模試を2回以上解いたことがある
本番に近い環境での練習=模試は、実力の確認だけでなく、時間配分や緊張感に慣れるためにも不可欠なステップです。
2回以上受けている人は、1回目の反省点をもとに改善できており、自分の弱点や傾向を把握できています。ただ解いて終わりではなく、解説を読んで復習し、2回目に同じミスをしないよう対策できていることが成功のカギです。
□ タイマーを使って時間を意識している
SPIでは、限られた時間の中で正確に問題を解く力が求められます。そのため、時間を意識したトレーニングをしているかどうかで、当日の結果は大きく変わります。
実際にタイマーを使って問題集や模試を解くことで、「解く順番」「1問にかけるべき時間感覚」「焦りへの対処力」など、実戦力が身につきます。時間に追われて思うように解けなかった…という失敗を防ぐには、この“本番想定演習”が効果的です。
□ 性格検査の内容と自己分析が一致している
SPIの性格検査は、嘘をつくと見破られるという噂もありますが、本当に大切なのは“自己分析との一貫性”です。
例えば、自己PRやESで「チームワーク重視」と書いているのに、性格検査の回答では「1人でやりたい」「指示されるのが苦手」といった傾向が出ていれば、採用担当者は違和感を抱くかもしれません。
成功する人は、自分の性格を客観的に理解したうえで、ブレのない回答を選べているのが特徴です。特にSPIが足切り要素ではなく“人物評価の一部”として使われる場合、この一貫性が評価に直結します。
チェック数が多いほどSPI突破の可能性は高まる
上記の項目はすべて、特別な能力がなくてもできることばかりです。完璧でなくても、1つずつ取り組めば確実に力がついていきます。
「まだできていない項目がある」という方は、今から意識して習慣にしていけば十分間に合います。SPIは“慣れ”と“準備量”が結果に直結する試験です。まずは、今日から1つでもチェック項目を増やすところから始めてみましょう。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPI対策を成功に導くリアルな事例
「自分もちゃんとSPIを乗り越えられるのだろうか……」
そんな不安を抱える就活生にとって、実際に成功した人の体験談は大きなヒントになります。
ここでは、対策のタイミングも方法も違う2名のリアルな就活体験を紹介します。スタートが遅くても、苦手意識があっても、しっかりと工夫すればSPIは突破可能です。
Aさん(文系・地方大学)
「計画的に動いたおかげで、SPIが“自信の源”に変わった」
「6月に就活を意識し始めた頃、SPIという言葉を初めて聞きました。最初は“筆記試験なんてなんとかなるでしょ”と軽く考えていたのですが、ネットで調べるうちに多くの企業でSPIが足切りに使われていると知り、さすがに焦りました。
ただ、地方の大学で周囲もSPIの話題に疎く、何から始めればいいのかも分からず……。そんなとき、SNSで見つけた『SPI対策早押しクイズ』をとりあえず試してみたんです。
そこからは週3回のペースでアプリを使い、通学中や寝る前にコツコツ問題を解くようにしました。わからなかった問題は、週末に問題集やWebで調べて補うスタイルで進めていきました。
9月には模試形式でも安定して得点できるようになり、12月の本選考ではSPIで落ちることがほとんどなくなりました。早めに気づいて地道に取り組んだことで、SPIが“自信に変わった”実感があります。」
Cさん(理系・MARCH)
「初戦敗退からの大逆転。失敗が、本気になるきっかけだった」
「理系ということもあって、『SPIぐらい勉強しなくても解けるだろう』と完全に油断していました。実際、1社目のWebテストもノー勉で受けてみたんですが、結果は不合格。そのとき初めて、SPIを甘く見ていたことを後悔しました。
そこからは本気で1ヶ月間、毎日2〜3時間をSPI対策に投下しました。市販の問題集を一気に2周し、模試を3回。さらにアプリでスキマ時間にも練習。問題のパターンを覚えるまで、同じミスを何度も繰り返しました。
1ヶ月後、再び始まった企業の選考では、4社連続でSPIを通過。自信もつき、SPIが“苦手”から“得意”に変わっていました。
落ちた経験があったからこそ、本気になれた。SPIは、努力がそのまま結果に出る試験だと思います。」
どちらのケースにも共通するのは、「気づいたときから対策を始めたこと」そして「自分に合ったペースとツールで継続したこと」です。
SPIは確かに最初は難しく感じるかもしれませんが、パターンに慣れればぐっと楽になります。焦らず、一歩ずつ進めていきましょう。あなたもきっと、SPIを“得点源”にできます。
よくある質問Q&A
まとめ
SPI対策は理想的には大学3年の12月頃から始めるのがベストですが、直前からでもやるべきことを明確にすれば巻き返しは十分可能です。
自分に合ったタイプとスケジュールを見極めて、問題集・アプリ・模試をうまく活用しましょう。SPIは努力が得点に直結しやすい分野です。しっかり準備すれば、選考通過の大きな武器になります。自信を持って対策に取り組んでください。