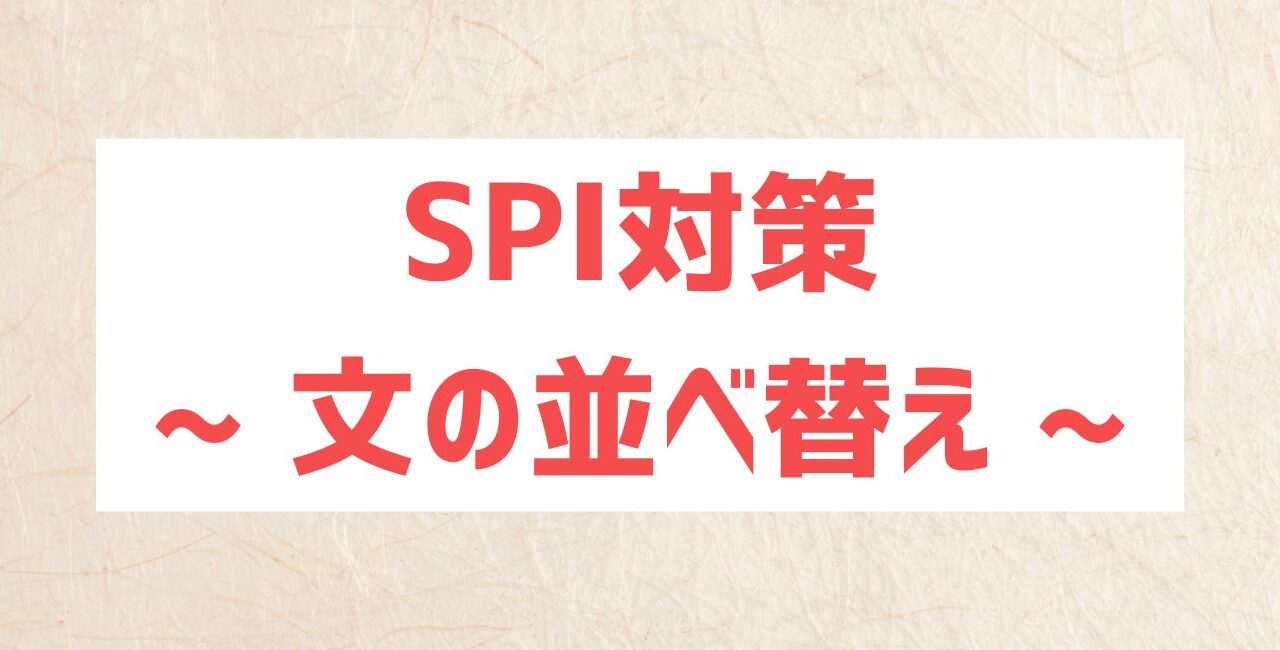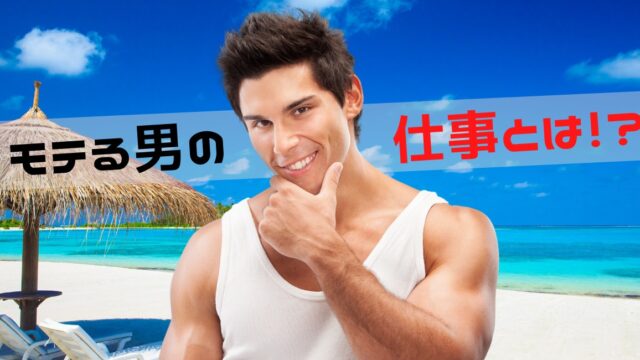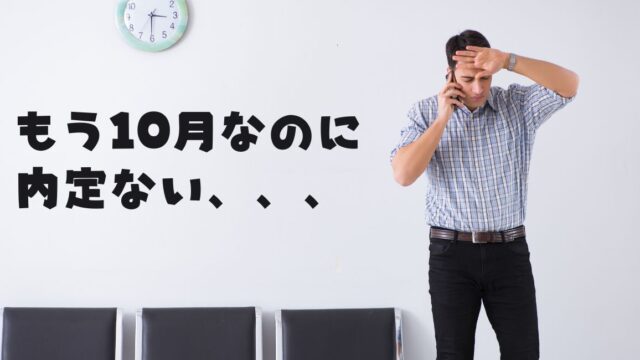①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「文の並べ替えって、なんとなくで選んでしまう…」
「全部の文が自然に見えて、どこが先か判断できない…」
SPIの言語分野では、語彙や文法だけでなく、「文を正しく並べる力」も試されます。特にこの文の並べ替え問題は、文構造の理解力、論理的な展開、接続語の使い方など、国語の総合的な力が問われる問題として、多くの就活生が苦戦しがちです。
ですが、実はこの問題にはよく出るパターンと明確な解法のコツがあり、それを押さえておけば、感覚に頼らず論理的に並び順を決めることができるようになります。
この記事では、SPIの文の並べ替え問題の出題形式に解説しつつ、正解にたどり着くための解法パターン、並び順を見極めるための具体的なコツ本番を想定した練習問題といった内容を、就活生向けにわかりやすくまとめました。苦手意識を持っている方でも、読み終える頃には「対策すれば確実に伸びる」ことを実感していただけるはずです。
SPIの文の並べ替えとは
SPIの「文の並べ替え」では、複数の文や文節がバラバラに並べられて提示され、それを意味の通る自然な順序に並び替える問題が出題されます。一般的には、A・B・C・Dなどの文が与えられ、最も自然な流れになる順番を選択肢から選ぶ形式が多いです。
この問題で求められるのは、
・文全体の主語と述語の関係を理解する力
・接続語や指示語の使い方から論理的展開を読み取る力
・時間の流れや原因と結果といった論理構成を意識する力
といった、文構造を見抜く力と論理的思考力です。
例題としては以下のような形式が多く見られます。
例:
以下の文を意味が通るように並べ替えたとき、正しい順番はどれか。
A:昨日は雨が降っていた。
B:そのため、傘を持って出かけた。
C:夕方にはやんでいた。
D:朝から空がどんよりとしていた。
この場合、「D→A→B→C」のように、時間の流れと因果関係を意識すると自然な文の流れになります。
SPIで落ちたくない。でも時間がない、、
だからこそスキマ時間にサクッと対策しよう!
「SPIの結果が原因で落とされた…」なんて後悔、したくないですよね。かといってSPI対策にたくさん時間を割くわけにもいきません。
そこでおすすめするのが「SPI対策早押しクイズ」です!このツールならゲーム感覚でSPIの予想問題2000問の演習ができ、AIによる解説もついています。また模擬テスト機能により短時間で実力試しもできるので、忙しい就活生にぴったりです!
ぜひらくらく就活のLINEを追加して使ってみてください。
SPI文の並べ替えでよく出る問題
SPIの文の並べ替え問題には、一定の出題パターンがあります。文の意味だけでなく、構造的な特徴や論理的なつながり方に注目することで、選択肢を素早く絞ることができます。
ここでは、特に出題頻度の高い3つのパターンを紹介します。
主語・述語の対応に注目する問題
このタイプは、文の中で「誰が何をしたか」が明確になる順序を見抜くことが求められます。主語が提示されてから、述語や目的語が続くのが自然な流れです。
例:
A:新入社員の山田さんは
B:チームメンバーと相談して
C:新しい提案書を作成した
D:昨日、営業会議で
→正しい並び:「A→D→B→C」
ポイントは、「誰が・いつ・どうした」という要素が時系列と主述の一致で無理なくつながることです。
接続詞や助詞から順序を判断する問題
「しかし」「そのため」「また」「そして」などの接続詞や助詞の働きに注目することで、文同士の関係が明確になる問題です。
例:
A:彼は体調が優れなかった。
B:そのため、試合には出場しなかった。
C:試合当日の朝、
D:熱があったにもかかわらず
→正しい並び:「C→A→D→B」
「そのため」は結果を示すので前に原因がくる、「にもかかわらず」は逆接なので直前の文と対比構造になる、という接続語の論理的な意味づけを理解することが重要です。
時間や論理構成に基づく並び替え問題
時間の流れ(朝→昼→夜、過去→現在→未来)や、論理の順序(原因→結果、前提→主張→結論)に従って、文を自然に並べるタイプの問題です。
例:
A:社会人としての心構えが身についた
B:最初はわからないことばかりだったが
C:数多くの経験を通して
D:仕事にも少しずつ慣れてきた
→正しい並び:「B→D→C→A」
このように、ストーリーや論理の流れがある場合には、「まず何が起こり」「その結果どうなったのか」という文章全体の展開を意識して判断することが大切です。
次の章では、こうした出題パターンをどう見抜き、どう並べ替えを進めていくかという「解き方のコツ」をより詳しく解説していきます。特に、コツの章は実践的な技術を中心に構成していますので、ぜひ丁寧に読み込んでください。
SPI文の並べ替えを解くコツ
並べ替え問題を正確に解くには、出題パターンを知るだけではなく、実際の解答の場面でどう考え、どう処理していくかという具体的な解法のコツを身につけることが重要です。
ここでは、SPIの並び替え問題を効率的かつ正確に解くための3つのコツを、実例とともに詳しく解説していきます。
コツ①:「まず何が起きたか」を意識する
並べ替えのスタートは、物語や出来事の始まりを見つけることです。文章全体をストーリーのように捉えて、「最初に書かれるべき内容はどれか?」という視点で読みましょう。
例:
A:最終的には彼が優勝した。
B:決勝戦は白熱した試合になった。
C:彼はこれまで多くの努力を重ねてきた。
D:観客たちはその戦いに釘付けになった。
→正しい並び:「C→B→D→A」
このように、「まず何が起きたか」をつかむことで、その後の展開が自然につながっていきます。逆に、結末から始まるような文(たとえば「最終的に〜」など)は、後半に来ることが多いです。
コツ②:接続語・指示語に注目する
「しかし」「そのため」「また」「このように」などの接続語や、「それ」「この」「あの」などの指示語は、前後の文との関係性を明示するキーワードです。これらを頼りにすると、文のつながりがぐっと見えやすくなります。
例:
A:このように、準備は完璧だった。
B:彼女は数週間前から計画を立てていた。
C:当日はトラブルもなく進行した。
D:リハーサルも繰り返し行った。
→正しい並び:「B→D→A→C」
「このように」は、それ以前に理由や具体例が語られている必要があります。そのため、「A」が文頭にくることは考えづらく、前に「B→D」の流れがあると自然になります。接続語や指示語は、選択肢を2〜3つに絞るうえでとても有効なヒントになります。
コツ③:主語と述語が自然に続く形を探す
文の中で「誰が」「どうした」という構造(主語+述語)が自然に接続しているかどうかを確認するのも、非常に重要なチェックポイントです。
不自然な例:
「彼は昨日、試合に出場した。そして、多くの応援があった。」
→後半の文の主語が「彼は」ではなく「応援」になってしまって不自然。
自然な接続:
「彼は昨日、試合に出場した。そして、多くの人が彼を応援した。」
→主語が明確に切り替わっており、論理的な流れができている。
主語と述語のつながりの自然さを意識すると、違和感のある選択肢を見抜く力がつきます。
これらのコツを意識するだけで、「なんとなく」選ぶのではなく、論理的に順序を決定する力が格段にアップします。次の章では、これらの解法を定着させるための具体的な対策方法を紹介します。着実に得点力を上げたい人は、ぜひ実践に取り入れてみてください。
SPI文の並べ替えの対策ポイント
コツを理解したら、実際の問題を通じてスキルを定着させていくことが重要です。ここでは、SPIの文の並べ替え問題で得点力をつけるために有効な3つの学習法を紹介します。日々の学習に取り入れることで、「選び方の感覚」ではなく「論理で正しく並べる力」が身についていきます。
ポイント①:文の構成パターンに慣れる
まずは、SPIでよく出る並び替えの構成パターン(主述・接続語・時系列・因果関係など)に繰り返し触れて慣れることが大切です。慣れてくると、初見の文章でも「この流れはA→C→Dだな」と自然に読めるようになってきます。
おすすめの学習法:
・問題集で「解説を読む前に構成の型を言語化する」練習
・似たパターンの問題をまとめて解き、流れをパターン認識する
パターン学習を通じて、文章の構造を瞬時に見抜く力が養われます。
ポイント②:実際に声に出して自然さを確認
文の自然さは、「頭の中」よりも「音」で確認すると判断しやすいという特徴があります。特に、接続語の使い方や主語の入れ替わりによる違和感は、黙読よりも音読のほうが気づきやすいです。
おすすめの方法:
・並べ替えの答えが決まったら、実際に声に出して読んでみる
・「意味は通るがリズムが悪い」などの違和感にも注意する
音にしてみると、微妙な不自然さがクリアに分かるようになります。就活の面接対策にもつながるので一石二鳥です。
ポイント③:過去問・模試で実践練習を重ねる
やはり最も効果的なのは、制限時間内での実戦演習を繰り返すことです。特に、制限時間がある状況では、焦って選択肢を雰囲気で選びがちになるので、論理的思考の訓練にもなります。
学習のポイント:
・1問1〜2分を目安に、時間を測りながら解く
・不正解の問題は、正解の並びが「なぜ自然か」を必ず言語化する
・週に1度は模試形式で5〜10問まとめて解く
演習を積み重ねることで、論理的な読みの精度とスピードが高まり、本番でも落ち着いて対応できるようになります。
早押しクイズ形式で楽しくSPI対策できる!
完全無料のSPI予想問題2000問
選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPI文の並べ替え練習問題3つ
ここでは、SPI本番を意識した文の並び替え問題を3問用意しました。それぞれに正解と解説をつけているので、これまで学んできたコツとパターン認識を活かしながら解いてみましょう。
問題1:日常的な文章の並び替え
次の文を、意味が通るように並び替えたとき、正しい順番はどれか。
A:すぐに連絡を取ることにした。
B:財布が見当たらず、焦って探していると
C:バス停のベンチに置き忘れていたのを思い出した。
D:ようやく、どこに置いたのかを思い出した。
選択肢:
①B→D→C→A
②D→B→C→A
③B→C→D→A
④A→B→D→C
正解:
①B→D→C→A
解説:
「財布が見当たらず〜(B)」→「ようやく思い出した(D)」→「どこにあったか具体的に思い出す(C)」→「連絡を取る(A)」と、時間と心理の流れが自然につながっています。
問題2:ビジネス文書の論理展開整理
A:その結果、目標を上回る成果を上げた。
B:営業部では今期、新たなキャンペーンを実施した。
C:SNS広告を活用し、若年層へのアプローチを強化した。
D:さらに、既存顧客へのDM施策も同時に行った。
選択肢:
①B→C→D→A
②C→D→B→A
③B→D→C→A
④A→B→C→D
正解:
①B→C→D→A
解説:
「今期の活動(B)」→「具体策その1(C)」→「具体策その2(D)」→「結果(A)」という、起承転結・原因と結果の順番が明快な流れになっています。
問題3:指示語・接続語を含む応用問題
A:それにもかかわらず、彼は計画を変えなかった。
B:天気予報では、大雨の恐れがあると告げられていた。
C:仲間たちは中止を提案した。
D:当日は、空模様が怪しかった。
選択肢:
①D→B→C→A
②B→D→C→A
③C→B→A→D
④B→C→D→A
正解:
②B→D→C→A
解説:
「予報(B)」→「実際の天気(D)」→「提案(C)」→「彼の判断(A)」という、時系列+逆接の展開が自然な並びです。「それにもかかわらず」は、直前に中止すべき理由が出ている必要があるため、Aは文末になります。
以上のような問題に数をこなして取り組むことで、パターン認識と論理的思考の力が定着していきます。
まとめ
SPIの文の並べ替え問題は、一見シンプルに見えて、実は論理的な構成力や文の流れを見抜く読解力が問われる奥深い問題です。しかし、よく出る出題パターンや構成の特徴を知っておけば、「なんとなくの感覚」で解くのではなく、根拠を持って正しい順序を選べるようになります。
さらに、音読による確認や構成パターンの整理、実践形式での演習を継続することで、読解力と処理スピードが同時に鍛えられます。SPIの言語対策において、文の並べ替え問題は「落とさず拾いたい得点源」です。丁寧な対策を積み重ねて、自信を持って本番に臨みましょう。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。