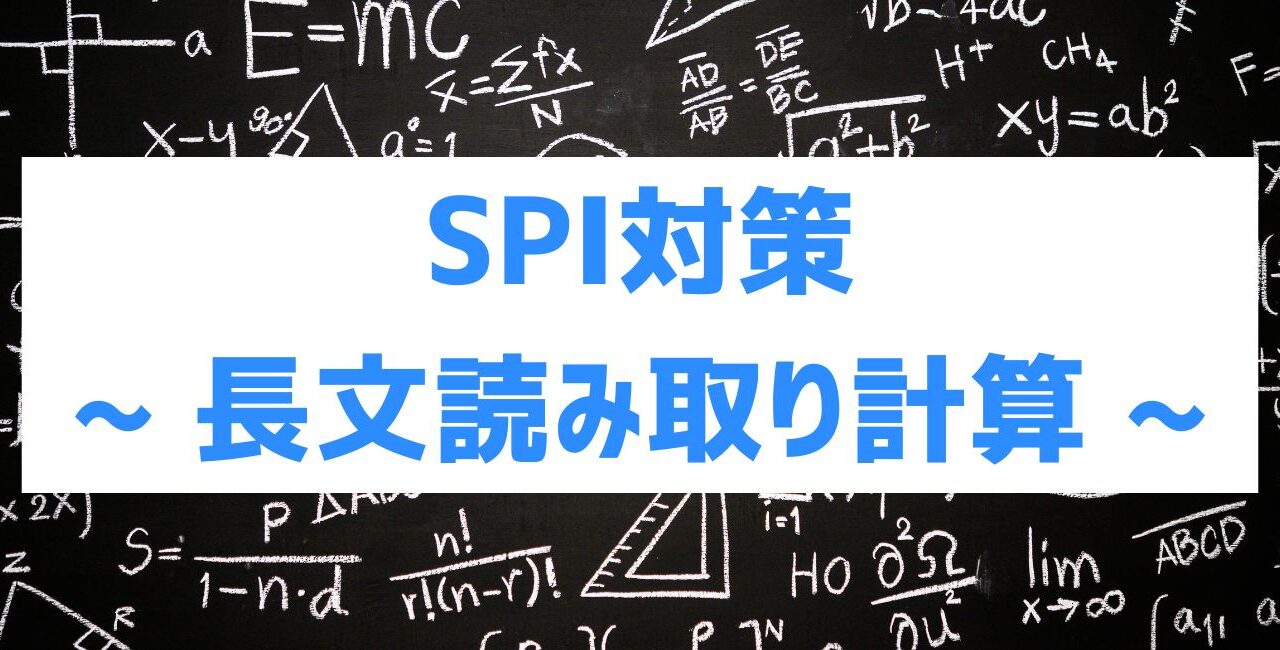【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
SPIの非言語分野において、苦手と感じる受験者が多いのが「長文読み取り計算」です。一見すると国語のような文章問題なのに、実はしっかり計算も求められる。そんな複雑さから、読み間違い・思い込み・時間オーバーなど、ミスをおこしがちな問題でもあります。
また長文の読み取り計算は、ただ計算が得意なだけでは解けません。読み取る力(読解力)と、情報を正確に処理する力(計算力)の両方が求められるからです。
とはいえ実は」出題されるパターンはある程度決まっており、「どの情報に注目すればよいか」「どの順で解けばよいか」といったコツを押さえることで、確実に得点できるようになります。
この記事では、長文読み取り計算に関して出題形式の傾向と特徴、正しく情報を読み取るための解法のコツ、頻出パターンを押さえた練習問題などを中心に、丁寧に解説していきます。数学が苦手な方も、考え方を理解すれば必ず対応できるようになるので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
SPIの長文読み取り計算とは
SPIの長文読み取り計算とは、文字どおり長い文章の中に埋め込まれた数値情報をもとに、計算問題を解くタイプの設問です。
通常の計算問題と異なり、問題文の中には無関係な情報や、一見してすぐに使えない条件なども含まれています。そのため、必要なデータを正確に抜き出し、式に落とし込む力が問われます。
このタイプの問題は、以下のような特徴があります。
- 複数人の行動や金銭のやり取りが含まれている
- 時間、距離、金額など複数の数値条件が入り混じっている
- 文章の中にある前提条件を正しく読み取らないとミスしやすい
たとえば、「AさんがBさんに1,000円を渡した後、BさんがCさんに300円借りた」など、登場人物のやりとりが時系列で続くケースでは、状況を図やメモで整理できないと混乱しやすくなります。逆に言えば、読み取りと情報整理のコツを身につければ、安定して得点できるようになるのがこの分野の特徴でもあります。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
長文読み取り計算の出題形式
ここではSPIの長文読み取り計算でよく出題される出題形式3つを紹介します。例題がついているので、ぜひ目を通してください。
複数人の行動や金銭のやりとりを含むストーリー型問題
このタイプは、Aさん・Bさん・Cさんなど複数の人物が登場し、それぞれの行動や金銭のやり取りを時系列に沿って追っていく必要があります。問題文は短編小説のように構成されていることが多く、読みながらメモを取りつつ登場人物の関係を整理していく力が求められます。
例題
Aさん、Bさん、Cさんの3人は、それぞれ7,000円、5,000円、4,000円を持っていました。
・Aさんは、Bさんに2,000円貸しました。
・Bさんは、そのうち1,000円を使ってCさんに昼食をおごりました。
・Cさんは、Aさんに500円を返しました。
このとき、最終的に最も多くのお金を持っているのは誰かを求めなさい。
【解き方】
・A:−2,000(→B)+500(←C)=−1,500→7,000−1,500=5,500円
・B:+2,000(←A)−1,000(→Cの昼食)=+1,000→5,000+1,000=6,000円
・C:+1,000(昼食をおごってもらう)−500(→A)=+500→4,000+500=4,500円
【答え】
Bさん(6,000円)
このとき、各人物の変化(増えた・減った)を記号で整理するのが有効です。AさんがBさんにお金を渡したなら、「A:−金額、B:+金額」と書く。これを一人ずつまとめておくことで、最終的な比較や合計の計算がスムーズになります。
時間や距離、金額など複数条件が含まれる問題
このパターンでは、数値が複数あり、条件が絡み合っているのが特徴です。例えば「往復にかかる時間」「購入する商品数と価格」「割引条件」などを同時に扱う必要があり、正しく情報を分類・整理する力が必要になります。
例題
あるオンラインショップでは、商品の送料が以下のように設定されています。
・注文金額が2,000円未満の場合は送料300円
・2,000円以上3,000円未満の場合は送料200円
・3,000円以上で送料は無料
田中さんは、1,800円の商品と1,200円の商品を購入しました。
さらに、ポイント割引として500円が適用されました。
このとき、田中さんが支払った合計金額を求めなさい。
【解き方】
・合計金額(商品代):1,800+1,200=3,000円
・ポイント割引後:3,000−500=2,500円
・送料条件:2,000円以上3,000円未満 →送料200円適用
・最終支払い金額:2,500+200=2,700円
【答え】
2,700円
どの条件がいつ適用されるか、単位(分・時間・円など)の整合性が取れているかを意識して読むことが重要です。すぐに計算に入るのではなく、情報を表に整理してから取りかかる癖をつけましょう。
前提条件を読み取ったうえで判断を求められる問題
「○○であることを前提としたとき、正しいのはどれか」など、条件の理解を踏まえて判断を求める形式も多く出題されます。計算式はシンプルでも、前提を読み間違えると正答にたどり着けません。
例題
ある塾では以下の条件で月謝が決まります。
・週1回のコース:月額6,000円
・週2回のコース:月額10,000円
・週3回以上は月額13,000円
佐藤さんは4月から通い始め、以下のようなスケジュールで通いました。
・1週目:2回
・2週目:3回
・3週目:1回
・4週目:2回
このとき、佐藤さんが選ぶべき最も合理的な料金プランはどれか。
【解き方】
・合計出席日数=2+3+1+2=8回(4週) → 平均2回/週
・週2回コースの条件に最も合致(週3は不規則)
・週2回コース(月額10,000円)が最適
【答え】
週2回コース(10,000円)
設問文の最後までしっかり読み、条件が途中で変わっていないか、計算すべき対象が明確かを確認することがポイントです。条件付きの正誤問題として解釈すると、選択肢の吟味がしやすくなります。
長文読み取り計算を解く時のコツ
ここでは長文読み取り計算を解く時のコツを3つ紹介します。
「条件」「数値」「質問」を3つに分けて読み取る
文章の情報量が多い長文問題では、最初からすべてを正確に理解しようとすると逆に混乱してしまいます。そこで、最初に行うべきは、出てくる情報を「役割ごとに分けて読む」ことです。
- 条件:問題を解くうえでの制限やルール(例:「○○円以上の買い物で割引が適用される」など)
- 数値:具体的な金額や人数、時間、距離などの数値情報(例:「商品Aは800円」「距離は30km」など)
- 質問:最終的に何を答えればよいのか(例:「最終的に所持金が一番多いのは誰か」など)
この3つを明確に意識して問題文を読むことで、必要な情報がどこに書かれているのかを見失わずに済み、整理しながら読み進めることができます。特に質問文の内容を把握しておくと、最初からゴールを意識した読み方ができるため、解答時間の短縮にもつながります。
メモや図を使って整理することで読み飛ばし・勘違いを防ぐ
長文問題でありがちなのが、「どこに何が書いてあったか分からなくなる」「1つ前の数値と混同してしまう」といったミスです。これを防ぐためには、手を動かして情報を可視化することが非常に有効です。
- 金銭のやりとり:登場人物ごとに増減を+・−で記録し、最終的な合計を出す
- 距離や時間の移動:線や図を描いて、どこからどこまで何km移動したかを可視化
- 複数の条件:表を作って、どの条件がどの項目に影響しているかを一覧で整理
視覚的に整理することで、文章から頭に入れる情報量が減り、記憶の混乱を防ぐことができます。また、メモをとっておくことで途中で迷ってもすぐに戻って見直せるのも大きなメリットです。
問題文を全部読んでから解くより、設問先読みで効率UP
長文問題では、読み始めた途端に情報が次々と出てくるため、最初から全文を読むと「どの情報が何に使えるか」が分からないまま読み進めてしまい、再度読み直すことになる場合があります。これを避けるためには、設問(質問)を先に読んでしまう戦略が非常に効果的です。
- 設問が「Aさんの所持金はいくらか?」→Aさん関連の情報に集中して読む
- 設問が「最も多く持っている人は誰か?」→全員の所持金を整理して比較すればよい
あらかじめゴールが分かっていれば、不要な情報を読み飛ばすことも可能になります。また、設問に応じて読み方のスタンスを変えることで、読むスピードや処理スピードが大きく上がり、時間短縮にもつながります。
問題のゴール(質問部分)を先に読んでおくと、読むべき情報と読み流してもいい情報の見極めができ、時間の短縮につながります。
長文読み取り計算の対策ポイント
次に長文読み取り計算の対策をする上で抑えるべき3つのポイントを紹介します。
時間配分の管理が重要。読みすぎ・考えすぎを避ける
SPIの非言語分野では、1問に使える時間は限られており、特に長文問題は読み取りと計算に時間がかかるため、「時間を意識した解答」が必須です。どんなに正確でも、時間内に解けなければ意味がありません。
例えば最初に問題を読んで「重そう」と感じたら後回しにする選択も大切です。丁寧に読みすぎて時間をロスするより、情報をメモにして即座に整理する意識をする方が時間配分しやすいです。
1問にかける時間の目安は2分程度。練習からタイマーを使って制限時間で問題を解くことに慣れ、もし3分を超える場合は本番前には制限時間内で解く練習を必ず繰り返しましょう。
時間管理の感覚を体に染み込ませておくことで、余裕を持って問題に取り組めるようになります。
語句・言い回しのパターンに慣れておくと処理が早くなる
SPIの長文計算では、文章に特有の「言い回し」や「条件提示の仕方」がよく出てきます。それらに慣れていないと、どんなに計算力があっても読み取りに時間がかかってしまいます。
- 「○○円以上購入で○○円引き」→割引の有無や計算の切り替えポイント
- 「AはBに○○円渡した」→お金の動きをプラスマイナスで即時整理
- 「移動時間は距離÷速さ」→単位換算を含む条件問題の基本公式
このような表現が繰り返し登場するため、模擬問題や過去問でパターンに慣れておくことが重要です。「読むのに時間がかかる文章」から「一目でパターンが分かる文章」へと感覚を変えることが、処理スピードの鍵になります。
文章の中にある「ヒントワード」に注目する癖をつける
SPIの長文問題では、答えにつながる重要な条件や変化が文中にさりげなく書かれていることがあります。これを見逃すと、大きな計算ミスや選択肢の選び間違いにつながります。
- 「その後」「続いて」「最終的に」→時系列の変化が起きたサイン
- 「もし~なら」「仮に~した場合」→条件付き計算や仮定の分岐ポイント
- 「合計で」「全体の中で」→総量比較や割合に関する設問の伏線
読みながら、こういった語句を見つけたら下線を引く・丸をつけるなど視覚的に強調して読む癖をつけましょう。ヒントワードを見つけることが、効率的な読み取りと計算精度を高める近道になります。
長文読み取り計算の練習問題3つ
それではこれまで解説したコツとポイントを意識して、以下の練習問題を3つ解いてみましょう。
問題1:3人の金銭のやりとりに関する計算問題
Aさん、Bさん、Cさんの3人がいます。はじめに全員がそれぞれ5,000円ずつ持っていました。・AさんはBさんに2,000円渡しました。・BさんはCさんに1,500円渡しました。・その後、CさんはAさんに1,000円返しました。
このとき、最終的に一番多くのお金を持っているのは誰ですか?
【解き方】
→A:−2,000+1,000=4,000円
→B:+2,000−1,500=5,500円
→C:+1,500−1,000=5,500円
【答え】
BさんとCさん(同額で最も多い)
問題2:移動と時間を含む条件整理型問題
あるバスは駅からショッピングモールまでを時速40kmで移動しています。Aさんはモールに行くため、午前10時にバスに乗り、10時45分に到着しました。
このとき、駅からモールまでの距離は何kmか?
【解き方】
→所要時間:45分=0.75時間
→距離=速さ×時間=40km/h×0.75時間=30km
【答え】
30km
問題3:前提条件をもとにした判断・比較問題
あるセールでは、1,000円以上の買い物をすると、合計金額から10%の割引が受けられます。Bさんは800円の商品と250円の商品を購入しました。Bさんは割引を受けられたでしょうか?
【解き方】
→合計:800+250=1,050円→割引適用対象
→割引額:1,050×0.1=105円
→支払額:1,050−105=945円
【答え】
受けられた(945円)
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
まとめ
SPIの長文読み取り計算は、「読む力」「情報を整理する力」「正しく計算する力」の3つが問われる、いわばSPI非言語分野の総合問題です。
「なんとなく読む」から「目的を持って読む」へ。
「なんとなく計算する」から「整理してから計算する」へ。
このように、読み方と解き方の質を上げていくことで、SPI本番でも落ち着いて対応できるようになります。ぜひこの記事で紹介した内容を活かして、今日から対策を始めてみてください。応援しています!