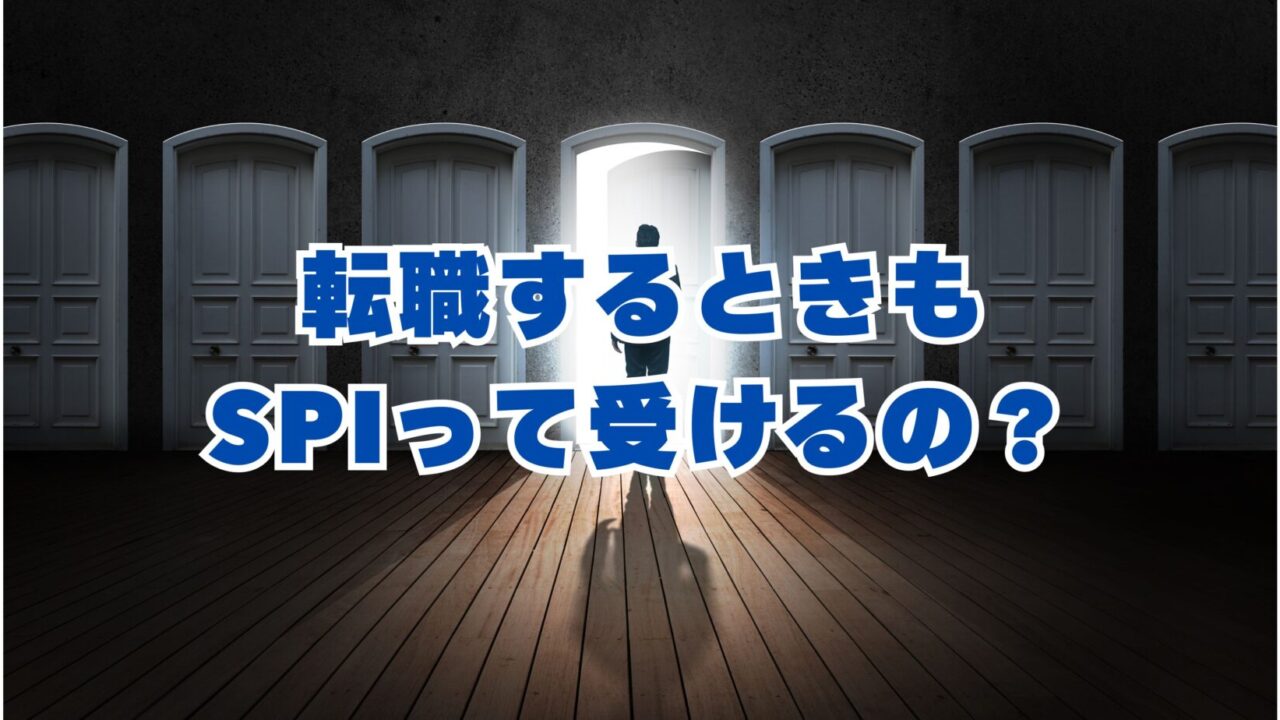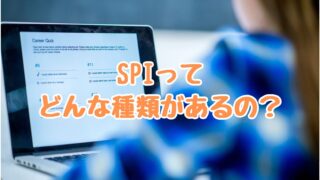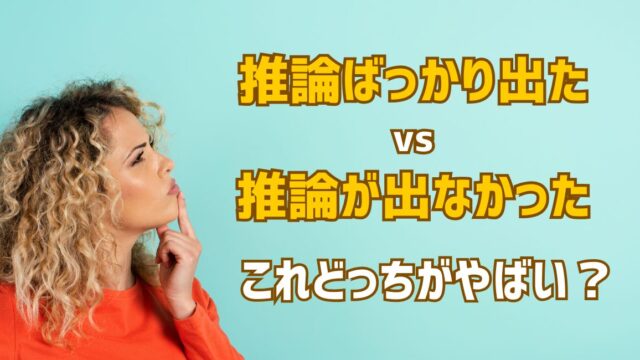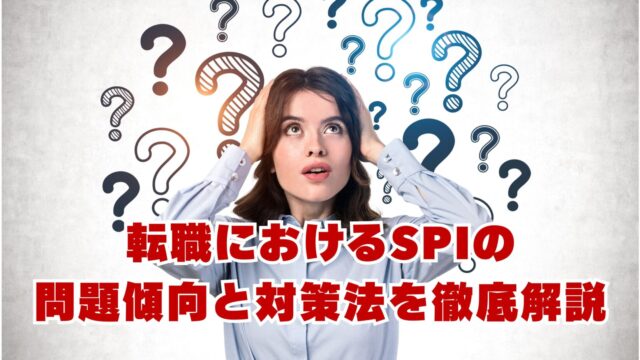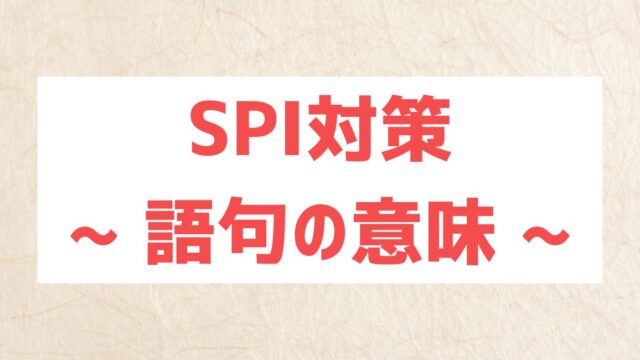【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「転職活動でもSPIって受けるの?」「新卒のときとは違うの?」——そんな疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか。新卒就活の定番ともいえるSPI(Synthetic Personality Inventory)は、実は中途採用の選考でも導入している企業が一定数存在します。
とはいえ、転職活動では職務経歴書や面接の比重が大きいイメージがあるため、「筆記試験なんてあるとは思わなかった」と不意打ちをくらうケースも少なくありません。中にはSPIの結果が原因で不合格になるケースもあるため、事前に知識をつけておくことは重要です。
本記事では、転職時にSPIが課される背景から、新卒との違い、出題されやすい分野、具体的な対策方法までを詳しく解説します。さらに、記事後半では【オリジナル診断チャート】や【業界別出題傾向】【SPIを課す企業一覧】など、実践的かつ最新の情報も掲載しています。
「SPIなんて久しくやってない…」という方も、「短期間で対策したい!」という方も、この記事を読めば必要な対策が見えてきます。さっそく見ていきましょう。
目次
SPIは転職でも使われる?
SPIというと新卒採用のイメージが強いかもしれませんが、実は中途採用SPIを活用している企業は多数存在します。特に一定規模以上の企業や、新卒・中途で一貫した採用基準を設けている会社では、筆記試験としてSPIを用いるケースが一般的です。
ここでは、なぜ企業が中途採用においてもSPIを導入するのか、そしてどういった業界・職種で多く用いられているのかを順に解説します。
転職者にもSPIが課される理由
転職希望者にSPIを課す背景には、応募者の「基礎的な能力」を測りたいという企業側の意図があります。職務経験が豊富な中途採用者であっても、基礎的な読解力・計算力・論理的思考力といったスキルが不十分であれば、入社後のパフォーマンスに影響が出る恐れがあります。
また、職種や業務の専門性が高まる中で、「即戦力」としての能力を客観的に評価するためにSPIを用いる企業が増えているのも事実です。応募者のバックグラウンドに左右されず、一定の基準でスクリーニングできるのもSPIの強みです。
企業がSPIを導入する目的
企業がSPIを採用フローに組み込む目的は大きく以下の3つです。
1つ目は、「基礎能力の可視化」です。履歴書や職務経歴書だけではわからない、論理的思考力や語彙力、数的処理能力などを客観的に測ることができます。
2つ目は、「選考の効率化」。大量の応募がある場合、SPIのスコアを基準に一定レベルの足切りを行うことで、選考にかかる手間やコストを抑えることができます。
3つ目は、「組織との適性確認」です。SPIには性格検査も含まれており、企業文化との相性やストレス耐性、協調性などをチェックすることも可能です。
SPIが実施されやすい業界・職種
SPIが転職時にも多く使われているのは、主に以下の業界・職種です。
- 大手IT・通信系企業:数的処理や図表問題を重視し、論理的思考が問われます。
- 金融・保険系:正確性やリスク管理能力を確認する目的でSPIを導入しているケースが多いです。
- メーカー・商社:全国一律の評価基準を設けるため、SPIを活用している企業が多数。
- 総合職・営業職:適性や対応力を重視し、SPIの結果が重視される傾向があります。
反対に、専門職やスキルが重視されるエンジニア、デザイナー、クリエイティブ系職種ではSPIを実施しない企業も増えています。ただし、企業規模や採用方針によって運用が異なるため、応募先の情報は事前にしっかり確認しておきましょう。
転職向けSPIと新卒向けSPIの違い
「SPIって学生向けの試験じゃないの?」と思っている方も多いかもしれませんが、実際には転職者向けに内容が一部調整されている場合もあります。とはいえ、基本的な構成は新卒と同様で、言語・非言語・性格検査の3つのパートから成り立っています。
では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、問題の難易度や傾向、そして適性検査の内容に焦点を当てて解説します。
問題の難易度や傾向は違う?
SPIの難易度そのものは、新卒と中途で大きく異なるわけではありません。しかし、転職向けに出題される問題では、より実務に近い思考力や判断力が問われる傾向があります。
たとえば、非言語分野では単純な計算問題よりも、ビジネスシーンを想定した図表の読み取りや論理的な推論問題が出題されやすくなっています。言語分野でも、一般常識に近い語彙や読解力が問われることが多く、学生向けよりもやや実務的な文脈での理解力が重視されるケースが目立ちます。
また、時間制限が厳しく設定されていることが多いため、内容の理解だけでなく「素早く正確に処理する力」がより重要になります。
適性検査(性格診断)は同じ?
SPIの性格検査は、新卒・中途に関わらず基本的には同じ形式です。多くの設問に短時間で直感的に答えていくことで、「ストレス耐性」「チーム適性」「主体性」「几帳面さ」などのパーソナリティを測定します。
ただし、転職者の場合は企業側も「即戦力」「社風との適合度」を重視するため、新卒のようにポテンシャル採用とはやや異なる観点で結果を見ています。たとえば、過去の業務経験からくるリーダーシップや安定感が求められる場面では、性格検査の結果が選考に影響を与える可能性もあります。
また、企業によってはSPIの性格検査を「入社後の配属先の参考資料」として利用することもあるため、変に背伸びをせず、自分の素直な性格を反映することが大切です。
SPIの試験形式と受検方法
転職活動でSPIを受けることになった場合、試験の形式や受検方法について事前に知っておくことが重要です。SPIには複数の受検方式があり、どの方式が採用されるかによって準備すべきポイントも変わってきます。
このセクションでは、SPIの代表的な受検方法の種類や、それぞれの違い、受検日や場所の決まり方まで詳しく解説します。
SPIには4つの受検方法がある
SPIの受検方法は、大きく以下の4つに分類されます。
- テストセンター受検
リクルートの指定する会場(テストセンター)に赴いてPCで受検する形式です。設備が整っており、カンニング対策も施されているため、企業側が信頼を置いている形式です。多くの大手企業で採用されています。 - Webテスティング受検
自宅など、インターネット環境のある場所で受検できる方式です。受検者の利便性は高いものの、不正対策が弱いため、企業によっては利用を避ける傾向もあります。 - ペーパーテスティング受検
紙の問題用紙を使って受検する昔ながらの形式です。SPIが普及する前から用いられていた方式で、主に地方の企業や中小企業で見られます。 - インハウスCBT受検
企業が独自に準備した会場(本社や支店など)でパソコンを用いて受ける方式です。テストセンターに近い環境ながら、企業が主導して運営するため、日程の自由度が高いのが特徴です。
テストセンターとWebテスティングの違い
多くの転職者にとって馴染みがないのがテストセンター方式ですが、これはリクルートが運営する専用の試験会場で受検するもので、都心部を中心に全国主要都市に設置されています。試験監督員の管理下で受検するため、信頼性が高く、企業側からの評価も安定しています。
一方、Webテスティングは自宅で受けられる反面、受検環境が人それぞれ異なるため、公平性に課題があります。そのため、企業によっては性格検査だけをWebで済ませ、本番の筆記は別形式で実施することもあります。
どちらもPCを用いた試験ですが、制約や評価の重みが異なるため、事前に指定された方式を確認した上で準備を整えることが重要です。
受検日・場所はどう決まる?
SPIの受検日や場所の決定方法は、採用企業の運用方法によって異なります。テストセンター受検の場合は、企業から案内されたURLにアクセスし、自分で空いている日程・会場を選んで予約する形式が一般的です。
一方、WebテスティングやインハウスCBTでは、企業が指定した期間内であればいつでも受検可能な「期限付きフリー受検」スタイルが多く採られています。受検案内のメールが届いたら、できるだけ早めに受検することをおすすめします。
なお、案内が来てから受検できるまでの期間は短いことが多いため、日頃からSPIの形式に慣れておくと安心です。
SPIで出題されやすい問題と対策のポイント
SPIでは、大きく分けて「言語分野」と「非言語分野」の2つが出題されます。これらは中途採用でも出題範囲に大きな差はなく、どちらも基礎学力と論理的思考力を測るための重要な指標とされています。
ただし、出題される問題の種類にはある程度のパターンがありますので、効率よく対策するためには「よく出る問題」を把握しておくことが近道です。この章では、言語・非言語それぞれの出題傾向と対策のポイントについて詳しく解説します。
よく出る問題カテゴリ(言語・非言語)
SPIの問題は、言語・非言語のどちらもいくつかのカテゴリに分けられます。
言語では、主に語彙力・読解力・論理的整合性などが問われる問題が出題されます。具体的には「二語の関係」「空欄補充」「長文読解」などです。
非言語では、計算力や論理思考が中心になります。「集合」「表の読み取り」「順列・組合せ」「割合」「損益計算」「確率」など、数学的な知識をベースにした問題が多く出題されます。
これらは暗記よりも「考える力」や「手を動かして計算する力」が問われるため、問題形式に慣れておくことが最も効果的です。
SPI非言語の定番問題とは
非言語分野では、特に以下のような問題が定番です。
- 表の読み取り
グラフや表をもとに情報を読み取り、設問に答える形式。スピードと正確さのバランスが問われます。 - 損益算・割合計算
利益率や割引率、費用対効果などを計算する問題で、ビジネスシーンにもつながる実用的なテーマが多く含まれます。 - 確率・組合せ
確率的な事象の発生率や、ものの並べ方・取り方を問う問題。基本公式に加えて「条件設定」に注意が必要です。
これらの問題に共通しているのは、**「問題文を読み解く力」と「手計算の速さ」**です。慣れていないと時間切れになる可能性が高いため、繰り返し練習を通じてスピード感を養いましょう。
SPI言語分野で出やすい問題
言語分野は比較的取り組みやすく感じるかもしれませんが、意外と落とし穴が多いのも特徴です。特に以下の問題は頻出なので要注意です。
- 二語の関係
2つの単語の関係性を把握し、同様の関係を持つ語を選ぶ問題。語彙力だけでなく、論理的な思考が求められます。 - 空欄補充
文中の空欄に適切な語句を補う問題。文脈把握力と日本語センスが問われるため、選択肢を慎重に比較することがカギです。 - 長文読解
あるテーマに関する文章を読んで、設問に答える形式。内容一致・要旨把握など、ビジネス文書的な文章が出ることも多く、読解スピードが重要になります。
これらの問題では、「日頃から文章に慣れているかどうか」が点差に大きく影響します。苦手意識のある方は、まずは短文問題から練習し、徐々に難易度を上げていくのがおすすめです。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPI対策レベル診断チャート
「SPI対策、どこから手をつければいいかわからない」「そもそも自分のレベルがわからない」——そんな方のために、ここではSPI対策レベルを自己診断できるチャートをご用意しました。
簡単な質問に答えるだけで、あなたが今どの段階にいるのかがわかり、そのレベルに合わせた対策法を提案します。
あなたはどのタイプ?診断スタート!
以下の質問に「はい」または「いいえ」で答えてください。
- 数学が苦手で、計算問題は見るだけでストレスを感じる
- SPIがどんな試験か、正直あまり理解していない
- 試験問題を時間内に解き終えられたことがほとんどない
- 問題集やアプリを開く習慣がまだできていない
- 問題のパターンや出題形式が覚えられていない
「はい」が4つ以上:初級者タイプ
SPI未経験で何から手をつければいいか迷っている方。まずは基本問題と用語の解説から学びましょう。問題集の1冊目は「全体像をつかむこと」に集中し、苦手分野の把握を優先してください。
「はい」が2〜3個:中級者タイプ
問題を見ればある程度解けるが、スピードがついてこないタイプ。演習問題を通して時間配分トレーニングを強化しましょう。実際の試験形式に合わせた模試やアプリを使うのがおすすめです。
「はい」が0〜1個:上級者タイプ
得点力もあり、形式にも慣れている方。SPI対策に時間をかけすぎるより、面接や職務経歴書のブラッシュアップにシフトしても問題ありません。あえて言えば、苦手な1分野だけを集中的に補強しておくと万全です。
診断結果に応じた対策本や勉強法は、次章で詳しくご紹介します。
転職者におすすめのSPI対策法
「転職でSPIがあると知らなかった」「準備期間が短くて不安」という方でも、ポイントを押さえた対策を行えば十分に対応可能です。特に社会人は勉強時間を確保しにくいため、効率的かつ実践的な学習が鍵となります。
このセクションでは、短期間で結果を出すための具体的な対策法を3つ紹介します。
短期間で効率よく仕上げるには
転職活動では限られた時間の中で準備を進める必要があります。そのため、まずは「出題される形式」と「頻出パターン」に絞って取り組みましょう。すべての分野を網羅的に勉強するのではなく、自分の苦手分野と出題頻度が高い分野に集中することがポイントです。
特に非言語分野は時間を要するため、苦手意識がある場合は早めの着手がおすすめです。言語分野は比較的点が取りやすいので、短時間でも得点を伸ばしやすい領域です。
また、SPIはスピードも求められるため、「満点を取ろうとしない」意識も大切です。解ける問題を確実に得点する戦略で臨みましょう。
模試やアプリを使って慣れる
本番形式に近い練習を積むことは、対策の中でも非常に重要です。市販の模試問題集やSPI専用アプリを活用することで、時間配分や解答スピードを自然と身につけることができます。
とくにアプリはスキマ時間に取り組めるため、移動中や就寝前など、日常生活に無理なく取り入れられます。問題のバリエーションも豊富なため、苦手分野を繰り返し対策するにも効果的です。
実際の試験と同様の制限時間で解く練習を何度も行い、時間内に一定の問題数を解くリズムを体に染み込ませましょう。
頻出パターンに絞って対策する
SPIでは、過去の出題傾向から一定の「お決まり問題」が存在します。たとえば、非言語であれば「表の読み取り」や「損益算」、言語であれば「空欄補充」や「二語の関係」などです。
こうした頻出パターンに絞って対策を進めることで、効率よく得点力を高めることができます。解き方に慣れれば、見た瞬間に「あ、これはこのパターンだ」と判断できるようになるため、時間短縮にも直結します。
自分の診断タイプ(前章参照)に応じて、「基本の型を覚える」「時間配分を意識する」「弱点を潰す」といったテーマで学習計画を立てましょう。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPIで落ちることはある?
「SPIはあくまで参考程度」「経験重視の中途なら大丈夫」——そんな油断が、思わぬ足元をすくうことがあります。実際、SPIの結果が原因で書類選考を通過しても次の面接に進めなかった、という事例は少なくありません。
ここでは、SPIスコアが選考に与える影響と、企業ごとの基準の違いについて解説します。
SPIスコアが合否に与える影響
SPIの結果が選考にどう影響するかは、企業によって温度差があります。完全に「足切りライン」として使っている企業もあれば、あくまで参考情報として扱っている企業もあります。
しかしながら、大手企業や応募者が多い企業ほど、SPIを合否の明確な判断材料としているケースが多いのが実情です。特に、以下のようなケースではSPIスコアが重視されやすくなります。
- 書類だけでは候補者の学力が判断しにくい場合
- 類似経歴の候補者が多数いる場合
- 職種に計算・読解スキルが強く求められる場合
このような背景から、「SPIで落ちる」ことは十分にあり得ると考えて対策をしておく必要があります。
通過基準は企業ごとに異なる
SPIの合否基準は、非公開であることがほとんどです。そのため「何点以上取れば安心」といった明確なラインは存在しません。ただし、一般的に高得点を取るためには、非言語・言語ともに正答率70~80%以上が目安とされています。
また、SPIには性格検査も含まれているため、単純な正答数だけでなく、「回答の一貫性」「極端な偏りがないか」といった観点も評価対象になる場合があります。性格検査で不自然な回答が続くと「取り繕っている」と判断される可能性もあるため、自然体で回答することが大切です。
さらに、SPIのスコア評価方法は企業ごとに設定が異なります。ある企業では総合スコア重視、別の企業では言語スコア重視という場合もありますので、受験する企業の業界・職種の傾向を押さえておくと安心です。
業界別SPI出題傾向まとめ
SPIの内容は基本的に統一された形式ですが、実際には「どの問題が重視されやすいか」は業界によって異なります。なぜなら、各業界で求められる人物像や業務上のスキルが違うからです。
この章では、代表的な業界ごとのSPIの出題傾向をまとめました。「この業界を受けるなら、何に力を入れて対策すべきか?」を把握する参考にしてください。
業界によって重視される問題は異なる
IT・Web系:論理的思考とスピード重視。非言語で図表問題が頻出
ITやWeb系の企業では、情報を素早く処理し、的確に分析する力が求められます。そのため、非言語問題の中でも「表の読み取り」や「順序整理」「場合の数」など、論理的思考を要する問題が頻繁に出題されます。
また、時間配分のスピード感も見られているケースがあるため、「早く・正確に解く」訓練が有効です。
金融・保険系:正確性と計算力が問われるため、非言語対策が必須
数字に対する信頼性が業務の根幹にある金融・保険業界では、非言語の中でも「損益算」「割合」「確率」「金利の計算」など、計算力を重視する問題がよく出題されます。
ミスなく正確に答えられるかが評価につながるため、計算問題を丁寧に解く練習が欠かせません。計算が苦手な方ほど、ここは重点対策が必要です。
メーカー・商社系:言語問題・性格適性重視の傾向
メーカーや商社では、論理的な読解力やコミュニケーション能力、そして組織適性が重要視される傾向にあります。
そのため、言語分野では「長文読解」「空欄補充」「二語の関係」が中心に出題され、性格検査では「協調性」「責任感」「主体性」などが評価されやすくなっています。
サービス・流通系:Webテスティングで手軽に実施されるケース多数
人材の流動性が高く、多数の応募がある業界では、コストとスピードの観点からWebテスティング方式が選ばれることが多くなっています。
内容的にはバランス重視で、言語・非言語の基本的な問題が中心。手軽に受けられるぶん、準備不足での失点も多いため、最低限の対策が必要です。
SPI受検時に気をつけたい注意点
SPIを受けるにあたっては、試験対策だけでなく「当日の環境や心構え」も合否に関わる重要なポイントです。特にWebテスティング方式では受検者側の準備に依存する部分が大きく、思わぬミスでスコアが下がることもあります。
ここでは、SPI受検時にありがちなトラブルや失点リスクを防ぐための注意点を紹介します。
受検環境に関する注意
自宅で受けるWebテスティング形式では、試験中の通信環境や周囲の騒音が大きなストレスになります。試験が中断したり、集中力が切れたりすると、本来の実力が発揮できません。
以下のような点に注意して環境を整えましょう。
- 通信環境はWi-Fiより有線が理想
万一の回線不安定化を防ぐため、可能であればLAN接続を推奨します。 - 静かな部屋で受検する
家族やペットの声、外の騒音などが気になる場合は、時間帯や部屋の選定を工夫しましょう。 - マウスと電卓の準備
非言語分野ではマウス操作や手元の計算効率が得点に直結します。テンキー付きのキーボードもあると便利です。
企業によっては「外部ツール禁止」「カメラONでの監視型」などルールがあるため、事前に指示内容をよく確認しておきましょう。
時間配分ミスで点を落とさないために
SPIは試験時間が限られており、問題によっては1問につき数十秒しかかけられないこともあります。そのため、「完璧主義でじっくり解こうとする」タイプの人ほど時間配分に失敗しやすい傾向があります。
特に注意したいのは以下の点です。
- 時間のかかる問題に固執しない
1問にこだわりすぎると、後半の簡単な問題を解く時間がなくなります。 - 最初に問題全体の構成を確認する
出題パターンを先に把握し、解ける問題から優先して取り組むことで、得点を伸ばしやすくなります。 - 「あと〇分」の表示を常に意識する
画面上に残り時間が表示されている形式では、時間の進みを意識的に確認するクセをつけておくと安心です。
SPIは満点を狙う試験ではありません。「いかに得点源を落とさずに拾えるか」が勝負の分かれ目です。
よくある質問(FAQ)
転職活動中にSPIを受けることが初めての方にとっては、不安や疑問も多いものです。ここでは、受検者からよく寄せられる質問に答える形で、事前に知っておくべきポイントをQ&A形式で紹介します。
勉強時間はどのくらい必要?
人によって異なりますが、目安としては10~20時間程度の対策で基本的な問題に対応できるレベルになります。短期集中で対策するなら、1日30分〜1時間を2〜3週間続けると効果的です。
初学者や数学に苦手意識のある方は、30時間ほど余裕を見ておくと安心です。反対に、SPIに慣れている人や以前に受けたことがある人は、模擬試験数回+復習だけでも対応可能な場合もあります。
SPIを受ける前に準備しておくべきこと
受検形式にかかわらず、以下の3つは事前に準備しておきましょう。
- 試験形式の確認(テストセンター・Webテスティングなど)
- 使える文具やPC環境の準備
- 模擬問題やアプリでの予習
とくにWeb受検の場合は「途中で回線が切れたらどうなるか」なども企業の案内に記載されているので、細かい点まで確認しておくと安心です。
何日前に受検案内が来るの?
企業や選考ステージによって異なりますが、書類選考通過後すぐに案内が届き、受検期限が3〜5日後というケースが一般的です。
特にテストセンター形式では早めに予約しないと希望日時が埋まってしまうこともあるため、案内が来たらすぐに対応するようにしましょう。
また、応募後しばらく経ってから突然SPIの案内が届くケースもあるので、選考が進んでいる企業については、常に準備しておく意識が大切です。
SPIを課す企業一覧(2025年最新版)
「この企業ってSPIあるの?」「どの形式で受けるの?」と不安に思う方のために、ここではSPIを選考に取り入れている代表的な企業を一覧でご紹介します。
企業ごとにSPIの出題形式や受検のタイミングも異なるため、志望企業の傾向を事前に把握しておくことで、対策の方向性が明確になります。気になる企業がある場合は、ブックマーク推奨です。
実際にSPIを課している企業リスト
| 企業名 | 業界 | SPI実施の形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 株式会社NTTデータ | IT | テストセンター | 技術職対象。得点重視の傾向あり |
| 三井住友信託銀行 | 金融 | 自宅受検(Web) | 適性検査を重視。性格診断が評価に直結 |
| パナソニック株式会社 | メーカー | テストセンター | 総合職採用にてSPI導入。面接前に実施 |
| 楽天グループ株式会社 | IT・EC | Webテスティング | 初期選考段階で実施。通過基準がやや高め |
※上記情報は2025年現在の選考傾向をもとに作成。企業ごとに変更される可能性がありますので、最新情報は各社の採用ページでご確認ください。
まとめ
転職活動におけるSPIは、新卒と同じようでいて、求められる観点や対策方法が少し異なります。特に社会人経験者としての「地頭力」や「スピード感」が見られており、準備を怠ると意外なところで足元をすくわれてしまうこともあります。
とはいえ、SPIには出題傾向や頻出パターンがあるため、正しく情報をつかみ、効率的に学習を進めれば、短期間でも十分に高得点を狙えます。
本記事で紹介した「レベル別診断チャート」や「業界別出題傾向」「SPIを課す企業一覧」などを活用しながら、自分に合った勉強法と教材を選び、対策を進めてください。
転職活動は、限られた時間の中で成果を出すことが求められる場面です。SPI対策もその一部として、今から少しずつ取り組んでおくことで、本命企業のチャンスをしっかりつかみにいけるはずです。
効率的な準備で、自信をもってSPIに臨みましょう。応援しています!