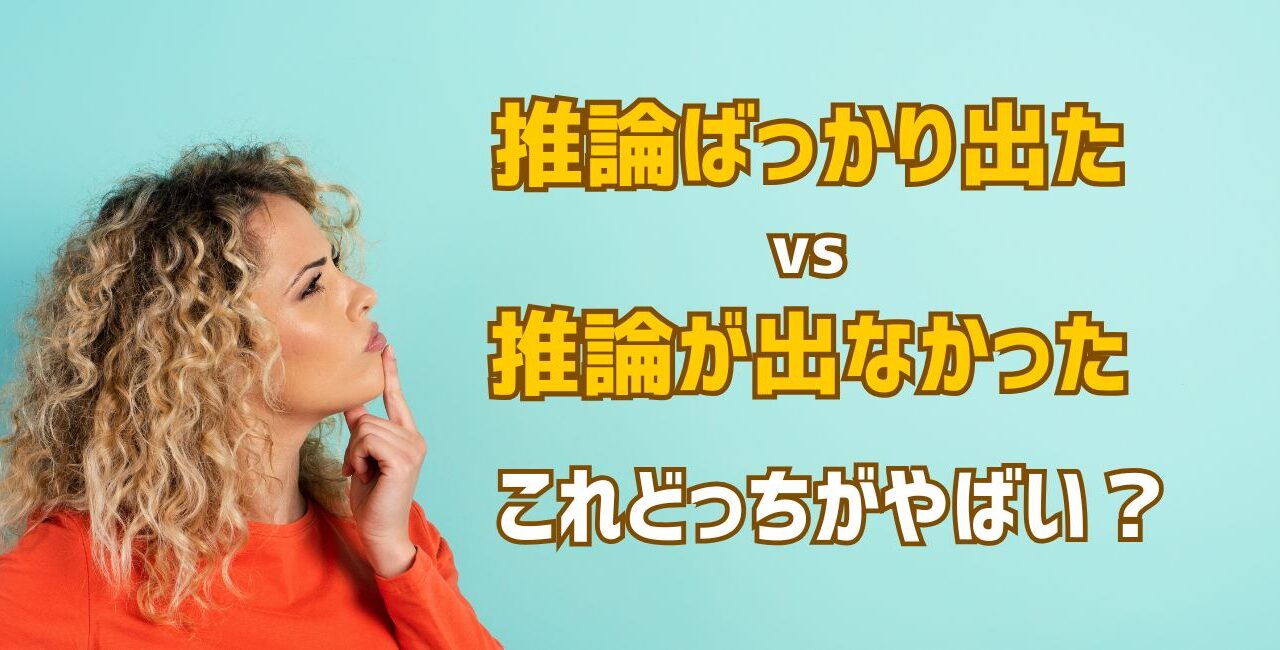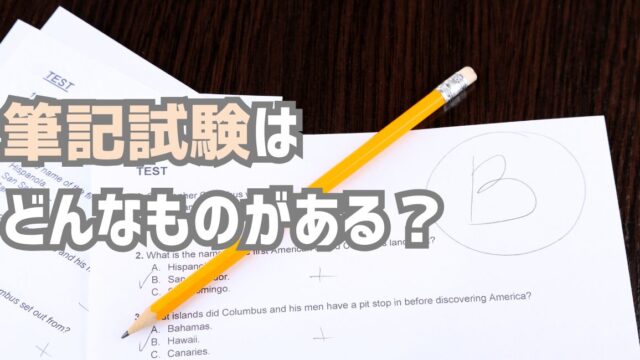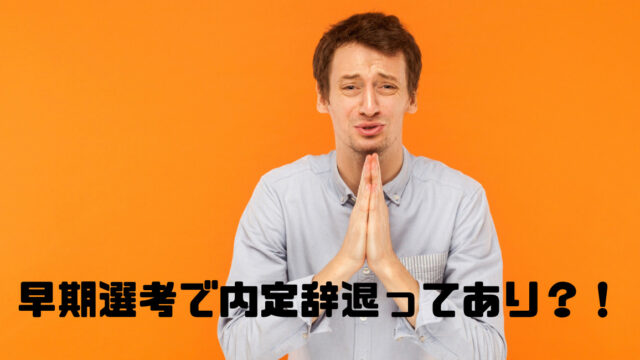【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
SPIの非言語問題を解いたのに、推論がまったく出なかった…
逆に推論ばかり出て、計算問題が少なかった…
こうした体験をしたり、体験談をSNSや掲示板で目にして、不安になったことはありませんか?SPIを受験する就活生の多くが出題内容の偏りに不安を感じています。その中でも特に「推論」に対する疑問や戸惑いの声が多く聞かれます。
SPIの推論問題は本来頻出の重要なパート。しかし、受験方式や正答率、企業ごとの出題設定によって、出るときは集中して出る/出ないときはまったく出ないということも十分に起こり得るのです。
この記事では、
・SPIの推論が出る・出ない理由は?
・推論が多かった=高スコア?
・推論を捨てるのはアリなのか?
・推論が出なかったらどうすれば?
といった就活生の疑問にひとつひとつ答えながら、SPIの推論問題にどう向き合えばよいかを丁寧に解説します。受験前の不安を和らげたい人、試験後のモヤモヤを解消したい人、そして今から対策を練り直したい人に向けて、役立つ情報をわかりやすくお届けします。
目次
SPI非言語で推論は最頻出分野の1つ
推論問題は、SPIの非言語分野の中でも出題頻度が非常に高く、毎年ほぼ確実に出題されます。問題の内容はバラバラですが、基本的には論理的思考力を問うものとなっています。
問題で与えられる限られた情報から筋道を立てて考え、答えに辿り着きましょう。
「Webテスティングでは推論が出ない」との噂もあるが間違い
一部で「Webテスティングでは推論が出ない」という噂が流れていますが、結論から言うとこれは誤解です。
Webテスティングでも推論問題は出題されます。出題される形式や量が異なるだけで、問題としてはしっかり含まれているので油断禁物です。
推論の出題数は受験方式で異なる
SPIには複数の受験方式がありますが、代表的なのが「テストセンター方式」と「Webテスティング方式」です。実はこの2つでは、推論問題の出題タイミングや頻度に大きな違いがあります。
・テストセンター方式
正答率に応じて、出題される問題の難易度や分野が変わる方式。推論問題は正答率が高いほど多く出題される傾向があります。推論問題に正解すれば正解するほど、推論が出てくるイメージです。
・Webテスティング方式
問題の出題順と内容が固定されている方式。最初から順に問題が出題され、途中で変更されることはありません。推論問題は中盤あたり(全体の半分前後)に3〜4問程度含まれているケースが多いとされています。
つまり、「推論の出題が多かった・少なかった」といった現象には、試験形式が深く関係しているということを理解しておきましょう。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPIで推論ばかり出たら高スコア?
では早速本題のSPIの非言語で推論ばかり出た場合は、どんなことを意味するのかを解説します。
Webテスティングの場合:事前に決まっているから判断できない
まずWebテスティング形式では、問題の出題順と出題内容があらかじめ決まっています。そのため、推論が多く出たとしても、それが「高スコアを取れている証拠かどうか」は判別できません。
推論問題が3〜4問出る構成はよくあるパターンであり、単純にそのパートに強く印象が残っただけという可能性もあります。
テストセンターの場合:正答率が高い証拠でスコアが期待できる
一方で、テストセンター方式の場合は話が変わります。
前述した通りテストセンターは正答率に応じて、出題される問題の難易度や分野が変わる方式なので、受験者の解答状況に応じて次の問題の内容や難易度が変わる仕組みです。つまり、正答率が高い受験者には、より難しい問題、つまり推論が多く出題されやすくなるのです。
言い換えれば、SPI非言語で推論問題ばかりが出てきたとしたら、それは非言語問題の正答率が高いと推測され、スコアが高い可能性が十分にあるということです。
テストセンターでの推論の出題数とスコア目安
以下に、テストセンター方式での推論出題数とスコアの関係性を段階別に紹介します。※あくまで目安です。
(スコアが低い)
①推論が出ない
②推論が1〜2問出る
③推論が全体の半分程度出る
④推論が半分以上出る(そのうち4タブ問題あり)
⑤推論が半分以上出る(チェックボックス形式が1問含まれる)
⑥推論が半分以上出る(チェックボックス形式が2問含まれる)
(スコアが高い)
このように、推論の出題割合が多く、かつ問題形式が複雑になっていくほど、非言語分野のスコアが高いと推定されます。逆に、推論がまったく出なかった場合は、非言語の正答率が低く、スコアも振るわなかったと受け取ることができます。
SPIで推論が出ないとやばい?
「推論が1問も出なかったんですが、大丈夫ですか?」
こんな声をよく聞きます。特にSNSなどで「推論ばかり出た」という報告を見た直後だと、自分との違いに不安を感じる方も多いはずです。
ただし、推論が出なかった=絶対に落ちるというわけではありません。以下のポイントを押さえて、冷静に判断しましょう。
出題形式は企業によって異なるされる
SPIは出題形式が企業ごとに異なります。つまり、ある企業のSPIでは推論が出題されない設定になっている可能性もあるということです。
特にWebテスティングでは、受験者全員が同じ問題を解く形式なので、企業側の方針によって、推論の代わりに図表や確率などが多く出るケースもあります。
また、選考段階によっても問題構成が変わることがあるため、「たまたま出なかった」可能性があるのです。
テストセンターで推論が出ないと高スコアは期待しにくい
一方で、テストセンター形式の場合は、推論が出なかったら注意が必要です。
前述した通り、テストセンターでは正答率が高いほど、難易度の高い推論問題が多く出題される仕組みです。つまり、推論がまったく出なかった=正答率が低く、スコアがあまり伸びていないと推測できます。
この場合は、次回以降のSPI対策に向けて、非言語全体の基本問題(割合、表、速さなど)を見直しつつ、推論への対応力も磨いておくと安心です。
推論以外の問題で差がつく場合もある
とはいえ、非言語は推論だけで構成されているわけではありません。他にも出題される分野はたくさんあり、図表・割合・確率・集合・順列・長文読み取りなど、スコア源になりうる問題は多く存在します。
そのため、たとえ推論が出なかったとしても、それ以外の分野でしっかり正解を積み重ねていれば、合格ラインに乗ることは十分可能です。
大切なのは出題形式のブレに振り回されすぎないことです。次の選考や別の企業で推論が出る可能性もあるので、備えはしておくべきですが、出なかったことを必要以上に気にする必要はありません。
SPIで推論は捨てていい?
SPI非言語の中でも推論は難易度が高く、苦手に感じる人も多い分野です。問題文が長く、選択肢も紛らわしく、しかも時間もかかるため、「もういっそ推論は捨てた方がいいのでは?」と考えたことがある人も少なくないと思います。
ですが、結論から言えば基本的に捨ててはだめです。
特に足切りがある大手や人気企業志望の人は絶対に捨てられない
SPIでは、企業側が非言語・言語それぞれに「足切りライン」を設けている場合があります。つまり、全体でバランスよくスコアできないと、ほかのセクションで高スコアでも不合格になることがあるのです。
大手・人気企業になればなるほどこの傾向は強く、非言語での安定したスコアが必須条件。
そして非言語の中でも「推論」は差がつきやすいパートなので、ここを捨ててしまうと一気に選考通過の可能性が下がってしまうというわけです。
もし捨てるなら他の分野は絶対に落とせない
「どうしても推論が苦手で、もう手をつけられない…」という人もいるかもしれません。その場合は、他の分野を完璧に仕上げる必要があります。
つまり、推論を捨てる=他で落とさないための負荷が倍増する、ということになります。
時間や労力の配分を考えたとき、「推論対策に時間を割くvs他分野を完璧に仕上げる」を天秤にかけると、実は推論をある程度解けるようにする方が圧倒的に効率的です。そのため他の分野を完璧にするよりも、推論を捨てずに対策することをおすすめします。
推論は「慣れ」でかなり点数が取れるようになる分野。パターンを掴めば、短時間で正答にたどり着けるようになります。
最初は苦手でも、形式ごとに解法を練習すれば確実に成果がみるはずです。
SPIの推論が苦手でも安心!推論の攻略方法
「推論は難しいし、なんとなく避けてきた…」という方も多いですが、実は推論には明確なパターンと攻略ステップがあります。感覚で解くのではなく、手順を踏んで論理的に処理する練習を重ねれば、誰でもスコア源にすることができます。
ここでは、よく出る推論の形式と、それを攻略するための具体的な手順を紹介します。
よく出る形式を事前に押さえる(正誤・順序・対戦など)
SPIの推論問題には、いくつかの典型パターンがあります。まずはこの形式を把握しておくだけでも、問題に取り組む際の心理的ハードルが下がります。
- 正誤問題:文章内の条件をもとに、結論の正誤を判断するタイプ
- 順序問題:複数人や複数項目の順位や並び順を推理するタイプ
- 対戦結果問題:勝敗やスコアをもとに、順位や勝者を導き出すタイプ
- 割合や関係性の推理:グループの条件や割合から結論を導くタイプ
- チェックボックス問題:複数の選択肢から、正しいものを複数選ぶタイプ(難易度高め)
これらの形式は、いずれも情報整理・図解・消去法を使うことで、正確に解けるようになります。苦手な人は、まず順序問題や対戦結果問題など、視覚的に整理しやすいタイプから慣れていくのがおすすめです。
推論問題を早く・正確に解く3つのステップ
どの形式の推論でも、以下の3ステップを意識すれば、正解にたどり着くスピードと精度が格段に向上します。
コツ①:「情報整理」が最優先
まず最初にやるべきことは、問題文に書かれている条件を一つずつ整理することです。頭の中だけで処理しようとすると、情報がごちゃごちゃになりがちなので、紙やメモ機能を使って、整理する癖をつけましょう。
・条件を一文ずつ書き出す
・人物ごとに条件をまとめてみる
・表やメモにして、あとから確認しやすくする
情報を「目で見える形にする」ことで、ミスを減らせます。
コツ②:「全体像」を図でつかむ
条件を整理したら、それらの情報をもとに図にしてみることが重要です。例えば順序問題なら横に並べる、対戦なら勝敗表を作るなど、図にすると関係性が一気にわかりやすくなります。
・順位→□□□□で埋めていく
・勝敗→○×表を作って勝ち数・負け数を整理
・条件付きの人数→ベン図や表を使って記入
視覚化することで、複数の条件が矛盾していないか、何が分かっていて何が未確定なのかがクリアになります。
コツ③:「当てはめ・除外」で正答を絞る
最後に行うのが、当てはまりそうな選択肢を試しながら、消去法で絞っていくステップです。推論問題の選択肢は、意外と「1つの条件にだけ反しているもの」が多いので、落ち着いて確認すれば必ず矛盾に気づけます。
・条件に合っていない選択肢を即除外する
・可能性がありそうなものは仮置きして、他の条件と照らす
・1つずつ確認していく姿勢が大切
焦らず、手順通りに進めれば、感覚やひらめきに頼らなくても正答を導けるようになります。
「推論が苦手=頭が悪い」ではなく、「解き方を知らないだけ」です。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPI推論に関するよくある質問
推論問題に関しては、SPIを実際に受験した就活生から多くの質問が寄せられます。ここでは、その中でも特に多い「よくある3つの質問」に対して、明確な答えとアドバイスをお伝えします。
Q.推論が一問も出なかったんですが大丈夫?
まず前提として、出題される問題は企業によって異なります。SPIには「Webテスティング」「テストセンター」などの形式があり、出題内容が固定されている場合も、受験者の正答率によって変化する場合もあります。
Webテスティングの場合、出題順が固定されているため、受験した問題セットにたまたま推論が含まれていなかった可能性もあります。
テストセンターの場合、推論が出なかった=非言語の正答率があまり高くなかったという可能性はありますが、それでもすぐに「落ちた」と判断する必要はありません。他の分野で点数を稼げていれば合格ラインに達していることも十分あります。
つまり、「推論が出なかった」=「不合格確定」ではありません。過度に心配せず、今後の試験や選考に向けて、他分野も含めてバランスよく対策していきましょう。
Q.出題された8割以上が推論だったのですが異常ですか?
これは特にテストセンターを受験した方から多い質問です。非言語の出題の半分以上が推論だった、しかもチェックボックス形式や4タブのような高難易度問題ばかりだった、という場合ですね。
結論から言えば、異常ではありません。むしろ高スコアが期待できます。
テストセンターは「適応型」出題のため、正答率が高い受験者ほど難易度が高く、推論問題が多く出される仕組みになっています。特にチェックボックス形式や複数条件を同時に考慮する推論は、上位層のみに与えられる高難度問題です。
このような問題が多く出た=実力を高く評価されている証拠と捉えて大丈夫です。
Q.苦手なので推論は最初から捨ててもいいですか?
先に結論を言うと、基本的には捨てない方がいいです。
推論は慣れの影響が大きく、苦手に感じている人でも、解法を知って練習すれば着実に伸ばすことができる分野です。スコア差がつきやすく、出題されれば数点の上乗せが可能になるため、捨てるのは非常にもったいないです。
また、大手企業や人気企業を狙っている人、足切りのある試験を受ける人は特に、非言語でのスコアが重視されます。推論を捨てることで合否に直結する可能性もあります。
どうしても対策の時間が限られている場合でも、最低限の形式(正誤・順序・対戦など)には慣れておくのがおすすめです。1〜2問でも正解できれば、全体のスコアを押し上げる効果があります。
まとめ|SPIの推論は出ても出なくても慌てず対応しよう
SPI非言語における「推論問題」は、出題数にばらつきがあるために、多くの就活生を不安にさせるパートです。しかし、出題形式や仕組みを正しく理解していれば、どんな状況でも冷静に対応できるようになります。
推論対策で得たスキルは、SPIに限らず、面接やグループワークなどあらゆる場面で活きてきます。就活力そのものを高めるトレーニングだったと捉えましょう。
SPIの推論は「出たらラッキー」「出なかったら切り替え」でOK。大事なのは、どんな出題にも動じず、地に足のついた対策を続けていくことです。
あなたの努力は、きっと次のチャンスで活かされます。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう!