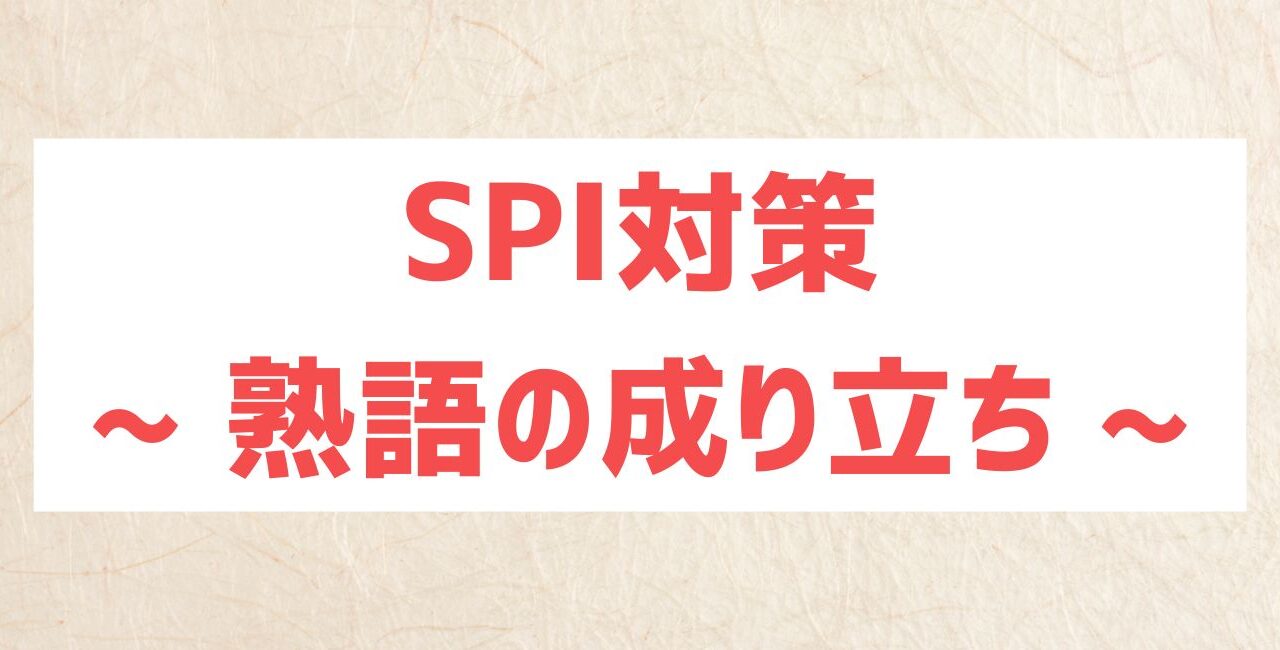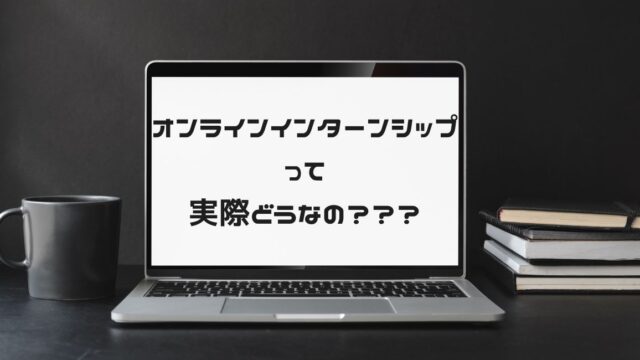【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
SPIの言語分野では、読解力や語彙力を問うさまざまな問題が出題されますが、その中でも「熟語の成り立ち」は、語の構造と意味の理解を問う独特な形式の問題です。
一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、実はこの問題はパターンを覚えれば安定して得点できる狙い目のジャンルです。漢字2文字の意味の組み合わせを読み解く力が求められるため、国語に自信がない方でも、論理的に対策を積めば十分に対応できます。
この記事では、SPIで出題される熟語の成り立ちのルールとはどんなものなのか、よく出る構成パターンとその特徴、意味を見抜くためのコツと解き方の手順、練習問題を通じて理解を深める演習といった内容を、就活生向けにわかりやすくまとめました。
「漢字の意味がなんとなくしか分からない」「熟語の使い方に自信がない」と感じる方も、記事を読み終わる頃には着実に力がついているはずです。
SPIの熟語の成り立ちとは
SPIの「熟語の成り立ち」問題では、2文字の漢字がどのような意味的関係で結びついているかを見抜くことが求められます。単に「意味が通じるかどうか」を判断するだけでなく、主語と述語の関係なのか、修飾と被修飾の関係なのか、あるいは対照や類似の関係なのかといった、構造の見極めが鍵になります。
例えば、
- 「読書」→「読む(動作)」+「書(名詞)」=本を読むこと(目的語との関係)
- 「高温」→「高い(形容詞)」+「温(名詞)」=温度が高いこと(修飾関係)
- 「進退」→「進む⇔退く」=正反対の意味を持つ語の組み合わせ(対義関係)
このように、漢字同士の関係性を捉えることで、熟語の構造が理解でき、問題にも対応しやすくなります。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPI熟語の成り立ちでよく出る問題
SPIの熟語問題では、漢字2文字の意味的なつながりを読み取る必要があります。出題されるパターンには一定の傾向があり、大きく分けて以下の3つの構成が頻出です。各パターンの特徴を押さえておくことで、選択肢を絞るスピードと精度が大きく向上します。
主語+述語の構成
このタイプは、前の漢字が主語、後ろの漢字が述語のような意味を持ち、熟語全体が1つの文のように機能する構造です。
例:
・「日照」→「日(太陽)」+「照(照らす)」=太陽が照ること
・「魚泳」→「魚(主語)」+「泳(泳ぐ)」=魚が泳ぐこと
このように、「何がどうするか」という意味の流れが自然に成立していれば、主述構造と判断できます。主述構造は、比較的わかりやすい組み合わせですが、動詞の意味を正確に捉える必要があります。「○○が〜する」という関係を意識しながら読んでいくと見分けやすくなります。
修飾語+名詞の構成
こちらは、前の漢字が後ろの漢字を修飾する(詳しく説明する)関係になっている構成です。
例:
・「高熱」→「高い(修飾)」+「熱(名詞)」=高い熱
・「大雨」→「大きい(修飾)」+「雨(名詞)」=大きな雨
前の漢字が形容詞的な意味合いを持ち、後ろの名詞を説明している関係が特徴です。形容詞+名詞の語感で考えるとスムーズに判断できます。このパターンは、語の意味が直感的にも理解しやすいので、判断に迷ったときに消去法の軸として使えることも多いです。
対義語・同義語の組み合わせ
最後に紹介するのが、意味が対立・対照する語や、近い意味を持つ語を並べた構成です。
例(対義関係):
・「進退」→「進む」⇔「退く」
・「善悪」→「良い」⇔「悪い」
例(同義関係):
・「破壊」→「破る」+「壊す」=似た意味を重ねて強調する構造
・「検索」→「探す」+「調べる」
このタイプの熟語は、2つの語が並列的に並んでいることが多く、どちらか一方でも意味が強く伝わるケースもあります。「対立する意味の語が並んでいるか」「似た意味を重ねているか」の2視点で関係性を見極めましょう。
これら3つの構成パターンは、SPIの熟語問題において非常によく出題されます。
SPI熟語の成り立ちを解くコツ
SPIの熟語問題は、ただの語彙力チェックではありません。構造を見抜く力と、漢字の意味を丁寧にたどる姿勢が得点を分けます。
ここでは、特に初見の熟語でも立ち向かえるようになるための3つの具体的なコツを紹介します。
コツ①:漢字1文字ごとの意味を丁寧に確認する
まず基本になるのは、漢字1文字ずつの意味をきちんと分解して考えることです。
例えば「読書」という熟語の場合、「読」は「読む」、「書」は「本・文章」を指します。これを合わせて「本を読むこと」と自然に解釈できれば、正しく意味がつかめている証拠です。
意味を知らない熟語が出たときほど、いきなり全体を推測しようとするのではなく、1文字ごとにどんな意味かを辞書的に思い出す癖をつけましょう。
・前の字:「何の動作?何を表す?」
・後の字:「何に関するもの?名詞?状態?対になる語?」
このように、1字ごとの役割を探るように考えると、構造の見通しが良くなります。
コツ②:「〜するもの」「〜の状態」など構文で考える
熟語を見たとき、「○○するもの」「○○の状態」など、文としての骨組みに当てはめてみる方法はとても有効です。たとえば「発電」という語を考えてみましょう。
例:
「発(起こす)」+「電(電気)」=「電気を起こす=電気を作る」
→「電気を発する行為」という文構造で成り立っています。
このように、「AはBを〜するもの」といった形に置き換えると、主語・述語や修飾の構成を確認しやすくなります。
・「進学」=「学校へ進むこと」→動作と目的
・「高音」=「高い音」→修飾語+名詞
・「破壊」=「壊す・破る」→類義語での強調
意味が通れば自然な構造。通らなければ、別の関係を疑う――これを繰り返すことで、熟語の論理的構造を見抜く力が育ちます。
コツ③:熟語を分解して意味が成り立つか検証する
実際に問題を解くときは、必ず「この2文字で本当に意味がつながっているか?」を検証する癖をつけましょう。
具体的には、以下のようなチェックを頭の中で行います。
・片方の漢字が全体の意味に大きく貢献していない場合→不自然な熟語の可能性
・意味が逆方向に向いているのに1つの動作になっている場合→対義構造かも?
・どちらも同じ意味を繰り返しているように感じたら→同義語型を疑う
例:
「閉会」→「閉じる」+「会」=会を閉じる
→成立している(主述構造)
例:
「強力」→「強い」+「力」=力が強い
→成立している(修飾構造)
逆に、「雨車」などの意味が曖昧な語(※実在しないもの)なら、「雨の車…?」と考えたときに不自然さに気づけるはずです。
熟語は意味の通じるペアであることが大前提。意味がつながるか・つながらないかを自分で確かめる工程を省かないことが、正解への最短ルートです。
この3つのコツは、すぐに意識できるうえに、どんな問題にも応用が利く基本原則です。
続いては、覚えた構成パターンや解き方のコツを定着させるための学習法を紹介します。苦手意識のある人でも、ポイントを押さえて取り組めば自然と得点できるようになりますよ。
SPI熟語の成り立ちの対策ポイント
コツをつかんだら、次は実践的な対策に進みましょう。熟語の成り立ち問題は「感覚」で解くよりも、知識を整理しながら論理的に考える練習を積むことで、着実に得点源にすることができます。
ここでは、短期間でも成果が出やすい3つの対策ポイントを紹介します。
ポイント①:構成パターンごとに熟語を分類して覚える
ただ漢字を見て意味を覚えるだけでは、問題での応用力はなかなか身につきません。重要なのは、構成パターン(主述・修飾・対義・同義など)ごとに熟語を整理しながら覚えることです。
たとえば、以下のようにまとめると、記憶が整理され、問題文の熟語を見たときにすぐ構造の予測がつきます。
・【主述型】日照、雨漏、魚泳、地震
・【修飾型】高温、長距離、大雨、短時間
・【対義型】進退、善悪、上下、貧富
・【同義型】破壊、調査、捜索、収集
このように自分だけの「構成別熟語リスト」を作っておくと、SPI本番でも判断の助けになります。
ポイント②:実際に使われる例文で用法を理解する
単語の構造だけを見ていても、文中での意味や使い方がわかっていないと、問題に応用しづらいことがあります。そこで有効なのが、熟語を含む文章や例文での使い方を確認することです。
例:
・「会議は日照時間の短さについて話し合った」
・「強風により交通機関に影響が出た」
このような文脈での熟語の用法に触れることで、「あ、この語はこういう意味で使うんだ」と具体的に理解でき、意味が曖昧なまま覚えることを防げます。国語辞典や語彙アプリを使い、意味+用例を一緒にインプットしておくのが効果的です。
ポイント③:語源や由来から意味を連想して覚える
「語呂合わせ」や「イメージ」で覚えるのが得意な人には、漢字の語源や構成背景から意味を連想する学習法がおすすめです。
例:
・「雨漏」→「雨が漏れる」→構造は主述(雨がどうなるか)
・「火山」→「火を吹く山」→火+山=火山(意味がそのまま)
・「善悪」→「善いか悪いか」→対立するものの並列=対義語型
こうした連想記憶を使うことで、単なる丸暗記よりも定着が良くなり、思い出すスピードもアップします。特に似た構造の語が多い場合でも、語源や漢字の成り立ちを意識することで、混同を避け、意味の理解が深まるのがこの方法の強みです。
対策を積むうえで大切なのは、「構造を理解しながら覚える」こと。
これまで紹介してきたコツや対策ポイントをもとに演習を重ねることで、確実に得点力が伸びていきます。
SPI熟語の成り立ち練習問題3つ
ここからは、SPI本番を意識した練習問題に取り組んでみましょう。
構成パターンを意識して、どのような意味のつながりになっているかを論理的に考えることがポイントです。
各問題には解答と簡単な解説もつけていますので、復習用にも活用してください。
問題1:構成関係の判別問題
次の熟語のうち、主語+述語の関係に当てはまるものはどれか?
①雨音
②魚泳
③大地
④善悪
⑤火災
正解:
②魚泳
解説:
「魚が泳ぐ」→主語が「魚」、述語が「泳ぐ」で、主述関係が成り立っています。①は修飾語+名詞(雨の音)、③も修飾構造、④は対義語、⑤は名詞の合成であり主述ではありません。
問題2:意味に合った熟語選び
「温度が高い状態」を表す熟語として最も適切なものはどれか?
①高熱
②熱火
③強熱
④灼熱
⑤熱力
正解:
①高熱
解説:
「高」+「熱」=高い熱→修飾語+名詞の構成で、意味が自然に成り立ちます。他の選択肢は実在する語もありますが、この中では「高熱」が最もストレートに意味を伝える熟語です。
問題3:誤った熟語構成を選ぶ問題
次のうち、意味的に不自然な組み合わせになっている熟語はどれか?
①長距離
②暑冷
③読書
④雨量
⑤大雨
正解:
②暑冷
解説:
「暑い」+「冷たい」という意味が正反対で、しかも「暑冷」という熟語は一般的には使用されません。他の選択肢はいずれも意味が自然に成立する熟語構成です。
これらの問題を通じて、熟語の構造・意味・語感をバランスよく判断する練習ができます。
本番で見たことのない熟語が出ても、今回学んだコツやパターンに当てはめて考えれば、確実に得点できる力が身につきます。
まとめ
SPIの「熟語の成り立ち」問題は、漢字の意味とそのつながり方を正確に読み取る力が求められます。ですが、出題される構成パターンには明確な傾向があり、主述・修飾・対義・同義などの型を押さえておけば、初見の語句にも冷静に対応できます。
本記事で紹介したように、1文字ずつ意味を確認する、構文に当てはめてみる、意味の通り方を検証する――といったコツを意識しながら演習を重ねれば、熟語の成り立ち問題は確実に得点源になります。さらに、構成パターン別の整理や、例文による用法の理解、語源への着目などを通じて知識を深めることで、語彙力そのものも高まっていきます。
SPIの言語分野で差をつけたい人にとって、「熟語の成り立ち」は絶対に避けて通れない重要パートです。コツコツと積み上げた理解が、そのまま得点につながる分野ですので、焦らず丁寧に対策していきましょう。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。