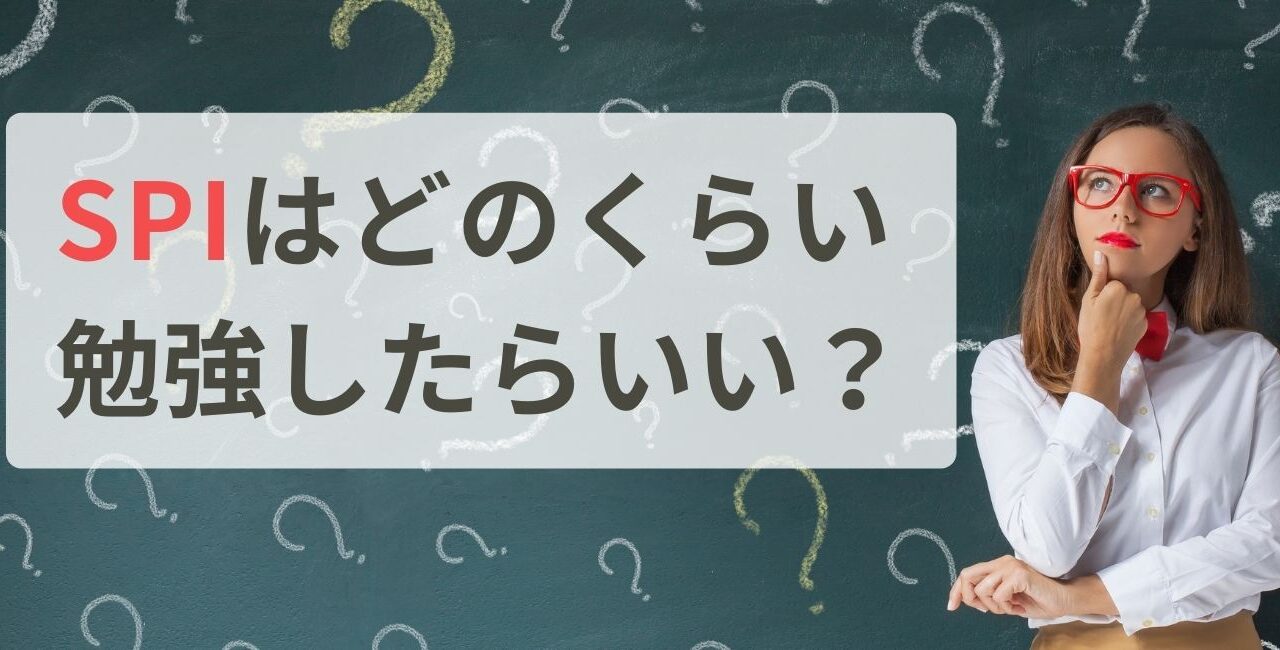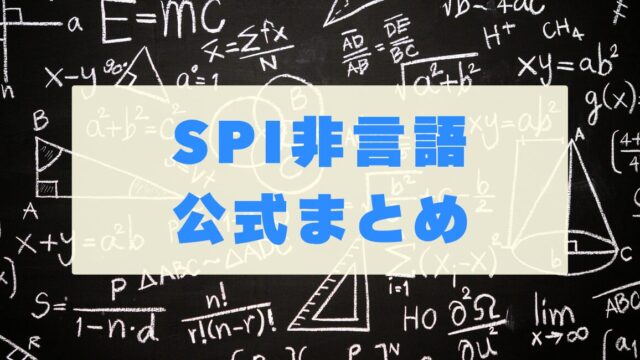【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
就活が本格化してくると、ESや面接だけでなく「SPI対策っていつからやればいいの?」と焦り始める人も多いはず。特に文系学生の中には、「数学苦手だし、非言語分野が怖い…」なんて声もよく聞きます。
でも安心してください。SPIは出題パターンが決まっているので、ちゃんと対策すれば確実に得点できるテストです。
とはいえ、やみくもに問題集を始めるのではなく、自分の志望企業やレベルに合わせて「どのくらい勉強するか」を見極めることが大切です。
この記事では、
- SPI対策って、どのくらいやればいいの?
- 志望企業によって必要なスコア(偏差値)は変わるの?
- 効率よく対策する方法は?
といった就活生の不安や疑問に答えながら、勉強時間の目安や偏差値別の対策法、ジャンルごとの勉強ポイントをわかりやすく解説していきます。
SPIは「早く始めた者勝ち」のテストでもあります。この記事を参考に、今日から自分に合った対策を始めましょう!
目次
SPI対策はどのくらい必要?就活生のよくある不安
「SPIって、ぶっちゃけどれくらい対策すればいいの?」
就活中によく聞くこの疑問。実際、周りの就活生の中にも「勉強ほぼゼロで通った!」という人もいれば、「対策してたのに落ちた…」という人もいて、何が正解か分からなくなりますよね。
ここではまず、就活生が感じやすいSPIに関する不安と、「どれくらいやればいいか」を考えるために知っておきたい基礎知識を整理していきます。
「SPIの勉強、どのくらいやればいいの?」と悩む就活生が多い
SPI対策を始めようとしたとき、よく出てくるのがこの2つのタイプ。
- Aタイプ:何も対策しないまま受ける
→「まぁいけるでしょ」とノー勉で受けて痛い目を見るパターン - Bタイプ:完璧を目指して勉強しすぎてしまう
→何から手をつけていいかわからず、勉強だけで疲れてしまうパターン
どちらも極端になりすぎて失敗するケースです。大切なのは、自分の志望企業や受験形式に合わせて、必要な対策量を把握することです。
企業によって求められるSPIのスコア(偏差値)の違い
そもそもSPIは点数ではなく、偏差値で評価されます。つまり相対評価で結果が決まるイメージです。そのためどのレベルの企業ならどのくらいの偏差値を目指すべきかが変わります。
特に大手や人気企業では一定の偏差値を下回ると足切りされる可能性があります。
特に注意したいのが以下の企業群:
- 大手・有名企業(総合商社・大手メーカーなど)→書類通過後の1次選考でSPIの結果が重要視されることが多い
- 金融・保険業界→数値に強い人材を求めるため、非言語分野の結果が重視されがち
- IT・コンサル業界→論理的思考力が重視され、推論系の問題がよく出る
一方で、中小企業やベンチャー企業では、SPI自体を実施していないところも多いので、企業によって必要性はかなり違います。
「とりあえず対策」では落ちる?SPIの重要性とは
「SPIは筆記だから軽視してもOK」と思っている人もいますが、それは危険です。
たとえば、ESや面接がうまくいっても、SPIで足切りにあえばそこで終了。SPIは選考の入口を通過するための関門ともいえる存在です。
特にテストセンターで受ける場合は、全国の受験者との相対評価になるため、何となく受けて通過できるほど甘くありません。
だからこそ、SPIは「やれば確実に点が取れるテスト」だからこそ、ちゃんとやるべきなんです。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPIでどのくらいの偏差値を目指すべき?
SPI対策を始める前に、まず考えたいのが「どれくらいの偏差値になればいいのか?」という目標設定です。この目標があいまいなままだと、勉強していても「どこまでやればOKなの?」と不安が残ってしまいますよね。
ここでは、大手・中小企業の違いや、業界ごとの傾向をもとに、自分に合った目標の立て方を解説します。
大手企業・有名企業の場合:高偏差値が求められる(偏差値60以上)
総合商社、メガバンク、大手メーカー、コンサルなどの人気企業や倍率が高い企業では、SPIが足切りとして機能しているケースが多いです。
こうした企業では、SPIで偏差値60以上(=上位20〜30%)が必要になることも珍しくありません。
特にテストセンター形式では「受験者の中でどれくらいの位置にいるか」が重視されるため、「8〜9割の正答率を安定して出せる」レベルを目指しておくと安心です。
中堅・中小企業の場合:平均的な偏差値でOK(偏差値50前後)
一方で、中堅企業や地域密着型の企業、ベンチャーなどでは、SPIの扱いがそこまで厳しくないケースもあります。その場合は、偏差値50(=平均レベル)前後で問題ないことが多く、対策もそこまで重くならない傾向です。
ただし、「SPIの結果がよくなくても通る」というわけではなく、他の選考(ES・面接)と合わせて総合的に評価されると考えておきましょう。
業界別のSPI重要度
SPIの偏差値の重視度は、業界によっても違いがあります。以下にざっくりと傾向をまとめました。
| 業界 | SPIの重視度 | 特徴・傾向 |
| 金融(銀行・証券など) | 高い | 数字・論理に強い人材を求める。非言語(計算・推論)の配点が高いケースも。 |
| メーカー | やや高い | 大手ほどSPIの結果を重視。安定した基礎能力が求められる。 |
| IT・通信 | 高い | 論理的思考力を測るため、非言語・推論が重要視される傾向。 |
| 商社・コンサル | 高い | 学力・地頭の評価の一環としてSPIが活用される。点数によってES選考免除もあり。 |
| 小売・サービス | やや低い | 面接重視でSPIの配点は低め。最低限クリアできればOKという企業もある。 |
| ベンチャー | 低い〜不要 | そもそもSPIを課さないケースも多く、重視されないこともある。 |
目標偏差値は「志望企業+自分の実力」で決める!
- 志望企業が「大手」や「選考が厳しい」と感じるなら、偏差値60以上を目指す本気対策が必要
- 一方で、SPIよりも人物重視の企業を目指すなら、まずは偏差値50を安定して出せるレベルでOK
大事なのは、自分にとっての必要最低ラインと安心できるラインを把握することです。
このラインが明確になれば、「どれだけ対策すればいいか」も自然と見えてきます。
【偏差値別】必要な勉強時間と対策法
「目標偏差値は決まったけど、実際どれくらい勉強すれば届くの?」そんな疑問に答えるために、この章では偏差値ごとに必要な勉強時間の目安とおすすめの対策法を紹介します。
時間が限られている就活生にとって、「効率よく」「確実に点数を取る」ための戦略を立てることが超重要です。あなたの現状に合わせて、どのプランから始めるか考えてみてください。
SPI対策なし(0〜1時間)
「とりあえずぶっつけ本番でやってみる」という人もいますが、正直これはおすすめしません。SPIには独特の出題形式や時間制限があるため、ノー対策だと途中で時間切れor正解率がボロボロになる可能性が高いです。
特にテストセンターでは「相対評価」になるため、ノー勉で挑むと他の受験者に大きく差をつけられてしまいます。
受験直前にできる最低限の対策
どうしても時間がない場合でも、以下のような最低限の対策だけはしておきましょう。
- 過去問アプリやWeb問題集で出題形式を確認する
- 「推論」「図表読み取り」「語句の意味」など頻出ジャンルだけざっくりチェック
平均(偏差値50程度)を狙う(10〜20時間)
偏差値50前後、つまり「足切りを回避する」「中堅〜中小企業を目指す」レベルなら、
1日1〜2時間×1〜2週間の勉強で十分対応できます。市販のSPI問題集や無料のSPI対策アプリを使って、次のような対策を進めましょう。
- 言語分野:語句の意味・語句の使い方・二語の関係
- 非言語分野:割合・速さ・集合・推論などの基本問題
言語・非言語の頻出問題を押さえる
時間が限られているなら、よく出る問題だけを集中的にやるのが最も効率的です。
問題集の「頻出マーク」や「基本レベル」の問題を優先的に取り組むのがポイントです。
高偏差値(偏差値60以上)を狙う(30時間以上)
偏差値60以上を目指すなら、最低30時間(目安:1日1〜2時間×2〜3週間)の対策が必要です。目標企業が人気業界・大手企業であれば、本格的に準備しておくべきです。
このレベルになると、「1周解くだけ」では足りません。
模試形式の問題を使って、時間制限の中で解く練習も組み込みましょう。
弱点克服のためのピンポイント対策
高スコアを狙う人ほど、「苦手分野の放置」が命取りになります。
- 非言語の中で割合・損益算が苦手
- 言語の中で熟語の成り立ちがよく分からない
といった場合は、そのジャンルだけを集中してトレーニングする時間を確保するのが効果的です。
【ジャンル別】SPIの勉強時間と効率的な勉強法
SPIは「言語」「非言語」「英語(企業によっては課される)」の3つの分野に分かれていて、それぞれ対策のコツや効果的な勉強法が異なります。この章では、ジャンルごとに勉強時間の目安と効率の良い学習法を解説していきます。
言語分野(長文読解・語彙・文法)
SPIの言語分野では、「文の並び替え」や「空欄補充」「長文読解」など、文章の流れを理解する力=読解力が重要になります。
勉強時間の目安:10〜15時間程度(平均狙いなら10時間でOK)
勉強法のポイント
- 長文読解は「段落ごとの要点」を意識して読む
- 「接続詞」や「指示語(これ・それなど)」に注目して流れをつかむ
- 並び替え問題は「導入文」「結論文」を見極める練習をする
語句の意味や用法、熟語の成り立ちといった問題は、暗記力よりも「見たことがあるか」が勝負です。対策アプリや問題集で、1日10〜20問をコツコツ解く習慣をつけるのがおすすめです。
非言語分野(計算・推論・確率など)
非言語は計算問題が多く、正確さとスピードの両立がカギになります。
特に「割合」「損益算」「速さ」「図表の読み取り」などは頻出です。
勉強時間の目安:15〜20時間程度(高スコア狙いなら+10時間)
勉強法のポイント
- 四則演算(足し算・引き算・かけ算・割り算)をスムーズにこなせるようにする
- 「割合=元に対していくらか」のイメージをつかむ
- 問題文はまず何を求められているかを読み取ることに集中する
- 1問に時間をかけすぎない練習を意識
よく出る「割合・確率・速さ」の攻略ポイント
- 割合→公式(変化量÷元の数×100%)を使いこなす
- 確率→全体に対する「起こる可能性のある数」を数える練習
- 速さ→「みはじ(道のり=速さ×時間)」の公式を使って素早く処理
英語(英語が課される企業向け)
英語分野はSPIでは任意形式の企業が多いですが、課される場合はTOEICリーディングのような問題形式が多く、読解+語彙+文法の総合力が求められます。
勉強時間の目安:7〜10時間程度(受験予定がある人のみ)
勉強法のポイント
- 英文を読むスピードを意識して、1日1〜2問でも演習を積む
- 長文読解は「先に設問を読む」→「本文から答えを探す」クセをつける
- 単語は大学受験レベルの基礎単語で十分
各ジャンルの勉強は、1日5〜10問ずつでもOK。大事なのは毎日ちょっとでも続けることです
SPIで点が取れないときの対策法
「勉強してるのに全然正解できない…」
「問題集を何度も解いてるのにスコアが上がらない…」
SPI対策をしている就活生の中には、こんなふうに壁を感じる人も少なくありません。
この章では、言語・非言語それぞれで点が伸び悩む原因と、そこから脱出するための具体的な対策法を紹介します。
言語が苦手なら「問題パターン」を覚える
言語分野で点が取れない原因の多くは、「読解力」ではなく「問題の型に慣れていない」ことです。
特に次のような人は要注意
- 毎回、文章を最初から最後までじっくり読んでしまう
- 接続語やキーワードを見逃してしまう
- 語彙や熟語の意味がなんとなくで曖昧
対策ポイント
- 問題のパターンを覚える:「並べ替え」「空欄補充」などは出題形式が決まっている
- 選択肢を先に読む→本文を読む流れに変えることで、読むスピードが格段に上がる
- 語彙系の問題は、覚えるより見慣れることを意識して毎日演習
→「読むのが遅い=苦手」ではないので、問題を繰り返して慣れることがカギです。
非言語が苦手なら「計算のクセ」をつける
非言語で点が伸びない人の多くは、そもそも計算の進め方に自信がないorミスが多いことが原因です。
どの公式を使えばいいのか分からない、割合や比が出てくると混乱してしまう、問題文を読んでいる間に何を求めているのか忘れるなど、慣れていないとこういったミスが発生します。
対策ポイント
- まず「解き方のパターン」を頭に入れる(問題集の解説を読んで真似するだけでもOK)
- 式をきちんと書きながら解くクセをつけると、計算ミスが減る
- 苦手分野は「1日1テーマ集中」で、たとえば「今日は割合」「明日は図表」など分けて取り組む
特に非言語は「計算力」よりも「考え方の慣れ」で点数が変わります。毎日少しずつの積み重ねが勝負。
模試を活用して本番レベルの問題に慣れる
「問題集だと解けるのに、本番形式になると時間が足りない…」という人も多いですよね。
そんなときに効果的なのが、模試形式でのトレーニングです。
模試対策のコツ
- 時間制限ありの模試問題に挑戦する(アプリや市販の模試形式問題集がおすすめ)
- 終わったら「なぜ間違えたか?」「時間が足りなかった理由は?」を振り返る
- 解けなかった問題はそのまま放置せず、必ず2回目を解く
本番に近い環境で練習しておくと、当日も焦らず自分のペースで解けるようになります。
「苦手」は誰にでもありますが、それを早めに認識してコツコツ対策すれば、必ず克服できます。最初はうまくいかなくても、自分のペースで一歩ずつ進んでいきましょう。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
【まとめ】SPI対策は「どのくらい」やるべきか?
SPI対策って、どこまでやれば安心なのか。この記事をここまで読んでくれたあなたなら、きっと「自分に必要な対策の量」が少しずつ見えてきたはずです。
最後にもう一度、SPI対策を効率よく進めるための考え方と、就活本番で焦らないためのポイントを整理しておきましょう。
- 志望企業に合わせた目標偏差値を設定する
- 自分のレベルに合った勉強時間を確保する
- 苦手分野を放置せず、効率的に対策することが大事
SPIは、センター試験のような「難問で差をつけるテスト」ではなく、一定のレベルに達すれば誰でも突破できる選考です。だからこそ、「やった人が勝つ」構造になっています。
今からでも遅くありません。自分の目標に向けて、今日から少しずつ、SPI対策を始めていきましょう。