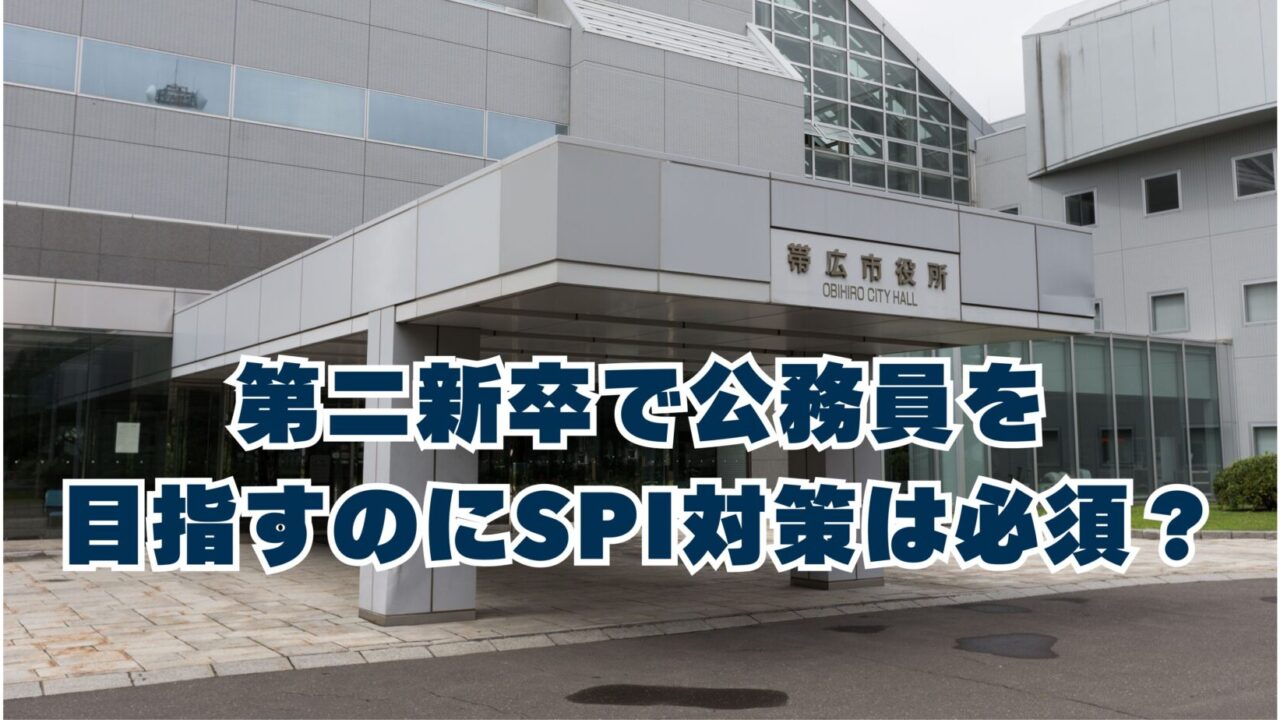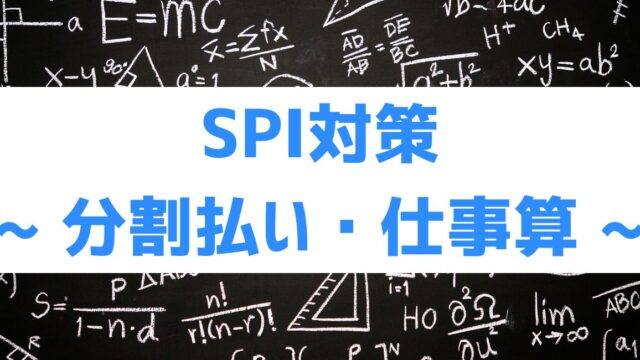【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「第二新卒でも公務員になれるの?」「SPIって、民間企業の就活だけに出てくるものじゃないの?」
そんな疑問を抱えながら情報を集めている方も多いのではないでしょうか。
確かに公務員試験と聞くと、「一般教養」や「専門試験」といった筆記試験を思い浮かべる方が大半です。しかし実は、最近では民間企業で使われているSPIを公務員採用に導入している自治体も増えてきています。特に第二新卒層など、社会人経験が浅い人材を対象とした採用区分では、その傾向が顕著です。
とはいえ、民間と公務員の採用試験では選考の流れも評価の観点も異なるため、「SPIが使われる理由」や「出題傾向」「通過ラインの目安」など、しっかりと理解しておくことが欠かせません。
本記事では、第二新卒で公務員を目指す方に向けて、SPIが課される自治体や職種、スコアの仕組み、効果的な対策法まで徹底的に解説していきます。さらに独自データとして、【地域×職種のSPI出題傾向マップ】や【2025年度対応の試験リスト】なども盛り込んでいるので、「これから本格的に準備したい」という方にとっても、非常に実用的な内容になっています。
公務員を目指すうえでSPIは“避けて通れない試験”になる可能性があります。情報不足でチャンスを逃さないためにも、まずはこの記事でしっかり理解を深めていきましょう。
目次
公務員試験でSPIが使われる理由とは?
「公務員試験=教養試験や論文試験」といったイメージがある中で、なぜ一部の自治体ではSPIが採用されるのでしょうか。これは、公務員試験における“採用のあり方”そのものが変化してきたことと深く関係しています。
筆記試験代替としてのSPIの役割
これまで多くの自治体では、教養試験(いわゆる一般知識や時事・文章理解など)を実施してきました。しかし、こうした試験は作問や採点に時間とコストがかかり、職員側の負担が非常に大きくなるのが課題でした。
そこで登場したのがSPIです。SPIは、リクルートが開発・提供する民間企業向けの適性検査ですが、既存のテストセンターやオンラインシステムを活用できるため、自治体としてはコストや人手を削減できるという大きな利点があります。
標準化された評価基準を活用できる
もうひとつの大きな理由は、SPIが「標準化された客観的評価ツール」であることです。たとえば、教養試験は自治体ごとに内容やレベルがまちまちで、他地域との比較が難しい面があります。
一方でSPIは、全国どこでも同じ形式・内容で実施されるため、受験者の能力や適性をよりフラットに判断しやすくなります。これは、民間企業でも「学歴や履歴書だけでは見えない人物像」を測るツールとして長年使われてきた背景があります。
「人物重視」採用との相性の良さ
特に第二新卒や経験者採用では、「過去の実績よりも将来の伸びしろ」=ポテンシャルを重視する傾向が強くなります。SPIはまさに、基礎的な能力や性格面の適性を測るのに適した検査であり、公務員試験でもその有効性が認められ始めています。
結果として、受験のハードルを下げる意味でも、多くの自治体がSPIを取り入れやすくなっているのです。
SPIが課される自治体・職種一覧
「どの自治体でSPIが出るのか?」これは受験計画を立てる上で、もっとも気になるポイントの一つではないでしょうか。実際には、全国すべての自治体で導入されているわけではありませんが、特定の地域や職種では年々導入例が増えています。
ここでは、代表的な自治体とSPI出題傾向について整理していきます。
代表的な自治体と職種
SPIを公務員採用に取り入れている代表的なケースとしては、以下のような自治体や職種があります。
まず、東京都特別区(23区)では一部の技術職や経験者採用枠でSPIを採用しています。また、首都圏の市役所や町役場でも、民間の転職者を対象とした採用枠で導入されている例が見られます。
たとえば、
- 神奈川県内の某市役所では、行政職の第二新卒枠でSPI(言語・非言語・性格検査)を採用
- 埼玉県の一部町役場では、一般教養試験を廃止し、SPIテストセンター方式に移行
- 大阪府内の政令指定都市では、土木・建築などの技術職枠でSPI形式を採用
といったように、地域や採用区分によって導入形態は異なりますが、「試験の簡略化」「標準的な能力評価」を理由に、SPIが活用される場面は着実に増えているのが現状です。
行政職以外でも導入されるケースがある
意外と知られていませんが、SPIは行政職以外でも活用されています。特に技術系職種(土木、建築、電気、機械など)や、福祉職、事務補助職などで、基礎的な能力と適性を測る手段としてSPIを採用する自治体もあります。
これらの職種は、専門試験だけでは人物像がつかみにくい面があるため、SPIでの補完的な評価が有効だと考えられているのです。
SPIを課す公務員試験リスト
以下は、2025年度採用試験においてSPIが出題される予定または過去に出題されたことがある自治体・職種をまとめた一覧表です(※公式HP等の最新情報をもとに作成)。
| 自治体名 | 職種区分 | SPI有無 | 出題形式 |
| 東京都特別区 | 技術職(建築) | あり | テストセンター形式 |
| 川崎市 | 行政職(経験者) | あり | Webテスティング |
| さいたま市 | 行政職(一般) | あり | 自宅受検形式 |
| 名古屋市 | 福祉職 | あり | テストセンター形式 |
| 大阪市 | 土木職 | あり | テストセンター形式 |
| 北九州市 | 事務補助職 | あり | SPI簡易版 |
※最新の募集要項や採用ページにて随時ご確認ください。
第二新卒にSPIが課されやすい理由
第二新卒として公務員を目指す場合、SPIが選考フローに組み込まれる可能性は高くなります。その背景には、第二新卒という人材カテゴリー特有の事情があります。ここでは、その理由を詳しく解説していきます。
ポテンシャル採用が基本だから
第二新卒とは、新卒で入社後、数年以内に退職して再就職を目指す若手層のことを指します。民間企業においても公務員においても、この層は「即戦力」よりも「ポテンシャル(将来性)」を評価されやすい傾向があります。
特に自治体では、第二新卒層に対して「若手で育成しやすい」「順応性が高い」という期待がある反面、職務経験が浅く、実績で評価するのが難しいという実情もあります。そのため、基礎能力や性格的な適性を測るSPIのような試験が、重要な評価ツールとして活用されているのです。
学力の“見える化”に役立つから
SPIは、言語・非言語・性格の3つの側面から、応募者の基礎的な知的能力や性格傾向を測定できます。第二新卒の場合、最終学歴や新卒時の就職先は参考にはなるものの、そこからの社会人経験が浅いため、「現在の実力や適性」が不明確になりがちです。
SPIを活用すれば、そうした“見えづらさ”を補い、客観的に学力や適性を把握することができます。自治体側としても、SPIスコアがあることで判断の材料が増え、より公平で透明性のある選考がしやすくなるのです。
新卒と同様の評価基準が使われやすいから
自治体によっては、第二新卒の採用においても、新卒とほぼ同じフローを用いる場合があります。たとえば、エントリーシート→SPI→面接という流れや、試験内容が新卒とほぼ同じというケースです。
これは「実務経験が浅い=新卒と変わらない」という捉え方をしているからです。そうなると、新卒時と同じようにSPIでの評価がなされるのも自然な流れといえます。
SPIの基本構成と出題形式
SPIは「Synthetic Personality Inventory(総合適性検査)」の略称で、リクルートが提供する代表的な採用試験形式の一つです。公務員試験においても、民間と同様に3つのパート(言語・非言語・性格)が出題されるのが一般的です。
ここでは、それぞれの構成と出題形式について詳しく解説します。
言語分野
言語分野では、日本語の語彙力や読解力、文法知識などを問われます。試験形式としては選択式が主流で、以下のような問題が出題されます。
- 長文読解:複数段落の文章を読み、内容の正誤や要旨、筆者の主張を問う問題。設問の形式はセンター試験に似た構造で、情報処理力と読解スピードが求められます。
- 語句の用法:文中における単語の意味や使い方が問われる問題で、同音異義語や類義語に関する知識も必要になります。
- 空欄補充:文の一部が空欄になっており、文脈に合う適切な語句を選択する問題。前後の文との論理的なつながりを意識する必要があります。
この分野で重要なのは、いかに素早く正確に文章の主旨を捉えられるかです。語彙力だけでなく、全体の文構造を把握する力も試されます。
非言語分野
非言語分野では、数学的な思考力や論理力、図表の読解力が問われます。文系出身者にとっては苦手意識を持ちやすい分野ですが、頻出パターンを押さえておけば得点源にもなります。
主な出題形式は以下の通りです。
- 表やグラフの読み取り:売上や人数などの情報が表形式で与えられ、そこから計算や比較を行う問題。情報を正確に拾う注意力が求められます。
- 確率や割合の計算:例えば「赤玉と白玉が何個ずつある箱から2個取り出したとき、同じ色になる確率は?」といったような、基本的な確率論の知識が出題されます。
- 順列・組合せ:並び方や選び方のパターン数を計算する問題で、公式と論理の両方の理解が重要です。
- 論理推論:いわゆる“正しい推論”を選ぶ問題で、「Aが真ならBも真になる」などの命題形式の問題が出題されます。
これらの問題はすべて、限られた時間の中で正確な計算と判断を行う必要があります。時間配分の管理と、出題傾向の把握が得点の鍵となります。
性格検査
性格検査は、いわゆる“嘘のつけないテスト”と呼ばれるもので、主にその人の性格傾向や行動特性を把握する目的で行われます。選択式で数十〜百問以上が出題され、回答内容に一貫性があるかどうかもチェックされます。
公務員試験では、次のような性質を測る目的で利用されています。
- 安定性:ストレス耐性があるか、落ち着いて業務に取り組めるか
- 誠実性:ルールを守り、真面目に取り組む傾向があるか
- 協調性:組織内で円滑に人間関係を築けるか
- 主体性・リーダーシップ:指示を待つのではなく、自発的に動けるか
この検査では「自分をよく見せよう」とすると逆に不自然になりやすく、回答の一貫性が崩れてしまいます。素直な回答を心がけることが通過のコツです。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPIのスコアのつき方と通過ライン
SPIの難しさは、単に「何問正解したか」だけで評価されるわけではない点にあります。特に公務員試験においては、「スコアの構造を理解して対策を組む」ことが、通過率を大きく左右します。
ここでは、SPIのスコア算出方式とその通過ラインの考え方について、図解イメージとともに解説します。
難易度によってスコアが調整される
SPIでは、受検者の解答に応じて出題される問題のレベルが変わる「適応型」の構成が取られることがあります。これは、テストセンター方式で特に顕著で、以下のような流れでスコアが決定します。
このように、「同じ数だけ正解しても、どの難易度の問題を解いたか」によって評価が変わります。つまり、高得点を取るには「正解数」だけでなく「レベルの高い問題をどこまで解けたか」が重要になってくるのです。
SPIは“量より質”が重視される試験
「とにかく全部解ければいい」と考えがちですが、SPIは限られた時間でどれだけ精度高く、難問まで進めたかが問われます。特にテストセンター形式では、序盤での“つまずき”がそのまま低スコアにつながる可能性もあるため、最初の10問ほどで確実に点を取ることが非常に重要です。
また、公務員試験の場合、企業のような「他要素との総合評価」ではなく、SPIが事実上の一次通過ラインになっているケースもあります。そのため、他の選考に進むためには“平均以上”ではなく“上位20〜30%”に入る必要があるとも言われています。
通過ラインの目安は?
スコアの具体的な基準は公表されていませんが、一般的には以下のような水準が通過目安とされています。
- 言語・非言語それぞれで正答率80%以上
- 全体で偏差値60前後以上
もちろん、自治体や職種によって基準は異なりますが、「苦手な分野を放置しない」「1問1問の精度を上げる」という姿勢が最終スコアを大きく左右する点は共通しています。
SPI対策の必要性チェック
「SPIって対策しなくても大丈夫?」「一度やったことがあるから勘は戻るはず」
そんなふうに考えている第二新卒の方もいるかもしれません。しかし、SPIの難易度は甘く見ていると痛い目にあうことも。特に公務員試験では、一発勝負の意味合いが強いため、対策の有無で結果が大きく変わります。
この章では、SPI対策が本当に必要かを見極めるための簡易診断チャートと、対策が必要な人の特徴について解説します。
あなたは対策が必要?
以下の質問に「はい」「いいえ」で答えてみてください。
3つ以上「はい」がついたら、SPI対策を始めるべきサインです。
- 大学受験以来、文章読解や計算問題に触れていない
- 模試や問題演習で時間内に解き終えられない
- グラフや表を読むのが苦手だと感じる
- 試験になると焦って読み間違いや計算ミスが増える
- 自分の性格を分析するのが苦手で、性格検査に不安がある
- 「SPI=就活でしか使わないもの」という印象しかない
- 問題のパターンや出題傾向を全く知らない
SPIは一見すると「基礎学力テスト」ですが、限られた時間の中で正確な処理を求められる試験です。慣れていなければ、時間切れやケアレスミスで実力を発揮できないまま終わってしまうことも珍しくありません。
対策が必要な人の特徴
SPI対策が必要かどうかは、「今の自分の状態」を見つめ直すことから始まります。以下のような人は、特にしっかりと準備することをおすすめします。
1. 大学受験以来、勉強していない
文系・理系問わず、大学以降は実務的な勉強やゼミ中心だったという方は、SPIのような試験形式に対応する“受験脳”が鈍っている可能性があります。特に非言語の計算問題では、基本的な割合・比・順列などの復習が不可欠です。
2. 文章や数字に苦手意識がある
「文章を読むと内容が頭に入ってこない」「数字を見ると拒否反応が出る」というタイプは、まず問題形式に慣れる訓練が必要です。特に長文読解やグラフ問題は、慣れで得点率が大きく変わります。
3. 模試で時間内に終わらない
SPIは“スピード勝負”の試験でもあります。解ける問題でも、制限時間内に終わらなければ評価されません。問題演習の中で「時間内に終えられない」「後半に進めない」という感覚がある場合は、対策が必須です。
SPIは事前準備の有無で結果が大きく変わる試験です。過去に民間就活で経験したことがあっても、ブランクがあるなら対策は再スタートする必要があります。
効果的なSPI対策方法
SPIは、「出題形式に慣れること」と「時間内に解き切る練習」ができれば、着実に得点力を伸ばせる試験です。しかし、過去問が非公開であることや、試験の性質上“勘違いしやすい”ポイントが多いことから、やみくもな勉強は非効率になりがちです。
ここでは、第二新卒におすすめのSPI対策方法を、スケジュールやツール別に紹介します。
勉強のスケジュール例(2週間・1ヶ月)
対策期間は、試験日までの残り日数に合わせて調整しましょう。ここでは、2週間と1ヶ月の2パターンでスケジュールを例示します。
【2週間集中型】
- 1〜3日目:問題集を通読し、出題形式の全体像を把握
- 4〜10日目:言語・非言語を交互に演習。毎日30〜60分
- 11〜12日目:性格検査対策と模擬テストを実施
- 13〜14日目:間違えた問題の復習+テスト形式で時間配分練習
時間が限られている中でも、「問題形式に慣れる」ことに重点を置くと、得点が安定してきます。
【1ヶ月しっかり型】
- 1週目:基礎問題の演習と苦手分野の発見(言語・非言語ともに)
- 2週目:頻出テーマ(割合・読解・空欄補充など)を徹底的に練習
- 3週目:模擬テスト→弱点分析→集中トレーニング
- 4週目:全体の総復習+性格検査対策+本番形式でのリハーサル
1ヶ月あると、時間管理や思考の速さにも余裕が生まれ、より高得点が狙えるようになります。
無料アプリ・おすすめ参考書紹介
SPIは参考書とアプリの併用が最も効果的です。問題パターンの理解とスピード強化を同時に進められるためです。
おすすめの無料アプリ
- らくらく就活SPI対策アプリ
新卒・第二新卒向けに最適化されたSPI演習アプリ。言語・非言語・英語に対応。
出題形式別に学べるうえ、時間を測っての模擬テスト機能があるため、実践力も鍛えられます。
おすすめ参考書
- 『これが本当のSPI3だ!』(ナツメ社)
基礎から応用まで網羅されており、非言語が苦手な人にもわかりやすく解説されています。 - 『最短突破 SPI問題集』(高橋書店)
時間がない人向けの要点整理版。演習量を確保したい人におすすめです。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
過去問が少ないSPIの対策法とは?
SPIの難しさの一つは、「本番の過去問が公開されないこと」です。そのため、民間で流通している“模擬問題”や“形式再現問題”で対策する必要があります。
対策法としては以下の通りです。
- 出題形式を徹底的に分析する
たとえば、「表の読み取りは3ステップで解く」といった解法パターンを身につけることが有効です。 - 模試を繰り返す
市販の模試やアプリの演習モードを活用し、時間内に処理する練習を重ねましょう。 - 性格検査は“素直に答える”を徹底する
対策しすぎると一貫性が崩れ、逆に評価が下がることもあります。自分の性格を冷静に見つめ直すことが対策になります。
第二新卒で公務員を目指した人の声
SPIは「対策次第で得点が伸びる」とよく言われますが、実際に第二新卒として公務員を目指した人たちは、どのように準備し、どのような課題に直面したのでしょうか。ここでは、実際にSPIを乗り越えて内定を得た第二新卒の方々の声を紹介します。
リアルなエピソードを通じて、「どのような対策が効果的だったか」「何に苦労したか」を知ることができ、自分の対策にも活かせるはずです。
Aさん(民間企業から市役所へ転職):「SPI対策だけで合格できた」
Aさんは、大学卒業後に民間企業で営業職として2年間働いたのち、地元市役所の行政職に転職しました。受験先の自治体は一般教養試験を廃止し、代わりにSPIを導入していたのがきっかけだったといいます。
「最初は公務員=難しい専門試験というイメージが強く、勉強が続くか不安でした。でも、受験先がSPI形式だとわかってからは、問題集1冊とスマホアプリで絞って対策しました」
使用したのは『これが本当のSPI3だ!』と「らくらく就活SPIアプリ」。約1ヶ月の間、毎朝30分・帰宅後1時間のペースでコツコツ続けたところ、本番では8割以上の正答が取れたそうです。
「試験がSPIだけだったので、むしろ民間経験があって有利に感じました。対策した分だけ結果が出るので、やりがいがありました」と話します。
Bさん(ブランク2年→町役場採用):「性格検査が意外と重要だった」
Bさんは、新卒で入社した企業を1年で退職し、しばらく非正規の仕事をしていましたが、25歳のときに地元の町役場の採用試験に挑戦。経験者枠ではなく「一般枠(第二新卒可)」での受験でした。
「正直、学力テストはどうにかなると思っていました。でも、性格検査があると知ってからは少し焦りましたね。自分の“素”を出すことに抵抗がありました」
性格検査対策として、Bさんはアプリの模擬診断を繰り返しながら、「自己分析ノート」を作成。自分の行動傾向や、働く上で大事にしたい価値観を言語化することで、矛盾のない回答ができるようになったといいます。
「公務員に向いてる性格って、安定感とか協調性って言われるじゃないですか。自分はそこが強みだったんだって、振り返る中で気づけました。SPIの性格検査って、就活の自己分析にもつながると思います」
共通点は「短期間でも継続した対策」
2人の体験談に共通するのは、「限られた時間でも、目的を絞って継続した」こと。特にSPIは、問題形式への慣れと、性格検査への理解が合格のカギとなったようです。
「完璧にやる」のではなく、「今の自分に必要な対策に集中する」ことが、第二新卒で公務員を目指す際には効果的だと言えます。
SPIと他の公務員試験との違い
第二新卒で公務員を目指す場合、自治体ごとに試験方式が異なるため、選考フローや筆記試験の内容をよく比較しておくことが重要です。特にSPIが課される自治体を受験する場合は、一般的な「教養試験」や「専門試験」との違いを理解しておかないと、対策の方向性を誤ってしまうことがあります。
この章では、SPIと他の筆記試験との違いや、受験戦略を立てる上での注意点について詳しく見ていきましょう。
一般教養試験・専門試験との比較
まず、最も広く行われているのが「教養試験(一般知能・一般知識)」です。これは中学~高校レベルの知識や論理的思考力を問う試験で、時事問題や日本史、地理、理科、数学、文章理解など、出題範囲が広いのが特徴です。
これに対し、SPIは出題範囲が明確に決まっており、文系・理系を問わず一定のフォーマットで出題されます。
| 試験形式 | 出題範囲 | 難易度 | 対策方法 |
| 教養試験 | 時事・知識・文章・計算・理科など | 高め(暗記+応用) | 過去問・問題集で暗記と理解 |
| 専門試験 | 法律・経済・土木・建築など | 高い(学部レベル以上) | 大学の履修内容と並行して対策 |
| SPI | 言語・非言語・性格検査 | 中程度(スピード重視) | 問題集・アプリで形式慣れ |
SPIのメリットは、短期間で効率よく対策が可能な点にあります。専門知識の習得が必要な他の試験と異なり、「出題形式に慣れること」と「時間配分の練習」に絞って学習できるため、学業や仕事と並行して準備しやすいのが強みです。
SPI導入自治体では「一発勝負」の傾向が強い
教養試験や専門試験では、筆記と人物面接、論文など複数の要素で合否が判断されますが、SPI導入型の自治体では「SPIでふるいにかけられる」ケースも珍しくありません。
つまり、SPIで基準を下回ってしまうと、その時点で不合格になるリスクが高いということです。
このようにSPI型試験では、一次試験(SPI)が実質的な通過ラインとなるケースもあるため、しっかりと事前準備をしておくことが不可欠です。
複数受験する場合の戦略的な受験計画
複数の自治体を併願する場合は、「試験形式の違い」に注意しましょう。
- A市:教養試験+面接
- B市:SPI(テストセンター)+面接
- C市:SPI(自宅受検)+論文
このように、各自治体ごとに試験内容や実施方法が異なるため、1ヶ月単位でのスケジュールと対策内容を整理しておくことが大切です。
SPI型を含む複数併願を予定しているなら、SPIは最初に対策を終えておくと、他の筆記試験や論文対策にも余裕を持って取り組めるようになります。
まとめ|第二新卒×公務員SPIは情報と準備がカギ
第二新卒として公務員を目指すなら、SPIの有無とその対策は合否を左右する重要なポイントになります。この記事を通じてお伝えしてきたように、SPIを導入している自治体は着実に増えており、とくに第二新卒枠や経験者枠では、SPIが選考の主軸として扱われることもあります。
自治体ごとにSPIの有無・形式が異なるので要リサーチ
まず大前提として、すべての自治体でSPIが使われているわけではありません。そのため、志望する自治体の採用情報を早めにチェックし、「SPIが必要なのか?」「どの形式か?(テストセンター・Web・自宅受検)」を確認することが第一歩です。
この記事内でも紹介した「SPI出題マップ」や「試験リスト」を参考にしながら、自分の受験プランに合わせて情報収集を進めましょう。
第二新卒はSPI重視されやすい立場
社会人経験が少ない第二新卒にとって、SPIは「学力」と「人物像」の両面を判断するツールとして非常に有効に使われます。これは企業でも公務員でも同じで、「今の実力」や「職務への適性」を客観的に測ることができるからです。
裏を返せば、SPIで良いスコアを取ることができれば、経歴に自信がなくても挽回が可能になります。
対策すれば十分に突破可能。早めの行動が内定を引き寄せる
SPIは、出題範囲が明確で対策しやすく、短期間の勉強でも成果が出やすい試験です。「何をすればいいか」がわかれば、あとは継続して取り組むだけ。
特に第二新卒のSPI対策においては、以下のポイントが成功の鍵になります。
- 問題形式に慣れるためにアプリや参考書で演習する
- 時間配分の練習を繰り返し、本番のスピード感に慣れる
- 性格検査に向けて、自分の強み・価値観を整理する
本記事で紹介した体験談や勉強法を参考に、ぜひ今日から対策を始めてみてください。しっかり準備をすれば、SPIは怖くありません。
「自分にはまだ早いかも」と思うのではなく、「今からでも間に合う」と信じて一歩を踏み出すことが、公務員合格への最短ルートです。