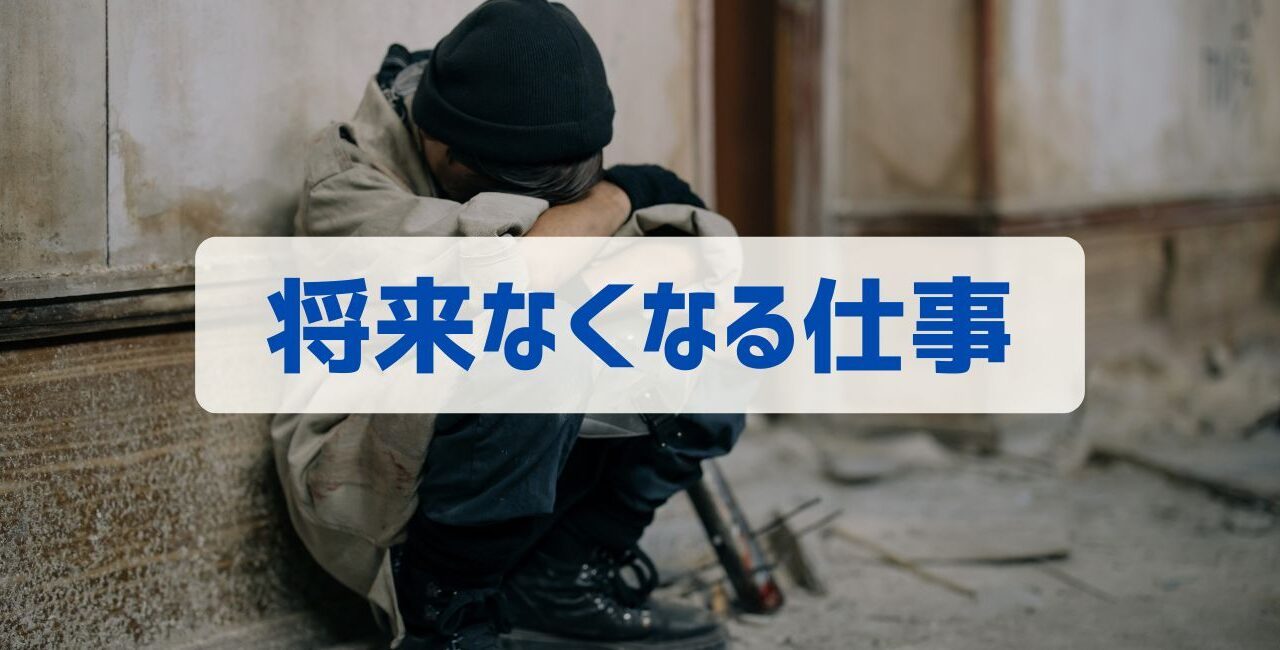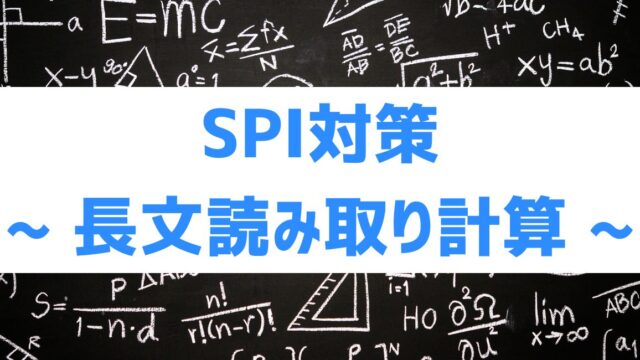【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「この仕事、10年後もあるのかな…」
就活を進める中で、ふとそんな不安を感じたことはありませんか?
AIやロボットの進化がめざましい現代。
「将来なくなる仕事」という言葉を耳にするたびに、自分の選ぼうとしている職業が大丈夫かどうか、不安になる人も多いと思います。
でも、悲観する必要はありません。
大切なのは、これからの時代に合った仕事とは何かを知り、将来を見据えて動き出すことです。
この記事では、将来なくなる可能性がある仕事の具体例を32職種紹介しながら、AIや自動化の影響を受けやすい仕事の特徴や今のうちからできる対策と行動について解説していきます。
不安を行動に変えたい就活生の方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
目次
AIやテクノロジーの進化で仕事がなくなる時代が来ている
これまで「人間にしかできない」と思われていた仕事が、次々と機械に置き換わる時代が近づいています。
この変化は、未来の話ではなくすでに始まっている現実です。
10年〜20年で仕事の約半数がなくなる?オックスフォード大学の衝撃データ
オックスフォード大学と野村総合研究所の共同研究では、今後10〜20年のうちに約49%の仕事が自動化によって代替される可能性があると指摘されています。
特に、単純作業・定型業務の仕事は、AIやロボットの進化によって真っ先に影響を受けると考えられています。(参考:日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に)
自動化・AI導入が加速する社会で何が変わるのか
すでに私たちの身近な場所でも、自動化の波は進んでいます。
・スーパーのセルフレジ
・ネットバンキング
・カスタマーサービスのチャットボット
・飲食店の自動注文システムや配膳ロボット
・オンラインでの翻訳や文章生成ツールの普及
こうした技術は、効率化やコスト削減の観点から導入が進んでおり、人が行っていた業務が機械に置き換わるスピードは年々加速しています。
実際に減少傾向にある職業の具体例
すでに国内でも、人手が減少している職種が出てきています。
・銀行の窓口業務
・百貨店の受付・案内スタッフ
・新聞・雑誌の編集・校正・ライター職
・工場のライン作業員
・単純な入力業務の事務職
仕事が消えるというよりも、「人がやる必要がなくなる仕事が増える」と言った方が正確かもしれません。
将来なくなる仕事32選|AI・ロボットで代替されやすい職業
将来なくなる可能性がある仕事32選を一覧形式で解説していきます。
「必ずなくなる」というわけではありませんが、AIや自動化によって代替される可能性が高いとされる仕事です。選ぶ際の参考にしてみてください。
事務職
仕事内容:
・データ入力
・書類作成
・備品管理
・スケジュール調整など
なぜ代替される?
定型的な作業が多く、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIツールでの自動化が進んでいます。ミスが少なく、24時間稼働できることがメリットです。
今後の変化:
簡単な処理業務は機械が担当し、人間は企画や顧客対応など、より判断力や提案力が求められる仕事にシフトしていく可能性があります。
銀行員(窓口業務)
仕事内容:
・口座開設
・振込・入出金対応
・金融商品案内など
なぜ代替される?
ネットバンキングやATM、スマホアプリの普及により、来店者数が減少。店舗の統廃合も進み、人的コスト削減が進行しています。
今後の変化:
対面での説明が必要な複雑な資産運用相談などは残るが、多くの処理業務は無人化され、店舗自体がなくなる可能性もあります。
受付・フロントスタッフ
仕事内容:
・来訪者の案内
・電話応対
・予約確認など
なぜ代替される?
タブレット型受付端末やAI音声案内が普及し、無人で対応できるケースが増加。人手を介さずに効率よく管理できるからです。
今後の変化:
企業の顔としての受付は減少し、施設案内や顧客対応はオンライン・遠隔で行う流れが主流になります。
清掃員
仕事内容:
・オフィス・施設の床清掃
・ゴミの回収
・トイレや共用部の清掃など
なぜ代替される?
自動掃除ロボットの精度向上により、床の清掃などは人手をかけずに対応可能になってきています。
今後の変化:
広い施設や深夜清掃などはロボット対応に置き換わり、人間はロボットがカバーできない細かい場所やメンテナンス業務へ移行すると考えられます。
秘書
仕事内容:
・スケジュール管理
・会議設定
・出張手配
・資料作成など
なぜ代替される?
GoogleカレンダーやAIアシスタント(例:x.ai、TimeHeroなど)によるスケジュール調整が可能になってきたためです。
今後の変化:
定型業務はAIが対応し、人間の秘書は「経営陣との信頼関係構築」「臨機応変な判断」など、高度なコミュニケーション能力が求められる部分に集中していくと見られます。
テレマーケター/電話オペレーター
仕事内容:
・商品・サービスの電話案内(発信)
・問い合わせ・クレーム対応(受信)
・応対履歴の記録
なぜ代替される?
音声認識技術やAIチャットボットの進化により、定型的な問い合わせや案内は自動音声で対応可能になっています。24時間対応も可能で、人件費削減効果も高いです。
今後の変化:
感情に配慮した対応が必要な場面や、クレーム処理などは人間が担当し、一般的な質問や予約受付などはAIが担うようになります。
スーパー・コンビニ店員/レジ打ち
仕事内容:
・商品のレジ打ち、精算
・商品補充・陳列
・簡単な接客
なぜ代替される?
セルフレジや無人店舗(例:AmazonGo)の導入が進み、“レジを通す”作業自体が不要になる未来が近づいています。
今後の変化:
人間の役割は、トラブル対応や高齢者の補助などに限定され、フロアの管理者に近い立場へ変化していくと予想されます。
工場作業員
仕事内容:
・ライン作業(組立、検査、梱包など)
・機械の操作・監視
・資材の搬入出
なぜ代替される?
すでに製造業では、産業用ロボットによる自動化が進んでおり、繰り返しの単純作業は完全に自動化可能です。
今後の変化:
人間はロボットの操作や保守管理など、より技術的な役割にシフトしていくことが求められます。
配達員
仕事内容:
・荷物の受け取り・仕分け
・配達先までの輸送・受け渡し
・再配達対応
なぜ代替される?
ドローン配送や自動運転車の実証実験が進み、最後の“ラストワンマイル”の自動化が現実味を帯びてきています。
今後の変化:
すべての配達が自動になるわけではありませんが、都市部や定期便のようなルートは自動化され、人間は「例外対応」や高齢者サポートなどに特化する可能性があります。
タクシー/バス/電車の運転手
仕事内容:
・車両の運転
・乗客対応(案内、運賃の収受など)
・安全運行の確認
なぜ代替される?
自動運転技術の進化により、無人での運行実験が進行中。交通量の少ない区間や定期運行ルートでは、すでに導入が始まっています。
今後の変化:
完全自動運転には法整備や安全性の問題があるため段階的になりますが、特に都市交通やシャトル運行から無人化が進みます。
翻訳者
仕事内容:
・書類、資料、Webサイトなどの翻訳
・多言語間の文章の正確な変換
・語調や文脈の調整
なぜ代替される?
DeepLやGoogle翻訳などの高精度AI翻訳ツールが普及し、ビジネス文書や観光案内など、一定の分野ではすでに人手が不要に。
今後の変化:
専門性や表現力が問われる文芸翻訳や法務翻訳は残る一方で、汎用的な翻訳は完全に自動化される可能性が高いです。
ライター
仕事内容:
・記事やコラムの執筆
・SEOを意識したWebコンテンツの制作
・情報収集・構成・編集
なぜ代替される?
ChatGPTやBardなど、生成AIの台頭により、情報整理・構成・文章作成の自動化が急速に進んでいます。
今後の変化:
データ中心のライティング(例:商品紹介・旅行記事など)はAIが担当し、人間はインタビューや取材、独自視点の企画記事に特化していくでしょう。
校正・校閲
仕事内容:
・文章の誤字脱字チェック
・表記の統一
・内容の事実確認やファクトチェック
なぜ代替される?
AIは文章の構造分析や文法チェックが得意で、校正ツール(例:JustRight!、Grammarly)が高精度化しており、人間よりも早く正確に処理できます。
今後の変化:
完全自動化は難しいものの、AIツールを活用しながら人間が最終確認をする「ハイブリッド型」に移行していくと考えられます。
調理スタッフ
仕事内容:
・仕込み・加熱・盛り付けなど調理工程の実施
・衛生管理
・食材の在庫管理
なぜ代替される?
チェーン店を中心に、調理ロボットやセントラルキッチン方式が普及しており、決まった手順の料理は全自動で調理可能になっています。
今後の変化:
高級レストランや個人経営の店では人の技術が重要ですが、ファストフードや量産型業態では機械化がさらに加速すると見られています。
プログラマー
仕事内容:
・Web・アプリ・業務システムのプログラミング
・バグ修正や機能追加
・コードレビューやテスト
なぜ代替される?
GitHubCopilotやChatGPTなどのAIが、人間の入力した指示からソースコードを自動生成する技術が急速に進化しています。
今後の変化:
単純なコーディング作業はAIに任せるようになり、人間は仕様設計や複雑なロジック開発など、上流工程へと役割がシフトしていくでしょう。
デザイナー(特にWebバナー・広告系)
仕事内容:
・広告バナーやLPなどの制作
・SNSやWeb用のビジュアル作成
・簡易的なロゴ・画像編集
なぜ代替される?
Canva、AdobeFirefly、FigmaAIなど、デザインテンプレートや自動生成機能が整ってきており、非デザイナーでも作成可能になりつつあります。
今後の変化:
テンプレート化しやすい単純作業はAIが担い、ブランディング設計や独自性の高いクリエイティブ制作に人の価値が集中していきます。
広告運用者(Web広告)
仕事内容:
・Google広告やSNS広告の設計・配信・効果測定
・予算管理・入札調整
・クリエイティブのABテストなど
なぜ代替される?
GoogleやMetaの広告プラットフォームが、AIによる最適化(自動入札・自動ターゲティング)機能を備えており、専門知識がなくても成果を出せるように。
今後の変化:
「運用作業」は自動化され、広告戦略立案やブランド構築など、上流の企画力が重視される時代になります。
税理士・会計士・監査・法務関連
仕事内容:
・税務申告書の作成
・帳簿のチェック
・契約書の作成・確認
・監査業務
なぜ代替される?
会計ソフトやAI会計(freeeやマネーフォワードなど)により、日々の仕訳・帳簿作成・税計算はほぼ自動化可能。法務分野でもAIによる契約書レビューが広がっています。
今後の変化:
形式的なチェックや定型書類作成は機械が担い、人間はアドバイザー・コンサルタント的役割へと変化していく見込みです。
医療関係(一部)
仕事内容(対象職種):
・レントゲンやCTなどの画像診断
・薬の処方判断
・問診と診断業務
なぜ代替される?
画像診断AI(例:医用画像認識技術)は、人間よりも高精度で病変を検出するケースもあり、補助的に活用が進んでいます。
今後の変化:
AIが初期診断・予測を行い、医師はそれをもとに最終判断を下す「意思決定者」としての役割がより強くなると考えられます。
このように、すべての仕事が消えるわけではありませんが、一部業務が機械に代替され、働き方や求められるスキルが変化するのが現実です。
将来なくなる仕事の共通点3つ
AIやロボットによって代替されやすい仕事には、いくつかの共通点があります。以下の3つの特徴を理解しておくことで、自分の志望職種や今後のキャリア設計に役立てることができます。
共通点①:ルーティン化しやすい・自動化しやすい業務
もっともAIに置き換えられやすいのは、「決まった手順で行える作業」や「例外が少ない処理」です。
例:
・書類の作成・管理(事務職)
・帳簿や仕訳の処理(経理・会計)
・画像のスキャンと病変の判別(放射線科医)
・バナーの自動生成(広告デザイナー)
これらは、過去のデータやアルゴリズムによって学習すれば、人間以上のスピードと正確さで実行できるようになるため、代替が進みやすいのです。
共通点②:人と対話せずに完結する仕事
「人間同士のコミュニケーション」を必要としない仕事も、AIや機械が得意とする分野です。
特に、感情のやり取りや状況判断が必要ない仕事は、無人化が進みやすい傾向にあります。
例:
・無人受付(来客の案内)
・チャットボットによる問い合わせ対応
・定型化された面談予約や日程調整
・セルフレジやスマホ決済による接客削減
反対に、感情を読み取って対応する接客や、雑談・空気を読む必要がある仕事は、現時点ではAIが苦手とする部分です。
共通点③:マニュアル通りにこなすことが求められる職種
手順が明確で、正確に実行することが重要な仕事は、AIやロボットが得意とするジャンルです。
例:
・工場のライン作業
・調理工程の再現
・契約書や請求書のフォーマット入力
・カスタマーサポートでのFAQ対応
こうした業務は、効率化・ミス削減の観点から、人手よりも機械に任せた方がコストパフォーマンスが高いという理由で自動化が進んでいます。
この3つの特徴を複数持つ職種ほど、将来AIやロボットに置き換えられるリスクが高いと考えられます。
逆に言えば、これらの特徴に「当てはまらない仕事」や「人間だからこそできる仕事」こそが、今後も価値を持ち続ける仕事です。
将来もなくならない仕事の特徴と代表職業
AIやロボットが進化する一方で、人間にしかできない仕事、人間だからこそ価値を発揮できる仕事もあります。
ここでは、そうした「将来もなくならない仕事」に共通する特徴と、代表的な職業を紹介します。
特徴①:人間的なコミュニケーションが必要な仕事
AIは情報処理は得意でも、「相手の気持ちを汲み取る」「空気を読む」「信頼関係を築く」といった人間らしい対話や感情理解はまだ苦手です。
このため、以下のような仕事は今後も人間にしかできないと考えられています。
代表的な職業:
・カウンセラー、臨床心理士
・介護士、保育士
・営業職(特に法人営業・コンサル営業)
・教師・教育関連職(生徒ごとの対応が求められる)
・医師・看護師(患者との信頼関係が重要)
特徴②:創造性やアイデアが求められる仕事
ルールや過去のデータにとらわれずに、新しいものを生み出す力=創造力は、AIには模倣はできても本質的に発揮することが難しい分野です。
代表的な職業:
・企画職(商品開発・サービス設計)
・マーケター(市場の変化を読み、戦略を考える)
・プロデューサー、ディレクター(全体をまとめあげる)
・起業家(新しいビジネスを創る)
・作家、映像クリエイター、アーティスト
今後、生成AIはアシスタントとして使われることはあっても、“最初の発想”や“本質をとらえる視点”は人間にしか出せない価値です。
特徴③:複雑な判断や多面的な調整が求められる仕事
現実社会は単純なルールだけで動いているわけではありません。
複数の立場や状況を踏まえながら柔軟に判断する仕事は、AIによる完全代替が難しいとされています。
代表的な職業:
・経営者、マネージャー
・プロジェクトマネージャー(PM)
・人事(採用・人材配置・組織開発など)
・コンサルタント(課題解決の提案)
・政治家、政策担当者など
これらは、「データ通りに動けば正解」とはいかないため、経験や勘、人間関係の調整力など、目に見えない能力が求められます。
特徴④:トラブルや想定外への柔軟な対応が求められる仕事
AIはマニュアル化された仕事には強いですが、予定外の事態やその場の判断が求められる状況には対応が遅れることがあります。
代表的な職業:
・看護師(急変対応など)
・災害現場の救助隊員
・警察官・消防士
・接客業(複雑な顧客対応)
・現場監督(複数業者との調整が必要)
特に医療・福祉・公共安全の領域では、人間が現場で臨機応変に動く力が今後も重要視され続けるでしょう。
これらの特徴をふまえると、今後AI時代においても仕事を失わないためには、
・感情を扱う
・新しい価値を生む
・多面的な視点で判断する
・予測不能な状況に対応する
といった力がますます大事になってくることがわかります。
将来性のある仕事に就くために今からできること
①AIに使われる側でなく、活用する側になる
今後、「AIを使いこなせる人材」には大きな価値が生まれます。
単純作業を奪われる側ではなく、AIを使って効率化・生産性向上ができる人になることが、将来性のあるキャリアへの第一歩です。
例えば以下のようなスキルが有効です。
・ChatGPTなど生成AIツールの使い方
・Excel関数やGoogleスプレッドシートの自動化
・簡単なプログラミング(Pythonなど)
・ノーコードツールの活用(Notion、Airtable、Zapierなど)
“AIで何ができるかを理解し、それを仕事にどう活かすか”という視点を持つことが重要です。
②コミュニケーション・課題解決スキルを磨く
今後もAIにできないのは、「人との信頼関係を築く力」や「本質的な課題を見つけて解決する力」です。
つまり、“人間力”や“思考力”は時代が変わっても武器になります。
具体的には…
・傾聴力や説明力を磨く(プレゼン、ディスカッションの練習)
・課題発見・改善提案の経験を積む(ゼミ・インターン・バイトなど)
・相手の立場を想像して行動するトレーニング
こうした力は、営業・企画・人事・教育など、AIでは代替できない多くの職種で重視されるポイントです。
③将来性の高い分野(IT・医療・教育など)を知る
「どんな仕事が将来も価値があるか」は、産業構造や社会ニーズによっても左右されます。
以下のような分野は、今後10年〜20年でニーズが伸びると予測されています。
・IT・デジタル分野(AI、セキュリティ、DX、Webマーケなど)
・医療・介護・福祉(高齢化社会に向けた人材需要)
・教育・キャリア支援(リスキリングや研修業界)
・再生可能エネルギー・環境ビジネス
・地域活性・観光などの地方創生系職種
興味のある分野を少し広げて、社会的に伸びている業界を探してみることも、就活戦略の一つです。
④複数のスキルをかけ合わせて自分だけの強みを持つ
「1つの専門だけ」ではAIに負ける時代になるかもしれません。
しかし、「自分にしかできないスキルの組み合わせ」があれば、代替されにくく、唯一無二の価値を発揮できます。
例:
・ITスキル×語学→グローバル対応できるエンジニア
・デザイン×マーケティング→売れるクリエイティブが作れる人
・福祉×教育→発達支援の専門家
・経理×データ分析→数字で意思決定を支援できる人材
今から少しずつで構いません。
「+αのスキルや知識」を増やす意識が、将来の武器になります。
まとめ
AIやロボットの進化により、私たちの働き方は大きく変わり始めています。
事務・レジ・翻訳など、「効率化しやすい」「人と関わらない」「マニュアル通りにこなす」といった仕事は、これからますます自動化が進むでしょう。
一方で、人間にしかできない仕事や、人間だからこそ価値を発揮できる仕事も確実に存在します。
「自分のやりたい仕事が将来なくなったらどうしよう」と不安になるのは自然なことです。
でも、大切なのは“なくなるかどうか”ではなく、“どのように価値を発揮できるか”を考えることです。
もしAIに仕事の一部が代替されるなら、自分は何をするべきか?
その視点でキャリアを描いていけば、変化の激しい時代でもきっと自分らしい働き方を見つけられます。
将来を悲観せず、「自分の可能性は、自分で広げられる」という前向きな気持ちで、ぜひ就活に取り組んでください。
あなたの未来に役立つ選択ができることを、心から応援しています。