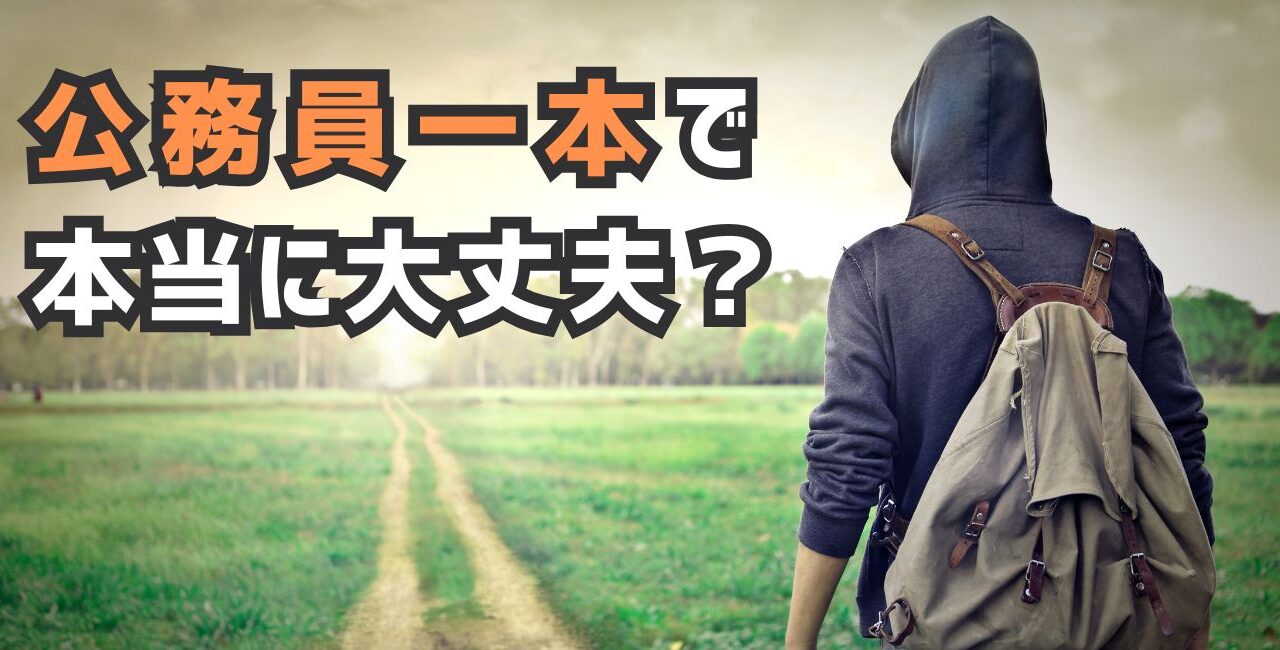【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
公務員になりたい場合、公務員試験は長期にわたる勉強が必要です。そのため対策に集中するために公務員専願を選ぶ人もいれば、試験に落ちたときのリスクを考えて民間企業との併願をする人もいます。
どちらを選ぶべきかは、自分の性格や志望度、リスク許容度によって異なります。公務員試験が初めての大学生だとどちらにすべきか決めかねている人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、公務員専願と併願の違いや、それぞれのメリット・デメリット、選び方のポイントを詳しく解説します。さらに、公務員試験に落ちた場合の進路や、両立するためのスケジュール管理の方法についても紹介します。
自分に合った選択をするために、まずはしっかり情報を整理していきましょう。
目次
公務員専願とは?併願との違いを理解しよう
公務員試験を受けるにあたり、最初に決めるべきことが「専願にするか、併願にするか」です。それぞれの違いを理解し、自分に合った進め方を考えましょう。
公務員専願と併願の定義
一方で、公務員併願とは、公務員試験を受けながら、並行して民間企業の就活も行うことを意味します。最終的な選択肢が広がるメリットがありますが、試験勉強と就活を両立するための負担が大きくなるのがデメリットです。
公務員専願とは、民間企業の就活を行わず、公務員試験一本に絞ることを指します。試験対策に集中できるため、合格率を高めるメリットがありますが、もし試験に落ちた場合、次の進路をどうするか考える必要があります。
公務員試験のスケジュールと選考プロセス
公務員試験は、受験する自治体や職種によってスケジュールが異なりますが、一般的な流れは以下のようになっています。
| 時期 | 試験の流れ |
| 4月~6月 | 地方公務員(市役所・県庁)や国家公務員の一次試験 |
| 7月~8月 | 一次試験合格者が二次試験(面接)を受験 |
| 9月~10月 | 最終合格発表 |
| 10月以降 | 採用者の内定・研修準備 |
公務員試験の結果が出るのは、9月~10月が多いため、専願の場合、この時点で不合格だと次の進路を考える必要があります。
民間企業との選考スケジュールの違い
民間企業の就活は、公務員試験とはスケジュールが異なります。
| 時期 | 民間企業の流れ |
| 3月~6月 | 企業説明会・エントリー |
| 6月~8月 | 面接・内定出し |
| 9月~11月 | 追加募集・秋採用 |
| 12月以降 | 通年採用や二次募集 |
このように、公務員試験と民間企業の就活は時期がずれているため、上手く計画を立てれば両立も可能です。
次の章では、公務員専願と併願、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。
公務員専願・併願それぞれのメリットとデメリット
公務員試験に向けて「専願にするか、併願するか」を決める際には、それぞれのメリット・デメリットを把握しておくことが重要です。ここでは、公務員専願と公務員併願の特徴を比較しながら解説します。
公務員専願のメリット・デメリット
【メリット】試験対策に集中できる
公務員試験は、筆記試験の範囲が広く、民間企業の就活と並行するのは負担が大きいです。専願にすることで、勉強時間を十分に確保でき、対策に集中することができます。
特に、数的処理や法律系科目は短期間で習得するのが難しいため、じっくり取り組む必要があります。専願であれば、時間を気にせず試験勉強に専念できるのが最大のメリットです。
【メリット】早期に民間企業の就活ストレスから解放される
民間就活は、企業ごとのエントリーシートや面接準備、筆記試験対策など、多くのタスクをこなさなければならず、精神的にも負担が大きいです。
公務員専願にすれば、民間企業の選考スケジュールに振り回されることなく、試験対策に集中できます。「面接対策やグループディスカッションが苦手」という人にとっては、ストレスを減らせるメリットがあります。
【デメリット】試験に落ちた場合のリスクが大きい
公務員試験は倍率が高く、1回で合格できるとは限りません。もし最終合格できなかった場合、その年の採用には間に合わず、翌年の再チャレンジを考えなければならなくなることもあります。
また、不合格が決まるのは9月~10月頃が多いため、その時点で民間就活を再開するのは難しく、既卒として翌年の就活をする可能性が出てきます。
【デメリット】民間企業の経験を積む機会を逃す
民間企業との併願をしない場合、ビジネススキルや面接経験を積む機会が減ることになります。
例えば、公務員試験の面接では、民間企業の面接とは異なり「志望動機」「公務員としての適性」が重視されます。しかし、併願していれば民間企業の面接を経験し、実践的な面接力を鍛えることができるため、公務員試験の二次試験(面接)にも活かすことが可能です。
公務員併願のメリット・デメリット
【メリット】最終的に選択肢が広がる
併願をすることで、公務員試験に落ちた場合の保険を持つことができるため、精神的な安心感があります。
また、公務員試験に合格した場合でも、「本当に公務員になりたいのか?」を冷静に考える機会を持つことができるため、最終的なキャリアの選択肢が広がります。
【メリット】面接経験を積めるため、公務員試験でも有利
公務員試験の面接対策をする上で、民間企業の面接経験が役立つことがあります。
例えば、公務員試験の二次試験(面接)では、自己PRや志望動機をしっかり伝えられるかが重要ですが、民間企業の面接で練習を積んでおけば、より自信を持って受け答えができるようになります。
【デメリット】試験勉強と並行するのが大変
併願をする場合、公務員試験の勉強と民間企業の就活を両立する必要があるため、スケジュール管理が大変になります。
特に、6月以降は公務員試験の一次試験が本格化する時期であり、民間企業の選考とも重なります。そのため、どちらも中途半端にならないよう、事前にスケジュールをしっかり立てることが重要です。
【デメリット】公務員対策に十分な時間を割けない可能性がある
民間企業の就活を進めながら公務員試験の勉強をする場合、どうしても試験対策の時間が削られてしまいます。
特に、公務員試験の筆記試験は範囲が広く、数的処理や法律・経済科目など、長期的な学習が必要な科目が多いため、十分な対策ができないと合格が難しくなります。
公務員専願・併願のどちらを選ぶべき?
ここまでのメリット・デメリットを踏まえると、次のような考え方ができます。
| 公務員専願が向いている人 | 公務員併願が向いている人 |
| 「絶対に公務員になりたい!」という強い意志がある人 | 公務員試験に落ちた場合のリスクを減らしたい人 |
| コツコツ勉強を続けるのが得意な人 | 複数の選択肢を持っておきたい人 |
| 面接より筆記試験に自信がある人 | 面接経験を積みながら公務員試験の準備をしたい人 |
どちらを選ぶか迷ったら、「自分はどのくらい公務員にこだわりがあるか」「試験に落ちたときにどうするか」を考えることが大切です。
これから公務員専願・併願それぞれの選び方について、さらに詳しく解説していきます
自分に合った選び方のポイント
専願と併願を決める際には、以下のポイントを考えると判断しやすくなります。
- 公務員になりたい理由は明確か?
→「安定しているから」などの理由だけでなく、「どんな公務員になりたいのか?」を考える。 - 試験勉強に集中する環境を作れるか?
→長期間の勉強が必要なため、モチベーションを維持できるかどうか。 - 試験に落ちた場合のリスクを許容できるか?
→不合格時の進路を考えた上で、公務員専願を選ぶか併願するかを決める。
このように、自分の状況を冷静に分析しながら選択することが大切です。
「絶対に公務員になりたい!」場合の考え方
「どうしても公務員になりたい!」という気持ちが強い場合、公務員専願を選ぶのも一つの方法です。ただし、リスク管理も重要になります。
専願にする場合のポイント
- 長期間の勉強計画を立てる
- 途中でモチベーションが下がらないように工夫する
- 試験に落ちた場合のプランも考えておく(再受験or既卒就活)
また、国家公務員と地方公務員の両方を受けることで、合格のチャンスを広げるのも有効です。
「公務員試験が不安…」なら併願も検討しよう
「公務員試験に落ちたらどうしよう…」と不安を感じるなら、併願を検討するのがおすすめです。
併願する場合のポイント
- 公務員試験のスケジュールに影響しない範囲で民間企業も受ける
- 筆記試験の勉強時間を確保できるよう、就活の負担を軽減する
- 最終的にどちらを選ぶかを冷静に判断する
特に、筆記試験の勉強時間を十分に確保するために、就活のエントリー数を絞るのが効果的です。
公務員試験に落ちた後の進路をどう考えるか
公務員試験に専念していた場合、もし不合格になったときの進路をどうするかが重要になります。
- 翌年の再受験を考える(この場合、浪人期間の過ごし方を計画する)
- 既卒で民間就活をする
- スクールや資格取得を考える
次の章では、公務員試験と民間就活を両立する方法について解説します。
公務員試験と民間就活を両立する方法
公務員試験を受けつつ、民間企業の就活も進めるのは簡単ではありません。しかし、うまくスケジュールを管理すれば、どちらの選択肢も残しつつ就職活動を進めることができます。ここでは、公務員試験と民間就活を両立するための具体的な方法を紹介します。
スケジュールを整理して両立の可能性を探る
まず、公務員試験と民間就活のスケジュールを比較し、どこで両立できるかを確認しましょう。
| 時期 | 公務員試験 | 民間就活 |
| 3月~5月 | 筆記試験対策 | エントリー・説明会・書類提出 |
| 6月 | 地方公務員試験の一次試験 | 面接・内定獲得 |
| 7月~8月 | 二次試験(面接) | 秋採用や追加募集へのエントリー |
| 9月~10月 | 最終合格発表 | 民間企業の追加募集 |
このように、3月~5月の時点で民間企業のエントリーを進めておき、6月以降は公務員試験に集中するという形を取ると、比較的負担が少なくなります。
民間企業のエントリーはどこまで進めるべきか
併願する場合、民間就活にどこまで力を入れるかがポイントになります。
- エントリーを最小限に絞る(5~10社程度に限定)
- 志望度が高い業界や企業に集中する
- 公務員試験と日程が被らない企業を優先する
無理にたくさんエントリーすると、面接や筆記試験が重なり、両立が難しくなるため、慎重に進めましょう。
面接や試験日が重なった場合の対処法
公務員試験と民間企業の選考が同じ日に重なってしまうこともあります。その場合の対処法を考えておきましょう。
- 民間企業の選考日程を調整する
→企業によっては、別日程での面接を相談できることもあるため、早めに問い合わせてみる。 - 公務員試験を優先し、民間就活は秋採用に切り替える
→6月以降の公務員試験が本格化する時期は、民間就活を一時中断し、秋採用で再開する選択もあり。 - どちらの優先度が高いかを決める
→本命が公務員試験なら、民間企業の面接を辞退する選択肢も視野に入れる。
両立を目指す場合、どこまで民間就活を進めるかを早めに決めておくと、迷わず行動できるようになります。
次の章では、公務員専願で不合格だった場合の選択肢について解説します。
公務員専願で不合格だった場合の選択肢
公務員試験は倍率が高く、1回で合格するとは限りません。もし不合格になった場合、その後の進路をどうするかが重要になります。ここでは、公務員試験に落ちた場合の主な選択肢と、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
1.再チャレンジする場合
公務員試験に落ちても、翌年に再受験することは可能です。ただし、浪人期間をどう過ごすかが重要になります。
再受験のメリット
- 筆記試験の対策が進んでいるため、次回はより有利に挑める
- 自治体や職種によっては、翌年の試験で加点制度がある場合もある
- 早めに再チャレンジを決めれば、予備校などでさらに対策を強化できる
再受験するデメリット
- 1年間のブランクができる
- 家族や周囲のプレッシャーが大きくなる
- 民間企業の新卒採用には参加できなくなる(既卒扱いになる)
再受験を決めるなら、「この1年をどう過ごすか」を計画し、無駄にしないことが大切です。
2.既卒で民間就活をする場合
公務員試験が不合格だった場合、既卒として民間企業の就活をする選択肢もあります。ただし、新卒と比べると、就職活動の難易度がやや上がるため、対策が必要です。
既卒での就活のポイント
- 既卒向けの就活エージェントを活用する
- 公務員試験で培った知識やスキルをアピールする
- 未経験でも応募できる職種(営業、事務、ITエンジニアなど)を探す
既卒就活のメリット
- 公務員試験の経験を活かして応募できる企業もある
- キャリアの幅を広げるチャンスになる
- すぐに社会人経験を積めるため、スキルアップが早い
既卒就活のデメリット
- 新卒採用枠には応募できないため、求人の選択肢が狭まる
- 企業によっては、既卒を採用しないところもある
- 「なぜ公務員試験に落ちたのか?」と聞かれることがある
既卒として就活をするなら、「公務員試験に落ちた理由」を前向きに説明できるように準備しておくことが大切です。
公務員専願で成功した人・後悔した人の事例
公務員専願を選んだ人の中には、「対策に集中して合格できた!」という成功例もあれば、「落ちてしまい、進路に迷った…」という後悔の声もあります。ここでは、3つの事例を紹介し、それぞれのケースから学べるポイントを解説します。
試験対策に集中して合格したNさんの成功談
Nさんの状況
- 大学3年の夏から本格的に公務員試験対策を開始
- アルバイトを減らし、1日5時間以上の勉強時間を確保
- 予備校に通いながら計画的に学習
- 模試を何度も受けて、試験本番の感覚をつかんだ
- 面接対策も早めに始め、対策講座を受講
成功したポイント
早めの対策開始で余裕を持てた
筆記試験・面接ともに計画的に対策できた
公務員以外の進路を考える必要がなかった
Nさんのように、公務員試験一本に集中して早めに計画を立て、しっかり対策を進めることができれば、高い確率で合格できる可能性があります。
専願にしたけど落ちて後悔したRさんのケース
Rさんの状況
- 大学4年の春から本格的に勉強を始めた
- 民間就活は全くせず、試験勉強のみに集中
- 一次試験には合格したものの、二次試験(面接)で不合格
- 9月に不合格が決まり、そこから民間企業の就活を始めるが苦戦
- 結局、就職が決まらず、翌年の再受験を選択
後悔したポイント
勉強時間が足りず、試験対策が不十分だった
面接対策をしっかり行わなかったため、二次試験で落ちた
公務員試験に落ちた後の進路を考えていなかった
Rさんのケースでは、筆記試験に合格しても、面接対策が不十分だと最終的に不合格になることがあることがわかります。また、公務員専願にする場合でも、「万が一落ちたらどうするか?」というリスク管理をしておくことが重要です。
併願して民間と迷ったKさんの決断ポイント
Kさんの状況
- 大学3年の冬から公務員試験の勉強を開始
- 民間企業も並行してエントリーし、春には内定を獲得
- 公務員試験に合格したが、民間企業の内定も魅力的だった
- 最終的に、公務員ではなく民間企業への就職を選択
決断のポイント
併願することで選択肢を広げられた
実際に内定をもらってから、公務員と民間を比較できた
民間企業でのキャリアに魅力を感じ、そちらを選択
Kさんのように、併願をしておくと、「本当に公務員が自分に合っているのか?」を冷静に考えることができます。また、もし公務員試験に落ちた場合でも、すでに民間企業の内定があれば安心して次のステップに進むことができます。
まとめ:後悔しない選択をするために
公務員試験に向けて、専願にするか併願するかを決めるのは重要な判断です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った選択をすることが大切です。
公務員試験は、一度の挑戦で必ず合格できるとは限りません。しかし、しっかりと計画を立て、リスク管理をしながら進めれば、後悔のない選択ができるはずです。
どの選択をするにしても、まずはしっかりと情報を集め、自分に合った道を見つけましょう。