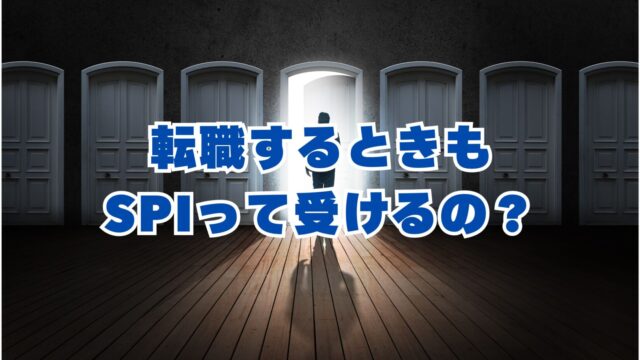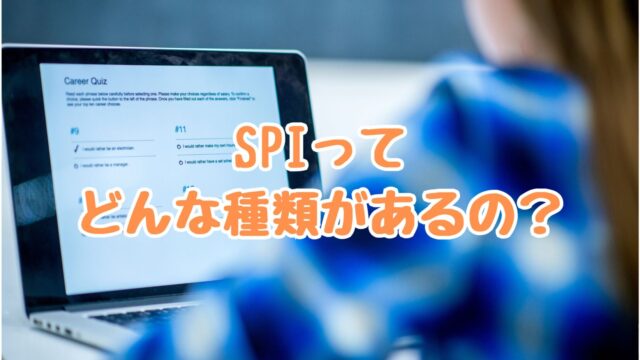【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
転職活動を始めると、思わぬ壁として立ちはだかるのが「SPI(適性検査)」です。新卒のときに一度受けた経験がある方もいるかもしれませんが、いざ転職で再び向き合うとなると、「前より難しく感じる」「どのくらいの点数が必要?」「そもそも落ちることってあるの?」と、不安や疑問が浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
特に書類選考を突破して「いざ面接」と思った矢先にSPI受検を求められると、どうしても焦ってしまいがちです。転職活動は時間との戦い。準備不足のまま臨んで失敗すると、後悔が残ってしまいます。
本記事では、転職におけるSPIの通過率の目安や、スコアごとの対策法、企業ごとのSPIの位置づけ、さらにはSPIで落ちないためのポイントまで徹底的に解説します。さらに、あなたが今どれくらい通過できる可能性があるのかを判断できる診断チャートや、実際にSPIで苦戦・成功した転職者の体験談も紹介します。
SPIの通過率は決して「運」ではありません。しっかり準備すれば、あなたも十分に通過可能です。この記事を通して、自信を持ってSPIに臨めるようになっていただけたら幸いです。
目次
SPIの通過率はどれくらい?
転職におけるSPIの通過率は一律ではなく、企業や職種によって大きく異なります。ここでは通過率の目安や、スコアごとの基準について解説します。
全体の通過率の目安
転職時に行われるSPIの通過率は、一般的にはおおよそ30~50%程度といわれています。つまり、ざっくり言えば半分くらいの人は通過できるというイメージです。ただし、この数値はあくまでも平均的な目安であって、応募する企業の業界・規模・選考フローによって大きく変わってきます。
たとえば、人気の高い大手企業や有名外資系企業などでは、SPIを「足切り目的」で実施しており、ここで一気に半数以上が落とされるというケースも珍しくありません。一方で、ベンチャー企業や中小企業の中にはSPIをそこまで重視しておらず、「面接重視」の姿勢を取っている場合もあります。そのような企業ではSPIの通過率が70%以上という例もあります。
このように、SPIの通過率は企業によってまったく異なるため、まずは「自分が受ける企業がSPIをどの段階で実施するのか」「選考の中でどれくらい重視されているのか」を理解することが、的確な対策を行ううえでの第一歩になります。
また、SPIの通過率は応募者全体のレベルにも影響されます。書類選考の倍率が高い企業ほどSPI通過のハードルも上がりやすく、いわば「SPI=学力のふるい」によって、選考全体の母集団をコントロールしているのです。
このように、単なる数字だけで一概に通過率を語るのは難しいですが、全体像を掴むうえでは30~50%がひとつの基準となります。次の項目では、さらに詳しく「スコア別」の通過ラインについて見ていきましょう。
スコア別の通過ライン目安
SPIは「◯点以上なら必ず合格」という明確な基準があるわけではありませんが、過去のデータや転職者の体験談から、ある程度の「スコア別通過ライン」が見えてきます。
まず5割、つまり全体の半分程度正解できた場合ですが、このスコアでは正直ギリギリのラインです。企業によっては5割でも「他要素で補える」と判断され通過する可能性がありますが、面接前の足切り段階であれば不合格となる可能性も高くなります。
7割程度正解できていれば、かなり安定した通過が見込めるラインです。多くの企業が合否判定の目安として使っているのがこのあたりで、特に事務職や総合職などの一般的な職種では、7割が一つの目安として機能しています。
8割以上を取れるようになると、上位企業や選考倍率の高いポジションでも通過の確率が高まります。このスコア帯の方は、SPIで足を引っ張られることはほとんどありません。ただし、企業によっては8割以上のスコアが前提条件となるケースもあり、その場合は時間内に解き切るスピードや、非言語・言語の両方で高得点を取れるかが鍵になります。
つまり、7割を「目指すべき基準」、8割以上を「安心スコア」として、そこに到達するためにどのように対策をしていくかがポイントになります。次章では、SPIがどのタイミングで実施されるかによって、通過率や重視される度合いがどう変わるかについて解説していきます。
選考フローとSPIの位置づけ
SPIは選考のどの段階で実施されるかによって、その重要度が変わります。選考フロー別にSPIがどのような意味を持つかを整理して解説します。
一次面接前にSPIがある場合
転職活動において、最も多く見られるのが「SPIが一次面接の前に行われる」パターンです。このケースでは、SPIは主に「足切り」の役割を果たします。つまり、一定の基準に達していない応募者を、面接に進ませないためのフィルターとして用いられているのです。
企業にとっては、限られた人事リソースの中で、できるだけ効率的に優秀な人材を選びたいというニーズがあります。そのため、書類選考を通過した後、いきなり面接に進むのではなく、SPIを通じて「基礎的な能力や論理的思考力があるか」「会社の求める人物像と適合しているか」といった点を事前にチェックしています。
このような背景から、一次面接前のSPIは比較的「得点重視」で評価される傾向にあります。たとえば、5割台のスコアでは面接に進めない場合が多く、少なくとも7割以上のスコアが求められることが一般的です。
また、この段階でのSPIには「適性検査(性格)」と「能力検査(言語・非言語)」の両方が含まれるケースが多く、性格検査で極端な結果が出てしまうと、スコアが良くても通過できない可能性もあります。
したがって、SPIが一次面接前に設定されている場合は、事前にしっかりと対策し、高スコアを取ることが求められます。準備不足で挑むと、面接にすら進めずに選考が終了してしまう可能性があるため、十分な注意が必要です。
一次・二次面接後にSPIがある場合
次に、SPIが一次または二次面接の後に実施されるパターンについて見ていきましょう。このパターンは、人物面での評価をある程度行ったうえで、最終的な判断材料としてSPIを活用するという位置づけです。
この場合、SPIは「補足情報」としての意味合いが強くなります。たとえば、面接では好印象だったけれど、「実際の地頭はどうだろうか?」「論理的思考力に欠けていないか?」といった点をSPIで裏付けたいと企業側が考えているのです。
したがって、このタイミングでのSPIでは、極端に低いスコアでなければ選考に大きな影響は出にくい傾向があります。実際、6割前後のスコアであっても、面接の評価が高ければ通過できるケースは少なくありません。
とはいえ、「面接での評価が高ければSPIは適当でいい」と油断するのは危険です。SPIのスコアがあまりに低かった場合、評価に悪影響を及ぼす可能性もゼロではないため、最低限の対策は怠らないようにしましょう。
このタイミングでSPIが課される場合は、特に「性格検査」の結果が重視されることが多く、企業文化やチームとの相性を測る目的で使われる傾向があります。そのため、正直かつ一貫性のある回答を心がけることが重要です。
最終面接後にSPIがある場合
最後に紹介するのは、最終面接後にSPIが課されるパターンです。この形式は比較的珍しいですが、一部の大手企業や公的機関ではこの順序が採用されています。
このタイミングでのSPIは、採用を決定づける最終的な確認としての役割が強く、どちらかといえば「念のためチェックしておこう」という意味合いで使われることが多いです。すでに面接を複数回クリアしている応募者に対し、SPIで致命的な問題がないかを確認する段階です。
そのため、スコアが極端に低かったり、性格検査で一貫性のない回答をしていたりしない限り、SPIの結果が直接的に不合格の理由になることは少ないとされています。むしろ、内定後の配属や教育の参考資料として活用されるケースもあります。
ただし、逆に言えば「よほどのことがない限り通過できる」と油断してしまい、無対策で受けてしまうと、SPIの結果だけで足元をすくわれる可能性もあるということです。特に性格検査は、企業の求める人物像との相性を問われるため、自己分析をしっかり行ってから臨むようにしましょう。
SPI通過率診断チャート
SPIに通過できるか不安な方に向けて、簡単な5つの質問で自分の通過率をセルフチェックできる診断チャートを紹介します。
5つの質問で自分の通過可能性をチェック!
SPIの通過率は、スコアだけで決まるわけではありません。実は、応募する企業の特性や選考フロー、自分の準備状況などの複数の要素が絡み合って結果が左右されます。ここでは、あなたのSPI通過率がどの程度なのかを簡易的にチェックできる「通過率診断チャート」を用意しました。
以下の5つの質問に対して、自分の状況にあてはまるかどうかを確認しながら読み進めてみてください。
1. 応募企業は大手企業か?
大手企業は応募者が多いため、SPIを利用して大量の応募者をふるいにかけるケースが多くなります。特に人気業界や総合職採用ではSPIの得点によって面接に進めるかどうかが決まることも珍しくありません。そのため、応募企業が大手であるほど、SPIの通過ラインは高くなります。
2. 書類選考の倍率は高いか?
倍率が高いということは、それだけ「選考を通過しにくい」ということです。書類選考である程度ふるいにかけられた後、SPIでさらに選抜するというケースでは、通過率はよりシビアになります。倍率が高い企業ではSPIの結果が合否に直結しやすくなるため、注意が必要です。
3. SPIは何次選考のタイミングか?
先ほど紹介したように、SPIが「一次面接前」に設定されている場合、通過率は低くなりがちです。逆に、一次・二次面接の後や最終面接後であれば、SPIの重みは軽くなります。選考のどのタイミングで受けるかによって、合格に求められるスコアの水準も変わってきます。
4. 応募職種は総合職・ポテンシャル採用か?
職種によってもSPIの重視度は異なります。たとえば、エンジニアやクリエイター職では、SPIよりも実務スキルやポートフォリオの方が重視される傾向にありますが、営業や総合職、ポテンシャル採用ではSPIがスクリーニングツールとして活用される場面が多く見られます。そのため、職種によってはSPIの得点が合否に大きく影響することがあります。
5. 対策期間を3日以上とれているか?
SPI対策は「とにかく量をこなすこと」が重要です。とはいえ、1日で全体を完璧に仕上げるのは至難の業。最低でも3日間、理想は1週間ほど、毎日1~2時間程度の対策を行うことで、安定して7割以上のスコアを狙えるようになります。もし対策期間が1日だけであれば、通過率は下がる可能性が高くなります。
この5つの質問のうち、「Yes」が多ければ多いほどSPI通過率を高めるための準備が必要です。逆に、「No」が多い場合はSPIの通過ハードルが比較的低く、面接や職務経歴書など他の要素で勝負できる可能性もあります。
このチャートを通じて、自分の現在地を把握し、どの部分に力を入れるべきかを考えるきっかけにしてみてください。次章では、SPIの通過率を上げるための具体的な勉強法について紹介していきます。
SPI通過率を上げる勉強法とは
SPIは対策次第で通過率を大きく上げることができます。ここでは実際に効果的な勉強法をステップごとに紹介します。
まずは無料模試やアプリで腕試し
SPI対策を始める際に、最初から分厚い問題集に取りかかるのはハードルが高く、効率もよくありません。まずは、自分の実力を把握することからスタートしましょう。そのために最適なのが、無料で使える模試やアプリです。
特におすすめなのが、らくらく就活のSPI対策アプリです。このアプリでは、実際のSPI試験に近い形式で問題演習ができ、言語・非言語・性格検査の3分野に対応しています。通勤時間やスキマ時間に手軽に使えるうえ、正答率の記録や弱点の把握にも役立つため、効率よく学習を進めることができます。
アプリの魅力は、初心者でも始めやすいシンプルな操作性と、必要な範囲だけを短時間で学べるコンパクトな構成です。「SPIが不安だけど、何から始めたらいいかわからない」という方には、まずこのアプリを使って、自分の得意・不得意を把握することをおすすめします。
また、アプリで解いた問題の中から「解き直しリスト」を作成しておくと、復習の際にも便利です。いきなり完璧を目指す必要はありません。まずは気軽に取り組み、少しずつ実力を高めていきましょう。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
問題集を1冊仕上げる+復習を重視
SPIのスコアを安定して伸ばすには、「良質な問題集を1冊選び、徹底的にやり切る」ことが何より重要です。あれこれ手を出して中途半端に終わるよりも、信頼できる1冊に絞って反復練習を重ねる方が、得点アップへの近道となります。
問題集を選ぶ際には、「非言語分野に強い」「図表問題が多め」「解説が丁寧」など、自分の苦手分野や対策したいポイントに合ったものを選ぶことが大切です。特に、数年前の古い問題集では出題傾向にズレがある場合があるため、最新の形式に対応している2024年度版・2025年度版などの最新版を使うようにしましょう。
また、1周解いて終わりにするのではなく、間違えた問題や時間がかかった問題を復習することがカギになります。正答率だけを気にするのではなく、「なぜ間違えたのか」「別の解き方はあるか」などを深掘りすることで、同じミスを繰り返さない力が身についていきます。
特に非言語分野は、公式やパターンを身につけることで正答率が飛躍的に伸びる分野です。問題集で学んだ内容を、自分なりの「解法メモ」や「苦手分野ノート」にまとめると、復習効率も上がりやすくなります。
頻出分野の絞り込みと短時間の反復練習
SPIの範囲は広いため、全体を網羅的に対策しようとすると時間が足りなくなりがちです。そこで大切になるのが、「頻出分野に絞って対策を集中させる」戦略です。
非言語分野では、特に出題率が高いのが「表の読み取り」「集合」「割合」「損益算」「順列・組合せ」「推論」などです。言語分野では、「空欄補充」「二語の関係」「語句の用法」「文の並び替え」などが高頻度で出題されます。
これらの頻出分野は、解き方のパターンを覚えることで効率的に得点を伸ばしやすいのが特徴です。対策にあたっては、長時間机に向かうよりも、1回10~15分程度の短時間学習を1日2~3回に分けて繰り返す「反復練習」が効果的です。
また、苦手な問題はあえて毎日同じものを解いてみるのも一つの手です。時間を置いて繰り返すことで、理解が定着し、実戦でも迷わず解答できるようになります。
SPIは「頭の良さ」を試す試験ではなく、「慣れているかどうか」が結果を左右します。繰り返し練習することが、最終的に通過率アップにつながる最大のポイントだといえるでしょう。
SPIのスコアと通過率の関係
SPIは単なる点数だけでは評価されません。ここでは、企業ごとに異なるスコア基準や、見落とされがちな評価ポイントを詳しく解説します。
企業によって求めるスコアが異なる理由
SPIは全国共通の試験ですが、実は「合格ライン」が企業によって異なります。同じようなスコアを取っても、ある企業では合格、別の企業では不合格ということがあり得るのです。この背景には、それぞれの企業がSPIに対して持つ「位置づけ」や「選考目的」の違いが関係しています。
たとえば、大手企業や知名度の高い会社では、応募者数が多いため、選考の初期段階でSPIを足切りとして利用することが一般的です。そのため、7割以上のスコアが求められることが多く、受験者の間でも「SPIの点数で落とされた」という声がよく聞かれます。中には、8割を切ると面接に進めないという高い基準を設けている企業も存在します。
一方で、中堅企業やベンチャー企業では、SPIをあくまで「参考情報」として見ているケースが多く、選考の中心はあくまで職務経歴書や面接の内容です。こうした企業では、6割前後でも問題なく通過できることがあり、SPIよりも人物重視の採用を行っているといえます。
また、職種によってもスコアの重要度は変わります。事務職や総合職では一定の処理能力や正確性が求められるため、SPIのスコアを重視する傾向が強くなりますが、営業職や専門職では人物評価や経験重視で、SPIがそれほど影響しない場合もあります。
つまり、SPIのスコアは「絶対評価」ではなく、「企業ごとの期待値」に応じた「相対評価」として見られているのです。自分が受ける企業がどのような基準でSPIを評価しているかを知ることが、戦略的な転職活動には不可欠です。
スコア以外に見られている点とは?
SPIでは能力検査の点数が注目されがちですが、実はそれだけでは選考は判断されません。多くの企業が重視しているのが、「性格検査(適性検査)」の結果です。
性格検査は、論理的思考力や知識量を測る能力検査とは異なり、「価値観」「行動傾向」「職場での協調性」「ストレス耐性」など、人物の内面に関わる要素を可視化するための検査です。つまり、その人がどのような環境で力を発揮するか、企業文化に適応できるか、といった点を測る材料になります。
この性格検査で、企業の理想像と大きくかけ離れた結果が出た場合、たとえ能力検査で高得点を取っていても、選考を通過できないことがあります。たとえば、チームワークを重視する企業で「単独行動型」の傾向が強く出ると、「この人はうちには合わないかもしれない」と判断されるリスクがあるのです。
また、性格検査は「一貫性」も重要です。前後の回答で矛盾があると、「信頼性に欠ける」とされ、スコア全体が無効になることすらあります。ですので、「どう答えたら通過できるか」と答えを操作しようとするよりも、自分自身の考えや性格に正直に、ブレずに答えることが大切です。
加えて、SPIの結果は「全体的なバランス」も見られています。たとえば、言語が高得点でも非言語が極端に低かったり、処理スピードと正答率に大きな差があったりすると、「実務でのバランス感に不安がある」と判断されることがあります。スコアが平均的でも、全体としての一貫性やバランスが良ければ、好印象を与えることも十分にあり得ます。
このように、SPIの通過率は単純な点数だけでなく、「性格検査」「回答の一貫性」「分野間のバランス」など、総合的に判断されているということを理解しておきましょう。
スコア別SPI対策マップ
自分のスコアに応じて、どのような対策を取るべきかが変わります。スコア帯ごとの具体的な学習アプローチを紹介します。
スコアごとのおすすめ対策内容
SPI対策では、現状のスコアに応じて取り組み方を変えることが大切です。誰もがいきなり高得点を目指すのではなく、まずは自分が今どの段階にいるかを把握し、必要な対策に絞って実行していく方が効果的です。ここでは、スコア帯ごとの最適な対策方法を紹介します。
~5割:基礎固めから。非言語中心に取り組む
SPIのスコアが5割以下の場合、まず必要なのは「基礎力の定着」です。この段階では、問題文の読み取りや基本的な計算処理に時間がかかっていることが多く、特に非言語分野でつまずいているケースが目立ちます。
対策の第一歩は、SPIの問題形式に慣れることです。初見の問題に慌てないように、繰り返し問題演習を行って基本パターンを体にしみこませましょう。算数の基礎力に不安がある方は、SPI以前の四則演算や割合、分数、小数の計算など、土台となる計算練習も並行して行うと効果的です。
また、解答に時間がかかってしまうこともあるので、まずは正確に解くことを重視し、時間はあまり気にせず丁寧に取り組むようにしましょう。問題を解くたびに「なぜ間違えたか」を振り返り、解説を読み込んで理解を深めていくことが大切です。
~7割:弱点を克服+演習量を増やす
スコアが5割を超えたあたりからは、弱点克服と演習量の拡大が主なテーマになります。この段階では、多くの問題を一度は解いたことがあり、形式にはある程度慣れているものの、得意・不得意に偏りが出やすい状態です。
ここで重要になるのが、「自分のミス傾向」を把握することです。たとえば、損益算で何度も間違えている、グラフの読み取りで時間がかかる、といった具体的な傾向を把握し、それに絞って集中的に練習を行います。
問題集を解く際は、1周目で終わらずに、2周目・3周目と繰り返していくことが重要です。1度正解した問題でも「偶然の正解」かもしれないので、再度解いて理解を確認することを習慣にしましょう。
また、制限時間を意識して練習を重ねることで、時間内に多くの問題を処理する力も徐々に養われていきます。アプリや模試などを活用して、「時間×正確性」を意識した対策を進めましょう。
~8割以上:応用問題・制限時間の短縮に注力
スコアが7割を超えてくると、すでに基本的な力は十分に身についていると考えられます。ここからさらに上を目指すためには、「応用力」と「スピード」がポイントになってきます。
まずは、正答率が高い問題に時間をかけすぎていないかを見直しましょう。SPIでは、全問正解を狙うよりも、「時間内にできる限り多くの問題を正確に解く」ことが求められます。つまり、「見直すよりも次の問題に進む」という判断力も必要です。
また、応用問題や複数の情報を統合して解く問題など、1問に時間がかかるタイプの問題への慣れも重要になります。これらの問題では、情報の整理力や読み替えのスキルが求められるため、解法を「型」として覚えるだけでなく、「なぜそのように考えるか」という視点から理解を深めることが大切です。
さらに、時間感覚を鍛えるためには、「1問○秒以内に解く」といったルールを決めて、タイマーを使いながら演習するのがおすすめです。試験本番で焦らないためにも、普段から時間を意識したトレーニングを行っておくと安心です。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPIで落ちる人の特徴
「SPIで落ちる人」には共通点があります。ここでは、実際によくある失敗パターンとその対策を整理して紹介します。
対策不足/古い問題集しか使っていない
SPIで不合格になる人の多くに共通しているのが、そもそも「対策が不十分だった」というケースです。SPIは何となく「高校の復習みたいなもの」と考えられがちですが、実際には出題傾向や形式に独特の特徴があり、慣れないまま臨むとあっという間に時間切れになります。
また、過去に使っていた古い問題集を引っ張り出して対策をする人もいますが、これは非常に危険です。SPIは年々アップデートされており、古い問題集では出題傾向がズレていることが多く、特に計算問題や推論の形式が異なる場合もあります。その結果、準備していたつもりでも実際の試験で「見たことがない形式に戸惑ってしまった」という事態になりがちです。
つまり、対策をした「つもり」になっているだけで、実践力が伴っていないというのが、SPIで落ちる人に多く見られる共通点です。最新の問題集やアプリを活用し、出題傾向に合った練習を積むことが重要です。
時間配分を意識していない
SPIでは「正解率」だけでなく「時間管理能力」も合否に大きく影響します。限られた時間の中でどれだけ多くの問題を解けるかが重要であり、ゆっくり丁寧に解いていては時間が足りなくなってしまいます。
実際に、SPIで落ちた人の中には「解けた問題は多かったのに、最後までたどり着けなかった」「最初の数問で時間を使いすぎて、後半が全く手つかずになってしまった」という声が多く見られます。
時間配分のミスは、試験慣れしていない人にとって非常にありがちな落とし穴です。特に非言語分野では、1問あたりにかけられる時間が非常に短いため、「解く順番」「飛ばす判断力」など、戦略的に進める力も求められます。
そのため、普段の演習から「タイマーを使って練習する」「1問にかける時間を意識する」「わからない問題は一度スキップして、後で戻る癖をつける」といったトレーニングが必要です。
性格検査を適当に答えてしまう
SPIの中で見落とされがちなのが「性格検査」です。多くの受験者が「性格検査は合否に関係ない」と考えて、適当に回答してしまったり、嘘の自分を演じようとして矛盾した回答をしてしまったりする傾向があります。
しかし実際には、性格検査の結果が選考に大きく影響するケースもあります。たとえば、協調性や誠実性が極端に低く出たり、短期離職の傾向が見える回答をしていたりすると、「チームとの相性が合わなそう」「すぐ辞めてしまうかもしれない」と判断されることがあります。
また、性格検査は同じような内容の質問が形式を変えて何度も出されるため、答えに一貫性がないと「信頼できない結果」として、企業側が参考にしないどころかマイナス評価をつける可能性もあります。
性格検査で最も重要なのは「正直に答えること」です。「理想的な人物像になろう」と背伸びするのではなく、自分らしさをきちんと伝えることが、結果として評価につながります。
SPIで落ちる人の多くは、「準備不足」「時間感覚の欠如」「性格検査の軽視」といった、基本的な対策ポイントを見落としてしまっています。これらの失敗例を知っておくことで、自分自身が同じ轍を踏まないように、より効果的な準備ができるようになるでしょう。
SPIと通過率に関する疑問
SPIの通過率や活用方法について、よくある質問を取り上げ、選考中に抱きがちな疑問にわかりやすく答えます。
Q. SPIが難しかったら落ちる?
必ずしも「難しかった=落ちる」ではありません。SPIは受験者全体の中での相対評価の要素もあるため、全体的に難易度が高い年や問題セットだった場合は、平均点も下がる傾向があります。そのため、自分が「難しい」と感じたからといって、即不合格と判断されるわけではないのです。
また、企業によってはSPIのスコアを「参考程度」として扱っており、面接や職務経歴書の評価を優先している場合もあります。ただし、足切り目的で使っている企業ではスコアが低すぎると次に進めない可能性もあるため、「難しかったから対策しても無駄」とは考えず、事前準備をしっかりしておくことが大切です。
Q. 面接が良くてもSPIが悪ければ不合格?
面接の評価が非常に高かったとしても、SPIの結果が極端に悪い場合は、最終的に不合格となることもあります。特にSPIが一次面接より前に行われている場合、SPIの点数で足切りされるため、面接まで進めないこともあります。
一方で、SPIが面接の後に行われる企業では、SPIの結果が多少悪くても面接の印象が良ければ合格となる可能性もあります。このように、選考のどの段階でSPIが実施されるかによって、SPIの影響度合いは大きく変わってくるのです。
ですので、面接とSPIは両方しっかりと準備するのが理想です。特にSPIの苦手意識がある方は、面接に自信があってもSPIで落ちないような最低ラインの得点は確保できるようにしておきましょう。
Q. 結果は他社と共有される?
SPIの結果は、原則として受験した企業とSPI提供元(リクルートなど)との間だけで扱われ、他社と共有されることはありません。たとえば、A社でSPIを受けた結果がB社に知られるといったことは基本的にはありません。
ただし、「テストセンター方式」の場合には、同一のSPIスコアを複数企業に使い回す仕組みになっているため、同じスコアが他社でも共有されるという意味では情報が再利用されるケースもあります。とはいえ、これはあくまで「自分がそのスコアを他社にも使った場合」の話です。
個人情報や選考結果の共有は法律上も厳しく制限されているため、「一度受けて悪かったから他社にバレたらどうしよう」といった心配は不要です。
SPI通過率に関する転職者体験談
実際にSPIを受けた転職者の声を紹介します。成功例や失敗例を通して、リアルな気づきや学びを共有します。
実際に受けた人のリアルな声
SPIに関する不安を抱えるのはあなただけではありません。ここでは、実際に転職活動でSPIを受けた方々のリアルな体験談を紹介します。成功談・失敗談の両方を知ることで、自分の対策に活かすことができます。
「SPI対策せずに一次面接前で落ちた…」
以前勤めていた業界の経験をアピールすれば通過できると思い、SPI対策は一切せずに応募。しかし、応募先の企業はSPIが一次選考前に行われる方式で、結果的に面接に進めず落ちてしまいました。悔やんでも後の祭りで、それ以降はしっかりと問題集で対策するようにしました。
「アプリで1週間対策して通過できた!」
もともと数学が苦手でSPIは不安だったのですが、通勤時間にSPI対策アプリを毎日使って1週間ほど練習した結果、7割超のスコアが取れました。応募した企業の面接でも「SPI良かったですね」と言われ、評価につながったと実感しています。
「性格検査で落ちたかも…と感じた企業も」
能力検査は得意だったのですが、性格検査は少し“理想的すぎる答え”を選んでしまいました。受けた後に矛盾が多かったかも、と不安になったところ、最終的に不合格。別の企業では正直に答えて通過したので、性格検査もあなどれないと感じました。
これらの体験談からもわかる通り、SPIは「勉強すれば通過できる試験」です。準備を怠れば足元をすくわれることもありますが、地道な対策が結果につながると、多くの転職者が語っています。
まとめ
転職におけるSPIは、企業や選考段階によって通過率や重視されるポイントが大きく異なります。一律の基準で語ることはできませんが、おおよその通過率の目安としては30〜50%程度。スコア別に見ると、7割以上が安心ラインであり、8割を超えると上位企業でも通過の可能性が高くなります。
SPIが一次面接前にある場合は足切り目的であることが多いため、特に対策が重要です。一方、面接後や最終段階で実施される場合は、性格検査としての意味合いが強くなります。自身の対策状況や企業の選考フローに合わせて、SPIの重要度を正しく見極めましょう。
この記事では、SPI通過率診断チャートやスコア別対策マップ、落ちやすい人の特徴、体験談なども紹介しました。これらの情報を活用し、自分に必要な対策を見極めてください。
SPIは、慣れと準備で乗り越えられる試験です。自信を持って取り組み、選考を一歩一歩確実に進めていきましょう。