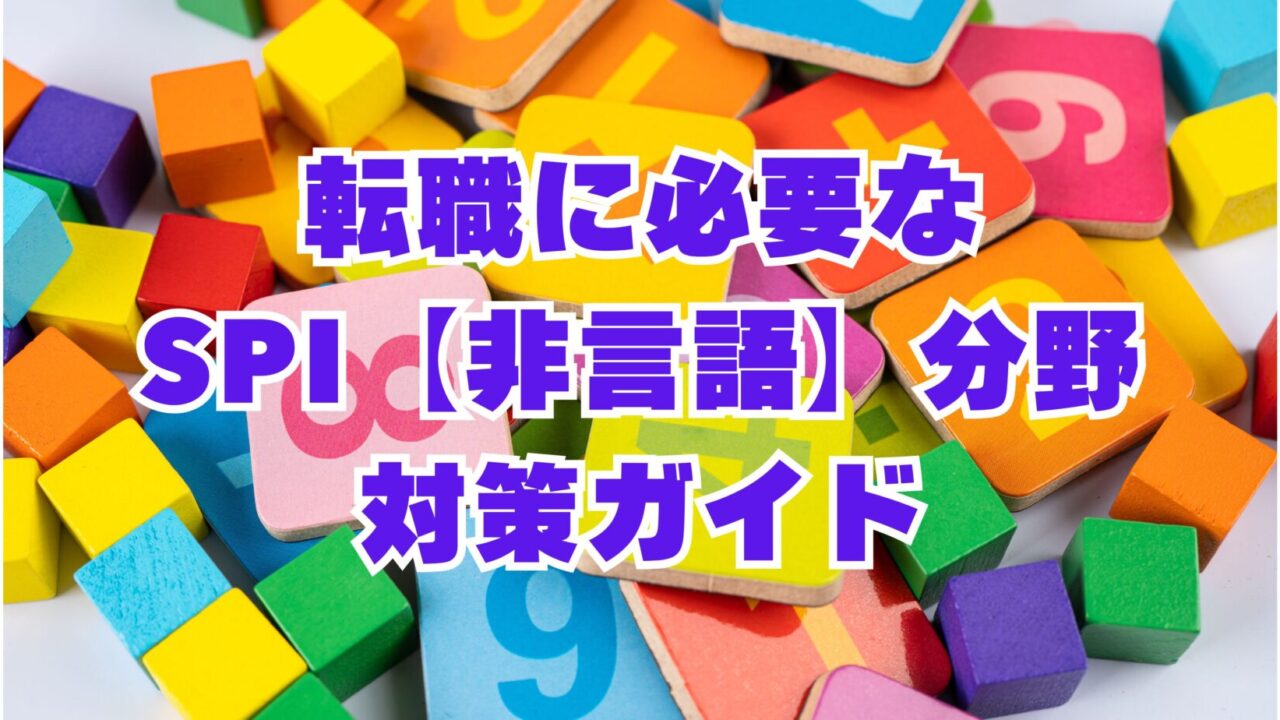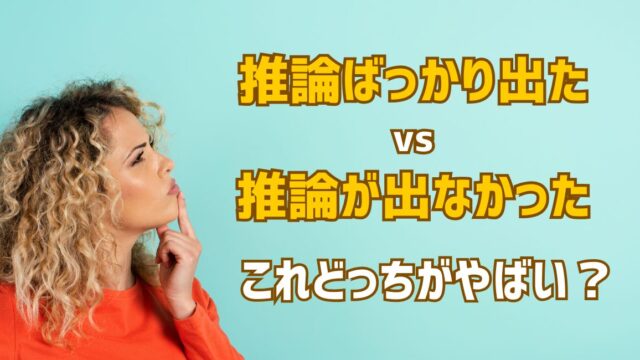【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「転職SPIの非言語が不安すぎる…」
「文系で数学が苦手だから避けたい」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。特に転職活動では、実務経験や人柄に加え、SPIのようなテストでも評価される場面があり、「非言語=数学」と聞いただけでハードルの高さを感じる人は少なくありません。
ですが、安心してください。SPI非言語分野は、やみくもに勉強しても効果が薄く、実は“出るところ”がある程度決まっているテストでもあります。本記事では、そんなSPI非言語を効率的に対策するために、以下の内容を網羅的に解説していきます。
- なぜSPIで非言語分野が出題されるのか?
- 自分のレベルを5つの質問で診断できるチャート
- 頻出単元をまとめたヒートマップ
- 問題パターン別の攻略法
- 文系でも突破できた対策体験談
- 模試・アプリ・問題集の使い方
この記事を読み終える頃には、「何から手をつければいいかわからない」という不安が、「こう進めれば大丈夫」という自信に変わっているはずです。まずはSPI非言語の全体像をしっかり掴んでいきましょう。
目次
SPI非言語とは?転職時に出題される理由
SPI非言語分野とは、簡単に言えば「計算力」「論理的思考力」「情報処理能力」を測るためのテストです。グラフや数式を使って問題が出題され、時間内に正確に処理するスキルが求められます。出題されるのは、中学~高校初期の数学レベルが中心ですが、意外と忘れてしまっている人も多い内容です。
では、なぜ企業はこのようなテストを中途採用でも課すのでしょうか?以下でその背景を詳しく見ていきます。
企業が非言語分野を重視する背景
企業がSPI非言語を導入する理由の一つは、「業務上で求められる論理的思考力」や「正確な情報処理能力」を事前に測るためです。たとえば、事務職や営業職であっても、数値データの理解・資料の読み取り・条件に応じた判断など、日常的に“考える力”が問われるシーンが多くあります。
履歴書や職務経歴書だけではわかりづらい「地頭力」や「処理スピード」を数値化し、公平に比較する手段として、非言語テストが活用されているのです。
新卒と違う?中途採用ならではの目的
新卒採用のSPIでは、学力やポテンシャルを見ることが主な目的ですが、中途採用の場合は少し目的が異なります。企業は「業務に必要なスキルを持っているか」「即戦力として活躍できるか」という観点でSPIを活用しています。
たとえば、同じ非言語でも新卒向けは幅広い基礎問題が出題されるのに対し、転職者向けSPI(通称:SPI-G)は実践的な問題や、時間制限の厳しい問題が多くなる傾向があります。そのため、対策も「効率的に頻出単元だけを押さえる」戦略が求められるのです。
SPI非言語対策レベル診断チャート
SPI非言語の対策を始める前に、まず大切なのは「自分のレベルを正しく把握すること」です。やみくもに勉強を始めても、必要以上に時間を使ってしまったり、実力に合わない難易度の問題に挑んで心が折れてしまったりすることがあります。
特に転職活動中の社会人にとって、限られた時間の中で効率的にSPI対策を進めるには、“今の実力に合ったレベルの学習”を選ぶことが最重要です。
そこで役立つのが、この「SPI非言語対策レベル診断チャート」です。たった5つの質問に答えるだけで、あなたがどの段階にいるかが簡単に把握できます。ここでの診断をもとに、今後の対策の方向性を考えていきましょう。
5つの質問であなたの現在地がわかる
以下の5つの質問に対して、「YES」か「NO」で答えてみてください。どれくらいの数「YES」が出るかによって、おおよそのレベル感が見えてきます。
質問1:数学の基礎はいつ以来?
「学生時代以来、まったく計算問題に触れていない」「一次方程式や割合の計算も不安がある」という方は、基礎からの見直しが必要です。反対に、仕事で日常的に数字を扱っていたり、簿記やFPなどの資格勉強をしていた経験があれば、思い出すだけで対応できる可能性が高いです。
YESなら → 基礎力は比較的キープできている
NOなら → 計算トレーニングから再スタートを
質問2:割合や確率の計算に自信はある?
割引率、利益率、増加率、確率──SPIで頻出するこのような問題は、日常ではあまり使う機会がないため、感覚を取り戻すのに時間がかかる分野です。特に、文章問題の中で複数の割合が絡んでくると、混乱しやすくなります。
YESなら → 商業計算や確率の基礎は押さえ済み
NOなら → 公式の意味や使い方から復習すべき
質問3:図表の読み取りは得意?
グラフや表を正確に読み取り、必要なデータを抽出するスキルは、SPI非言語の中でも非常に重要な能力です。見慣れない形式の表が出てきても、焦らず「どこを見て、どう処理するか」を判断できるかがポイントになります。
YESなら → データ読解力があり、対応力も期待できる
NOなら → 表の構造や読み取りの順序を練習する必要あり
質問4:制限時間内で解ける自信は?
SPIでは、1問にかけられる時間が非常に短いため、焦らずスピーディーに処理できるかどうかがカギになります。普段の勉強でも、時間を測りながら演習している方は、本番でも時間感覚が自然と身につきます。
YESなら → 解法のパターン習得が進んでいる状態
NOなら → スピード感を意識した模試演習が必要
質問5:参考書やアプリで演習済み?
一度でもSPI非言語の問題を実際に解いてみたことがある方は、出題形式や難易度に対する“肌感”ができているはずです。問題集やアプリに触れた経験がない方は、まず“慣れる”ところから始める必要があります。
YESなら → 基本対策は済んでおり実践強化フェーズへ
NOなら → 問題演習を通して形式に慣れることが先決
診断結果の目安
YESが0~1個:初心者レベル
SPI非言語が初めて、もしくはかなりブランクがある状態です。中学レベルの計算力や公式の使い方を、やさしい問題から丁寧に思い出すことが第一歩です。焦らず基礎固めに集中しましょう。
YESが2~3個:中級者レベル
一部の単元や問題形式には慣れてきた段階。今後は「苦手ジャンルを絞って潰す」→「スピードと正確さを高める」という2段階の対策がおすすめです。模試の活用で実戦力を強化しましょう。
YESが4~5個:上級者レベル
基本的な知識・経験がある状態で、さらに高得点を目指すためには「苦手単元を減らし、得意単元で確実に得点する戦略」が重要です。応用問題やミス対策にも取り組み、安定した得点力をつけましょう。
このチャートで現在地を把握することで、必要以上に焦ったり、不必要な教材に手を出して遠回りしたりするリスクを減らせます。SPI非言語は、ただ頑張るだけでなく「自分に合った段階的なアプローチ」が結果を左右します。
まずは今日、自分の“今の実力”を知ることから始めましょう。
SPI非言語の出題形式と特徴
SPI非言語では、計算力や論理的思考を測るためにさまざまな形式の問題が出題されます。転職時に使われるSPI(とくにSPI-G)では、スピードと正確さの両方が求められるのが特徴です。問題パターンを知っておくことで、「どんな問題が来てもパニックにならない」という安心感にもつながります。
ここでは、非言語でよく出る問題パターンと、転職者向けSPI-Gならではの注意点を解説していきます。
よく出る問題パターン
SPI非言語の問題は、ある程度パターンが決まっています。具体的には以下のような形式が頻出です。
まず代表的なのが「損益算」や「割合」の問題です。たとえば「商品を2割引で販売した場合の利益率は?」といった計算問題は頻出です。内容自体は中学校レベルですが、出題の仕方がややトリッキーなこともあり、文章の条件を読み間違えると正答が出せません。
次に「速度算」や「時間・距離・速さ」の計算もよく見られます。電車や車の問題が定番で、「ある距離を往復するときの平均速度」など、複雑な計算が必要になるケースもあります。
「場合の数」や「組合せ・順列」の問題もよく出題されます。特に選択肢の数え漏れや重複カウントを防ぐ論理性が問われるため、慎重な処理が求められます。
「図表問題」では、与えられたグラフや表から数値を読み取って答えるタイプが中心です。データ量が多いので、どこに注目すべきかを見極める“目の使い方”が問われます。
そのほかにも、「集合(ベン図)」や「推論問題」など、数的思考と論理力をフルに使うジャンルが出題されることが多く、これらは難易度も高めです。
転職向けSPI-Gでの注意点
中途採用で使われるSPI-G(General)は、新卒向けSPIよりも問題の質と時間制限がシビアです。とくに注意すべき点は以下の通りです。
まず、「解答スピード」が重視される点です。SPI-Gでは問題数に対して時間がかなりタイトに設定されており、迷っている暇はほとんどありません。問題の選別、時間配分、切り替え力など“解き方の戦略”が必要になります。
次に、問題の文章がやや長く、条件も複雑に設定されている傾向があります。「日本語の読解ができていないと正答にたどりつけない」というケースも多く、算数的な処理以前に、設問の読み取りでつまずくことがあるのです。
また、SPI-Gは出題内容が非公開なため、実際に受検した人の体験談や、企業からの情報提供が対策の命綱になります。市販の問題集や模試、アプリなどを活用して“類似問題”に慣れておくことが非常に重要です。
非言語が得意ではない方ほど、早めに問題の形式に慣れることで、スピードと正確さを両立できるようになります。次のセクションでは、出題傾向を「視覚的に」把握するためのヒートマップを紹介します。
頻出単元の出題ヒートマップ
SPI非言語の対策を効率的に進めるには、「出る単元から優先的に攻略する」ことが非常に重要です。限られた時間の中で、すべての単元を網羅するのは現実的ではありません。そこで活用したいのが、「出題頻度」「難易度」「優先度」を視覚的に整理した“出題ヒートマップ”です。
このマップを見ることで、「どの単元から手を付けるべきか」「難しい単元をどう扱うべきか」の戦略が立てやすくなります。以下に、主要単元ごとの分析結果を紹介します。
| 単元名 | 出題頻度 | 難易度 | 優先度 |
| 損益算 | 高 | 中 | 高 |
| 速度算 | 高 | 高 | 高 |
| 場合の数 | 中 | 高 | 中 |
| 図表読解 | 高 | 中 | 高 |
| 集合・ベン図 | 中 | 中 | 中 |
| 推論 | 高 | 高 | 高 |
解説:
損益算:出題頻度 高/難易度 中/優先度 高
価格、割引率、利益率などの基本的な商業計算が中心。ルールを理解していれば点が取りやすく、短時間で処理できるのが魅力です。文系・理系問わず、最優先でマスターしたい単元です。
速度算:出題頻度 高/難易度 高/優先度 高
「A地点からB地点まで何分かかるか」といった問題は、日常でも使う計算のはずですが、条件が複雑になると急に難しく感じます。特に「往復」や「すれ違い」「追い越し」の問題は時間配分が重要です。
場合の数:出題頻度 中/難易度 高/優先度 中
計算というよりは、パターンを数える論理問題。ミスしやすく、見落としやすいので難易度は高めです。理解できれば確実に点が取れますが、優先度としては中程度です。
図表読解:出題頻度 高/難易度 中/優先度 高
SPI非言語の定番。表やグラフを読み取り、条件に合うデータを抜き出して答える形式。数値処理だけでなく、どこを見て何を読み取るかの“目の付けどころ”が得点のカギです。
集合・ベン図:出題頻度 中/難易度 中/優先度 中
複数の条件が重なる問題に対し、ベン図で整理して答えるタイプ。感覚的にわかりにくい人もいますが、ルールを覚えれば処理は簡単です。頻度はそこそこあるので、時間に余裕があれば取り組みましょう。
推論:出題頻度 高/難易度 高/優先度 高
最も“考える力”が問われる難関分野。条件の真偽を検証したり、矛盾を見つけたりする問題が多く、処理スピードだけでなく論理の正確さも問われます。正答率が低くても評価されやすい分野なので、取り組む価値は十分あります。
このように、SPI非言語には「効率よく得点できる単元」と「戦略的に捨てるべき単元」が明確に存在します。すべての問題を解こうとせず、ヒートマップをもとに“勝てる単元”に絞って取り組むことが、通過率を上げる近道です。
SPI非言語が難しいと感じる理由
SPI非言語に対して苦手意識を持つ人は少なくありません。特に文系出身の方や、学生時代に数学を避けてきたという方にとっては、「SPI非言語=数字の羅列」と感じてしまい、心理的ハードルが高くなりがちです。
ここでは、なぜ多くの転職者が非言語を「難しい」と感じるのか、その理由を3つの観点から掘り下げていきます。
計算力が問われる形式が多い
SPI非言語の大半は、数字を使った計算問題です。単純な足し算・引き算なら問題ありませんが、現実には「割合」「利益」「速さ」「平均」など、複数の条件を組み合わせた問題が多く、解くためには式の立て方や変換の知識が必要になります。
さらに、計算そのものも一筋縄ではいきません。たとえば、ある商品の定価から割引され、その後さらに税率が加わった場合の実際の支払額を求める…といったように、複数ステップの処理を一度に行う必要があるのです。
普段の生活や業務でこうした複雑な計算をすることが少ない人にとっては、スムーズに式を立てるのも一苦労。問題を読む→条件を理解する→式を立てる→計算する、という一連の流れに慣れていないと、プレッシャーも相まって非常に負担に感じてしまうのです。
時間制限のプレッシャーが大きい
SPIは「スピード」が評価の大きな要素です。特にSPI-G(転職者向け)の場合、1問あたりにかけられる時間はわずか30秒〜1分程度。しかも計算問題が多いため、じっくり考え込む時間の余裕はありません。
そのため、「あと少しで解けそう」と思っても、1問にこだわってしまうと他の問題を解く時間がなくなってしまうというリスクもあります。
この“時間に追われる感覚”が、非言語問題の難易度をさらに高めているのです。焦りが出るとケアレスミスも増え、実力が正しく発揮できなくなってしまうケースも多く見られます。
中学〜高校範囲の知識が問われる
SPI非言語で扱われる内容は、「中学〜高校の初級程度」とされていますが、受験から数年〜十数年が経過している方にとっては、忘れてしまっている知識も多いでしょう。
たとえば、損益算に必要な「仕入れ・原価・利益率」の関係や、速度算で必要な「距離=速さ×時間」の式など、昔は覚えていたはずの公式も、いざ出されるとすぐには思い出せないことが多いのです。
しかもSPIでは、そうした知識を単に覚えているだけでは不十分で、「文章から条件を読み取り、適切な式を組み立てる力」まで求められます。つまり、公式の丸暗記ではなく、それをどう使うかまで含めての実力が問われるのです。
このように、SPI非言語が「難しい」と感じる背景には、単なる数学の苦手意識だけでなく、計算スピード・論理思考・知識の活用といった、複合的なスキルが求められることが影響しています。
次のセクションでは、そんな難しさを乗り越えるための【パターン別攻略マトリクス】を紹介します。
非言語パターン別攻略マトリクス
SPI非言語は、出題される問題にある程度の「型」があります。逆に言えば、頻出パターンをしっかり押さえておくことで、未知の問題にも落ち着いて対応できるようになります。ここでは、代表的な非言語の問題タイプについて、それぞれの“コツ”と“使うべき解法”を整理した攻略マトリクスを詳しく解説します。
まずは全体像を表で確認しましょう。
| 問題タイプ | コツ | 使うべき解法パターン |
| 割合問題 | 100基準で置き換える | 比の変換、差集めのテクニック |
| 損益算 | 利益の定義を明確にする | 公式丸暗記よりも因果で理解 |
| 図表問題 | グラフ全体→単位→該当箇所 | 見る順番を固定 |
| 速度算 | 距離=速さ×時間の逆算が基本 | 問題ごとの設定図で整理 |
| 集合・ベン図 | 条件を図に落とし込む | 和集合・共通集合の考え方 |
| 場合の数 | すべて書き出すよりパターン化 | 樹形図 or 式化で対応 |
| 推論 | 否定文や例外に注目する | 可能性の排除法を使う |
ここからは各問題タイプについて、より具体的に解説していきます。
割合問題|100基準で置き換える
よくある出題例:
「ある商品の価格は定価の20%引きで販売されました。利益率が25%のとき、原価は?」など
攻略ポイント:
割合の問題では、実際の数値が与えられていないことも多いため、「100を基準に計算する」方法が非常に有効です。たとえば、定価を100とすれば、20%引きは80、25%の利益なら原価は?といったように、数値を自分で設定することで頭の中が整理されやすくなります。
落とし穴:
割引と利益を混同したり、「原価からの利益率」と「売価からの値引き率」の違いを見落とすと間違いやすいです。文章中の“基準”がどこかを明確にするクセをつけましょう。
損益算|利益の定義を明確にする
よくある出題例:
「原価の20%の利益を見込んで定価を設定し、さらに10%割引して販売した場合の実際の利益率を求めよ」など
攻略ポイント:
損益算では、「原価・定価・売価・利益」の関係性をしっかり理解しておくことが大切です。公式を丸暗記するよりも、「なぜこの計算になるのか」を因果で理解しておくと、応用問題でも混乱しません。
使えるテクニック:
“定価=原価×(1+利益率)”“売価=定価×(1-割引率)”といった式を、数字を当てはめながら練習すると定着しやすくなります。
図表問題|グラフ全体→単位→該当箇所の順で見る
よくある出題例:
「以下の売上推移グラフから、2023年上期の売上合計が前年より増えた店舗はどれか」など
攻略ポイント:
最も重要なのは「どこを見るかの順番を固定する」ことです。はじめにグラフや表全体の構造を把握し、次に単位(千円か万円か)を確認し、最後に設問で求められている箇所に目を向けるという順番を徹底しましょう。
注意点:
急いで答えようとして「単位を見落とした」「横軸と縦軸を逆に読んだ」というミスが多発する分野なので、慎重さとスピードのバランスが重要です。
速度算|距離=速さ×時間の逆算が基本
よくある出題例:
「ある人が往路は時速60km、復路は時速40kmで移動した場合、平均速度はいくらか」など
攻略ポイント:
「速さ=距離÷時間」「時間=距離÷速さ」「平均速度=総距離÷総時間」など、基本公式の使い分けができれば怖くありません。また、「往復」や「すれ違い」「追い越し」などパターン別に図を描く習慣をつけると、情報整理がぐっと楽になります。
よくある勘違い:
単純平均で計算してしまう(例:時速60と40の平均を50とする)など、数学的根拠のない計算に注意。総距離と総時間での計算が正解です。
集合・ベン図|条件を図に落とし込む
よくある出題例:
「英語が話せる人が20人、フランス語が話せる人が15人、その両方を話せる人が5人のとき…」など
攻略ポイント:
ベン図を描くことで複数の条件を視覚的に整理できるようになります。問題を読んだら、すぐに2つまたは3つの円を描き、重なりを埋めていくイメージを持ちましょう。
補足:
“いずれか一方を話せる人数”“どちらも話せない人数”など、ひねった聞き方がされることも多いため、図にきちんと数字を埋めて全体像を押さえることがカギになります。
場合の数|書き出すよりパターン化
よくある出題例:
「3人の中から2人を選んで順番に並べる方法は何通り?」など
攻略ポイント:
数え上げが必要な問題は、一見難しそうに見えても「選ぶ→並べる」「並べる→区別する」といったパターンに分解すれば対応可能です。すべてを手作業で書き出すのではなく、樹形図や公式(順列・組合せ)を使えるようにするのがコツです。
注意点:
「順番を区別するかしないか」「同じものを含むか」など、条件の読み違いに注意。問題文を丁寧に読み取る力が試されます。
推論|否定文や例外に注目する
よくある出題例:
「AはBより背が高く、CはBより低い。ではCとAの関係は?」といった条件整理型の問題
攻略ポイント:
推論問題は、条件が多くなるほど混乱しやすくなります。そのため、“可能性を消去する”“明確にわかることだけを結論に使う”という姿勢が大切です。また、「必ず」「ある場合は」「〜ではない」といった否定や限定条件が含まれている場合は、真っ先に注意を向けましょう。
戦略:
すべてを記憶だけで処理しようとせず、簡単な図やメモで整理すること。自分なりの表記法を持つと、時間短縮にもつながります。
まとめ
非言語分野の問題は、知識や公式だけでは太刀打ちできない場面が多くあります。大切なのは、“パターンごとの考え方”を身につけておくことです。
この攻略マトリクスを使えば、「この問題はどう処理するべきか?」が感覚でわかるようになります。反復して練習すれば、解法の引き出しが自然と増え、難しいと感じていた問題にも落ち着いて対処できるようになるでしょう。
転職成功者の非言語対策体験談
SPI非言語に苦手意識を持っていたとしても、正しい対策法を実践すれば、転職選考を突破することは十分可能です。ここでは、実際にSPI非言語を乗り越えて転職を成功させた方々のリアルな体験談を紹介します。
どのエピソードにも共通しているのは、「短時間でも継続して対策したこと」「解ける問題を確実に取る戦略を持っていたこと」。文系・理系を問わず、多くの方が試行錯誤を経て、着実にスコアを伸ばしています。
文系出身でもSPIを突破できた理由
Aさん(28歳・サービス業出身/人事職志望)
「毎日通勤中に1問ずつ解くだけで、3週間後には7割得点できるようになりました。最初はベン図や割合の意味がまったくわからず、参考書を開くのも憂うつでしたが、YouTubeの無料講座とSPIアプリを併用して、解説を“聞きながら”学習するようにしたら、だんだんとパターンがつかめるようになりました。
特に助かったのは、アプリの“解き直し”機能。間違えた問題だけを繰り返し練習することで、自分の弱点がクリアに見えて、時間を無駄にせずに済みました。文系だからといって苦手意識だけで避けていたら、絶対に損だったと思います。」
中卒・高卒で数学に自信ゼロだった私でも突破できた
Bさん(31歳・製造業出身/営業職へ転職)
「高校卒業後、ずっと現場仕事だったので、いわゆる“学力テスト”なんて10年以上ぶり。SPIという言葉を初めて聞いたときは正直、諦めかけていました。
でも、無料で使えるアプリを1日10分から始めて、最初は“わからない問題は調べながら解く”を徹底しました。通勤前と昼休みにスマホでコツコツやっていたら、2週間後には基本問題なら解けるようになってきて、自信が持てるように。
模試形式で時間を計るようになってからは、“解ける問題を見極める感覚”が鍛えられた気がします。本番では難しい問題はスキップして、簡単な問題を確実に取りにいった結果、通過できました。要は戦い方なんだなって思いました。」
数字に強いと思っていた理系出身でも意外とつまずいた
Cさん(26歳・エンジニア職から事務職へ転職)
「大学では情報系を専攻していて、理系だからSPIは余裕だろうと思っていました。が、実際に問題集を解いてみると、計算力よりも“問題文の条件整理”に苦戦することが多かったんです。
特に図表問題や推論問題では、“答えは計算じゃなく読解と判断”という場面が多くて、焦ると凡ミスが続きました。そこでやったのは、“とにかく問題文を丁寧に読む癖”をつけることと、“時間を測って練習する”こと。1問1分以内で判断する練習を重ねることで、自然とスピードと集中力が上がっていきました。
SPIは数学の試験というより、“制限時間内で判断と処理ができるか”のテストなんだと実感しました。」
子育て中の転職活動でも、スキマ時間を活用して合格
Dさん(30歳・主婦/事務職志望)
「子育て中で、勉強する時間を確保するのがとにかく大変でした。でも、どうしても事務職に就きたかったので、毎朝子どもが起きる前の20分、夜の寝かしつけ後の30分を“SPIタイム”に決めて勉強していました。
紙の問題集よりも、すぐに開けるスマホアプリが重宝しました。わからない問題はお気に入りに登録して、時間のある日にまとめて復習。2ヶ月ほど地道に続けていたら、最初は半分も取れなかった模試で8割近く取れるようになり、自信を持って選考に臨めました。
“毎日短くてもいいから続ける”ということが、モチベーションにも繋がったと思います。」
体験談から見える共通点とは?
上記の体験談からも分かるように、SPI非言語の対策で成功する人たちにはいくつかの共通点があります。
- 「完璧主義ではなく、“できることから始める”姿勢」
- 「短時間でも継続する努力」
- 「解ける問題を優先する現実的な戦略」
- 「ミスを“自分のクセ”として分析し、修正する姿勢」
特に転職活動では、本業や家庭と両立しながらの対策が求められるため、限られた時間をどう使うかが重要になります。“毎日1問でも解けばOK”というような柔軟な考え方を持つことで、挫折せずに継続できる可能性が高まります。
SPI非言語は、最初の一歩さえ踏み出せれば、誰でも確実に成長できる分野です。大切なのは、「今の自分にできることから始めてみる」こと。焦らず、地道に、自分に合ったやり方で取り組めば、必ず結果はついてきます。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
転職SPI非言語のおすすめ対策方法
SPI非言語のスコアを上げるには、ただ問題を解くだけでは不十分です。重要なのは、「自分の課題に合った対策を、正しい順番で実行すること」。非言語分野は、出題傾向がある程度決まっているため、学習の優先順位を工夫するだけで、短期間でもスコアを安定させることが可能です。
ここでは、転職者の忙しい生活の中でも無理なく実行できる、おすすめの対策方法を3ステップに分けて解説していきます。
苦手分野の洗い出しと重点対策
まず最初に取り組むべきなのは、「自分が何に弱いのか」を明確にすることです。SPI非言語ではさまざまな問題タイプが出題されますが、すべてを均等に対策するのは非効率。限られた時間で成果を出すには、“捨てる単元”と“集中すべき単元”を分ける判断がカギになります。
たとえば、以下のようなパターンがよくあります。
- 割合や損益算は得意だが、ベン図になると手が止まる
- 計算は早いが、図表読解で条件整理に時間がかかる
- 問題は解けるが、時間内に終わらない
このような状態を放置せず、まずは模擬問題を5〜10問解き、自分のミスの傾向を分析することから始めましょう。間違えた問題に共通する「ジャンル」や「ミスの種類」(計算ミス、読み違い、公式ミスなど)を洗い出し、苦手分野には重点的に時間を割くのが鉄則です。
対策としては、解説の詳しい問題集や解説付きアプリを使い、「なぜその解法になるのか」を言語化して理解することが大切です。わかった“つもり”で進めてしまうと、同じような問題で再び間違えるリスクが高くなります。
時間を意識した模試演習の活用
SPI非言語で最も厄介なのが、時間制限の厳しさです。多くの人が、「わかっているはずの問題を時間内に解けずに落とす」という失敗を経験しています。
この問題に対処するには、模試形式での演習が非常に効果的です。単に「問題を解く」だけでなく、「制限時間内に、どの問題を先に解き、どこで切り上げるか」といった“戦略的解答スキル”を養うための訓練が必要です。
たとえば、30問を20分で解く模試を実施することで、「1問あたり40秒以内で処理する練習」「簡単な問題を最初に拾う判断力」「途中で切り替える勇気」など、本番さながらの実戦感覚を養えます。
模試の結果は、単なる正答率だけでなく、以下の点を振り返ってください。
- 時間切れになった問題の位置
- 解けたはずの問題を飛ばしていないか
- ミスの原因は計算ミスか読解ミスか
こうした分析を繰り返すことで、試験に対する“時間の感覚”が自然と身についていきます。
スマホアプリと紙の問題集の併用
対策の継続には、「続けやすさ」と「実戦形式での練習」の両方が必要です。そのため、スマホアプリと紙の問題集の併用がおすすめです。
スマホアプリの利点:
- スキマ時間に1問だけでも解ける
- 解説付きで理解が進む
- 間違えた問題を記録・復習しやすい
- 模試モードで時間制限のある練習が可能
特に転職活動中は、在職中であれば仕事の合間や通勤時間しか勉強時間が取れないことも多いため、「机に向かわなくてもできる対策手段」としてスマホアプリは非常に便利です。
紙の問題集の利点:
- 試験本番と似た形式で演習できる
- 書き込みやメモを活用して思考の整理ができる
- 問題を一覧で見渡せるため、優先順位が立てやすい
特に“自分で手を動かして計算する習慣”をつけたい場合には、紙の問題集が最適です。苦手単元をまとめて復習したいときにも、書籍ベースの学習は便利です。
これらをうまく使い分けて、たとえば「平日はアプリ、休日は紙の問題集」など、自分なりのルールを作ることで、対策がルーティン化しやすくなります。
まとめ:3つのステップを自分のペースで
- まずは苦手を知る
- 次に実戦形式で慣れる
- 最後にツールを組み合わせて習慣化する
この3つのステップを踏むことで、SPI非言語の対策は“勉強”というよりも“慣れ”の領域に変わっていきます。完璧主義を目指す必要はありません。6~7割の得点を安定して取れる状態を目指すことが、転職選考においては最も効率的なゴールです。
SPI非言語で注意すべきポイント
SPI非言語は、対策次第で得点が安定しやすい一方で、“意外なミス”や“時間の浪費”によって実力を出し切れないケースが多く見られます。試験本番では、ただ問題を解く技術だけでなく、「戦略」と「判断力」も同じくらい重要になります。
このセクションでは、SPI非言語で特に注意すべき2つのポイントを取り上げ、それぞれの落とし穴と対処法を詳しく解説します。
見直し時間を確保するための工夫
SPI非言語では、1問にかけられる時間が非常に短いため、時間の使い方ひとつで結果が大きく変わります。特に、全問を見直す余裕がないのが当たり前という前提で、戦略的に「見直しの時間を確保する動き方」が求められます。
よくある失敗例:
- 序盤の難問に時間をかけすぎて、後半の易しめの問題を飛ばしてしまう
- 簡単な計算ミスに気づかず、そのまま提出してしまう
- 最後までたどり着かず、白紙で終わる問題が出てしまう
これを避けるためには、あらかじめ「解く順番のルール」を決めておくことが効果的です。たとえば以下のような戦略が有効です。
- 1周目は“見た瞬間に解けそうな問題”だけを拾っていく
- 2周目で“少し考えればいけそうな問題”に取り組む
- 残り時間で“時間のかかる問題”や“自信がなかった問題”を見直す
このように「3段階に分けて解く」癖をつけることで、焦らず対応できる余裕が生まれます。特に時間配分を意識しないまま突っ込むと、解ける問題を落とす“もったいないミス”が起こりがちです。
見直しでは、「符号(+-)」や「単位(%、円、kmなど)」のミスを重点的に確認しましょう。簡単なケアレスミスを防ぐだけで、正答率は大きく上がります。
途中で解けなくても切り替える判断力
SPI非言語で合否を分ける大きな要素のひとつが、“切り替えの判断力”です。1問にこだわって考え込みすぎると、全体の時間バランスが崩れてしまい、結果として得点が伸びなくなってしまいます。
なぜ「粘りすぎ」は失点につながるのか?
SPIでは「全問正解を目指す必要はない」ことを理解しておくべきです。多くの企業では6〜7割程度の得点で十分合格ラインをクリアできます。つまり、全体の中で“取りに行くべき問題”を見極める力が、学力以上に重要になる場面があるのです。
難問に時間をかけすぎた結果、後半の“簡単なのに未着手”な問題がそのまま終わってしまうのは、非常にもったいない事態です。
判断を切り替える目安:
- 30秒考えても糸口が見えなければ飛ばす
- 長い文章や計算量が多そうな問題は後回しにする
- 「見たことあるけど、処理が複雑そう」と感じたら印をつけて一時保留にする
このように“あえて捨てる勇気”を持つことは、SPI非言語における合格戦略の一部です。心理的に「最後まで考えれば解けるかも…」と粘りたくなる気持ちはわかりますが、合否を左右するのは「いかに解ける問題を確実に得点するか」に尽きます。
特に焦っていると「解けそうな気がするのに解けない…」という問題に時間を奪われやすくなります。判断を冷静に保つためにも、模試の段階から「一定時間経ったら次へ進む」という意識を習慣づけておきましょう。
補足:この2点を押さえるだけでSPI非言語の“落とさない力”が身につく
SPI非言語で高得点を取るためには、知識や公式ももちろん重要ですが、それ以上に「解ける問題を確実に拾い、ミスを減らすこと」が鍵になります。
- 見直しの時間を確保して、ミスを1問でも減らす
- 解けない問題は潔く切り替えて、時間を有効に使う
この2点を意識するだけでも、安定して6〜7割の得点を目指すことができます。対策に自信がなくても、戦い方を工夫すれば十分合格ラインに到達可能です。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPI非言語に関するよくある質問
SPI非言語の試験は、就職試験に不慣れな転職希望者にとって不安の種になりやすいポイントです。特に「どれくらい点を取ればいいのか」「苦手分野をどう克服すればいいのか」といった疑問は非常によく聞かれます。
ここでは、実際の転職者や受験経験者からよく寄せられる代表的な質問を2つピックアップし、単なる回答にとどまらず、納得感のある解説を交えて丁寧にお答えしていきます。
Q. どのくらいの得点率で通過できる?
A. 一般的には「6〜7割以上」が合格の目安とされています。
SPI非言語は、満点を取る必要はありません。むしろ、**「いかにミスを減らし、解ける問題を確実に拾うか」**が合格の鍵です。企業によって評価基準は異なるものの、筆記選考の段階で落とされないためには、6割〜7割を安定して取れるレベルを目指しましょう。
たとえば、30問中20問前後が正解できていれば、多くの企業では次の選考に進めると考えられます。ただし、高倍率の人気企業や大手企業では、SPIのスコアをもとに足切りをしている場合もあり、得点率が7割を切ると不安が残ることもあります。
また、性格検査とのバランスも見られるため、「非言語が多少低めでも、性格検査で適正があると判断されれば通過できる」ケースもあります。とはいえ、安心して次に進むためには“7割”をひとつの基準と考えるのがよいでしょう。
Q. 計算ミスが多くて悩んでいます
A. 「読む順番」と「書き出しのクセ」を見直すことで改善することが多いです。
計算ミスに悩む方の多くは、単純な計算力の問題というより、「問題文を正しく理解できていない」「数字をメモせずに頭の中だけで処理している」といった“解き方のクセ”が原因になっているケースが目立ちます。
たとえば、文章問題では、
- 情報が多く整理しきれない
- 複数の数値が出てきて、どれを使えばいいか混乱する
- 単位(%・円・kmなど)を見落としてしまう
といったミスが起こりやすくなります。
これを防ぐために有効なのが、「情報を読みながら書き出す癖をつけること」です。
たとえば、読みながら次のようなメモを簡単に取っておくだけでも精度が上がります。
- 原価=?
- 定価=原価×1.25
- 売価=定価×0.9
また、計算の順序も「頭の中でやらない」ことが鉄則です。特に損益算や割合問題のように数値が入り組んでいる問題では、メモスペースを活用して途中計算を書き出すことで、ミスの予防と見直しの効率化が同時に叶います。
加えて、ケアレスミスが多い人は「計算そのもの」より「焦り」や「見落とし」が原因になっていることもあるため、模試の段階で意識的に「深呼吸して読む」「ゆっくり式を立てる」といった行動を取り入れてみましょう。
Q. 苦手な分野がありすぎて、どこから対策すればいいかわかりません
A. 頻出分野の中でも“自分が正解できる可能性が高い単元”から始めるのが最善です。
SPI非言語は全体を網羅しようとすると時間がかかりすぎます。したがって、まずは**「出題頻度が高く」「難易度が比較的低い」分野**に絞って練習するのが賢いやり方です。
たとえば、
- 損益算や割合問題は、パターンが少なく、基本公式を覚えるだけで対応できるため取り組みやすい分野です。
- 図表問題も、視点を整理するだけで得点できることが多く、対策コスパが高いです。
逆に、場合の数や推論問題などは時間がかかりやすく、理解に時間を要するため、最初から取り組むのは非効率になることもあります。
まずは「自分が理解しやすい」「過去に正解できた」問題の分野から取り組み、自信をつけながら徐々に守備範囲を広げていくのがおすすめです。
Q. 文系で数学が本当に苦手なのですが、それでも対策すれば通過できますか?
A. 十分可能です。実際、文系出身で通過している方は多数います。
SPI非言語で必要なのは「数学的センス」よりも、「パターンへの慣れ」と「戦略的に点を取る力」です。
計算自体は中学レベルが中心であり、難解な数学知識はほとんど必要ありません。逆に、“簡単な問題を見極めて解く”ことこそ、合格する人に共通する力です。
実際、文系出身者の多くが、
- スマホアプリで1日10分だけでも継続した
- 苦手な分野を捨てて、得意な単元だけで点数を稼いだ
- 解説が丁寧な参考書で、1問ずつ理解しながら進めた
といった対策で、合格点に達しています。
自信を持って挑むためにも、まずは「問題を解いてみる」「間違えた原因を理解する」ことからスタートしてみましょう。
補足:Q&Aは自分の“思い込み”を修正するチャンス
SPI非言語の対策では、「苦手だから無理」「点数が高くないと落ちる」「時間がないと対策できない」といった誤解や思い込みに縛られがちです。しかし、正しい知識と戦略を持てば、どんなバックグラウンドの人でも通過は十分可能です。
不安や疑問がある時こそ、情報を正しく知っておくことが、選考突破の第一歩になります。
まとめ
転職におけるSPIの非言語分野は、確かに難しさを感じる場面もありますが、対策すればするほど結果に結びつく“努力が報われやすい”領域でもあります。
この記事で紹介したように、自分の現在地を診断し、出題頻度の高い単元を優先的に対策すれば、確実に合格ラインへと近づくことができます。攻略マトリクスやヒートマップを活用して効率よく学習し、文系でも突破できた体験談から勇気をもらいながら、自分に合った対策を進めていきましょう。「SPI非言語が不安だったけど、しっかり準備して良かった」
そんなふうに思える日が、あなたにもきっと訪れます。