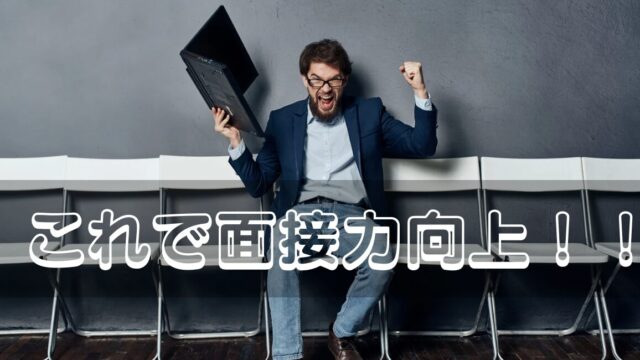【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
就活をしていると、「この会社、給料はいいけど…福利厚生ってどうなんだろう?」と気になったことはありませんか?
でも、「福利厚生」って具体的に何をチェックすればいいのか、イマイチ分からない…そんな声も多く聞きます。
実は、福利厚生は入社後の生活や働き方に直結する重要な要素。
給与と違って「見えにくい」部分だからこそ、知らずに入社して「え、こんなはずじゃなかった…」と後悔してしまうケースもあります。
この記事では、新卒でもチェックすべき福利厚生の基礎知識や特に注目すべきポイントと見極め方、面接や説明会での確認方法などを分かりやすく解説します。
「福利厚生ってよく分からないから後回し…」という人ほど、読んでおいて損はない内容です。ぜひ参考にしてください。
目次
新卒が「福利厚生」を確認すべき理由とは?
「福利厚生って、家族がいる人やベテラン社員向けの制度でしょ?」
そんなふうに思っている人もいるかもしれません。たしかにそういった制度もありますが、実は新卒だからこそチェックしておきたい福利厚生のポイントがたくさんあります。
この章では、新卒が福利厚生に注目すべき理由と、どんなメリットがあるのかを解説していきます。
福利厚生が充実している企業のメリット
福利厚生が手厚い企業には、こんなメリットがあります。
- 生活費を抑えられる(住宅手当・昼食補助など)
- 健康を維持しやすい(健康診断・メンタルケア制度など)
- 働きやすい環境が整っている(フレックスタイム・休暇制度など)
つまり、給料以外にも“実質的に得られる価値”が高いということ。
たとえば、家賃補助が月2万円出るとしたら、年間で24万円も手取りが増えるのと同じような効果があります。
さらに福利厚生がしっかりしている会社は、社員のことを長期的に考えてくれていることが多く、企業の「社員を大切にする姿勢」が見える部分でもあります。
「思っていた待遇と違う…」と後悔しないために
就活生の中には、内定後や入社後に「こんなに残業があるとは思わなかった」「制度はあるけど使えない」など、福利厚生に関するギャップで後悔する人も少なくありません。
たとえば…
- 有給はあるけど、実際はほとんど取れない
- 退職金制度はあるけど、実際は金額がほとんどない
- リモート勤務OKと書いてあっても、上司が嫌がって使わせてくれない
こうした「形だけの福利厚生」に惑わされないように、事前にどこを見て、何を確認すればいいのかを知っておくことが重要です。
福利厚生利用率も重要
もうひとつ重要なのが、「その制度、実際に使われているの?」という視点。
いくら制度が豪華でも、実際に社員が使っていなければ意味がありません。
チェックポイント:
- 企業説明会やHPに「利用率」が明記されているか
- 口コミサイトで「制度はあるが使いにくい」といった声が出ていないか
- OG・OB訪問でリアルな使用状況を聞く
“使える福利厚生”かどうかを見極めることが、福利厚生重視の就活には不可欠です。
最低限チェックすべき法定福利厚生とは?
福利厚生には大きく分けて、「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。
この章では、企業が法律で義務づけられている“法定福利厚生”についての基礎知識と、就活生が知っておくべきチェックポイントを紹介します。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の基礎知識
就職すれば自動的に入ると思っている人も多いこれらの制度ですが、正社員として働く以上、会社がちゃんと加入手続きをしているかは重要なチェックポイントです。
●健康保険
病院の診察や治療を受けるときに使う保険。会社に入ると「健康保険組合」や「協会けんぽ」に加入します。
●厚生年金保険
将来もらえる年金のための保険。会社と自分が半分ずつ保険料を払います。
国民年金よりも給付額が多くなるため、厚生年金に加入しているかどうかは老後に直結するポイントです。
●雇用保険
失業したときに失業手当をもらうための保険。アルバイトでは加入しない場合もあるので、正社員なら必ずチェック。
●労災保険
仕事中や通勤中にケガや病気になったときに補償される保険。こちらは全額会社負担で加入します。
これら4つの保険は「社会保険」とまとめて呼ばれることもあるので、求人情報に「社会保険完備」と書かれているかもチェックポイントです。
有給休暇の付与条件と消化率の確認方法
正社員であれば、入社6か月後から有給休暇が10日間付与されるのが基本ルールです(週5日勤務の場合)。
ただし、「制度として有給がある=ちゃんと取れる」とは限りません。
チェックすべきポイント:
- 1年で何日くらい消化できているか(消化率)
- 「忙しくて取りづらい雰囲気」がないか
- 社員の有給取得について企業がどう考えているか(説明会などで質問するのも◎)
制度があるだけで使えない“形だけの有給”になっていないか、事前に確認しておくことが大切です。
残業代の支払いルール(みなし残業・固定残業制に注意)
見落としがちですが、残業代の支払い方も立派な福利厚生の一部です。
特に「みなし残業制」や「固定残業代あり」と書かれている場合は、その中身をしっかり確認しましょう。
チェックポイント:
- 「月20時間分の残業代を含む」→超過分は支給される?
- 固定残業代に含まれている金額が妥当か?
- 残業そのものが多すぎないか
面接や説明会で「平均残業時間」や「超過分の支払い」について質問しておくと、入社後のギャップを減らせます。
企業ごとに差が出る「法定外福利厚生」のポイント
「法定外福利厚生」とは、企業が独自に用意している福利厚生のことです。
ここが会社ごとにかなり差が出るポイントで、働きやすさや生活の安定度に直結する部分でもあります。
この章では、就活生が特に確認しておきたい法定外福利厚生の中でも、重要なものをピックアップして紹介します。
住宅手当・家賃補助の有無(特に都市部での就職では重要)
新卒で一人暮らしを始める人にとって、家賃の負担はかなり大きな出費になります。
そのため、「住宅手当」や「家賃補助」があるかどうかは、実質的な手取りを左右する重要な要素です。
チェックポイント:
- 月額いくら支給されるのか?(相場は1〜3万円程度)
- 上限額や対象条件はあるか?(勤務地、実家通勤かどうかなど)
- 社宅制度や借上げ社宅がある企業も要チェック!
都市部での就職を考えている人は、ここがあるだけで生活の余裕がかなり変わってきます。
通勤手当の上限額や支給条件
一見当たり前に思える通勤手当ですが、支給条件や上限額に企業ごとの違いがあります。
- 全額支給なのか?それとも月〇円まで?
- 定期代なのか、実費精算なのか?
- リモート勤務が多い会社では通勤手当が出ない場合も
自宅から職場までの距離や、勤務地の交通事情によっても負担額が変わるので、説明会や面接時に確認しておくと安心です。
賞与・退職金制度の有無
賞与(ボーナス)や退職金制度は、給与以外での“長期的な収入”に関わる大きなポイントです。
賞与について:
- 支給の有無(年2回が多いが、業績次第の企業も)
- 新卒1年目から満額支給されるか?(半額スタートの場合もあり)
退職金について:
- 退職金制度があるか(中小企業では導入されていない場合も)
- 確定拠出年金(DC制度)との違いも理解しておくと◎
長く働くつもりがある人にとっては、退職金制度の有無が将来の資産形成に大きく影響します。
フレックスタイム・リモートワークの導入状況
働き方の自由度を左右するのが、フレックス制度やテレワーク制度の有無です。
とくに最近では「ライフスタイルに合わせて働き方を選べる企業」が人気になっています。
チェックポイント:
- フレックス制度は全社員対象?一部の部署だけ?
- リモートワークは制度としてあるだけでなく、実際に使われているか?
- 出社頻度や勤務時間の柔軟性はどれくらいか?
求人情報に書かれていても、「制度がある=実際に使える」とは限りません。
OG・OB訪問などでリアルな運用状況を確認しておくと安心です。
ワークライフバランスを左右する福利厚生
「この会社、仕事は面白そうだけど、プライベートの時間もちゃんと取れるのかな?」
就活生なら一度は感じたことがある不安ではないでしょうか。
ワークライフバランスを支えてくれるのが、生活系の福利厚生です。
この章では、働きすぎを防いだり、健康を維持したりする上で大切な制度を中心に紹介します。
休暇制度(育休・介護休暇・リフレッシュ休暇など)
休暇制度といえば「有給休暇」だけを思い浮かべがちですが、実はそれ以外にもさまざまな休暇制度があります。
チェックしておきたい制度:
- 育児休暇・産前産後休暇:男女ともに取得しやすい雰囲気か?実績はあるか?
- 介護休暇:将来のライフステージを見据えても大切
- リフレッシュ休暇・誕生日休暇など:会社独自のユニークな制度もあり
制度があるかどうかだけでなく、実際に活用されているかも重要なチェックポイントです。
健康支援制度(健康診断・人間ドック・メンタルヘルス対策)
社会人になると、体調管理も自己責任になります。だからこそ、会社のサポートがあると安心です。
年1回の健康診断は義務化されていますが、会社によってオプション検査や費用負担の違いがあります。また一部の企業では、人間ドックの補助や、メンタルヘルス相談窓口などの支援も充実していたり、健康に関するセミナーや産業医との面談が定期的に行われている企業もあります。
心と体の健康を守る仕組みがあるかどうかは、長く働く上で非常に重要です。
社員食堂・昼食補助・カフェテリアプランの有無
昼食代の負担を減らせたり、栄養バランスを意識できたりするのが「食」に関する福利厚生です。
社員食堂がある企業では、安くて栄養バランスのいいごはんを毎日食べられます。もし食堂がない場合でも、昼食補助(お弁当支給、食事代補助など)がある企業もあります。
また中にはカフェテリアプランというポイント制の福利厚生を導入している企業もあり、食事だけでなく旅行や健康関連サービスにも使えるのが特徴です
毎日使う制度だからこそ、実質的な生活のしやすさに大きく関わってくる部分です。
キャリアアップにつながる福利厚生とは?
就職する企業を選ぶうえで、「この会社で成長できるかどうか」も大事な判断軸ですよね。
そんなときに注目してほしいのが、キャリアアップを支援するタイプの福利厚生です。
この章では、「スキルを伸ばしたい」「いろんな働き方にチャレンジしたい」と考える就活生に向けて、成長につながる制度を紹介します。
研修制度・資格取得支援の充実度
入社後の“学び”をサポートしてくれる制度は、特に新卒にとって重要なポイントです。
よくある制度の例:
- 新入社員研修(ビジネスマナー・社会人基礎など)
- OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)
- 外部セミナー受講制度
- 資格取得支援(受験料補助・合格祝い金など)
「スキルアップを応援する風土があるかどうか」は、その後のキャリア形成にも関わってくるので、研修制度の内容や運用実績も確認しておきましょう。
社内公募制度・異動希望制度があるか
「いずれは別の職種にも挑戦してみたい」
「社内でキャリアチェンジしたい」
そんな希望が叶えやすい企業には、社内公募制度や自己申告制の異動制度があります。
- 社内公募制度:新しいプロジェクトや部署に自分から手を挙げて応募できる仕組み
- 異動希望制度:年に1回、自分のキャリア希望を会社に伝える機会がある制度
配属ガチャやキャリアの不透明感に悩まされないよう、社員にとって「選べる道」が用意されているかどうかも見ておくと◎です。
副業・兼業OKかどうか
最近は、副業を認める企業も増えてきました。
就業後や週末にスキルを活かして働ける環境があると、本業で得た知識をさらに広げたり、自分の市場価値を高めたりすることができます。
- 副業可でも「申請が必要」「条件付きOK」など、企業ごとにルールが異なる
- 特にIT・Web業界やスタートアップでは柔軟なケースが多い
- 副業制度がある企業=「社員の成長を信頼している企業」とも言える
将来的に独立や転職を視野に入れている人にとっては、副業の可否も大切な判断材料になります。
企業は「入社して終わり」ではなく、あなたの成長をどう支えるかも問われています。
キャリアアップに直結する福利厚生があるかを確認することで、長く成長できる環境かどうかが見えてくるはずです。
ここまで見ておこう!福利厚生を重視する人がチェックすべきポイント
ここまでで紹介してきた福利厚生は、いわば“基本セット”。
でも実は、それ以外にも企業ごとのカラーが出やすい+実は見落としがちな制度があります。
この章では、「福利厚生を重視して企業を選びたい!」という人が最後にもうひと押しで見ておくと良いチェックポイントをまとめました。
持ち株制度・確定拠出年金(老後資金の準備につながる)
正直、学生のうちはあまりピンとこないかもしれませんが、「資産形成」系の制度も大切です。
将来のために“働きながらお金を育てる”仕組みが整っているかどうかは、長く働くうえでの安心材料になります。
- 持ち株制度:自社株を割安で購入できる制度。会社の成長とともに資産も増える可能性あり
- 確定拠出年金(企業型DC):老後の資金を積み立てる制度で、企業が一部負担してくれる場合も
こうした制度を導入している企業は、「長く働いてほしい」という思いを制度に込めているケースが多いです。
社員割引・レジャー・保養施設などの充実度
レジャー施設の割引やスポーツジム利用補助、社内旅行など、楽しみながら使える福利厚生もチェックしておきたいところです。
- 社員割引(自社サービスやグループ企業の割引など)
- 宿泊補助・保養所の利用制度
- 映画・スポーツ観戦チケットの優待
こうした制度があると、オンオフの切り替えもしやすく、リフレッシュに役立ちます。
意外と「働きやすさ」に直結することもあるので、福利厚生が手厚い企業ほど、生活の満足度が高くなる傾向にあります。
家族向け福利厚生(扶養手当・育児支援制度の有無)
結婚・出産といったライフイベントを迎えたときに支えになるのが、家族向けの福利厚生です。
- 扶養手当や家族手当:家族を養っている社員への金銭的サポート
- 育児支援制度:保育料の補助、子育て支援休暇、在宅勤務の活用など
「まだ自分には関係ない」と思うかもしれませんが、長く働くことを見据えると、非常に重要な制度でもあります。
求人票だけでは分からない!企業の福利厚生を見極めるコツ
ここまでで、「どんな福利厚生があるといいのか」はだいぶイメージがついたと思います。
でも実際の就活では、「制度があるかどうか」は求人票や企業HPにざっくりとしか書かれていないことが多いですよね。
そこでこの章では、求人情報だけでは分からない企業の“本当の福利厚生の中身”を見極める方法を3つの視点から解説します。
①求人情報や企業HPで見るべきポイント
まずは基本の確認から。求人票や企業HPを見るときは、ただ「福利厚生:各種制度あり」と書いてあるだけで済ませるのではなく、次のような具体的な情報が載っているかをチェックしましょう。
- 各制度の内容が具体的に書かれているか(例:住宅手当2万円支給など)
- フレックスやリモート勤務の実施状況(制度だけでなく“実施している”と明記されているか)
- 社員インタビューで福利厚生が実際に使われているエピソードが語られているか
企業によっては、福利厚生の利用事例や社員の声を紹介している特設ページがあることもあります。こういった情報が豊富な企業ほど、実際の運用に力を入れている可能性が高いです。
②口コミサイトやOG・OB訪問でリアルな情報を得る方法
実際の利用状況や「制度はあるけど使われていない」といった裏事情は、外部の口コミや現場の声でしかわかりません。
情報収集に使える手段:
- OpenWork・転職会議・ライトハウスなどの口コミサイト
→福利厚生の項目に注目。「有給が取りづらい」「実質使えない」などのコメントに注意。 - OG・OB訪問
→実際に働いている先輩から、「制度はあるけど使いやすい?」「周りは利用してる?」などのリアルな声を聞ける貴重な機会。
気になる制度があれば、遠慮せずに具体的に質問することが大切です。
③面接・説明会で企業に確認すべき具体的な質問例
選考中にも、企業に直接質問するチャンスはあります。説明会や面接の場では、以下のような聞き方をするとスマートです。
- 「御社では有給休暇の平均取得日数はどれくらいでしょうか?」
- 「リモート勤務制度があると伺いましたが、実際に利用されている社員の割合は?」
- 「研修制度について、特に新卒向けに力を入れている内容があれば教えてください」
- 「福利厚生の中で、社員に特に好評な制度があればぜひ知りたいです」
言いづらい質問も、聞き方を工夫すれば好印象につながることもあります。
企業も「制度に関心を持っている=将来を真剣に考えている」と受け取ってくれることが多いです。
【まとめ】新卒が福利厚生で失敗しないために
ここまで読んでくれたあなたは、もう「福利厚生ってなんとなくで見るものじゃない」って気づいてきたはずです。
給与や職種、企業名だけでは測れない、“働きやすさ”や“安心感”に直結するのが福利厚生です。
そのため以下の3つは必ず行うようにしましょう。
- 「自分にとって必要な福利厚生」を明確にする
- 企業ごとの違いを理解し、比較・検討する
- 入社後に後悔しないために、しっかりリサーチを行う
「どこに入るか」ではなく、「どう働くか」が重要になる時代。
だからこそ、福利厚生は就活の“後回しポイント”ではなく、“判断材料のひとつ”としてしっかり見ていきましょう。
あなたの就活が、より自分らしい選択につながることを願っています!