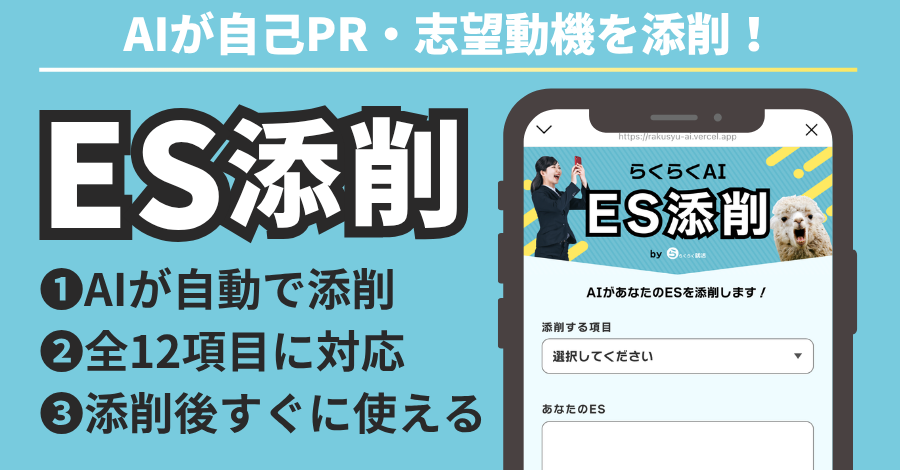【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
就活の面接で必ずといっていいほど聞かれるのが「自己PR」です。履歴書やエントリーシートに書くだけでなく、面接の場で直接伝えることが求められるため、避けて通ることはできません。しかし「何をどう話せばいいかわからない」「時間配分が難しくてまとまらない」と悩む学生は非常に多いです。
特に面接官が重視するのは、話す内容だけではなく「話し方」です。どれだけ良い経験をしていても、伝え方が長すぎたり曖昧だったりすると、面接官には響きません。逆に、1分ほどで簡潔かつわかりやすく伝えられれば、それだけで評価が大きく変わります。つまり「自己PR=内容×話し方」の掛け算なのです。
本記事では、就活面接での自己PRの話し方を徹底的に解説します。1分で伝えるための構成方法やタイム配分、話すときの声・姿勢・表情のポイント、NG例と改善例、さらには例文や練習法まで幅広く紹介します。読み終えた頃には、面接で自信を持って話せる「伝わる自己PR」が完成するはずです。
目次
就活面接で求められる自己PRとは
自己PRは、ただ自分の性格や特徴を伝えるものではありません。面接官が知りたいのは「この学生が入社後にどんな活躍をしてくれるか」「会社にどう貢献できるか」です。したがって、自己PRは「自分の強みを根拠とともに示し、それを仕事にどう活かせるかを伝えるプレゼンテーション」と捉えるのが正解です。
自己PRの評価は、エピソードの立派さよりも「話の一貫性」「わかりやすさ」「会社での活躍イメージ」によって決まります。たとえば「私はリーダーシップがあります」と言うだけでは不十分で、「リーダーとしてどんな経験をし、どんな成果を出し、その力を入社後どう使うのか」まで示すことで説得力が生まれるのです。
自己紹介と自己PRの違い
就活生がよく混同するのが「自己紹介」と「自己PR」です。自己紹介は、名前・大学・専攻など基本的なプロフィールを簡単に述べるもので、面接の冒頭で行われます。いわば「自分が誰なのか」を知らせるための入り口のような役割です。
一方、自己PRは「自分の強みを証明するためのプレゼン」です。名前や学歴を述べるだけではなく、自分の能力や価値を具体的な経験を通して伝える必要があります。たとえば、自己紹介が「私は〇〇大学の△△です」だとすれば、自己PRは「私は△△の経験から□□という強みを身につけました。それを御社で活かしたいです」という形になります。
つまり、自己紹介は「事実を伝えること」、自己PRは「強みをアピールすること」と覚えておくと区別しやすいでしょう。
企業が自己PRで見ているポイント
では、企業は自己PRのどんな部分を評価しているのでしょうか。大きく分けると次の3つです。
まず1つ目は「強みの内容」です。その学生ならではの力や資質が見えるかどうかを確認します。面接官は「この学生はどのような場面で力を発揮できるのか」を知りたいのです。
2つ目は「強みを裏付けるエピソード」です。強みをただ口にするだけでは説得力がありません。過去の経験を具体的に話すことで「本当にその力を持っているのか」が伝わります。特に成果や役割を数字や具体的な事実で示せると信頼性が高まります。
3つ目は「入社後に活かせるかどうか」です。面接官が最も重視しているのは、学生の強みが会社の業務や職種に結びつくかという点です。どれほど立派な経験でも、業務に直結しないと評価は上がりません。
自己PRは「自分の強みを伝える場」であると同時に、「自分が会社にどう貢献できるかを証明する場」でもあるのです。
自己PRで話すエピソードの選び方
自己PRの印象を大きく左右するのは、どんなエピソードを選ぶかです。せっかく強みを言葉にできても、裏付けとなる経験が弱ければ説得力は生まれません。逆に、日常的な経験でも「どんな課題に直面し、どう行動し、何を得たか」を整理して話せば、強いアピールにつながります。ここでは、エピソード選びのポイントを解説します。
強みを示す具体的な経験を選ぶ
まず重要なのは、自分の強みを最もよく表す経験を選ぶことです。面接官は「この学生はどんな資質を持ち、どう行動する人なのか」を知りたいため、抽象的な出来事ではなく具体的な行動が伝わるエピソードが望まれます。
たとえば「私は協調性があります」と述べるだけでは弱いですが、「大学のゼミ活動で、意見の対立があったときに全員が納得できる方向性を提案し、発表を成功に導いた」というエピソードなら説得力が増します。つまり、強みを「証明する舞台」を選ぶことが大切なのです。
数字や成果で裏付けると効果的
次に意識したいのは、エピソードを成果や数字で補強することです。数字は説得力を強める強力な武器です。「売上を120%伸ばした」「部員の参加率を30%改善した」「模擬試験で学年10位に入った」など、定量的な結果を加えると、強みの実在感が一気に高まります。
もちろん、すべての経験に数字がつくとは限りません。その場合も「◯人のチームをまとめた」「半年間続けた」「100枚以上の資料を整理した」といった量的な表現を工夫することで、経験をよりリアルに伝えることができます。
入社後に活かせる要素を含める
最後に大事なのは、その経験が入社後の仕事にどうつながるかを示すことです。面接官は「過去の経験」そのものよりも、「その経験で得た強みを今後どう活かすのか」に注目しています。
たとえば、アルバイトで接客を頑張った経験なら「お客様の要望を正確に理解し、満足度向上につなげた。その姿勢は営業職として顧客の信頼を築くことに活かせる」と話すと、企業側がイメージしやすくなります。
エピソードを選ぶときは、「強みが伝わる」「成果が示せる」「仕事に活かせる」という3つの条件を満たすかどうかを基準にすると、自然と効果的な内容になります。
面接で自己PRを伝える話し方の基本
どんなに良いエピソードを用意しても、話し方が整理されていなければ面接官には伝わりません。自己PRを評価してもらうためには、話す順序や時間の配分を意識することが不可欠です。この章では、基本的な構成方法や話す量の目安、効果的な流れを解説します。
PREP法を使った構成の作り方
自己PRをシンプルかつ説得力をもって伝えるには、PREP法が有効です。PREP法とは、Point(結論)→ Reason(理由)→ Episode(具体例)→ Point(再結論) の流れで話す方法です。
たとえば「私の強みは継続力です(Point)。なぜなら、困難な状況でも粘り強く取り組み成果を出した経験があるからです(Reason)。具体的には、アルバイトで人手不足の中でも半年間欠かさず出勤し、新人教育まで任されました(Episode)。この粘り強さを御社の業務でも発揮できます(Point)」という流れになります。
結論から始めることで面接官にテーマが明確に伝わり、その後の理由とエピソードで納得感を与えることができます。最後に再び結論を述べると、印象に残る自己PRになります。
1分にまとめる文字数と分量の目安
面接での自己PRは1分前後が理想とされます。長すぎると冗長に感じられ、短すぎると内容が薄い印象を与えてしまうからです。目安としては、300〜350字程度の文章量にすると1分に収まります。
自分で文章を作ったら、一度文字数を数えてみると良いでしょう。原稿用紙1枚分を超えると1分では収まらないケースが多いため、要点を絞る工夫が必要です。
強み→経験→成果→活かし方の流れ
自己PRの内容を整理するときは「強み→経験→成果→活かし方」という流れを意識しましょう。強みだけでは根拠が弱く、経験だけでは単なる思い出話に終わります。そこに成果と未来の活かし方を加えることで、自己PRとして完成度が高まります。
たとえば「私はリーダーシップが強みです(強み)。大学のサークル活動では、発表会に向けてメンバーをまとめました(経験)。その結果、観客数が前年より2割増加し、学外からの招待も受けました(成果)。この経験を活かして、御社のプロジェクトを円滑に推進していきたいです(活かし方)」という流れです。
この型に沿えば、内容が整理され、面接官も理解しやすくなります。
1分自己PRタイム配分練習法
おすすめなのが「タイム配分を意識した1分練習法」です。自己PRを4つのパートに分け、それぞれに目安の時間を割り振ります。
- 強みの提示:10秒
- 根拠・理由の説明:15秒
- 具体的なエピソード:25秒
- 成果と入社後の活かし方:10秒
このように区切ると、全体でちょうど1分前後になります。自分の自己PRを実際に声に出して時間を測りながら練習することで、話しすぎや省略のバランスを調整できます。
このトレーニングを繰り返すと、面接本番でも時間を意識しながら自然に自己PRを伝えられるようになります。
自己PRの良い話し方のコツ
自己PRの内容を整えたら、次に大切なのは「どう話すか」です。同じ内容でも、話し方によって印象は大きく変わります。ここでは、面接官に伝わりやすい話し方のコツを具体的に紹介します。
ゆっくり落ち着いたペースで話す
多くの学生は緊張すると早口になりがちです。しかし、早口では言葉が聞き取りづらく、面接官が内容を理解しにくくなります。自己PRは「丁寧に伝えること」が大切なので、普段の会話より少しゆっくりめを意識しましょう。
目安は1分間に300字程度。録音して確認すると、自分が想定以上に早口になっていることに気づけます。息継ぎを意識的に入れるだけでも、落ち着いた印象に変わります。
明るい声で、聞き取りやすさを意識する
声のトーンも重要です。小さな声や暗いトーンでは、自信のなさや消極的な印象を与えてしまいます。逆に、明るくはっきりとした声は、前向きさや熱意を感じさせます。
特に冒頭の「私の強みは〜です」の部分は、声のトーンを一段階上げて話すと自己PRの印象が強まります。単に大きな声を出すのではなく、相手に届くように「相手に聞かせる声」を意識するのがポイントです。
「えー」「あのー」を減らす練習法
口癖で「えー」「あのー」が多くなると、話の流れが途切れてしまいます。これを減らすには、自己PRを繰り返し練習して頭に入れておくことが効果的です。
さらにおすすめなのが「録音しながら練習する」方法です。自分の話し方を客観的に聞くと、無意識に出ている filler words(つなぎ言葉)に気づき、改善しやすくなります。慣れないうちは一文ごとに区切って練習し、徐々に滑らかにつなげていくと良いでしょう。
面接官に伝わる目線・姿勢・表情
話し方は声や言葉だけではありません。目線・姿勢・表情も「伝わる自己PR」に直結します。目線を下に落としたままでは自信がない印象になり、逆に面接官をにらむように見ても不自然です。自然な会話のように、面接官の目元を見るイメージで視線を向けると好印象です。
姿勢は背筋を伸ばし、両手を膝の上に置くのが基本です。猫背や貧乏ゆすりは落ち着きのなさを感じさせます。表情については、無理に笑顔を作る必要はありませんが、柔らかい表情で話すと安心感を与えられます。
自己PRの話し方チェックリスト
最後に、面接前に確認できる「話し方チェックリスト」を紹介します。
- 1分で収まるように話せているか
- 強み・根拠・エピソード・活かし方の流れが明確か
- 声の大きさ・トーンは聞き取りやすいか
- 「えー」「あのー」といった filler words が少ないか
- 姿勢や目線に落ち着きがあるか
面接直前にこの項目を頭の中で確認するだけで、自信を持って話せるようになります。
自己PRのNGな話し方
自己PRは伝え方次第で評価が大きく変わります。せっかく良い経験を持っていても、話し方に問題があると面接官に魅力が伝わりません。この章では、ありがちなNGな話し方とその理由を解説します。
長くダラダラ話す
自己PRでよくある失敗が、話が長くなりすぎることです。自分の経験をすべて伝えたくなる気持ちはわかりますが、長い話は要点がぼやけ、面接官に「結局何が強みなのか」が伝わりません。面接官は1日に何十人もの学生と会うため、短時間で理解できるかどうかを重視しています。1分以内で簡潔にまとめることが基本です。
強みが複数あって焦点がぼやける
「アピールできる強みがたくさんあるから全部話したい」と考えてしまう学生もいます。しかし強みを複数並べると、一つ一つが薄まり、結果的に何も印象に残らなくなります。大切なのは「この人といえばこの強み」という一貫性です。強みは一つに絞り、具体的に深掘りする方が効果的です。
抽象的すぎて伝わらない
「私の強みは責任感です」「私は努力家です」といった抽象的な表現は、面接官にとってイメージしづらく、説得力に欠けます。責任感や努力という言葉自体は悪くありませんが、具体的なエピソードと結びつけなければ、ただの自己評価に終わってしまいます。
話し方が暗い・早口
どんなに良い内容でも、声が小さく暗かったり、早口でまくしたてるように話すと印象が悪くなります。面接官は「一緒に働く姿」を想像するため、暗い印象や焦った印象はマイナス評価につながります。特に自己PRは自分を売り込む場ですから、明るく落ち着いた話し方を意識しましょう。
NGな話し方と改善例の比較
ここで、典型的なNGな話し方と、それをどう改善できるかを比較してみます。
- NG例:「私は責任感があります。小学校のころから何事も最後までやり遂げてきました。大学でも同じで、いろいろ頑張りました。」
- 改善例:「私の強みは責任感です。大学のゼミ活動では、リーダーとして企画運営を任されました。準備段階でトラブルが発生しましたが、最後まで諦めず対応した結果、無事に発表会を成功させることができました。この責任感を御社のプロジェクト推進に活かしたいです。」
両者を比べると、改善例は具体性があり、入社後に活かせるイメージが湧きます。NGな話し方をそのままにせず、改善例を意識することで自己PRは格段に伝わりやすくなります。
ESの添削をしたいけど誰かに見せるのは嫌だ、、
「志望企業に提出する前に誰かにESを添削してほしい」こんなこと考えたことありますよね。できる限りESの質を高めるには誰かに読んで読んでもらって評価してもらのが1番です。でもESを家族や友人に読まれるのも気が進まず、なかなか頼める相手は見つからないのではないでしょうか?
「ES添削ツール」なら、自分で考えたESをコピペするだけで、AIが自動でESの文章を添削してくれるため、あなたのESを即座に添削・改善することが可能です。
そのため誰かに読まれるのが嫌だな、、という方にもぴったりです。
らくらく就活をLINE追加して、簡単なアンケートに答えるだけで無料で使えるので、すぐにESを添削してみましょう!
自己PRの話し方の例文を紹介
ここまで自己PRの作り方や話し方のポイントを解説してきましたが、実際の例文を見た方がイメージが湧きやすいでしょう。以下では、代表的な強みごとに1分以内で伝わる自己PR例文を紹介します。文章の流れや表現方法を参考に、自分の経験に置き換えてみてください。
例文① 継続力をPR
「私の強みは継続力です。大学では英語力を伸ばすため、毎日30分以上の勉強を3年間続けました。その結果、TOEICのスコアを300点以上伸ばすことができました。目標に向けて粘り強く取り組める力は、御社での長期的なプロジェクトにも活かせると考えています。」
→ シンプルですが、継続力を証明する事実と成果が盛り込まれており、説得力があります。
例文② コミュニケーション能力をPR
「私の強みはコミュニケーション能力です。アルバイト先の飲食店では、スタッフ同士の意見の食い違いが原因で業務が滞ることがありました。私は双方の意見を整理し、改善点を提案することで、店舗運営がスムーズになり、店長からも信頼を得られました。この力を御社のチームワークを支える場面で活かしたいと考えています。」
→ トラブル解決の場面を具体的に示すことで、単なる「話すのが得意」ではないことが伝わります。
例文③ 分析力をPR
「私の強みは分析力です。ゼミ活動では市場調査を担当し、アンケートデータを統計的に分析して発表を行いました。その結果、教授から『客観的なデータに基づいた説得力のある報告だった』と高い評価をいただきました。この力を活かし、御社のマーケティング業務においてデータから課題を発見し、改善策を提案していきたいです。」
→ データ活用の経験を具体的に示すことで、企業での実務イメージが浮かびやすくなります。
例文④ リーダーシップをPR
「私の強みはリーダーシップです。大学のサークルでは発表会の実行委員長を務め、20名のメンバーをまとめました。準備段階で意見が割れましたが、全員の意見を整理して方向性を決定し、結果的に前年よりも来場者数が2割増加しました。この経験を活かし、御社のプロジェクトでも成果を上げられるよう貢献したいと考えています。」
→ 成果が数字で示されているため、リーダーシップの効果が具体的に伝わります。
例文⑤ 目標設定力をPR
「私の強みは目標設定力です。アルバイトで売上を伸ばすため、1か月ごとの目標を自ら設定し、接客方法を改善しました。その結果、担当していた商品の販売数を前年比150%にすることができました。今後も課題を明確にし、達成までの道筋を立てて取り組む姿勢を御社でも発揮したいです。」
→ 「目標を立てる→行動→成果」という流れが明確で、論理的に伝わっています。
面接とエントリーシートで自己PRはどう使い分ける?
自己PRは就活のあらゆる場面で必要になりますが、エントリーシート(ES)と面接では求められる役割や伝え方が微妙に異なります。同じエピソードを使うにしても、強調すべき部分や表現方法を変えなければ効果的に伝わりません。ここでは、ESと面接の違いを踏まえた自己PRの使い分けを詳しく解説します。
ESは文章で詳細に、面接は要点を話す
ESは自分の経験を文章としてじっくり説明できる場です。文字数が指定されていることが多いため、背景から結果までストーリーを順序立てて丁寧に書くことが可能です。例えば「どういう課題に直面したか」「なぜその課題に取り組んだのか」「具体的にどんな行動を取ったのか」「結果として何を得たのか」という流れを、論理的に示すことができます。文章量がある分、細かい経緯や感情の動きまで含めることができるのが強みです。
一方、面接の自己PRは時間が限られています。1分程度で伝えることが求められるため、ESのように細かく説明していると途中で面接官に話を遮られることもあります。面接で意識すべきは「要点を端的に話すこと」。強みとエピソードを絞り込み、余分な描写は省きながら「結論→根拠→エピソード→活かし方」の流れで話すのが基本です。
つまり、ESは「詳細なレポート」、面接は「短時間のプレゼン」とイメージするとわかりやすいでしょう。
面接官が深掘りする前提で準備する
さらに重要なのは、面接では面接官が必ず深掘りしてくるという前提で準備することです。ESは一方通行の提出物であり、読み手が勝手に理解してくれるものですが、面接は対話の場です。
たとえばリーダーシップをアピールした場合、面接官から「具体的にどんな工夫をしましたか?」「メンバーから反発はありませんでしたか?」「その経験を社会人になってどう活かせると思いますか?」といった追加質問が投げかけられる可能性が高いです。この時に答えられないと、「本当にその強みを持っているのか?」と疑問を持たれてしまいます。
したがって、面接では「自己PRの核となる1分スピーチ」と、それを支える「詳細な裏話」をセットで用意しておくことが大切です。ESに書いた内容を土台にして、深掘り質問に備えられるように準備しておきましょう。
ESと面接の連動性を意識する
もう一つ忘れてはいけないのが、ESと面接の内容が食い違わないようにすることです。ESで書いた強みと、面接で話す強みがバラバラだと一貫性がなく、信頼性が下がってしまいます。
もちろん、複数の強みを持っていても構いませんが、同じ企業に提出するESと面接では「一貫性を重視する」ことが重要です。例えばESで「協調性」を強調したなら、面接でも「協調性」を軸にして具体的に話を展開すると、面接官も「この学生は本当に協調性を大切にしているのだな」と納得しやすくなります。
このように、ESは「背景から成果までの詳細な説明」、面接は「要点を短くまとめたプレゼン」として役割を使い分けつつ、両者の内容に一貫性を持たせることが、評価を高めるためのコツです。
自己PRを1分で話すためのトレーニング法
自己PRは1分程度で簡潔にまとめるのが理想ですが、実際にやってみると「短すぎて伝えたいことが入らない」「気づいたら2分以上話してしまった」と悩む学生が多いです。そこで効果的なのが、時間を意識したトレーニングです。ここでは、実践しやすい練習方法を紹介します。
録音して時間と内容をチェック
まず試してほしいのが、自分の自己PRをスマホなどで録音する方法です。録音すると、自分がどのくらいのスピードで話しているのか、どの部分に時間を使いすぎているのかが明確にわかります。
「ここで細かい説明を入れすぎているな」「この部分は短くても伝わるな」と気づけるので、自然と内容の取捨選択ができるようになります。さらに録音を繰り返すことで、自分の口癖や話し方のクセを客観的に確認でき、改善につなげられます。
第三者に聞いてもらい改善点を把握
次に効果的なのが、友人や家族など第三者に自己PRを聞いてもらう方法です。自分では気づけない弱点を指摘してもらえるため、修正のスピードが早まります。
特に「結局何が強みだったのかわかりにくい」「長い部分が退屈に感じる」といった感想は、面接官の印象と近いケースが多いです。聞き手からの率直なフィードバックをもとに改善を重ねれば、より伝わる自己PRに磨き上げられます。
面接練習アプリやAI添削の活用
近年は、AIを活用した面接練習アプリや添削サービスも充実しています。自分の話すスピードや声のトーン、表情まで解析してフィードバックをくれるツールもあり、個人練習より効率的に改善できます。
また、文章ベースで自己PRをAIに入力し「わかりやすさ」「論理性」などの観点で添削してもらうのもおすすめです。人に頼みにくいときや、短時間で改善したいときに役立ちます。
特に弊社の「らくらく就活」のES添削ツールは、自己PRや志望動機をAIが添削し、改善ポイントを具体的に提示してくれるのが特徴です。自己PR・志望動機に加え、他の11項目にも対応しているため、ES全体を効率よくブラッシュアップできます。添削後は完成した文章をそのままコピペして使えるので、就活の準備をスピーディに進めたい学生にとって非常に心強いサービスです。
受かるESを作りたいけど、自分の文章に自信がない、、
→AIにESを添削してもらいませんか?
自己PR、ガクチカ、志望動機など頑張って作ってみたけど、採用担当者に評価されなきゃ意味がいない。そんな不安に駆られる就活生は多いです。そこで志望企業に提出する前に添削を受けてみませんか?
「ES添削ツール」なら、自分で考えたESをコピペするだけで、AIが自動でESの文章を添削してくれるため、あなたのESを即座に添削・改善することが可能です。
らくらく就活をLINE追加して、簡単なアンケートに答えるだけで無料で使えるので、すぐにESを添削してみましょう!
成功者体験談と失敗談の比較
さらに実践的な方法として「成功した自己PR」と「失敗した自己PR」を比較して学ぶことがあります。
- 成功例:話し始めに結論を伝え、エピソードは簡潔に。最後に入社後の活かし方を述べ、1分でまとめた。面接官から「わかりやすかった」と好印象を得られた。
- 失敗例:エピソードを細かく説明しすぎて2分以上かかり、最後まで話せなかった。面接官から「結局何を言いたいの?」と聞かれてしまった。
この比較を参考にすると、「どの部分を削り、どこを残すべきか」が具体的に見えてきます。自分の自己PRを客観視する訓練として非常に有効です。
よくある質問(FAQ)
自己PRの準備を進めていく中で、多くの学生が同じような悩みを抱えます。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。
1分でまとめられないと不利になる?
結論から言うと、不利になることはありません。ただし、長すぎる自己PRは「要点を絞れない人」という印象を与える可能性があります。面接官は限られた時間の中で多くの学生と話すため、1分程度で簡潔に伝えることが好印象につながりやすいのです。
もし1分に収められない場合は、話す内容を優先順位で整理しましょう。大切なのは「強み」「エピソード」「入社後の活かし方」の3点が伝わること。細部を削っても、この流れさえ押さえれば評価は下がりません。
強みが複数ある場合はどうすればいい?
強みが複数あって迷う学生も多いですが、自己PRでは基本的に「一つに絞る」ことをおすすめします。一つの強みに焦点を当てることで印象が明確になり、面接官の記憶に残りやすくなるからです。
ただし企業によっては「他に強みはありますか?」と追加で聞かれることもあります。その場合に備えて、サブの強みを一つか二つ用意しておくと安心です。メインの強みは一貫して話し、状況に応じて補足できるよう準備しておきましょう。
暗記した文章をそのまま話してもいい?
暗記自体は問題ありませんが、「棒読み」になってしまうと逆効果です。面接官は自然な会話を期待しているため、暗記をそのまま読み上げるように話すと不自然に感じられます。
おすすめは「キーワード暗記」です。全文を覚えるのではなく、「強み→エピソード→成果→活かし方」という流れと、話すキーワードだけを押さえておきましょう。これにより自然な口調を保ちながら、内容のブレを防ぐことができます。
面接で緊張して話せないときの対処法
緊張は誰にでもあるものです。大切なのは、緊張しても最低限の内容を伝えられるよう準備しておくことです。例えば「結論だけは必ず言う」と決めておくだけでも印象は大きく変わります。
また、緊張を和らげる方法として「深呼吸をしてから話し始める」「面接官の目ではなくネクタイや額あたりを見る」などがあります。実際の面接を想定して繰り返し練習することも、自信につながり緊張を和らげる効果があります。
まとめ
自己PRの話し方で大切なのは、「短く・わかりやすく・伝わる」という3つのポイントです。強みをただ述べるだけでなく、具体的なエピソードや成果を示し、それを入社後にどう活かすかまで結びつけることで、面接官に「この学生は活躍できそうだ」と思わせることができます。
そのためには、1分程度で話せるように内容を整理し、PREP法などの構成を活用してまとめることが欠かせません。また、話すスピードや声のトーン、目線や表情といった非言語的な要素も印象を大きく左右します。
さらに、チェックリストを活用した振り返りや、NG例と改善例の比較、録音練習や第三者のフィードバックを取り入れることで、自己PRは確実にブラッシュアップされていきます。エントリーシートでは詳細を、面接では要点をといった使い分けも意識し、一貫性を持って伝えることが評価アップの秘訣です。
面接で緊張するのは自然なことですが、繰り返し練習を積むことで落ち着いて話せるようになります。最終的には、型を守りながらも自分の言葉で話すことが最も大切です。この記事で紹介したタイム配分法やチェックリストを活用し、何度も実践してみてください。
あなたの強みを1分で的確に伝えられる自己PRは、必ず面接官の記憶に残るはずです。