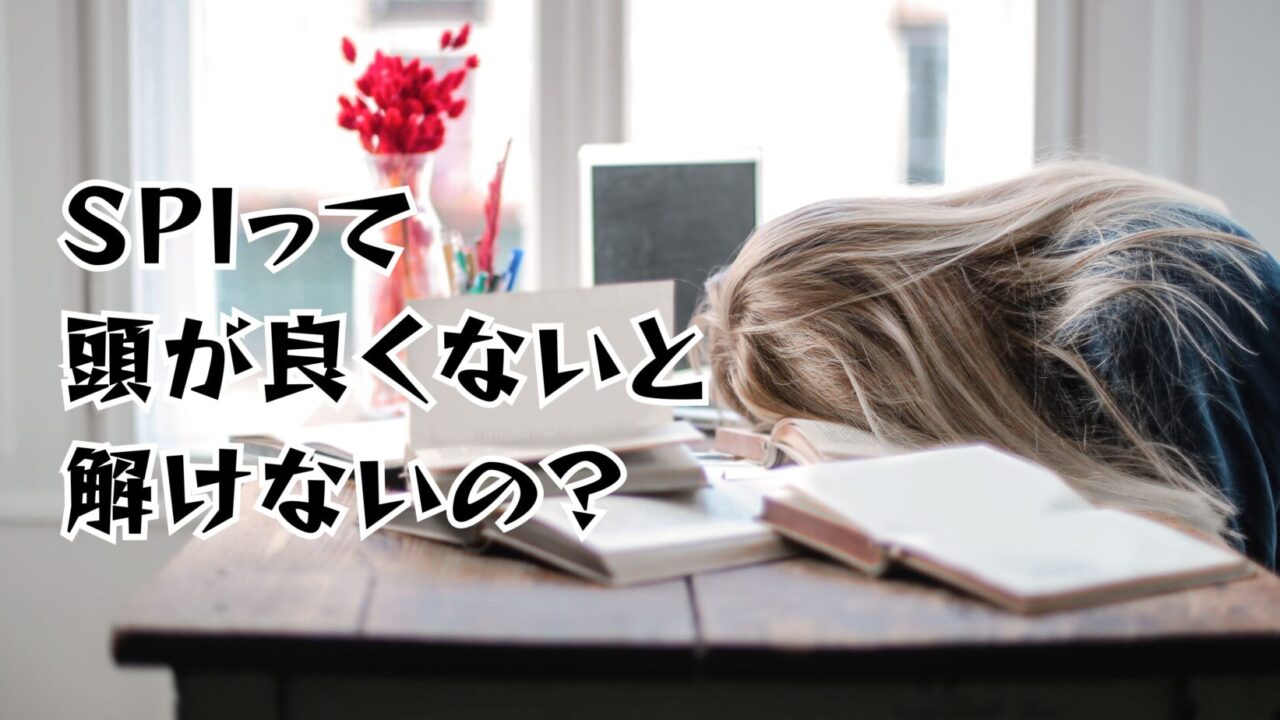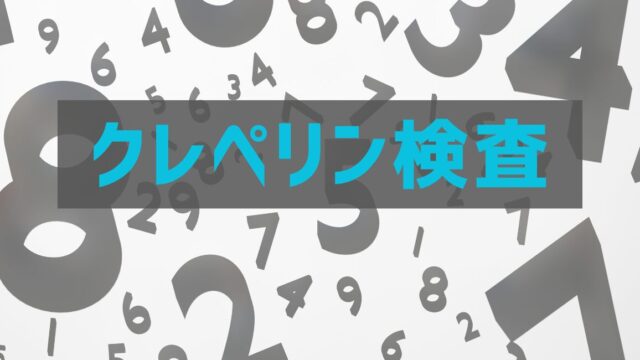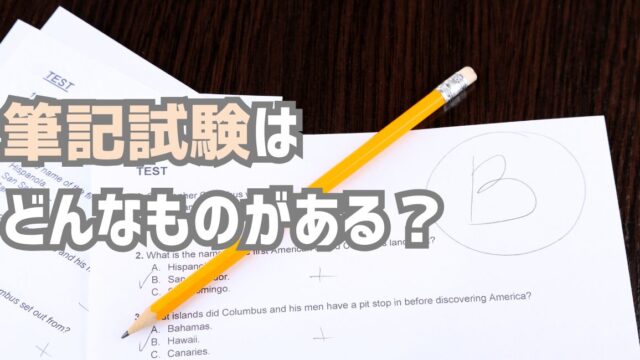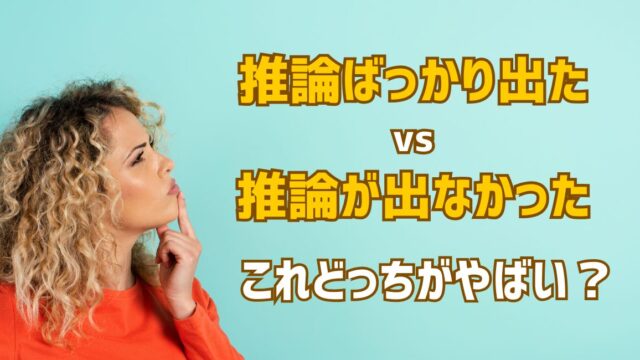【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「SPIって、学力がないと解けないのでは…?」
そんな不安を感じている就活生は少なくないはずです。特に文系学生の中には、「数学が苦手」「高校の内容なんて忘れた」と感じて、SPIの非言語分野を避けたくなる人も多いのではないでしょうか。
ですが、結論から言えば、SPIは学力に自信がなくても対策次第で突破可能です。なぜなら、SPIの出題傾向にはある程度のパターンがあり、「知識の量」よりも「慣れ」や「要領」の方が問われる場面が多いからです。
この記事では、SPIで実際に測られている力や、学力との関係性、またスコアの目安や対策法について、わかりやすく解説していきます。学力に不安があっても大丈夫。この記事を読み終えるころには、SPIに対する見方が少し変わっているかもしれません。
目次
SPIで学力は測られているのか?
SPIって結局、どれくらいの学力が必要なの?と気になる方へ。実際に出る問題の内容とレベルを確認しながら、SPIが測ろうとしている力について見ていきましょう。
SPIはどんな試験?
SPIはリクルートが開発した就職適性検査で、多くの企業で選考の初期段階に使われています。大きく分けると「性格検査」と「能力検査」の2種類があり、今回は主に能力検査の中でも「言語分野」「非言語分野」について取り上げていきます。
非言語分野では、主に以下のような内容が出題されます。
・四則演算(足し算・引き算・掛け算・割り算)
・割合や比、速さなどの計算問題
・表やグラフを見て答える図表問題
・論理的に考える推論問題など
一方、言語分野では、
・語句の意味の理解
・文の並び替え
・文章読解
などが出題されます。
このように、SPIは「数学」や「国語」の延長線上にある試験だといえます。では実際に、どの程度の学力が必要とされているのでしょうか?
SPIは「基礎学力」に近い
SPIは、大学入試や難関資格試験のような“高度な学力”を問う試験ではありません。出題される内容の多くは、中学〜高校入試レベルの基礎学力で十分対応できます。
たとえば、割合の計算や文章の読解は中学の授業で習う内容ですし、図表問題も高校入試に出てくるような内容がベースになっています。もちろん油断は禁物ですが、専門的な数学の公式や難解な読解問題はほとんど出ません。
つまり、「受験勉強が得意だったかどうか」よりも、「中学〜高校の基礎をどれだけ忘れていないか」「初見の問題に対して柔軟に対応できるか」がSPIでは問われているのです。
また、SPIには問題数が多く、時間制限も厳しいため、スピード感や集中力も重要になってきます。学力だけで勝負が決まる試験ではないということを、まずは理解しておきましょう。
出題分野と難易度の目安
SPIでは幅広いジャンルの問題が出題されますが、それぞれの分野がどれくらいの難易度なのか、学力レベルとあわせて見ていきましょう。以下にSPI出題ジャンルと難易度、求められる学力の目安をまとめました。
| 出題分野 | 難易度 | 必要な学力レベル | 備考 |
| 計算(四則演算) | ★☆☆☆☆ | 中学1年程度 | ミス防止が重要 |
| 割合・比・速度 | ★★☆☆☆ | 中学2年程度 | 慣れれば解ける |
| 推論 | ★★★☆☆ | 中学数学+応用力 | 時間配分がカギ |
| 図表読み取り | ★★☆☆☆ | 中学理科・社会レベル | 情報整理力を問う |
| 語句の意味 | ★☆☆☆☆ | 中学国語 | 知識より感覚が重要 |
| 文の並べ替え | ★★☆☆☆ | 高校現代文 | ロジカルさが大事 |
この表からもわかるように、SPIに登場する問題は一見難しそうに見えても、中学〜高校基礎レベルが中心です。たとえば、図表問題では理科や社会の知識そのものよりも「グラフや表の読み取りに慣れているか」が問われますし、語句の意味も日常語に近いものが中心です。
つまり、SPIは“試験”とはいえ、知識の詰め込みではなく、「使える知識」と「解くための慣れ」がものを言うテストだといえるでしょう。
SPIは学力が高い人ほど有利?
「頭のいい人が有利なんじゃ?」と思われがちですが、それだけではありません。学力の高さとSPIのスコアの関係、そして“慣れ”の重要性について解説します。
確かに有利な面もある
当然ながら、学力が高い人は処理スピードや理解力の点で有利な部分があります。たとえば、計算問題においては、基本的な四則演算が瞬時にできる人の方が時間を節約できますし、長文読解にも慣れていれば、読解問題で得点しやすくなります。
また、学力の高い人は、「勉強に慣れている」「時間制限のあるテストに慣れている」といった点でもアドバンテージを持っています。
ですが、それだけではSPIを突破できないのが難しいところです。
ただし「慣れ」がなければ点は取れない
SPIの問題は一見すると簡単そうですが、独特の形式に慣れていないと正解できません。特に非言語分野では、「この情報は使わない」「この問題文のクセはこう解く」といったパターン認識が求められます。
また、SPIは制限時間が厳しいため、いくら学力があっても時間内に解き切れないとスコアにはつながりません。時間配分をどうするか、どこで見切るかといった“戦略”も重要です。
つまり、高学力=高得点というわけではなく、形式に慣れているか、戦略的に解けるかがカギを握っているのです。これは、逆に言えば「学力に自信がない人でも慣れ次第で点が取れる」ということでもあります。
SPIスコアと企業通過の目安
SPIのスコアと企業選考の通過率には、一定の相関関係があります。もちろん選考基準は企業ごとに異なりますが、SPIを一次選考の「足切り」に使う企業も少なくありません。そのため、一定以上のスコアを取っておくことが、エントリーシートや面接へ進むための“前提条件”になる場合もあります。
下記はあくまで概算の目安ですが、実際のSPIスコア帯と企業の選考傾向を整理すると、次のようになります。
| SPIスコア帯(概算) | 通過しやすい企業の傾向 |
|---|---|
| 80~100% | 外資系/大手総合職/商社など |
| 60~79% | 大手メーカー/インフラ系 |
| 40~59% | 中堅・準大手/成長ベンチャー |
| ~39% | 性格検査重視の企業/非SPI型企業 |
80〜100%:外資・総合商社・コンサルなどを狙う層
このスコア帯は、いわゆる最上位層の企業を目指す就活生が求められるレベルです。特に外資系企業・総合商社・コンサル・メガバンクなどでは、SPIを初期のフィルターとして活用し、ある程度の得点水準に達していないと通過が難しい傾向があります。
SPIの高スコアは、企業にとって「情報処理能力」「論理的思考力」の証明とされることもあり、ESや学歴に関係なく足切りされることもあります。選考通過率を高めたいなら、90%以上の得点を目指す意識が必要です。
60〜79%:大手メーカー・インフラ志望者が多いスコア帯
この層は安定志向の大手企業を狙う学生が多く含まれます。具体的には、総合電機メーカー、化学、自動車、エネルギー、鉄道、通信インフラなどが該当します。これらの企業では、SPIスコアはエントリーシートや面接とセットで評価されるケースが一般的です。
60%を超えていれば、最低限の学力・処理能力があると判断され、選考で不利になることは少なくなります。とはいえ、同程度のESや学歴の応募者が並んだ際にSPIの得点が比較材料になることもあるため、できるだけ高得点を目指したいところです。
40〜59%:中堅企業や成長ベンチャーで重視されにくいスコア帯
このスコア帯では、SPIを重視しない企業が増えてきます。たとえば、BtoB中堅企業や急成長中のITベンチャー、人柄重視の営業職採用などでは、SPIよりも志望動機や人物評価を重視するケースが多いです。
SPIで高得点が取れなくても、選考に通過できる可能性は十分にあります。特に自分の言葉で語れる志望動機や、企業研究の深さ、面接時の印象が評価される傾向があります。SPIで苦戦している場合は、面接対策や自己PR強化にシフトするのも有効です。
〜39%:SPIを課さないor性格検査のみの企業も
SPIの得点が40%未満であっても、選考に進める企業は多数あります。たとえば、サービス業・介護福祉・販売職・中小企業・非SPI型選考などでは、SPIをまったく課さなかったり、性格検査のみで判断するケースがよく見られます。
こうした企業では、人柄やコミュニケーション能力、仕事への適性を重視する傾向があるため、SPIの点数が足を引っ張ることはほとんどありません。むしろ、自己分析や職業適性への理解が選考突破の鍵になります。
このように、SPIスコアの高低によって選考の通過率には傾向があるものの、点数だけで就活の勝敗が決まるわけではありません。大切なのは、自分が志望する業界・企業がどのような選考フローを採用しているかを理解し、その企業に合わせた対策を取ることです。
SPIに不安がある方も、「SPIをあまり重視しない企業」や「性格検査中心の企業」を軸に就活を進めることで、戦略的に内定獲得を目指せます。点数に一喜一憂せず、“勝てるフィールド”を見極めることが成功への近道です。
SPIは学力以外に何が評価される?
SPIでは学力以外の部分、つまり“人となり”も評価対象になります。どんな力が見られているのか、性格検査や対応力のポイントを紹介します。
性格検査で見られる非認知スキル
SPIの中でもう一つ重要なのが、「性格検査」です。これは、いわゆるIQや学力ではなく、協調性・誠実性・安定性といった人間性の面を見るものです。
性格検査は嘘をつかずに答えることが基本ですが、企業によっては特定の傾向(例えばリーダーシップや柔軟性)を評価する場合もあります。つまり、SPIでは単なる知識だけでなく、職場でのふるまいや考え方も見られているのです。
また、性格検査の結果は、選考後半や配属決定にも影響することがあります。学力に自信がない人でも、この部分で高評価を得ることで、全体の印象を良くすることもできるのです。
応用力・スピード・注意力も問われる
SPIの問題は、ただ知っているかどうかだけでなく、「初見の問題にどう対応するか」「ミスなく速く解けるか」といった実践的な力が求められます。
特に推論問題や図表問題では、情報を素早く整理し、必要なデータを読み取り、適切に判断する力が問われます。これは単なる“お勉強”ではなく、実務にも直結する力として多くの企業が注目しています。
言い換えれば、SPIは“机上の知識”だけで戦うものではなく、日頃から考える力や注意力を意識している人が有利になる試験なのです。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPIと大学の授業のつながり
「SPIって、高校までの内容で勝負するんでしょ?大学の授業って関係ないよね」
こんなふうに思っている方も多いかもしれません。確かにSPIの多くの問題は中学〜高校の基礎学力をベースにしています。しかし、大学での学びも意外とSPI対策に役立っていることに気づいていない人も少なくありません。
以下は、大学の主要な授業とSPIの出題分野との対応例です。
| 大学の授業 | SPIで活かされる力 |
|---|---|
| 統計学 | 図表問題、グラフ読み取り |
| 数学・論理学 | 非言語分野(推論・集合・数列など) |
| 国語表現・現代文 | 読解力、文整序問題、語句の用法 |
統計学は図表問題の基礎に直結する
統計学の授業では、「平均」「中央値」「割合」「分布」といった概念を扱います。これはSPIの図表問題やグラフ読み取りにそのまま活かされる内容です。
たとえば、「ある店舗の売上データを読み取る」「複数のグラフを比較する」「表から条件に合った数値を見つける」といったSPI問題は、統計的な視点と数的処理力が問われます。大学でレポートやデータ分析を経験していれば、自然と情報の取捨選択に慣れているため、SPIでも有利に働きます。
数学・論理学で養った思考力が推論に効く
大学での数学や論理学の授業では、計算だけでなく「いかに筋道を立てて考えるか」が重視されます。これらの思考力は、SPIの非言語分野、特に推論問題や集合問題、順列・組合せ、数列などで必要とされる能力と直結しています。
たとえば、「AさんはBさんよりも先に出発した」「BさんはCさんより遅い」などの条件整理が求められる問題では、論理的に矛盾のない順序で思考を積み上げるスキルがカギになります。論理学で鍛えた「前提から結論を導く」力は、まさにこの場面で活きるのです。
国語表現・レポート作成が言語分野に活きる
一方、SPIの言語分野では、文の並べ替え問題や語句の意味、読解問題などが出題されます。大学でのレポート作成や国語表現の授業では、「正確な語句選び」「論理の通った文章構成」「要点を捉える読解力」が求められるため、自然とSPIに必要な力が身につきます。
特に文の整序問題では、「起→承→転→結」の文章構成や、指示語・接続詞の使い方への理解が求められます。これは、レポートでの論理的な段落構成とほぼ同じ考え方です。
このように見ていくと、SPIは“受験の延長”というよりも、大学での日常的な学びや思考の訓練がそのまま問われている試験とも言えます。もし大学での授業を「単位のためだけ」に受けていたとしても、そこで身についた基礎的な力は確実にSPI対策に役立っています。
自信を持って、日々の学びを“SPI対策の一部”として捉えてみてください。それだけでも、これからの勉強のモチベーションが変わってくるはずです。”につながります。大学での学びがSPIに役立つ場面は、実は想像以上に多いのです。
学力に不安がある人でもSPIを突破できる理由
「自分には無理かも…」と不安に思っている方も、対策次第でSPIは十分突破できます。その理由と、実際に突破した就活生の声を紹介します。
SPIはパターンと慣れで解ける試験
SPIは、毎年出題される内容にある程度のパターンがあります。たとえば、割合の問題やグラフ読み取り、推論問題などは頻出ジャンルとして知られており、それに対して対策をすれば、確実に点が取れるようになります。
さらに、時間制限の中で解くためには、「形式に慣れていること」が何より大切です。出題傾向を理解し、パターンに沿って反応できるようになれば、学力に関係なく得点力は大きく伸びます。
リアルな就活生の声(体験談)
実際にSPIを受けた就活生のリアルな声を紹介します。
Aさん(文系/私大)
「高校数学は赤点ばかりで、SPIは絶対無理だと思っていました。でも、‘割合’と‘図表’に絞って毎日練習したら、普通に通過できました!」
Bさん(理系/国公立)
「理系で数学は得意だから余裕だと思ってたら、SPIの形式に慣れてなくて時間が足りず…。模擬試験で対策する大切さを痛感しました」
このように、学力の高さだけでは測れないのがSPIです。形式に慣れた人の方が、むしろ有利になることすらあります。
学力に不安がある人のためのSPI対策法
ここでは、学力に自信がない人でも実践できる具体的なSPI対策法を紹介します。パターンを押さえて、無理なく得点を伸ばしましょう。
基本パターンを反復しよう
まずは、頻出ジャンルを押さえることが最優先です。非言語では計算・割合・推論、言語では語彙・文整序・読解といった部分が重点になります。
これらは一度しっかりパターンを身につけてしまえば、あとは反復で精度を高めていくだけで得点につながります。「わからない問題を解く」のではなく、「慣れた問題を素早く解く」ことを目指しましょう。
初心者向けおすすめ参考書・アプリ
SPI対策の王道として、多くの学生が利用しているのが『これが本当のSPI3だ!』シリーズです。問題の解説が丁寧で、初心者でも取り組みやすい一冊です。
また、スキマ時間に活用できるスマホアプリは、らくらく就活の「SPI早押しクイズ」がおすすめです。LINE上で解けるので、アプリをわざわざ入れる必要がなく、気軽に取り組めるのが魅力です。楽しみながら問題形式に慣れることができます。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
1日15分でも続けるコツ
「毎日たくさん勉強しなきゃ…」と気負わず、まずは1日1問からでもOKです。寝る前や通学中など、スキマ時間を使って解くだけでも、確実に慣れていきます。
重要なのは、“継続して触れること”です。問題形式に慣れるだけで、焦らずスムーズに問題を処理できるようになります。
まとめ
SPIは学力だけでなく、「思考力」「慣れ」「パターン対応力」がカギになる試験です。
高学力でも形式に慣れていなければ得点できませんし、逆に学力に不安があってもパターンをつかめば突破できます。
不安な人ほど、まずは「できる問題」から自信をつけていきましょう。少しずつ慣れていけば、SPIは必ず突破できるテストです。
焦らず、じっくりと取り組んで、自分に合った方法でSPIを乗り越えていきましょう。