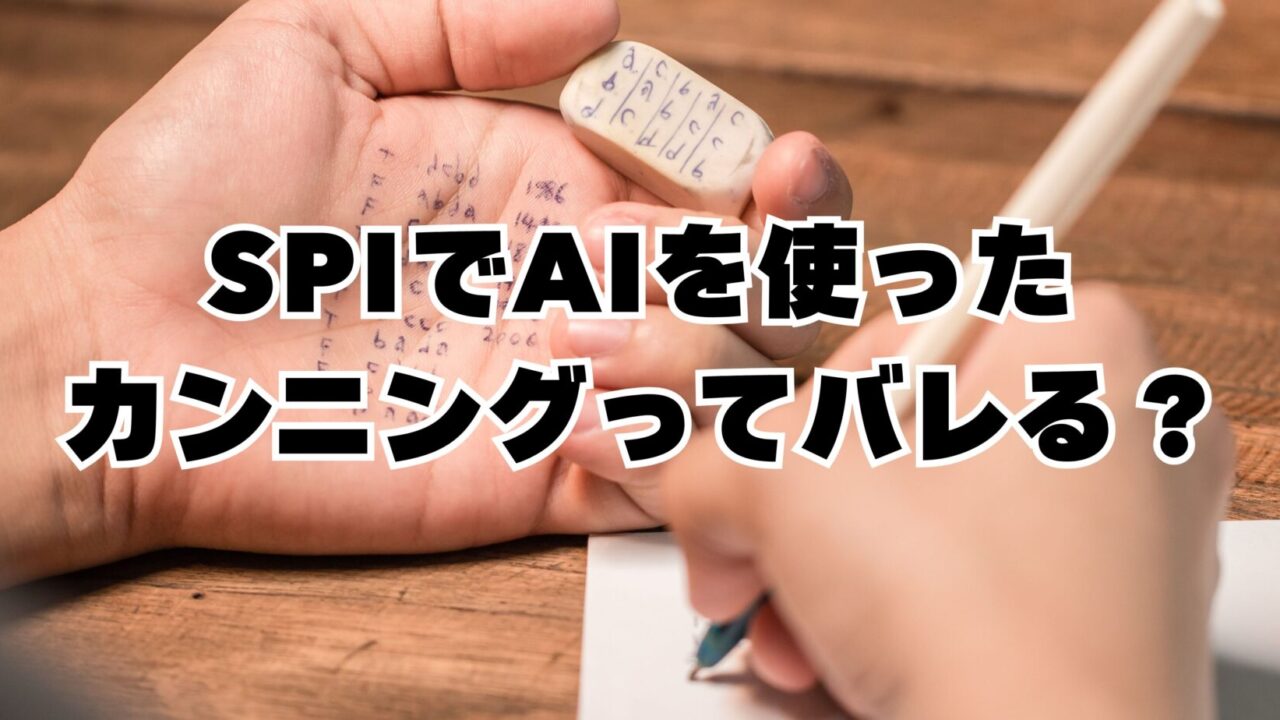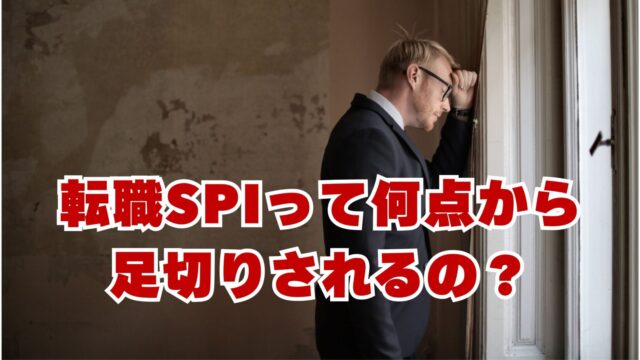【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
WebテストやSPI対策をしている就活生の間で、近年ひそかに話題になっているのが「AIを使ったカンニング」です。特にChatGPTなどの生成AIの登場により、「試験中に答えを聞けば簡単に突破できるのでは?」という声も聞かれるようになりました。SNSや就活掲示板でも「使ってみた」「バレた」「通過できた」などさまざまな体験談が投稿され、カンニングのハードルが下がったように見えるかもしれません。
しかし、企業側もAIの進化に伴って監視体制を強化しており、「バレなければOK」といえるほど甘くはありません。たとえその場を切り抜けたとしても、その後の面接や入社後の評価でギャップが露呈すれば、取り返しのつかない事態にもなりかねません。
この記事では、「SPIでのAIカンニングは本当に可能なのか」「バレるとどうなるのか」「リスクを避けて通過するにはどうしたらいいのか」などを、実際の就活生の声や企業の対策状況も交えて、わかりやすく解説していきます。就活生として知っておきたいSPIカンニングのリアルを、ぜひチェックしてください。
目次
SPIやWebテストでのAIカンニングは可能?
AIを活用してSPIやWebテストのカンニングはできるのか、具体的な手法や実際の事例、企業側の対策状況について解説します。
ChatGPTなどのAIを使ったカンニングとは?
ChatGPTのような生成AIは、問題を入力すれば即座に解答を提示してくれるため、「SPIやWebテストでも使えるのでは?」と考える人が出てきています。実際に行われている手口としては、大きく2つに分かれます。
1つは、試験中に問題文をそのままAIに入力し、回答をリアルタイムで得るという方法です。この方法では、時間との勝負になりますが、正確に聞ければ正答率はある程度高くなります。特に言語分野の問題であれば、AIの得意領域でもあるため、高得点を狙いやすいと思われがちです。
もう1つは、事前に問題をスクリーンショットで保存しておき、AIに解析してもらうというやり方です。これにより、傾向をつかんで模擬的に対策を立てるという使い方もあります。表面上は「カンニング」とは言い切れませんが、限りなく黒に近いグレーゾーンの方法といえるでしょう。
ただし、どちらの方法も試験の受け方や企業の監視体制によってはすぐにバレてしまうリスクがある点に注意が必要です。
実際にAIでSPIをカンニングした就活生の声も?
SNSや就活掲示板では、AIを活用してSPIを受験したという体験談が散見されます。例えば、X(旧Twitter)や5chなどでは「ChatGPTでSPIを突破できた!」「無事にWebテストを通過して、面接の案内が来た!」といった成功体験が投稿されていることもあります。
しかし、その一方で「途中でバレて強制終了にされてしまった…」「その後の面接でSPIとレベルが合っていないと突っ込まれた…」という失敗談も見受けられます。実際に、成功例とバレた例を比較すると以下のような傾向があります。
成功しているケースでは、監視のない自己受験形式のWebテストで、問題の難易度がそれほど高くなかったことが多く、AIで解ける範囲内だったという特徴があります。一方、バレた例では、試験中にタブを切り替えすぎたり、正答率が高すぎて逆に不自然だったりと、AIの利用が推測できるような挙動をしていた点が共通しています。
「バレなければ使ってもいい」と考えるかもしれませんが、企業はそのような不正行為を見逃してくれるわけではありません。
企業側はカンニング対策をしているのか?
カンニングのリスクを防ぐため、企業側もさまざまな対策を講じています。最近では、AIや人による監視が導入されているケースが増えており、以前よりも不正を見抜く精度が上がってきています。
たとえば、顔認証や視線検知、音声検出などを使ったAI監視システムを導入している企業では、試験中に視線が大きく動いたり、何かを話していたりすると、それだけで不審行為としてフラグが立つ仕組みがあります。中には、試験中の映像を録画して後で人が確認するケースもあり、後日バレるというパターンも存在します。
さらに、回答内容やタイピングのスピード、正答率のバランスなどから不正を検出するアルゴリズムも存在しており、実力とはかけ離れた回答をしていると判定されることもあります。こうした対策が進んでいる今、AIを使ったカンニングはかえってリスクを高める行為になりつつあるのです。
SPIでのカンニングは本当にバレるのか?
SPIでのカンニングがどのような状況でバレるのか、監視方法ごとの違いやバレやすい行動パターンを紹介します。
監視タイプ別のバレやすさ
SPIやWebテストでのカンニングがバレるかどうかは、主に「どのような監視が行われているか」によって大きく左右されます。ここでは代表的な3つの監視タイプごとに、カンニングのバレやすさを見ていきましょう。
監視なし(自己受験)
もっとも油断しがちなのが、この「完全な自己受験タイプ」です。多くの就活生が「誰にも見られていないならバレないだろう」と思いがちですが、実はシステム側で不正行為を検出する仕組みが導入されているケースもあります。
特に不自然な回答スピードや、試験中のタブ切り替えなどはログとして残されており、企業側が後からチェックすることが可能です。また、明らかに高得点を取っていても、その後の面接で一貫性のない回答をしてしまうと、「あのスコアはおかしいな」と疑念を持たれるきっかけになります。
AI監視(顔・視線・音声検知など)
近年増えているのが、AIによるオンライン監視です。試験中はカメラとマイクをオンにする必要があり、視線の動きや顔の向き、キーボードのタイピング音などを常にチェックされています。たとえば、頻繁に画面の外に視線が向いたり、誰かと会話しているような口の動きが検出されると、「不正の可能性あり」とフラグが立つことがあります。
これらのデータはAIが自動的に判定するだけでなく、後から人が再確認することもあるため、カンニングがバレる確率は格段に高まります。
有人監視(試験官が常時監視)
もっとも厳しいのが、試験官がリアルタイムで監視している形式です。企業によっては、Zoomや専用の試験ツールを使って、1対1、あるいは少人数単位で試験を実施するケースがあります。
この場合、試験中に何か怪しい動きがあれば即座に注意される可能性があり、不正が発覚した場合はその場で試験が終了することもあります。AIよりも判断が柔軟で、ちょっとした挙動でも疑われるリスクがあるため、最もハイリスクな環境といえるでしょう。
バレる5つの典型的なパターン
では、実際にカンニングがどのような状況でバレやすいのか、代表的なパターンを紹介します。
回答スピードが不自然
極端に早く、かつ正確な回答が続くと、企業側は「あまりにも出来すぎている」と疑念を持ちます。特に普段の成績や面接内容と整合性が取れない場合、すぐに矛盾が浮き彫りになります。
正答率が極端に高すぎる
SPIの難問を連続で正答していると、「本当にこの人が解いたのか?」という疑問が湧きます。企業によっては模試的な問題やフェイク問題を混ぜていることもあり、そこに完璧な正答をしてしまうと逆に怪しまれる要因になります。
タブの切り替えが頻繁に起きる
テスト中にブラウザのタブを頻繁に切り替えると、ログにその回数が記録されます。これにより「外部サイトを参照していた可能性が高い」と判断され、要注意対象になるケースがあります。
回答に一貫性がない
SPIでは思考の筋道や論理性も問われます。AIに頼った結果、答えには正解しているのに途中のステップや説明がちぐはぐになってしまうと、明らかに自分で考えていないことが見抜かれやすくなります。
面接で答えられずに疑われる
SPIで高得点を取っても、面接で基本的な問題に答えられなかったり、論理的な説明ができないと「実力ではないのでは」と疑われてしまいます。SPIと面接は一貫性が重視されるため、ここで破綻すると信頼を失うきっかけになります。
SPIカンニングがバレたときのリスク
SPIカンニングが発覚した場合の就活への影響や、内定後・入社後に起こりうるリスク、さらには法的・倫理的な問題について整理します。
選考への影響
まず最も直接的な影響として挙げられるのが「その企業の選考に落ちる」ことです。SPIやWebテストで不正が発覚した場合、多くの企業では不合格扱いとなり、場合によっては選考自体から除外されてしまいます。
また、一度不正のフラグが立つと、企業内で「この学生は要注意」とマークされる可能性もあります。たとえ最終的にバレなかったとしても、不審な挙動が残っていれば、面接や適性検査などでも厳しく見られることになるかもしれません。
さらに、SPIを外部委託している企業では、テスト提供元のシステムに不正履歴が記録される場合もあります。これが他の企業の選考にも波及するケースもゼロではありません。「1社だけなら…」という軽い気持ちが、複数の企業に影響を与えることもあるのです。
内定後・入社後の影響
仮にSPIカンニングがバレずに内定をもらえたとしても、入社後に「なんか違う」と思われるリスクは極めて高くなります。SPIは単なる足切りではなく、ある程度の基礎学力や論理的思考力、職種との適性を見極めるための指標でもあります。
そのため、SPIで高得点だったはずの人が、入社後に期待されたパフォーマンスを発揮できないと「おかしい」と気づかれます。特に数字を扱う部署や論理的思考が求められる職種では、SPIの結果とのギャップがはっきりと現れてしまいます。
最悪の場合、研修中や試用期間中に「能力不足」と判断され、早期退職につながることもあります。せっかく勝ち取った内定が水の泡になるだけでなく、「不誠実な人材」という印象まで残してしまう可能性も否定できません。
企業間で不正情報が共有される可能性も?
実は、学生が考える以上に企業間での情報連携は進んでいます。特に「スカウト型就活サービス」や「適性検査を提供するベンダー」などの第三者を経由する場合、受験ログや挙動の記録が蓄積されているケースがあります。
また、企業同士が連携しているケースでは、不正が発覚した学生についての情報が間接的に共有される可能性も否定できません。公にはされていなくても、「過去にこの学生は不正の疑いがある」といった評価が人事内で引き継がれてしまえば、他の選考にも影響が出てしまうでしょう。
現時点で「完全にブラックリスト化される」とまではいえないものの、リスクはゼロではありません。「どうせ他社にはバレない」と思って行った行為が、後から自分の首を絞めることになりかねません。
法的リスクや倫理的問題もある?
SPIやWebテストにおけるAIカンニングは、法的にもグレー、あるいはアウトとみなされる可能性があります。たとえば、企業によってはテスト受験時に「本人が正しく受験すること」を明記しており、それに反する行為は「虚偽申告」として法的トラブルに発展するリスクもあります。
さらに、就活という場は、学生と企業が「誠実な姿勢」で向き合う前提のもとに成り立っています。そこに不正が介在することで、学生側の信用が大きく損なわれてしまいます。たとえ一時的に内定が得られても、その後ずっと「本当にこれで良かったのか」と不安や後悔がつきまとうことも少なくありません。
倫理的な観点から見ても、「みんなやってるから」「バレなければいい」では済まされないのが就活です。社会人としての第一歩を踏み出す場面で、いきなり不正行為から始めることの重大さを改めて認識する必要があります。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
AIに頼らずSPI対策をする方法
カンニングに頼らず、自分の力でSPIを突破するための学習方法やおすすめの参考書・ツールを紹介します。
実力でSPIに通過するメリット
カンニングに頼らず、正攻法でSPIに取り組むことで得られるメリットは想像以上に大きいものです。まず一つは、「面接での一貫性」が確保できるという点です。SPIはあくまでも選考の一部であり、その後の面接で試験の結果と人柄、受け答えの整合性をチェックする企業がほとんどです。
たとえば、論理性が求められる非言語分野で高得点を出したのに、面接では論点がずれた回答ばかりしていると、「この人は本当に自分で解いたのか?」と疑念を持たれます。実力で通過していれば、SPIと面接とのギャップがなくなり、自信を持って面接に臨むことができます。
もう一つのメリットは、「入社後も安心して働ける」という点です。SPIの結果は、配属先や適性判断の参考資料として用いられることもあります。自分の力で突破していれば、配属先でもスムーズに業務をこなせる可能性が高まり、上司や同僚からの信頼にもつながります。
短期的に見ればAIを使ったほうがラクに見えるかもしれませんが、長期的に見ると「自分の力で突破した」ことは、内定後の安心感や社会人としての自信にも大きく影響します。
効率よく学ぶSPI対策法
SPI対策と聞くと、「問題が多すぎて何から手をつけていいかわからない」と感じる人もいるかもしれません。しかし、SPIは出題傾向が明確であるため、正しい手順で学習を進めれば、効率的にスコアを伸ばすことが可能です。
まずは頻出問題に集中することが大切です。非言語では「割合」「確率」「表の読み取り」など、言語では「語彙」「二語の関係」「空欄補充」など、定番問題を繰り返し解くことで、問題の型に慣れていくことができます。
次に意識したいのは「時間」です。SPIは時間制限があるため、正確に解けるだけでなく、速く解く力も求められます。模試形式の問題集やアプリを使って、制限時間内に解く練習を重ねていくことで、本番の焦りを軽減できます。
また、自分の思考のクセやミスの傾向を把握することも重要です。たとえば、「つい暗算で済ませてミスが多い」「問題文を読み飛ばしてしまう」など、自分なりのミスパターンを振り返ることで、次に活かすことができます。
おすすめのSPI対策書・ツール
実力でSPIを突破するためには、信頼できる教材やツールを活用することが近道です。ここでは、就活生からの評価も高い代表的な対策書やツールをいくつか紹介します。
まず定番中の定番として挙げられるのが『これが本当のSPI3だ!』(著:SPIノートの会)です。非言語・言語ともに網羅されており、解説も丁寧で、初学者にも使いやすい一冊です。多くの就活生がこの本から対策を始めています。
次に『SPIスーパードリル』もおすすめです。こちらは演習量が豊富で、「とにかく問題をこなして慣れたい」という人にぴったりです。問題→答え→解説の流れがスムーズで、短時間でも効果的な学習ができます。
さらに、Webアプリを活用する方法もあります。もちろん、おすすめは弊社のSPI対策ツールです。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
実際にChatGPTを使ってSPIの問題を解いてみた
実際にらくらく就活のNAGAがChatGPTを使って、SPIの問題に挑戦してみます!
英語
英英辞典
問題:次の説明文と意味が最も近い単語を選択肢より選びなさい。
disagreement or a lack of friendship among people who have different opinions about something
①diversity ②friction ③distress ④discrimination ⑤concern
ChatGPTの回答:②friction
正解:②friction
結果:〇
空欄補充
問題:文中の( )に入れる語として最も適切な選択肢を1つ選びなさい。
あなたのおかげで、私は今日楽しむことができました。
Thanks ( ) you, I was able to enjoy myself today.
①to ②above ③from ④with ⑤of
ChatGPTの回答:①to
正解:①to
結果:〇
言語
語句の意味
問題:次の意味の言葉を1つ選びなさい。
広く全体を見渡すこと
①洞察 ②刮目 ③座視 ④大観 ⑤静観
ChatGPTの回答:④大観
正解:④大観
結果:〇
二語関係
問題:上の二語の関係を読み取り、下の二語も同じ関係になるように( )に入る語を選びなさい。
百科事典:紙
日本酒:( )
①米 ②飲料 ③酔っ払い ④徳利 ⑤ウイスキー
ChatGPTの回答:①米
正解:①米
結果:〇
非言語
割合と比
問題:ある作業の60%を終了した段階で当初の60%にあたる作業が追加された。終了した仕事は与えられた仕事の何%か。(小数第2位以下は四捨五入する)
①33.3 ②41.3 ③52.5 ④24.8 ⑤いずれでもない
ChatGPTの回答:⑤いずれでもない
正解:⑤いずれでもない
結果:〇
確率
問題:AとBが4回じゃんけんをする。2人ともグー・チョキ・パーを全て1/3の確率で出すと考え、あいこも1回と数える時、Aが少なくとも1回は負ける確率はどれか。
①65/81 ②17/27 ③19/27 ④いずれでもない ⑤49/81
ChatGPTの回答:①65/81
正解:①65/81
結果:〇
実際にChatGPTで問題を解いてみて感じたこと
ChatGPTなどのAIツールに複雑な問題を解いてもらおうとすると、PCのスペックによってはかなり時間がかかりますが、SPIなどの簡単な問題を解いてもらう分にはほぼ一瞬で答えを出してくれます。
またプロンプトで指定をすれば、答えまでの解説を省いて回答だけを出力してくれるので、何も考えずに解き進めてしまうと、回答スピードを疑われるのも必然でしょう。
さらにPCでChatGPTを使用する際には、タブやウィンドウの移動は必然となり、スマホで操作する場合も目線の移動は避けられません。
しかし、これらの監視がないWebテストでは、適度に回答スピードを遅らせて、所々でわざと誤答を挟めば、回答者がAIツールを使っていることを見抜くのは難しいと感じました。
ただし、使用は自己責任とかではなく厳禁です!
前述した「カンニングがバレた時のリスク」や、次で解説する「カンニングをしない方が良い理由」を読んで、ぜひ自分の力で立ち向かってもらいたいと思います。
SPIカンニングが「やめとけ」と言われる3つの理由
なぜSPIカンニングはやめたほうがいいのか、就活生が後悔しやすい理由を3つの視点から解説します。
理由①:バレるリスクが高すぎる
AIを使ったSPIカンニングは、「やれば必ずバレる」というわけではありません。しかし、さまざまなリスクを考えると、「かなり高い確率でバレる」といっても過言ではありません。先ほど紹介したように、企業はAI監視や有人監視、不正検出アルゴリズムなど多層的な対策を講じています。
特にChatGPTをはじめとする生成AIは、SPIの一部の問題には対応できても、すべてのジャンルに万能とは限りません。また、解答中にブラウザの切り替えや口の動き、カメラ外への視線などの「人間の不審な挙動」は、システムにも試験官にも簡単に見抜かれてしまいます。
つまり、AIに頼ってテストを受けることは、企業の目から見ると「わかりやすい不正行為」になりがちなのです。一見うまくいったように見えても、受験データに不審な動きが記録されていれば、後から選考中止になるケースもあります。バレた瞬間のダメージは非常に大きく、信用回復も困難です。
理由②:面接・入社後でミスマッチが起きる
たとえAIカンニングでSPIを突破できたとしても、その後の選考や入社後に大きなギャップが待っています。SPIのスコアは、その人の適性や基礎能力を表すものであり、企業はその情報をもとに面接の質問や配属の判断を行います。
たとえば、非言語で高得点を取った学生には、論理的思考力が高いと判断され、コンサル系や企画系のポジションを提案されるかもしれません。しかし、実際にはAIに解いてもらっただけで、本人にその能力がなかった場合、入社後にその職務についていけず、評価が下がるどころか退職を余儀なくされることもあります。
また、SPIと面接の整合性が取れていないと、「この学生は信用できない」という印象を与えます。一度不信感を持たれると、その後のやりとり全体に疑いの目が向けられ、素直に自分を出すことができなくなってしまいます。
理由③:後悔と不安が残りやすい
AIを使ってSPIをカンニングしたとしても、それが成功だったか失敗だったかにかかわらず、心の中には「不安」や「後悔」が残るケースが非常に多いです。
たとえば、「もしバレたらどうしよう」という不安を抱えながら受ける面接は、余計な緊張や焦りを生み、本来の自分らしさを出せなくなります。また、「本当はあの企業に自分の実力で受かりたかった」という思いが、内定後に重くのしかかってくることもあるのです。
さらに、AIカンニングを一度経験してしまうと、「また次も使ってしまおう」と依存しやすくなる傾向があります。そうなれば、自分の力で乗り越える力が育たず、社会人としての自信や成長の機会を逃してしまうかもしれません。
就活は、人生の中でも数少ない「自分と向き合うチャンス」です。そこを不正で乗り切ってしまうと、「この結果に意味はあるのか?」というモヤモヤが残り続けます。
まとめ
AIによるSPIカンニングは、「バレないなら得だ」と考えられがちですが、実際には多くの就活生がそのリスクと代償に悩まされています。企業側も高度な監視技術を導入し、さまざまな角度から不正を見抜こうとしています。
もし運よくバレなかったとしても、面接や入社後のミスマッチ、企業との信頼関係の破綻など、思わぬところで自分に返ってくることもあります。そしてなにより、自分自身が納得できる就活ができなくなるというのは、大きな損失です。
AIや裏技に頼らず、自分の力でSPIを突破することは、面接や入社後にもつながる自信になります。遠回りに見えるかもしれませんが、正しい努力が、最終的に納得のいく結果をもたらすはずです。
あなたの就活が、誠実で実りあるものになることを願っています。