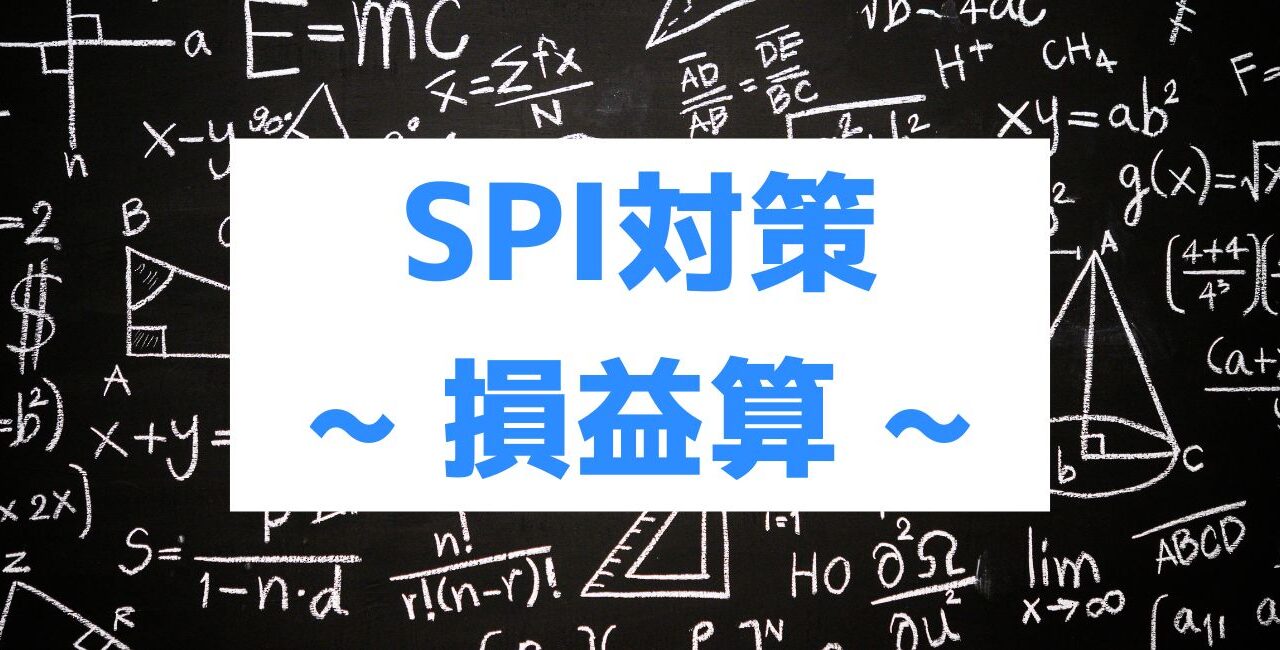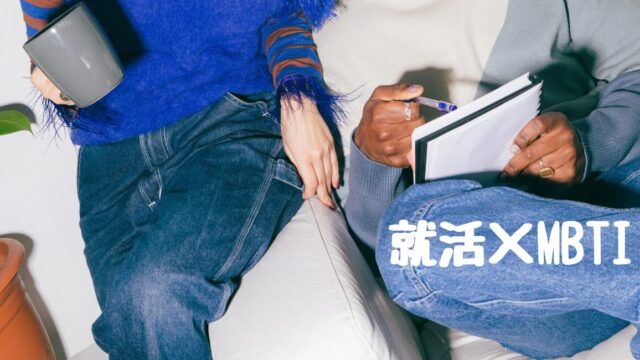【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
就活で避けて通れないのがSPIですが、中でも非言語の損益算に苦手意識を持つ学生も少なくありません。商売やお金の計算に関する問題と聞くと、ちょっと身構えてしまう人も多いのではないでしょうか。
ですが、実は損益算はパターンさえ覚えてしまえば、得点しやすいジャンルのひとつです。利益や原価、売価の関係をきちんと理解し、計算の流れを整理できれば、どんな問題にも対応できるようになります。
この記事では、SPIに出題される損益算の仕組みや出題パターン、解き方のコツから練習問題までを丁寧に解説します。SPI対策のスタートとしても、直前の復習としても活用できる内容になっているので、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
損益算とは
SPIの中でも、損益算は「お金の流れ」に関する計算を問う分野です。主に、商品の仕入れ(原価)と販売価格(売価)、そしてそこから得られる利益の関係性をもとに、さまざまな数値を計算していく問題が出題されます。
この損益算は、数字の扱いに慣れていないとやや複雑に感じるかもしれませんが、基本となる公式と考え方をおさえれば、実はパターンが決まっているため得点源にしやすい分野です。
まずおさえておきたい基本用語は次の3つです。
- 原価:商品を仕入れるのにかかった費用
- 売価(定価):お客さんに販売する価格
- 利益:売価から原価を引いた差額
この3つの関係性を図で示すと、以下のようになります。
- 売価=原価+利益
- 利益=売価−原価
- 原価=売価−利益
つまり、どれか2つの数値がわかっていれば、残り1つも計算できるという関係です。問題文を正しく読み取り、どの数値が与えられていて、どれを求めるのかを整理することが第一歩です。
また、損益算では「利益率」や「割引」といった要素も頻繁に登場します。これらも基本的には上の関係式から派生しているもので、やり方さえつかめば難しくありません。
SPIでは、就活生の数的処理能力や論理的思考力を測るために、このような現実的なビジネスシーンを想定した計算問題が出題されます。最初は難しく感じても、数をこなして慣れていけば、自然と速く正確に解けるようになりますよ。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
損益算の出題形式
SPIにおける損益算の出題は、大きく3つのパターンに分類されます。それぞれに特徴があり、問われる力も異なります。ここでは各出題形式と、実際の例題を交えて解説します。
定価・原価・利益率を用いた計算問題
最も基本的な損益算の問題パターンです。原価に対して何%の利益を上乗せして売ったか、あるいは利益率から定価を求めるといった問題が出されます。
ここで重要になるのが、「利益率=利益÷原価×100」という考え方です。売価に対してではなく、原価を基準にして利益がどれくらいかを見るのがポイントです。
例題
ある商品を原価300円で仕入れ、40%の利益を見込んで販売しました。このときの売価はいくらですか?
【解き方】
・原価:300円
・利益率:40%→0.4
→利益=原価×利益率=300×0.4=120円
→売価=原価+利益=300+120=420円
このように、まずは利益を計算してから、売価を求めるという順番が基本です。慣れてくれば暗算でも対応できるようになります。
割引後の利益を求める問題
次に、商品を割引して販売する場合の損益を問う問題があります。
このパターンでは、いったん定価(売価)を設定したあと、割引価格に基づいた利益や利益率を計算する必要があります。
「割引されたことで利益がどう変わるのか」を読み取る力が試されます。
例題
ある商品を原価600円で仕入れ、定価800円で売る予定でしたが、20%引きで販売しました。このときの利益はいくらですか?
【解き方】
・定価:800円
・割引率:20%→0.2
→実際の売価=定価×(1−割引率)=800×0.8=640円
→利益=売価−原価=640−600=40円
このように、まずは割引後の売価を出してから利益を計算するという流れになります。
複数商品を扱う損益の合計計算
少し応用的な出題として、複数の商品を扱い、それぞれの損益から全体の利益を求める問題も出題されます。
このタイプの問題では、1つずつ冷静に整理していく力が求められます。
例題
ある店で、A商品を5個(原価200円、売価300円)、B商品を3個(原価400円、売価450円)販売しました。全体の利益はいくらですか?
【解き方】
・A商品:利益=300−200=100円→100×5=500円
・B商品:利益=450−400=50円→50×3=150円
→合計利益=500+150=650円
商品ごとに利益を出し、それを個数でかけて合計するのがポイントです。
このように、SPIの損益算にはいくつかのパターンがありますが、基本の考え方はすべて「利益=売価−原価」に集約されます。
損益算を解く時のコツ
損益算の問題は、内容が複雑に感じられても、実は決まった考え方と手順で解くことができます。ここでは、SPIの損益算を効率よく、かつ正確に解くためのコツを2つ紹介します。
基本は「利益=売価−原価」で組み立てる
損益算において、最も重要な基本式は以下の通りです。
利益=売価−原価
どんなに問題がややこしく感じても、最終的にはこの式に落とし込むことができます。問題文で与えられている情報が「定価」「割引価格」「利益率」などだったとしても、最終的には原価と売価の関係に帰着させることが解決の鍵になります。
たとえば、「定価から30%引きで販売し、10%の利益が出た」などの問題では、まず割引後の売価を求め、そこから利益の計算に入ります。慣れてくると、問題文を読んだ時点で「まず売価を出して、次に原価か利益を計算するな」と見通しを立てることができるようになります。
問題文が長くても、情報を整理し、「この式に当てはめるには何が必要か?」と逆算的に考えるクセをつけると、迷わずに解けるようになります。
%表示はすべて数字(小数・分数)で整理
損益算でよく出てくる「〇〇%」という表現。これをそのまま文の中で見ていると、頭の中で処理しにくくなってしまいます。そこで大切なのが、%は必ず小数(または分数)に直すという習慣です。
- 10%→0.1
- 25%→0.25または¼
- 40%→0.4
- 120%→1.2(利益が原価の1.2倍など)
小数に直すことで、掛け算や割り算がスムーズになり、式にそのまま代入できるようになります。たとえば「利益率が20%」という情報は、利益=原価×0.2という形で活用できます。
また、複数の%が登場する場合にも、小数や分数で整理しておけば、混乱を防ぐことができます。ポイントは以下の通りです。
- すべての%を一度ノートに数字として書き換える
- 計算式では小数(または分数)で処理
- 必要なら最後に%に戻して答えを表記する
このように、数字で整理するクセをつけることで、正確性とスピードの両方をアップさせることができます。
損益算の対策ポイント
損益算は、基本的なパターンとコツをおさえていれば得点しやすい分野ですが、確実に得点源にするためには日ごろからの対策も重要です。ここでは、効率よく対策を進めるためのポイントを2つ紹介します。
損益三要素(原価・売価・利益)をしっかり理解
繰り返しになりますが、まずは原価・売価・利益の3つの関係を頭に入れておくことです。これは損益算の土台とも言える部分であり、この3つの値がどう関係し合っているのかをきちんと理解しておくと、どんな問題でも慌てずに対応できます。
- 売価=原価+利益
- 利益=売価−原価
- 原価=売価−利益
この3つの公式は、ただ暗記するのではなく、実際に何度も使って感覚として身につけることが大切です。
たとえば、「定価の20%引きで売っても10%の利益が出た」といった問題でも、裏にあるのはこの3つの要素です。問題文の情報を見たら、まずどれにあたるのか分類するようにしましょう。
「割引後の利益率」に注意して練習する
損益算で間違いやすいポイントの1つが、「割引が絡んだときの利益率」です。定価や原価の金額と、割引後の価格がバラバラに登場するため、混乱しやすいのです。この対策として効果的なのが、「割引後の売価がいくらか?」をまず出すクセをつけることです。
- 定価の〇%引き→売価=定価×(1−割引率)
- 売価と原価がわかったら→利益率=利益÷原価×100
このように、一つひとつ順番に整理すれば、割引があっても怖くありません。
また、応用問題では「実際には定価より〇円安く売ったが、利益率は〇%だった」といったように、逆算が求められるケースもあります。こうした問題に対応するには、単純な計算に慣れるだけでなく、「式を組み立てる力」も身につけておくことが重要です。
割引問題でよくあるミスとして、「割引率をそのまま原価にかけてしまう」パターンがあります。あくまで割引は定価に対するものなので、計算のスタート地点を間違えないよう注意しましょう。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
損益算の練習問題3つ
損益算を攻略するには、実際に手を動かして問題を解くことが一番の近道です。ここでは、基本から応用まで対応できるように、3つの練習問題を用意しました。時間を計って解くなど、本番を意識しながら取り組んでみてください。
問題1:利益率から原価・売価を求める問題
【問題】
ある商品を利益率30%で販売したところ、利益が90円だった。このとき、商品の原価と売価を求めなさい。
【解き方】
・利益率=30%→0.3
・利益=90円
→利益=原価×0.3
→原価=利益÷0.3=90÷0.3=300円
→売価=原価+利益=300+90=390円
【答え】
原価:300円
売価:390円
問題2:割引後の利益を求める応用問題
【問題】
定価800円の商品を原価600円で仕入れた。定価の25%引きで販売したとき、利益はいくらか?
【解き方】
・定価:800円
・割引率:25%→0.25
→割引後の売価=800×(1−0.25)=800×0.75=600円
・原価:600円
→利益=売価−原価=600−600=0円
【答え】
利益:0円(つまり、利益なし・損もなし)
※このように、割引率が大きいと利益が出ないケースもあります。
問題3:合計利益の計算問題
【問題】
商品A(原価500円、売価650円)を4個、商品B(原価800円、売価1000円)を3個販売した。このときの合計利益を求めなさい。
【解き方】
Aの商品:利益=650−500=150円→150円×4個=600円
Bの商品:利益=1000−800=200円→200円×3個=600円
→合計利益=600+600=1200円
【答え】
合計利益:1200円
このように、損益算はパターンごとに整理して練習を積めば、確実に力がつきます。最初はメモを取りながらでも構いませんので、丁寧に手順を追っていきましょう。
まとめ
SPIの損益算は、一見すると複雑に感じるかもしれませんが、基本的な構造と考え方をしっかりおさえておけば、確実に得点できる分野です。
SPIでは短時間で正確に答えを出す力が求められるため、損益算においても「読み取り→整理→計算」のプロセスを素早くこなす必要があります。ですが紹介したような考え方やパターンを習得しておけば、本番でも落ち着いて対応できます。
最初は苦戦するかもしれませんが、数をこなすことで自然と身についていきます。ぜひ繰り返し練習して、SPIの損益算を自信の持てる得意分野にしてください。