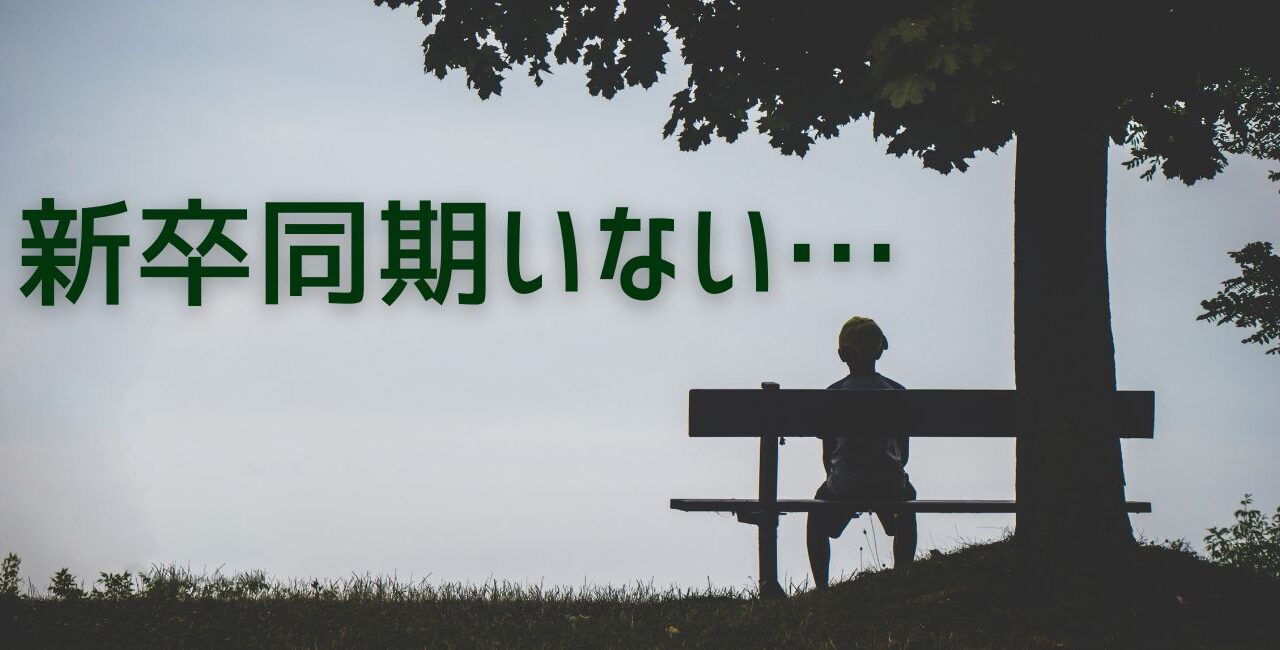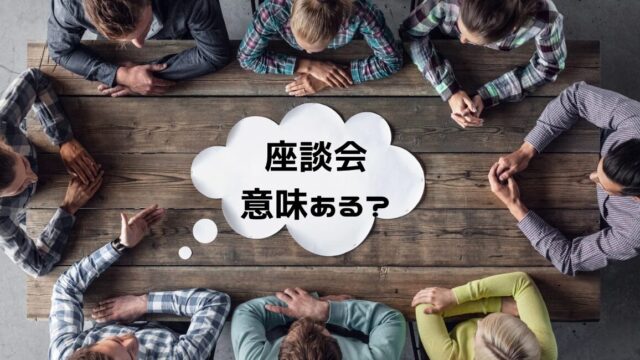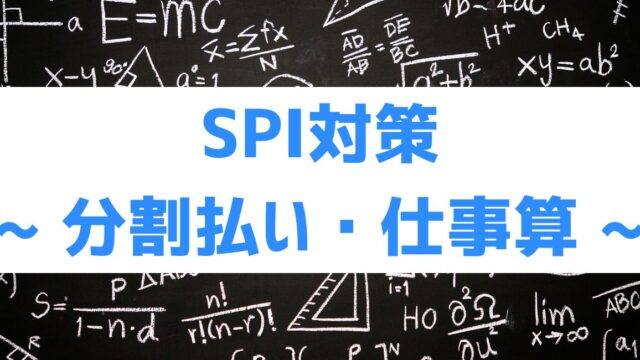【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
新卒採用では、複数人採用する企業が多いため同期がいます。
しかし、新卒採用が1人だけの企業ももちろんあるため、場合によっては新卒入社が自分だけで新卒1年目から同期がいないこともありえます。特にスタートアップやベンチャー、中小企業などではよくあることです。
そして実は筆者も、弊社の23卒唯一の新入社員であるため同期がいません。また学生時代はベンチャーで他の学生とともに長期インターンをしていたため、同期がいる環境についてもある程度イメージできます。
そこで今回は、新卒で同期がいない筆者の実体験をもとに、新卒で同期がいる場合と比較した時の新卒で同期がいないメリット・デメリットを紹介していきます。
目次
新卒で同期がいないのは珍しいこと?
すべての会社に同期がいるわけではありません。特に小規模な企業やベンチャー企業では、新卒採用の人数が少なく、入社してみたら同期がいないというケースも珍しくありません。
まずは、同期がいない新卒の実態を詳しく見ていきましょう。
同期がいない新卒の割合と実態
大手企業では毎年数十人から数百人単位で新卒採用を行うことが一般的ですが、中小企業やベンチャーでは、新卒採用がそもそも少ない場合があります。また毎年必ず新卒を採用すると決めている企業はさらに少なく、結果的に同期がいない新卒というケースが生まれます。
また、業界によっても違いがあり、例えばスタートアップ企業や専門職系の企業(デザインなど)では、新卒採用を実施しても1〜2名だけということがよくあります。このような環境では、同期と一緒に入社することがそもそも難しく、同期なしの環境で働くことが当たり前になっているケースもあります。
中小企業・ベンチャーではよくあるケース
同期がいないケースは、特に中小企業やベンチャー企業でよく見られます。理由としては、以下のような点が挙げられます。
- 新卒採用の枠が少ない:そもそも大量に採用できる予算や体制がない
- 即戦力採用が中心:経験者を優先して採用することが多い
- 成長フェーズによる影響:企業の規模や事業の成長状況によって新卒を採る年と採らない年がある
特にベンチャー企業では、今年は新卒採用をしないといった方針の変化が起こることもあるため、数年前までは同期がいたのに、今年は自分一人だけというケースもあります。
また、地方の企業やニッチな業界では、採用市場自体が小さいため、結果的に同期が少なくなることもあります。
このように、新卒で同期がいないという状況は決して珍しいことではなく、特定の業界や企業の特徴としてごく普通に起こり得ることなのです。
同期がいる会社との違い
新卒で同期がいない場合、周囲に同じ立場の仲間がいないため、会社での経験が大きく変わります。同期がいる会社と比べて、どのような違いがあるのかを具体的に見ていきましょう。
- ・相談相手がいない孤独感
- ・仕事の悩みを共有できない不安
- ・比較対象がいなくて成長を実感しづらい
それぞれ詳しく解説します。
相談相手がいない孤独感
同期がいないと、同じスタートラインに立つ仲間がいないため、気軽に相談できる人がいないと感じることがあります。
例えば、大手企業では同期同士でランチをする仕事終わりに愚痴を言い合うといった交流が生まれやすく、職場になじむまでのストレスを軽減できます。しかし、同期がいないと最初から先輩や上司と接する必要があり、気軽に話せる人がいない…と感じることがあるのです。
特に入社して間もない頃は、業務に慣れていない状態で自分だけが取り残されているのでは…?と不安を感じることもあるでしょう。同期がいれば自分も同じ状況だと安心できますが、一人だとどうしても孤独を感じやすくなります。
仕事の悩みを共有できない不安
社会人になると、仕事の悩みが増えるものです。しかし、同期がいないと同じ目線で悩みを共有できる相手がいないというデメリットがあります。
例えば、上司からの指示が分かりにくい業務の優先順位がうまくつけられないといった悩みがあっても、同期がいれば自分も同じことで悩んでる!と共感し合えます。しかし、同期がいないとこれって自分だけ…?と余計に不安になってしまうことがあります。
また、先輩や上司にすぐ相談できる環境でない場合、悩みを抱え込んでしまうこともあります。こんなことを質問していいのか分からない…仕事ができないと思われたくないといった気持ちが強くなりやすいのです。
ライバルや比較対象がいなくて成長を実感しづらい
同期がいると、あの人はもうこの業務をマスターしているのに、自分はまだできていない…といった刺激を受けることができます。同期と競い合うことで、自分の成長スピードを確認しやすくなるのです。
一方で、同期がいないと今の自分は成長しているのか?周りと比べてどの程度のスキルが身についているのか?が分かりにくくなります。先輩や上司とは経験値に差があるため、比べる対象として適切でないことも多く、自分はまだまだダメだと自己評価が低くなりがちです。
このように、同期がいる会社と比べると孤独を感じやすい仕事の悩みを共有しづらい成長を実感しにくいといった違いがあります。しかし、逆に言えば、これらの課題をうまく乗り越えられれば、同期がいない環境でも十分に活躍できるのです。
次の章では、同期がいない職場でうまく馴染む方法について具体的な対策を紹介します。
同期がいない職場でうまく馴染む方法
同期がいないと、入社直後に職場に馴染めるか不安…と感じる人も多いでしょう。しかし、工夫次第で職場にうまく適応し、充実した社会人生活を送ることは十分に可能です。ここでは、同期がいない環境での立ち回り方を紹介します。
先輩・上司との関係を築くコツ
同期がいない分、職場での人間関係は先輩や上司が中心になります。そのため、早めに信頼関係を築くことが重要です。具体的には、以下のポイントを意識しましょう。
- 自分から挨拶をする
最初の印象を良くするために、明るく元気に挨拶をすることは基本中の基本です。職場の雰囲気をつかむためにも、自分から声をかける姿勢を大切にしましょう。 - 仕事の質問は積極的にする
分からないことがあれば、遠慮せずに質問しましょう。特に、入社したばかりの時期は質問しすぎて迷惑にならないか…と考えがちですが、むしろ何も聞かずにミスをする方が問題です。事前に質問する内容を整理してから聞くメモを取るなどの工夫をすると、スムーズに教えてもらいやすくなります。 - 先輩の得意分野を把握する
職場にはこの分野ならこの人に聞けばいいという暗黙のルールがあることが多いです。例えば、書類作成が得意な先輩、交渉が上手な先輩など、それぞれの強みを理解しておくと、質問や相談をするときにスムーズになります。 - ランチや雑談で交流を深める
仕事の話だけでなく、オフの時間を活用してコミュニケーションを取るのも大切です。無理に飲み会に参加する必要はありませんが、ランチに誘われたら積極的に参加してみると良いでしょう。また、仕事の合間に最近ハマっていることや休日の過ごし方などの雑談を交えると、先輩との距離が縮まりやすくなります。
他部署や社外のコミュニティを活用する
職場に同期がいない場合、社外に相談できる仲間を作ることも一つの方法です。以下のようなコミュニティを活用すると、同じような立場の人とつながることができます。
- 社内の他部署の新卒社員と交流する
自分の部署に同期がいなくても、会社全体で見れば他の部署に新卒社員がいることもあります。社内イベントや研修を活用して、他部署の同年代の人とつながると、職場での孤独感を減らせます。 - 社外の勉強会や交流イベントに参加する
業界ごとの勉強会やセミナーには、同世代の若手社会人が多く集まります。例えば、エンジニア向けの勉強会や、マーケティングのワークショップなど、興味のある分野のイベントに参加すると、仕事のスキルアップと人脈形成の両方を兼ねられます。 - オンラインのコミュニティを活用する
SNSやビジネス向けのオンラインコミュニティ(LinkedIn、Xの就活・ビジネス系アカウントなど)を活用すると、同じ業界・職種の人とつながることができます。特に、同期がいなくて不安という悩みを共有できる場があると、モチベーション維持にも役立ちます。
メンターやロールモデルを見つける
同期がいない分、この人のようになりたい!と思えるロールモデルを見つけることも重要です。身近にいる先輩や上司の中で、仕事の進め方や考え方が参考になる人を見つけると、キャリアの方向性を明確にしやすくなります。
- 尊敬できる先輩に学ぶ
仕事の進め方が丁寧な人、コミュニケーションが上手な人など、職場の中でこうなりたいと思える先輩を見つけ、その人の行動を観察したり、積極的に話を聞いたりすると、成長のヒントが得られます。 - 社外のメンターを見つける
会社の中にロールモデルが見つからない場合は、社外でメンターを探すのも一つの方法です。例えば、大学のOB・OG訪問を通じて話を聞いたり、ビジネス系のイベントで知り合った人に相談してみたりすると、異なる視点を得ることができます。
同期がいない環境では、職場内での信頼関係を築くこと社外にも相談できるつながりを作ることロールモデルを見つけることが大切になります。これらの工夫をすれば、孤独感を感じることなく、スムーズに職場に馴染むことができるでしょう。
同期がいなくても成長できる働き方
同期がいないと、仕事の成長スピードが遅くなるのでは?と不安に思うかもしれません。しかし、環境をうまく活かせば、むしろ自分のペースで効率的にスキルアップできるメリットもあります。ここでは、同期がいなくても成長できる働き方を紹介します。
自分のペースでスキルアップできるメリット
同期がいると、自然と競争意識が生まれますが、それがプレッシャーになることもあります。同期がいない環境では、周りのペースに振り回されず、自分に合った成長プランを立てられるのがメリットです。
例えば、以下のようなポイントを意識すると、スムーズにスキルアップできます。
- 自分の得意・不得意を客観的に把握する
同期がいないと、他の人と比べて自分はどのレベルなのか?を把握しにくいものです。そこで、定期的に自分のスキルを振り返ることが大切です。例えば、業務ごとにどこまでできるようになったか?をリスト化しておくと、成長を実感しやすくなります。 - マイペースに学習計画を立てる
同期と足並みをそろえる必要がない分、自分の得意な分野を深く掘り下げたり、苦手な部分を重点的に学んだりできます。例えば、1カ月ごとに新しいスキルを習得する週1回、仕事の振り返りをするといった計画を立てることで、着実にスキルアップできます。 - 早い段階で専門性を磨ける
同期が多い環境では、みんなが同じ研修を受け、似たようなスキルを身につけていきます。しかし、同期がいない場合は、自分に合ったスキルや専門性を早い段階で極められるというメリットがあります。たとえば、エンジニアなら特定のプログラミング言語を極める、営業職なら業界特有の営業ノウハウを学ぶといった形で、自分だけの強みを作ることが可能です。
ライバルがいない環境をどう活かすか
同期がいないと、競争意識が生まれにくいため、モチベーションを保つのが難しいと感じることがあります。そこで、自分の成長を促す仕組みを作ることが大切です。
- 目標を過去の自分と比較する
同期がいないと成長が分かりにくいと感じる人は、自分自身をライバルにするのが効果的です。例えば、入社1カ月目と比べて、どれだけ成長したか?を定期的に振り返ると、成長を実感しやすくなります。 - 社内で負けたくない先輩を見つける
この先輩みたいになりたいこの人には負けたくないという存在を見つけることで、自然とモチベーションが上がります。例えば、あの先輩が2年目でこれくらいできていたなら、自分もそれを目標にしようといった形で目標を設定すると、成長の指標が明確になります。 - 社外のライバルを意識する
もし社内で競争相手がいない場合は、社外に目を向けるのも有効です。例えば、同じ業界・職種で活躍している若手社会人のSNSをチェックしたり、業界のイベントに参加して他社の人と交流したりすると、自分も負けていられない!という刺激を受けやすくなります。
目標設定を工夫してモチベーションを維持する
同期がいない環境では、自分の成長スピードを把握しにくいため、目標設定の仕方を工夫することが重要です。具体的には、以下のような方法を試してみましょう。
- 短期目標と長期目標を設定する
今月中に○○の業務をマスターする1年後には○○の資格を取得するといった形で、短期・長期の目標を分けて考えると、モチベーションを維持しやすくなります。 - 見える化して進捗を確認する
目標を立てても、達成度が分からないとモチベーションが下がりがちです。タスク管理アプリや手帳を活用して、今どこまで達成できているのか?を視覚的に確認できるようにすると、達成感が得られます。 - ご褒美を設定する
モチベーションを維持するために、目標を達成したら自分へのご褒美を用意するのも効果的です。例えば、1カ月間、毎日30分勉強できたら好きなものを買うといった形で、自分をうまくコントロールすると、継続しやすくなります。
同期がいない環境では、自分で成長を管理し、モチベーションを維持する力が求められます。しかし、工夫次第で同期がいないからこそ得られる成長のチャンスを最大限に活かせます。
同期がいないことで得られる意外なメリット
同期がいないことはデメリットばかりではありません。実は、同期がいないからこそ得られるメリットもあります。ここでは、意外な利点を3つ紹介します。
先輩や上司からのサポートを受けやすい
同期がいる会社では、新人研修やOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)が同期全員に向けて一括で行われることが多いです。しかし、同期がいない場合、会社側もこの新人をしっかり育てなければという意識が強くなり、個別で手厚いサポートを受けられる可能性が高まります。
例えば、大手企業では新人が多いため、教育係の先輩が一人ひとりに深く関わるのは難しいですが、小規模な企業ではこの子はうちの会社で初めての新卒だから、ちゃんと育てようといった形で、マンツーマンに近い指導を受けられるケースもあります。
また、同期がいると自分が分からなくても誰かが質問してくれると思いがちですが、同期がいない環境では自分が動かないと仕事が進まないという意識が強くなり、結果的に成長が早くなることもあります。
仕事の成果を直接評価してもらいやすい
同期がいると、どうしても新人はみんな同じような評価を受けるという流れになりがちです。しかし、同期がいない場合、あなたの仕事ぶりがダイレクトに評価されるため、努力がしっかりと見てもらいやすいというメリットがあります。
- 良い成果を出せば、すぐに評価される
例えば、同期が多い企業では、評価のタイミングが年1回や半年に1回と決まっていることが一般的です。しかし、同期がいない環境ではこの新人はすごく頑張っていると早い段階で認められ、通常より早く昇進・昇給のチャンスを得られる可能性もあります。 - 個別のフィードバックがもらいやすい
上司や先輩が全員に同じことを言うのではなく、あなた個人に合わせたフィードバックをしてくれるため、仕事の改善点や成長の方向性が明確になります。
同期がいないと、仕事の出来不出来がすぐに分かってしまうため、サボれないというプレッシャーもありますが、それは頑張れば頑張った分だけ評価されるというメリットでもあります。
社内の人間関係に縛られず、フラットな関係を築ける
同期がいないことで、社内の人間関係において同期グループに縛られない自由さがあります。
- 派閥やグループに巻き込まれにくい
大手企業では、同期同士で仲良くなる一方で、同期内での派閥ができる同期の中で評価の差が生まれてギクシャクするといったケースもあります。しかし、同期がいない環境では、そういった人間関係のストレスが少なくなります。 - 年次に関係なく、いろんな人と交流しやすい
同期がいないからこそ、先輩や他部署の人ともフラットに接しやすいというメリットもあります。例えば、同期がいると同期同士で固まってしまい、なかなか先輩に話しかけづらいということがありますが、同期がいない環境では会社のさまざまな人とコミュニケーションを取る必要があるため、結果的に社内での人脈が広がるのです。 - 年齢に関係なく、自分の実力で評価される
同期がいると同じ年齢だからという理由で一括りにされることもありますが、同期がいない環境では、年齢ではなく仕事の実力や成果で評価される傾向が強くなります。
このように、同期がいないことで、余計な人間関係のストレスが減り、よりオープンに社内の人と関われるというメリットがあります。
同期がいないことは、不安に感じることもあるかもしれませんが、見方を変えれば成長のチャンスが多い環境とも言えます。次の章では、そんな不安を解消するための具体的な行動リストを紹介します。
同期がいない不安を解消するための行動リスト
同期がいないと、相談できる人がいなくて不安モチベーションを保つのが難しいといった悩みが出てくることがあります。しかし、積極的に行動することで、そうした不安を解消することができます。ここでは、具体的なアクションプランを紹介します。
社外のコミュニティや勉強会に参加する
職場に同期がいなくても、社外に同じ立場の仲間を作ることで、不安を解消できます。
- 業界や職種ごとの勉強会に参加する
例えば、エンジニアなら技術系のミートアップ、マーケティング職ならデジタルマーケティングのセミナーなど、自分の業界や職種に関連する勉強会に参加すると、他社の同世代の人とつながることができます。 - 異業種交流イベントに参加する
業界にこだわらず、ビジネス全般のセミナーや交流イベントに参加するのもおすすめです。さまざまな業種の若手社会人と知り合うことで、新しい視点を得られたり、職場での悩みを共有できる仲間が増えたりします。 - オンラインイベントを活用する
リアルのイベントに行くのはハードルが高いと感じる場合は、オンラインのセミナーや勉強会を活用するのも良い方法です。SNSで○○勉強会○○コミュニティなどと検索すると、さまざまなオンラインイベントを見つけることができます。
SNSやオンラインのつながりを活用する
最近では、SNSを通じて就活生や若手社会人が情報交換できる場が増えています。こうしたオンラインのつながりを活用することで、孤独感を減らし、モチベーションを維持できます。
- X(旧Twitter)やLinkedInで同期のいない社会人の投稿をチェック
#新卒1年目#社会人1年目といったハッシュタグで検索すると、同期がいない環境で働く人たちの投稿を見ることができます。自分と似た境遇の人の体験談を読むだけでも、不安が和らぐことがあります。 - キャリア系のオンラインコミュニティに参加する
若手社会人向けのオンラインサロンやコミュニティも増えています。例えば、社会人1年目の学び20代のキャリア形成といったテーマのコミュニティに参加すると、仕事の悩みを共有できる仲間が見つかることもあります。 - 企業公式のコミュニティに参加する
一部の企業では、新卒社員向けのオンラインコミュニティを運営していることがあります。社外の同期のような存在を作れる場なので、こうした機会があれば積極的に活用しましょう。
OB・OG訪問をして他社の新卒と交流する
大学時代の先輩(OB・OG)を訪問して話を聞くことで、他社の新卒社員の状況を知ることができ、不安を解消しやすくなります。
- 大学のキャリアセンターを活用する
多くの大学では、卒業生の就職先リストを管理しており、OB・OG訪問のサポートを行っています。興味のある企業や業界の先輩を紹介してもらい、話を聞いてみると良いでしょう。 - OB・OG訪問サービスを利用する
ビズリーチ・キャンパスマッチャーといったOB・OG訪問サービスを活用すると、企業や職種ごとに先輩を見つけることができます。特に、新卒時に同期がいなかった先輩に話を聞くと、具体的なアドバイスをもらいやすいです。 - 同じ職種の人に話を聞く
例えば、エンジニアなら1年目のエンジニアがどんな仕事をしているのか?、営業職なら新人営業の最初の壁は何か?など、自分の職種ごとのリアルな話を聞くと、今後の働き方のヒントが得られます。
このように、社外のつながりを作るオンラインで情報を得るOB・OG訪問で他社の状況を知るといった行動を取ることで、同期がいない不安を軽減することができます。次の章では、これまでの内容をまとめ、同期がいなくても充実した社会人生活を送るための考え方を紹介します。
同期がいなくても充実した社会人生活を送るために
同期がいないことに最初は不安を感じるかもしれませんが、視点を変えれば、自由に学び、成長し、人間関係を築ける環境でもあります。
社会人生活は長いものです。同期がいるかどうかに関わらず、自分の成長を大切にし、前向きに行動していくことが、充実したキャリアにつながります。
同期がいないからダメだではなく、同期がいない環境をどう活かすか?を考えながら、主体的に社会人生活を楽しんでいきましょう。