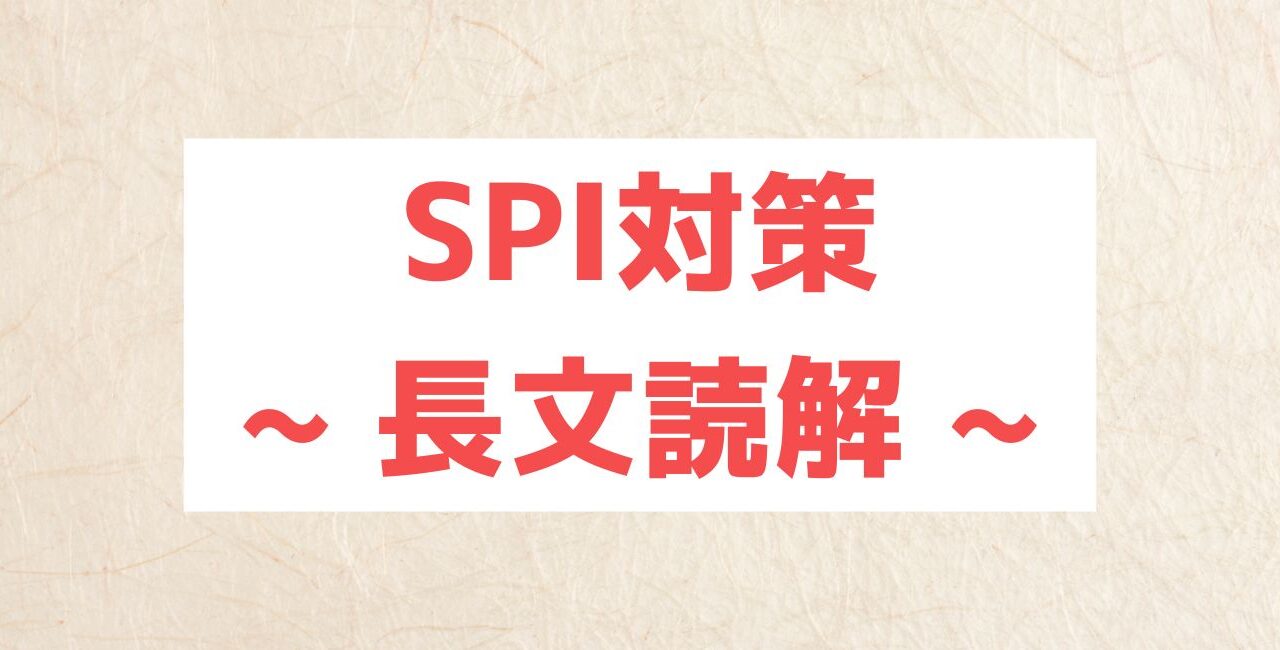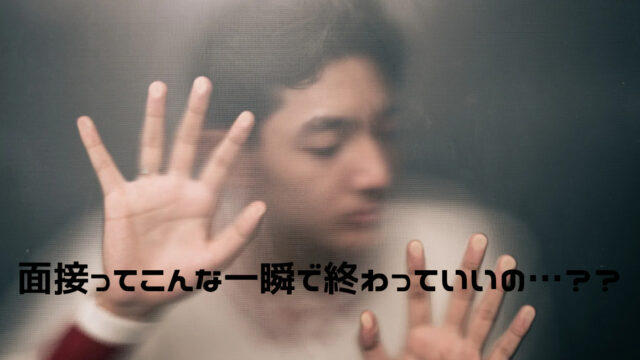【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
SPIの言語分野の中でも、「長文読解問題」は最頻出でかつ、時間配分と集中力が問われるジャンルです。文章量が多く、設問も複数出ることが多いため、「読むのが遅くて間に合わなかった」「なんとなく選んで間違えた」という問題が発生しやすくもあります。
ですが、実はSPIの長文読解はある程度出題パターンが決まっており、正しい読み方と解き方のコツをつかめば、読み飛ばしたり、焦ったりすることなく安定して得点できるようになります。
この記事では、SPI長文読解問題の基本から、出題されやすいパターン、読み方と設問の解き方のコツ、そして読解スピードと正答率を高めるための学習法までを詳しく解説します。「文章を読むのが苦手」「時間が足りない」という人こそ、ぜひ読み進めて、着実な得点アップにつなげてください。
目次
SPIの長文読解とは
SPIの長文読解問題では、複数段落から成る文章を読んで、その内容に関する設問に答える形式が出題されます。文章のジャンルは、ビジネスや時事的なテーマ、社会問題、教育論など幅広く、論理性の高い内容が多いのが特徴です。
設問では、文章の主張、言い換え、具体例の意味、文章全体の要旨、筆者の考えと合う選択肢などが問われます。つまり、ただ読むだけではなく、筆者の立場や意図を読み取りながら、論点を整理して答える力が必要になります。
【問題の特徴】
・文章は400〜600字程度が一般的
・設問は1~3問で、選択肢は意味が似ていて迷いやすい
・本文に「直接書かれていないこと」は正解になりにくい
【求められる力】
・段落構成を理解し、要点をすばやく把握する力
・筆者の主張と、それを支える理由・具体例をつかむ力
・「なんとなく」ではなく「根拠をもとに」選択肢を判断する力
長文読解は、語彙力と読解スピードの両方を求められる応用的な問題です。しかし、読み方の型を覚えて、読み慣れてくると、内容把握も設問対応も格段にラクになります。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPI長文読解でよく出る問題
SPIの長文読解では、一定の出題パターンがあります。これを把握しておけば、本文のどこに注目すればよいか、設問で何を問われているのかが明確になり、無駄な読み返しや迷いを減らすことができます。ここでは、特に出題頻度が高い3つの問題タイプを紹介します。
筆者の主張を問う問題
最も基本で頻出なのが、筆者が言いたいこと(主張)を正確に読み取れているかを問う問題です。文章全体のテーマや、結論として筆者が何を主張しているのかを把握する必要があります。
【例】
「この文章で筆者が最も伝えたいことはどれか。」
このタイプでは、表面的な情報ではなく、筆者の立場・意見が明確に表れている箇所(冒頭・結論・接続詞の後など)に注目するのがポイントです。
【注意点】
・具体例や事例は主張を補足する材料であることが多い
・「筆者の意見」ではなく「客観的事実」ばかり書かれている選択肢は誤答になりやすい
言い換え・要約を選ぶ問題
文章中のある一文や段落を、別の言葉で言い換えるとどうなるか、あるいは簡潔にまとめるとどう表現できるかを問う問題もよく出題されます。
【例】
「下線部ともっとも近い意味を表しているのはどれか。」
「この段落の要点として適切なものを選びなさい。」
このタイプの問題では、「表現は違っても中身は同じ」という関係を見抜く必要があり、論理構造(原因・結果、対比、具体例など)を正しく把握しているかが問われます。
【対策ポイント】
・「なぜそうなるのか」「この話の目的は何か」と常に問いながら読む
・表現が難しくても、かみ砕いて理解し、自分なりに置き換えてみる習慣をつける
文章中の根拠を探す問題
もう一つの定番の出題形式は、選択肢の正誤を、本文の記述をもとに判断するタイプの問題です。これは事実の確認や内容の正確な読解力が試される問題になります。
【例】
「本文の内容と一致するものを選びなさい。」
「筆者の意図と最も合致する選択肢はどれか。」
この問題では、本文中の表現を丁寧にたどって、選択肢とどこまで一致しているかを確認することが重要です。「本文と一部だけ合っているが、全体で見ると合致しない」というパターンもあるため、選択肢の一語一句に注意を払う癖をつけておくと有利です。
これら3パターンを意識しておくだけで、読解問題に取りかかる前の「読みの構え方」が変わります。
長文読解を解くコツ
SPIの長文読解は、速く読んで正しく選ぶことが求められるため、読み方に工夫が必要です。ただ何となく全文を読むのではなく、設問の意図を先に把握し、要点を押さえながら読む姿勢が大切です。
ここでは、SPIの長文読解問題を効率よく、かつ正確に解くための具体的な3つのコツを紹介します。
コツ①:設問を先に読んでから本文を読む
時間制限のあるSPIでは、最初に設問を読んでから本文に入ることで、どこに注目すべきかを意識しながら読めるようになります。設問の意図を知らずに読むと、すべての情報を覚えようとして時間がかかり、設問を読んでからまた本文を読み返すという非効率な流れになってしまいます。
【具体的な実践法】
・設問が「筆者の主張」か「言い換え」か「根拠照合」かを見極める
・設問文中にあるキーワード(例:筆者の立場、言い換え、段落番号など)を把握
・本文を読むときに「設問と関係ありそうな部分」にマークや意識を集中させる
この手順を徹底することで、本文を1度読むだけで設問に答えられる確率が上がり、時間の節約と正答率の向上の両方が期待できます。
コツ②:段落ごとに要点を整理しながら読む
長文読解では、1文1文の細かい意味よりも、段落ごとの主張や構成の流れを捉えることが重要です。各段落が文章全体の中でどういう役割を持っているのかを理解することで、主張や要点をつかみやすくなります。
【段落ごとの読み方のポイント】
・第1段落:テーマや問題提起が書かれていることが多い
・中盤の段落:主張の根拠や具体例、対比構造が入りやすい
・最終段落:筆者の主張のまとめや提案で締めくくられることが多い
【意識すべき視点】
・この段落で筆者は何を伝えたいのか?
・段落の冒頭と最後で話の展開がどう変わったか?
・「つまり」「したがって」「たとえば」などの接続語を見逃さない
段落ごとに要点をメモしたり、頭の中でざっくりまとめたりすることで、全体像が把握しやすくなり、選択肢の正誤判断も的確になります。
コツ③:「根拠のある選択肢」を探すクセをつける
SPIの読解問題では、選択肢の中に「本文と似たようなことが書いてある」ものが複数ある場合があります。その中から正解を選ぶには、必ず本文中に根拠となる記述があるかどうかを確認するクセをつけることが重要です。
【ありがちな誤り】
・選択肢だけを読んで「何となく合ってそう」で選んでしまう
・筆者の気持ちや一般常識から判断してしまう
・具体例だけに目を奪われ、全体の趣旨を見失う
【対策】
・「本文に書かれているかどうか」を常に自問しながら選ぶ
・少しでもあいまい・脚色されていると感じた選択肢は除外
・「本文に近い表現」を選ぶのではなく、「本文の論理と一致する」ものを選ぶ
この習慣を身につけることで、設問で迷っても論理的に正解を絞り込めるようになります。
SPI長文読解の対策ポイント
SPIの長文読解で高得点を取るには、試験直前に身につける小手先のテクニックではなく、日常の中で読解力を高める学習習慣を作ることが大切です。ここでは、時間内に要点を見抜く力と、正確に文章を理解する力を伸ばすための、実践的な3つの対策ポイントを紹介します。
ポイント①:ビジネス系・評論系の文章に慣れる
SPIで出題される文章は、会話文や物語文ではなく、論理的で抽象度の高い「評論的な文章」が中心です。
内容も、働き方、情報社会、教育、経済、倫理など、社会人としての視点が求められるテーマが多く、慣れていないと読みにくく感じることもあります。
【おすすめの読み物】
・新聞の社説(朝日新聞・日経新聞など)
・ビジネス書の冒頭部分
・新書の解説文や論考パート
・SPI対策本の長文読解問題集
【学習法】
・読みながら段落ごとに「この段落の要点は何か?」を意識する
・難しい語句や表現が出てきたら、調べて語彙ノートにまとめる
・音読することで、論理の流れや文章のリズムに慣れる
「論理的な文章に慣れておくこと」が、読みやすさと理解スピードの底上げにつながります。
ポイント②:文章を要約する練習を重ねる
読解力を根本から高めるのに効果的なのが、文章の要点をつかむ=要約する練習です。要約力が身につけば、「どこが主張で、どこが例なのか」が自然に整理できるようになり、選択肢を選ぶときの判断が格段にスムーズになります。
【おすすめのトレーニング】
・1段落ずつ、要点を10~15字で書き出す練習
・文章全体を「一文」でまとめる要約トレーニング
・自分で書いた要約が本文と合っているか、照らし合わせて確認する
最初は時間がかかっても構いません。継続することで、文章の骨格を素早くつかむ力=本番での読解スピードアップに直結します。
ポイント③:毎日1問読む習慣でスピードを鍛える
読解力を確実に伸ばすためには、毎日少しでも「読む・考える・選ぶ」練習を積み重ねることが何より重要です。特に長文読解は、「一気にたくさんやる」よりも、「毎日短時間でも触れる」ことで読解スピードが自然と上がっていきます。
【実践例】
・SPI対策問題集の長文読解を1日1問(所要時間:5〜10分)
・時間を計りながら「読む時間+設問を解く時間」を記録する
・選択肢の検討理由を簡単にメモすることで思考を言語化する
この習慣を続けることで、「どこに注目して読めばいいか」「どこで迷いやすいか」を自分なりに把握できるようになり、試験本番でも落ち着いて対応できる力がついていきます。
長文読解練習問題3つ
ここでは、SPI長文読解で頻出の3つのパターン「主張の要約」「言い換え」「根拠の確認」に沿った練習問題を紹介します。時間を意識しながら挑戦し、どこに注目して読めば正解にたどり着けるかを体感してみてください。
問題1:主張の要約問題
【本文】
近年、在宅勤務が急速に広まりつつある。その背景には、通勤時間の削減や仕事の効率化といった利点がある一方で、社員間のコミュニケーション不足や、自宅環境の格差といった課題も存在する。しかし、企業側がオンラインでの交流施策を積極的に導入するなど、働き方改革の一環として在宅勤務を進化させる努力が続いている。
【設問】
この文章の筆者の主張として最も適切なものを選びなさい。
①在宅勤務は多くの問題を抱えているため、導入は慎重に進めるべきだ。
②在宅勤務のデメリットを解消できれば、今後も主流になるだろう。
③在宅勤務は非効率なため、出社型の働き方に戻るべきだ。
④在宅勤務によって生産性は下がったが、改善の余地はある。
【正解】
②在宅勤務のデメリットを解消できれば、今後も主流になるだろう。
【解説】
本文では「利点と課題の両面」に触れた上で、企業が課題解消の努力をしていると締めくくられており、前向きな姿勢が読み取れます。①や③のような否定的な主張は本文と合致しません。
問題2:具体例と言い換えを問う問題
【本文】
人の行動を変えるためには、単に「正しいこと」を伝えるだけでは不十分である。たとえば、健康のために運動が良いと分かっていても、すぐに行動に移す人は少ない。重要なのは、本人が「自分にもできる」と実感できることや、小さな成功体験を積み重ねていくことである。
【設問】
下線部「重要なのは、本人が〜」の内容と最も近いものはどれか。
①行動変容には、強い意志と継続的な努力が求められる。
②行動を変えるには、根拠のある知識を与えることが効果的だ。
③自信や成功体験が、行動を後押しする要因になる。
④行動の前に、健康リスクをしっかり認識させる必要がある。
【正解】
③自信や成功体験が、行動を後押しする要因になる。
【解説】
本文では「自分にもできると実感すること」「小さな成功体験」がキーワードになっており、これは選択肢③の内容と一致します。他の選択肢は焦点がずれていたり、本文に書かれていない内容を含んでいます。
問題3:根拠をもとに選択する読解問題
【本文】
AI技術の進歩によって、人間の仕事が奪われるという懸念が広がっている。しかし実際には、AIが人間の仕事を補完することで、新しい価値を生み出す例も多く見られる。たとえば、医療現場ではAIが画像診断を支援することで、医師の判断をより正確なものにしている。
【設問】
この文章の内容と合致するものを選びなさい。
①AIによってすでに多くの人が職を失っている。
②AIは今後、医師を完全に代替する存在になる。
③AIの導入により、人間の仕事が不要になる可能性が高い。
④AIは人間の業務を支援し、新たな価値を生み出す場合もある。
【正解】
④AIは人間の業務を支援し、新たな価値を生み出す場合もある。
【解説】
本文では「AIが仕事を補完している」「医師の判断を支援している」と明確に書かれており、選択肢④がそれに合致します。①〜③は本文の内容と一致しないか、誇張的な表現になっているため誤りです。
3つの問題を通じてわかるように、SPIの長文読解は「本文に沿って正しく読み取る力」が問われます。本文中の根拠を見逃さず、設問の意図を冷静に読み取ることが、高得点への最短ルートです。
まとめ
SPIの長文読解は、文章量が多く、設問も複雑に見えるため、「時間が足りない」「なんとなくで選んで間違える」といった悩みを抱えがちな分野です。
しかし、読み方のコツをつかみ、頻出パターンを押さえた学習を積み重ねることで、確実に得点源へと変えることができます。
長文読解は、読むスピードと理解力のバランスが問われる実践的な分野ですが、裏を返せば、継続的な訓練で誰でも伸ばせる力です。
毎日1問、段落ごとの要点をまとめたり、本文と照らし合わせて選択肢を検証したりする習慣をつけるだけでも、少しずつ「読める感覚」が身についていきます。
読み方を変えるだけで、SPI全体の時間配分にも余裕が生まれ、言語問題への自信が高まります。この記事で紹介したコツや対策を、ぜひあなたの学習に役立ててください。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。