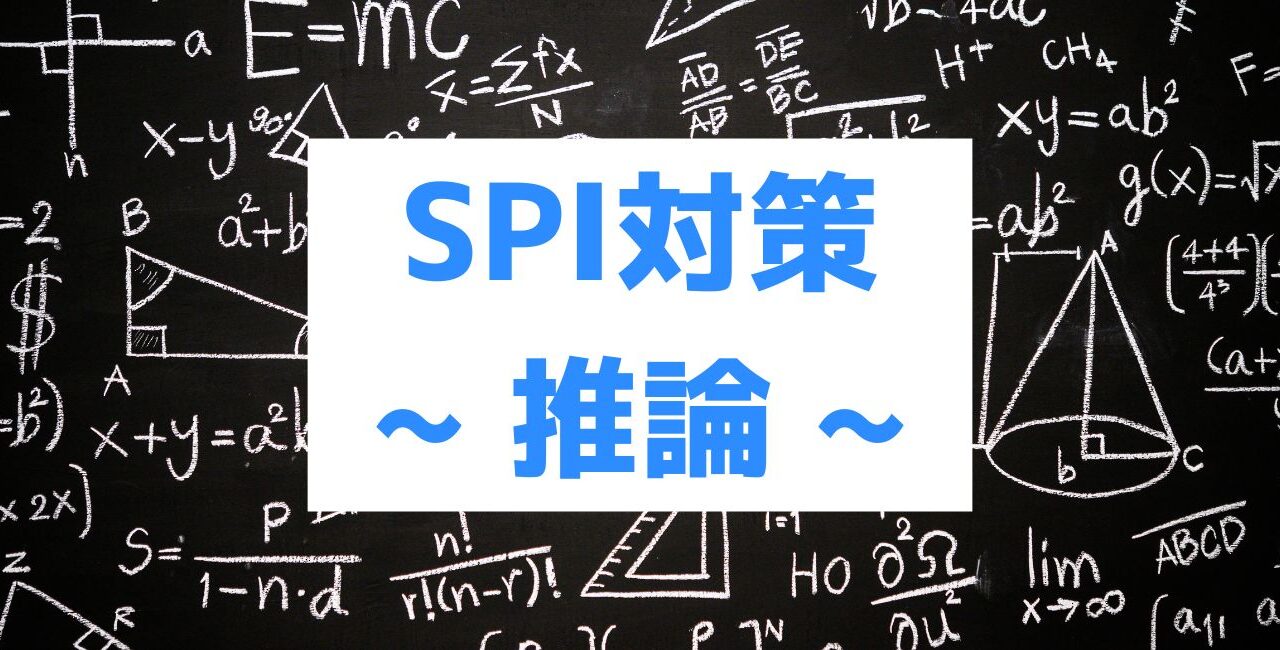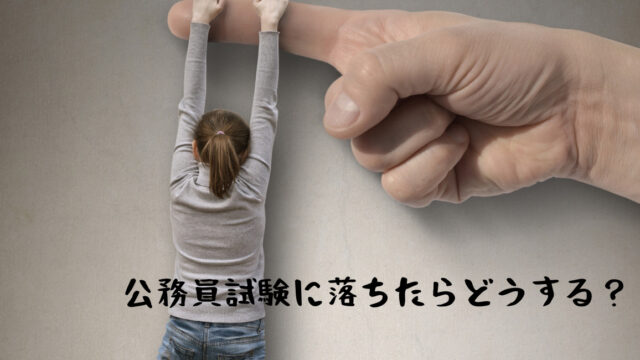【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
就活で避けて通れないのがSPI。中でも「推論」は、多くの受験者が苦手意識を持つ分野です。問題文が長く、条件が複雑で、一見すると何を聞かれているのかわからなくなることもあるかもしれません。
でも安心してください。推論問題には“出題パターン”があり、ポイントを押さえて練習すれば、誰でも着実に得点できるようになります。
この記事では、SPIの推論分野についてどんな形式で出題されるのか、効率的な解き方や対策方法を解説したのち、練習問題を3つ準備しています。初めて対策を始める人も、苦手克服を目指したい人も、ぜひ最後までチェックしてみてください。
目次
SPIの推論とは
SPIの「推論」は、与えられた情報から筋道を立てて答えを導き出す力を試す問題です。計算問題のように公式を使えばすぐ解ける、というものではなく、自分で条件を整理しながら「考え抜く力」が求められます。
推論は最頻出問題!ロジック思考が求められる
推論問題は、SPIの非言語分野の中でも出題頻度が非常に高く、毎年ほぼ確実に出題されます。内容は一見するとバラバラに見えますが、根底にあるのは「論理的に考える力」です。
・AさんはBさんに勝った。BさんはCさんに勝った。→では、AさんとCさんは?
・3人の中で背が高いのは誰?条件を元に順位を導けるか?
・ある条件のもとで、正しい選択肢はどれ?
このように、限られた情報から筋道を立てて結論を出す力が問われます。言い換えれば、「ひらめき」よりも「整理力」と「粘り強さ」が大事な分野といえます。
また、企業によっては「問題数が多く、時間に追われる形式」で出題されるため、素早く情報を把握して判断するスキルも求められます。つまり、ただの知識ではなく“実践的な思考力”が試されるのです。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
推論の出題形式
SPIの推論問題には、さまざまなタイプがあります。どれも共通して「条件整理」がカギになりますが、形式ごとの特徴を知っておくことで対策しやすくなります。
ここでは、代表的な出題パターンを6つ紹介します。
正誤問題
与えられた複数の条件と、いくつかの選択肢(文章)が提示され、それぞれが「正しいのか」「誤っているのか」を判断するタイプの問題です。
- 条件をもとに、すべての選択肢を検証する必要がある
- 「○○である」「○○でない」といった言い回しの違いに注意
正誤問題は、1つ1つの文を丁寧に検証しながら消去していく“慎重さ”が求められます。
例題
ある町にはA店、B店、C店の3つのスーパーがある。以下はそれぞれの店舗に関する事実である。
・A店では毎週火曜日に特売が行われる。
・B店は日曜日には閉店している。
・C店は毎日開いているが、特売は週1回のみである。
次の文のうち、正しいものをすべて選びなさい。
1.B店は火曜日に特売を行っている。
2.C店は土曜日にも営業している。
3.A店では週に2回特売がある。
4.B店は週7日すべて営業している。
【答え】
正しいのは2番のみ。
【解説】
1→B店の特売について記載なし。×
2→C店は毎日営業。○
3→A店は火曜のみ特売。×
4→B店は日曜休みなので×。
対戦結果からの推論
複数の人物やチームが対戦した結果をもとに、誰が最も強いか・勝敗の関係はどうかなどを推測する問題です。
- AはBに勝ち、Cに負けた→どんな順位になるか?
- 勝った・負けたが入り混じるため、全体像を図で描くと整理しやすい
情報の抜けや勘違いが起きやすいため、「見える化」が非常に有効です。
例題
3人の学生、Aさん、Bさん、Cさんがじゃんけん大会を行いました。結果は次の通りです。
・AさんはBさんに勝った。
・BさんはCさんに勝った。
このとき、次のうち正しいといえるものはどれか。
A. AさんはCさんにも勝った。
B. CさんはAさんに勝った。
C. Aさんが最も強かったとは限らない。
D. Cさんは誰にも勝っていない。
【答え】
正解:CとD
【解説】
A→直接対戦の記述がないため不明。×
B→同上。×
C→AはBに勝ち、BはCに勝ったが、AとCの直接対戦結果がないため断定できない。○
D→CはBに負けている記載あり、勝った記載なし。○
割合の関係性
条件の中に「○割の人がAを選んだ」などの比率情報が出てくるパターンです。
- 人数や比率の関係を数式で表して考える
- 逆に、「何人か不明」という条件をもとに仮定して解くこともある
特に苦手な人が多いのがこの形式。割合や比率の基礎が理解できていないと混乱しやすいため、事前の復習も必要です。
例題
ある学校の100人の生徒のうち、A部に所属しているのは60人。そのうち40%がB部にも所属している。
このとき、A部とB部の両方に所属している生徒は何人か?
【答え】
24人
【解説】
A部の60人のうち40% → 60 × 0.4 = 24人
平均値と条件の関係
平均値を使って、ある数値を導くタイプの問題です。
- 「3人の平均点が60点で、Aが70点、Bが50点のとき、Cは?」
- 条件を式にして整理することで正解に近づける
中学校レベルの数学知識があれば解ける内容なので、基本の「平均=合計÷人数」の使い方は必ず復習しておきましょう。
例題
3人のテストの平均点は80点である。Aさんは90点、Bさんは85点だった。
このとき、Cさんの点数は何点か。
【答え】
65点
【解説】
平均80点 × 3人 = 合計240点
A+B = 90+85 = 175点
→ C = 240 − 175 = 65点
整数条件を使った推理
条件に出てくる数値をもとに、成り立つ数字の組み合わせやパターンを推理する問題です。
- 「AとBはどちらも偶数」「合計は10以下」などの条件から導く
- 数の特徴(偶数・奇数、倍数など)を活用する力が求められる
簡単そうに見えても、情報が複数重なると整理が難しくなるため、メモや表の活用がポイントです。
例題
XとYはともに1〜10の整数で、次の条件を満たしている。
・Xは偶数
・YはXより小さい
・X+Y=10
このとき、Xの値として考えられるのはどれか。
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
【答え】
B. 4、C. 6、D. 8
【解説】
条件を満たす組み合わせは:
X=4, Y=6 → OK(偶数、Y < X、合計10)
X=6, Y=4 → OK
X=2 → Y=8(Y > X)→×
X=8 → Y=2(OK)→ 8+2=10 → OK だが Y<Xではない → ×
※YがXより小さいのでX=8, Y=2はOK(失礼)、したがって正解はB, C, D
位置関係や順序の整理
人や物の並び順、場所の位置関係から正しい配置を推理する問題です。
- 「Aの左隣にはBがいる」「CはDより前にいる」などの条件が多い
- 矛盾がないように仮置きして整理するのがコツ
視覚的に整理しやすいタイプの問題なので、図や簡単な表を使いながら解くと正答率が上がります。
例題
5人の生徒A〜Eが縦一列に並んでいます。以下の条件に従って並び順を推測してください。
・AはCの前にいる。
・DはBのすぐ後ろにいる。
・Eは一番後ろにいる。
このとき、先頭にいる可能性があるのは誰か。
【答え】
B
【解説】
DはBのすぐ後ろ → B-Dの並び固定
Eは最後尾 → 5番目に確定
AはCより前 → AはCより上
→ B-D以外の並び:A、C、E
→ A, Cの関係から A < C
→ 一例:B-D-A-C-E(成立)
→ 先頭はBの可能性あり
これら6つの形式は、SPIの推論問題で繰り返し出題される定番パターンです。すべてに共通して言えるのは、情報の「読み取り力」と「整理力」が問われるということ。
推論を解くコツ
SPIの推論問題は、「読み取って、整理して、推理する」までの思考プロセスがカギとなります。特別な知識は不要ですが、解き方にはちょっとしたコツがあります。ここでは、効率よく解くための基本的な考え方と習慣を紹介します。
「情報の整理」と「仮定検証」がカギ
推論問題の最大のポイントは、「何が与えられていて、何が問われているか」を正しく整理することです。
- 問題文に線を引きながら読む
- 条件を1つ1つメモにまとめる
- 結論を出す前に、仮定を立てて検証する
たとえば、「AはBより背が高く、Cより低い」といった条件があれば、AはB>A>Cといった並びであると仮定し、それが矛盾しないかを確認していきます。
「仮定してみる」→「矛盾があるか検証」→「正しければそのまま使う」というサイクルを意識することで、答えにたどり着きやすくなります。
図や表を書いて視覚化する習慣をつける
頭の中だけで考えようとすると、情報が混乱してしまいがちです。紙に書き出すことで、より正確な判断ができるようになります。
- 人物の順位や並び順は、図で線を引いて表現
- 条件を表にして整理する(例:AはBより大きい→○×などで表す)
- 数字が出てくる場合は、メモとして「仮の数字」を置いてみる
視覚化することで、複雑に見える問題もぐっとシンプルに見えるようになります。
このような考え方と習慣を身につけることで、難しいと思っていた推論問題もスムーズに解けるようになります。続いては、より得点を伸ばすための「対策のポイント」について解説していきます。
推論の対策ポイント
SPIの推論問題は、ただ解き方を知るだけでなく、「試験本番でどう対応するか」までを見越した準備が必要です。ここでは、限られた時間の中で得点を最大化するためのポイントをお伝えします。
時間をかけすぎず「見切る力」も大事
推論問題は1問1問のボリュームが多いため、時間をかけすぎてしまうと他の問題に手が回らなくなってしまいます。
- 1問あたりの目安は約1分〜1分半
- 解けそうにないと感じたら、すぐ次の問題に進む勇気も必要
- 消去法や最小限の条件検証で、短時間で解く訓練を積む
「全部正解する」よりも「取れる問題を確実に取る」ことが重要です。
覚えておくべき基本パターン
繰り返し出題されるパターンには、あらかじめ「型」を覚えておくと対応しやすくなります。
- 対戦結果を表に整理する方法
- 順序整理問題での仮置きの手順
- 正誤問題で条件を1つずつ検証する流れ
過去問や問題集を使って、似た形式の問題を繰り返し解くことで、初見でも「あ、このパターンだな」と気づけるようになります。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPI推論の練習問題3つ
最後にSPIの推論問題の代表的な形式を3問紹介します。それぞれに対して、問題文と解き方のポイントをセットで掲載します。演習として解いてみてください。
問題1:位置関係の推論
Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさんの5人が横一列に並んでいます。以下の条件をもとに、各人の並び順を推測してください。
・AさんはCさんの右隣にいる
・BさんはDさんの左隣にいる
・Eさんは一番端にいる
このとき、Aさんは何番目に並んでいるか?
【考え方】
まずは与えられた条件を図で整理しましょう。
・「AさんはCさんの右隣」→AはCのすぐ右
・「BさんはDさんの左隣」→BはDのすぐ左
・「Eさんは端」→左端または右端に位置
並び方のパターンを仮定して、条件と矛盾がないように埋めていくと、以下の並びが成り立ちます。
左から:E→C→A→B→D
この場合、Aさんは左から3番目に位置します。
【答え】
3番目
問題2:対戦結果の推測
Aさん、Bさん、Cさんの3人がじゃんけんをしました。結果は以下の通りです。
・AさんはBさんに勝った
・CさんはAさんに負けた
このとき、BさんとCさんの勝敗はどうなるか?
【考え方】
まず、勝敗を図にしてみます。
A>B(AがBに勝ち)
A>C(AがCに勝ち)
この場合、AはBにもCにも勝っています。
ただし、BとCの直接対決は不明です。つまり「情報が足りず、勝敗は判断できない」のが正しい答えです。
SPIでは、あえてこうした「判断できない」選択肢を用意してくることがあるので、「わからない」と答えるべき問題を見抜けることも重要です。
【答え】
判断できない
問題3:正誤判定の条件整理
あるクラスにはAさん、Bさん、Cさん、Dさんの4人がいます。以下の条件が与えられています。
・AさんはBさんより背が高い
・CさんはDさんより背が低い
・BさんはCさんより背が高い
このとき、正しいと言えるものを次の中から選びなさい。
1.Aさんは全員の中で一番背が高い
2.DさんはAさんより背が低い
3.BさんはDさんより背が低い
4.CさんはBさんより背が高い
・A>B
・C<D
・B>C→A>B>C
→DはCより高いので、A>B>C<D
【考え方】
条件を順番に整理します。
ここからDの位置がまだ不明確ですが、C<DかつB>Cなので、DがBより高いとは断定できません。
選択肢を検討すると、確実に正しいのは「1.Aさんが一番背が高い」です。他の人物はAさんに届かないためです。
【答え】
1.Aさんは全員の中で一番背が高い
以上が、SPI推論の練習問題3問です。実際に解いてみて、どのように条件を整理するか、仮定からどう結論を導くかのプロセスに慣れておくことが重要です。
まとめ|推論対策は「整理」と「慣れ」が決め手
SPIの推論問題は、一見すると複雑に見えるかもしれませんが、実はパターンとコツをつかめば着実に得点できる分野です。特に就活本番のSPIでは、どれだけ落ち着いて情報を整理し、素早く正確に判断できるかが大きな差になります。
最初こそ難しく感じるかもしれませんが、地道に取り組めば必ず実力がついてきます。
この記事で紹介した出題形式や解法のコツ、練習問題などを活用して、自信を持ってSPI本番に臨めるよう準備を進めていきましょう。