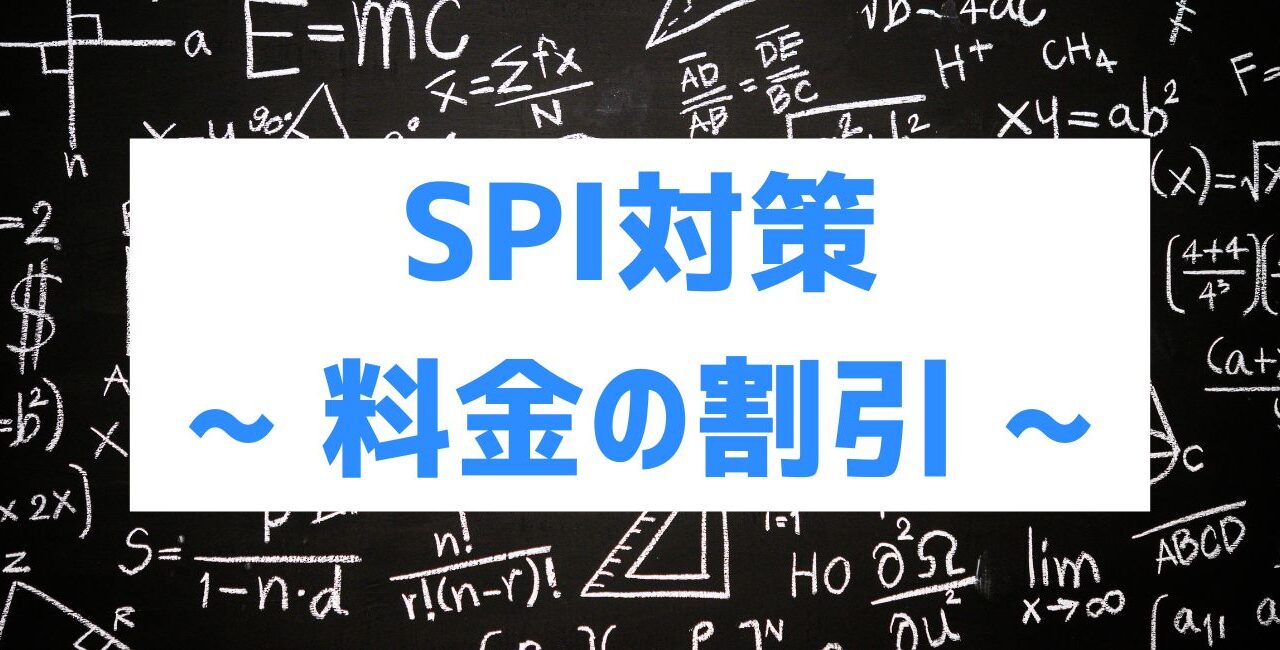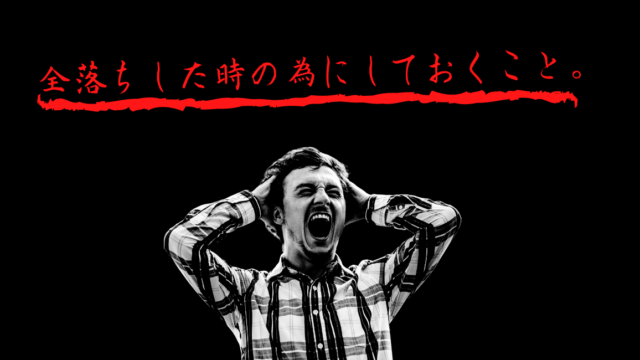【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
SPIの非言語分野の中でも、「料金の割引」問題は日常生活に近い内容で出題されるため、一見わかりやすそうでいて意外と間違えやすいジャンルです。
「30%OFFの商品を2つ買ったら?」「2割引のあと、さらに10%引きってどう計算するの?」といったように、見慣れた表現でも、正確に計算しようとすると戸惑う人も少なくありません。
そこでこの記事では、SPIに出題される「料金の割引」問題を徹底的に解説します。
基本の考え方から、割引率の計算方法、2段階割引といった応用パターンまで、すべて網羅的に解説。最後には実践的な練習問題も紹介しているので、本番対策にもぴったりです。
数学が得意でない人も、この記事を読み終える頃には自信を持って割引計算ができるようになるはずです。ぜひ最後までチェックしてみてください。
目次
料金の割引とは
SPIの非言語分野に出題される「料金の割引」問題とは、定価に対して一定の割合で値引きが行われたとき、実際の支払額や割引額を求める問題です。たとえば、次のような出題形式が典型です。
- 「定価800円の商品を25%引きで販売した。販売価格はいくらか」
- 「2,000円の商品を10%引きで販売したときの割引額はいくらか」
- 「1回20%引きのあと、さらに10%引きされた商品の最終価格を求めよ」
このように、SPIの割引問題では、割合の計算(%)と、そこからの価格計算が求められます。
特に重要なのは、「割引率=そのまま引くだけではない」という点です。よくあるミスとして、「20%引きのあと10%引き=30%引き」としてしまうケースがありますが、実際は違います。これは2段階割引という別の計算方法になるので、注意が必要です。
SPIの割引問題は、考え方がシンプルな分、正しい公式と数字の扱い方を知っているかどうかが大きな差を生む分野です。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
料金の割引の出題形式
SPIの割引問題では、「単品の割引」「複数商品の割引」「2段階割引」といったパターンが出題されます。ここでは、それぞれの出題形式について具体例を交えて解説します。
割引率から販売価格を求める問題
最も基本的な問題形式です。定価と割引率が与えられ、実際に支払う販売価格を求めるものです。
【例題】
定価1,200円の商品を30%引きで販売する。このときの販売価格を求めなさい。
【解き方】
割引率30%=0.3
販売価格=定価×(1−割引率)
=1,200×(1−0.3)=1,200×0.7=840円
【ポイント】
- 「割引後の価格=定価×(1−割引率)」をそのまま使う
- %は必ず小数に直してから計算
複数商品の合計割引額を求める問題
この形式では、複数の商品の割引額をそれぞれ求め、合計金額を出す力が問われます。スピード感と整理力が必要です。
【例題】
定価1,000円の商品を20%引き、定価2,000円の商品を10%引きで販売した。それぞれの割引額の合計はいくらか?
【解き方】
・1,000円の商品→割引額=1,000×0.2=200円
・2,000円の商品→割引額=2,000×0.1=200円
→合計割引額=200+200=400円
【ポイント】
- 割引額をそれぞれ計算して合計
- 販売価格ではなく「割引額」が問われている場合に注意
複数回の割引(2段階割引)問題
この形式は応用問題としてよく出ます。「まず20%引き、次にさらに10%引き」といったように、割引が連続して適用されるケースです。
【例題】
定価10,000円の商品を、まず20%引きで、さらに10%引きで販売した。最終的な販売価格はいくらか?
【解き方】
①1回目:10,000×(1−0.2)=10,000×0.8=8,000円
②2回目:8,000×(1−0.1)=8,000×0.9=7,200円
【ポイント】
- 2段階割引は「順番に割引後の価格に次の割引をかける」
- 単純な「20%+10%=30%」とはならない
料金の割引を解くコツ
SPIの割引問題を素早く、そして正確に解くためには、「計算の型」と「数字の扱い方」に慣れておくことが大切です。ここでは、問題を解くときに意識しておきたい基本的なコツを2つ紹介します。
「割引後の価格=定価×(1−割引率)」を覚える
まず絶対に押さえておきたい公式がこれです。
割引後の価格=定価×(1−割引率)
割引率を100%から引いた割合で計算することで、すぐに販売価格を出すことができます。
【例】
定価2,000円の商品を25%引きで販売
→割引後の価格=2,000×(1−0.25)=2,000×0.75=1,500円
このように、販売価格を直接求めることができるため、割引額をいちいち引いてから販売価格を出すよりも計算が速く、正確性も上がります。また、2段階割引のような複雑な問題でも、この式を順に適用すれば対応可能です。
%を小数に変換して計算の効率化を図る
SPIでは、計算スピードも重要です。そこでポイントとなるのが、%を小数に変換する習慣を身につけることです。よく使う%と小数の変換例は以下の通りです。
- 10%→0.1
- 20%→0.2
- 25%→0.25
- 30%→0.3
- 50%→0.5
- 75%→0.75
また0.8=20%引き、0.9=10%引きなど、逆に小数から割引率をすぐ想起できると便利です。
特に注意したいのは、2段階割引のように連続して計算する場合。一度でも割引率を間違えると、答えが大きくズレてしまうため、正確な小数化が重要になります。
料金の割引の対策ポイント
割引問題は、基本の計算さえできれば得点しやすいジャンルですが、出題パターンによって必要なアプローチが少しずつ異なるため、事前の準備が重要です。ここでは、試験本番でミスを防ぐための具体的な対策ポイントを2つ紹介します。
金額ベースと割合ベースの切り替えが重要
SPIの割引問題では、「販売価格はいくらか」と聞かれることもあれば、「割引額はいくらか」「割引率はいくらか」といったように、出題の観点が異なることがあります。たとえば、以下のような違いです。
- 金額ベース→「いくら安くなるか」「いくら支払うか」
- 割合ベース→「何%引きか」「元の価格に対して何割の値引きか」
これらの違いを意識せずに計算してしまうと、答えは合っていても単位が違う(販売価格を聞かれて割引額を答えてしまう)といったミスにつながります。
【対策法】
- 問題文を読んだら、「求めるのは金額か?割合か?」を明確に意識する
- 計算前に、「定価・割引率・販売価格・割引額」のうち何が与えられているかを整理
2段階割引に注意して練習しておく
SPIで間違えやすいのが「2段階割引」です。1回目の割引と2回目の割引が連続して適用されるパターンですが、単純に割引率を合計してはいけません。
【例】
定価10,000円の商品を「20%引きのあとに10%引き」で販売した場合
誤答例:
20%+10%=30%引き→10,000×0.7=7,000円←これはNG
正しい計算は、
・1回目:10,000×0.8=8,000円
・2回目:8,000×0.9=7,200円
2段階割引は「連続して減らす」という考え方が必要です。これは就活生にとって馴染みが薄く、ミスが多いポイントなので、実際に何度も問題を解いて体に覚えさせるのが効果的です。
【対策法】
- 「1回ごとに価格を更新する」意識を持つ
- 練習問題ではあえて2段階割引に絞って解く日を作ると効果的
料金の割引の練習問題3つ
ここでは、SPIで出題されやすい割引問題の形式をカバーした練習問題を3つ用意しました。単一商品の割引から、複数商品、2段階割引まで幅広く対応しています。本番を想定して、できれば計算用紙を用意しながら取り組んでみてください。
問題1:単一商品の割引計算
【問題】
定価3,600円の商品を25%引きで販売した。販売価格はいくらか?
【解き方】
・割引率25%→0.25
・販売価格=3,600×(1−0.25)=3,600×0.75=2,700円
【答え】
2,700円
問題2:複数商品の割引額の合計
【問題】
A商品(定価2,000円、10%引き)と、B商品(定価3,500円、20%引き)を購入したときの割引額の合計を求めなさい。
【解き方】
A:2,000×0.1=200円
B:3,500×0.2=700円
合計割引額=200+700=900円
【答え】
900円
問題3:2段階割引の総額を求める問題
【問題】
定価5,000円の商品が、まず20%引きされ、その後さらに15%引きされた。最終的な販売価格はいくらか?
【解き方】
1回目:5,000×0.8=4,000円
2回目:4,000×0.85=3,400円
※2段階割引は順番に適用する!
【答え】
3,400円
これらの問題をスムーズに解ければ、SPI本番でも割引問題に自信を持って取り組めるはずです。特に2段階割引の処理はミスが起きやすいので、計算過程を正確に追えるように練習しておくと安心です。
まとめ
SPIにおける「料金の割引」問題は、一見簡単そうに見えて、実は細かなミスが起きやすい分野です。しかし、しっかりと計算の基本とパターンをおさえておけば、安定して高得点を狙えるジャンルでもあります。
焦らず、着実に。今日から少しずつ練習を積んでいけば、SPI本番ではきっと自信を持って割引問題に取り組めるようになります。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。