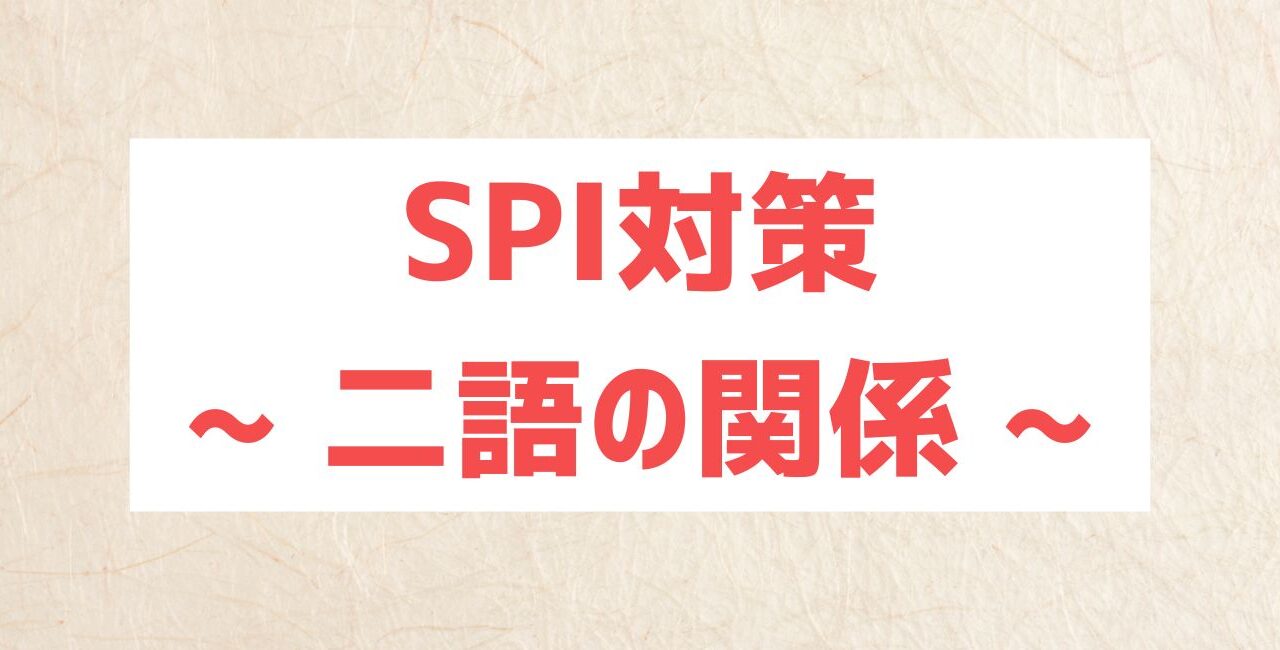【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「二語の関係って、なんとなくで選んじゃってる…」
「語彙に自信がないから、意味が似てるだけで選んでしまう…」
SPIの言語分野には、数ある問題形式の中でも論理的な思考力+語彙力が問われる「二語の関係」というジャンルがあります。一見シンプルに見えますが、「正確な関係性の見極め」ができていないと、迷いやすい問題のひとつです。
この記事では、
・SPIの二語の関係ってどんな問題?
・よく出るパターンは?
・どうやって解けばいい?
・苦手でも解けるようになる方法は?
といったポイントを、練習問題付きで丁寧に解説していきます。
語彙力や読解力に自信がなくても、コツとパターンを掴めばしっかり得点できるジャンルなので、ぜひ読み進めてみてください。
SPIの二語の関係とは
SPIにおける「二語の関係」は、2つの単語の間にある意味的なつながりを考え、それと同じ関係になっている語句のペアを選ぶ問題です。たとえば、以下のような問題が出されます。
例題
「親:子」と同じ関係の語句はどれか?
・教師:生徒
・医者:患者
・花:つぼみ
・子:孫
・上司:部下
この場合、「親:子」は血縁関係の上位・下位の関係です。同じように直接的な上下の関係を持つ語句は「子:孫(4)」が最も近いため、正解になります。
つまり、この問題のポイントは、「単語の意味を知っているか」ではなく、「その2語の関係性を論理的に捉えられるか」です。
二語の関係には、いくつかの代表的なパターンがあります。次のセクションでは、SPIで特によく出る3つの関係性を紹介していきます。パターンを知っておくだけで、解答の精度がぐんと上がりますよ。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPI二語の関係でよく出る問題
SPIの二語の関係問題には、出題されやすい定番のパターンがあります。すべての問題がこれらの型に当てはまるわけではありませんが、多くの問題は次の3つの関係性のいずれかに分類できます。
反対語・同義語の関係
最も基本的で頻出なのが「対義語」や「類義語」の関係です。
たとえば、
・暑い:寒い(反対語)
・正解:答え(類義語)
このような語句ペアと同じ関係のものを選ぶ問題がよく出ます。
例題
「始める:終わる」と同じ関係のものはどれか?
・高い:安い
・増える:減る
・行く:来る
・成功:失敗
・集める:散らかす
→この場合は、「始める:終わる」=反対語の関係です。
最も自然な対義語の関係になっているのは「増える:減る(2)」なので正解です。
このタイプでは、「この2語は何がどう違うのか?」を一言で言い表せるようにすると、判断がしやすくなります。
包含・部分の関係
ある語がもう一方の語を含んでいる関係、または一部を構成するような関係性もよく出ます。
- 鳥:カラス(カラスは鳥の一種)
- スポーツ:野球(野球はスポーツの一種)
このような「AはBの一種」「Bの中にAがある」という関係を見抜く問題です。
例題
「果物:りんご」と同じ関係のものはどれか?
・植物:花
・果物:野菜
・犬:動物
・色:赤
・本:ページ
→「果物:りんご」=「りんごは果物の一種」→「色:赤(4)」が同じ関係です。
ポイントは、「下位語と上位語の関係か?」を問いかけること。「○○は△△の一種か?」と自問すると、正解にたどり着きやすくなります。
因果・手段と目的の関係
やや難易度が高いのが、因果関係(原因と結果)や手段と目的の関係です。
・火事:消火(火事を起因として消火が行われる)
・包丁:切る(包丁は切るための道具)
このように「なぜ?」「何のために?」といった視点で考える必要があるため、言語的な理解力が求められます。
例題
「病気:治療」と同じ関係のものはどれか?
・薬:効果
・勉強:合格
・ケガ:応急処置
・寝る:疲れ
・食事:健康
→「病気を治すために治療する」=「ケガを治すために応急処置をする(3)」が最も近いです。
このタイプの問題は、2語の間に「○○するために△△」「○○が原因で△△」という文章を補ってみると、関係性が明確になります。
これらの関係パターンを押さえておくことで、「どこを見て比較すればいいか」が分かりやすくなります。次は、これらをどう見抜き、どう考えるかという解き方のコツについて紹介していきます。
SPI 二語の関係を解くコツ
問題のパターンを知っていても、実際に解く際には「この2語はどういう関係だろう?」と戸惑うこともあるはずです。そんなときは、以下の3つのコツを意識してみてください。
どれもすぐに使える実践的な考え方で、迷ったときのヒントになります。
コツ①:まず2語の関係性を日本語で言語化してみる
最初にすべきことは、問題文に出てくる2語の関係を自分の言葉で説明してみることです。
- 「先生:生徒」
→「教える人と教えられる人」
→「立場が対になっている関係」 - 「雪:氷」
→「どちらも水が凍ったもので、雪は粒子状、氷は固体のかたまり」
→「似た性質をもつが、形態の異なる同種のもの」
このように、「~と~は〇〇な関係」と一言でまとめてみると、選択肢との比較がしやすくなります。特に、漠然とした言葉の意味に引っ張られるのではなく、関係性そのものに焦点を当てるのがポイントです。
コツ②:選択肢を入れ替えて文として意味が通るか試す
選択肢が与えられたとき、ただ意味を比べるだけでなく、「文章として使ってみる」ことで違和感をチェックするのも有効な方法です。
たとえば、「料理:包丁」という関係に対して、選択肢の「音楽:楽器」があるとします。
→包丁は料理に使う道具→楽器は音楽に使う道具
→「道具と目的」の関係なので、意味は通っている
一方で、「料理:包丁」に対して「本:知識」などがあると、「知識を得るために本を使う」という間接的な関係で、少しズレていると判断できます。
このように、「言い換えたときに文として自然かどうか」を基準にして考えることで、迷った選択肢を減らすことができます。
コツ③:「〜は〜の一種」など関係性の公式パターンを活用
問題を解く際には、定型文に当てはめてみると関係性を見抜きやすくなります。以下は代表的な公式パターンです。
- AはBの一種→「犬:動物」「トマト:野菜」
- AはBの反対→「勝利:敗北」「暑い:寒い」
- AはBをするための道具→「包丁:切る」「ペン:書く」
- Aが原因でBが起こる→「けが:出血」「風邪:発熱」
これらの文章を「問題の語句に当てはめてみる」ことで、選択肢とのズレを見抜きやすくなります。迷ったときほど、こうした型を使って関係を明確にすると良いでしょう。
この3つのコツを意識することで、なんとなくの語感で選ぶのではなく、論理的に正しいペアを選べるようになります。
SPI二語の関係の対策ポイント
SPIの二語の関係問題は、出題形式がシンプルな分、差がつきやすい分野です。
だからこそ、事前にしっかりと対策しておけば、得点源に変えることができます。
ここでは、短期間でも効果が出やすい3つの対策ポイントを紹介します。語彙力や論理力に自信がない人こそ、基本をおさえて効率よく対策しましょう。
ポイント①:頻出の関係パターン(類義語・対義語など)を暗記
まず取り組みたいのが、二語の代表的な関係パターンを見て分かるレベルで覚えることです。以下のような関係は特に頻出なので、例を押さえながら何度も確認しましょう。
- 類義語→「困難:苦難」「努力:精進」
- 対義語→「賛成:反対」「進歩:後退」
- 包含関係→「果物:ぶどう」「動物:馬」
- 因果関係→「疲労:休息」「失敗:反省」
- 目的と手段→「登山:地図」「料理:鍋」
ただ単語を覚えるだけでなく、「このペアはどういう関係?」と自問して、言語化する練習をセットにするのがポイントです。
ポイント②:言い換えの練習を通じて語彙の幅を広げる
語彙が少ないと、そもそも語句の意味や関係を理解することが難しくなります。特に類義語・対義語のパターンは、語彙の豊かさが正解率に直結します。対策としては、以下のようなものが効果的です。
- 1語につき3つ以上の言い換え語を考える(例:嬉しい→楽しい・喜ばしい・幸せ)
- 新聞・ニュース記事の見出しを読み、知らない単語は調べてストック
- SPI用語帳やアプリで、類語・対義語をまとめてチェック
語彙の幅が広がると、自然と選択肢を感覚ではなく関係性で判断できるようになります。
ポイント③:ペアの語句を分類・整理して記憶する
ただ語句を覚えるだけでなく、関係性ごとに分類して記憶することで、問題に出てきたときの気づきが早くなります。
たとえば、以下のようなリストを自分で作ってみると良いでしょう。
- 【対義語】多い⇔少ない、高い⇔低い、攻撃⇔防御
- 【類義語】確認=点検、改善=向上、作成=作製
- 【包含】楽器→ピアノ、動物→ネコ、言語→英語
- 【因果】勉強→合格、暴風→停電、睡眠不足→集中力低下
- 【手段と目的】運転→移動、火→料理、筆→描く
こうした関係性別の語彙マップを作ることで、実際の試験でもすぐに関係性に気づけるようになります。
「暗記+整理+言い換え」の3ステップを習慣化することで、SPIの二語の関係は安定して得点できるジャンルになります。次は、実際の出題をイメージした練習問題で、ここまでの知識を定着させましょう。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPI二語の関係練習問題3つ
ここでは、実際のSPIの出題傾向を意識した「二語の関係」練習問題を3つ紹介します。解答と簡単な解説もつけているので、コツを意識しながら取り組んでみてください。
問題1:対義語の関係性問題
次の語句ペアと同じ関係のものを選びなさい。
「上昇:下降」
・運転:歩行
・乾燥:湿気
・勉強:学習
・笑顔:怒り
・出発:移動
【正解】
2.乾燥:湿気
【解説】
「上昇:下降」は、上下という方向の反対の関係です。同様に、「乾燥(乾いている状態)」と「湿気(湿っている状態)」も状態が真逆なので、正しい対義語ペアです。1と3は関連語、4と5は因果・部分関係に近いため不正解です。
問題2:包含関係の語句ペア
「果物:りんご」と同じ関係の語句ペアを選びなさい。
・海:魚
・車:自動車
・犬:動物
・飲み物:ジュース
・人間:家族
【正解】
4.飲み物:ジュース
【解説】
「りんごは果物の一種」=下位語と上位語の関係(包含関係)。同様に、「ジュースは飲み物の一種」であるため、4が正解です。1は包含関係のように見えますが、「魚は海にいる」=場所と生物の関係であり、ズレがあります。
問題3:因果関係の適切な語句選び
「運動:疲労」と同じ関係のものを選びなさい。
・勉強:知識
・火災:煙
・睡眠:快眠
・音楽:感動
・道具:作業
【正解】
2.火災:煙
【解説】
「運動した結果、疲労が起こる」=原因→結果の因果関係です。同様に、「火災が起きると煙が出る」も明確な因果関係なので、2が正解です。
1や4は目的と結果の関係に近く、少し違った分類になります。
このように、問題に取り組むときは「この2語はどんな関係なのか?」を文章にして説明できるかどうかがカギになります。
まとめ
SPIの「二語の関係」問題は、語彙力だけでなく論理的な思考力も試される分野です。ですが、よく出るパターンを知り、関係性を言語化する練習を重ねれば、安定して得点できるジャンルになります。
特に類義語・対義語・包含・因果関係といった代表的な関係性は繰り返し出題されるため、対策の効果が出やすいのが特徴です。この記事で紹介したコツや対策方法を活用し、練習問題で実践力を高めていくことで、自信を持って本番に臨めるようになるでしょう。