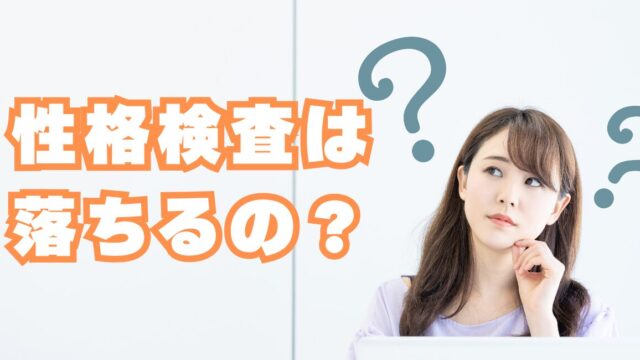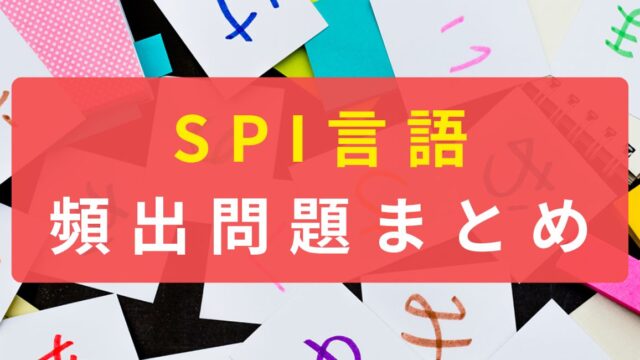【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
就活を進めていく中で、多くの学生が最初につまずくのが「SPI(総合適性検査)」です。選考の早い段階で登場し、これが通らなければ面接にも進めないため、「SPIが無理ゲーすぎる」と感じてしまうのも無理はありません。問題の難易度や制限時間の厳しさ、見慣れない出題形式に圧倒され、何から対策すればいいのかさえわからなくなるケースも少なくありません。
しかし、SPIはしっかりと対策をすれば誰でもある程度得点を伸ばすことができるテストです。「苦手だから」「もう間に合わないから」と諦めてしまうのではなく、まずは原因を知り、できるところから克服していきましょう。
この記事では、SPIが「無理ゲー」と言われる理由や、得点が伸び悩む人の特徴、そして実際に効果的な対策方法までを詳しく解説します。SPIに不安を感じている就活生にとって、少しでも突破の糸口が見つかるような内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
SPIが「無理ゲー」に感じる主な理由とは?
SPIを「無理ゲー」と感じる就活生は少なくありません。その背景には、学力や努力不足だけでは語れない、さまざまな理由があります。ここでは、多くの学生がつまずく原因を5つの視点から掘り下げてみましょう。
中学・高校の内容を忘れている
SPIの問題は中学〜高校レベルの学力を前提に作られており、特に非言語分野では数学の知識が問われます。しかし、文系学生を中心に「もう何年も数学を勉強していない」という人も多く、基本的な公式や考え方を忘れてしまっているのが現実です。たとえば、速さの問題や割合、確率などは出題頻度が高いにもかかわらず、「解き方すら思い出せない」という声が多く聞かれます。
知識が抜け落ちている状態で時間制限のある問題に直面すれば、焦りと混乱が生まれるのは当然です。そのため、「全然解けない」「無理ゲーすぎる」と感じることにつながってしまいます。
制限時間がとにかく短すぎる
SPIの最大の難点とも言えるのが「時間の短さ」です。1問あたりの制限時間が非常にタイトで、特に非言語分野では1問に1分もかけていられません。計算を丁寧にやっているとすぐに時間切れになり、途中で全く手を付けられない問題が残ってしまうこともあります。
時間に追われると冷静な判断力が鈍り、ミスが増えてさらに得点が伸びにくくなる悪循環に陥ります。問題の内容以前に、試験のスピード感そのものが「無理ゲー」と感じさせる要因になっているのです。
問題形式に慣れておらず焦る
SPIには独特の出題形式があります。たとえば、ベン図を使った集合問題、図表の読み取り、長文読解など、普段の学業ではあまり触れない形式の問題が多く出題されます。これに初見で対応しようとすると、内容自体は理解できても解き方がわからず、焦ってしまうことになります。
問題のパターンに慣れていないことが、実力以上の不安や緊張を引き起こし、「自分には無理」と感じさせてしまう原因となります。
英語・構造把握など苦手分野が足を引っ張る
SPIでは企業によって英語問題や構造把握といった追加科目が課されることもあります。特に英語に苦手意識を持っている学生にとっては、単語の意味や文法の理解不足から「全く読めない」という状態になることも少なくありません。
また、構造把握問題は論理的な読解力が求められ、「なんとなく」で解くことが難しい分、慣れていない人にとっては高い壁になります。こうした苦手分野があると、「得点が伸びない」「対策のしようがない」と感じやすくなり、結果的にSPI全体への苦手意識が強まります。
性格検査に「正解」がなく不安になる
SPIには学力試験だけでなく、性格を測る「性格検査」も含まれます。こちらは一般的な筆記試験とは異なり、正解・不正解が存在しません。そのため、「この回答で本当にいいのか」「変な性格だと思われないか」といった不安が生まれやすいです。
さらに、学力試験の点数が良くても性格検査で評価が下がるケースもあるため、「努力ではどうにもならない無理ゲー」と感じてしまう就活生も多くいます。
SPIが解けない人の特徴と共通点
SPIで苦戦している人には、ある共通した傾向があります。もちろん、個々の背景や学習状況にもよりますが、ここではSPIを「無理ゲー」と感じる人によく見られる4つの特徴について解説します。自分に当てはまる部分がないかチェックしてみてください。
時間配分が苦手で途中で終わる
SPIは制限時間が非常に厳しいテストであり、各問題にかけられる時間がごく限られています。そのため、すべての問題をじっくり解こうとすると、途中で時間切れになってしまうことが多々あります。
特に非言語分野では、計算問題や図を使った問題に手間取ってしまい、「2割しか解けなかった」という人も少なくありません。時間配分の感覚が身についていないまま本番を迎えると、実力以前に「試験として成立しない」状態に陥りやすいのです。
問題の読み違い・勘違いが多い
SPIは問題文が短くても情報量が多く、正確な読解が求められます。焦って読むと主語と目的語を取り違えたり、条件を読み落としたりといったミスが発生しやすくなります。
特に図表や推論系の問題では、1つの言葉の解釈ミスが大きな失点につながります。こうした「読み違い」を連発してしまう人は、本来の実力を出せずに終わってしまい、結果として「SPIは難しすぎる」と感じるようになります。
苦手分野を放置している
SPIには得意・不得意が分かれやすい分野があります。たとえば、文系の学生であれば非言語分野、理系の学生であれば長文読解や英語が苦手というケースが多く見られます。
しかし、苦手だからといって何の対策もしないままにしておくと、得点に大きな差が生まれてしまいます。SPIは総合点で判断されることが多いため、苦手分野を完全に放置すると合格基準に届かなくなるリスクが高くなります。
対策せずにぶっつけ本番で受けている
SPIを初見で受けて「全然解けなかった…」という人も多いですが、それは当然です。SPIはある程度の対策を前提としたテスト設計になっており、特に非言語問題は慣れていないと解法のイメージすら持てません。
「SPIは中学レベルだから簡単」と思って油断した結果、実際の出題形式や時間制限に対応できず、「自分には無理だ」と落ち込む学生も多くいます。事前の準備不足が「無理ゲー化」を加速させてしまうのです。
SPI=無理ゲーを克服するための現実的な対策法
SPIを「無理ゲー」と感じてしまうのは、慣れや準備が不足していることが大きな原因です。逆に言えば、出題傾向を知り、効率的な対策を講じることで、少しずつでも確実に得点を伸ばすことができます。ここでは、現実的に取り組みやすい対策方法を段階的に紹介します。
まずは頻出分野を絞って対策する
全範囲をまんべんなく対策しようとすると、時間がいくらあっても足りません。そこで重要になるのが、出題頻度の高い分野に的を絞ることです。まずは以下のような分野から着手するのが効果的です。
言語:語彙問題と長文読解を優先的に
言語分野の中でも、よく出題されるのが語彙の知識や二語の関係を問う問題、そして長文読解です。これらは暗記や慣れによって点数を伸ばしやすいため、初期対策としておすすめです。
特に語彙問題は、意味の似た言葉や対義語をセットで覚えることで対処できます。長文読解においては、設問文を先に読み、目的を持って文章にあたる訓練をすると正答率が上がります。
非言語:表や推論・確率問題を中心に
非言語では、表の読み取り・集合・推論・確率といったジャンルが頻出です。これらの問題はパターンがある程度決まっており、反復練習によって処理スピードが確実に向上します。
中でも確率や表の読み取り問題は、1問で複数の設問がセットになっているケースも多く、得点源にしやすいため、優先的に取り組む価値があります。
1冊の問題集を繰り返すことで自信をつける
SPI対策には問題集を使うのが一般的ですが、何冊も手を出して中途半端に終わるのは逆効果です。まずは1冊に絞り、その1冊を3周以上解き直すことで、解き方の感覚が身につきます。
1回目で理解できなかった問題も、2回目・3回目では驚くほどスムーズに解けることがあります。繰り返しの学習が、焦りや不安を和らげる大きな支えになります。
苦手分野の分析→部分集中学習
自分がどの分野で得点できていないのかを把握することも大切です。まずは模擬試験や過去問演習を通じて、苦手分野を明確にします。
その上で、苦手なジャンルだけを集中的に解く「部分集中学習」を実施しましょう。たとえば「確率が苦手」だと感じたら、1日30分ずつでも確率問題だけを解き続ける期間をつくると、着実に自信がついていきます。
模擬テストで時間配分の練習をする
知識やスキルだけでなく、時間配分の練習も不可欠です。特にSPIの非言語分野は、全問を制限時間内に解き切るための戦略が求められます。
そのためには、模擬テスト形式で時間を計って練習することが非常に有効です。実際の試験と同じ緊張感の中でトレーニングを積むことで、本番での焦りや時間切れを防ぎやすくなります。
分野別:SPIが全くできない人向けの具体的な解き方
「SPIが全然解けない…」と感じる就活生は少なくありません。しかし、各分野の特徴を理解し、解き方のコツを身につければ、着実に得点を伸ばすことが可能です。ここでは、SPIが苦手な人でも取り組みやすい分野別の具体的な攻略法を紹介します。
言語対策:暗記・設問読み・文構造に注目
言語分野で苦戦する理由の多くは、「言葉の意味があいまい」「設問の意図が読み取れない」「文全体の構造がつかめない」といったものです。まずは語彙力を補うことが第一歩です。
意味の似た単語・対義語・四字熟語などは、まとめて暗記すると効果的です。また、二語の関係や空欄補充などは、設問文を丁寧に読むことが大切です。特に「この語とこの語の関係は?」と問われたときに、「主従関係」「包含関係」「反対語」など、関係の種類を自分で言葉にして分類できるようになると、正答率が格段に上がります。
長文読解では、最初に設問文を読んでから本文を読む「設問先読み」の方法がおすすめです。これにより、何を探しながら読むべきかが明確になり、読み進めるスピードと精度が高まります。
非言語対策:公式暗記と問題パターン理解が鍵
非言語分野の対策では、まず基本的な公式や計算方法を押さえることが大前提です。たとえば、速さ・割合・損益・濃度・確率といったジャンルには、それぞれ決まった計算式があります。これを暗記して使いこなせるようになるだけで、解答までのスピードが大きく変わります。
次に大切なのは、問題パターンの理解です。SPIの非言語問題は、ある程度出題形式がパターン化されており、同じようなタイプの問題が何度も登場します。たとえば「〇人中△人がA社を志望していて…」といった集合問題や、「時給◯円で△時間働いたら…」といった損益問題などは、練習を重ねることで「こういうときはこう解く」という型が自然と身についていきます。
苦手意識が強い人ほど、まずは1日1ジャンルに集中して解き続け、成功体験を重ねることが自信と実力につながります。
英語対策:苦手な人は「出題パターン」から入る
SPIの英語問題は、難易度自体はそれほど高くありません。中学~高校初級程度の英文法・語彙がベースになっているため、内容としては基礎的なものです。
ただし、英語が苦手な人にとっては「問題文を読むのもつらい」という状況もあり得ます。そうした場合は、まず「どんなパターンの問題が出るのか」を把握することから始めましょう。たとえば、空欄補充、語句整序、内容一致など、出題形式ごとの攻略法を1つずつ覚えるだけでもハードルがぐっと下がります。
また、長文読解は単語を一語一語訳すよりも、段落の主旨をざっくり捉える読み方に切り替えることが効果的です。すべてを理解しようとせず、設問に関係する部分だけを重点的に読み取る技術が得点のカギとなります。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
どうしてもSPIができないときの選択肢
どれだけ努力しても、どうしてもSPIが苦手という人はいます。「SPI=無理ゲー」と強く感じてしまい、心が折れそうになることもあるでしょう。しかし、就活の道は1つではありません。SPI以外の選択肢も十分に存在します。ここでは、どうしてもSPIを突破できないときの現実的な対応策を紹介します。
SPIを複数回受けて慣れる
SPIは一度の受験ですべてを決める必要はありません。特にテストセンター形式で受験する場合、同じ結果を複数の企業に使い回すことができますが、再受験も可能です(前回の受験から一定期間を空ける必要があります)。
最初の1〜2回は「模試」と割り切って受けることで、問題の形式や試験の空気に慣れることができます。場慣れするだけでも、得点が大きく変わることはよくあります。「本番で試す前に、数回練習してみる」くらいの気持ちで、複数回受けてみるのも一つの戦略です。
SPI以外の選考方法を採用している企業を探す
企業によっては、SPI以外の適性検査を導入しているケースもあります。たとえば、「玉手箱」や「GAB」「CAB」「TG-Web」などの別形式のテスト、あるいは筆記試験を行わず、書類と面接のみで選考する企業も存在します。
中小企業やベンチャー企業の中には、筆記試験をそもそも実施していないところも多いため、SPIにこだわらず、そうした企業にも視野を広げてみましょう。SPIが苦手な自分に合った選考フローの企業を選ぶことも、就活の立派な戦略の一つです。
テストセンターよりWebテストを優先して受ける
SPIには「テストセンター形式」と「Webテスト形式」があります。テストセンターは全国の専用会場で受けるタイプで、カンニングや不正ができない一方、緊張感や制限時間の厳しさがあります。
一方、自宅などで受けられるWebテスト形式は、慣れた環境で受験できる分、プレッシャーが軽減されやすくなります。また、企業によってはWebテスト形式の方が問題数が少ない、あるいは時間に余裕がある場合もあります。
どうしてもテストセンターが苦手な場合は、Webテスト形式の企業を優先して選ぶという戦略も、実力を発揮しやすくする上で有効です。
絶対にやってはいけないNG行動
SPIがうまくいかないと、「どうにか突破したい」「短期間でなんとかしたい」という焦りから、誤った方向に走ってしまう人もいます。しかし、以下のようなNG行動は結果的に就活全体に悪影響を及ぼすリスクがあります。焦っているときこそ、冷静に行動することが大切です。
受験代行など不正な手段に頼る
「SPI 代行」といったワードで検索すれば、不正を請け負う業者が見つかるかもしれません。しかし、こうした行為は当然ながら明確なルール違反です。企業は受験結果の信頼性を高めるため、ログの解析や不正対策を厳しく行っています。
仮に不正が発覚した場合、その企業の選考から外されるだけでなく、他社に情報が共有されることもあります。今後のキャリア全体に傷をつけるようなリスクを負ってまで得る内定には、意味がありません。
勉強法をコロコロ変えて非効率になる
「この問題集が良いと聞いた」「YouTubeでこの方法が紹介されていた」といった情報に影響されすぎて、次から次へと対策方法を変える人がいます。新しい方法を試すのは悪いことではありませんが、やり方が安定しないと、学習の効果も積み重なりません。
SPI対策は「繰り返し」が基本です。1冊の問題集、1つの勉強スタイルに腰を据えて取り組むことで、理解やスピードが徐々に定着していきます。焦って手法ばかり変えるのではなく、自分に合ったやり方を見つけたら、地道に続けることが合格への最短ルートです。
「どうせ無理」と思って対策をやめる
最も避けたいのが、「どうせ無理だから」と考えて何もしなくなることです。SPIの問題は確かに最初は難しく感じますが、数をこなすほどに理解できるようになり、慣れも生まれます。
成績が上がらなくても、続けていれば必ず成長の実感は得られます。特に非言語のような「慣れゲー」に近い分野は、演習量がものを言います。対策をやめた瞬間から、得点アップの可能性はゼロになってしまいます。できることからで構いません。諦めず、少しずつ進むことが最終的な合格につながります。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPIが「無理ゲー」じゃなくなる日は来る
「SPIが無理ゲーにしか思えない」と感じている人にとって、今はゴールが見えず、不安でいっぱいかもしれません。でも、努力が無駄になることはありません。適切な対策を続けることで、少しずつですが、必ず状況は変わっていきます。ここでは、SPIが“無理ゲー”から“普通のテスト”になるまでの心構えや過程を紹介します。
最初は誰でもつまずくもの
SPIに限らず、初めて挑戦するものに対しては、多くの人が最初はうまくいかないものです。特に非言語分野のように、慣れていない形式やスピード感を求められる問題では、最初から完璧に解ける人の方が稀です。
実際、SPIを「意味がわからない」「何をすればいいかわからない」と感じたという人は非常に多くいます。それでも、毎日少しずつ問題を解いていく中で、苦手意識が薄れ、「あれ、意外といけるかも」と感じられる瞬間が訪れます。
続けることで解ける問題は確実に増える
SPIは繰り返し学習に非常に向いているテストです。出題傾向が一定しており、よく出る問題のパターンが決まっているため、対策すればするほど“慣れ”が蓄積していきます。
初めは10問中2問しか解けなかった人が、数日後には5問、さらに数週間後には8問正解できるようになる、というのはよくあることです。このように「解ける問題が増える」ことが、自己肯定感ややる気の回復にもつながります。
「昨日より今日、今日より明日」と前向きに取り組むことで、自然とスキルは高まっていきます。
1点でも多く取る意識が突破につながる
SPIは「満点を取らなければいけない」試験ではありません。企業ごとに設定された合格ラインを超えれば十分であり、それは6~7割程度であることが多いです。
つまり、完璧を目指す必要はなく、1点でも多く積み上げていく姿勢が大切です。「あと1問だけでも解けるようにしよう」「このジャンルだけでも正答率を上げよう」といった小さな目標を設定して、一歩ずつ進んでいけば、着実に合格に近づきます。
焦らず、少しずつ自分のペースで対策を続けることで、気づいたときにはSPIが「無理ゲー」ではなく「ちゃんと戦える試験」になっているはずです。
まとめ
SPIを「無理ゲー」と感じてしまう理由は、単なる学力不足だけではありません。中学・高校の知識の忘却、制限時間の厳しさ、見慣れない出題形式、苦手分野の存在、そして正解がない適性検査への不安といった、さまざまな要因が複合的に絡んでいます。これらにより、「自分だけができない」と落ち込んでしまう学生も少なくありません。
しかし、SPIは正しい方法で対策を積み重ねれば、誰でも得点を伸ばすことが可能な試験です。頻出分野に絞った学習や、1冊の問題集を繰り返し解く方法、模擬テストでの時間配分の練習など、現実的で再現性の高い取り組み方を実践することが、突破のカギになります。
それでもうまくいかない場合には、SPI以外の選考手段を選ぶことも立派な選択肢です。就活は「SPIに勝つ」ことが目的ではなく、「自分に合った企業に出会う」ことが本質です。不正や無理な勉強法に頼らず、自分にできることを着実に続けていくことが、最終的な成功につながります。
今日できなかったことが、明日できるようになる——その繰り返しがSPIを「無理ゲー」から「乗り越えられる試験」へと変えてくれるはずです。諦めず、焦らず、自分のペースで一歩ずつ進んでいきましょう。