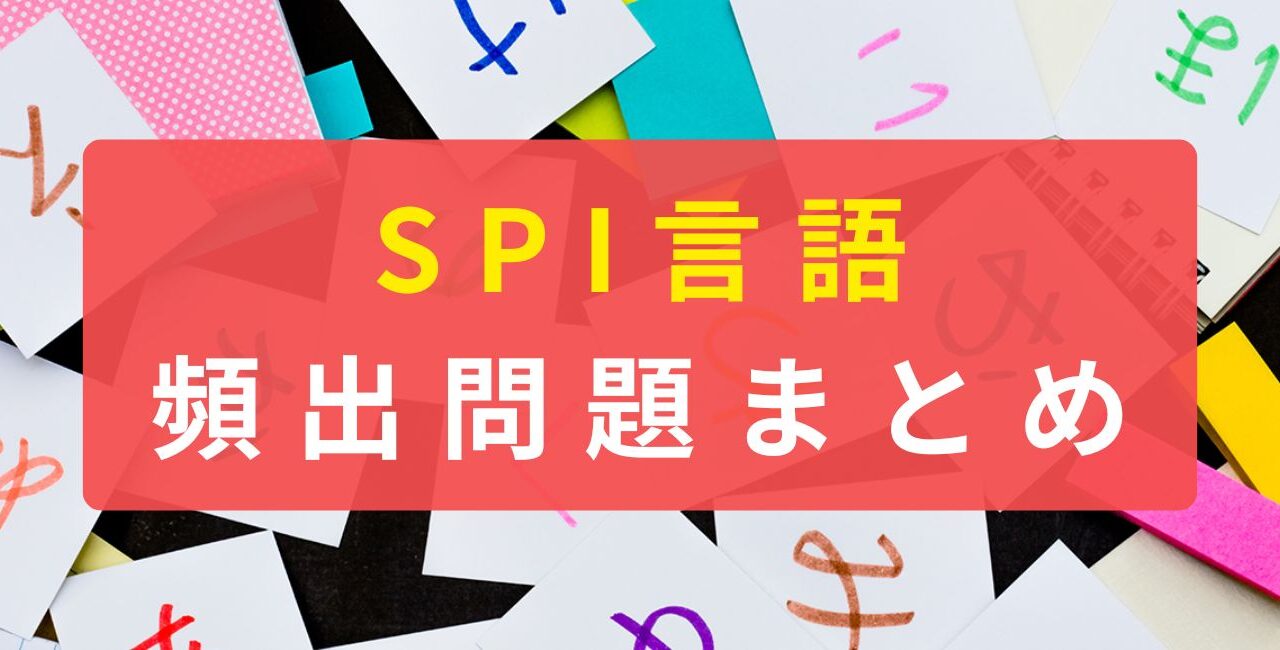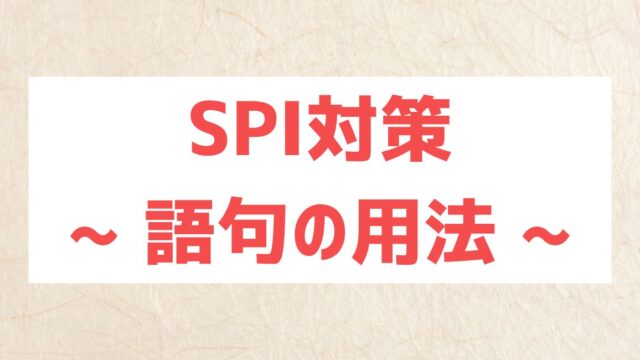【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
就活で避けて通れないのが「SPI試験」。特に大手企業や人気企業では、エントリーシート通過後に筆記試験としてSPIが課されることが多く、ここでつまずくと先に進めません。
そんなSPIの中でも、多くの人が「対策しておけばよかった…」と後悔しがちなのが「言語分野」です。
「国語は得意だから大丈夫」
「なんとなく解けそうな問題ばかりじゃない?」
と思って対策を後回しにしてしまうと、思ったよりも点が取れず、面接に進めないなんてことも。実はSPIの言語分野には独特のクセがあり、事前に出題傾向を押さえて練習しておくことがとても大事です。
この記事では、SPIの言語分野について、出題範囲と頻度、よく出る問題の具体例解き方のコツなどを、就活生向けにわかりやすく解説していきます。
「SPI対策、そろそろちゃんとやらなきゃな…」と思っている人も、「これから始めるよ!」という人も、ぜひ参考にしてみてください。
目次
SPIの言語分野とは
SPIの言語分野は、ざっくり言えば“日本語の力”を試す問題が出題されます。ただし、学校の国語のテストとはちょっと違い、「スピード感」や「論理的思考力」が問われるのが特徴です。
目的は「ビジネスで使える言語力の確認」
企業がSPIの言語分野を出題する理由は、単に漢字や語彙を知っているかを見たいからではありません。実際の仕事では、メールのやり取りや資料の読み書き、会議での発言など、言葉を正確に扱う力が求められます。
SPIではそういった「実務に使える日本語の力」が備わっているかを、限られた時間の中で判断されるのです。
具体的にはこんな問題が出る
言語分野で出題される問題は、大きく分けて以下のようなものがあります。
- ・語句の意味
- ・二語の関係
- ・熟語の成り立ち
- ・語句の用法
- ・文の並べ替え
- ・空欄補充
- ・長文読解
一見シンプルに見える問題が多いですが、語彙の正確な理解や文の構造を素早くつかむ力が必要になります。
「速く・正確に読む」力が重要
SPIは制限時間がタイトで、1問にかけられる時間は1〜2分程度しかありません。読解力に加えて、時間内に解き切るための速読力や判断力も問われるため、慣れていないと途中で時間切れになることも。
だからこそ、出題傾向を知り、頻出問題に慣れておくことが得点アップのカギになるのです。
SPIの言語分野の出題範囲/出題頻度
SPIの言語分野は、出題パターンがある程度決まっています。そのため、どこがよく出るのかを把握して、重点的に対策することが効率的な勉強につながります。
この章では、各分野の出題範囲と出題頻度を◎・⚪︎・×の3段階で示し、どの分野をどれくらい優先的に勉強すれば良いかを分かりやすく整理していきます。
出題範囲と出題頻度一覧
| 出題分野 | 出題頻度 | 内容の概要 |
| 語句の意味 | ◎ | 言葉の正確な意味を問う問題。四択で選ばせる形式が多い。 |
| 二語の関係 | ◎ | ペアとなる語の関係性(類義語・反対語・原因と結果など)を問う。 |
| 熟語の成り立ち | ◎ | 熟語を構成する漢字の関係性(修飾・目的語など)を判断する問題。 |
| 語句の用法 | ⚪︎ | 言葉を正しく使えているかを文の中で判断する。やや応用的。 |
| 文の並べ替え | ⚪︎ | バラバラの文を正しい順序に並べる。論理的思考力が必要。 |
| 空欄補充 | ⚪︎ | 空欄に入る適切な語や文を選ぶ問題。文脈理解が求められる。 |
| 長文読解 | ◎ | 複数段落の文章を読んで設問に答える。時間管理が重要。 |
| 四字熟語 | × | ほとんど出題されないため、優先度は低い。 |
| 敬語・ビジネスマナー | × | SPIの言語分野では基本的に出題されない。 |
重点的に対策すべき分野は?
上の表からわかるように、SPIで得点を伸ばすには次の3つの分野が特に重要です。
- ・語句の意味
- ・二語の関係
- ・熟語の成り立ち
これらは毎年のように複数問出題されるうえに、問題数も多いため、得点源としてしっかり押さえておきたいところです。特に「語句の意味」や「熟語の成り立ち」は、知識があれば短時間で解けるので、コスパの良い分野でもあります。
一方で、「語句の用法」「文の並べ替え」「空欄補充」などは、思考力が必要な分、やや難易度が高く、得点までに時間がかかる場合があります。ただし出題頻度はそれなりにあるため、時間がある人は余裕をもって取り組むと良いでしょう。
このように、出題傾向をふまえてメリハリをつけた勉強をすることで、SPIの言語分野の得点力はグッと上がります。
【SPI言語分野:頻出問題例】二語の関係
「二語の関係」は、SPIの言語分野の中でも特に出題頻度が高いジャンルのひとつです。一見単純な語彙の問題に見えますが、実はかなり奥が深く、論理的な思考力と語彙力が問われます。
このパートでは、「二語の関係」の出題パターンや、解き方のコツ、そして実際の例題を紹介していきます。
出題形式
問題の形式はいたってシンプルです。
2つの語句がペアで提示され、その2語がどんな関係なのかを見極めて、同じ関係性を持つ選択肢を選ぶというものです。
例題:
「医者:患者」と同じ関係なのはどれか?
①先生:学校
②警察官:犯罪者
③店員:商品
④作家:本
この問題では、「医者:患者」が「サービスを提供する側:受ける側」の関係にあることに気づけるかがポイントです。
正解は②の「警察官:犯罪者」で、こちらも「対処する側:される側」という関係性があります。
よく出る関係のパターン
SPIでは、以下のようなパターンがよく出題されます。
| 関係性のタイプ | 例 |
| 類義関係(似た意味) | 喜び:うれしさ |
| 対義関係(反対の意味) | 勝利:敗北 |
| 原因と結果 | 雨:洪水 |
| 包含関係(大→小) | 動物:犬 |
| 属性関係 | 火:熱い |
| 目的・機能 | ペン:書く |
| 行為と対象 | 教師:生徒 |
| 場所とそこでの行動 | 学校:学ぶ |
| 作る人と作られる物 | 作家:小説 |
こうした関係性を知っておくだけでも、選択肢を絞るヒントになります。
解くコツ・対策方法
- まず、問題の2語の関係を日本語で説明する
例:「靴:歩く」なら「歩くときに使うもの」など - 選択肢の中で、同じように説明できるものを探す
他のペアでも同じ説明が通用するかどうか確認 - ひとつでも当てはまらない語があれば消去する
単純な暗記ではなく、「2語の意味を正確に理解して関係性を説明できる力」が問われます。普段から身の回りの言葉の関係性を意識しておくと、解くスピードがどんどん上がっていきます。
【SPI言語分野:頻出問題】語句の意味
「語句の意味」はSPI言語分野の中でも最も基本的で、かつ出題数も多い重要なジャンルです。
問題形式としては、ある語句の意味として正しいものを選ばせる選択式で出題されることがほとんどです。
このパートでは、「知らないと解けない」ではなく「見たことはあるけど、意味があやふや」になりがちな言葉を中心に、頻出語句を20個紹介していきます。
よく出る語句と意味(頻出20語)
| 語句 | 意味の説明 |
| 厄介 | 面倒で扱いにくいこと |
| 漠然 | はっきりせず、ぼんやりしているさま |
| 斡旋 | 間に入って、うまく取り持つこと |
| 齟齬(そご) | 食い違い。意見などが一致しないこと |
| 詭弁(きべん) | もっともらしく見せかけたが、実は筋の通らない議論 |
| 割愛 | 惜しいと思いながら省略すること |
| 逸脱 | 本来あるべき道筋からそれてしまうこと |
| 緩和 | 厳しさや激しさをゆるめること |
| 暗黙 | 言葉にしなくても了解していること |
| 革新 | 古い制度や習慣を改めて新しくすること |
| 忍耐 | 辛抱強くこらえること |
| 膨大 | 非常に大きいこと |
| 阻止 | 行動などを押しとどめること |
| 包括 | 全体をひとまとめにすること |
| 流布 | 広く世間に広まること |
| 扶養 | 経済的に養うこと |
| 閑散 | 人が少なく、にぎやかさがない様子 |
| 概要 | 物事のおおまかな内容 |
| 真偽 | 本当か嘘か、真実かどうかということ |
| 適宜 | 状況に応じて、ちょうどよく対処すること |
解くコツ・対策方法
SPIで出題される語句は、日常会話では使わないけれど、ビジネス文書やニュースではよく見かけるものが多いです。
したがって、「なんとなく聞いたことがある」ではなく、正確な意味を覚えておくことが大切です。
- 意味だけでなく、「例文」で覚えると記憶に残りやすい
- 類義語・対義語も一緒に確認すると理解が深まる
- 覚えた語句を使って、実際に文章をつくってみるのも効果的
たとえば「齟齬(そご)」という語句は、「意見の齟齬を防ぐために事前に共有しておく」などの形で覚えると、使い方ごと記憶に残ります。
この分野は知識さえあれば確実に得点できるので、語句リストを使った暗記やアプリの活用もおすすめです。
【SPI言語分野:頻出問題例】熟語の成り立ち
「熟語の成り立ち」は、SPI言語分野で毎年出題される超頻出ジャンルです。
このパートでは、熟語を構成する漢字の関係性を問う問題が出題されます。
たとえば、「前の漢字が後ろを修飾している」などのルールを理解しておくことで、初見の熟語でも意味を推測できるようになります。
ここでは、よく出る5パターンに分けて、例題と解説を紹介していきます。
パターン1:前が後ろを修飾(形容)する
意味の方向が「○○な△△」という形になっている熟語です。これは最も出題されやすいパターンで、比較的意味もとりやすいので、得点源にしたいところです。
例)高速(高い速度)
重罪(重い罪)
遠足(遠くへ行く足=外出)
パターン2:反対の意味の漢字を組み合わせている
正反対の漢字を組み合わせて、バランスをとったような熟語になっているケースです。このパターンも意味が直感的にわかりやすいですが、「反対語」と気づけるかが正解のカギです。
例)善悪(善いことと悪いこと)
強弱(強さと弱さ)
上下(上と下)
パターン3:動詞の後に目的語がくる(動作と対象)
これは「動詞:名詞」のような構造になっていて、「何をするか」と「何に対してか」がセットになっています。
例)飲酒(酒を飲む)
読書(本を読む)
掃除(汚れを掃く)
パターン4:似た意味の漢字の組み合わせ
同じような意味を持つ漢字を2つ重ねることで、意味を強調している熟語です。
例)堅固(どちらも「固い」)
俊才(どちらも「優れている人」)
温暖(どちらも「暖かい」)
パターン5:主語と述語の関係
主語(行う人)+述語(動作)という構造の熟語です。これはやや判断が難しいですが、動詞っぽい熟語の中にはこの構造が隠れていることが多いです。
例)国会(国が開く会議)
雪解(雪が解ける)
鳥鳴(鳥が鳴く)
出題形式
SPIでは、例として出された熟語と同じ構造のものを選ばせる形式で出題されます。
例題:
「高速」は「高い速度」という関係です。次のうち、同じ成り立ちの熟語はどれか?
①飲酒
②善悪
③強弱
④重罪
→答えは④の「重罪(重い罪)」=前が後ろを修飾する関係。
解くコツ・対策方法
- 熟語を分解して、意味を言葉で説明する練習をする
- 漢字の意味に注目して、主従関係や並列関係を見極める
- パターンを知っておくことで、初見の語でも対応しやすくなる
熟語の成り立ちは一見難しそうに見えて、実はパターンで割り切れる分野です。
演習を重ねるほどスムーズに解けるようになるので、問題集やアプリで数をこなすことがポイントです。
【SPI言語分野:頻出問題例】語句の用法
「語句の用法」は、単に語の意味を知っているだけでは解けない応用力が求められる問題です。
具体的には、ある語句が複数の文の中で正しく使われているかどうかを判断する形式で出題されます。
このパートでは、よく出る語句の用法問題を通じて、どんな力が求められるのか、そしてどう解けば良いのかを解説していきます。
用法で問われやすい語句
これらは意味が似ている語句も多く、混乱しやすいポイントでもあるので、意味+用法の両方を押さえることで確実に得点できます。
| 語句 | 意味 | 例文 |
| 斡旋(あっせん) | 間に入って両者の関係をまとめること | 求職者に合った仕事を企業に斡旋する。 |
| 割愛(かつあい) | 惜しいと思いながら省くこと | 時間の都合により、詳細な説明は割愛します。 |
| 詭弁(きべん) | 一見正しく見えるが道理に合わない理屈 | 彼の発言はただの詭弁に過ぎない。 |
| 流布(るふ) | 広く世の中に広がること | その噂はSNSを通じて瞬く間に流布した。 |
| 憶測(おくそく) | 根拠のない推測 | 憶測で人を批判するのはよくない。 |
| 暗黙(あんもく) | はっきりとは言わないこと | 暗黙の了解でその案は却下された。 |
| 逸脱(いつだつ) | 一定の範囲や基準から外れること | 彼の発言は議題から逸脱していた。 |
| 緩和(かんわ) | 厳しさや強さをやわらげること | 規制が緩和され、旅行がしやすくなった。 |
| 包括(ほうかつ) | すべてをひとまとめにすること | この保険は幅広いリスクを包括している。 |
| 適宜(てきぎ) | 状況に応じて適切に | 資料は適宜修正してください。 |
| 促進(そくしん) | 物事の進行をうながすこと | 地域経済の活性化を促進する政策が求められる。 |
| 敬遠(けいえん) | わざと避けること | 難しい案件はみな敬遠しがちだ。 |
| 歓迎(かんげい) | よろこんで受け入れること | 新しいメンバーを心から歓迎します。 |
| 追及(ついきゅう) | 責任や原因などを厳しく問いただすこと | 記者が不正の責任を追及した。 |
| 追求(ついきゅう) | 理想や目的を求めて努力すること | 真理の追求こそが学問の本質だ。 |
| 措置(そち) | ある目的のためにとる手段 | 政府は感染拡大防止の措置を講じた。 |
| 折衷(せっちゅう) | 複数の案の良い部分を取り入れてまとめること | 両者の意見を折衷して結論を出した。 |
| 遺憾(いかん) | 思い通りにならず残念なこと | 今回の結果は誠に遺憾である。 |
| 打診(だしん) | 相手の意向や様子を事前にさぐること | 上司に転職の意向を打診した。 |
| 含蓄(がんちく) | 表に出ていない深い意味 | 含蓄のある言葉に考えさせられた。 |
出題形式
語句が提示され、正しい使い方の文章を選択する形式で出題されます。
例題:
次の語句の使い方として、正しいものを選びなさい。
【語句】「斡旋」
①友人に頼んで、アルバイトを斡旋してもらった。
②雨の斡旋で試合が中止になった。
③彼は斡旋のある性格で、誰からも慕われている。
④その映画は、社会の斡旋をテーマに描かれている。
→正解は①
「斡旋」は「間に入ってうまく取り持つこと」という意味で、就職や取引を仲介する場面で使われます。
頻出語句と誤用されやすい例
SPIでは、「日常でなんとなく使ってしまっているけど、実は意味を誤解している」ような語句が狙われがちです。
| 語句 | 正しい使い方(例文) | 誤用されやすいパターン |
| 憶測 | 事実ではなく、憶測でものを言うな | 「予想」と混同される |
| 割愛 | 時間の都合で一部の内容は割愛します | 「重要ではないから省略する」と勘違いされがち |
| 詭弁 | それは詭弁であって、正論ではない | 「うまい言い方」とポジティブに捉えられることも |
| 流布 | 誤情報がSNS上で流布されている | 「配布」と混同される |
| 適宜 | 作業手順は適宜調整してください | 「適度に」と混同される |
解くコツ・対策方法
語句の用法問題は、「語の意味+文脈判断」がセットで必要になります。
以下のような解き方が効果的です。
- まず語句の意味を正確に理解する
意味をイメージではなく“言葉で説明できるか”を意識 - 選択肢の文が自然かどうかをチェック
「なんとなく読める」ではなく「意味が通るか」「文法が正しいか」を重視 - 明らかにおかしい選択肢は先に除外する
文法ミスや意味不明な表現がある文は消去して絞る
語句の用法は、「知識だけじゃ足りないけど、慣れれば一気に得点源になる」分野です。
過去問や問題集で出題パターンに慣れておくことが一番の近道です。
【SPI言語分野:頻出問題例】文の並べ替え
「文の並べ替え」問題は、バラバラになった文の順序を並べ替えて、意味の通る文章を完成させる問題です。
一見パズルのようですが、実は論理の流れや接続語の使い方に注目すれば、コツをつかんで正解に近づくことができます。
頻出のテーマ
SPIでは以下のようなテーマで並べ替え問題が出ることが多いです。
- 社会問題(高齢化、雇用、環境など)
- 経済活動(企業の取り組み、制度の導入など)
- 自然科学(気候変動、動植物の進化など)
- 日常の話題(スマホ依存、働き方など)
内容自体はそこまで難しくありませんが、「論理的に正しい順序か?」が見抜けるかどうかがポイントです。
出題形式
以下のように順序がバラバラにされた文が提示されます。
例題:
次の文を並べ替えて、意味の通る文章にしなさい。
A.そのために、新たな制度の導入が検討されている。
B.近年、若年層の雇用が不安定化している。
C.国としても、これを問題視している。
D.対策を講じる必要があると考えられている。
この場合、正しい並びは→B→C→D→A
Bで現状の問題提起をし、Cが問題に対する反応を示し、Dで対策の必要性に言及し、Aで具体的な対策が提示されるという流れです。
解くコツ・対策方法
解くコツ
- まず全体の内容を把握する
一文ずつ読むよりも、まずは「全体で何の話か」をざっくり理解することが大事です。 - 接続語・指示語に注目
「そのため」「しかし」「このように」などの接続語や、「それ」「これ」などの指示語は、前後関係を読み取るヒントになります。 - 主語・述語のつながりを意識
バラバラの文の中でも、誰が何をしたのかという構造を考えながら並べていくと、順序が見えやすくなります。 - 選択肢を絞り、消去法を活用
明らかに導入として不自然な文や、前後関係がつながらない文は先に除外。
すべての組み合わせを試すよりも、「最初に来そうな文」や「最後に来そうな文」からあたりをつけていくと効率的です。
対策方法
- 毎日1問でも並べ替え問題に触れることで「文章の感覚」が身につく
- 接続語や因果関係に敏感になる練習をする
- 「この文は導入だ」「これは結論だ」など、役割を考えながら読む癖をつける
文の並べ替え問題は、慣れていないと難しく感じるかもしれませんが、解き方の型を覚えれば安定して得点できるようになります。
【SPI言語分野:頻出問題例】空欄補充
「空欄補充」問題は、文や文章の中に空いている部分に、最も適切な語句や文を選ぶ問題です。SPIの中では比較的オーソドックスな問題形式ですが、語彙力と文脈理解の総合力が試されるため、難易度が高く感じる人も多いジャンルです。
頻出パターン
| 出題タイプ | 例 |
| 性格・態度に関する語句 | 無関心、冷淡、誠実、謙虚、傲慢など |
| 状況判断系 | 適切、不十分、不当、過剰、妥当など |
| 感情表現 | 喜び、悲しみ、怒り、失望、満足、不安など |
| 逆接・対比の文脈 | しかし、にもかかわらず、それにもかかわらずなどを含む文 |
| 因果関係 | そのため、だから、ゆえに、したがって、結果としてなど |
これらのパターンを覚えておくと、選択肢の見極めがスムーズになります。
出題形式
文や文章の中に空いている部分に、最も適切な語句や文を選ぶ形式です。
例文:
次の文の( )に入る最も適切な語を選びなさい。
彼は会議での発言に対して( )な態度を取り続けたため、信頼を失ってしまった。
①積極的
②無関心
③謙虚
④熱心
この場合、空欄の前後に注目すると「信頼を失ってしまった」とあるので、ネガティブな意味を持つ語が入るのが自然です。
→正解は②無関心
解くコツ・対策方法
- 一文全体を読み、「どういう意味の語が入れば自然か?」を感覚ではなく論理で判断する
- 接続語や前後の意味の流れを必ずチェックする
- 選択肢をひとつずつ入れてみて「違和感がないか」を確認する
- 意味が近い選択肢があるときは、ニュアンス・使い方の違いを意識する
空欄補充は、見た目以上に論理力が求められる分野です。選択肢に引っ張られる前に、「自分ならここにどんな言葉を入れるか」を考えるクセをつけると、自然と正解に近づけます。
【SPI言語分野:頻出問題例】長文読解
SPIの言語分野で、最も時間を消耗しやすく、差がつきやすいのが「長文読解」です。
「読むのが遅くて時間が足りない…」
「選択肢がどれもそれっぽくて迷ってしまう」
そんな声が多いのが、この分野の特徴です。
ただし、出題パターンや解き方のコツを押さえておけば、長文読解も得点源に変えることができます。
この章では、SPIの長文読解の問題形式と攻略法を、実例を交えて紹介します。
出題形式
SPIの長文読解では、400〜800文字程度の文章が出題され、それに対する設問が1〜3問程度ついてきます。
設問のタイプは主に以下の通りです。
- 筆者の主張はどれか?
- 空欄に入る文として最も適切なのは?
- 内容と合致している選択肢は?
- 内容と異なるものを選べ(“NOT”問題)
文章の内容は、社会問題(少子化・働き方改革など)、科学やテクノロジーのトピック、経済・ビジネスに関する内容が多く、やや抽象的なテーマが扱われることもあります。
解き方の基本ステップ
①先に設問を読む(特にNOT問題は要注意)
設問を先に読むことで、「どこに注目して読むべきか」が明確になり、読み飛ばしを防げます。
特に「内容と一致しないものを選べ」という“NOT問題”は、思い込みで間違えやすいため、事前に設問の形式を理解しておくことが重要です。
②各段落の要点をつかむ
段落ごとに「何を言っているか」を簡単に頭の中で要約しながら読むと、全体の構成が見えやすくなります。
たとえば、
- 第1段落:問題提起
- 第2段落:具体例
- 第3段落:筆者の意見やまとめ
というような構成はよく出ます。
③設問と選択肢を照らし合わせて消去法
選択肢の中には、細かい部分でズレているものや、言い回しだけ変えて意味を変えているものが混ざっています。
- 「一部だけ合ってる」
- 「言い換えが極端すぎる」
- 「書いてないことを勝手に補っている」
こうした選択肢は、冷静に見れば除外できます。
よくあるミスと注意点
| ミスパターン | 防止法 |
| 雰囲気で選んでしまう | 根拠が文中にあるかどうかを確認する |
| 設問を読み間違える(NOT問題) | 問いの形式をメモするor注意して2回読む |
| 選択肢を最後まで読まない | 全文をしっかり読むクセをつける |
長文読解では、焦りからくる思い込みが一番の敵です。
落ち着いて、論理的に考えることが重要です。
解くコツ・対策方法
- 新書や新聞の社説など、抽象度の高い文章を日常的に読む習慣をつける
- 過去問・模試形式で時間を計って練習する(時間感覚が大事)
- 正解の根拠を文中から探す癖をつける(根拠なしで選ばない)
長文読解は苦手意識を持つ人が多い分、きちんと対策しておけば他の受験者に差をつけやすい分野でもあります。
“読む力”はSPIだけでなく、面接や仕事にも役立つ力です。地道な練習を積んで、確実に得点できるようにしておきましょう。
次はいよいよ最後の章。SPI言語分野のまとめとして、どのように対策を進めていけばよいかを総整理していきます。
SPIの言語分野は知識と慣れが重要!
ここまで、SPIの言語分野について、出題範囲から頻出問題のパターン別対策まで詳しく解説してきました。
最後に改めて、SPIの言語分野で得点を伸ばすために大切なことをまとめます。
- 出題傾向を覚える
題ジャンルが明確なので、まずは自分の得意・不得意を把握したうえで、頻出分野から優先的に対策を進めましょう。 - 語彙力を鍛えて知らない語を減らす
語彙力は一朝一夕では身につかないので、通学中やスキマ時間を使って、コツコツと語句を覚えていくことが一番の近道です。 - 問題演習で慣れる
実際にタイマーを使って問題を解いたり、解説を読んでなぜ間違えたかを分析する - 焦らず着実に対策を進める
出題傾向が決まっていて、対策すればちゃんと点が取れる」テストでもあります。逆に言えば、ノー対策で挑むと高確率で失敗する試験でもあるので、少しずつでもいいので早めに手をつけておくのがおすすめです。
おすすめの対策手順
- 出題範囲と頻度を把握する
- 語句の意味・二語の関係・熟語の成り立ちから優先的に対策
- 問題集・アプリで演習→間違えた問題は解説を見て復習
- 長文や並べ替えは時間を意識しながら練習
- 定期的に全体の模試形式で実力をチェック
SPIの言語分野は、知識と慣れを組み合わせれば、誰でも確実にスコアアップできる分野です。
本記事を参考にしながら、自分に合ったペースで着実に準備を進めていきましょう。
SPI突破は、内定への第一歩。がんばるあなたを応援しています。