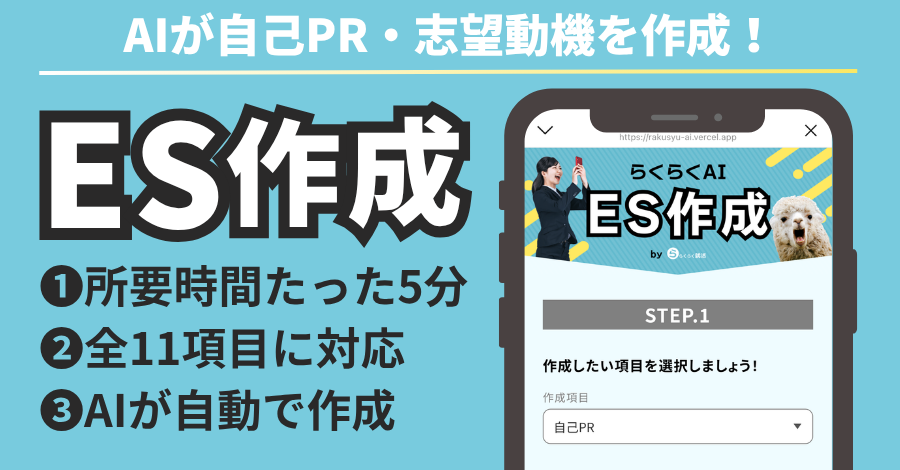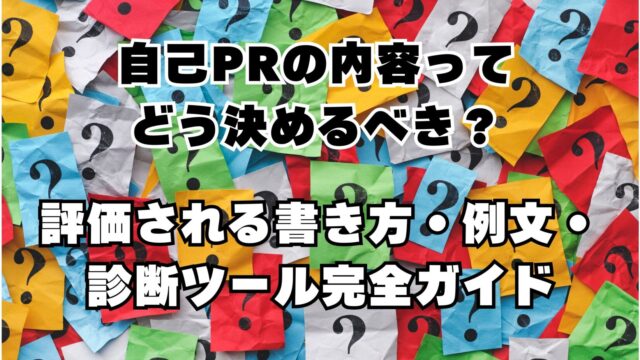【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
自己PRで「エピソードを2つ話すのはアリなのか?」と迷ったことはありませんか。
1つのエピソードだけだと物足りなく感じたり、複数の経験を伝えたくなったりするのは自然なことです。特に、学生時代に部活動・アルバイト・研究・ボランティアなど幅広い経験をしてきた人ほど、「1つに絞るのはもったいない」と感じやすいでしょう。
一方で、面接官の立場からすると、2つの話を無理に詰め込むことで印象が薄まってしまうケースも少なくありません。大切なのは「量」ではなく「質」と「伝え方」です。うまく構成すれば、2つのエピソードで強みの再現性を証明でき、面接官により深い印象を与えることも可能です。
この記事では、自己PRにおけるエピソードの数をどう扱うべきかを、採用担当者の評価基準に沿ってわかりやすく解説します。
さらに、2つ使う場合の構成テンプレートや例文、一貫性の作り方、エピソードが浮かばないときの対処法まで紹介します。
目次
自己PRでエピソードを2つ使うのはアリ?
結論:基本は1つでOK、でも「戦略的に2つ」もあり
まず結論から言えば、「自己PRのエピソードは基本1つで十分」です。
なぜなら、面接官が自己PRで求めているのは「あなたの強みと、その根拠が明確に伝わるか」であり、エピソードの数は重視されないからです。
1つの経験を深く掘り下げ、課題・行動・成果・学びをしっかり整理すれば、それだけで強い説得力を持ちます。むしろ、2つ以上入れると話が散らかりやすく、「結局どんな強みなのか」がぼやけてしまうこともあります。
しかし例外的に、“戦略的に2つ使う”ことで自己PRの印象を高められるケースも存在します。
例えば「同じ強みを異なる場面で発揮した」場合は、再現性を証明できます。また「異なる強みを企業ごとに使い分ける」場合には、柔軟性や多様な能力をアピールできます。
つまり、エピソードは“増やすために2つ使う”のではなく、“目的が明確なら2つ使ってもよい”というのが正解です。
採用担当者が見ているのは「再現性」と「一貫性」
面接官が自己PRを評価するとき、最も重視するのは「その強みが入社後も発揮されるか」という再現性です。
たとえば「リーダーシップがあります」と言われても、その根拠となる行動が一度きりでは説得力が弱いですが、別の環境でも同じ行動を取っていたら、「この人は自然とリーダーシップを発揮できるタイプだな」と納得感が生まれます。
また同時に、「一貫性」も見られています。自己PRの中で話す2つの経験がバラバラだと、「軸が定まっていない」と判断されてしまいます。どんな経験でも共通して発揮されている姿勢や考え方が伝わると、「どんな環境でも力を発揮できそうだ」と評価されるのです。
したがって、2つのエピソードを話す場合は、共通する“価値観”や“強みの軸”を意識することが欠かせません。
判断基準チャート:2つ使うべき?それとも1つで十分?
以下のチャートで、自分がどちらのタイプかを確認してみましょう。
Q1:同じ強みを別の環境でも発揮した経験がある
→ YES:2つ使うのがおすすめ(再現性の証明)
→ NO:Q2へ
Q2:企業によってアピールしたい強みが異なる
→ YES:2つ準備して使い分ける
→ NO:Q3へ
Q3:話したい内容が多く、どれも浅くなってしまう
→ YES:1つに絞るべき
→ NO:Q4へ
Q4:1つの経験だけで十分に成果と成長を語れる
→ YES:1つでOK
→ NO:2つ構成で整理してもよい
自己PRでエピソードを2つ使うと評価が上がるケース
①同じ強みを別の場面で発揮しているとき(再現性の証明)
たとえば「課題解決力」をアピールしたいときに、研究活動とアルバイトの両方で問題解決に取り組んだ経験があるなら、それは大きな武器になります。
1つ目のエピソードでは分析力を中心に、2つ目ではコミュニケーション力を通じて課題を解決したと説明すれば、「環境が変わっても課題解決に向けて動ける人」と伝わります。
このように「同じ強みを異なる環境で再現している」ことは、入社後の再現性を裏づける証拠になります。
②異なる強みを職種や企業ごとに使い分けるとき
例えばメーカー志望では「粘り強さ」を、コンサル志望では「論理的思考力」を、それぞれ前面に出すなど、企業の特性に合わせて使い分ける戦略も有効です。
自己PRは一度作って終わりではなく、相手企業に合わせて調整するものです。2種類の自己PRを用意しておくと、どんな業界にも対応しやすくなります。
③深掘り質問への対策としてストックしておきたいとき
面接では「ほかに似た経験はありますか?」と聞かれることがあります。このとき、別のエピソードを準備しておけばスムーズに対応できます。
「アルバイトでも同じように課題を分析して改善した経験があります」と答えられると、行動の一貫性が示せて好印象になります。
2エピソード構成テンプレート(PREP+比較構成)
以下のテンプレートを使うと、2つのエピソードを整理しやすくなります。
①結論(P):私の強みは○○です。
②理由(R):どんな状況でも○○を意識して行動してきました。
③具体例(E1):研究活動では〜に取り組み、結果〜を達成しました。
④具体例(E2):アルバイトでも同様に〜を意識し、〜の成果を上げました。
⑤まとめ(P):このように環境が変わっても○○を発揮できると考えています。
自己PRでエピソードを2つ話すと逆効果になるケース
エピソードを2つ話すことは、一見「経験が豊富」「努力家」といった印象を与えられそうに思えます。
しかし、実際には「何を伝えたいのか分からない」「話が散らかって印象に残らない」と感じさせてしまうケースが少なくありません。
ここでは、2つのエピソードが“逆効果”になる典型的な3つのパターンと、その理由を詳しく見ていきましょう。
1つの強みがぼやけて印象に残らない
最も多いのが、「強みが散ってしまい、結局何を伝えたいのかわからない」というパターンです。
たとえば、「1つ目はチームワーク、2つ目は努力」と異なるテーマで話すと、面接官の頭の中には「この学生はどんなタイプなんだろう?」という疑問が残ります。
自己PRの目的は“多才さのアピール”ではなく、“あなたの人となりを明確に伝える”ことです。
面接官は短い時間の中で、「この人がどんな考え方で行動する人か」「入社後にどう活躍できるか」を判断しようとしています。
そのため、強みが複数提示されると焦点が定まらず、印象が薄くなってしまうのです。
たとえば以下のような印象を持たれるリスクがあります。
- 「いろいろやってきたのは分かるけど、結局何が得意なの?」
- 「器用そうだけど、専門性や軸が感じられない」
- 「真面目な印象はあるけど、深みがない」
こうした印象は、どれもプラスには働きません。
「チームでの協調性を大切にしてきた」ならそれを一貫して貫き、他のエピソードも“協調性を発揮した別の場面”として補足的に話すようにしましょう。
あくまで「共通の強みを異なる場面で再現する」という目的がある場合のみ、2つのエピソード構成は効果的です。
時間が長くなり要点が伝わらない
面接官が自己PRに割ける時間は、通常1〜2分程度です。
それ以上になると、「話が長い」「まとまりがない」という印象を与えかねません。
実際に多くの面接官は、1分を超える自己PRの中盤で内容を理解し、「この学生の本質は何か」を瞬時に判断しています。
そのため、時間配分が甘いと、せっかくのエピソードも途中で打ち切られたり、最後の学びや入社後の抱負まで話せずに終わってしまうこともあります。
特に2つの話を同じ比重で語ってしまうと、どちらも中途半端になりがちです。
たとえば以下のようなケースが典型です。
「サークルでは企画をまとめ、成功に導きました。またアルバイトでも売上改善に貢献しました。さらに〜」
このように話がどんどん展開していくと、面接官は途中で理解を追うのをやめてしまいます。
結果として「内容は悪くなかったけれど、何が言いたかったのか分からなかった」という評価になるのです。
効果的に伝えるためには、1つ目をメイン、2つ目をサブとして位置づけ、「2つ目は補足的に短く添える」くらいのバランスを意識するのがポイントです。
また、話す前に「2つ話しても1分半で終えられる構成か?」を必ず確認しておきましょう。
論理の軸がブレて説得力が落ちる
2つのエピソードを組み合わせるときにありがちなミスが、「論理的な一貫性がなくなる」ことです。
強みや目的が異なる話を続けてしまうと、ストーリーのつながりが見えず、面接官の印象に残りません。
たとえば、「部活ではリーダーとしてまとめた」「アルバイトでは数字管理を頑張った」と話しても、行動の背景が異なるため、一貫性が生まれないのです。
自己PRは、物語のように「行動の動機 → 実践 → 成果 → 学び」がつながっていることが大切です。
この“ストーリーライン”が断片的になってしまうと、どれだけ実績が良くても「表面的な話」に聞こえてしまいます。
また、論理がブレている自己PRには次のような共通点があります。
- 強みの定義があいまいで、話すたびにテーマが変わる
- 1つ目と2つ目のエピソードの関係性が説明されていない
- 最後のまとめが“どちらの話”に対する結論なのか不明確
この状態では、話の筋道を追う面接官も混乱してしまい、「整理されていない人」「考えが浅い人」という印象を持たれかねません。
論理の一貫性を保つためには、2つの話を貫く「共通の軸」を意識することが不可欠です。
たとえば「相手に貢献する姿勢」「最後までやり抜く粘り強さ」など、行動の根底にある価値観を1本通しておくと、説得力が一気に増します。
NG構成例:話が分散してしまう自己PRのパターン
例:
私はリーダーシップと計画性が強みです。
部活ではチームをまとめて大会で優勝しました。
一方でアルバイトでは顧客満足度を上げるための仕組みを作りました。
さらにボランティアでも責任感を持って〜
このように複数の方向に話が広がると、どの経験も中途半端に終わってしまいます。
聞いている側は「どれも悪くないけれど、結局この人は何が得意なの?」と混乱するだけです。
また、「強みが2つある」と最初に言ってしまうのも危険です。
面接官は限られた時間の中で1つの印象を定着させたいと思っているため、複数の要素を同時に伝えられると、どちらも印象が薄くなってしまいます。
理想は、上記の例を次のように修正することです。
修正版:
私の強みは、チームをまとめるリーダーシップです。
部活では〜(メインエピソード)。
さらにアルバイトでも、同じように周囲を巻き込みながら目標達成に向けて取り組みました。
数よりも「焦点」と「一貫性」が大事
自己PRで最も大切なのは、エピソードの数ではなく「何を伝えたいのかが一目で分かること」です。
1つの話を深く掘り下げた方が、強みや価値観が明確に伝わりやすく、結果的に印象に残ります。
2つ話す場合は、次のような自問をしてみましょう。
「この2つの話に共通する軸はあるか?」「時間内に両方を効果的に伝えられるか?」
どちらかが“NO”なら、無理に2つにせず、1つに絞る勇気を持つことも戦略のうちです。
自己PRは「どれだけ多くを語るか」ではなく、「どれだけ明確に伝えるか」。
焦点を絞ることこそが、面接官の記憶に残る自己PRを作る第一歩です。
自己PRを2つのエピソードで伝えるときの構成
構成①:共通の強みを異なる場面で示す(再現性重視)
「粘り強く課題を解決した」「主体的にチームを動かした」など、同じ強みを異なる環境で再現するパターンです。
最初の話では行動プロセスを、2つ目では成果や成長を中心に語ると、自然な流れになります。
構成②:2つの強みを職種・企業別に使い分ける(柔軟性重視)
自己PRを企業ごとに調整する際に有効です。
たとえば、営業職向けには「行動力」、企画職向けには「分析力」を使うなど、異なる強みを使い分けることで、複数業界への応募にも対応しやすくなります。
強み×エピソード対応マッピング表(整理テンプレート)
| 強み | エピソード1 | エピソード2 | 共通する価値観 |
| 粘り強さ | 研究での実験改善 | アルバイトで売上アップ | 困難に対して諦めない姿勢 |
| 協調性 | サークル運営 | 学園祭実行委員 | 周囲と協力して成果を出す |
| 主体性 | インターンで提案 | 学内プロジェクト立案 | 自ら課題を見つけて行動する |
このように表で整理すると、一貫したストーリーを作りやすくなります。
自己PRで2つのエピソードを話すときのコツ
各エピソードに“結論→根拠→成果”を入れる
PREP法(Point→Reason→Example→Point)を意識して、各エピソードにミニ構成を作ることがポイントです。
「私は〇〇です(結論)」「なぜなら〜だからです(理由)」「具体的には〜を行いました(根拠)」「その結果〜を得ました(成果)」という流れで話すと、2つのエピソードでもまとまりが生まれます。
2つの話に共通する“軸”を意識する
再現性や一貫性を示すためには、どんな場面でも共通して発揮された考え方を中心に据えることが重要です。
「相手の立場に立って考える」「粘り強くやり抜く」など、軸となる価値観を言葉で明確にしておくと、ブレない自己PRになります。
面接官が聞きやすい順番で構成する
最初に“主エピソード(印象に残る経験)”を、次に“補足エピソード(再現性を支える経験)”を話すと、聞き手に負担をかけずに伝わります。
話の順番を変えるだけで、説得力が大きく変わります。
一貫性を作る「ストーリーライン設計法」
1. 強みの軸を1文で決める
2. 軸が共通する2つのエピソードを選ぶ
3. 1つ目で行動の型を示す
4. 2つ目で再現性や成長を見せる
5. 最後に入社後の活かし方を述べて締める
この流れに沿えば、2つの話でも自然で印象的なPRになります。
受かるESを作りたいけど、自己PRも志望動機も思いつかない、、
そこでAIにES作成を手伝ってもらいませんか?
自己PR、ガクチカ、志望動機など、ESにはたくさんの項目があり、そのどれもが簡単に考えられるものではありません。特に初めてのES作りには時間がかかってしまうものです。できればパッと簡単に短時間でESを完成させたいと思いませんか?
そんな人は、「ES自動作成ツール」を活用しましょう。質問に答えるだけで自動でESの文章を作成してくれるため、自分で1から作るよりも簡単に短時間でESを作ることができます。
らくらく就活をLINE追加するだけで使えるので、すぐにES作成を始めましょう!
自己PRの作り方ステップ(1つでも2つでも共通)
自己PRは、思いついたエピソードを並べるだけではうまく伝わりません。
「自分の強みをどう定義し」「どんな順番で話すか」を意識的に設計することで、どんな面接官にも伝わる自己PRが完成します。
1つのエピソードでも、2つ構成でも、この4つのステップを押さえれば、説得力のある自己PRが作れます。
ステップ①:強みを一言で定義する
最初にすべきことは、「私は○○が強みです」という一文を明確にすることです。
この“冒頭の一言”が、自己PR全体の軸になります。
多くの学生が陥りがちなのは、「協調性」「努力」「責任感」といった抽象的な言葉だけで終わってしまうこと。これでは面接官の印象に残りません。
重要なのは、「どんな行動でその強みが現れたか」をイメージできるようにすることです。
たとえば次のように変換してみましょう。
- 「協調性」→「意見の違うメンバーの間に入り、調整しながらチームをまとめる力」
- 「努力」→「課題に直面しても諦めず、原因分析をして解決策を見つける粘り強さ」
- 「責任感」→「任された役割に最後まで責任を持ち、チーム全体の成果に貢献する姿勢」
このように、**「行動の型」+「目的」**を入れて定義すると、あなたの強みが具体的に伝わります。
面接官は「どんな行動を取る人か」を見ています。したがって、“何をしたか”が思い浮かぶ表現を使うことが重要です。
ステップ②:具体的なエピソードを選ぶ
次に、強みを最も発揮したエピソードを選びます。
1つのエピソードで十分伝わるならそれを軸に、必要であれば再現性を示すための2つ目を補助的に準備します。
この段階で意識したいのは、「努力した経験」よりも「課題を解決して成果を出した経験」を選ぶことです。
なぜなら、面接官が知りたいのは「どれだけ頑張ったか」ではなく、「どう考え、どう行動し、結果を出したか」だからです。
たとえば次のような比較を考えてみましょう。
- 【悪い例】「大会で優勝するために一生懸命練習しました」
→ 努力の事実は伝わるが、行動の工夫や成果が不明。 - 【良い例】「チームの士気が下がっていたため、練習内容を見直し、メニューを提案して全員の意欲を高めた結果、優勝できました」
→ 問題意識・行動・成果の流れが明確。
また、2つ目のエピソードを選ぶ際には、次のような補完関係を意識するとバランスが取れます。
- 「研究活動」+「アルバイト」=分析力と実行力の両立
- 「サークル」+「学園祭」=リーダーシップの再現性
- 「ボランティア」+「インターン」=価値観と行動力の一貫性
同じ強みを異なる場面で示せると、「この人はどんな環境でも同じ行動ができる」と評価されやすくなります。
ステップ③:成果と学びを整理する
エピソードを選んだら、次は「結果」と「学び」を明確にします。
成果とは、単なる結果報告ではなく、「自分の行動がどう影響したか」を数字や変化で説明することです。
たとえば次のように整理します。
- 「メンバーの出席率が上がり、チームの目標達成率が20%向上した」
- 「アルバイトの売上を前年比で15%伸ばした」
- 「授業のプレゼンで学内コンペ最優秀賞を獲得した」
このように具体的な数字や成果を入れると、客観的に評価されやすくなります。
また、成果が数字で表せない場合も、「行動の変化」や「周囲からの評価」を示すと効果的です。
「後輩に相談されるようになった」「先生に改善提案を褒められた」といった小さな変化も、面接官にとっては“行動の結果”として十分価値があります。
さらに、「学び」を語ることも忘れてはいけません。
自己PRの目的は、“過去の成功体験を自慢すること”ではなく、“その経験を通じて何を得たか”を伝えることにあります。
「なぜその行動を取ったのか」「そこから何を学び、今後どう活かせるか」を語ることで、単なる経験談が“成長ストーリー”に変わります。
ステップ④:入社後の活かし方を明確にする
最後に、「過去の経験をどう仕事に活かすか」を必ず言葉にしましょう。
ここまでで伝えた強みや行動特性を、応募先の仕事内容と結びつけて締めることで、自己PRの説得力が一気に上がります。
たとえば次のように結ぶと効果的です。
- 「課題を発見し、粘り強く解決策を探る力を活かし、貴社の製品開発にも主体的に貢献したいです。」
- 「周囲を巻き込みながら目標を達成した経験を活かし、チーム営業としてお客様に信頼される存在を目指したいです。」
“過去→現在→未来”の流れを意識すると、話の筋が通り、印象に残る自己PRになります。
また、企業研究をしっかり行い、「この会社でだからこそ活かせる」と伝えられると、志望動機との整合性も取れて好印象です。
エピソード選定チェックリスト
自己PRのエピソードは、思いついた順ではなく“評価される順”に選ぶのがポイントです。
以下の5つの基準を満たすかを確認しながら整理してみましょう。
- どんな課題があったか明確に語れるか
「何が問題だったのか」を説明できないと、行動の意義が伝わりません。課題を一文で言えるか確認しましょう。 - 行動内容が具体的か
「頑張った」「努力した」ではなく、「何を」「どのように」したのかを具体的に話せることが大切です。行動がイメージできるかを基準に。 - 自分の工夫や判断が反映されているか
誰がやっても同じ結果になりそうな話は印象に残りません。あなた独自の工夫や考え方を盛り込みましょう。 - 成果が数字や変化で示せるか
定量的な成果(%や件数)があると説得力が高まります。数字がない場合は「周囲の反応」「目に見える変化」で代替してもOKです。 - 学びが他の場面でも活かせそうか
「この経験から何を学び、それを今後どう活かすのか」まで語れれば、再現性の高い強みとして評価されます。
これら5項目をすべて満たしているエピソードは、どんな構成でも強力な自己PRの土台になります。
1つの経験でも2つの経験でも、この基準に沿って整理すれば、面接官の心に残るストーリーを作ることができます。
自己PR例文:エピソード2つ版・1つ版の比較
例文①:同じ強みで2つの場面を話す場合(研究+アルバイト)
「私の強みは課題解決力です。研究活動では、実験データの再現性が低いという課題に直面しました。原因を分析し、仮説検証を繰り返した結果、データ精度を20%向上させることに成功しました。
またアルバイト先でも、売上が低迷していた原因を分析し、商品陳列を工夫することで売上を15%改善しました。
このように環境が異なっても課題を分析し改善に導く姿勢を大切にしてきました。」
例文②:異なる強みを企業別に使い分ける場合(リーダーシップ+分析力)
「私の強みはリーダーシップと分析力です。サークルでは部長として20名のメンバーをまとめ、役割分担と目標設定を徹底したことで大会で優勝できました。一方で、ゼミではデータ分析を担当し、仮説検証によって研究の精度を高めました。
この2つの経験を通じて、人を動かす力とデータを読み解く力の両方を身につけました。」
例文③:1エピソード型と2エピソード型の違い比較
1つ型は「深さ重視」、2つ型は「広がり重視」です。
1つ型は印象がシンプルで、短時間でもまとまりやすい。
2つ型は説得力と再現性を補強できますが、構成の整理が必要です。
面接官コメント例:どちらのPRが印象に残るか
- 1つ型:「1つの経験を掘り下げていて軸が明確。短時間でも理解しやすい」
- 2つ型:「行動に一貫性があり、どんな環境でも力を発揮できそう」
どちらも評価される可能性はありますが、構成力と一貫性がカギを握ります。
エピソードが2つ思いつかないときの対処法
自己分析をやり直して他の経験を掘り起こす
ノートに「頑張った経験」「苦労した経験」「人に感謝された経験」を書き出してみましょう。
自分では当たり前と思っていた行動も、振り返ると強みの源になっていることがあります。
高校・趣味・サークルなどにも目を向ける
大学以外の経験も立派なエピソードになります。
高校時代の部活、趣味の活動、ボランティアなども含めると、新しい発見があるかもしれません。
他己分析で意外な強みを見つける
友人や家族、ゼミの仲間に「自分の長所って何だと思う?」と聞いてみましょう。
自分では気づかない意外な特徴を教えてくれることがあります。
【オリジナル】エピソード発掘ワークシート
①頑張った経験:
②苦労した経験:
③成果を出した経験:
④感謝された経験:
⑤失敗から学んだ経験:
⑥仲間と協力した経験:
⑦自分で考えて行動した経験:
この項目を埋めていくと、自己PRに使える素材が見えてきます。
ESを作りたいけど、どう書けばいいかわからない、、
「志望企業に提出するESを書かなきゃいけないけど、何から始めればいいのか分からない」そんな悩みを抱えたことはありませんか?限られた時間で質の高いESを仕上げるには、書き出しから構成までサポートがあると安心ですよね。
「ES作成ツール」なら、簡単な質問に答えるだけで、AIが自動であなたの強みや経験を文章化してくれるので、ゼロからESを作り上げることが可能です。
「うまく言葉にできない…」という方でも安心して始められます。
らくらく就活をLINE追加して、簡単なアンケートに答えるだけで無料で使えるので、すぐにESを作成してみましょう!
自己PRのエピソードを複数準備しておくメリット
自己PRのエピソードは「1つを極める」ことが基本ですが、実は“複数ストックしておく”ことにも大きな価値があります。
面接は思い通りの流れで進むとは限らず、想定外の質問や企業ごとの評価基準に柔軟に対応する力が求められます。
1つしか話せる内容がないと、「他に何かありますか?」と聞かれたときに言葉が詰まってしまうリスクがありますが、複数のエピソードを持っていれば落ち着いて対応できるのです。
ここでは、エピソードを複数用意することがどのようなメリットにつながるのかを詳しく解説します。
面接官の深掘りに対応しやすくなる
面接官は自己PRを聞いた後、「もう少し詳しく教えてください」「他の場面でも同じように行動しましたか?」といった“深掘り質問”をして、再現性や一貫性を確認します。
このとき、別のエピソードを持っていると非常に強力です。
たとえば、「サークルでチームをまとめた」という話をしたあとに、「他でもリーダーシップを発揮した経験はありますか?」と聞かれた場合、
「アルバイトでも同様に、メンバー教育を任されて新人の離職率を下げた経験があります」
とスムーズに答えられれば、面接官は「どんな環境でも行動できる人だ」と確信します。
このように、2つ目のエピソードは“予備のカード”として活用できます。
言い換えれば、1つ目で「軸となる強み」を伝え、2つ目で「再現性と信頼性」を補強するイメージです。
面接官にとっては「一貫して強みを発揮してきた人」という印象になり、信頼度が一段階上がります。
また、複数のエピソードを用意しておくと、緊張して頭が真っ白になったときの“保険”にもなります。
メインの話が途中で飛んでも、「別の経験でも同じように〜」と切り替えられることで、落ち着きを取り戻しやすくなります。
面接の場では、準備の量がそのまま安心感につながるのです。
面接ごとにアピール内容を変えられる
エピソードを複数準備しておくもう1つのメリットは、「企業に合わせて自己PRを最適化できる」ことです。
同じ自己PRでも、求められる人物像が異なれば伝え方を変える必要があります。
たとえば、以下のように使い分けることが可能です。
- メーカー志望:粘り強さや探究心を軸にした「研究活動のエピソード」
- コンサル志望:論理的思考や課題解決を示す「ゼミ・分析系のエピソード」
- 営業志望:行動力や成果志向を示す「アルバイトでの改善経験」
企業によって「どんなタイプの人を採用したいか」は異なります。
1つのエピソードしか持っていないと、すべての企業に同じ内容で臨むことになり、印象が弱くなってしまうことがあります。
一方で、複数の自己PRを準備しておけば、「この会社ではどの強みを前面に出すべきか」を柔軟に選択できるようになります。
また、企業研究や面接対策の中で「この会社はチームワークを重視している」と気づいた場合、チームで成果を出したエピソードをメインに差し替えるなど、微調整が可能になります。
このように、複数のエピソードは“企業ごとに最適化するための素材”としても役立ちます。
就活は「同じ話を繰り返す場」ではなく、「相手に合わせて伝え方を変える場」です。
そのための引き出しを増やすことが、最終的に“伝える力の差”につながります。
他の質問(ガクチカ・長所など)にも転用できる
複数のエピソードを整理しておくと、自己PR以外の質問にも対応しやすくなります。
特に就活面接では、自己PRと似たテーマである「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」や「長所・短所」「失敗経験」などが頻出です。
それぞれの質問に完全に別の話を用意する必要はありません。
同じエピソードを角度を変えて話すことで、一貫性を持たせつつ、会話に深みを出すことができます。
たとえば、同じ経験を以下のように使い回せます。
- 自己PR:「課題解決力を発揮した経験」として紹介
- ガクチカ:「目標達成のためにチームで努力した経験」として説明
- 長所:「粘り強く行動する性格」として再定義
- 失敗談:「最初はうまくいかなかったが、分析して改善した経験」として応用
このように一つのエピソードでも、質問に応じて視点を変えれば、面接全体で一貫した印象を与えることができます。
複数のエピソードを整理しておけば、場面ごとの使い分けがよりスムーズになり、「どんな質問にも対応できる人」として評価されるのです。
さらに、エピソードを体系的に整理しておくことで、面接対策そのものが効率化します。
自己PR・ガクチカ・志望動機をバラバラに考えるのではなく、「共通の価値観や行動原則」を中心に組み立てられるため、ストーリーの一貫性が自然に保てます。
結果として、どんな質問にも「あなたらしい答え」で返せるようになります。
エピソードの数は“量より整理の質”
複数のエピソードを持つことは、単に「たくさん話せるようにする」ためではありません。
本当の目的は、“どんな質問にも一貫性を持って対応できる柔軟な自分を作る”ことにあります。
面接は想定外の質問が多く、1つの答え方に固執するとすぐに詰まってしまいます。
しかし、あらかじめ3〜4個のエピソードを整理しておけば、どんな展開にも自信を持って対応できます。
「一貫性のある複数エピソード」は、いわば“就活の武器庫”のようなものです。
使い方次第で、どんな企業・どんな面接官にもあなたの魅力を伝えられるようになります。
まとめ
自己PRのエピソードは、基本的には1つで十分です。
しかし、「同じ強みを異なる場面で発揮した」「職種ごとに使い分けたい」といった明確な目的がある場合は、2つ構成にすることで再現性と柔軟性をアピールできます。
大切なのは“数”ではなく、“軸の一貫性”と“構成の整理”です。
2つのエピソードを話す場合も、強みを中心にストーリーラインを組み立て、「結論→根拠→成果→学び→今後」までを明確に伝えることが重要です。就活では、どんな経験を持っているか以上に、「その経験をどう語れるか」が評価されます。
1つでも2つでも、自分の強みを一貫したストーリーで伝えることが、内定への近道です。