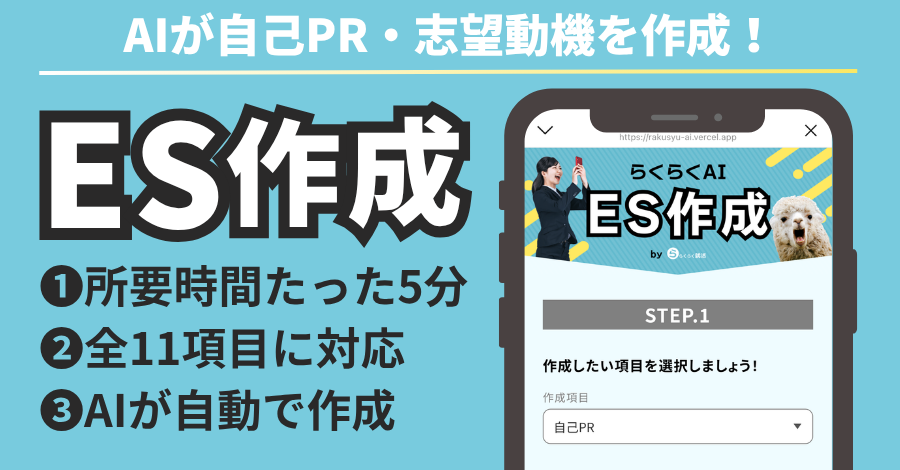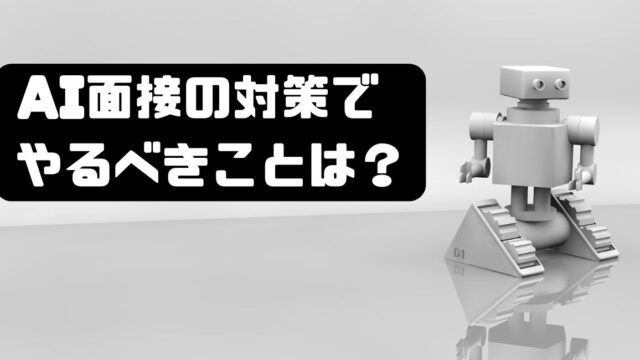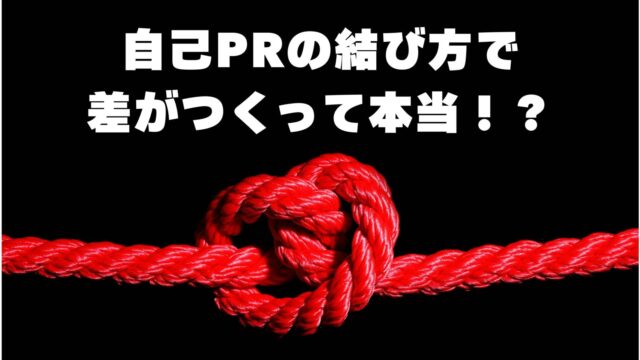【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
就職活動で「自己PRを書いてください」と言われたとき、
「部長」や「リーダー」と比べて「副部長」という役職をどう扱えばいいのか、悩む人は少なくありません。
「自分はあくまでサブポジションだったから…」「部長ほど目立つ成果はないし…」と不安に感じる人も多いでしょう。
しかし実際には、副部長の経験は立派な自己PRの題材になります。
なぜなら、副部長は“チームを円滑に動かすための潤滑油”であり、
リーダーとメンバーの間で意見をつなぎ、組織を支える役割を担っているからです。
企業の採用担当者は、単に「指示を出す人」よりも、
“全体のバランスを見て動ける人”“周囲との関係を大切にできる人”を高く評価します。
つまり、副部長としての経験を適切に伝えられれば、
あなたの「調整力」や「サポート力」「責任感」を印象づけることができるのです。
本記事では、
「副部長を自己PRに使っていいのか?」という疑問から、
アピールできる強み・伝え方のコツ・構成テンプレート・例文・面接での話し方まで、
すべてを一つずつ丁寧に解説していきます。
さらに、オリジナル要素として
「副部長タイプ診断チャート」「強み変換マッピング表」「職種別マッチングMAP」なども掲載。
自分の経験を“強み”として再定義する手助けになる内容です。
副部長という立場で培った「支える力」「まとめる力」を、
自信をもってアピールできるようになりましょう。
目次
「副部長」の経験は自己PRに使える?
結論:副部長は“リーダーを支え、チームを動かす”重要なポジション
副部長の経験は、自己PRとして十分に価値があります。
「部長ほど目立たないから…」と感じる人も多いですが、実際はチームを支える要となる立場です。
副部長は、部長の方針を理解しつつ、メンバーが動きやすいよう環境を整える調整役。
いわば、組織を円滑に動かす“潤滑油”のような存在です。
部長のように指示を出すだけでなく、現場を観察し、問題を早期に解決する力も求められます。
また、副部長はリーダーシップとフォロワーシップの両方を体験できる貴重な役割でもあります。
上を支え、下をまとめる両方の視点を持つ人は、社会人になっても組織運営の中心として重宝されます。
つまり、副部長の経験は「チーム全体を動かす力」を持つ人としてアピールできるのです。
採用担当者が注目する副部長の強み
副部長には、リーダーとは違う形のリーダーシップが求められます。
採用担当者は特に次の3点を重視しています。
① 組織を支える調整力
部長とメンバーの間に立ち、双方の意見をまとめて行動に移す力です。
社会に出ても上司・同僚・取引先など、立場の異なる人を調整する力は欠かせません。
② 責任感のあるサポート姿勢
目立たなくても、チームを支える意識を持って行動できるのが副部長。
特に、リーダー不在時に代わりに行動した経験などは高く評価されます。
③ 信頼関係を築くコミュニケーション力
人と人の間に立つ立場だからこそ、相手を理解し、適切に関わる力が求められます。
聞く力や共感力を発揮できる人は、どんな職場でも重宝されます。
副部長タイプ診断チャート:「あなたのリーダーシップスタイルはどれ?」
自分の“副部長タイプ”を知ることで、PRの軸を明確にできます。
| 質問 | 多く当てはまるタイプ |
| 部長とメンバーの意見をまとめるのが得意 | 【調整型】バランス感覚に優れるタイプ |
| 周囲のサポートを自然にしていた | 【支援型】気配りと優しさで支えるタイプ |
| 部の運営改善を提案していた | 【改革型】主体的に課題を見つけるタイプ |
| トラブル時に間に入って対応していた | 【調停型】人間関係を円滑にするタイプ |
このように、自分の副部長としての“支え方”を整理しておくことで、
自己PRをより具体的かつ印象的に伝えられるようになります。
「副部長」経験からアピールできる主な強み
調整力:リーダーとメンバーの橋渡し役
副部長の代表的な強みは「調整力」です。
部長の意図を理解しつつ、メンバーの声を拾い、両者の意見をすり合わせる役割を担います。
例えば、方針に納得していないメンバーがいれば、個別に話を聞いて不安を解消したり、
逆に現場の課題を部長に伝えて改善策を提案したりと、双方にとって最善の形を探る力が問われます。
このスキルは、社会人になってからも上司や他部署、取引先との関係構築に直結します。
単なる“仲介”ではなく、「人と人をつなぐ力」として企業が重視する要素です。
協調性:立場や意見の異なる人をまとめる力
副部長は、さまざまな立場のメンバーをまとめる必要があります。
意見の対立や温度差が生まれたときに、それぞれの考えを尊重しつつ合意点を見つける――
この「協調性」は、組織の安定を支える欠かせない力です。
たとえば、「試合で出場できないメンバーのモチベーション維持」「役割分担の不公平感の調整」など、
人の感情に関わる問題を扱うことも多かったのではないでしょうか。
相手の立場を理解しながらチーム全体をまとめる経験は、企業でも高く評価されます。
サポート力:他人を支える視点・気配り
副部長は常に「誰かのために動く」立場です。
部長の負担を減らしたり、困っているメンバーをフォローしたりする行動の積み重ねが、
チームの信頼を生み出します。
この「サポート力」は、組織で成果を出すための土台。
ときに自分が目立たなくても、全体を良くするために動ける姿勢は、どの職種でも重宝されます。
面接では「どんな状況で誰を支えたのか」「その結果どう変わったのか」を具体的に話すと効果的です。
主体性:自ら課題を見つけ、動ける姿勢
副部長は「指示待ち」では務まりません。
部長が忙しいときには代わりに判断したり、チームの問題に気づいて先回りで動いたりする必要があります。
こうした経験を通じて培われるのが「主体性」です。
リーダーの指示に頼らず、自ら課題を見つけて改善に向けて行動する姿勢は、
社会に出てからも大きな武器になります。
特に「自分の提案でチームが良くなった」ようなエピソードがあれば、説得力が増します。
強み変換マッピング表:「役割→行動→強み」に変える方法
副部長の経験をそのまま語るだけでは伝わりません。
下のように「役割 → 行動 → 強み」という形に整理すると、印象的に伝えられます。
| 役割 | 行動 | 強み |
| 部長の補佐 | ミーティングの内容を整理し、メンバーに共有 | 調整力・情報伝達力 |
| チーム全体のまとめ役 | 意見の衝突を仲裁し、全員が納得できる結論を導く | 協調性・冷静な判断力 |
| サポート担当 | 部長不在時の業務を代行し、滞りなく進行 | 責任感・主体性 |
| メンバー支援 | 落ち込んでいる後輩に声をかけ、行動を促す | 共感力・サポート力 |
このように整理しておくと、自己PRや面接で質問された際にも一貫して答えやすくなります。
副部長の自己PRで高評価を得る3つのコツ
①「支える姿勢」をポジティブに語る
副部長という立場は、どうしても「裏方」や「補佐役」として見られがちです。
しかし、採用担当者が知りたいのは“サブポジションで何を考え、どう動いたか”という点です。
たとえば「部長を支える立場でした」と言うだけでは受け身に聞こえますが、
「部長が意思決定しやすいよう、意見を整理して伝えるようにしていました」と言い換えると、
自分の判断と行動が伝わります。
“支える=能動的に動く”という姿勢を強調しましょう。
② チーム全体を見て行動したエピソードを入れる
自己PRでは「自分がどう動いたか」だけでなく、「チームがどう変わったか」まで語ることが重要です。
副部長は、メンバーの状況を最も近くで見ている立場。
全体のモチベーションを保ったり、個々の意見を反映させたりといった動きができる点が強みです。
たとえば「メンバー間の意見の食い違いを調整し、全員が納得する方針をまとめた」など、
チーム全体に良い影響を与えた行動を具体的に伝えると、評価につながります。
③ リーダーシップだけでなく“フォロワーシップ”を意識
多くの学生が「リーダーシップ」を前面に出しますが、企業が求めているのは
“リーダーを支えながらチームを成功に導ける人”です。
フォロワーシップとは、主体的に考え、上司や仲間を支援して成果を上げる力のこと。
副部長の経験はまさにこの要素を示す最適な材料です。
自分がどのようにリーダーを支え、チームの成果に貢献したかを明確にすると、
「協調性と主体性を併せ持つ人」として印象に残ります。
面接官の本音:「“副部長=サブポジ”ではなく“組織運営の要”」
採用担当者は「副部長」という役職そのものよりも、
そこから見える“行動の質”を重視しています。
実際の面接現場では、次のような印象の違いが生まれます。
- NG例:「部長の指示を補助していました」→受け身な印象
- 好印象例:「部長が決断しやすいように、メンバーの意見を整理しました」→能動的で信頼できる印象
つまり、副部長は“リーダーの右腕”としてチームを支える存在。
あなたの行動が「組織を動かしていた」と伝われば、評価は一段と高まります。
自己PRで副部長を伝える構成
① 結論:自分の強みを一言で伝える
まずは「自分の強み」を最初に簡潔に示しましょう。
たとえば「私は副部長として、チーム全体を支える調整力を発揮してきました」のように、
強みと役割をセットで伝えるのがポイントです。
この一文で「何をアピールしたいのか」が明確になるため、
面接官も話の軸を理解しやすくなります。
② 根拠:副部長としての行動や工夫を具体的に話す
次に、その強みを裏づける行動や工夫を具体的に説明します。
「部長の指示内容を整理して共有した」「意見の食い違いを調整した」など、
あなたがチームのためにどんな役割を果たしたのかを描く部分です。
この段階では“自分が何を考えて行動したか”を中心に語ると、
主体的に動いた印象を与えることができます。
③ 成果:チームの変化・周囲からの評価を加える
エピソードを語ったら、その結果どうなったのかを伝えましょう。
「チームの雰囲気が良くなった」「部長から信頼されて任される範囲が広がった」など、
数字や言葉で成果を表現できると説得力が高まります。
自分だけの成果ではなく、「チーム全体の前進」を示すことで印象がより良くなります。
④ 未来:入社後の活かし方を述べる
最後に「この経験をどう活かすか」で締めます。
「職場でも、上司とメンバーの橋渡し役として組織を支えたい」といった形で、
副部長で得たスキルを社会人としてどう発揮できるかを語りましょう。
この“未来視点”があると、成長意欲の高い学生として評価されます。
PREP+STAR法テンプレート:「副部長経験を構造的に伝える」
自己PRを整理する際は、「PREP法」と「STAR法」を組み合わせると分かりやすくなります。
| 構成 | 内容 | 例文の一部 |
| P(Point) | 結論 | 私の強みは、チームをまとめる調整力です。 |
| R(Reason) | 理由 | 副部長として、部長とメンバーの意見をつなぐ役割を担っていました。 |
| E(Example) | 具体例(STAR法) | S:大会準備で意見が割れた際、A:双方の主張を整理して提案し、R:全員が納得する方針を決定。T:結果的に練習効率が上がり、目標を達成。 |
| P(Point) | まとめ | この経験から、相手を理解しながら組織を動かす力を身につけました。 |
この流れを意識すると、短い時間でも一貫性のある自己PRを組み立てられます。
受かるESを作りたいけど、自己PRも志望動機も思いつかない、、
そこでAIにES作成を手伝ってもらいませんか?
自己PR、ガクチカ、志望動機など、ESにはたくさんの項目があり、そのどれもが簡単に考えられるものではありません。特に初めてのES作りには時間がかかってしまうものです。できればパッと簡単に短時間でESを完成させたいと思いませんか?
そんな人は、「ES自動作成ツール」を活用しましょう。質問に答えるだけで自動でESの文章を作成してくれるため、自分で1から作るよりも簡単に短時間でESを作ることができます。
らくらく就活をLINE追加するだけで使えるので、すぐにES作成を始めましょう!
自己PR例文:「副部長」経験を活かしたアピール例
例文① 調整役としてチーム全体を支えた経験
私は副部長として、部長とメンバーの間に立ち、意見を調整する役割を担っていました。
大会に向けて方針が対立した際には、それぞれの意見を整理し、全員が納得できる案を提案しました。
結果的にチームのまとまりが生まれ、練習効率も向上。部長からも「全員の意見を生かしてくれて助かった」と評価されました。
この経験を通じて、立場の異なる人をまとめ、チームとして前進させる調整力を身につけました。
今後も、周囲の意見を尊重しながら最適な方向に導ける人材を目指します。
例文② 主体的に行動し部の士気を高めた経験
副部長として、部長の負担を減らすために自ら行動することを意識していました。
特に大会直前、メンバーのやる気が下がっていたときには、ミーティングを提案し、全員で目標を再確認。
一人ひとりが「自分の役割」を再認識できたことで、練習への参加率が大幅に上がりました。
この経験から、組織の課題を自ら見つけて行動する主体性を学びました。
社会に出ても、状況を分析し、自分から動いてチームを良い方向に導ける存在でありたいと考えています。
例文③ トラブル対応を通じて信頼を得た経験
私が副部長を務めていた際、文化祭の準備中にメンバー間で対立が起こりました。
そのとき私は、双方の意見を丁寧に聞き取り、冷静に話し合いの場を設けました。
結果、誤解が解け、全員で協力して当日の運営を成功させることができました。
この経験を通して、相手の立場を理解しながら課題を解決する力が身につきました。
今後も人と人をつなぎ、信頼を築きながらチームの成果に貢献したいと考えています。
例文④ リーダーを支え、チームの成果を上げた経験
私は部長を支える立場として、チームの運営を円滑に進める役割を担っていました。
特に大会準備の時期は、部長の負担が増えたため、練習計画の立案や連絡調整を代わりに行いました。
その結果、準備がスムーズに進み、前年より良い成績を残すことができました。
「支えることもリーダーシップの一つ」であると実感し、状況に応じて最適な役割を果たす力が身につきました。
仕事でも、周囲の動きを見ながら組織全体を支えられる人材を目指しています。
NG例文と改善例:「“地味な副部長”で終わらせない書き方」
副部長のPRでありがちなのが、「裏方でした」「部長をサポートしていました」とだけ述べるケースです。
この書き方では、自分の行動や成果が伝わらず、“印象に残らない”自己PRになってしまいます。
【NG例】
「私は副部長として部長のサポートをしていました。特に目立った成果はありませんが、地道に頑張りました。」
【改善例】
「副部長として、部長が意思決定しやすいように意見を整理し、全員が納得する方針を導きました。その結果、チームの雰囲気が改善しました。」
ポイントは、「どんな行動をとり、どう変わったか」を具体的に伝えること。
“支える”ことを“能動的な貢献”として表現するのが、副部長PR成功のカギです。
面接で「副部長経験」を話すときのポイント
「自分の役割」を明確にする(何を担っていたか)
面接では、まず「自分がどんな役割を担っていたのか」をはっきり伝えることが大切です。
副部長といっても、人によって仕事内容は異なります。部長の補佐、メンバー管理、運営全般など、
自分が具体的にどの部分を担当していたのかを示すことで、話に説得力が生まれます。
たとえば「部長の方針をチームに浸透させる役割を担っていました」や
「日々の進捗管理とメンバーとの調整を担当していました」など、
“責任の範囲”を最初に明確にするのがポイントです。
「工夫したこと」「変化させたこと」を具体的に語る
面接官が知りたいのは「あなたが何を変えたか」です。
単に“頑張った”ではなく、“どう工夫して成果につなげたか”を伝えましょう。
たとえば「意見の食い違いが多かったため、定期的なミーティングを設けた」など、
自分の発案で取り組んだ改善点を話すと印象が強まります。
組織をより良くするために“自ら動いた姿勢”を伝えるのがコツです。
「チームの成果」に結びつけて話す
副部長の自己PRは、個人よりも“チームとしての成果”と結びつけるとより効果的です。
「自分が動いたことでチームがどう変わったか」「雰囲気や成績がどう改善したか」を具体的に述べると、
組織全体に貢献できる人材として印象づけられます。
面接官は、“周囲を巻き込みながら結果を出せる人”を求めています。
成果は数字でなくても構いません。行動の結果として「信頼を得た」「協力体制が強まった」といった変化でも十分評価されます。
副部長の“話し方チェックリスト”:謙遜しすぎず自信を持つコツ
副部長経験を語るとき、多くの学生が「自分は裏方なので…」と控えめになりすぎる傾向があります。
しかし、面接では“責任を持って動いた姿勢”をしっかり伝えることが重要です。
以下のチェックリストを意識してみましょう。
| チェック項目 | ポイント |
| 「〜を手伝いました」ではなく「〜を担当しました」と言えているか | 受け身ではなく主体的な表現にする |
| 「部長の指示で」ではなく「自分で考えて」動いた部分を語れているか | 主体性を明確にする |
| 「大したことはしていません」と否定していないか | 自分の努力を過小評価しない |
| 「支える」行動の結果を具体的に伝えているか | 影響力を客観的に説明する |
副部長は「裏方」ではなく「組織を支える中心」。
自信を持って語ることで、あなたの誠実さと実行力が自然と伝わります。
副部長の経験を他の職種に活かすには
営業職:相手に合わせて行動する調整力
営業職では「相手の立場を理解して行動する力」が非常に重要です。
副部長として部長とメンバーの意見をまとめた経験は、顧客と会社の間で調整する営業に直結します。
たとえば、顧客の要望を正確に把握し、自社の提案を最適化する際には、
相手の気持ちをくみ取りながら最善策を導く“橋渡し力”が求められます。
副部長として培った柔軟な対応力やコミュニケーション力は、営業現場で確実に活きます。
事務・管理職:サポート力・報連相の徹底
事務や管理職では、正確さとサポート力が仕事の質を左右します。
副部長として裏方で支えてきた経験は、まさにこの分野にマッチします。
リーダーを支えながら全体を円滑に動かす姿勢、細やかな気配り、
そして「報・連・相(報告・連絡・相談)」を怠らない習慣。
これらは企業の組織運営に欠かせない力です。
副部長経験を通して学んだ「サポートを通じてチームを成功に導く力」を、そのまま強みとして活かせます。
リーダー職志望:支える経験を“マネジメントの基礎”として語る
副部長としての経験は、将来リーダーを目指す人にも大きな強みになります。
なぜなら、チームを支える経験は「人を動かす仕組み」を理解する土台になるからです。
リーダーシップは“指示を出す力”ではなく、“チーム全体を見渡し最適化する力”です。
副部長時代に培った「全員の立場を理解して行動する力」は、
将来のマネジメントにおいて、非常に実践的なスキルになります。
面接では「支える経験があったからこそ、将来リーダーとしての視野が広がった」と語ると効果的です。
職種別マッチングMAP:「副部長経験を活かせる仕事」
| 職種 | 活かせる副部長スキル | 活躍ポイント |
| 営業職 | 調整力・対人理解 | 顧客と社内の意見をまとめる力 |
| 事務職 | サポート力・正確性 | チームの運営を円滑に支える姿勢 |
| 管理職 | 報連相・責任感 | 組織全体を見て動ける信頼性 |
| リーダー職 | マネジメント視点 | 支える経験を活かした統率力 |
| 接客・サービス職 | 共感力・気配り | 相手の感情をくみ取る対応力 |
このように、副部長として培った力は特定の職種に限らず、
あらゆる仕事の基盤になる“社会人力”として活用できます。
「副部長」を自己PRに使う際の注意点
「部長が主役、自分は補佐」だけでは印象に残らない
自己PRで「部長のサポートをしていました」とだけ伝えると、どうしても受け身な印象になります。
副部長としての価値は、“リーダーの指示を聞いて動く”ことではなく、
“チーム全体を動かすために自分で考えて行動した”部分にあります。
たとえば、「部長が意思決定しやすいようにメンバーの意見を整理した」など、
あなたが主体的に動いた場面を具体的に挙げましょう。
「自分がどう貢献したか」を明確にすれば、印象に残るPRになります。
「何を考えて行動したか」を中心に語る
行動そのものよりも、そのときの“考え方”を伝えることが重要です。
採用担当者は「この人が入社したら、どう行動するか」を想像しながら話を聞いています。
たとえば「意見が対立した際、全員の意見を聞くことで納得感を高めようと考えた」など、
目的を持って行動したことを示すと、判断力や思考力のある印象を与えられます。
「結果」よりも「プロセス」重視で伝える
副部長の経験は、派手な成果よりも“過程の工夫”を評価されます。
たとえば「勝利した」「受賞した」といった結果よりも、
「チームの意見をまとめるためにどんな工夫をしたか」「雰囲気をどう変えたか」など、
プロセスに焦点を当てて話す方が、副部長らしい誠実さが伝わります。
企業は“コツコツ型のリーダーシップ”を評価する傾向があるため、
自分の努力を地道に語ることが高評価につながります。
面接官コメント例:「良い副部長PR」「もったいない副部長PR」
| パターン | コメント内容 |
| 良い副部長PR | 「役職よりも行動で語れていて、自分の考えがしっかりしている」「周囲を支える姿勢が伝わり、チーム貢献の意識が高い」 |
| もったいない副部長PR | 「具体的な行動がなく、ただ『支えていた』だけに聞こえる」「リーダーに比べて印象が薄く、強みが伝わらない」 |
“地味だけど信頼できる人”という印象を狙うのが理想です。
自分の行動と考えを中心に語れば、副部長という立場の価値がより際立ちます。
ESを作りたいけど、どう書けばいいかわからない、、
「志望企業に提出するESを書かなきゃいけないけど、何から始めればいいのか分からない」そんな悩みを抱えたことはありませんか?限られた時間で質の高いESを仕上げるには、書き出しから構成までサポートがあると安心ですよね。
「ES作成ツール」なら、簡単な質問に答えるだけで、AIが自動であなたの強みや経験を文章化してくれるので、ゼロからESを作り上げることが可能です。
「うまく言葉にできない…」という方でも安心して始められます。
らくらく就活をLINE追加して、簡単なアンケートに答えるだけで無料で使えるので、すぐにESを作成してみましょう!
副部長経験をさらに魅力的にする+α要素
リーダー不在時の対応など“危機管理”エピソードを入れる
副部長としての経験をより印象的にするには、「予想外の事態にどう対応したか」を語るのがおすすめです。
たとえば、部長が体調不良や急用で不在になった際に、あなたが代わってチームをまとめた経験。
そうした“非常時の判断力”は、社会人にとっても重要なスキルとして評価されます。
「誰かがやらなければならない場面で、自分が一歩踏み出した」
──このようなストーリーは、責任感と行動力の両方を伝える強力なPRになります。
メンバー育成・サポートの経験を加える
もう一つ効果的なのは、「他のメンバーを成長させた経験」を加えることです。
副部長は、チーム全体を見渡せる立場にいるからこそ、後輩や仲間の変化に気づきやすい存在です。
たとえば「練習に消極的だった後輩に声をかけ、意欲を引き出した」など、
人を支え、成長を促したエピソードは“人材育成の素質”として高く評価されます。
これは将来リーダーを目指す際にも強い武器になります。
経験振り返りワークシート:「副部長としての成長を言語化する」
自分の経験をより深く整理したい人は、以下のシートを使って振り返ってみましょう。
| 振り返り項目 | 自分の回答例 |
| 1. 副部長として特に印象に残っている出来事は? | 部員の対立をまとめ、チームが一体化した瞬間 |
| 2. そのとき、自分はどんな行動をした? | 双方の意見を聞いて整理し、話し合いの場を設けた |
| 3. その行動でチームや自分はどう変わった? | お互いの信頼関係が深まり、自分も責任感が強くなった |
| 4. この経験から学んだことは? | 問題を人任せにせず、自分から動く姿勢の大切さ |
| 5. 社会人になってどう活かしたい? | チームの調整役として、組織を円滑に動かしたい |
このように整理しておくと、ESや面接で質問されたときにも一貫したストーリーで答えられます。
「自分の経験を“支える力”として再定義する」ことが、副部長PRを完成させる最終ステップです。
まとめ
副部長は“影のリーダー”としてチームを支える重要な存在です。
調整力・サポート力・主体性を具体的なエピソードとともに伝えれば、
「チームで信頼される人」という印象を強く残すことができます。
大切なのは、役職名よりも“行動と考え方”で自分の価値を示すこと。
あなたがチームの中でどんな役割を果たし、どんな変化を生み出したのかを丁寧に語れば、
“副部長”という経験は、確かな強みとして輝きます。