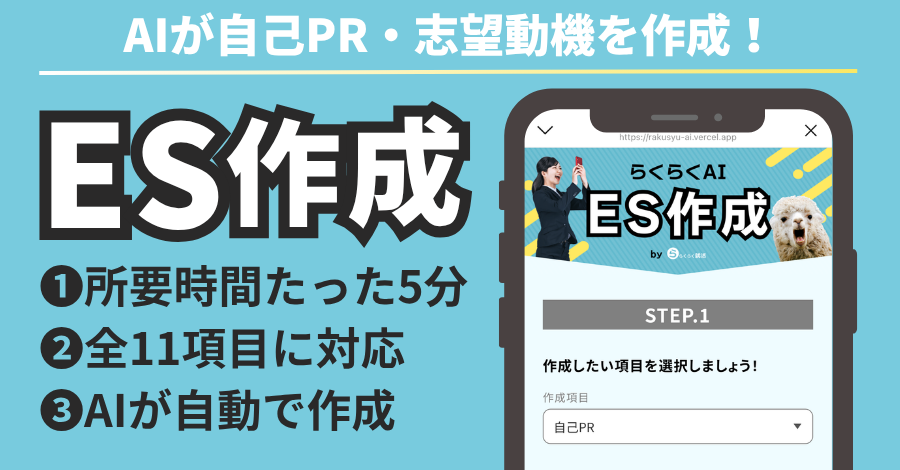【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
自己PRの内容選びでつまずく就活生が多い理由
就活において避けては通れないのが「自己PR」です。履歴書やエントリーシート(ES)だけでなく、面接でも必ずといっていいほど質問されるため、就活の成否を分ける重要なポイントになります。しかし、多くの学生が「自分の強みがわからない」「エピソードが思い浮かばない」「企業が評価するポイントが見えない」と悩み、なかなか納得できる自己PRを完成できないのが実情です。
この背景には、そもそも自己PRの目的や評価基準を理解できていないことが大きく影響しています。単に「性格の良さ」や「学力」を伝えるのではなく、企業は入社後に活躍できる可能性を見極めたいと考えています。そのため、自己PRの内容選びでは「企業目線」が不可欠なのです。
「評価される自己PR」はどう作るのか
評価される自己PRを作るためには、自分の強みをただ主張するだけでは不十分です。具体的な経験や成果を示し、その経験を通じて得た学びを明確にしたうえで、入社後どのように活かすのかを一貫して伝える必要があります。また、表現の仕方や構成にも工夫が求められ、読み手にとって理解しやすく説得力のある文章に仕上げることが大切です。
本記事でわかること(内容の決め方、例文、診断ツール 等)
この記事では、自己PRを作成するうえで役立つ以下の内容を網羅的に解説します。
- 自己PRの基礎知識と目的
- 企業が評価するポイントと選び方
- 独自の診断チャートやマトリクスによる強み発見ツール
- 強み別の例文や業界別に好まれる傾向
- 通過率を上げるためのテクニックとチェックリスト
- NG例と改善方法
- 相談先やAIツールの活用法
これらを踏まえることで、「どんな内容にすればよいか」「どう書けば評価されるのか」という悩みを解消し、あなたに合った自己PRを完成させられるようになります。
目次
そもそも自己PRとは?内容を考える前に押さえる基礎
自己PRの内容を考える前に、まずは「そもそも自己PRとは何か」を正しく理解することが大切です。目的や役割を整理しておくことで、内容選びの方向性が明確になり、企業に伝わりやすい文章へと仕上げることができます。ここでは、自己PRの目的や企業が注目している視点、そして「長所」「志望動機」との違いについて解説していきます。
自己PRの目的と企業が見るポイント
自己PRとは、就活生が自分の強みや特性を企業に伝え、「入社後に活躍できる可能性がある人材である」と示すためのアピールです。単なる自己紹介や長所の羅列ではなく、具体的な経験や成果を通じて自分の強みを裏付けることが重要になります。
企業が自己PRで知りたいのは、「この学生はどんな場面で力を発揮できるか」「組織に貢献できるか」という点です。言い換えれば、過去の経験そのものよりも、その経験を通じて培われた行動特性や考え方が、今後の仕事でどのように再現されるのかを重視しているのです。
例えば「アルバイトで後輩指導を担当した」というだけでは弱いですが、「新人が業務を理解できるようにマニュアルを作成し、定着率を高めた」といった具体性を持たせると説得力が増します。さらに「この経験を活かして、入社後は新人教育やチーム運営に積極的に取り組みたい」と未来につなげることで、企業は成長の可能性をイメージしやすくなるのです。
「長所」「志望動機」との違いとは?
自己PRと似ているようで混同されがちなものに、「長所」と「志望動機」があります。いずれも就活で必ず問われるテーマですが、それぞれの役割を明確に理解しておかないと、内容が重複したり一貫性を欠いたりしてしまいます。ここでは、3つの違いを整理してみましょう。
まず「長所」は、自分の特徴を端的に伝えるものです。たとえば「責任感がある」「行動力がある」といった、自分の性格的な強みをシンプルに表現します。ただし、長所は短い言葉で示すため、その裏付けまでは求められません。
次に「志望動機」は、なぜその会社で働きたいのかを伝えるものです。企業の理念や事業内容に共感した理由、自分のキャリアプランとの接点などを語り、応募先への適性や意欲を示すのが目的です。
一方で「自己PR」は、長所を裏付ける具体的なエピソードを提示し、その強みを入社後にどう活かすかまで伝える役割を持ちます。たとえば「協調性」という長所を自己PRに発展させるなら、「サークル活動で異なる立場のメンバー同士を調整し、合意形成に導いた経験がある。入社後もチームの調和を意識し、成果を最大化したい」といった形です。
つまり、長所は“素材”、志望動機は“目的”、自己PRは“証明と未来への接続”という位置づけです。この3つを意識的に切り分けることで、説得力と一貫性を兼ね備えた就活対策が可能になります。
履歴書・ES・面接での使い分け
自己PRは、提出する書類や面接などの場面によって表現の仕方を変える必要があります。どの媒体でも伝えたい「強み」は同じで構いませんが、文字数や話し方の形式に合わせて調整することで、より効果的に相手に届くようになります。
履歴書では、限られたスペースの中で簡潔にまとめることが求められます。おおよそ300〜400字程度が目安で、強みを冒頭で示し、経験の要点を一つ紹介し、最後に入社後の活かし方を一文で結ぶのが王道の構成です。文章が短いため、エピソードは細部まで語らずに「何をして、どうなったのか」の流れを端的にまとめることが重要です。
エントリーシート(ES)では、企業ごとに文字数が指定されることが多く、600〜800字程度の分量を求められる場合もあります。この場合は、経験を深く掘り下げて詳細を記述し、課題や工夫した点、成果の背景などを具体的に示しましょう。エピソードの「プロセス」をしっかり書くことで、あなたの思考力や行動力が浮き彫りになります。
面接では、文章を暗記してそのまま読み上げるのではなく、聞き手に伝わりやすい話し方を心がけます。時間の目安は2〜3分程度で、話の流れは履歴書と同じく「強み→経験→学び→入社後の活かし方」にまとめるのが効果的です。緊張して話が長くなりがちですが、面接官が聞きたいのは「この学生は仕事で活躍できるかどうか」という一点なので、焦点を絞って伝えましょう。
このように、自己PRはどの媒体でも「強みの一貫性」を保ちつつ、文字数や話し方に応じて柔軟に使い分けることが重要です。
企業に伝わる自己PRの内容の選び方
自己PRを考えるとき、多くの学生は「自分の強みは何だろう」と自己分析から始めます。しかし、自己分析だけでは自己満足に終わってしまい、企業にとって魅力的に映らないこともあります。大切なのは「企業がどんな人材を求めているか」という視点と、自分の経験や強みを結びつけることです。ここでは、企業が実際に評価しているポイントや、その整理の仕方について解説します。
企業が評価する5つのポイント
企業が自己PRで見ているのは、単に「良い人そうか」「優秀そうか」ではありません。実際には、以下のような具体的な観点を持っています。
入社後の再現性
企業が最も重視するのは、過去の経験から得られた行動特性が入社後にも発揮されるかどうかです。例えば、サークル活動で培った調整力は、社会人になってからも会議やプロジェクトで再現されやすいと評価されます。自己PRを作る際は、「この経験で身につけた力は、入社後にも同じように発揮できる」というストーリーを描くことが大切です。
強みと企業ニーズの一致
どれほど立派な強みでも、企業が求めていないものなら評価されにくいものです。例えば「独創的なアイデアを出す力」が強みでも、決められたルールを守ることを重視する業界では響きにくいでしょう。企業研究を通じて「その企業が求める人物像」を理解し、自分の強みと接点を見つけることが重要です。
論理性・構成力
自己PRは論理的な構成で伝えることで、説得力が増します。エピソードを時系列に並べるのではなく、「強み→エピソード→成果→学び→入社後の活かし方」という流れを意識することで、面接官に理解しやすい文章に仕上がります。
数値的根拠
評価される自己PRには、具体的な数値や成果が盛り込まれています。たとえば「売上を伸ばした」よりも「前年比120%の売上を達成した」と書く方が、説得力は格段に高まります。数値がない場合でも「○人をまとめた」「○か月間継続した」といった定量的な表現を加えることが効果的です。
第三者評価の有無
自分だけが「頑張った」と言うよりも、他者から評価された実績があると信頼性が増します。例えば「教授から表彰された」「アルバイト先の店長から感謝された」といったエピソードは、第三者の視点を加えることで客観性を補強できます。
自己PRのタイプ別診断チャート
自己PRを作るときに「自分の強みが見つからない」「どんな内容を書けばいいかわからない」と悩む学生は少なくありません。そんなときに役立つのが、簡単な診断チャートです。Yes/Noで答えながら進むことで、自分がどのタイプの強みに近いのかを把握できます。診断はあくまで目安ですが、方向性を見つける手がかりになります。
Yes/Noで進むチャート形式
以下の質問に答えてみましょう。
- 新しいことに挑戦するのが好きだ → Yes → Aタイプへ
No → 次の質問へ - 周囲との関係を大切にして動くことが多い → Yes → Bタイプへ
No → 次の質問へ - 論理的に物事を分析したり改善したりするのが得意 → Yes → Cタイプへ
No → Dタイプへ
このように進めることで、自分がどのタイプに近いかを見極められます。
診断結果別におすすめの強みタイプを紹介
診断の結果は、次のようなタイプに分類できます。
- 挑戦型(Aタイプ)
新しい環境や課題に積極的に飛び込み、困難を乗り越えることで成長するタイプ。ベンチャー企業や企画系の職種で評価されやすい。 - 貢献型(Bタイプ)
周囲を支え、チームの成果を最大化することに力を発揮するタイプ。協調性やサポート力を求める企業で高く評価されやすい。 - 分析型(Cタイプ)
データや事実をもとに課題を整理し、改善策を考えるタイプ。メーカーやIT、コンサル業界などで重視される傾向がある。 - 努力型(Dタイプ)
一見目立たなくても、継続力や粘り強さで成果を出すタイプ。営業職や研究職などで力を発揮しやすい。
このように自分の傾向をタイプとして捉えると、自己PRの方向性が見えやすくなります。たとえば「挑戦型」なら困難な課題への挑戦経験を中心に据える、「貢献型」ならチームを支えた経験を強調するといった具合に、内容を組み立てやすくなるでしょう。
自己PRに使える内容の強み別アイデアと例文
自己PRは「自分の強みをどう伝えるか」が重要ですが、その強みを裏付ける経験をどう選ぶかで説得力が大きく変わります。特に就活生がよく悩むのは、「どのエピソードを選べばいいのか」「平凡な経験しかないのでは」という点です。ですが、部活動やアルバイト、ゼミ活動など身近な経験でも、切り口を工夫すれば立派な自己PRになります。ここでは強みと経験を掛け合わせるアイデアや具体的な例文を紹介していきます。
よくある強み×経験の組み合わせパターンを紹介
自己PRでは「強み」と「経験」を掛け合わせることで、エピソードが生き生きと伝わります。ここでは代表的なパターンを紹介します。
自己PRアイデア生成マトリクス
強みの方向性と経験のカテゴリを掛け合わせると、自己PRのネタが見つけやすくなります。
- 部活 × リーダーシップ
例:キャプテンとして部員をまとめ、試合で過去最高成績を残した経験 - アルバイト × 調整力
例:シフト管理を工夫し、店長からも評価される店舗運営に貢献した経験 - ゼミ × 分析力
例:膨大なデータを整理し、ゼミ論文の方向性を導き出した経験 - ボランティア × 協調性
例:地域活動で多世代の人と協働し、プロジェクトを成功に導いた経験 - 長期インターン × 課題解決力
例:営業チームの課題を分析し、業務効率を改善した経験
このように「経験カテゴリ × 強み」というマトリクスを意識することで、平凡だと思っていた経験も説得力のある自己PRに変換することができます。
性格別に自己PRの強みの例文を10個紹介
主体性
私の強みは主体的に行動できる点です。学園祭の企画において、予算が不足し運営が難航していた際に、私は自ら代替案を提案しました。スポンサー企業に協賛を依頼し、必要な費用を確保したことで、企画を予定通り実施できました。この経験から、課題に直面しても受け身にならず、自ら動くことで道を切り開けることを学びました。入社後も業務の中で課題を発見した際には、自ら改善策を考え、行動に移す姿勢で貢献したいと考えています。
協調性
私の強みは協調性です。飲食店でのアルバイトでは、スタッフ間の意見対立が原因でシフト調整が難航することがありました。私は全員の希望を整理し、勤務状況を見える化するシステムを提案して、店長と共に導入しました。その結果、スタッフの不満が減り、離職率も改善されました。この経験を通じ、立場や考え方の異なる人の意見を尊重しながら合意形成を行う力を磨くことができました。入社後もチームワークを重視し、円滑な業務遂行に貢献します。
継続力
私の強みは継続力です。高校時代から大学までの7年間、毎日欠かさずトレーニングを続け、大学の部活動では3年間レギュラーを維持しました。特に体調を崩した時期もありましたが、軽いメニューに切り替えるなど工夫し、継続することを優先しました。この経験から「小さな努力を積み重ねることで、大きな成果につながる」という考えを身につけました。社会人になってからも、成果が出るまで粘り強く努力し続ける姿勢を大切にします。
課題解決力
私の強みは課題解決力です。所属していたサークルでは毎年イベントが赤字で、存続の危機にありました。私は過去の収支を分析し、赤字の原因が「集客不足とコストの高さ」にあることを突き止めました。その上でイベント形式を変更し、SNSを活用して宣伝を強化した結果、参加者数が前年の1.5倍に増え、黒字化を実現しました。この経験を通じ、現状を正確に把握し、根本的な課題を解決する力を養いました。入社後も業務改善や新しい提案に活かしたいと考えています。
行動力
私の強みは行動力です。留学先で国際交流が十分に行われていないと感じた私は、自ら現地の学生に声をかけ、交流イベントを企画しました。最初は参加者が集まらず苦労しましたが、継続的に告知活動を行い、最終的に50人以上が参加するイベントに成長させました。この経験を通じ、行動に移すことで環境を変えられることを実感しました。入社後も必要な行動を恐れずに取り、周囲を巻き込んで成果を生み出したいと考えています。
責任感
私の強みは責任感です。アルバイト先で新人教育を任された際、最初は指導方法が不十分で離職する人も出てしまいました。そこで私はマニュアルを作成し、OJTの流れを体系化しました。その結果、半年後には新人の定着率が大幅に改善し、店長からも高く評価されました。この経験から、与えられた役割を最後までやり遂げる姿勢を大切にするようになりました。入社後も責任を持って業務を遂行し、信頼される存在を目指します。
リーダーシップ
私の強みはリーダーシップです。ゼミ活動では研究発表に向けてチームリーダーを務めました。メンバーの意見が分かれて研究テーマが定まらない状況でしたが、全員の意見を整理し、共通点を見つけ出すことで方向性を決定しました。その後も役割分担を明確にして進行管理を行い、学会発表では高い評価をいただくことができました。この経験から、人をまとめながら成果を出す力を身につけました。入社後もリーダーシップを発揮し、チームの成果最大化に貢献します。
柔軟性
私の強みは柔軟性です。ゼミの研究発表直前、予定していた会場が急遽使用できなくなるトラブルがありました。私はすぐにオンライン発表に切り替える提案を行い、資料を修正して発表に臨みました。その結果、大きな混乱なく研究を発表できました。この経験から、状況に応じて柔軟に対応しながら成果を出す力を学びました。入社後も変化の多い環境において、冷静に最適な対応を選び取れる人材を目指します。
挑戦心
私の強みは挑戦心です。プログラミングに未経験で挑戦し、半年間独学を続けて簡単なアプリを開発しました。途中で壁にぶつかりましたが、オンライン講座を利用し、エンジニアの知人に質問するなど積極的に学ぶ姿勢を崩しませんでした。完成したアプリはゼミの仲間にも使ってもらえ、役立つツールとして評価されました。この経験を通じ、新しい分野にも果敢に挑戦し成果を出す力を培いました。入社後も新しい業務や環境に前向きに挑み続けます。
分析力
私の強みは分析力です。長期インターンでは営業活動の成果が伸び悩んでいたため、過去のデータを集めて顧客層ごとのアプローチ方法を分析しました。その結果、効率的な営業リストを作成でき、アポ取得率を20%向上させることができました。この経験から、事実に基づいて改善点を導き出す力を磨きました。入社後も冷静な分析で課題を見極め、成果につながる提案を行っていきたいと考えています。
ESを作りたいけど、どう書けばいいかわからない、、
「志望企業に提出するESを書かなきゃいけないけど、何から始めればいいのか分からない」そんな悩みを抱えたことはありませんか?限られた時間で質の高いESを仕上げるには、書き出しから構成までサポートがあると安心ですよね。
「ES作成ツール」なら、簡単な質問に答えるだけで、AIが自動であなたの強みや経験を文章化してくれるので、ゼロからESを作り上げることが可能です。
「うまく言葉にできない…」という方でも安心して始められます。
らくらく就活をLINE追加して、簡単なアンケートに答えるだけで無料で使えるので、すぐにESを作成してみましょう!
評価されやすい自己PRの内容の傾向を業界別に紹介
就活での自己PRは、どの業界を志望するかによって好まれる強みや評価されやすい内容が変わります。例えば、商社では行動力や挑戦心が重視される一方、メーカーでは継続力や分析力が評価されやすいといった傾向があります。自分の強みがどの業界にフィットするのかを知ることは、企業研究と自己分析を結びつける上で非常に重要です。ここでは、主要な業界ごとに「好まれる強み」とその理由を整理していきます。
業界別に好まれる強みとは?
業界ごとに働き方や求められる人物像は大きく異なります。そのため、同じ「強み」であっても評価される度合いが変わるのです。
企業・業界別強みマッピング表
- 商社
行動力・挑戦心・コミュニケーション力
理由:商社は海外事業や新規開拓が多く、不確実な状況に果敢に挑戦できる人材を求めるため。 - メーカー
継続力・分析力・改善志向
理由:長期的な製品開発や品質改善に取り組むため、地道に努力できる人材が評価されやすい。 - IT業界
論理性・柔軟性・課題解決力
理由:技術の進化が速く、状況変化に対応しながら効率的に問題を解決する力が求められる。 - コンサルティング
分析力・課題解決力・主体性
理由:クライアントの課題を特定し、仮説を立て解決策を導くため、論理的思考と自発的な行動が必須。 - 人材業界
協調性・責任感・行動力
理由:顧客や求職者との関係構築が不可欠で、人の成長に関わる責任感も重視される。
このように、業界ごとの特徴に合わせて自己PRを調整することで、説得力が増し「この業界で活躍できそうだ」と面接官に思ってもらいやすくなります。
自己PRの内容をより魅力的にするテクニックで通過率をアップ!
自己PRは「内容の正しさ」だけでなく、「伝え方の工夫」によっても大きく印象が変わります。せっかく良いエピソードを持っていても、伝え方が淡白だと魅力が半減してしまいます。ここでは、より効果的にアピールするための具体的なテクニックを紹介します。
通過率が高かった自己PRランキング
多くの就活生や内定者へのアンケート結果から、通過率の高かった自己PRには共通点が見られます。特に評価されやすい傾向を持つ自己PRのテーマをランキング形式で紹介します。
1位:課題解決力を示すエピソード
サークルやアルバイトで問題を解決した事例は、企業から「実務にも直結する」と評価されやすい。
2位:チームで成果を出した経験
協調性を発揮しながらリーダーシップも示したエピソードは、多くの企業で好印象につながる。
3位:挑戦心を持って新しいことに取り組んだ経験
留学や新規企画など、未知の環境に飛び込んだ経験は、成長意欲を感じさせる。
4位:継続力を発揮して成果を残した経験
部活動や資格取得など、コツコツ努力した事例は信頼感につながりやすい。
5位:数値や成果で裏付けられた経験
「売上120%達成」「参加者数1.5倍」といった具体的な成果は、説得力が格段に増す。
このようなテーマは特に通過率が高い傾向にあるため、自分の経験に当てはまるものがあれば積極的に活用するとよいでしょう。
読みやすさ・構成・論理性を高めるコツ
自己PRは内容だけでなく、構成の工夫で印象が大きく変わります。
まず、文字数の目安として履歴書では300〜400字、ESでは600〜800字程度が読みやすいとされています。冗長にならず、しかし内容を十分に伝えられる分量です。
次に、改行や文の長さにも注意が必要です。長文を詰め込みすぎると読みづらくなるため、適度に改行を入れ、1文は50〜60字以内を意識するとスッキリします。
また、書き出しと締めの一貫性を持たせることも重要です。冒頭で「私の強みは○○です」と提示し、最後に「この強みを活かして御社で○○に貢献したい」と結ぶことで、内容が一本筋の通った自己PRになります。
これらのテクニックを意識することで、同じエピソードでも格段に読みやすく、面接官の記憶に残りやすい自己PRを作ることができます。
自己PRを書いたらチェックしよう!
どれだけ時間をかけて自己PRを書いても、見直しを怠ると細かなミスや説得力不足で評価を落としてしまう可能性があります。完成したら必ず客観的にチェックを行いましょう。ここでは、自己PRを見直す際に役立つ具体的な観点を紹介します。
自己PRチェックリスト
以下の観点を順番に確認していくことで、内容の質を大きく高めることができます。
強みの明確さ
冒頭で「私の強みは○○です」と明示できているかを確認しましょう。強みが曖昧だと全体がぼやけてしまい、面接官に印象を残すことができません。
エピソードの具体性
強みを裏付ける経験が、誰が聞いてもイメージできる具体性を持っているかを確認します。「努力した」「頑張った」だけではなく、「どんな課題に対してどんな行動をとり、その結果どうなったのか」を明確にすることが重要です。
内容の一貫性と説得力
文章全体が「強み→エピソード→成果→学び→入社後の活かし方」という一貫した流れになっているかをチェックしましょう。途中で焦点がずれると説得力が弱まってしまいます。
入社後の活かし方まで書けているか?
最後に、入社後に強みをどう活かすかまで触れているかを確認します。未来への接続が示されていない自己PRは「過去の自慢」で終わってしまうため、必ず「御社ではこの強みを○○に活かしたい」と結びましょう。
このチェックリストを活用すれば、自分の書いた自己PRを客観的に評価でき、修正の方向性も見えやすくなります。
自己PRに向いていない内容やNG例にも注意
自己PRは自分の強みをアピールする場ですが、内容によっては逆効果になることもあります。企業に「信頼できない」「再現性が低い」と思われてしまう自己PRは避けなければなりません。ここでは、代表的なNG例と改善のポイントを解説します。
よくある失敗例と改善ポイント
抽象的な表現だけ
「私は努力家です」「私は人と話すのが得意です」といった抽象的な表現は、一見わかりやすそうですが、裏付けがないため説得力に欠けます。
改善するには、必ず具体的なエピソードを添えることが必要です。例えば「アルバイトで新規メニューの販売に取り組み、3か月間で売上を120%に伸ばした」という具体的な成果を加えると、一気に信頼性が高まります。
経験が浅すぎる内容
「1週間だけ参加したボランティアでリーダーを務めました」といった短期間の経験を自己PRの柱にしてしまうと、継続性や再現性に疑問を持たれる可能性があります。
改善のためには、できるだけ長期的な経験や、工夫や努力が積み重なった事例を選ぶと良いでしょう。もし短期間の経験しかない場合は、「短期間でも工夫したこと」「その後どのように活かしたか」を補足することで弱点を補えます。
嘘や誇張がある表現
「全国大会で優勝した」といった事実と異なる内容や、「売上を10倍に伸ばした」といった大げさすぎる誇張は、面接で深掘りされたときにすぐに見抜かれてしまいます。信頼性を損なうと、他の評価ポイントにも悪影響を及ぼす可能性があります。
改善策はシンプルで、「事実を正しく伝える」ことです。成果が小さく見える場合でも、その過程や工夫を強調することで十分にアピールになります。
自己PRの内容に悩んだときの相談先・対策ツール
自己PRは就活の中でも特に悩む人が多い項目です。「強みが見つからない」「エピソードが思い浮かばない」と行き詰まったときは、一人で抱え込まずに相談先やツールを活用することが効果的です。第三者の視点を取り入れることで、自分では気づかなかった強みや表現方法を発見できることがあります。
大学のキャリアセンターやエージェントの活用
大学のキャリアセンターは、履歴書やエントリーシートの添削、模擬面接などを通じて学生をサポートしてくれる心強い存在です。特に自己PRについては、客観的な立場から「企業がどう受け取るか」という視点でフィードバックをもらえるのが大きなメリットです。
また、就活エージェントを利用するのも一つの方法です。エージェントは企業との接点が多いため、どんな自己PRが評価されやすいのか具体的な傾向を把握しています。さらに、学生一人ひとりの強みを引き出し、それを企業ニーズと結びつけて表現するアドバイスをしてくれるため、効率的に自己PRをブラッシュアップできます。
AIツールや診断サービスの活用方法
近年はAIを使った自己分析ツールや文章添削サービスも充実しています。特にChatGPTのようなAIツールは、自分の経験を入力すると「どんな強みに変換できるか」や「文章構成の改善案」を提示してくれるため、一人で悩む時間を大幅に削減できます。
また、SPIや適性診断の結果を自己PRに結びつける方法も有効です。たとえば「SPIで論理的思考力が強みと出たので、その結果を裏付けるエピソードを自己PRに加える」といった工夫をすれば、説得力が増します。診断結果を自己分析の参考にしつつ、自分の経験で補強することで、より具体的で信頼性の高い自己PRに仕上げられます。
さらに、就活生におすすめしたいのが弊社、「らくらく就活」のES作成ツールです。LINEに登録するだけで完全無料で使え、たった5分で好印象な自己PRを作成できます。生成された文章はそのままエントリーシートにコピペできるため、短時間で効率的に準備が可能です。自己PRや志望動機だけでなく、他にも11項目に対応しているので、幅広い選考対策に活用できます。就活準備の負担を大幅に減らしつつ、企業に伝わる内容を整えたい方に最適なサービスです。
受かるESを作りたいけど、自己PRも志望動機も思いつかない、、
そこでAIにES作成を手伝ってもらいませんか?
自己PR、ガクチカ、志望動機など、ESにはたくさんの項目があり、そのどれもが簡単に考えられるものではありません。特に初めてのES作りには時間がかかってしまうものです。できればパッと簡単に短時間でESを完成させたいと思いませんか?
そんな人は、「ES自動作成ツール」を活用しましょう。質問に答えるだけで自動でESの文章を作成してくれるため、自分で1から作るよりも簡単に短時間でESを作ることができます。
らくらく就活をLINE追加するだけで使えるので、すぐにES作成を始めましょう!
まとめ
自己PRは就活において必ず問われるテーマであり、採用担当者が「この学生は入社後に活躍できるかどうか」を判断する重要な材料となります。内容を決める際には、自分の強みをただ伝えるだけでなく、企業が評価する観点や求める人物像と結びつけることが欠かせません。
本記事では、自己PRの基礎知識から始まり、企業が評価する5つのポイント、タイプ別診断チャート、強み別の例文、業界ごとの傾向、さらに通過率を高めるためのテクニックやチェックリストまで幅広く解説しました。また、NG例や改善策、相談先やAIツールの活用方法も紹介したことで、自己PR作成の具体的なステップがイメージできたのではないでしょうか。
自己PRで最も大切なのは「企業目線」を忘れないことです。自分の経験を整理し、そこから導かれる強みを企業が求めるニーズと結びつけることで、初めて評価される自己PRになります。
本記事で紹介したツールや診断表を活用し、自分に合った内容を見つけてください。そして最後にもう一度、文章を見直し、「強みが明確か」「具体性があるか」「入社後の活かし方まで書けているか」を確認しましょう。そうすることで、企業にしっかりと刺さる、あなたならではの自己PRを完成させることができます。