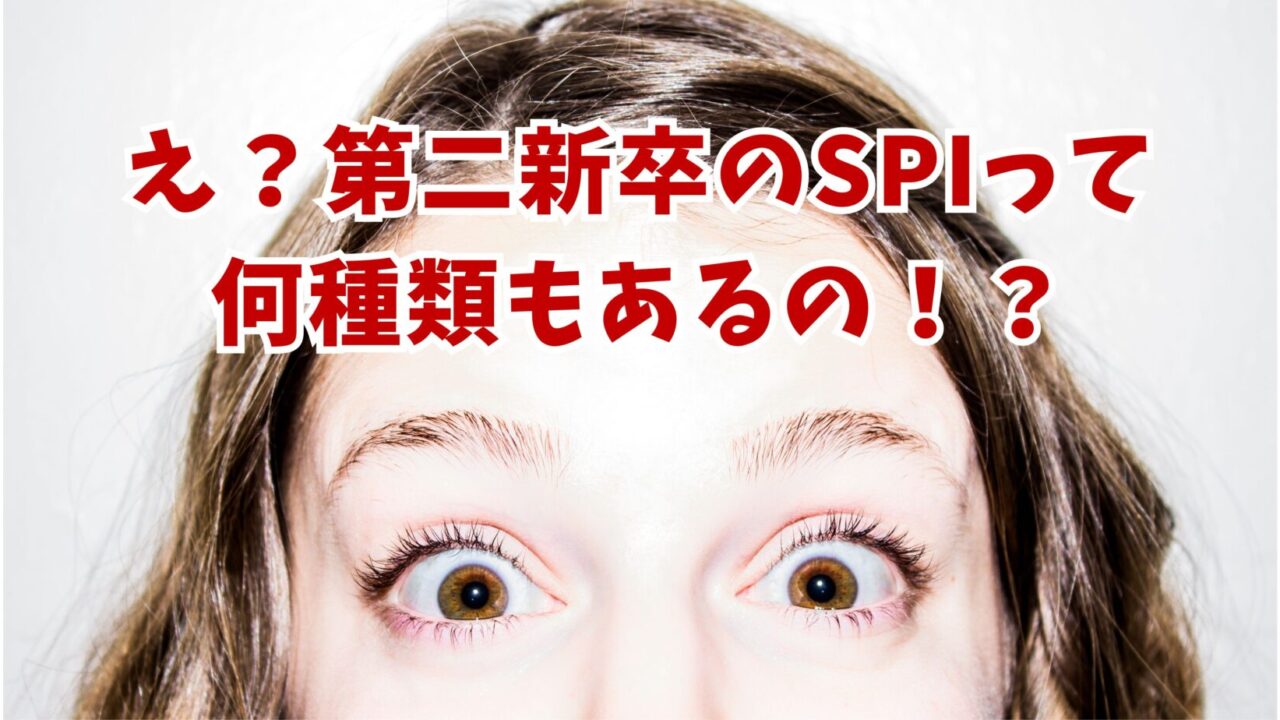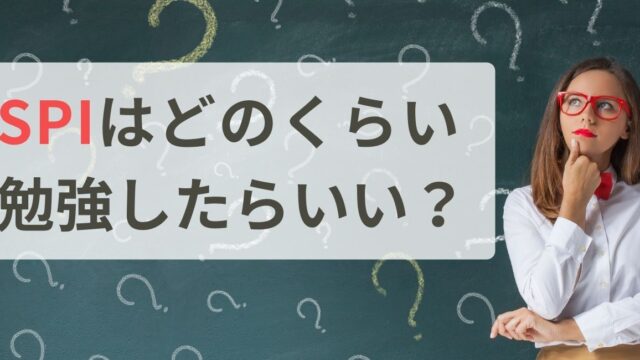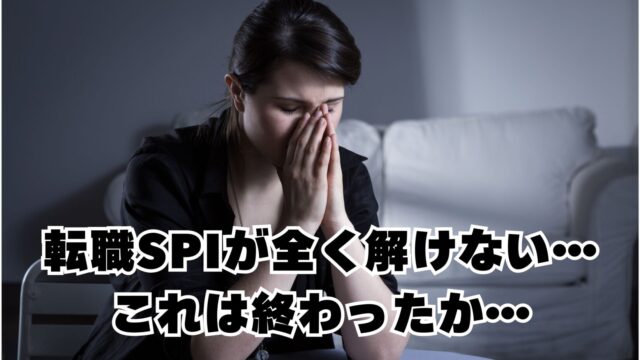【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
第二新卒として転職活動を進める中で、「またSPIを受けるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。就活時代に苦労して乗り越えた記憶が蘇り、「また対策しなきゃいけないのか」と気が重くなる気持ちもよくわかります。しかも、第二新卒採用では新卒採用と比べて、選考スケジュールも短く、準備期間が限られていることも多いため、焦りを感じる人も多いでしょう。
実は、第二新卒向けの採用でも、SPIが選考に取り入れられるケースは決して少なくありません。特に大手企業や人気業種に応募する場合、SPIは書類選考と同様に通過のハードルとなることが多く、準備していないと足切りされてしまう可能性もあります。しかもSPIには複数の種類があり、それぞれ出題される内容や受検方法が異なるため、形式を把握していないと効率的な対策ができません。
そこで本記事では、第二新卒として就職・転職活動をする際に必要な「SPIの種類」や「出題形式の違い」「企業ごとの傾向」などを丁寧に解説していきます。加えて、SPIを突破するための具体的な対策ポイントや、実際にSPIを経験した第二新卒の体験談も紹介していきます。
また、この記事独自のオリジナルコンテンツとして、「SPIの種類と企業タイプの対照表」や「出題形式の予測チャート」「対策レベル診断チャート」なども掲載しています。これらを活用することで、あなたに必要な対策が明確になり、準備がぐっと進めやすくなります。
SPIの壁を超え、自信を持って選考に臨むために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
第二新卒でもSPIは使われるのか?
企業の選考で使われるSPIは新卒だけのものと思われがちですが、実は第二新卒の採用でも広く使われています。では、なぜ第二新卒にもSPIが課されるのか、どのような企業が導入しているのかを詳しく見ていきましょう。
第二新卒はポテンシャル採用が主流
「第二新卒」とは、一般的に新卒で入社した会社を短期間(おおむね3年以内)で辞めて、再び転職活動を行う若手の求職者層を指します。実務経験が浅いため、企業側は「即戦力」よりも「ポテンシャル(将来性)」を重視して選考を行う傾向があります。つまり、前職での実績よりも、地頭の良さや人柄、成長性を見ているケースが多いということです。
そのような背景から、多くの企業では、第二新卒の採用選考においても新卒と同じようにSPI(Synthetic Personality Inventory)を活用しています。SPIは、応募者の基礎的な能力や性格特性を客観的に把握するためのツールであり、特に職種未経験の採用で重視されやすい検査です。
「学力ではなく、社会人としての能力を見てほしい」と思うかもしれませんが、SPIは知識や専門性を問うものではなく、日常的な思考力や問題解決力を見る検査です。そのため、第二新卒であっても新卒時代と同様、SPIでの評価が選考通過のカギを握るケースは少なくありません。
SPIを課す企業の傾向とは?
実際にどのような企業が第二新卒向けの選考でSPIを導入しているのでしょうか。傾向としては以下のような特徴がある企業で使われやすくなっています。
まず一つ目は、大手企業やナショナルクライアント系の企業です。これらの企業では、新卒・第二新卒問わず、多数の応募者が殺到することが多いため、一定の基準でスクリーニングする必要があります。そのため、SPIによって応募者の能力を定量的に測り、足切りや選考の参考資料として活用しているのです。
二つ目は、新卒採用を毎年行っている企業です。これらの企業は選考フローが整っており、SPIのような検査もルーチン化されています。そのため、第二新卒でもほぼ同じ選考フローを適用し、SPI受検を求められるケースが多いです。
三つ目は、営業職や総合職など、幅広い業務に携わることになる職種での採用です。このようなポジションでは、一定以上の基礎能力や柔軟な思考力が求められるため、SPIでその素養を確認したいと考える企業が多い傾向にあります。
また、近年は中小企業でもSPIを導入する例が増えており、特に自社で適性検査を設計する余裕のない企業が、外部サービスとしてSPIを活用するケースが目立ちます。
つまり「有名企業だからSPIがある」「ベンチャーだからない」とは一概に言えず、応募先の企業文化や選考設計によって、SPIの有無は異なるのです。
SPIにはどんな種類がある?
SPIと一口に言っても、実は複数の種類があり、それぞれ受検方法や出題内容、試験の雰囲気が異なります。ここをしっかり押さえておかないと、「過去に受けたことがあるから大丈夫」と油断してしまい、本番で戸惑うことになりかねません。
ここでは、代表的なSPIの出題形式と、SPIがどんな構成で成り立っているのかについて、わかりやすく解説していきます。
代表的なSPIの出題形式
現在、SPIには主に3つの実施形式が存在します。それぞれの特徴を理解することで、どのような準備が必要かが明確になります。
SPIテストセンター:専用会場で受ける形式
もっとも代表的なのが「SPIテストセンター形式」です。これは企業から案内された日時・場所に行き、専用会場のパソコンを使って受検する方式です。特徴的なのは、出題の難易度が受検者の回答状況によって変化する点です。序盤の問題に正解すると、徐々に難易度が上がっていく仕組みとなっており、実力がそのままスコアに反映されやすい形式です。
試験中はカンニングの余地がなく、公平性が保たれるため、大手企業を中心に多く採用されています。ただし、慣れていないと緊張感や会場の雰囲気に圧倒されてしまうこともあるため、模擬試験などで事前に練習しておくと安心です。
Webテスティング:自宅で受検できる形式
続いて「Webテスティング形式」は、自宅のパソコンから受検するタイプのSPIです。企業ごとに出題される問題の組み合わせが異なるのが特徴で、同じWebテストであっても内容にバラつきがあります。受検方法としては、専用のURLにアクセスし、所定の時間内に受検する形となります。
自由な環境で受けられる反面、試験開始後の時間管理や、PC・ネット環境に不備があると不利になりやすいです。また、AI監視やIPログなどにより、不正防止対策が施されているため、他人の手を借りたりAIツールで回答を探すといった行為はリスクが高く、発覚すると即不合格となります。
この形式は、柔軟な運用ができるため、ベンチャー企業やIT系の企業に多く採用されています。
ペーパーテスト(マークシート):集合形式で実施される旧来型の形式
最後に紹介するのが「ペーパーテスト形式」です。これは企業の会議室や学校の教室などで一斉に行われる試験で、紙と鉛筆を使ってマークシート方式で回答します。主に地方企業や中小企業で採用されることが多く、人事が直接問題を配布し、回収・採点を管理することができる点が特徴です。
この形式は、タイマーや進行もすべて人が行うため、他の形式よりもやや緩やかな雰囲気になることがあります。ただし、下書きができるスペースが限られているため、複雑な計算問題では工夫が求められます。さらに見直し時間の確保や、マークミスへの注意が重要です。
形式によって準備すべき内容や心構えも変わってきますので、自分がどの形式を受けることになるのか、事前にしっかりと確認しておきましょう。
SPIの構成:3つの要素
SPIというと計算や言語の問題ばかりに目がいきがちですが、実は3つの異なる分野から構成されています。出題形式にかかわらず、SPIのベースはこの3要素です。それぞれの特徴と注意点を見ていきましょう。
言語分野:語彙力や文脈理解を問う
言語分野では、日本語の理解力や語彙力、文脈を読む力が問われます。主な出題形式としては、二語の関係・空欄補充・文の並べ替え・長文読解などがあり、スピード感を持って読解し、正確に回答する力が求められます。
特別な知識がなくても対応できますが、読解のコツや問題パターンに慣れておかないと時間内に解ききれない可能性があります。文系・理系を問わず、対策の有無が点数に直結するパートです。
非言語分野:計算力・論理思考・図表の読解力
非言語分野は、数的処理と論理的思考力を測る分野です。具体的には、表の読み取り、割合・確率・順列・論理パズルといった問題が出題されます。中学〜高校レベルの数学をベースにしつつも、素早く解くためのテクニックや慣れが必要とされます。
時間配分が難しく、苦手意識を持つ人が多いパートでもありますが、問題のパターンが決まっているため、対策をすればするほど得点アップにつながるのがこの領域です。
性格検査:あなたの価値観や仕事との適性を診断
SPIの最後に登場するのが「性格検査」です。こちらは問題を解くというよりは、自分の性格や行動パターンについての質問に答えていく形式です。「あなたは周囲と協調するタイプですか?」「一人で作業するのが好きですか?」といった質問が繰り返され、自分の回答傾向に矛盾がないか、極端な回答になっていないかがチェックされます。
このパートでは“正直さ”が求められると同時に、“冷静さ”も重要です。あまりにも一貫性のない回答や、明らかに無理をしているような傾向が出ると、職務適性に合わないと判断されることもあるため注意が必要です。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPI種類別×企業タイプ対照表
ここでは、SPIの種類ごとに「どんな企業がどの形式を採用しているのか」を一覧でわかりやすくまとめた対照表を紹介します。これを活用することで、自分が応募しようとしている企業がどの形式を使っているか予測しやすくなり、対策の優先順位を明確にすることができます。
第二新卒の方は、企業のホームページや応募要項を見ても「SPI」としか書かれていないことが多く、「どの形式で受けることになるのかわからない」と戸惑うケースがよくあります。そんなときは、企業の特徴や業種、規模感からSPIの形式をある程度予測するのが効果的です。
以下が、SPIの代表的な形式と、それを採用しやすい企業の特徴を対比した一覧表です。
| SPIの種類 | 実施場所 | 主な企業タイプ | 特徴 |
| テストセンター | 会場 | 大手企業、メーカー系 | 問題の難易度が回答によって変化し、スコアが実力に応じて上下する。最もスタンダードな形式。 |
| Webテスティング | 自宅 | ベンチャー企業、IT系 | 柔軟な運用が可能で、コストも低いため導入が進んでいる。問題構成は企業ごとにカスタマイズされる。 |
| ペーパー形式 | 会場 | 地方企業、中堅企業 | 人事が直接配布・回収する形式。一括選考や合同選考の場で使われることが多い。 |
このように、テストセンター形式は「受験者の実力を正確に測定したい」という企業に好まれています。特に大手メーカーなどは公平性と信頼性を重視するため、この形式を選ぶことが多くなっています。
一方で、Webテスティング形式は、コロナ禍以降とくに導入が進んだ方式です。コストも低く、受検者の負担も少ないため、ベンチャーやスタートアップを中心に広まっています。ただし、出題内容は企業によってばらつきがあり、過去問の蓄積が難しい点には注意が必要です。
また、ペーパー形式はアナログな手法ではありますが、地方の中堅企業や、採用人数が少ない企業では根強く使われています。特に企業説明会と同時に行うケースも多く、その場でSPIを一括実施してしまうパターンも見られます。
つまり、SPIの出題形式は「企業規模」「業種」「採用スタイル」などと密接に関係しており、企業研究の一環として形式の予測も立てておくと、準備が非常にスムーズになります。
この対照表を手元に置きながら、応募予定の企業がどのカテゴリに当てはまるのかをチェックしてみてください。そうすることで、「何となくの対策」から一歩進んだ「戦略的なSPI対策」へとステップアップできるはずです。
SPI出題形式予測チャート
「応募先の企業で、どの形式のSPIが出るのかわからない…」
そんなモヤモヤを抱えたまま対策に取りかかろうとしていませんか?
実は、SPIの出題形式は応募要項だけでは明確に記載されていないことがほとんどです。特に「SPI受検あり」や「適性検査あり」とだけ書かれている場合、どの形式を想定すればよいか迷うのは当然です。
しかし、いくつかのヒントをもとに予測を立てることは可能です。そこでこの記事では、受検形式をある程度推測できる「簡易チャート」をご用意しました。これに沿ってチェックを進めていくことで、自分が受けるSPIの形式の傾向が見えてきます。
SPI出題形式予測チャート
以下の5つの質問に答えてみてください。該当するものが多ければ多いほど、「テストセンター」形式の可能性が高まります。
Q1:応募先は大手企業ですか?
→ YESの場合、テストセンター形式を導入している可能性が高いです。大手企業は公平性と標準化を重視する傾向があるため、テストセンター形式を採用しているケースが多く見られます。
Q2:募集職種は総合職ですか?
→ YESであれば、基礎能力の幅広いチェックが求められるため、SPIのような定量評価が用いられやすく、テストセンターやWebテスティングが選ばれがちです。
Q3:選考フローに「適性検査」の記載がありますか?
→ YESの記載があれば、SPIまたは類似の試験が行われる可能性が高いです。「筆記試験」とだけ書かれていれば、ペーパー形式も視野に入ります。
Q4:自宅受検の案内が来ましたか?
→ YESならWebテスティング形式の可能性が高くなります。メールやマイページで自宅受検のURL案内があれば、ほぼ確実にWebテストです。
Q5:「テストセンター」の文字が案内メールや求人票にありましたか?
→ YESなら、そのままテストセンター形式で間違いありません。専用会場での受検が必要になりますので、早めに予約を取るようにしましょう。
判定の目安
YESが4つ以上 → テストセンター形式の可能性が高い
→ テストセンター用の対策に力を入れるのがベスト。模試や演習アプリの活用を強く推奨します。
YESが2〜3個 → Webテスティング形式の可能性が高い
→ 自宅環境での受検を想定し、時間管理や問題の傾向をつかむ練習を重ねましょう。
YESが1個以下 → ペーパー形式や他の適性検査の可能性も
→ ペーパー形式に備えて、過去問演習を行いながら柔軟に対応できるようにしておくと安心です。
このように、SPIの形式は完全には明示されないことが多いため、事前に複数の情報から推測することが重要です。また、複数企業を受ける場合、異なる形式が混在することもあります。形式の違いによって求められるスキルや対策方法が変わるので、見誤らないように注意しましょう。
このチャートを活用して、自分が向き合うべきSPI形式を見極め、効率的な準備につなげてください。
SPI形式ごとの対策ポイント
SPIの出題形式ごとに、押さえるべき対策ポイントは大きく異なります。たとえば、同じ問題集を使ったとしても、テストセンターとWebテスティングでは注意すべきポイントがまるで違います。ここではそれぞれの形式に応じた具体的な対策法を紹介します。
テストセンター形式の注意点
テストセンター形式では、冒頭でも触れたとおり「問題の難易度が回答によって変化する」という特殊な仕組みがあります。これにより、序盤の問題にどれだけ正解できるかが、全体の評価に大きな影響を与えます。
このため、対策の最重要ポイントは「序盤の問題を落とさないこと」です。具体的には、最初の5問前後に集中し、丁寧に、かつ正確に解くことが求められます。逆に、序盤でミスが続くとその後に出題される問題のレベルが下がり、結果的に評価も伸びにくくなるという落とし穴が存在します。
また、時間配分の工夫も不可欠です。難易度が変化することで焦りや緊張を感じやすくなるため、模試やアプリなどで本番に近い形式で練習し、「どんな問題でも動揺しない力」を養うことが大切です。
Webテスティング形式の注意点
自宅受検型のWebテスティング形式は、一見すると「ラクそう」と思われがちですが、実際には落とし穴が多い形式でもあります。
まず注意すべきは、受検環境の整備です。ネット回線が不安定だと途中で接続が切れたり、試験が終了してしまうケースもあります。また、ブラウザの設定やセキュリティソフトが干渉してエラーが出ることもあるため、事前に受検案内メールの指示をよく読み、必要な設定やテストを済ませておきましょう。
また、「他人の協力」や「AIツールの使用」など、不正行為に手を出してしまう人もゼロではありません。しかし現在のSPIは不正検知システムもかなり高度になっており、IPアドレス・マウスの動き・回答のタイミングなどから異常検出されることもあります。不正が発覚した場合、選考の即終了はもちろん、以後その企業に応募できなくなるリスクもあるため、正攻法での対策が鉄則です。
本番環境に近い条件で練習することが、Web形式でも安定した実力発揮につながります。
ペーパー形式の注意点
ペーパー形式は、鉛筆と紙を使った昔ながらのSPI方式です。デジタルな形式とは違い、紙の限られたスペースに計算やメモを書き込みながら進めるため、「下書きの工夫」と「見直し時間の確保」がポイントになります。
特に計算が絡む非言語問題では、メモ欄が狭くて混乱しがちです。解答用紙を汚さず、かつ効率的にメモをとる練習をしておくと、本番でも慌てずに済みます。
また、ペーパー形式は時間管理もアナログです。タイマーが鳴るわけではなく、人事が「あと◯分です」と声かけするだけのことも多いため、自分の時計でこまめに時間をチェックし、余裕を持って見直しができるように計画的に進めることが重要です。
SPI対策レベル診断チャート
「どれくらい対策すればいいの?」と迷っている方のために、対策の必要度を測れる診断チャートをご用意しました。以下の5項目に当てはまる数をチェックしてみてください。
□ 最後にSPI問題を解いたのは半年前以上
□ 言語問題で語彙の意味がすぐに出てこない
□ 非言語の表問題に苦手意識がある
□ テストセンター形式の仕組みを知らない
□ 模試や演習を1回もやっていない
上記のうち、3つ以上当てはまった方は今すぐ対策を始めるべきです。SPIは一夜漬けでどうにかなる試験ではなく、ある程度の慣れと練習量が必要です。
逆に、当てはまる項目が1つ以下の方は、既に基礎力が備わっている可能性が高く、復習や形式の最終確認を中心に進めれば問題ないでしょう。
なお、2〜3個該当した方は「対策の見直し期」に当たります。演習量を増やす、模試を受けてみるなど、現状を底上げする対策を心がけましょう。
このチャートを使って、自分の現在地を把握したうえで、無理のない学習計画を立てるのがおすすめです。
第二新卒向けSPI対策の進め方
SPIの準備には時間がかかるイメージがありますが、実はポイントを押さえれば、短期間でも実力アップが可能です。ここでは、第二新卒の方にとって効果的なSPI対策の進め方をご紹介します。
1冊の問題集を繰り返すのが効果的
SPI対策を始めると、つい何冊も問題集を買い込んでしまう方がいます。しかし、それは非効率です。SPIは「形式になれること」が最も重要なので、同じ問題集を繰り返し解いて、問題パターンと答えの流れを体に染み込ませるほうが圧倒的に効果的です。
おすすめは、難易度別に分かれている1冊を選び、1周目は全体把握、2周目は苦手補強、3周目は時間を測って本番想定で、というように使い分ける方法です。
アプリや模試も併用しよう
通勤中や休憩時間などのスキマ時間を活用できるのが、SPI対策アプリの大きなメリットです。スマホがあればいつでもどこでも取り組めるので、10〜15分単位での学習を習慣にしやすくなります。
「らくらく就活」が提供するSPI対策アプリでは、出題傾向をもとに頻出問題を厳選しており、非言語・言語・性格検査までバランスよく対策できるように設計されています。苦手な分野だけを重点的に学習したり、ランダム出題で本番形式に慣れたりと、使い方の幅が広いのが特徴です。
また、週末には紙の問題集や模試形式の問題に取り組んでみましょう。本番に近い環境でチャレンジすることで、自分の得意・苦手の再確認や、時間配分の練習にもつながります。
アプリで日々のスキマ時間を活かし、紙の教材や模試で実戦力を磨く。この組み合わせが、効率よくSPIスキルを積み上げていくベストな方法です。特に時間のない第二新卒の方にこそ、こうした“ながら対策”の活用がおすすめです。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
性格検査も“正直に”かつ“冷静に”
性格検査を「適当に答えればいいや」と考える方が一定数いますが、それは非常に危険です。極端な回答(すべて「はい」「いいえ」など)や、矛盾する選択が続くと、性格的な一貫性が疑われ、通過率が下がる可能性もあります。
また、職種や企業文化との適合度もスコアに影響するため、「正直かつ冷静」に答えることが求められます。自己分析がある程度進んでいる人ほど、整合性のある回答ができる傾向にあるので、SPIと並行して「自分の強み・価値観の整理」も進めておきましょう。
第二新卒のSPI体験談
SPI対策のリアルなイメージをつかむには、実際に受けた人の体験談が一番参考になります。ここでは、実際に第二新卒としてSPIを受検した方の声を2つご紹介します。
大手メーカーに転職成功したMさん(25歳)
「新卒のとき以来で不安でしたが、SPI対策アプリで1週間練習しただけで通過できました。やっぱり慣れが大事だと実感しました。最初は忘れていた問題パターンも、アプリで反復したことで徐々に感覚が戻ってきました。正直、勉強が苦手な自分でも『形式を知っているだけでこんなに変わるのか』と驚いたほどです。」
Webテストで落ちたSさん(24歳)
「正直、SPIってもうやらないと思ってて、全く準備しませんでした…。油断してたら、思っていたより難しくて途中で時間切れに。悔しいですが、きちんと対策してから再チャレンジ中です!今はテストセンター形式の問題集を買って、少しずつ勘を取り戻しています。」
まとめ
第二新卒の転職活動においても、SPIはしっかりと出題される試験です。むしろ、経験が浅い分、SPIによって評価される割合が高くなるとも言えます。
また、SPIには「テストセンター」「Webテスティング」「ペーパー形式」といった複数の出題形式が存在し、それぞれ対策の方向性が大きく異なります。自分がどの形式で受けることになるのかを見極め、効率的に準備を進めることが重要です。
本記事では、出題形式別の特徴や、企業との対応表、診断チャートや対策の進め方まで、SPI対策に必要な情報を網羅しました。体験談も含めて、現場で役立つリアルな視点も盛り込んでいます。
第二新卒の就職・転職活動は、スピードが命です。だからこそ、SPI対策も「早めに」「効率的に」進めていくことが成功への第一歩。この記事が、皆さんの一歩を後押しするきっかけになれば幸いです。がんばってください!