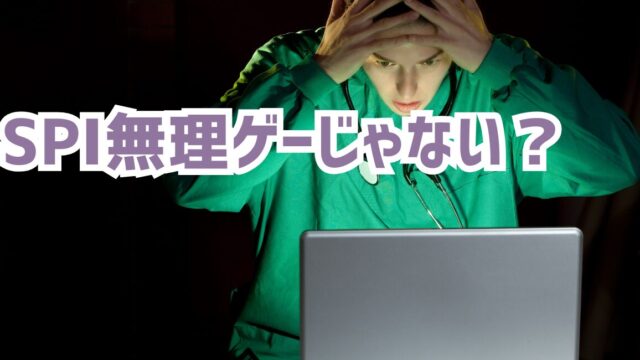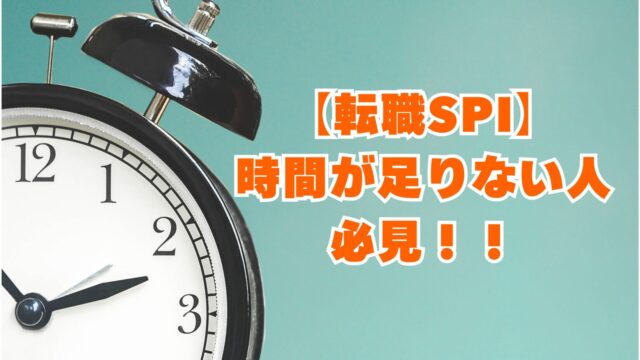【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「転職活動を始めたけど、第二新卒ってSPI出るの?」「種類が多くてどれを対策すればいいのか分からない…」
そんな不安を感じていませんか?
第二新卒として転職活動を始めると、新卒のときとは異なる点に戸惑うことも多いでしょう。特に多くの方が悩むのが「SPI(エスピーアイ)って必要なの?」「対策しておくべきなの?」といった適性検査に関する疑問です。
新卒採用ではよく耳にしたSPIですが、実は第二新卒の転職においてもSPIが課されることは珍しくありません。企業側は、社会人経験が浅い第二新卒に対しては、これまでの実績よりも「地頭の良さ」や「性格的な適性」などを見て判断しようとします。そのため、新卒と同じようにSPIを活用する企業が多いのです。
また、SPIと一口に言っても、実施形式や出題内容はさまざま。テストセンター、Webテスティング、ペーパーテストなど複数の形式があり、事前にどの形式になるかを知っておかないと、無駄な対策に時間を取られてしまうこともあります。
そこで本記事では、第二新卒の方に向けてSPIに関する不安や疑問を解消するための情報を徹底的に解説します。SPIが課される理由や出題形式の違い、企業別の傾向、さらには第二新卒の実体験や対策チャート、企業タイプ別の傾向表まで、役立つ情報を盛り込みました。
これから転職活動を本格的に始める方も、すでに選考をいくつか受け始めている方も、この記事を読むことで「何から対策すればいいのか」がはっきりと分かるようになります。
それではさっそく、第二新卒におけるSPIの必要性について見ていきましょう。
目次
第二新卒でもSPIは出る?
第二新卒として転職活動を始めた人の多くが、「SPIってまだ出るの?」「中途採用なら関係ないのでは?」と疑問に思うかもしれません。しかし実際には、第二新卒でもSPIが課されるケースは少なくありません。その背景には、第二新卒特有の採用スタイルが関係しています。
第二新卒は“ポテンシャル採用”が多いためSPIが課されやすい
第二新卒とは、新卒で一度就職したものの、1〜3年以内に退職し再び転職活動を始めた若手人材を指します。社会人経験があるとはいえ、業務経験はまだ浅く、「即戦力」というよりは「ポテンシャル(将来性)」を評価される傾向があります。
企業は第二新卒に対して、前職でどんな成果を出したか以上に、「この人は今後伸びそうか?」「基本的なスキルや素質は備わっているか?」といった観点から選考を行います。
その判断材料として、SPIのような適性検査は非常に有効なのです。
SPIでは、言語・非言語といった基礎学力に加えて、性格特性も測定できます。たとえば、論理的な思考ができるか、数字を扱うことが得意か、あるいはチームでの協調性や責任感があるかなどが分かります。
こうした情報は、第二新卒のように実績が少ない応募者に対して、企業が選考の第一ステップとして使いやすいのです。そのため、大手企業はもちろん、中堅企業でもSPIを導入しているケースは多く、事前準備が欠かせません。
特に事務職や総合職、営業職など幅広い職種でSPIが活用されており、志望業界や職種にかかわらず、第二新卒だからこそSPIが避けられない場面が多いのが現実です。
一般の中途よりも選考フローが新卒寄りになる理由
第二新卒と一般的な中途採用者との大きな違いは、選考フローの設計にあります。一般の中途採用では、即戦力としての職務経験やスキルセットを重視されるため、職務経歴書や面接内容が中心となり、適性検査を省略する企業も多く見られます。
一方、第二新卒の場合、職務経験が限定的で、書類や面接だけでは応募者の資質を判断しにくいという課題があります。そのため、企業側はより客観的なデータを得るために、SPIなどの適性検査を導入するのです。
実際、第二新卒向けの求人情報を見てみると、「新卒と同様の選考フローで行います」と明記されているものも多くあります。つまり、SPI→面接→最終面接といった流れで、まるで新卒採用のようなプロセスが組まれるのです。
また、企業側としても、第二新卒は「育成前提」で採用するケースが多いため、新卒同様の教育体制や配属計画に組み込むことが前提となります。だからこそ、選考の段階でも「新卒のときと同じような検査を実施する」というスタンスを取る企業が少なくないのです。
こうした背景から、第二新卒の転職では、新卒採用と似たような試験や選考が行われる可能性が高く、SPIが出るかどうかを曖昧に考えていると、選考突破に苦戦するリスクもあると言えるでしょう。
SPIとは何か?転職時に課される理由
「SPI」という言葉は知っていても、その内容や目的を詳しく理解している人は意外と少ないかもしれません。転職活動でSPIが課される理由を知るためには、まずその仕組みや企業が何を見ているのかを知ることが重要です。
SPIの基本構成と目的
SPIとは「Synthetic Personality Inventory(総合適性検査)」の略称で、リクルート社が提供する適性検査のことです。就活生の間では広く知られていますが、実は転職市場でも非常に多く使われている試験です。
SPIの目的は、応募者の基礎的な能力や性格的な傾向を客観的に測定することにあります。企業が応募者を「学歴」や「職務経歴」だけで判断するのではなく、「この人はどんなタイプの人物なのか」「どれだけ論理的・数的思考力があるのか」といった、定量的に把握しにくい部分を見極めるためのツールとして活用されています。
SPIは大きく分けて以下の3つの領域から構成されています。
- 言語分野:語彙力、読解力、論理的な文章理解の力などを測定。
- 非言語分野:計算力や論理的思考力、図表の読み取り能力などを測定。
- 性格検査:性格的な傾向や行動パターン、価値観、組織適応性などを診断。
これらを通して企業は「能力的な面(地頭の良さ)」と「性格的な面(職場とのマッチ度)」を把握することができます。
SPIの利点は、短時間で多くの応募者を客観的にスクリーニングできる点にあります。特に書類選考だけでは見えてこない個人の資質や能力を数値化できるため、企業にとっても「見落としを防ぎ、ミスマッチを避ける」ための重要な選考要素になっています。
企業がSPIで見ているポイントとは?
企業がSPIを通じて何を見ているのかというと、主に次のようなポイントが挙げられます。
まず、言語・非言語分野においては、論理的思考力、文章の読解力、基礎的な計算力が評価されます。これらはどの職種であってもビジネスの土台となるスキルであり、「社会人としての基本的な力を持っているか?」を測る目安になります。たとえば、営業職なら数字を扱う場面も多いため、非言語分野の得点が重視されることもあります。
一方で、性格検査は「組織との相性」を測るために用いられます。協調性があるか、責任感を持って物事に取り組めるか、ストレス耐性があるか──といった要素が検査結果に反映されます。企業はこのデータをもとに、自社の社風やチームとのマッチングを判断しているのです。
また、SPIはあくまで“選考の補助材料”であり、合否を直接左右する絶対的なものではありません。しかし、応募者が多い場合や、選考の初期段階においては、SPIの結果で一定ラインを超えないと面接に進めない「足切り」として使われることもあります。
つまり、SPIで見られているのは単なるテストの点数だけでなく、「この人を選考に進める価値があるかどうか」を判断するための総合的な評価。とくに第二新卒のようにキャリアの浅い層にとっては、SPIで良い結果を出すことが大きなアドバンテージになると言えるでしょう。
SPIが転職選考でも重要視される理由は、「経験が浅い人材ほど、将来の伸びしろや人柄を数値で見極める必要がある」から。だからこそ、第二新卒にとってSPIは避けて通れない壁のひとつなのです。
SPIの種類と出題形式の違い
SPIにはいくつかの実施形式があり、それぞれ受け方や対策方法が異なります。形式ごとの特徴を知っておくことで、効率的な準備ができ、当日の戸惑いも減らすことができます。
テストセンター/Webテスティング/ペーパーテストの違い
SPIと一口に言っても、その実施形式にはいくつかの種類があり、それぞれ受験方法や環境が異なります。これらを理解しておかないと、想定していなかった形式に戸惑ったり、対策がずれてしまったりする恐れがあります。ここでは主に使われる3つの形式について詳しく解説します。
まず1つ目がテストセンター方式です。これは全国に設置された専用会場(リクルートのテストセンター)で受験する形式です。事前に企業から受験案内が送られてきて、自分で日時と場所を予約する流れになります。設備の整った会場で実施されるため、操作性が安定しており、画面に表示された問題をマウスやキーボードで解答します。
この方式の特徴は、「テストセンターで一度受験すれば、他の企業にも同じ結果を使い回せる」点です。特に複数の企業に応募する場合、同じスコアが共有されるため、最初に高得点を取っておけば後が有利になります。ただし再受験には一定期間が必要で、1回限りのチャンスになることもあります。
2つ目がWebテスティング方式です。これは自宅などのパソコンからオンラインで受験する形式で、現在最も多くの企業で導入されています。応募者側の負担が少なく、企業としてもコストを抑えられるため、特にIT系やベンチャー企業で主流になっています。
この方式では自宅のネット環境やPCスペックが影響することもありますが、試験そのものはテストセンターと類似しています。注意点としては、カンニングなど不正行為を防ぐために受験中の画面録画やWebカメラでの監視を求められることがある点です。
最後に紹介するのがペーパーテスト方式です。これは企業が面接会場などで紙の試験用紙を配布し、手書きで回答させるアナログな方式です。最近では減少傾向にありますが、地方の中小企業や一部の業界では今も使われている場合があります。
この方式では、試験会場に集合する必要があり、集団で受けることが一般的です。また、問題内容が独自形式であることもあり、SPIと似ているけれど微妙に異なる問題が出題されるケースも見られます。
どの形式になるかは企業によって異なる
SPIの受験形式は、企業ごとの選考フローや方針によって大きく異なります。大手メーカーなど多くの応募者を一括で処理する必要がある企業では、テストセンターを採用する傾向があります。逆にスタートアップや中小企業では、Webテスティングやペーパーテストの比率が高いです。
応募前に企業の求人ページや説明会、選考案内メールで形式が明記されていることもあるので、必ずチェックしておきましょう。また、就活支援サイトの選考体験記などから、志望企業の過去の実施形式をリサーチすることも効果的です。
形式ごとに出題内容は基本的に共通ですが、解答方法や時間配分に慣れる必要があります。たとえば、Webテスティングではタイピングスピードが求められる一方、ペーパーテストでは書くスピードや計算の正確性が問われます。どの形式に当たっても対応できるよう、少なくとも一度はそれぞれの形式に近い模擬試験を経験しておくのがおすすめです。
なお、第二新卒の転職では、同じSPIでも新卒のときと出題傾向や難易度が微妙に変わっていることがあります。油断せず、最新の問題形式に合わせた対策を行うことが合格への近道になります。
SPI種類別×企業タイプの対照表
SPIの出題形式は企業によってさまざまですが、実は業界や企業規模ごとにある程度の傾向があります。ここでは、企業タイプごとに採用されやすいSPI形式をまとめてご紹介します。
どの企業がどのSPI形式を採用しがち?
「志望企業がどのSPI形式を採用しているか」は、事前の準備において非常に重要な情報です。対策すべき問題形式がまったく異なるため、効率よく準備を進めるには、その企業の採用傾向を押さえておく必要があります。
ここでは、業界ごとに多く見られるSPI形式を一覧にまとめました。もちろん例外もありますが、志望企業の業界がわかっている場合には、ある程度の予測が可能です。
◆ SPI形式別 × 企業タイプ早見表
| 業界・企業タイプ | 主に使われるSPI形式 | 特徴や傾向 |
| 大手メーカー・総合商社 | テストセンター | 受験者数が多く、全国対応できるためテストセンターを採用。安定志向の選考スタイル。 |
| メガバンク・大手金融 | テストセンター/ペーパーテスト | 記述式や計算量の多い問題が出る傾向。SPIの比重が高いことも。 |
| IT・Web系スタートアップ | Webテスティング | コスト削減と柔軟な対応を目的に、オンライン形式を採用する企業が多い。 |
| 地方中小企業 | ペーパーテストまたは適性検査のみ | SPIよりも独自問題や簡易適性検査を導入する傾向。対策不要なケースもあり。 |
| インフラ・電力・通信系 | テストセンター | 採用数が多く、標準化された試験で足切りを行うケースが多い。 |
| コンサル・人材・広告系 | Webテスティング | 選考のスピード重視。非言語よりも性格検査重視の企業も。 |
この表を見ればわかるように、「どの業界を志望するか」によって、対策すべきSPIの形式が変わってきます。
たとえば、メーカーや金融系を志望しているなら、テストセンターの問題形式に慣れておく必要があります。逆に、IT系やベンチャー企業ではWeb形式での実施が多いため、家での模擬テストを何度もこなしておくことが効果的です。
また、地方の中小企業を目指す場合は、SPIそのものが課されないケースもあるため、対策時間を面接練習や自己分析に回すほうが有効なこともあります。
なお、特定のSPI形式を指定していない企業でも、選考通知後に形式が明かされることが多いです。そのため、あらかじめ主要な2~3形式には慣れておくと、直前になって焦るリスクが減らせます。
この表はあくまで「傾向」ですが、業界研究と並行してこのような情報を把握しておくことが、賢い対策の第一歩です。
実際にSPIを受けた第二新卒の体験談
ここでは、実際に第二新卒としてSPIを受けた方の体験談を紹介します。成功例だけでなく、失敗を経て乗り越えたリアルな声から、対策のヒントや注意点を学んでみましょう。
Aさん(24歳・メーカー営業)「無対策で落ちたけど…」
私は新卒で食品メーカーに就職し、約1年半で退職しました。仕事内容そのものは嫌いではなかったのですが、配属先の人間関係や残業時間の多さが精神的にきつくなり、思い切って転職を決意。第二新卒としての転職活動は「なんとかなるだろう」と、正直かなり甘く見ていたと思います。
最初に応募したのは、また別の大手メーカーでした。書類はすんなり通過し、一次選考として案内されたのがSPIのテストセンター受験。大学時代にも受けたことがあったので、「まあ何とかなるだろう」とそのまま試験に臨みました。
しかし結果は不合格。通知では明確な点数はわかりませんが、「SPIの基準を満たしていないため」という理由が記載されていました。思い返すと、非言語分野の問題が特に苦手で、途中でかなり焦ってしまったのを覚えています。
これを機に「やっぱり対策しないとまずい」と実感し、問題集やアプリで毎日少しずつ勉強を始めました。1日30分から1時間程度でも、継続することで問題形式に慣れていき、2社目のSPIではかなり余裕を持って解答できました。その結果、無事に通過して最終面接まで進むことができました。
当時の自分にアドバイスできるなら、「新卒時の記憶に頼らず、必ず最新の問題で1回は模試を解いておけ」と伝えたいです。SPIは“落とすための試験”というより、“足切り”に使われることが多いので、特に大手企業を志望するなら準備しておくのは必須だと思います。
Bさん(25歳・IT企業内定)「アプリと模試でスピード攻略」
私は新卒で入社した不動産会社を約2年で退職しました。営業ノルマが厳しく、キャリアの将来像が描けなかったため、第二新卒枠での転職を決意。次はもっと柔軟な働き方ができる会社に行きたいと思い、IT業界を中心に応募していました。
いくつか応募してみて分かったのは、思っていた以上にSPIが課される企業が多いということ。特にIT業界でもしっかりSPIを導入している企業が多くて驚きました。しかも、形式がWebテスティングで、自宅のパソコンで受ける必要があることもあり、「このままだと落ちるな」と不安を感じて、対策を始めることに。
最初に手を出したのはSPI対策アプリです。スマホで手軽にできるので、通勤時間や寝る前の10分など、スキマ時間を活用していました。とくに非言語分野が苦手だったので、出題傾向のある問題を繰り返し解いて、時間配分の感覚を身につけました。
その後、模試も1回だけ受験。本番と同じ時間配分で解くことで、実戦感覚をつかめたのが大きかったです。最終的には3社のSPIを受け、すべて通過。最終的にはWebマーケティング系の会社から内定をもらい、無事に転職できました。
ポイントは「完璧を目指さず、短期集中で反復練習をすること」。特にアプリや模試を活用すれば、効率よく苦手分野を補えるので、時間のない第二新卒にはおすすめです。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPIで問われる具体的な問題内容
SPIでは、大きく分けて「言語」「非言語」「性格検査」の3つの分野が出題されます。それぞれの内容や特徴を理解することで、効果的な対策ができるようになります。ここからは分野ごとに具体的な出題例と対策のポイントを見ていきましょう。
言語分野の出題例と対策
SPIの言語分野では、主に「語彙力」「文法力」「文章理解力」が問われます。出題形式としては、「二語の関係」「熟語の成り立ち」「空欄補充」「文の並び替え」「長文読解」などがあり、大学受験の国語と似た感覚で捉えると分かりやすいかもしれません。
たとえば「二語の関係」では、「医者:患者」「教師:生徒」といった関係性をもとに、意味の近いペアを選ぶ問題が出題されます。「熟語の成り立ち」では、「前後で意味が成り立つもの」「修飾関係にあるもの」などを判断する必要があります。
実際に問題を見てみると、簡単そうに見えて意外と引っかけが多く、普段から活字に触れていないと苦戦する内容です。特に長文読解では、限られた時間内で情報を正確に読み取り、設問に答えるスピードが求められるため、読み慣れていない人は時間が足りなくなることもあります。
対策としては、まず問題形式に慣れることが第一。出題傾向が決まっているため、市販のSPI対策本やアプリで練習するのが有効です。時間制限のある中で解くトレーニングを繰り返すことで、自然と文章を読むスピードや設問の意図を見抜く力がついてきます。
また、苦手意識がある方は「語彙力強化」から始めるのもおすすめです。普段からニュース記事やビジネス系の文章に触れるだけでも、語彙力や文章理解力は向上します。
非言語分野の出題例と対策
非言語分野では、数字や論理を扱う問題が中心です。「四則演算」「割合・比」「損益算」「速度算」「表やグラフの読み取り」「順列・組合せ」「集合」など、いわゆる中学~高校レベルの数学の知識を使って解く問題が多く出題されます。
たとえば、「ある商品の原価が○円、利益率が○%のとき、販売価格はいくらか?」といった問題や、「ある人数のグループを条件に従って分けるには何通りあるか?」など、実生活に近い設定のものが多く、数字に対する直感的な理解力が試されます。
中でも時間との戦いになるのがこの非言語分野です。1問あたりにかけられる時間は短く、しかも問題によっては式の立て方に時間を要するものもあるため、スピードと正確性のバランスが重要になります。
対策のコツとしては、最初に「自分が解ける問題」と「時間がかかる問題」を見極めること。すべての問題を解こうとせず、取れる問題を確実に得点するスタンスが大切です。
また、対策アプリや市販の問題集を使って、ひたすら演習することがスピードアップにつながります。特に「表の読み取り」や「集合問題」などはパターンが決まっているので、数をこなせば自然と対応力が身につきます。
性格検査の評価ポイント
SPIの性格検査は、数十問にもおよぶ自己申告型のアンケートで構成されており、短時間で「どちらかというとAに近い」「まったくそう思わない」などの選択肢に回答していく形式です。
この性格検査は、「正解がない試験」とされている一方で、企業がかなり重視している項目です。というのも、性格検査の結果は、その人の「職場での行動パターン」や「組織への適応力」などを予測する材料になるからです。
企業がチェックしているポイントとしては、以下のような傾向があります:
- 一貫性があるかどうか:前半と後半で矛盾した回答をしていないか
- 協調性や責任感があるか:集団の中で浮かないか、仕事を粘り強く続けられるか
- ストレス耐性や自律性:困難に直面したときに冷静に対処できるか
性格検査は嘘をついてもバレないように思うかもしれませんが、同じような内容の質問が繰り返し出されるため、矛盾した回答をすると「一貫性がない」と判断されます。
つまり、「企業に好かれるように盛る」よりも、「正直に、かつ安定感のある回答」を心がけることが重要です。極端な性格に偏らないようにしつつ、バランスの取れた人物像を意識して回答することが、評価されやすいポイントになります。
SPI対策レベル診断チャート
「SPI対策をどこまでやるべきか分からない…」と迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、あなたの現在の状況に応じて、どのくらいの対策が必要かを簡単に診断できるチャートをご用意しました。
自分に必要な対策量を診断!
「SPI対策、どれくらい必要なのか分からない…」
そんな方のために、以下の診断チャートで現在のあなたの状況をチェックしてみましょう。YESかNOで進んでいくだけで、今すぐ対策が必要かどうか、どのくらいの対策をすべきかが分かります。
◆ SPI対策レベル診断チャート
- SPIの模試や対策問題を最近解いたことがある?
→ YES:2へ | NO:3へ - 模試で6割以上の正答率があった?
→ YES:4へ | NO:3へ - 学生時代に数学や国語が得意だった?
→ YES:5へ | NO:6へ - 本番形式のテストセンターやWebテスティングに慣れている?
→ YES:→【対策レベル:軽め】苦手分野の見直し程度でOK
→ NO :→【対策レベル:中】形式慣れのための模試実施推奨 - 1日30分程度の勉強時間を確保できる?
→ YES:→【対策レベル:中】基本問題を繰り返してOK
→ NO :→【対策レベル:重】短期集中型の対策が必要 - SPIを課される企業に複数応募予定?
→ YES:→【対策レベル:重】出題傾向別に演習を
→ NO :→【対策レベル:軽〜中】志望企業次第で対応可能
診断の結果、「軽め」と出た方も、油断は禁物です。第二新卒の転職活動は新卒より短期決戦になりやすいため、少ないチャンスで確実に通過する必要があります。短時間でもいいので、模試やアプリを活用して対策を習慣化しておきましょう。
逆に「重め」の対策が必要と出た方は、今すぐにでも取り組みを始めることをおすすめします。SPIは一朝一夕で得点できる試験ではないため、少しずつ慣れていくことが合格への鍵です。
第二新卒向けSPI対策の進め方
第二新卒の転職活動はスピード勝負になることが多いため、SPI対策も効率よく進めることが大切です。限られた時間の中で成果を出すための進め方を、順を追って紹介していきます。
短期集中で対策するならこの順番で
第二新卒の転職活動では、働きながらの対策になることが多く、十分な勉強時間を確保するのが難しいのが現実です。そこで、短期間でも効率的に成果を出すための対策ステップを紹介します。
まず、最優先で行うべきは問題形式の理解です。SPIは出題されるジャンルが決まっているため、最初に各分野の代表的な問題を一通り解いて、どのジャンルが苦手かを把握しましょう。
次に、苦手分野を中心に繰り返し演習します。特に非言語分野は慣れることで格段にスピードが上がるため、1日1~2問でも毎日続けることが重要です。
その後、時間を測って模擬試験形式で解く練習に移行します。問題集やアプリにある模試モードを使い、時間配分を体に覚えさせましょう。
この3ステップを2~3週間繰り返すだけでも、十分に本番対応できる力がついてきます。
おすすめ教材・アプリ・模試の選び方
SPI対策には、市販の問題集とアプリの両方を活用するのが効果的です。
書籍でおすすめなのは『これが本当のSPI3だ!』シリーズです。出題範囲が広く、解説も丁寧なので初心者にも適しています。また、非言語分野の基礎から応用までカバーできる一冊も持っておくと安心です。
アプリについては、弊社の「らくらく就活」SPI対策アプリがおすすめです。スマホでスキマ時間に取り組めるうえ、出題分野ごとにレベル別の問題が用意されており、第二新卒の学び直しにも最適です。
解説もわかりやすいので、まずは無料で使える「らくらく就活」アプリから始めると手軽に学習習慣をつけやすいでしょう。
また、Web模試を提供しているサービスもあるため、PC環境が整っていれば模試形式での練習も取り入れるのがおすすめです。本番環境に近い形で受けておくと、当日の緊張感にも対応しやすくなります。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPIが不安な人でも大丈夫な企業の特徴
「SPIが苦手で自信が持てない…」という方も心配はいりません。すべての企業がSPIを導入しているわけではなく、試験を重視しない選考スタイルの企業も多く存在します。ここでは、SPIに不安があってもチャレンジしやすい企業の特徴を紹介します。
SPIなし・適性検査だけの企業もある
「どうしてもSPIに自信が持てない…」という方もご安心ください。すべての企業がSPIを必須としているわけではありません。とくに中小企業やベンチャー系の企業では、SPIを省略して、面接や書類のみで選考を進める企業も多く存在します。
また、SPIの代わりに「性格診断のみ」「簡易的な適性検査のみ」を実施する企業もあり、難易度がぐっと下がるケースもあります。そうした企業を狙うことで、自分の強みを活かした選考がしやすくなります。
企業によっては「書類選考の時点でSPIの代わりにポートフォリオやスキルテストを重視する」といった選考方法を採用しているところもあるため、事前に企業情報をしっかり読み込むことが重要です。
書類・面接重視の企業を狙うのも一手
SPIが苦手だからといって、転職活動を諦める必要はありません。自分の強みが面接や実績にある場合は、それを重視する企業を狙うのも賢い戦略です。
たとえば、営業実績やプロジェクト経験がある方なら、SPIよりも「面接での話し方」や「職務経歴書の書き方」に注力することで、十分に内定を狙えます。
また、「人柄重視」「カルチャーフィット重視」と明言している企業では、SPIの点数よりも面接の印象が通過可否に直結する傾向が強く、第二新卒ならではの熱意や将来性が評価されることもあります。
第二新卒のSPI対策でよくある質問
第二新卒としてSPI対策を進める中で、多くの方が同じような疑問や不安を感じています。ここでは、よく寄せられる質問に答える形で、対策のポイントや選考での見られ方について解説していきます。
Q. どのくらいの点数で通過できる?
企業によって基準点は異なりますが、6〜7割程度の正答率が合格ラインとされることが多いです。特に足切り目的で使っている企業では、平均より低い点数だと面接に進めない可能性もあります。
また、SPIの点数は性格検査と合わせて総合的に評価されることもあるため、「どちらかだけ得意」でも油断せず、バランスよく対策することが重要です。
Q. 性格検査の結果はどう見られる?
性格検査は、企業が求める人物像とどれだけ合っているかを判断するために使われます。たとえば「チームワーク重視」の企業で「協調性が低い」と判定されると不利になる可能性があります。
ただし、明確な「正解」はなく、重要なのは一貫性と極端すぎない回答。正直に、安定感のある回答を意識しましょう。
Q. SPI結果は他社と共有される?
テストセンター形式の場合、複数企業にスコアを共有できる「使い回し」が可能ですが、企業同士で勝手に情報が共有されることはありません。
ただし、自分が志望企業に提出したSPI結果はその企業が保持している可能性があるため、スコアが悪かった場合には再提出のチャンスがない場合もあります。初回からしっかり準備して受けることが大切です。
まとめ
第二新卒の転職活動では、「SPIがあるのかないのか」が選考突破の明暗を分けることもあります。特に大手企業やポテンシャル採用枠では、SPIが新卒同様に課されるケースが多く、避けては通れない存在です。
本記事で紹介したように、SPIにはさまざまな形式と出題傾向があり、対策法もそれぞれ異なります。業界別の出題傾向表や、対策レベル診断チャートを活用することで、効率的に準備を進めることができます。
もしSPIに不安がある場合でも、適性検査だけで済む企業や、書類・面接重視の企業も多数あります。自分の強みに応じて戦略的に応募先を選ぶことで、内定獲得に一歩近づけるでしょう。
第二新卒だからこそ、限られた時間で効果的な対策を。SPIを「突破の壁」ではなく「通過点」として乗り越えられるよう、今日から少しずつ準備を始めてみてください。