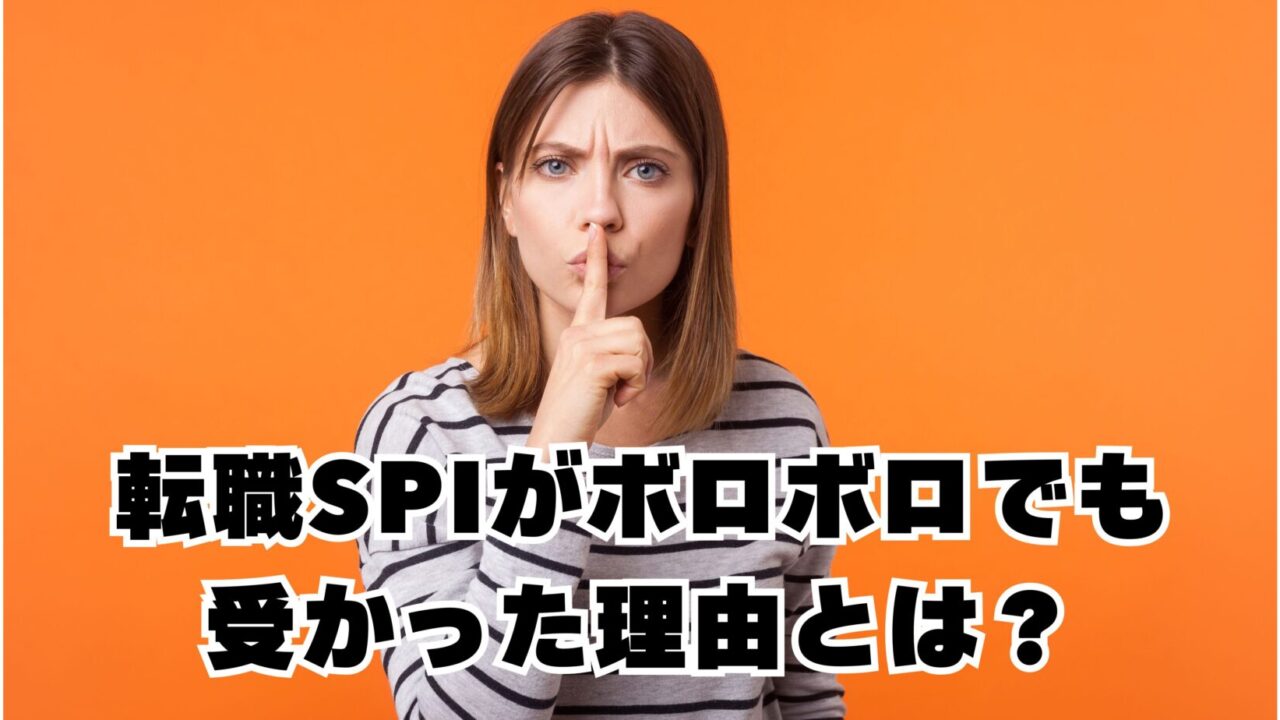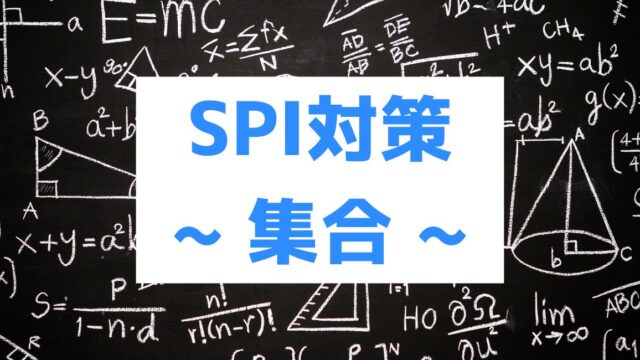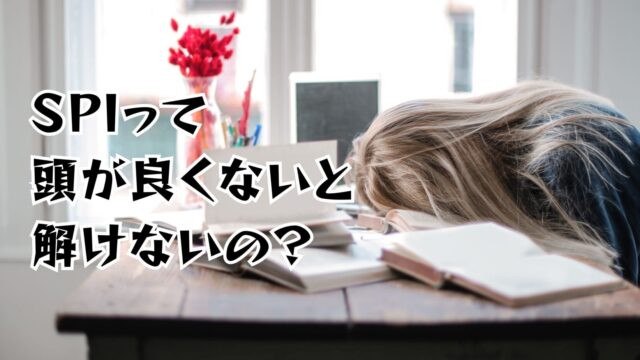【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
転職活動で多くの人を悩ませるのがSPIです。非言語や言語の問題はもちろん、性格検査の回答の仕方一つでも評価が変わる可能性があるため、受験者の心理的なプレッシャーは大きなものです。特に社会人として数年働いてから再び試験形式の問題に向き合うのは簡単ではなく、「全然解けなかった」「時間が足りずに半分も埋められなかった」といった声は少なくありません。
ところが、そうした人の中にも「SPIはボロボロだったのに通過できた」という体験談が数多く存在します。SNSや口コミサイトを調べてみると、「正直ほとんど勉強していなかったのに、なぜか次の面接に呼ばれた」「手応えゼロで落ちたと思ったら通過していた」という声が散見されます。
なぜこんなことが起こるのでしょうか?一見すると矛盾しているように思えますが、実は企業がSPIをどの程度重視するかは大きく異なります。SPIをあくまで「足切り」にしか使わない企業もあれば、最終評価の中心に据える企業もあります。そのため、SPIで点数が低くても、他の評価項目で十分に加点されれば合格につながるケースもあるのです。
このように「SPIがボロボロでも受かる人」は決して珍しい存在ではありません。では、具体的にどんな人がその対象になるのか、また企業側はどんな背景で判断を下しているのかを、これから詳しく解説していきます。
目次
SPIがボロボロでも受かった人は本当にいるの?
SPIが苦手な人にとって「本当にそんなことあるの?」という疑問は当然です。ここでは、実際の体験談や調査事例を通して、SPIの結果が芳しくなかったのに通過した人のケースを紹介します。
体験談に見る「ボロボロでも通過した」ケース
編集部が調査した事例やネット上の口コミには、いくつか共通するパターンがあります。例えば、営業職志望の30代男性は「数学問題がまったく解けず、ほとんど勘で埋めたが一次面接に進めた」と語っています。彼の場合、前職での営業実績が抜群だったため、職務経歴が大きく評価されたと考えられます。
また、20代女性のケースでは「時間が足りなくて最後の5問は白紙提出だったが、面接に呼ばれた」というものがあります。面接で直接話した際に、志望動機が明確でコミュニケーション力も高かったことから、SPIの点数よりも“人柄”が優先された形です。
さらに、「人手不足で大量採用していた時期だったので、SPIが悪くても落とされなかった」というケースも見られます。特に成長途上のベンチャー企業や地方拠点を急拡大している会社では、スコアよりも入社意欲や実務経験が重視される傾向があります。
このように、SPIがボロボロでも通過するのは都市伝説ではなく、実際に起きていることです。では、あなた自身が「受かるパターン」に当てはまるかどうか、次の診断チャートで確認してみましょう。
【診断チャート】あなたは“受かるパターン”?
SPIで思うような結果が出なくても、企業が重視する別のポイントで評価されれば十分に挽回できます。以下の簡易チャートで、自分がどのタイプに当てはまるかチェックしてみてください。
Q1. 前職での実績やアピールできる成果がある → Yesなら「経歴重視型」
Q2. 面接では会話が得意で、人柄をアピールできる → Yesなら「面接巻き返し型」
Q3. 志望先が人手不足や成長中の企業である → Yesなら「タイミング重視型」
Q4. 資格や学歴など、SPI以外の評価材料が豊富 → Yesなら「資格・学歴補強型」
診断の結果、自分が一つでも当てはまるなら「SPIがボロボロでも通過できる可能性がある人」といえます。逆にすべてNoだった場合は、SPIの対策を重点的に進めた方が安心でしょう。
SPIがボロボロでも受かる理由とは?
SPIで点数が取れなかったのに選考を通過した人がいるのは、決して偶然ではありません。そこには企業ごとの評価基準や採用のタイミングなど、いくつかの背景があります。ここでは、代表的な理由を整理して解説していきます。
企業がSPIを重視していないケースがある
まず大前提として知っておきたいのは、すべての企業がSPIを同じように重視しているわけではないということです。特に中小企業やベンチャー企業では、「SPIを足切りのために最低限導入しているだけ」というケースが少なくありません。
こうした企業では、SPIを学力テストというよりも「受験者が最低限の形式をこなせるか」を見る程度の意味しか持たせていないこともあります。実際、採用担当者の声を集めると「SPIは受験者の基礎力をざっくり確認するだけで、合否を決める材料ではない」と語る人も多いのです。
特に営業や販売など、人柄やコミュニケーション能力が重視される職種では、SPIよりも面接での印象の方がはるかに重要視される傾向があります。そのため、SPIがボロボロでも「一緒に働きたい」と思わせられる人物であれば、通過することは十分あり得るのです。
他の評価項目で加点されている可能性
SPIが低い点数でも合格する理由の一つに、他の評価項目で大きな加点を得ているケースがあります。具体的には以下のような要素が影響します。
まず、職務経歴です。過去に成果を上げた経験がある人材は、実務力がすでに証明されているため、企業はSPIの点数にそこまでこだわりません。特に即戦力を求めている中途採用では「前職での営業成績が優秀」「プロジェクトを成功させた」などの具体的な実績が強みになります。
次に、資格やスキルです。たとえばTOEICの高スコアや簿記、公認会計士、情報処理技術者など専門的な資格を持っている場合、それだけでSPI以上に価値があると見なされることもあります。
また、学歴も一定の影響を持ちます。すでに学歴フィルターを通過している場合、SPIの点数が思わしくなくても、基礎学力はあると判断されることがあるのです。
最後に面接評価も重要です。第一印象が良く、論理的に話せる人材は「試験では実力を発揮できなかっただけ」とポジティブに受け取られる可能性が高いでしょう。
時期や採用枠の影響も大きい
さらに見逃せないのが、採用時期や募集枠の状況です。
たとえば年度末や新規プロジェクトの立ち上げ時期には、多くの人材を短期間で確保しなければならないケースがあります。このようなタイミングでは「SPIで落とすより、面接で見極めた方が早い」という判断がされやすく、結果的にSPIのスコアが低くても通過する人が増えます。
また、地域ごとの採用事情も影響します。地方拠点や人材不足が深刻な業界では、SPIに厳しい基準を設けていると応募者が集まらず、基準を緩める企業もあります。
このように、SPIがボロボロでも受かる理由は、企業の評価基準の違い・他の加点要素・採用のタイミングといった複数の要因が絡み合っています。
【表でわかる】企業タイプ別 SPI重視度マップ
SPIがどの程度重視されるかは、企業の 業界・規模・採用スタンス によって大きく変わります。
「SPIができなかった=落ちる」と考えがちですが、実際には SPIを形式的にしか導入していない企業 も多いため、自分の志望先がどのタイプに当てはまるかを理解することが非常に重要です。
この章では、SPI重視度の違いを表で整理したうえで、それぞれのタイプに応募する際の戦略や注意点も解説します。
どの企業がSPIを重視しているのかを視覚的に把握
以下は業界・企業タイプごとのSPI重視度をまとめたマップです。
| 企業タイプ | SPI重視度 | 傾向・特徴 | 応募者へのアドバイス |
|---|---|---|---|
| 大手メーカー | 高い | 応募者数が非常に多く、SPIを効率的な「足切りツール」として利用。論理的思考力や基礎計算力を重視。 | SPI対策は必須。特に非言語(計算・確率)を重点的に練習しておくこと。 |
| 外資系企業 | 高い | グローバル基準で選考。数値処理や論理思考を重視し、場合によっては英語版SPIも実施。 | SPI+語学力の両方をアピールできるように準備する。スコアが低いと通過は難しい。 |
| 大手金融・サービス業 | 中〜高 | 金融は数字に強い人材を求めるため重視度高め。サービス業は人物重視だが、SPIを一次審査に活用。 | 非言語分野の強化を優先。最低限の得点ラインはクリアしておきたい。 |
| ベンチャー企業 | 低い | スピード採用が多く、人柄・熱意を最優先。SPIを実施しない企業も多い。 | SPIで失敗しても挽回可能。むしろ面接準備や志望動機を徹底することが重要。 |
| 中小企業 | 低〜中 | 採用基準は柔軟。SPIを導入していても「最低限解ければOK」というケースが大半。 | SPIに時間をかけすぎず、職務経歴や適性をしっかり伝えることに注力。 |
| 人手不足業界(介護・飲食・小売など) | 低い | 慢性的な人材不足のため、SPIの結果はほぼ形だけ。通過率は非常に高い。 | SPIは気にせず、面接で「長く働ける意欲」を強調すると効果的。 |
SPI重視度の違いから見える「戦い方」
この表からも分かる通り、SPI重視度は 応募者数や業界の特性 によって大きく変わります。
- 大手や外資系 はSPIが最初の関門になるため、しっかりと対策をしておくことが必須です。逆にSPIが低いと書類や経歴が良くても突破が難しい傾向があります。
- 中小やベンチャー は人物重視で、SPIが多少悪くても合格可能です。そのため、SPIに不安がある人はこうした企業を優先的に受けるのも戦略の一つです。
- 人手不足業界 はSPIがほとんど形骸化しているケースも多く、SPIに自信がなくても内定を狙いやすいフィールドです。
応募前に確認しておきたいこと
志望企業がどのタイプに属するかを事前に見極めることが大切です。求人票や採用情報に「SPI(テストセンター)」と明記されている場合は重視度が高い傾向があります。逆に「Web適性検査」とだけ記載されている場合は、性格検査が中心で能力検査は軽視される可能性もあります。
SPIがボロボロでも次の選考に影響する?
SPIを受けて「全然できなかった」と感じた時、多くの人が心配するのは「もし通過しても、この先の面接でマイナス評価されるのではないか」という点です。結論から言えば、SPIのスコアがボロボロでも 通過した時点で大きなハンデにはならない ことがほとんどです。
企業はSPIを「一次の足切り」に使うケースが多く、面接や最終選考でSPIの点数が話題に上ることはまずありません。実際に採用担当者の声を集めても「SPIは最低限のスクリーニングであって、合否を最終的に決めるのは人物評価」と答える人が大半です。
SPI通過=内定ではない、だが面接で逆転可能
ただし注意しなければならないのは、「SPIに通過したから安心」というわけではないということです。SPIを突破したとしても、それはあくまでスタート地点に立っただけ。実際の内定獲得には、面接での受け答えや熱意、職務経歴といった 人柄や能力の総合評価 が必要になります。
むしろSPIが不安だった人ほど、「面接で巻き返そう」という意識を持つことが重要です。例えば以下のようなケースでは、SPIの不安を帳消しにできるほどの逆転が可能です。
- 志望動機を企業のビジョンと具体的に結びつけて語れる
- 過去の成果を数字で示し、即戦力性をアピールできる
- 面接官と円滑なコミュニケーションを築き、「一緒に働きたい」と思わせられる
企業によってはSPI結果を参考資料として保持するケースもある
一方で、一部の企業ではSPIの結果を最終選考まで保持し、「参考資料」として利用することがあります。例えば「面接では好印象だが、非言語スコアが極端に低い」といった場合に「業務で数字に弱いと困るかもしれない」と懸念されるケースです。
ただし、これが直接的に不合格につながることは多くありません。実際には「SPIが苦手でも、それを補えるスキルがあるか」という観点で評価されます。営業職であればコミュニケーション力、企画職であれば発想力や資料作成力など、SPI以外の武器を示せる人は不利になりにくいのです。
SPI不安をプラスに変える考え方
「SPIがボロボロだった」と落ち込むよりも、「だからこそ面接で人柄を見てもらおう」「企業研究を徹底しよう」と切り替えた方が、結果的に良い評価につながります。SPIの点数はあなたの全人格や能力を決めるものではなく、あくまで一部の指標に過ぎません。
実際に、SPIに自信がなかった人ほど「面接対策を徹底していたから内定を取れた」という成功談は多くあります。重要なのは、SPIの結果を不安に思う気持ちを原動力に変え、次のステップで確実に成果を出すことです。
SPIがボロボロだった時の緊急対応
SPIを受けた直後に「全然解けなかった」「時間が足りなくて焦った」「ほとんど勘で答えてしまった」と感じる人は少なくありません。特に久しぶりに学力テストに挑む転職者にとって、SPIは大きな壁の一つです。しかし大事なのは、その瞬間に落ち込むのではなく「次にどう動くか」です。SPIはあくまで選考の一部であり、面接や経歴といった他の評価項目で十分に挽回することができます。ここでは、SPIがボロボロだった時に取るべき緊急対応を具体的に解説します。
受かった後の「見られポイント」を意識した準備
まず最も大切なのは「次のステップで何を見られるか」を明確に意識することです。SPIが不安でも、企業が次に注目するのは面接での受け答えや志望度の高さです。ここでしっかりと準備しておけば、SPIの不安を帳消しにすることができます。
1. 面接準備を徹底する
SPIでのマイナスを補うには、面接で「一緒に働きたい人材」と思わせることが最重要です。志望動機や自己PRを単なるきれいごとにせず、過去の経験や成果と結びつけて語れるように練習しましょう。たとえば「営業で〇%の売上アップを実現した経験があるので、御社でも顧客基盤拡大に貢献できる」という具体的なエピソードは説得力があります。
2. 逆質問で好印象を残す
面接の最後に必ず聞かれる「何か質問はありますか?」の場面は大きなチャンスです。SPIが不安でも、ここで企業研究に基づいた深い質問をすれば「準備ができている人」という評価につながります。たとえば「御社が直近で取り組まれている新規事業に関して、入社後どのように関わる可能性がありますか?」といった質問は、志望度と理解度を同時に示すことができます。
3. 企業理解を深めて差をつける
SPIの出来を補うには、企業研究を徹底的に行うことも効果的です。企業の公式サイトやプレスリリース、業界ニュースを調べ、自分のキャリアとどう接続できるかを整理しておきましょう。たとえSPIの点数が低くても、企業理解が深い応募者は「入社後に活躍してくれそう」という期待を抱かれやすいのです。
面接以外の緊急リカバリー方法
SPIがうまくいかなかったとしても、面接以外の場面で巻き返す工夫も可能です。
書類での強み強調
履歴書や職務経歴書において、数値で示せる成果や明確なスキルを盛り込むことは、SPIのマイナスを補う有効な手段です。資格や語学力、業務での定量的成果を記載すれば、選考全体での評価を底上げできます。
模擬面接や短期学習で再挑戦準備
もし次回の企業でもSPIが課される場合、直前の短期学習でも一定の効果は見込めます。市販の問題集やアプリを利用して「時間配分の感覚」を身につけるだけでも、次の試験では大きな改善につながります。
「失敗した」と感じても動きを止めないことが重要
何より大切なのは「SPIで失敗した」と感じても、そこで立ち止まらないことです。転職活動ではSPIの出来がすべてを決めるわけではなく、むしろ面接での印象や実務経験の方が大きな比重を占めます。SPIがボロボロでも、その後の行動次第で十分に挽回は可能です。
「SPIはダメだったけど、面接でしっかり自分をアピールする」「企業研究で他の候補者よりも理解度を示す」といった意識で次に備えることこそ、合格への最短ルートなのです。
SPIの通過率・落ちる人の割合は?
SPIを受験した人の多くが気になるのは「実際にどれくらいの人が落ちているのか」という点です。しかし、SPIの通過率は公式には公開されていません。リクルートが提供する適性検査である以上、企業ごとに利用方法が異なり、合格ラインも非公開だからです。とはいえ、実際に受験した人の体験談や採用担当者の声を集めると、大まかな傾向をつかむことは可能です。ここでは、SPIの通過率や落ちる人の割合について解説します。
実際にどれくらいの人がSPIで落ちているのか
一般的に、大手企業や外資系など人気企業では「応募者の半数近くがSPIで足切りされる」といわれています。倍率が高いため、効率的に候補者を絞り込む目的でSPIが使われるからです。特に非言語分野の点数が著しく低い場合、そこで落とされるケースが多いとされています。
一方で、中小企業やベンチャー企業ではSPIの点数を重視しないため、通過率は高めです。「受験者の7〜8割が通過した」という報告もあり、形式的に受験させているに過ぎないケースも少なくありません。つまり、企業の採用方針によって通過率は大きく異なるのです。
また、業界によっても差が見られます。金融やメーカーといった「数字に強い人材」を求める業界ではSPIの通過率は低めですが、人材サービスや小売、ベンチャーなど「人柄や意欲」を重視する業界では通過率が比較的高い傾向があります。
【図解】SPIスコアと通過率の相関イメージ
ここで、SPIのスコアと通過率の関係をイメージしやすいように整理してみましょう。あくまで参考値ですが、体験談や業界動向をもとにしたおおよその目安です。
SPIスコアと通過率の目安(イメージ)
- 40%未満:通過率は低め(大手や外資系ではほぼ不合格、中小なら一部通過あり)
- 50〜60%程度:ボーダーライン上。企業によって結果が大きく分かれる。人物評価次第で通過可能。
- 70%以上:安心圏。大手・人気企業でも十分戦えるスコア。SPIが原因で落ちる可能性は低い。
これをグラフでイメージすると、点数が上がるにつれて通過率が右肩上がりに増えていく形になります。ただし40%台でも面接に呼ばれるケースは珍しくなく、特に人手不足業界や柔軟な採用方針を持つ企業では、スコアの低さが致命的にならないことも多いのです。
通過率にとらわれすぎないことが大切
「SPIで落ちる人は多い」という話を聞くと不安になりますが、重要なのは「通過率が低いから自分はダメだ」と思い込まないことです。SPIはあくまで選考の一部であり、企業にとっては人物像や経験の方が重視される場面が多くあります。
仮にSPIで不安があっても、通過すればその後の面接や書類で十分に挽回できますし、SPIの点数を最終判断まで引きずる企業はそれほど多くありません。大事なのは「SPIの出来が悪くても、その後の行動で補える」と意識を切り替え、気持ちを落とさず次に進むことです。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPIの再受験はできる?
SPIを受けたあとに「全然できなかった」「やり直したい」と思う人は多いはずです。特に転職活動では一社の合否がキャリアに直結するため、「もし再受験できるなら挑戦したい」と考えるのは自然なことです。しかし、SPIの再受験にはいくつかのルールがあり、無制限に受け直せるわけではありません。ここでは再受験が可能かどうか、その条件や注意点について詳しく解説します。
再受験の条件と企業ごとのルール
SPIはリクルートが運営している適性検査で、受験者のデータは一定期間保存されます。そのため「一度受けたら同じ結果が他の企業でも使い回される」仕組みになっている場合があります。特に テストセンター方式 のSPIでは、受験者IDと成績が紐づけられているため、同じ時期に複数社へ応募すると、基本的に同じ結果が各社に共有されます。
つまり「この企業で失敗したから、もう一度やり直そう」と思っても、同じ期間に別の企業で受け直すことができず、以前の結果がそのまま使われるケースが多いのです。
一方で、 Webテスティング方式 や ペーパーテスト方式 のSPIでは、企業ごとに独自に受験する仕組みになっている場合があり、その場合は再受験の機会が発生します。例えばA社とB社で応募時期が近くても、それぞれの企業の指示に従って受験すれば、別々の結果になることがあります。
また、テストセンター方式でも 数か月〜半年程度の間隔 を空ければ再受験が可能になる仕組みがあります。そのため、長期的に転職活動を続ける場合は、以前のスコアがリセットされて新しい結果を利用できるチャンスがあるのです。
再受験に関する注意点
ただし、再受験の仕組みを理解する際に注意すべきポイントがいくつかあります。
- 企業によっては過去結果を必ず参照する
たとえ再受験が可能でも、企業が「過去の受験結果を採用に利用する」と設定していれば、最新のスコアではなく以前の結果を参照する場合もあります。 - 短期間でのやり直しは不可能
同じ時期の転職活動で「何度も受け直して点数を上げる」という方法は基本的にできません。準備不足で受けてしまうと、その結果がしばらく残ってしまうので、初回の受験前にある程度対策をしておくことが重要です。 - 企業に直接確認するのも有効
応募先がどの方式のSPIを採用しているのかは求人票に書かれていないことも多いため、選考案内メールや問い合わせ窓口で確認することが有効です。
「再受験不可」でも諦める必要はない
もしSPIがボロボロで再受験できなかったとしても、それで全てが終わるわけではありません。すでに述べたように、企業によってはSPIを一次選考にしか使わず、その後は人物面で判断するケースが多いからです。再受験できない場合でも、面接や書類でのアピールを強化すれば十分に挽回は可能です。
SPIがボロボロだった人の成功・失敗エピソード
SPIは転職活動における関門の一つですが、実際に「ボロボロだったのに受かった」という人もいれば、「やはりSPIが原因で落ちてしまった」という人もいます。両者の違いを知ることで、自分がどのように行動すべきかが見えてきます。ここでは、実際の体験談をもとに「成功」と「失敗」の両面から学べるポイントを整理していきます。
成功体験:SPIが悪くても“逆転合格”した人の共通点
まずは成功体験から見ていきましょう。SPIがボロボロでも合格できた人にはいくつかの共通点があります。
1. 柔軟な対応力を持っていた
ある30代の営業経験者は、非言語分野でほとんど答えられず「これは絶対に落ちた」と思ったそうです。しかし、その後の面接で「予算未達だった部署を立て直した経験」を具体的に語り、状況に応じた柔軟な対応力を示したことで高く評価され、最終的に内定を獲得しました。
2. 面接での巻き返し力が強かった
20代女性の例では、SPIの時間配分に失敗して問題を半分近く白紙で提出しました。それでも面接では「なぜ転職を決意したのか」「入社後にやりたいこと」を自分の言葉で熱意を込めて伝え、面接官に「一緒に働いてみたい」と思わせることができたそうです。SPIの点数が低くても、人柄や志望度が評価されれば逆転は可能だと分かります。
3. 人手不足の企業を狙っていた
別のケースでは、地方のIT企業に応募した転職者が「SPIは全然できなかったが通過した」と語っています。この企業は急速に事業を拡大しており、とにかく人材を確保したいタイミングだったため、SPIよりも実務経験や応募者の意欲を重視していました。
これらの事例からわかるのは、SPIが悪くても「面接で自分をどう見せるか」「企業の採用状況に合っているか」によって結果は大きく変わるということです。
失敗体験:SPIが原因で不合格になった事例
一方で、「やはりSPIが原因で落ちた」と考えられる失敗事例もあります。こちらからも学べる点は多いです。
1. 誤った対策方法で挑んだ
ある応募者は「市販の問題集を数ページだけ解いて安心してしまった」状態で本番に臨みました。結果、問題形式に慣れず時間が足りなくなり、ほとんど得点できなかったそうです。準備不足はSPIでは致命的になり得ます。
2. 焦って受験してしまった
別の応募者は、夜勤明けの疲れた状態でSPIを受験しました。集中力が切れて計算問題で凡ミスを連発し、不合格。体調管理や受験環境の整備がいかに重要かを物語る事例です。
3. 時間配分を誤った
「序盤の問題に時間をかけすぎて後半をほとんど解けなかった」という声も多くあります。SPIはすべての問題を解ききるのが難しい設計になっているため、割り切りが必要です。時間配分を誤ると、実力があっても点数が伸びません。
これらの失敗事例は、「SPIができなかったこと」自体よりも「準備不足や環境の不備」が原因になっているケースが多いです。つまり、次回以降にしっかりと準備すれば改善できる余地が大きいとも言えます。
【スコア別】SPI対策ロードマップ
SPIを受けて「手応えがあった」「全然ダメだった」と感じることは人それぞれですが、実際には自分のスコアに応じて取るべき行動が変わります。ここでは、スコアの目安ごとに「次にやるべきこと」や「狙うべき企業タイプ」を整理したロードマップを提示します。自分がどの段階にいるかを確認し、効率よく対策を進めましょう。
スコア40%未満:要再対策ゾーン
SPIの出来が40%未満と感じる場合は、残念ながら大手や外資系企業の選考通過は難しいと考えられます。このスコア帯は「基礎力が不足している」「問題形式に慣れていない」ことが原因であることが多く、まずは学習方法を根本的に見直す必要があります。
この段階では「SPI免除の企業」を狙うのも戦略の一つです。ベンチャーや中小企業の中にはSPIを実施していない企業も多く、人物評価で勝負できる可能性があります。
ただし、長期的な転職活動を見据えるなら「一からSPI対策を始める」ことが望ましいです。特に非言語(計算・確率・集合など)に苦手意識がある人は、基礎的なドリル形式の教材で少しずつ慣れていくことが効果的です。
スコア50〜60%:ボーダーラインゾーン
このスコア帯は「合格か不合格か」が企業によって分かれるボーダーラインです。大手企業ではやや厳しいものの、中堅企業や採用人数の多い企業では十分に通過できる可能性があります。
この段階の人に必要なのは「面接勝負」を意識した動き方です。SPIの結果が芳しくなくても、面接で志望動機や経験をしっかり伝えられれば評価を覆せます。
同時に「SPI補強」をしておくことも重要です。直前の短期対策だけでも、問題形式に慣れれば正答率を数%上げることは可能です。具体的には、時間配分の練習や出題頻度の高い単元を重点的に復習するなど、効率的に取り組みましょう。
狙うべきは「成長企業」「柔軟な採用を行っている企業」です。こうした企業は人材の可能性を重視する傾向があるため、SPIが多少低くても人物面での評価が上回れば通過できる可能性があります。
スコア70%以上:通過圏内ゾーン
SPIで7割以上の正答率を取れている場合、多くの企業で「SPIが原因で落ちる」リスクはほぼなくなります。大手企業や上場企業でも十分に通過できるスコア帯であり、安心して面接に臨むことができるでしょう。
ただし、注意が必要なのは「SPIが良いからといって内定が近いわけではない」という点です。あくまでSPIは選考の一部に過ぎず、人物評価や志望動機、企業理解が欠けていれば最終的に不合格になることもあります。
この段階の人は「SPIはもう十分だから、面接対策や企業研究に時間を割く」ことが重要です。SPIに安心して油断してしまうと、かえって本質的な選考準備がおろそかになるリスクがあります。
【スコア別ロードマップまとめ】
- 40%未満:SPI免除企業を狙う+基礎から再学習
- 50〜60%:面接重視の企業に応募しつつ短期対策で補強
- 70%以上:SPIは安心圏、面接・企業研究に注力
SPI対策はどうすべき?おすすめ参考書とアプリ紹介
SPIは「受かるための満点を取る試験」ではなく、「足切りを超えるために最低限の得点を取る試験」と言えます。つまり、闇雲に全範囲を完璧に勉強する必要はなく、自分に合った教材やツールを使って効率的に学ぶことが重要です。ここでは、忙しい転職者でも取り組みやすいアプリと参考書を紹介します。
らくらく就活のSPI対策アプリ
まず手軽に取り入れられるのが、SPI対策アプリの活用です。特に弊社の「らくらく就活SPI対策アプリ」は、無料で使えるうえに機能が充実している点が大きな魅力です。
このアプリは出題傾向に合わせて問題が分類されており、短時間でも効率よく学習できます。たとえば通勤中や休憩時間などの隙間時間に、非言語の計算問題や言語の語句問題を解くことが可能です。
また「テストモード」が用意されているので、試験直前に出題頻度の高い問題だけを集中的に解くことも可能です。SPIは短期集中で実力が伸びやすい試験でもあるため、このアプリを使えば効率的に合格ラインへ到達できます。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPI対策本:スコア別に選ぶおすすめ本
書籍でじっくり対策したい人には、スコアや目的に応じた本を選ぶことが大切です。ここではタイプ別におすすめの参考書を紹介します。
1. 短期集中型(時間がない人向け)
『7日でできる!SPI必勝トレーニング』
直前期に追い込みたい人向け。出題頻度の高い問題だけを厳選しており、1週間で主要範囲を回せます。
2. 全形式対応型(幅広く網羅したい人向け)
『これが本当のSPI3だ!【2025年度版】』
SPIの非言語・言語・性格検査を網羅した定番本。問題量が豊富で、全体像を理解するのに最適です。
3. Webテスト特化型(テストセンター受験者向け)
『史上最強SPI&テストセンター超実践問題集』
本番と同じ形式で模試を体験できる一冊。時間感覚をつかみたい人におすすめです。
4. コスパ重視型(1冊で完結させたい人向け)
『SPI3&テストセンター 出るとこだけ!完全対策』
要点を絞ってコンパクトにまとめられており、効率的に得点力を上げられます。
効果的な学習法のポイント
アプリと書籍を組み合わせることで、学習効果はさらに高まります。平日はアプリで短時間学習、休日は参考書でじっくり演習というスタイルを取れば、無理なく習慣化できます。
また、SPIは時間配分が最重要です。本番を意識して「1問にかける時間を測りながら解く」練習をすると、得点力が飛躍的に伸びます。
まとめ|SPIがボロボロでも「終わり」ではない
ここまで見てきたように、SPIは転職活動の大きな関門である一方で、「SPIがボロボロだった=即不合格」ではありません。実際に、スコアが低くても合格した人の体験談は多く存在し、その背景には企業の評価基準の違いや、人物面を重視する採用方針があります。
大切なのは、SPIをあくまで「選考の一部」として捉えることです。たとえ失敗したと感じても、次の面接での印象や職務経歴、志望度の高さによって十分に挽回できます。SPIに不安があっても行動を止めず、次に向けた準備を重ねることこそが、合格への最短ルートです。
さらに、SPIは一度失敗しても再受験の機会があったり、別の企業で改めて挑戦できる可能性があります。仮に点数が振るわなくても、それをきっかけに弱点を把握し、学習を積み重ねていけば次回は確実に成長できます。
本記事で紹介したように、成功体験者は「面接での巻き返し」「柔軟な対応力」「企業理解の深さ」を武器にしていました。逆に失敗体験者は「準備不足」や「時間配分の誤り」といった基本的な部分でつまずいていることが多くあります。つまり、SPIの結果以上に、その後の行動や準備の質が合否を分けているのです。
SPIがボロボロでも、それは転職活動の「終わり」ではなく「改善のきっかけ」です。むしろ、自分の強みを整理し、企業理解を深め、面接で自信を持って話せるように準備するチャンスと捉えましょう。
最後に強調したいのは、「SPIがすべてではない」ということです。企業が本当に知りたいのは、あなたが入社後にどのように活躍するか、どんな価値をもたらすかです。SPIに一喜一憂するのではなく、自分のキャリアをどう描きたいのかを明確にし、その姿を面接や選考の場でしっかり伝えていくことが、最終的に内定を勝ち取る最も確実な方法なのです。