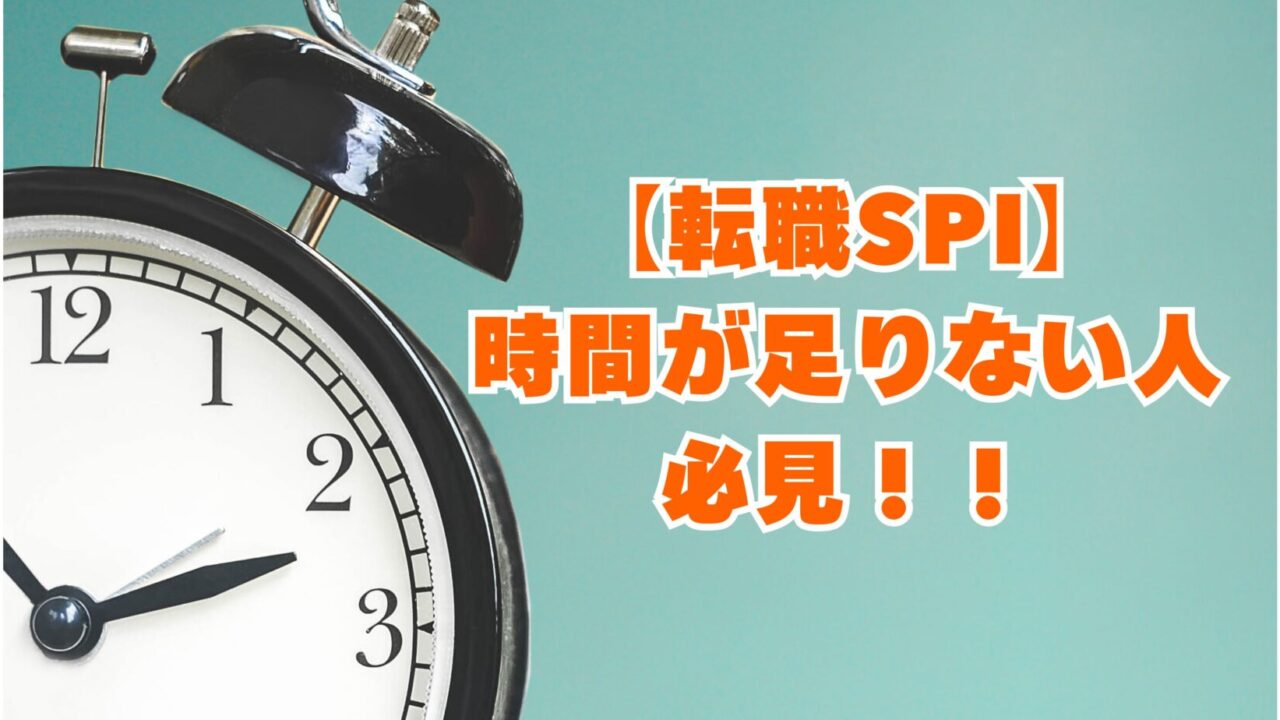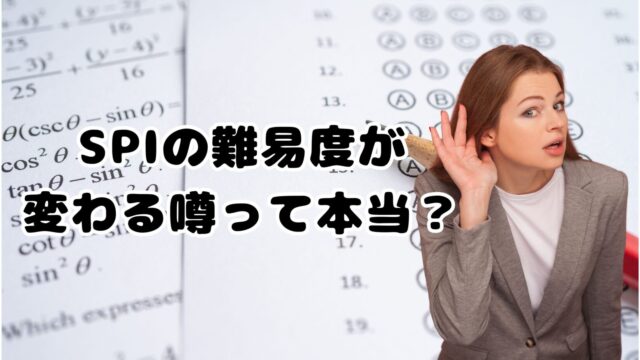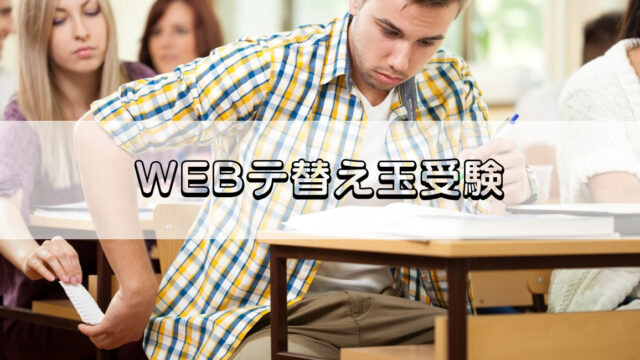【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
転職活動でSPIを受ける際、「時間が足りなかった」「全然解ききれなかった」という経験談をよく耳にします。特に、SPIにおいては“正答率”だけでなく“スピード”が重要な評価ポイントになるため、ただ解けるだけでは不十分です。時間内にどれだけ多くの問題を正確に処理できるかが、合否を分ける大きなカギとなります。
しかし、社会人になってから学習の時間を確保するのが難しい方や、テスト形式に慣れていない方にとっては、SPIの時間制限は非常に厳しく感じられるかもしれません。加えて、SPIでは非言語(計算問題)や長文読解など、時間を奪われがちなパートも多く、焦りから実力を発揮できないケースも少なくありません。
本記事では、SPI試験において時間が足りなくなる原因をはじめ、受検形式別の時間配分の目安、実際の体験談、時間配分がうまくいかない典型的なパターン、さらには事前対策と本番での工夫までを詳しく解説していきます。
また、診断チャートや時間配分シミュレーションといった“この記事ならではのオリジナル要素”も取り入れ、読むだけで自分の弱点や対策ポイントが明確になる構成にしています。
SPIでの時間切れを防ぎ、転職成功へと一歩近づくために、今からできる具体的な行動を一緒に整理していきましょう。
目次
SPIで時間が足りないと感じる理由
SPIを受けた転職者の多くが共通して抱える悩みのひとつが、「時間が足りず、すべての問題を解き終えられなかった」というものです。これは単なる個人の能力不足ではなく、SPIそのものが時間的に厳しく設定された試験であることが大きく関係しています。ここでは、SPIで時間が足りなくなる主な要因を具体的に解説していきます。
SPIはなぜ時間がシビアなのか
SPI試験が「時間勝負」と言われる最大の理由は、出題数に対して制限時間が非常に短く設定されている点にあります。たとえば、テストセンター方式でのSPIでは、40問前後を35分程度で解かなくてはなりません。単純計算で1問あたりおよそ50秒強。じっくり考えていたらすぐに時間が足りなくなるのです。
また、全問を通して時間が決まっている形式が多いため、ある問題に時間をかけすぎると他の問題に手が回らなくなるという構造的なリスクもあります。特に非言語分野では、1問の所要時間が問題の内容によって大きく変動しやすく、「一問に引きずられる」といったミスをしがちです。
出題数に対して制限時間が短い
SPIは試験時間が「30~35分」と短い割に、問題数は30問を超えるケースが一般的です。このバランスの悪さが、時間のシビアさを生み出す根本要因です。さらに、前半に言語、後半に非言語が配置されている構成が多く、時間の消費バランスを自分でうまく調整しなければ、後半に問題が残ったままタイムアップになるという事態も珍しくありません。
問題文が長く、読むだけで時間がかかる
SPIの言語問題では、短文空欄補充のような簡易な設問もある一方で、「長文読解」や「文の並べ替え」など、ある程度の読解力が求められる問題も含まれています。こうした問題では、設問にたどり着くまでに数行から十数行の文章を読む必要があり、それだけで時間を消費します。
特に読書量が少ない方や、文章を読み慣れていない方にとっては、設問文そのものを読む段階で焦ってしまい、解答スピードがさらに落ちてしまうという悪循環も起こりがちです。
非言語問題で計算に手間取る
非言語(計数)分野では、グラフや表の読み取り、割合、速度・時間・距離、確率などの算数・数学的な問題が多く出題されます。社会人になると、こうした基本的な計算に触れる機会が減るため、計算方法を忘れていたり、手順を整理するのに時間がかかったりすることもあります。
また、試験中は電卓が使用できないケースが多く、筆算や暗算に頼る必要があります。これに慣れていないと、正解率以前に「1問に2分以上かかってしまう」といった時間面での大きなロスが生じてしまいます。
慣れていない形式で緊張してしまう
SPIは特有の出題形式をとっており、一般的な筆記試験や面接とはまったく異なるアプローチが求められます。そのため、試験に不慣れな方は「この形式、初めて見る…」といった不安から緊張してしまい、頭が真っ白になって思考が止まってしまうケースもあります。
さらに、慣れていない人ほど「一問ずつ丁寧に読もう」「しっかり考えよう」という姿勢になりがちで、それが結果的に全体のペースダウンにつながります。SPIでは、ある程度“流れ作業的に進める感覚”を持つことが時間内解答のための鍵になります。
あなたのSPI時間対策レベルをチェック
SPIで「時間が足りない」と感じるかどうかは、事前の準備レベルによって大きく変わってきます。どんなに地頭がよくても、時間配分の感覚や形式への慣れがなければ、実力を発揮できずに終わってしまうことも。逆に、基礎学力に不安がある人でも、時間対策さえしっかり行っていれば、十分にスコアを出すことが可能です。
そこでまずは、以下のYes/Noチャートを使って、あなたのSPI時間対策レベルをチェックしてみましょう。該当する項目の数によって、今後の対策の方向性が明確になります。
【SPI時間対策レベル診断】
Q1. SPI模試を時間計測して2回以上実施したことがある
ただ解くだけでなく、制限時間を設けて模試を実施することで、実際の試験時間の短さを実感できます。経験済みなら、時間感覚が身についている可能性が高いです。
Q2. 苦手分野(非言語・言語)を明確に把握している
どちらの分野に時間がかかっているのかを把握していれば、重点的に対策を立てることができます。感覚ではなく、模試や練習問題の結果から分析できているかがポイントです。
Q3. 問題を見て、すぐに解法のパターンが浮かぶことが多い
SPIでは、「型」に慣れているかどうかで解答スピードが大きく変わります。問題を見た瞬間に「これは割合の問題だな」「表の読み取りだな」と判断できる人は、時間内に終える力がついてきています。
Q4. 解けない問題を後回しにする習慣がある
SPIは全問正解を狙う試験ではなく、限られた時間内で最大限の得点を稼ぐ試験です。解けそうにない問題にこだわらず、割り切って次に進める判断力があるかどうかも重要です。
Q5. 1問あたりの目安時間を意識しながら解いている
「1問にかけられるのは約50秒」といった感覚が染みついていれば、本番でも焦らずに時間配分を調整できます。問題を“時間内で解く”という意識を常に持てているかをチェックしましょう。
診断結果
Yesが4〜5個:実践型
あなたはすでに時間配分を意識した学習ができており、あとは模試を重ねて安定性を高める段階に来ています。本番でも焦らず、着実にスコアを出せるタイプです。引き続き、模試形式の練習を継続しましょう。
Yesが2〜3個:部分的対策型
時間対策の基礎はできているものの、まだムラがある状態です。苦手分野の補強や、より厳密な時間管理を取り入れた練習が必要です。時間をかけるべき問題・スキップすべき問題の見極めができるようになると、得点力がグッと上がります。
Yesが0〜1個:準備不足型
今のままでは本番で時間切れになるリスクが高いです。まずは模試を使って時間配分の感覚を養いましょう。いきなり完璧を目指さず、時間内に解き終える感覚を身につけることからスタートするのがポイントです。
この診断で自分の課題が明らかになった方は、次の章で紹介する「SPI形式別の時間配分シミュレーション」を参考にしながら、具体的な改善に取り組んでみてください。
SPI形式別|時間配分シミュレーション表
SPIは受検方式によって出題数や制限時間が異なります。そのため、どの形式で受けるかによって時間配分の戦略も変わってきます。特に転職者の場合、企業によってテストセンター・Webテスティング・CBT方式・ペーパーテストのいずれかが指定されるため、受験形式ごとの特徴を把握しておくことは必須です。
この章では、各SPI形式における問題数・試験時間・1問あたりの時間の目安をシミュレーション表で整理し、どの程度のスピードで解く必要があるのかを具体的に可視化していきます。
各受験形式の比較表
| 受験形式 | 設問数(目安) | 制限時間(目安) | 1問あたりの目安時間 |
| テストセンター | 約40問 | 約35分 | 約52秒 |
| WEBテスティング | 約35問 | 約30分 | 約51秒 |
| CBT方式 | 約30問 | 約25分 | 約50秒 |
| ペーパーテスト | 約35問 | 約30分 | 約51秒 |
各形式におけるポイントと注意点
テストセンター方式
もっとも一般的な形式で、パソコンを使用して受験するスタイルです。画面操作や表示の切り替えに慣れていないと、些細な動作でも時間をロスする恐れがあります。とくに「問題文を読みながら、選択肢をスクロールして選ぶ」など、想像以上に操作が時間を食うこともあります。事前に模擬試験をPC上で体験しておくとよいでしょう。
WEBテスティング方式
自宅で受けられる形式ですが、時間管理が自己責任になります。スマホではなくPCでの受験が前提であり、受験環境の整備(静かな部屋、時計の設置、通信環境)も含めて万全にしておきましょう。また、制限時間に対する警告表示がない場合もあるため、自分でこまめに残り時間を確認する癖をつけておくことが大切です。
CBT方式
パソコンで受けるテスト形式で、資格試験などでも広く採用されています。画面遷移に癖がある場合があるため、操作感に慣れておかないとミスを誘発します。SPIに限らず、普段からPC上で問題演習を行う習慣があると対応しやすくなります。
ペーパーテスト方式
あまり多くはありませんが、企業によってはいまだに紙でのSPIを採用していることもあります。マークミスやページの戻り忘れといった人的なミスが起きやすく、注意力が求められます。試験中に全体の進捗を把握するのが難しい点もネックとなるため、時間配分の管理はより慎重に行いましょう。
ポイント:SPIは1問1分未満で解き進める必要がある
上記の表を見て分かるように、どの受験形式でも1問にかけられる時間は「約50秒程度」です。これは、選択肢を確認し、計算し、解答を選ぶまでをすべて含めた時間です。そのため、「ゆっくり読んで考えて…」というスタンスでは到底間に合いません。
対策としては、以下のような点を意識するとよいでしょう。
- 各設問に「1分以上はかけない」と意識しながら練習する
- 難問にひっかかっても「飛ばして次へ」を徹底する
- 時間配分の目安を紙に書いて見える場所に貼っておく
時間管理の精度は、単なる試験対策だけでなく、転職活動全体の効率にもつながります。次の章では、実際に時間切れを経験した転職者の体験談を紹介しながら、リアルな課題と気づきを見ていきましょう。
SPIで時間切れになった転職者の体験談
SPIでの「時間切れ」は多くの受験者にとって現実的な悩みです。ここでは、実際にSPI試験中に時間が足りずに困ったという転職者の声を紹介します。どのようなミスが原因で時間配分に失敗したのか、そしてそこから得られる教訓は何かを具体的に見ていきましょう。
Aさん(29歳・メーカー志望)のケース
「最初の10問に時間をかけすぎて、後半は時間が全く足りず…。事前に時間配分を意識した模試をしておけばと後悔しました。」
AさんはSPIを受けるにあたり、事前に市販の問題集で対策をしていたものの、模試形式での練習はしていなかったそうです。本番では、最初の数問を丁寧に読みすぎてしまい、気がついたときには残り10分。そこから焦ってスピードアップしたものの、後半の非言語問題には十分な時間が取れず、点数を大きく落とす結果となってしまいました。
Aさんのように、「前半で時間を使いすぎて後半が崩れる」というのは非常に多いパターンです。問題の難易度に関わらず、時間の上限を意識しておく必要があります。
Bさん(27歳・IT企業志望)のケース
「電卓を使えないと知らず、計算問題で時間ロス。試験形式の把握が甘かったことが敗因でした。」
Bさんは理系出身で計算問題には自信があり、非言語分野での得点に期待していました。しかし、SPI本番では電卓の持ち込み・使用が不可だったため、急遽筆算で対応せざるを得ず、見積もっていた解答時間を大幅にオーバーしてしまいました。結果として、得意分野で点を稼ぐつもりが、むしろ足を引っ張ってしまう形となったのです。
この失敗からわかるのは、試験内容だけでなく「試験環境・ルールの確認」も対策の一部だということです。時間が足りない原因は問題の難易度だけでなく、準備不足や思い込みによる判断ミスにもあるのです。
教訓:本番で焦らないためにも、事前準備で“時間対策”のシミュレーションをしておくことが合格の鍵です
AさんもBさんも、「問題を解けなかった」のではなく、「時間が足りなかった」という共通の壁にぶつかっています。そしてどちらも、「本番形式での練習不足」「情報収集の甘さ」が原因でした。
SPIでは、1点を争う選考になるケースも珍しくありません。たった数問の差で次のステップに進めるかどうかが決まることもある以上、「時間を制する者がSPIを制する」と言っても過言ではないのです。
これから受験する皆さんには、過去の失敗例を他人事とせず、実践的な時間配分訓練を必ず取り入れていただきたいと思います。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
時間配分がうまくいかない6つの原因
SPIで時間が足りなくなる背景には、単なる“スピード不足”だけでなく、いくつかの共通する原因があります。問題の難易度に関係なく、これらの要素が重なったときに「焦り」「判断ミス」「タイムロス」といった連鎖が起こりやすくなります。この章では、時間配分がうまくいかない6つの代表的な原因について、具体的に解説します。
1. 問題形式に慣れていない
SPIの出題形式は、学校のテストや一般的な就職試験とは異なります。「四則計算」や「図表読み取り」、「語句の用法」など、一見簡単そうに見える問題でも、設問の聞き方や構成に独特の癖があるのが特徴です。
たとえば、ベン図を使う集合問題や、並べ替え問題、長文の空欄補充などは、出題パターンに慣れていないと、どこに注目すべきかがわからず、無駄に時間を費やしてしまいます。これらは反復練習を通して、形式に慣れることでしか対応できません。
2. 難問に固執してしまう
SPIは「できる問題から確実に解いていく」のが基本戦略ですが、真面目な人ほど1問ずつ丁寧に解こうとして、難問にハマってしまいがちです。「ここまで考えたからには解かないと損だ」「あと少しで解けそう」と粘ってしまうことで、全体の時間配分を崩す結果になります。
特に非言語分野では、数分悩んでも結論が出ない問題も多いため、こうした“粘り癖”は致命的です。問題に固執せず、適切な見切りをつける判断力もSPI攻略には欠かせません。
3. 時間計測しながら練習していない
自宅で問題集を解くときに「時間を測らずに」ゆっくり解いてしまう人は、試験本番で時間配分の感覚がつかめず、結果としてペースを見誤ってしまう傾向があります。
「1問あたり○○秒で解く」「10問で○分以内」といった具体的な時間目安を持ちながら練習していないと、知らぬ間に1問に1分以上使ってしまい、気づいたときには残り時間が足りなくなっています。
4. 基本の解法を暗記していない
SPIでは、似たような出題パターンが繰り返し出題される傾向があります。そのため、「このパターンはこう解く」という基本的な解法を頭に入れておくことが大切です。
たとえば、「仕事算」や「割合」「速さと時間」の公式を瞬時に使えるかどうかで、非言語の処理スピードは大きく変わります。いちいち公式を思い出していては、時間がいくらあっても足りません。繰り返し練習して、手が勝手に動くようになるまで反復しましょう。
5. 計算力・読解力の不足
非言語分野では計算スピードが、言語分野では読解スピードが試されます。つまり、SPIでは“処理スピード”がそのまま点数に直結するのです。
簡単な計算でもミスが多かったり、読み違いが起きたりすると、何度も問題を見直すことになり、結果的に時間をロスしてしまいます。演習を繰り返す中で、自然と計算と読解のスピードを高めていくトレーニングが必要です。
6. 試験形式(Web/テストセンターなど)を理解していない
SPIの受験形式によって、問題の表示方法や操作感は大きく異なります。テストセンターならスクロール操作が必要だったり、Webテスティングでは残り時間が表示されないケースもあります。
このような細かい環境要素に不慣れだと、画面操作に手間取ったり、時間配分の見通しが立てられなかったりと、想定外のミスにつながることがあります。試験形式を事前に把握し、それに合わせた演習を行っておくことが、スムーズな対応につながります。
以上のような原因を理解し、自分がどこで時間をロスしているのかを冷静に分析することが、SPI対策の第一歩です。次の章では、具体的な事前対策について紹介していきます。
【準備編】時間切れを防ぐ事前対策
SPIで時間が足りないと感じている人の多くは、「時間の使い方」そのものに慣れていないことが原因です。時間配分の感覚は、受験前に意識的にトレーニングしておかないと身につきません。ここでは、本番で焦らず時間内に解き切るための「事前準備」のポイントを解説します。
苦手分野を見極めて重点対策
SPIでは「言語」「非言語」の2つの分野に分かれていますが、どちらに時間を使いがちかは人によって異なります。たとえば、文系出身者は非言語で時間がかかる傾向があり、理系出身者は言語で足を引っ張られるケースが目立ちます。
まずは模試や問題演習を通じて、「自分がどちらの分野に時間を使ってしまっているか」を客観的に分析しましょう。苦手な分野がわかれば、そこを集中的に演習してスピードアップを図ることができます。特に、長文読解や複雑な非言語問題は時間を消費しやすいため、反復練習で解法パターンを体に染み込ませておくことが重要です。
模試形式で時間を計測して解く
「本番で緊張してうまくいかない」という人の多くは、時間を測っての演習が足りていません。制限時間がある試験では、「時間があるとき」と「時間がないとき」で思考のスピードや選択の基準が大きく変わります。
そのため、模試形式で制限時間を設けて問題を解くことを習慣にしましょう。特におすすめなのは、1回30分〜40分のセットを決めて、その中で何問正確に解けるかを記録していく方法です。最初は全問解けないかもしれませんが、回数を重ねることで、自然とスピード感が身につきます。
また、1問ごとにストップウォッチを使って「どの問題に何秒かかったか」を記録することで、自分の中で時間感覚を可視化できるようになり、改善点も明確になります。
【本番編】試験中に焦ったときの対処法
いくら準備をしても、本番で焦ってしまっては意味がありません。SPIの試験では、焦りによる判断ミスや、想定外の出題による動揺が得点を下げる原因になることもあります。この章では、本番中に「時間が足りないかも」と感じたときの、実践的な対処法をご紹介します。
解けない問題は即スキップ
本番で一番やってはいけないのは、難問に時間をかけすぎることです。「時間をかければ解けそう」でも、そこで立ち止まっている間に、後半の簡単な問題を解く時間がなくなってしまっては本末転倒です。
迷ったら即スキップ。「これは一度飛ばそう」と自分の中で決める基準を持つことで、全体のリズムが崩れるのを防げます。SPIは全問正解を目指す試験ではなく、「いかに正答を積み上げるか」が評価される試験です。得点を稼ぎやすい問題に時間を割くという視点で挑みましょう。
時間をブロックごとに区切る
試験全体を「35分間」とだけ意識するのではなく、「10問を8分」「5問を4分」というように、小さなブロックに区切って時間を管理することも非常に効果的です。
こうすることで、ペースが遅れているかどうかが途中で把握でき、調整がしやすくなります。たとえば、10問を8分で解く予定が10分かかってしまったなら、「次のブロックは少し早めに進めよう」と意識的に修正が可能です。
時間を見ながら自己管理をする意識を持つことで、全体の時間配分が安定し、結果として焦りも軽減されます。
SPI時間不足への対策本・アプリ紹介
時間対策を意識するなら、使う教材も“時間配分に強い”ものを選ぶことが大切です。ここでは、SPIのスピード対策に特化したおすすめの書籍やアプリを紹介します。
『これが本当のSPI3だ!』
SPI対策書の定番。実際の出題傾向を反映した模試形式の問題が収録されており、本番さながらの練習ができます。タイマーを使って模試に取り組めば、自然と時間感覚が鍛えられる1冊です。
難問にも対応しているため、すでに基本問題に慣れてきた方にもおすすめです。巻末には時間配分のコツや本番直前のチェックポイントも掲載されており、実践的な対策が可能です。
『スピード攻略Webテスト』
限られた時間で高得点を取るためのコツが詰まった、スピード重視の問題集です。「短時間で解くためには何を省略し、どこを見ればよいか」という視点で解説されており、時間内処理力を徹底的に鍛えることができます。
忙しい社会人の方が短期間で結果を出すためにも非常に使いやすく、短期間で点数を伸ばしたい人にとって心強い一冊です。
SPI模試アプリ(らくらく就活SPI対策アプリなど)
スマホで手軽に模試ができるアプリは、通勤時間やちょっとした隙間時間に活用できる点が魅力です。特に「らくらく就活のSPI対策アプリ」は、制限時間付きで各ジャンルの問題演習ができ、自然と時間感覚を鍛えられる仕様になっています。
紙の教材だけでなく、アプリを併用することで学習の幅が広がります。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
まとめ
SPIで「時間が足りない」と感じるのは、決してあなたの能力が低いからではありません。SPIそのものが、出題数に対して制限時間が厳しい構成になっているため、時間配分の対策なしでは誰でも苦戦してしまうのです。
本記事では、時間が足りなくなる原因を明らかにし、形式別の時間シミュレーション、失敗した転職者の体験談、時間配分が崩れる理由、そして準備・本番での具体的な工夫までを紹介してきました。
大切なのは、「時間切れを防ぐための戦略を持って本番に挑む」ことです。
- 自分の現状を診断チャートで把握する
- 模試形式で時間感覚を身につける
- 問題の取捨選択をする判断力を養う
- 焦らず進めるブロック管理を習慣化する
これらを意識することで、SPI本番でも余裕を持って取り組むことができ、スコアアップにつながります。
今からでも遅くありません。今日から、時間を意識したSPI対策を始めて、余裕を持って選考を突破できる力を身につけていきましょう。転職成功の第一歩は、SPIを制することから始まります。