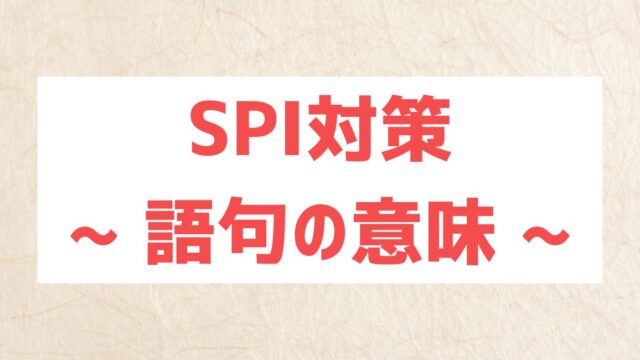【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「SPIが全然できなかった…」「手応えゼロで絶対落ちた気がする」──転職活動中にSPIを受けた人なら、一度はそんな不安に襲われるのではないでしょうか。特に転職では新卒就活と違い、SPIに慣れていないまま挑戦する人も多いため、試験後に自信を持てないケースは珍しくありません。
しかし、結論から言えば「SPIができなかった=即不合格」というわけではありません。実際に、SPIで失敗したと感じたのに通過できた人もいれば、逆にSPIはある程度できたのに不合格になった人もいます。その差を生むのは、企業がどのようにSPIを評価しているのか、またほかの選考要素との兼ね合いです。
本記事では、「SPIが全然できなかった」と感じたときに知っておきたいポイントを徹底解説します。まずはSPIの役割と企業ごとの評価のされ方を整理し、次に「落ちたかも?」を判定できる診断チャートを用意しました。さらに、実際にSPIで失敗した人の体験談や、次に取るべき行動、短期間でできる逆転対策も紹介します。
読んでいただければ、SPIの結果に一喜一憂する必要がないこと、そして今からでも十分に軌道修正できることが分かるはずです。転職活動での不安を少しでも軽くし、次のチャンスをつかむためのヒントを一緒に見ていきましょう。
目次
SPIが全然できなかった…それでも転職は通過できる?
転職活動においてSPIは多くの企業で利用されている適性検査です。そのため、受験後に「全然できなかった」と感じると、不安が一気に押し寄せてくるものです。しかし実際には、SPIの点数だけで合否が決まるわけではありません。
企業はSPIを「応募者の基礎学力や思考力を測る指標」として利用しているにすぎず、それがすべての判断材料になることは少ないのです。むしろ、多くの企業では書類選考や面接の評価と組み合わせ、総合的に判断しています。
SPI試験で手応えゼロだった時の不安
試験中に「時間が足りなかった」「計算問題が解けなかった」「そもそも問題文の意味が分からなかった」などの経験をすると、多くの人は「不合格確定だ」と感じてしまいます。特に新卒時と違って転職活動では、試験慣れしていないため余計に失敗感が強く残りやすいのです。
ただし、SPIは相対評価ではなく「一定の基準点を満たしているか」を確認するケースが多いため、全問正解を求められているわけではありません。仮に半分近くできなかったとしても、他の要素で評価が高ければ通過できる可能性は十分あります。
本当に落ちるのか?他にも評価される要素は?
SPIはあくまで「応募者の適性を知るための補助的ツール」であり、それ自体が採用の最終決定要因になるわけではありません。特に転職の場合は、実務経験やスキル、人柄、面接での受け答えなどの方が重視される傾向があります。
例えば、営業職や専門職では「即戦力としての経験」がSPI以上に評価されるため、試験で多少失敗しても内定につながるケースは珍しくありません。逆に金融や大手商社のように基礎学力を重視する業界では、SPIの比重が高く、点数がそのまま合否に直結することもあります。
本記事では、落ちたリスクの見分け方・次にすべきこと・対策法までを網羅
この記事では「SPIが全然できなかった」と感じた後の不安を整理し、次の行動につなげられるように以下の内容を解説していきます。
- SPIが全然できなかった=即不合格ではない理由
- 簡単に自己判定できる合否リスク診断チャート
- 実際に「SPIで失敗したけど通過した/落ちた」体験談
- 今からできる逆転対策と、SPIにこだわらない転職戦略
この記事を読み終える頃には、試験後のモヤモヤが整理され、不安を希望に変えて次の一歩を踏み出せるはずです。
SPIが全然できなかった=即不合格とは限らない理由
SPIを受けて「全然できなかった」と感じた瞬間、多くの人は「もう落ちたに違いない」と思い込みます。しかし実際には、SPIが不出来だったからといって即座に不合格となるわけではありません。転職活動におけるSPIは、あくまで評価材料のひとつに過ぎず、その点数が最終合否を決める絶対条件ではないのです。ここでは、その背景と理由を詳しく見ていきましょう。
SPIの役割と評価ポイント
SPIは、応募者の基礎的な学力や論理的思考力を測るためのツールです。言語や非言語の問題を通じて「業務を遂行するうえで必要な最低限の能力があるか」を確認することが主な目的となります。
ただし、SPIはあくまで「万能な試験」ではありません。試験だけでは測れない能力や強みは数多く存在します。たとえば営業力、リーダーシップ、専門スキル、社内文化との相性などはSPIでは判断できない領域です。そのため企業は、SPIの結果だけに依存せず、書類や面接を含めた総合評価を重視しているのです。
書類選考・面接との総合評価で判断される
転職活動における採用プロセスは、新卒採用に比べて「即戦力性」を重視する傾向があります。つまり、SPIが多少振るわなくても、職務経歴書に明確な成果や実績が記載されていれば評価される可能性が高いのです。
また、面接においては「人柄」「コミュニケーション力」「志望動機」などが見られます。たとえSPIで失敗しても、面接で好印象を残すことができれば十分に逆転が可能です。実際に「SPIはボロボロだったのに、面接での評価が高くて通過した」という声も少なくありません。
企業によってSPIの比重が異なる
SPIの位置づけは業界や企業ごとに大きく異なります。
- 金融・大手商社:応募者数が非常に多いため、SPIを足切り基準として厳格に用いる傾向があります。この場合は低得点が致命的になりやすいです。
- メーカー・インフラ:一定の基準点は求められますが、面接や経験との総合判断で評価されることが多いです。
- IT・ベンチャー・人材系:人物面やカルチャーフィットを重視するため、SPIはあくまで参考程度。得点が低くても他の評価軸で十分に巻き返せます。
このように、どの業界を受けているかによってSPIの影響度は変わります。したがって「SPIができなかった=絶対に落ちる」と短絡的に結論づけるのは誤りであり、企業ごとの特性を見極めることが重要です。
SPIで落ちるケースと落ちないケースの違い
SPIの結果が大きく響くケースは「応募者数が非常に多く、ふるい落としが必要な企業」です。例えば大手金融や商社は数千人単位の応募があるため、基礎学力試験を効率的なスクリーニングに使います。一方で、ベンチャーや専門性の高い職種では「この人のスキルは他に代えがたい」と判断されれば、SPIの出来はほとんど問題になりません。
この違いを知ることができれば、自分のSPIの結果に過剰に落ち込まず、次のアクションに集中できます。
SPIで落ちた?5問でわかる合否リスク判定
SPIを受け終えたあとに「全然できなかった」と感じても、実際に合否がどうなるかはすぐには分かりません。企業によって基準も異なるため、不安に感じて当然です。そこで、ここでは自分の置かれた状況を客観的に整理できるよう、簡易的な診断チャートを用意しました。Yes/No形式で答えていくことで、自分が「合格ラインに近いのか」「落ちている可能性が高いのか」を把握することができます。
Yes/No形式の5つの質問と意図
- 試験時間内にすべての問題に回答できたか?
→ 完答できなくても合格することはありますが、大問を丸ごと飛ばしてしまった場合、基準点を下回るリスクが高まります。 - 苦手分野が極端に多く、ほとんど手を付けられなかったジャンルはあったか?
→ 特定分野が壊滅状態だと全体の得点バランスが崩れ、基準点を割り込む可能性が出てきます。 - 職務経歴や書類で強くアピールできる実績があるか?
→ SPIが低くても、即戦力としての経験や成果があれば企業は合否判断を柔軟にしてくれる場合があります。 - 面接やこれまでの選考で手応えを感じられたか?
→ 面接評価が高ければSPIが多少悪くてもカバーできることがあります。逆に面接で弱さを感じているならSPIの失敗が致命的になりやすいです。 - 志望している企業は「SPIを重視する業界」に属しているか?
→ 金融や商社のようにSPIを足切り基準に使う業界なら、影響度は大きくなります。一方でベンチャーや人材系では参考程度に留まる傾向があります。
判定結果と具体的アドバイス
- リスク高(不合格の可能性が大きい)
質問1・2がNoで、さらに質問5がYesの場合。つまり「時間切れや未回答が多い」「苦手分野で失点が大きい」「SPI重視業界を受けている」人は危険ゾーンにいます。この場合は結果に期待するよりも、次回に備えて対策をやり直すことを優先しましょう。短期集中での復習や、SPIを課さない企業への応募を検討すると安心です。 - リスク中(五分五分の状態)
質問1・2のどちらかはYesで、かつ質問3や4にある程度自信がある場合。つまり「SPIで部分的にはできたが不安が残る」「ただし書類や面接では強みを出せている」というケースです。この場合は合否の可能性が半々なので、期待しすぎず準備を継続しましょう。面接や次の応募に備えることで、どちらの結果でも前に進めます。 - リスク低(合格の可能性が十分ある)
質問3や4がYesで、かつ質問5がNoの場合。SPIが多少できなくても、応募先企業がSPIを重視しない業界であれば大きな問題になりません。この場合はむしろ面接や職務経歴でのアピールに集中し、次のステップに備えるべきです。
診断チャートを使うメリット
このチャートを使うと、単に「SPIができなかったから落ちたかもしれない」と感情的に不安になるのではなく、自分の状況を構造的に整理できます。不安を漠然と抱えるのではなく「どこにリスクがあり、どこで補えるのか」を把握できるため、次の行動が具体的に見えてくるはずです。
SPIが全然できなかったけど通過した/落ちたリアルな声
SPIを受け終わったあと、「もう全然できなかった…」と感じた人の声は少なくありません。しかし実際には、その後の結果は人によって大きく分かれます。ここでは、通過できたケースと落ちてしまったケースを具体的に紹介し、どんな要素が合否を分けたのかを解説します。
通過したケース
ケース1:IT営業職で半分白紙回答、それでも一次通過
30代前半で営業経験豊富なAさんは、転職活動の一環でSPIを受けました。しかし数的処理が苦手で時間配分に失敗し、非言語の半分以上を白紙のまま提出。「絶対落ちた」と落ち込みましたが、一次選考は無事に通過。理由を後から人事に聞くと「営業実績の数字と面接でのコミュニケーション力を重視した」とのことでした。SPIの出来よりも、即戦力として成果を出せるかどうかが評価されたのです。
ケース2:ベンチャー企業志望、図表問題が壊滅的だったが内定獲得
20代後半のBさんは、ベンチャー企業の企画職に応募。SPIでは表やグラフの読み取り問題がほとんど解けず、「終了後に手が震えるほど不安だった」といいます。しかし、結果的に最終面接まで進み、内定を獲得。Bさんの場合、前職での新規事業立ち上げ経験が高く評価され、SPIは「一応受けてもらったが重視していない」と説明されたそうです。
これらのケースから分かるように、SPIが全くできなくても「経験」「人柄」「スキル」が評価されることで通過できる可能性は十分にあります。
落ちたケース
ケース1:大手金融機関で数的処理に失敗し、不合格
金融業界に転職を希望していたCさんは、SPIの数的処理で計算に時間がかかり、問題の半分しか解けませんでした。結果は書類通過後すぐの不合格通知。後に調べてみると、その企業は「SPIを足切り基準としている」との情報が多く、自分の失敗が直接的な原因だったと理解したそうです。金融業界は応募者数が多いため、効率的に選考を進める目的でSPIの点数を厳しく見ていたのです。
ケース2:大手商社、言語問題の未回答が多く不合格
総合商社を受験したDさんは、非言語はそこそこ解けたものの、言語分野で文章題に時間を取られ、最後の10問ほどを空欄のまま提出。その結果、書類は高評価だったにもかかわらず、一次面接に進む前に落ちてしまいました。大手商社は応募者数が桁違いに多いため、SPIでの「一定以上の得点」が一次選考の条件になっていたと考えられます。
体験談からわかること
これらのリアルな声から見えてくるのは、「SPIの影響度は業界や企業によって大きく違う」という事実です。
- SPIを軽視する企業:ベンチャー、IT、人材系 → 経験や人柄で逆転可能
- SPIを重視する企業:金融、商社、大手メーカー → 失敗が致命的になりやすい
つまり、「SPIで失敗=即不合格」ではなく、「どの業界・企業を受けているか」で結果は大きく変わるのです。不安を感じたら、自分の応募先がどちらのタイプに属しているかを調べ、今後の戦略を考えることが重要です。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPIで落ちたかも…次にやるべき行動とは?
SPIを受けたあとに「全然できなかった」「落ちたかもしれない」と感じる瞬間は、誰にでもあります。特に転職活動では1社ごとの機会が貴重なため、余計に不安が募るものです。しかし大切なのは、その不安に飲み込まれるのではなく、次に取るべき行動を明確にすることです。行動を起こすことで気持ちも前向きになり、次のチャンスを確実にものにできるようになります。
再挑戦するための5つのステップ
1. SPI不要の企業にエントリーする
すべての企業がSPIを課しているわけではありません。特にベンチャー企業やスタートアップ、外資系の一部企業は筆記試験を行わず、面接や職務経歴で判断するケースが多いです。「SPIが苦手」というだけで選択肢を狭めるのはもったいないため、まずはSPI不要の求人に応募し、自信を取り戻す機会を作りましょう。
2. 書類選考の精度を高める
SPIの不安を補うには、書類でのアピールを強化するのが効果的です。職務経歴書には「数字で表せる成果」を盛り込みましょう。たとえば「売上前年比120%達成」「新規顧客を半年で30件獲得」といった具体的な実績は、SPIの点数以上に強い説得力を持ちます。
3. 面接準備を強化する
SPIが不安でも、面接で逆転できるケースは多くあります。面接では「企業が求める人物像に自分がどう当てはまるか」を伝えることが大切です。過去の成果をエピソードで語る練習や、よくある質問に対する回答を整理しておくと、SPIのマイナスを十分に補えるでしょう。
4. SPI対策を短期集中でやり直す
次の応募で同じ不安を抱えないために、SPIの苦手分野を短期間で克服するのも有効です。すべての範囲を完璧にする必要はなく、頻出ジャンル(表やグラフの読み取り、推論、語句の用法など)に絞って対策するのがおすすめです。模試形式で時間を測りながら解く習慣をつければ、「時間切れ」のリスクを減らすことができます。
5. 応募企業を分散させる
SPIを重視する企業とそうでない企業を並行して受けることも大切です。金融や商社を本命にするなら、同時にITやベンチャーにも応募することで精神的な安心感が得られます。「この1社しかない」と思うとSPIの失敗が重くのしかかりますが、複数の選択肢を持っていれば気持ちも前向きに切り替えやすくなります。
行動に移すことが大切
不安を感じている間にも、転職市場は常に動いています。内定を出すスピードが速い企業も多いため、行動が遅れるほどチャンスを逃す可能性が高まります。「落ちたかも」と思った時点で、すぐに次の応募や対策に移ることが、結果的に最短で内定を得るための近道になります。
不安を抱えたまま立ち止まるのではなく、「いま自分にできること」を一つひとつ積み重ねることが、SPIの不安を超えて転職を成功させるカギとなります。
SPIが全然できなかった原因と対策法
SPIを受けたあと「全然できなかった」と感じる背景には、いくつか典型的な原因があります。これを理解せずに次へ進むと、同じ失敗を繰り返してしまう可能性が高いです。逆に言えば、原因を正しく分析すれば効果的な対策を立てられ、短期間で成績を改善することも可能です。
原因1:時間切れで最後まで解けなかった
SPIで最も多い失敗の一つが「時間切れ」です。特に非言語問題では1問に時間をかけすぎてしまい、残りの問題をほとんど解けずに終了するケースがよくあります。問題を解く順番を意識せずに挑むと、「序盤で詰まる → 焦ってケアレスミス → 全体的に解答数が少ない」という悪循環に陥ってしまいます。
対策:まずは「解ける問題を先に拾う」戦略を身につけることが大切です。模試形式で時間を測り、1問あたりにかける上限時間を意識する練習をしましょう。また、公式アプリや模擬試験を使い、時間配分の感覚を体に染み込ませるのが効果的です。
原因2:苦手分野に偏りがあった
「確率や推論が苦手」「長文読解が極端に遅い」など、特定分野に偏った苦手を抱えている人も多いです。SPIは幅広い分野から出題されるため、一つのジャンルで大きく失点すると全体の得点が大きく下がってしまいます。
対策:苦手分野をすべて克服しようとするのではなく、「頻出で簡単な分野を得点源にする」「苦手分野は最低限の基礎だけ抑える」とメリハリをつけることが重要です。例えば、表やグラフの読み取り問題は比較的得点しやすいため、まずは確実に取れるようにしておきましょう。
原因3:出題形式に慣れていなかった
SPIは独特の出題形式を持つため、初めて受けると「問題文の読み方自体が分からない」「解答パターンが分からない」という状態に陥りやすいです。理解できたとしても、解答手順に慣れていないため時間がかかり、結果的に解ける問題数が減ってしまいます。
対策:最初のうちは問題集やアプリで「解法パターンの暗記」を優先しましょう。SPIは出題形式がある程度固定されているため、パターンを理解しておくだけで解答スピードが格段に上がります。
原因4:緊張や焦りによるケアレスミス
「本番特有の緊張」で、普段なら解ける問題を間違えるケースも多くあります。特に転職のSPIは久しぶりに試験を受ける人が多いため、「試験慣れしていない」という心理的な要因も大きな原因の一つです。
対策:模試形式で何度も練習して「試験環境に慣れる」ことが最も有効です。特に自宅で時間を測りながら解く習慣をつけると、当日の焦りを軽減できます。また、計算問題では「検算の習慣」を持つだけでも大幅にケアレスミスを防げます。
優先して復習すべきジャンル
SPIを効率的に攻略するには、「頻出かつ得点しやすいジャンル」を優先するのが鉄則です。
- 頻出×簡単:表やグラフの読み取り、語句の用法
- 頻出×難:推論、確率
- レア×難:図形、特殊な数列
まずは「頻出×簡単」の分野を確実に得点できるようにし、その後「頻出×難」を部分的に克服するのが最も効率的です。
SPI対策に使える無料アプリ・模試
効率よく対策するためには、スキマ時間を活用できる学習ツールが有効です。弊社の「らくらく就活SPIアプリ」にはジャンル別の練習や模試モードが搭載されており、通勤時間や休憩中でも実戦感覚を磨けます。また、Web模試サービスを使えば本番同様の時間配分を体験でき、弱点を明確にできます。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPIにこだわらない転職戦略も視野に入れよう
SPIで失敗したかもしれない、あるいは「どうしてもSPIが苦手で不安」という人もいるでしょう。ですが、転職活動においてSPIはあくまで手段のひとつであり、それがすべてではありません。現実にはSPIを課さない企業や、SPI以外の基準で採用を決める企業も多く存在します。選択肢を広げて考えることで、転職の可能性を大きく広げることができます。
SPI非実施の企業を狙う方法
特にベンチャー企業や成長中のスタートアップは、SPIを導入していないケースが多いです。彼らはスピード感のある採用を重視し、人物やポテンシャルを面接で見極めることが中心です。SPIで苦戦した人にとっては、むしろ自分の強みを直接伝えやすい場になります。
外資系企業もSPIを課さない場合が多く、代わりに英語力や実績が評価対象になります。つまり、SPIに縛られず「自分のスキルや経験をアピールできる企業」を選ぶことが戦略の一つになるのです。
転職エージェントを活用して非公開求人を探す
転職エージェントを通じて求人を探すと、SPIを課さない非公開求人に出会える可能性が高まります。一般には出回らないポジションや、独自の選考フローを採用している企業も多いため、SPIの有無を事前に確認して応募先を選ぶことができます。
さらにエージェントは「この企業はSPIを重視しない」「人物重視で選考している」といった内部情報を把握していることもあります。そうした情報を活かすことで、無駄に不安を抱えず、自分に合った企業を効率的に受けることができるでしょう。
自分の強みを軸に戦略を立てる
SPIで結果を出せなくても、職務経験や実績を強みにすれば転職は十分に成功できます。たとえば、営業職であれば「売上実績」や「新規開拓数」、企画職であれば「提案が採用された経験」や「プロジェクト推進力」など、SPIでは測れない価値を提示するのです。
SPIが苦手な人ほど、自分の強みを再整理して「SPI以外で勝負できる武器は何か」を明確にしておくべきです。これが明確であれば、SPIにこだわらない企業を選んだ際に圧倒的な説得力を持たせられます。
柔軟な戦略がキャリアの可能性を広げる
「SPIを克服して次に挑戦する」という選択も正しいですが、「SPIを避けて戦いやすいフィールドを選ぶ」という選択もまた合理的です。転職活動は長期戦になりがちだからこそ、得意な土俵で勝負できる環境を探すのも立派な戦略です。
視野を広げれば、SPIにこだわらずとも自分に合った企業は必ず見つかります。苦手を無理に克服するだけでなく、自分が最大限評価される環境を見極めることが、キャリア成功の近道になるのです。
まとめ:SPIが全然できなくても逆転の道はある
SPIを受けたあとに「全然できなかった」と感じると、多くの人が不安に駆られます。しかし、ここまで解説してきた通り、SPIの出来がそのまま合否に直結するわけではありません。
企業によってSPIの重視度は大きく異なり、特に転職では「実務経験」「スキル」「人物面」がより強く評価される傾向にあります。たとえSPIで失敗したと感じても、他の要素で挽回できる可能性は十分に残されています。
本記事では以下のポイントを整理しました。
- SPIが全然できなかった=即不合格ではないこと
- 業界によってSPIの重視度は大きく異なること
- 簡易診断チャートで合否リスクを把握できること
- 「通過した/落ちた」体験談から見えてくる現実
- 落ちたかもと思ったときに取るべき行動ステップ
- 効率的な対策法と無料で使える学習ツール
- SPIにこだわらない柔軟な転職戦略もあること
大切なのは、SPIの手応えに一喜一憂するのではなく、「次にどう動くか」を具体的に考えることです。診断やチェックリストを活用して現状を冷静に整理し、必要なら対策を強化し、場合によってはSPI不要の企業を狙うといった柔軟な戦略を取ることも検討しましょう。
不安を希望に変える一歩は、行動からしか生まれません。SPIでつまずいたとしても、それをきっかけに自分のキャリアをより広く見直し、新しい可能性を切り開いていくことができるはずです。