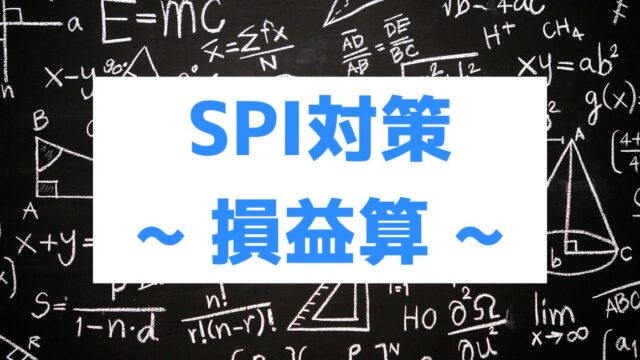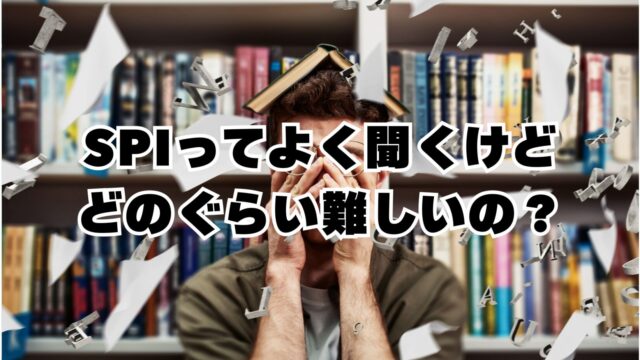【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「SPIって新卒のものじゃないの?」
「転職活動でSPIがあると聞いて焦っている…」
そんな声をよく耳にします。たしかに、SPI(Synthetic Personality Inventory)はもともと新卒採用でよく使われている適性検査の一つです。しかし、近年では中途採用の場でもSPIを実施する企業が増えてきました。
転職者にとっては、「職務経歴で評価されるのでは?」という考えがある一方で、実際にはSPIの結果が選考通過に大きく影響することもあります。書類や面接と違って、SPIには明確な“点数”の基準があり、特に大手企業や官公庁系の選考では一定のスコアに達していないと面接に進めないことも珍しくありません。
この記事では、転職時にSPIがどれほど重要なのかを解説していきます。なぜSPIが課されるのか、どんな能力が見られているのか、いつ・どのタイミングで実施されるのか、そしてどうすれば通過率を上げられるのか。
業種×職種別のSPI重視度マップや、実際に転職時にSPIに悩んだ人の体験談、学習レベル別の対策ルートなど、具体的かつ実践的な情報を豊富に盛り込んでいます。
この記事を読み終えるころには、「自分にとってSPIは重要なのか」「どのように対策すればいいのか」が明確になり、不安が解消されるはずです。それではさっそく見ていきましょう。
目次
転職でSPIが課される背景とは?
転職活動においてSPIがなぜ導入されるのか、その背景を理解することで、企業がSPIに求めている本質的な意図や、合格のために意識すべきポイントが見えてきます。
中途でもSPIが実施される理由
中途採用でSPIが課されるようになった背景には、企業側の「採用のミスマッチを防ぎたい」という思いがあります。
中途採用では、書類や面接を通じてこれまでの経験やスキルが評価されることが一般的です。しかし、実務経験だけでは測りきれない“地頭力”や“適性”も、入社後のパフォーマンスを左右する重要な要素となります。
たとえば、営業職であれば数字に強いか、論理的思考ができるかといった点が重要になりますし、事務系職種であれば正確性や処理スピードなどが求められます。SPIでは、こうした基本的な能力を可視化することができるため、経験やスキルだけでは判断が難しい求職者の“適性”を客観的に測るツールとして重宝されているのです。
さらに、SPIは性格検査も含まれており、企業文化との相性やストレス耐性、協調性など、職場にうまく馴染めるかどうかといった側面も見られています。
つまり、中途採用でもSPIが実施されるのは、入社後のミスマッチを防ぎ、長く活躍できる人材かどうかを見極めるためだと言えるでしょう。
SPIによって測られる能力と評価ポイント
SPIには大きく分けて「能力検査」と「性格検査」があり、能力検査はさらに「言語分野」と「非言語分野」に分類されます。
言語分野では、語彙力や文章理解力、文法的な正しさなどが問われ、非言語分野では、計算力・論理的思考・データ処理能力などが評価されます。いずれも、日々の業務に直結する基礎的なスキルを測るものであり、どの職種であっても一定の水準は求められがちです。
企業側が重視しているのは、単に正解数が多いかどうかだけではありません。「限られた時間内でどれだけ正確に問題を処理できるか」「問題の意図を素早く読み取れるか」といった、スピードと正確さのバランスも見られています。
また、性格検査では「素直に答える」「自分を良く見せようとしすぎない」「一貫性のある回答を心がける」ことが評価のポイントになります。ここで極端な回答や矛盾の多い回答があると、「ストレス耐性が低いのでは?」「実際とは違う自分を装っているのでは?」と見なされてしまうリスクもあります。
このように、SPIはただの「学力テスト」ではなく、企業が求める人物像に合致しているかを多角的に見るための検査なのです。
【業界別・職種別】転職活動におけるSPIの重要度の違い
SPIが転職活動でどの程度重要視されるかは、業種や職種によって大きく異なります。すべての企業がSPIを導入しているわけではありませんし、導入していても重視の度合いにはバラつきがあります。ここでは、業種×職種の視点からSPIの“重視度”を分類したマッピングチャートをもとに、どのようなケースでSPI対策が特に重要になるのかを解説していきます。
どの企業がSPIを重視する?一目でわかる分類表
以下は、SPIの重視度を「高・中・低」で分類したオリジナルのマッピング表です。一般職・総合職・専門職の3区分と、企業のタイプ(大手・中小・官公庁)によって傾向を可視化しています。
| 企業タイプ/職種 | 一般職 | 総合職 | 専門職 |
| 大手(メーカー等) | 中 | 高 | 中 |
| 中小(ITベンチャー等) | 低 | 中 | 低 |
| 官公庁・公的機関 | 高 | 高 | 高 |
このチャートからもわかる通り、大手企業や官公庁、特に総合職においてSPIが重視される傾向が強いです。
まず、大手メーカーやインフラ系企業などでは、応募者数が非常に多いため、最初のふるい落としとしてSPIを利用するケースが一般的です。特に総合職では、将来的にマネジメント層への登用を見据えているため、基礎能力や地頭の良さを重視しやすく、SPIのスコアが足切りの基準となることも珍しくありません。
一方、中小企業やベンチャー企業では、SPIの実施率はそれほど高くありません。選考においては、スキルやカルチャーフィットを重視する傾向があり、SPIを課さないことも多くなっています。ただし、総合職など将来性を評価するポジションでは、導入例がじわじわと増えています。
また、官公庁や公的機関ではSPIが重要な判断材料とされることが多く、ほぼすべての職種で高い重視度となっています。これは、公平性や透明性を担保する選考方式としてSPIが有効に機能するからです。特に市役所や独立行政法人などの中途採用では、SPIのスコアが一定以上でなければ面接に進めないケースもあります。
このように、業種や職種によってSPIの重視度は変わるため、自分の志望先がどの分類に該当するのかを事前に見極めておくことが、効率的な対策につながります。
中途採用の選考におけるSPIの実施タイミング
SPIが選考のどの段階で行われるかによって、その“意味”や“重み”が異なります。転職活動の流れは企業によってさまざまですが、SPIの実施タイミングによって、その目的や意図を読み取ることができます。
面接前にSPIがある場合の意味
書類選考のあと、一次面接の前にSPIが課されるケースは、大手企業や官公庁で特に多く見られます。このタイミングで実施されるSPIには、「ふるい落とし」の意味合いが強く、一定の基準を満たさない応募者は次のステップに進むことができません。
この段階でSPIが登場するということは、SPIが明確な選考基準の一つになっていることを意味します。つまり、いくら職務経歴やスキルが優れていても、SPIの結果が基準に達していなければ、その時点で不採用になるリスクが高まります。
また、SPIのスコアが企業内でどのように評価されているかは明かされることが少ないものの、平均点に満たない場合や、性格検査で一貫性のない回答をしてしまった場合には、不利になるのは間違いありません。
特に注意したいのが、Webテスト形式で実施される場合。自宅受検だとしても、企業は受験環境やスコアに一定のモニタリングを行っており、不自然な高得点や操作ミスがあると、選考に影響を与えることがあります。
SPIが面接前にあるということは、**“SPIが通過できなければ、面接で魅力を伝える機会すら得られない”**という状況です。受ける企業がこの形式の場合は、対策の優先順位を一段階上げる必要があります。
最終面接前・後にSPIがあるケースも
一方で、一次〜二次面接を通過したあとにSPIを課す企業もあります。これは比較的レアなパターンですが、採用に慎重な企業や、公的機関、インフラ系企業などで見られるケースです。
このような“後半でのSPI実施”は、「面接で感じた印象の裏付けをとる」目的や、「社内での最終判断材料とする」役割を持っています。
例えば、面接で評価が割れた場合にSPIの結果を参考にしたり、性格検査の内容がカルチャーフィットしているかどうかを最終確認することもあります。ここでSPIが極端に悪いと、「能力はあるけれど、組織になじまないのでは?」と懸念され、最終段階で不採用になるケースもあるのです。
さらに、内定後にSPIを実施する企業もごくまれに存在します。これは配属先を決める際の参考データとして利用されることが多く、選考通過自体には影響しないものの、性格検査の結果が職場とのミスマッチを起こすと、配属変更や再検討の対象になることもあります。
このように、SPIは選考の初期に登場するだけでなく、後半や内定直前にも出てくる可能性があるため、油断せずに備えておくことが大切です。
SPI通過のボーダーラインとその根拠
「SPIって何割取れれば通過できるの?」という疑問は、対策を始めるうえで多くの人が気になるポイントです。ここでは、SPIにおける合格の基準や企業が重視している点、そして実際に落ちてしまう人の特徴を詳しく見ていきましょう。
合格ラインは何割?5割・8割の違い
SPIには明確な合格点が公表されているわけではありません。しかし、複数の受験者や転職エージェントの報告をもとに、ある程度の“ボーダーライン”が見えてきます。
一般的に、最低でも5〜6割の正答率がないと通過は難しいと言われています。これは、SPIがあくまで足切りの役割を果たしているため、平均以下のスコアでは「最低限の基礎能力がない」と判断されるリスクが高いからです。
一方、人気企業や大手企業では、7〜8割以上の正答率が求められることもあります。特に、選考倍率が高い場合には、SPIの得点順に足切りされる傾向があるため、平均点では不十分です。
また、SPIは難易度に応じてスコア換算が行われるため、正答数だけでなく「どのレベルの問題まで解けたか」が結果に影響します。これは“順応式出題”と呼ばれ、正答が続くと難易度が上がり、より高得点が得られる仕組みです。
つまり、ただ正解数を増やすだけでなく、ミスを減らしつつ高難度の問題に挑める力が求められているということです。
SPIの形式によっても基準は異なりますが、以下は目安として意識しておきたいスコアラインです。
- 地方中小企業:5〜6割で通過可能性あり
- 中堅企業:6〜7割以上が安全ライン
- 大手企業・官公庁:8割以上が望ましい
特に、大手や官公庁では性格検査との組み合わせで足切りが行われるため、どちらも抜け目なく対策する必要があります。
SPIで落ちる人の特徴とは?
では、なぜSPIで不合格になってしまう人がいるのでしょうか。よくある落ちる人の特徴をいくつか紹介します。
まず多いのが、「SPIをなめて対策せずに受験する」パターンです。特に中途採用では、面接や職務経歴の方が重要だと考えてしまい、SPI対策を後回しにする人が少なくありません。しかし、実際にはSPIで足切りされてしまい、面接にすら進めないという事態が発生しています。
次に多いのが、「時間配分を間違える」ケースです。SPIは時間制限がシビアで、考えすぎて1問に時間をかけすぎると、最後までたどり着けず得点が伸びません。特に非言語分野では、計算に時間がかかる問題が多く、練習していないと本番で焦ってしまいます。
また、「性格検査での回答に一貫性がない」というのも、落選の原因となることがあります。性格検査では、似たような質問が形式を変えて何度も出てくるため、そのたびに矛盾した回答をすると「信用できない人物」「ストレス耐性が低い」と判断される可能性があります。
さらに、「見たことのない問題形式に対応できない」ことも問題です。SPIでは論理パズルやグラフの読み取りといった、学校では習わなかったタイプの問題も出題されます。これに対応するには、あらかじめ問題形式に慣れておくことが不可欠です。
こうしたリスクを避けるためにも、事前にしっかりとSPIの形式に慣れ、時間配分や回答の一貫性を意識した練習が重要です。
転職者のリアル体験談3選
実際にSPIで選考に影響を受けた転職者の声を知ることで、自分の対策に対する意識も大きく変わるはずです。ここでは、3人の体験談を通して、「どのような落とし穴があるのか」「どのように立て直したのか」など、リアルな失敗と成功のプロセスを紹介します。
Aさん(27歳・営業):「SPI対策せずに受けたら落選。悔しかったので模試を解いて再挑戦」
前職では個人営業をしていたAさんは、営業力に自信があり、転職活動でも書類と面接で勝負するつもりでした。実際に複数の書類選考は通過したものの、大手メーカーの選考でSPIを課され、まったく対策をせずに挑んでしまった結果、不合格に。
「面接に進めると思っていたのに、SPIで落ちるなんて…」とショックを受けたAさんは、その後SPIの重要性を痛感。模試形式の問題集やアプリで短期間集中対策を行い、次に受けた企業では無事SPIを通過して内定を獲得しました。
「ちゃんと準備していれば落ちずに済んだ。対策していない自分に悔しさを感じた」と話してくれました。
Bさん(30歳・エンジニア):「テストセンターで時間配分をミス。次は演習で慣れておくつもり」
Bさんは技術系の職種を目指していたため、SPIはあまり関係ないだろうと考えていました。しかし、応募先のIT企業ではテストセンターでSPIを受ける形式となっており、実際に受験してみると、計算問題に時間をかけすぎて最後の問題までたどり着けず、スコアが伸び悩む結果に。
「SPIの内容自体はそこまで難しくない。でも時間が本当に足りなかった」と振り返るBさんは、今後はタイムトライアル形式の演習を重視して対策するつもりだと語ります。
SPIにおいては“問題を解けるか”だけでなく、“時間内に解き切れるか”が問われることを実感した体験です。
Cさん(28歳・企画):「転職エージェントから『SPIで落ちた人が多い』と聞き、必死に対策しました」
Cさんは、志望企業がSPIを導入していることをエージェントとの面談で初めて知りました。エージェントからは「ここ最近、SPIで落ちる人が増えていてもったいない」と言われ、対策を勧められたそうです。
「新卒のときに受けた記憶があったけど、もう忘れていて…。最初は勘で解いていたけど、全然点が取れなかった」と話すCさんは、そこから参考書とアプリを併用して、毎日少しずつ勉強を続けました。
その結果、見事第一志望の企画職に内定。「SPIは軽く見ないほうがいい。情報収集も対策も、早めに始めることが大事」と語ってくれました。
こうした体験談に共通するのは、「SPIを軽視していたことによる失敗」と「対策を始めたことで巻き返せた成功」の両面です。特に転職では面接対策に目が向きがちですが、SPIが突破できなければ面接にすら進めないケースも多いため、“試験対策も選考の一部”という意識を持つことが重要です。
SPIで重視されるのは能力検査だけではない
SPIと聞くと「言語や非言語の学力テスト」というイメージを持ちがちですが、実はもう一つの大きな柱として「性格検査」が存在します。この性格検査の評価が選考に大きな影響を与えるケースも少なくなく、むしろ企業によっては能力検査よりも性格検査の結果を重視する場合もあるのです。
性格検査の重要性と落とし穴
SPIの性格検査では、受験者の性格や思考傾向、行動パターンなどを可視化することが目的とされています。具体的には、「協調性」「責任感」「ストレス耐性」「リーダーシップ」など、仕事を進めるうえでの基本的な資質が測られます。
企業がこの検査を重視する理由は、「社風との相性」「チームでの適応力」「継続的に働けるかどうか」などを判断したいからです。つまり、スキルや知識よりも、“人柄”や“組織適応力”を見ているというわけです。
たとえば、外向的な営業職には「主体性」「行動力」「忍耐力」が求められますし、事務職や管理部門では「正確性」「協調性」「安定志向」といった資質が重視される傾向があります。これらがSPIの性格検査結果と一致していないと、「向いていないのではないか」という判断を下される可能性があるのです。
性格検査には学力のような“正解”がありませんが、企業ごとに評価されやすい回答パターンがあります。にもかかわらず、特に対策をせずに「何となく」で回答してしまうと、企業の求める人物像とズレてしまい、不合格の原因になることもあるのです。
さらに、性格検査には“落とし穴”があります。それが「矛盾回答」と「極端な傾向」です。
SPIの性格検査では、似たような質問を少し言い回しを変えて何度も聞かれることがあります。そこで回答に一貫性がないと、「本当の性格を隠している」「信頼できない」と判断されることがあります。
また、「常に正直に」「自分は完璧に仕事ができる」といった極端にポジティブな回答ばかりを選ぶと、現実的でない自己評価と見なされ、逆効果になることもあります。
こうした落とし穴を回避するためにも、性格検査は対策不要と決めつけず、SPI全体の一部として意識的に取り組む姿勢が求められます。
正直すぎてもNG?バランス感覚が問われる
SPIの性格検査においては、「素直さ」と「バランス感覚」の両方が求められます。もちろん嘘をついて理想像を演じる必要はありませんが、社会人として求められる思考や行動パターンに“寄せていく”意識は必要です。
たとえば、極端に「単独で行動するのが好き」と答えると、「チームワークが苦手」と見なされるかもしれません。また、「すぐに気持ちが変わる」といった選択肢に賛同してしまうと、「情緒不安定で任せづらい」と判断されることも。
重要なのは、自分の本音をすべてさらけ出すことではなく、「企業に見られていることを理解したうえで、社会人としてのバランスある回答を心がける」ことです。
このバランス感覚は、就職後の人間関係や上司との接し方にも大きく影響するため、企業側も注目しています。
性格検査に向けた具体的な準備としては、
- SPI対策本やアプリで性格検査の傾向を把握する
- 自己分析を行い、自分の特性を理解する
- 志望企業の求める人物像と自分の特徴がどう重なるかを考える
といった取り組みが有効です。
SPI対策レベル別の学習方法
「何から始めればいいかわからない」「自分のレベルに合った対策が知りたい」といった声は、転職活動中の求職者からよく聞かれます。ここでは、SPI対策を3つのレベルに分けて、特徴や最適な学習方法を紹介します。自分がどこに当てはまるのかを確認しながら、最短ルートでスコアアップを目指しましょう。
自分に合った対策法を診断しよう
初心者レベル:SPI未経験・基礎力が不安な人
この層に多いのは、そもそもSPIに初めて触れる人、あるいは「名前は聞いたことがあるけど、内容はよく知らない」という人です。また、数学や国語に自信がなく、「中学・高校レベルの計算も不安…」という人もこのレベルに入ります。
まずはSPIがどんな試験なのかを知ることが最優先です。いきなり分厚い問題集に取り組むのではなく、入門書や無料のSPIアプリで出題形式を確認し、基礎的な問題に慣れることから始めましょう。
この段階では、「解ける・解けない」を気にするよりも、「どんな問題が出るか知っておく」ことが大切です。非言語の計算問題や推論問題、言語の語彙や文整序問題などをざっくり把握し、少しずつ問題の“型”に慣れていきましょう。
また、SPIには“スピード”も問われるため、初期段階から「時間を測って解く」ことも意識できると、後々のレベルアップがスムーズになります。
中級者レベル:一度経験あり・やや忘れている人
「新卒のときにSPIを受けた記憶はあるけど、細かい内容は忘れてしまった」「昔解いたときはなんとかなったが、今は自信がない」といった人は中級者に当てはまります。
このレベルでは、再確認と実戦練習を軸に対策を進めましょう。おすすめなのは、模試形式の問題集を使って、一度通しで解いてみることです。現在の実力を把握し、どの分野に弱点があるのかを明確にします。
特に非言語分野では、順列・確率・集合などの高校数学に近い問題が出るため、公式や考え方を忘れていると手が止まりやすくなります。ここを重点的に復習することが得点アップに直結します。
また、“タイムトライアル形式”の演習が効果的です。本番に近い時間設定で繰り返し問題を解くことで、時間配分の感覚が養われます。得点の安定化だけでなく、「焦らず落ち着いて解く力」も身につけましょう。
上級者レベル:高得点を狙いたい人
「SPIにはある程度自信があるが、大手企業や官公庁を受けるので8割以上を目指したい」「過去に高得点を取った経験があり、さらにスコアを伸ばしたい」という人は上級者レベルです。
この段階では、ミスを減らすための精度向上と、難問への対応力を高めることが課題になります。特に非言語分野では応用力が問われる問題が多いため、ワンランク上の問題集や、思考力系の演習問題に挑戦すると効果的です。
また、「時間が足りなくなるリスクを最小限に抑えるための戦略」も必要です。得意分野と苦手分野を明確にし、配点や解答時間を意識した戦略的な解答順序を練習しておきましょう。
上級者ほど「対策しなくても大丈夫だろう」と油断しがちですが、実際のSPIではちょっとしたミスや時間配分の乱れが命取りになります。高得点ゾーンではライバルとの差が小さいからこそ、安定して実力を発揮できる訓練が求められるのです。
以上のように、自分のレベルに合った対策をすることで、効率よくSPIのスコアを伸ばすことができます。「自分はどの段階にいるのか?」を意識しながら、無理のない計画で対策を進めていきましょう。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPIの形式と種類|転職で出されやすいタイプ
SPIとひと口に言っても、その中には複数の種類や出題形式が存在します。転職者向けに実施されるSPIがどのタイプなのかを事前に把握しておくことで、対策の方向性を間違えずに進めることができます。このセクションでは、代表的なSPIのバージョンや受験形式の違いについて詳しく見ていきます。
SPI-G、SPI-Uなどの違いとは?
SPIには複数のバージョンがあり、転職市場では特に「SPI-G」「SPI-U」という名称が使われることがあります。これらは新卒用のSPIと中途用のSPIを分けるための名称であり、それぞれ以下のような特徴があります。
- SPI-G(General)
新卒・中途問わず幅広い用途で使われる基本タイプのSPIです。言語・非言語・性格検査の3部構成で、最もスタンダードな形式です。転職時でも多くの企業がこのタイプを採用しています。 - SPI-U(Uターン・Iターン・中途採用用)
主に地方自治体やUターン採用、第二新卒〜中途採用者向けに用いられる形式です。SPI-Gと大きくは変わらないものの、対象層の特性に合わせて出題傾向が若干調整されています。 - CAB・GAB・TG-WEBなどとの違い
IT・技術系職種ではCAB、総合職ではGABが用いられることもありますが、SPIとは別物です。SPI対策をしていてもGABやTG-WEBには対応できない可能性があるため、企業が指定する形式を事前に確認しましょう。
このように、転職で使われるSPIは新卒用と大きく異なるわけではありませんが、ターゲット層に応じて調整されているケースがあるため、「自分が受けるSPIは何か」をしっかりと調べておくことが大切です。
Webテスト・テストセンター・ペーパーの違い
SPIの“受験形式”にもバリエーションがあります。ここでは代表的な3つの形式について、それぞれの特徴と注意点を紹介します。
Webテスト(自宅受験)
インターネット環境があればどこでも受けられる形式で、近年急速に導入企業が増えています。リモート選考が主流になってきた現在、特に地方在住者にとっては利便性の高い形式です。
注意点としては、受験時間やIPアドレスなどが記録されるため、不正防止の監視が強化されている点です。事前に企業から推奨環境の案内が来る場合もあり、必ずチェックしておきましょう。
また、計算用紙を用意してよいかどうか、再受験が可能かといったルールは企業ごとに異なるため、案内をよく読むことが重要です。
テストセンター形式(会場受験)
全国各地の指定会場に出向き、専用のパソコン端末でSPIを受験する形式です。出題内容はWebテストと同様ですが、テストセンターでは“順応型出題”が採用されている点が大きな違いです。
順応型出題とは、序盤の正答率に応じて後半の問題の難易度が変わる仕組みで、高得点を取るには「前半でミスをしないこと」が非常に重要になります。
また、会場ではタイピング速度やマウスの動きも記録されており、集中力と冷静さが試されます。システムトラブルやログインの手間などもあるため、30分前には現地入りしておくことをおすすめします。
ペーパーテスト形式
現在はあまり主流ではありませんが、公的機関や一部の中小企業では、紙に印刷されたSPI問題をその場で解く形式を採用しているケースもあります。
この形式は「制限時間中にすべての問題を解き終えること」が非常に難しく、瞬時の判断力と処理スピードが求められます。また、採点が人手によって行われる場合もあるため、マークミスや記入漏れに注意が必要です。
このように、SPIにはバージョンや受験形式によって対策すべきポイントが異なります。受験方式を事前に確認し、自分に合った練習方法で準備を進めることが、合格への近道となるでしょう。
SPI対策におすすめの参考書・アプリ
SPI対策を成功させるためには、自分に合った参考書やアプリを活用することが非常に重要です。ここでは、転職者が実際によく使っている人気の問題集や、スキマ時間にも使えるアプリを紹介するとともに、効果的な使い方も解説していきます。
人気問題集3選+用途別アプリ紹介
まずは定番のSPI対策本からご紹介します。これらの書籍は新卒・中途どちらにも対応しており、内容も幅広いため、どのレベルの方にもおすすめできます。
1. 『これが本当のSPI3だ!』(ナツメ社)
SPI参考書の王道。出題形式や頻出問題、性格検査の対策まで網羅されており、初学者から中級者まで幅広く対応しています。解説も丁寧で、問題の背景理解にも役立ちます。
2. 『最新版 SPI3攻略問題集』(成美堂出版)
「時間がないけど要点を押さえたい」という方にぴったりの一冊。頻出問題に絞って掲載されているため、短期間で効率よく対策したい中途の方にも好評です。
3. 『スピード攻略 SPI3』(実務教育出版)
とにかく短時間で全体像をつかみたい方におすすめ。本番形式に近い模試も収録されており、直前対策にも使える構成です。時間配分の練習にも最適です。
次に、スマホで使える便利なSPI対策アプリを紹介します。どれも無料または一部無料で使えるため、手軽に始められるのが魅力です。
・らくらく就活のSPI対策アプリ
転職者にも対応した設計で人気を集めているのが、弊社の「らくらく就活SPI対策アプリ」です。就活支援サービス「らくらく就活」から提供されており、新卒・第二新卒・若手社会人など、幅広い層の受験者が利用しています。
このアプリの最大の特長は、LINE上で完結できる手軽さにあります。アプリのインストール不要で、友だち追加をするだけで問題にアクセスでき、スキマ時間にすぐ取り組めるのが魅力です。
問題内容も充実しており、SPIの中でも特に出題頻度の高い「言語(語句・語彙・読解)」「非言語(割合・速さ・表の読み取り)」を中心に構成。1問ごとにすぐ答えが確認できる形式なので、テンポよく進めながら理解を深めることができます。
さらに、LINE通知による**“出題リマインド”機能**を活用すれば、毎日の習慣化もしやすく、「今日はまだ解いてないな」と気づかせてくれるサポート機能も便利です。
SPI対策は「とにかく手を動かすこと」「継続すること」が何より重要。机に向かう時間が取りづらい方や、仕事や家事と両立しながら転職活動を進めている方にとって、「らくらく就活のSPI対策アプリ」は非常に相性の良いツールです。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
演習のポイントは“繰り返し”と“時間配分”
SPI対策で最も重要なのは、「一度解いて終わりにしないこと」です。問題集やアプリで1回解いた問題でも、間違えたものや時間がかかったものは必ず見直し、2回目・3回目と繰り返すことが得点アップにつながります。
また、本番では限られた時間で多くの問題を解く必要があるため、「時間を測る」「時間内に解ききる」訓練も必要不可欠です。問題を解くスピードと正確さのバランスを意識しながら演習を繰り返すことで、試験当日の焦りを防ぐことができます。
参考書を読むだけで終わらせず、「問題演習をメインに」「何度も解いて」「時間配分も意識する」。この3つを意識すれば、SPI対策は確実に成果へとつながります。
転職時のSPIに関するよくある疑問
SPIを受けるにあたって、実際の転職者からよく寄せられる疑問や不安があります。この章では、特に多い2つの疑問について、わかりやすく解説します。事前に仕組みを理解しておけば、受験の際にも自信を持って臨むことができます。
SPIの点数は企業に共有される?
まず多くの人が気になるのが、「SPIの結果はどのように企業に伝わるのか」という点です。
SPIの実施方式によって、企業がどの情報まで把握できるかは異なりますが、基本的には**“スコアと評価コメント”が企業に提供される形式**になっています。
たとえばテストセンター方式では、リクルートが運営するSPIの評価システムにより、以下のような情報が企業側に送信されます。
- 能力検査(言語・非言語)の得点レベル(S〜D評価など)
- 性格検査の傾向とコメント(協調性や安定性など)
- 過去の受験者平均との比較
ただし、具体的な正答率や全体スコア(点数)そのものは開示されません。その代わりに、スコア帯ごとに分類されたランクや、長所・短所を示す所見コメントのようなかたちで企業に共有されます。
つまり、1問ミスしたかどうかという細かい情報ではなく、「おおよその実力」や「企業にフィットするかどうか」を判断するための情報として活用されているということです。
注意点として、企業によってはSPIの結果を社内データベースに保管し、配属や選考基準の一部として二次利用するケースもあります。SPIは選考終了後も評価材料になり得るという認識を持っておいた方がよいでしょう。
スコアの再利用はできるの?
「一度テストセンターで受けたSPIを、他の企業にも使い回せるのでは?」と考える人もいますが、基本的には“使い回し不可”が前提です。
SPIは企業ごとに試験IDが設定されており、たとえ同じ会場・同じ形式で受験したとしても、企業A用のSPI結果を企業Bが閲覧することはできません。つまり、受ける企業ごとに専用のテストを受ける必要があるということです。
ただし例外として、「複数の企業が合同でSPIのテストセンター日程を共有している場合(例:合同選考)」や「同一グループ企業内で結果を共通活用する」などのケースでは、一部結果が共有されることがあります。
また、稀に転職エージェント経由で「SPIの事前受験結果を提出してください」と言われることがありますが、これも基本的には目安としての参考情報にすぎません。本選考では必ず指定された方式で再受験する必要があると考えておいた方がよいでしょう。
したがって、「SPIは一度受ければ終わり」ではなく、本命企業ごとに毎回ベストパフォーマンスを発揮できるよう準備しておくことが大切です。
まとめ
転職活動におけるSPIの重要性は、企業の規模や業種、職種によって異なりますが、選考を左右する一つの大きな要素であることに変わりはありません。特に大手企業や官公庁、総合職などではSPIを重視する傾向が強く、通過するかどうかが内定獲得の分かれ道となるケースもあります。
SPIでは単なる“学力”だけでなく、「限られた時間で正確に処理できる力」「性格傾向の一貫性と社会性」など、ビジネス現場での活躍につながる総合的な資質が見られています。
この記事では以下のような情報を紹介しました:
- なぜ中途採用でもSPIが課されるのか
- 業種×職種別のSPI重視度マッピングチャート
- SPIの実施タイミングと選考での位置づけ
- 通過のボーダーラインと、落ちる人の共通点
- 実際の体験談から見えるSPI対策の必要性
- 性格検査の注意点とバランスある回答のコツ
- レベル別の学習ルートと使うべき教材
- SPIの形式やスコア共有・再利用の仕組み
SPIを“面倒なテスト”と捉えるか、“突破すれば道が開ける選考のチャンス”と捉えるかで、転職活動の結果は大きく変わります。特に、この記事で紹介したように、**「SPIで落ちるのが一番もったいない」**という声は実際の転職者からも多く聞かれるポイントです。
まずは、自分が志望している企業がSPIを導入しているかを調べ、対策が必要かどうかを判断しましょう。そのうえで、オリジナルのマッピングチャートやレベル別対策ルートを参考に、無理のない学習計画を立てることが成功の近道です。
SPIは一発勝負でありながら、しっかりと対策をすれば誰でもスコアアップが狙える試験です。選考突破率を高め、納得のいく転職を実現するためにも、今日からSPI対策を始めてみてはいかがでしょうか。