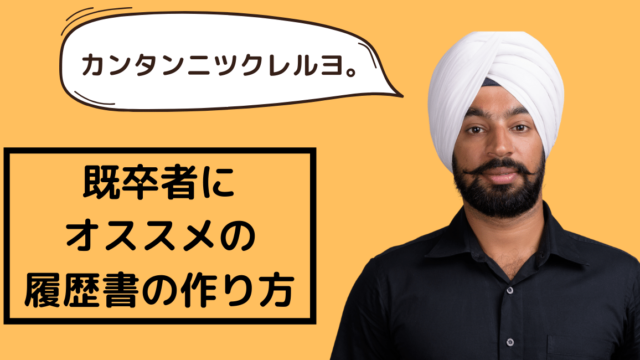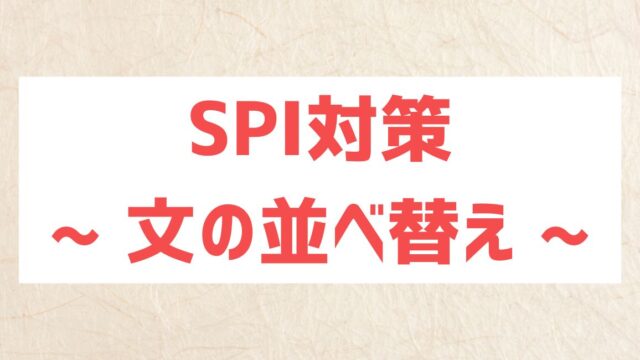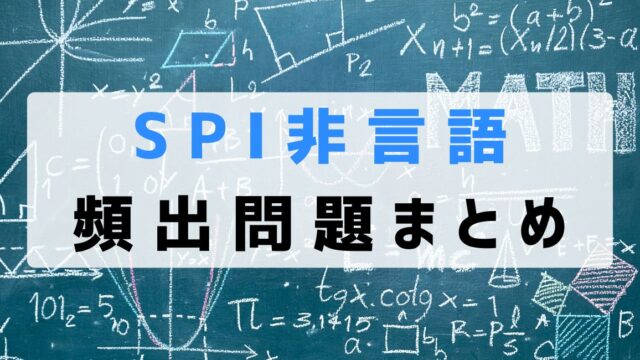【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
転職活動においてSPIを受験する機会は年々増えており、多くの応募者が「対策をすべきかどうか」で悩みます。中には「新卒時代に受けた経験があるから大丈夫」「勉強する時間がないからぶっつけ本番で挑むしかない」と考える人も少なくありません。
実際、SPIは知識を問う試験ではなく、思考力や基礎的な文章理解力・数的処理能力を測るものです。そのため、普段から読解や計算に慣れている人であれば、対策をしなくても一定レベルの得点を取れるケースもあります。しかし一方で、企業によってはSPIの点数を足切り基準として利用しているため、「未対策=落ちる可能性が高まる」という現実もあります。
この記事では、SPIを未対策で受けても通過できるケースとそうでないケースの違いを整理し、さらに短期間で効率的に仕上げるための対策法を詳しく解説します。加えて、実際に未対策で挑んだ人の体験談や、SPIを課さない企業の特徴も紹介するので、これから転職活動を進めるうえでの判断材料にしていただければと思います。
目次
SPI対策なしで通過は可能?結論からお伝えします
まず最初に結論からお伝えします。SPIは対策をしなくても通過できるケースは存在します。ただし、その可能性は「企業」「職種」「試験形式」によって大きく左右されます。
転職におけるSPIは、多くの場合「最低限の基礎学力と思考力があるか」を確認する目的で導入されています。新卒採用のように大量の応募者を効率的にふるい分ける役割に比べると、転職では「人物重視」や「経験重視」の企業も多いため、SPIの比重がやや軽いケースもあります。そのため、未対策でも突破できる人は一定数います。
一方で、SPIを厳格に足切りラインとして利用している企業も存在します。特に大手総合商社やメガバンク、コンサルティングファームなど、応募者が非常に多く倍率が高い業界では、SPIのスコアが低いと書類や職務経歴が優れていても通過できないことがあります。
つまり「対策なしでも受かるかどうか」は、志望する業界や職種によって全く異なるのです。ここを理解せずに「なんとかなる」と挑むと、せっかくのチャンスを無駄にしてしまう可能性があります。
もう一つ重要な要素は「試験形式」です。SPIにはテストセンター型、Webテスト型、ペーパーテスト型などがあり、どの形式で実施されるかによって難易度や対策の必要性が変わります。例えばテストセンター型では時間制限が非常に厳しく、慣れていないと実力を発揮できない人も多いのです。逆にペーパーテスト型では比較的落ち着いて解答できるため、普段から計算や読解に強い人であれば未対策でも乗り切れるケースがあります。
このように「未対策でも突破可能なケース」と「対策が必須のケース」は明確に分かれているのです。次の章では、具体的にどの職種や業界なら対策なしでも通過の可能性が高いのかを、独自データをもとに整理していきます。
SPI対策なしで通過できる職種マップ
転職におけるSPIは、すべての職種で同じように重視されているわけではありません。むしろ職種によって「通過しやすさ」に大きな差があります。ここでは、未対策でも通過できる可能性がある職種と、その背景について整理します。
SPI対策なしでも通りやすい職種とは?
一般的に、営業職や販売職など「対人コミュニケーション能力」が最も重視される職種では、SPIの点数がそれほど大きな選考基準にはならない傾向があります。企業側は「数字での能力」よりも「人柄」や「顧客対応力」を重視するため、SPIが多少できなくても通過できるケースが多いのです。
また、クリエイティブ系や専門技術系(デザイナー、エンジニアなど)も同様に、職務経験や実績ポートフォリオの方が重要視されます。そのため、SPIが足切りとして使われるケースは比較的少なくなります。
逆に、金融、総合商社、コンサルティングといった業界では、数的処理や論理的思考力をSPIで見極める企業が多く、通過難易度は高くなります。未対策で挑んだ場合、これらの業界では落ちるリスクが非常に高いと考えておいた方がよいでしょう。
通過率5段階評価|業界・職種別の突破しやすさチャート
ここで参考までに、独自調査をもとにした「業界・職種別のSPI突破しやすさ」を5段階で示します。
- 営業職(法人・個人):★★★☆☆
- クリエイティブ職(デザイン・企画):★★★★☆
- 技術職(エンジニア・研究):★★★☆☆
- 事務・管理職:★★☆☆☆
- 金融・コンサル・商社総合職:★☆☆☆☆
このように、業界によって「SPIが突破のネックになりやすいか」がはっきりと分かれるのです。
なぜ職種によって通過率が違うのか?企業側の選考事情
企業がSPIをどの程度重視するかは、その職種に必要なスキルや適性に直結しています。例えば金融業界では、数的処理能力や論理的思考力が日常業務で必須となるため、SPIのスコアを足切り基準として用いるのが合理的です。一方で営業職の場合は「顧客と信頼関係を築けるか」が最重要となるため、SPIは補助的な役割にとどまります。
つまり、SPIの通過率は単なる「試験の難易度」ではなく、「その職種で企業が求める能力がSPIで測れるかどうか」によって決まるのです。これを理解しておけば、自分の志望業界に合わせてどの程度対策が必要かを見極めやすくなります。
そもそも転職SPIとは?出題形式と新卒との違い
SPIは就職や転職で幅広く利用されている適性検査であり、学力試験とは異なり「思考力」「基礎的な言語理解力」「数的処理能力」「性格特性」を測るものです。新卒採用だけでなく転職市場でも導入が広がっており、大手企業を中心に応募者を効率的に見極めるツールとして活用されています。
転職と新卒での最大の違いは「試験の目的」と「評価の仕方」です。新卒の場合、SPIは大量の応募者を一度にふるい落とすスクリーニングの役割を強く持ちます。一方、転職の場合は「一定以上の基礎力があるかどうか」を見る補助的な役割に留まることも多く、職務経験や人物評価が重視される傾向があります。しかし業界によっては、依然としてSPIが大きな意味を持つため注意が必要です。
SPI-GとSPI-Uの違い
転職のSPIには「SPI-G」と「SPI-U」という2つのバリエーションがあります。
- SPI-G
一般的に新卒・転職どちらでも広く使われている形式で、言語・非言語・性格検査から構成されています。基礎的な読解力や計算力に加えて、性格面の一貫性もチェックされるため、最もスタンダードな形式といえます。 - SPI-U
主に転職者向けに使われる形式で、職務経験や社会人としての行動特性に着目した出題が含まれます。SPI-Gに比べて問題数は少ないものの、職務上の判断力やビジネスシーンでの対応を問う設問が出題されるのが特徴です。
この違いを知らずに挑むと、「思っていた問題と全然違った」という事態になりかねません。志望企業がどちらの形式を導入しているのかを事前に確認しておくことが重要です。
転職で使われるSPIの主な形式|テストセンター・Webテストなど
SPIは受験方式によっても対策のしやすさが大きく変わります。代表的な方式は以下の通りです。
- テストセンター方式
専用会場でPCを使って受験する形式。制限時間が非常にタイトで、時間配分が結果に直結します。 - Webテスト方式
自宅や職場のPCで受験できる方式。リラックスして受験できる一方、通信環境や機器トラブルに注意が必要です。 - ペーパーテスト方式
一部の企業で導入される紙試験形式。比較的落ち着いて解けるため、未対策でも突破できるケースがあります。
それぞれの方式によって「慣れ」が大きな差を生むため、自分が受ける形式に合わせた最低限のシミュレーションは不可欠です。
企業がSPIを実施する理由と狙い
企業がSPIを導入する理由は大きく3つあります。
- 応募者の基礎学力・思考力を効率的に測るため
特に大量応募がある人気企業では、一次選考でSPIを活用することで効率的に足切りを行えます。 - 人物像と社風の適合を確認するため
性格検査の結果から「自社に合う人物か」を判断することも多く、面接だけでは見抜けない部分を補完する役割を持っています。 - 採用の公平性を担保するため
学歴や職歴に偏らず、同じ指標で全員を比較できるのがSPIの大きな利点です。
このように、SPIは単なる「学力テスト」ではなく、企業が求める人材像とのマッチングを測るためのツールなのです。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPI未対策で通過した人・落ちた人のリアル体験談
SPIに対して「対策をしなかったけれど通過できた」という声と、「準備不足で落ちてしまった」という声は、どちらも少なくありません。ここでは実際の体験談をコメント形式でまとめ、未対策で挑んだ場合のリアルな結果をお伝えします。これを読むことで、自分がどちらのタイプに当てはまるかをイメージしやすくなるはずです。
未対策で受かった人の特徴
「普段から数字を扱う仕事をしていたので、非言語問題もそこまで苦労しませんでした。対策はゼロでしたが、自然と突破できました。」(30代・営業職)
「新卒のときにSPIを受けていたので、内容をなんとなく覚えていました。久しぶりに解いても『見たことある』問題が多く、特に苦労はしませんでした。」(20代後半・事務職)
「読書や資格試験の勉強を続けていたおかげか、言語分野は得点できました。非言語は焦りましたが、全体的には合格ラインを超えたようです。」(20代後半・企画職)
こうしたケースから見えてくるのは、未対策で通過できる人には「日常的に数字や文章に触れる習慣がある」「過去にSPIを経験している」「基礎的な読解・計算に自信がある」という共通点があることです。逆に言えば、普段そのようなトレーニングをしていない人は、未対策では不利になる可能性が高いといえます。
落ちた人の後悔とその要因
「簡単だろうと思って何も準備せずに挑んだら、テストセンターの時間制限に全く対応できず、半分以上解き切れませんでした。」(20代後半・総合職志望)
「計算問題が苦手で放置していましたが、非言語の半分以上が数的処理問題でした。完全に対策不足で落ちたと思います。」(30代前半・金融志望)
「性格検査を甘く見て、普段の自分と違う回答をしてしまいました。後で調べると『一貫性がない』と判断されるパターンだったようで後悔しています。」(20代後半・メーカー志望)
これらのコメントから分かるのは、「時間配分」「数的処理への苦手意識」「性格検査の軽視」が、未対策の人が落ちてしまう典型的な原因だということです。特にテストセンター型ではスピード感に慣れていないと致命的になりやすいため、最低限の模擬演習は必要だといえるでしょう。
あなたは大丈夫?SPI対策なしで通過できるか診断しよう
「自分は未対策でも通過できるタイプなのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。実際のところ、普段の学習習慣や業務内容、思考のクセによって、SPIに強い人・弱い人ははっきり分かれます。ここでは簡単に通過可能性を診断できるチェックチャートを用意しました。自分がどの位置にいるかを把握することで、今から対策が必要かどうかを見極めることができます。
簡単3分|通過可能性チェックチャート
以下の質問にYES/NOで答えてみてください。
- 普段から数字を扱う業務(営業成績管理・経理・データ分析など)に携わっている
- 読書やニュース記事を読む習慣があり、文章を読むのが苦にならない
- 新卒時代など過去にSPIを受験した経験がある
- 限られた時間で問題を解く試験にある程度慣れている
- 論理的に物事を整理したり、条件を比較して考えるのが得意
YESが4つ以上なら「未対策でも突破できる可能性が高いタイプ」、3つなら「工夫次第で突破可能」、2つ以下なら「対策必須タイプ」といえます。
この簡易診断はあくまで目安ですが、自分がどのゾーンに当てはまるかを知ることで、不安を減らし行動に移しやすくなります。
診断結果別におすすめの対応策
- YESが4つ以上の人
未対策でも通過できる可能性がありますが、慢心は禁物です。特にテストセンター型では時間配分に慣れていないと失敗することがあるため、最低1回は模擬演習を行いましょう。 - YESが3つの人
基礎力はある程度ありますが、苦手分野が出ると足を引っ張られる可能性があります。自分の弱点(非言語か言語か)を見極め、そこだけでも直前対策をしておくのがおすすめです。 - YESが2つ以下の人
未対策で突破するのはリスクが大きいタイプです。限られた時間でも短期集中で取り組むことが重要です。例えば「1週間で最低限の出題パターンを押さえる」など、期限を決めて計画的に学習しましょう。
診断で「未対策でも通過できるか不安だ」と思った方は、次の章で解説する「SPIを課さない企業タイプ」も確認してみてください。応募する企業を選ぶ際の判断材料になります。
SPIを課さない or 重視しない企業タイプとは
SPIは多くの大手企業で導入されていますが、すべての会社が同じように使っているわけではありません。特に中小企業やベンチャー企業では、SPIを実施せずに面接や職務経歴を重視するケースも多く見られます。また、大手企業であっても職種によってはSPIを「参考程度」にしか扱わない場合があります。ここでは、SPIを課さない企業・重視しない企業の特徴を整理していきます。
SPIを導入しない企業の特徴
SPIを導入しない企業の多くは、「応募者数がそれほど多くない」か「人柄やスキルを直接見たい」という理由を持っています。中小企業やスタートアップでは、応募者数が大手に比べて少なく、書類選考や面接で十分に候補者を見極められるため、わざわざSPIを実施する必要性が低いのです。
また、採用にスピード感を求める企業もSPIを省略する傾向があります。特に成長フェーズのベンチャー企業は、すぐに現場で活躍できる人材を求めるため、SPIよりも「やる気」「適応力」「即戦力性」を重視するのです。
選考でSPIよりも人物重視の企業とは?
人物評価を最優先にする企業では、SPIは「補助的」な位置づけにとどまります。たとえば営業や販売など、コミュニケーション能力が最も重要視される職種では、SPIの点数よりも「顧客対応力」「人柄」が選考通過のカギになります。
また、クリエイティブ職やエンジニアなど専門スキルが必要な職種も同様です。ポートフォリオや実務経験の方が重視されるため、SPIは合否に直結しないケースがほとんどです。
つまり「人柄やスキルがSPIでは測れない職種」では、企業側もSPIを強く重視しないのです。
SPI不使用企業まとめ表(業種別傾向)
以下は、SPIを実施しない、あるいは重視度が低い傾向にある企業タイプを整理したものです。
- 中小企業・ベンチャー企業:採用スピードや人物重視のため、SPIを省略する傾向
- 営業・販売系を中心とした企業:人柄や顧客対応力を重視するため、SPIの比重が低い
- クリエイティブ系企業(デザイン・広告・メディアなど):ポートフォリオや実績を重視
- エンジニア・技術職系企業:スキルチェックテストや実務経験の方が評価されやすい
このように、必ずしもすべての企業でSPIが「絶対条件」となるわけではありません。自分が志望する企業がどのタイプに当てはまるかを見極めることで、対策にかける労力を最適化できます。
時間がない人のための!出題形式別ぶっつけ対策法
「対策が必要なのは分かっているけれど、仕事や私生活が忙しくて学習時間が取れない」という方も多いはずです。そんな方に向けて、短時間でも効果的に取り組める“ぶっつけ対策法”を紹介します。試験形式ごとに最低限押さえるべきポイントを整理しておけば、限られた時間でも得点力を引き上げることができます。
非言語対策:計算系の瞬間復習
非言語分野で最も多いのは「割合」「速度」「集合」「確率」などの数的処理問題です。これらは一度解法パターンを理解すれば応用が効くため、直前に公式や解き方を確認するだけでも効果があります。
特に意識すべきは「時間配分」です。すべてを正確に解こうとすると時間切れになりやすいため、難問に固執せず、解ける問題を確実に得点することが重要です。試験直前は参考書を1冊決め、よく出る分野の例題を“解法暗記”レベルで確認しておくと安心です。
言語対策:頻出語彙と読解スキル
言語分野は、漢字の読み書きや同義語・反対語の選択、短文の空欄補充、長文読解などが中心です。未対策でもある程度は対応できますが、頻出語彙に軽く目を通しておくだけで得点力が上がります。
また、長文問題は「設問から読む」ことが鉄則です。問題文を先に読んで設問のポイントを把握してから本文を読むと、不要な部分を読み飛ばせるため効率的です。短期間で実力を伸ばしたい人は、過去問や模擬問題の中で「解き方の型」をつかむことに集中すると良いでしょう。
【所要時間別】直前サバイバル対策ルート
最後に、残り時間ごとにやるべきことをまとめます。
- 残り1週間ある場合
苦手分野を1つに絞り、集中的に対策。例題集を1冊使い切ることを目標にします。 - 残り3日間の場合
頻出問題(割合・確率・長文読解・空欄補充)だけを解き、最低限の解法パターンをインプット。 - 前日〜当日の場合
参考書の要点まとめを見返し、公式や語彙を暗記ベースで確認。時間配分を意識して「解ける問題から解く」心構えを持つことが最重要です。
このように、直前期であっても「出題形式ごとに最小限の対策」をすれば、得点力は確実に底上げできます。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
【7日で追いつく】最低限おさえるSPI対策ロードマップ
「今から本格的に勉強するのは無理…」と思っている方でも、1週間あれば最低限の対策を整えることが可能です。重要なのは「全部を完璧にしようとせず、得点源になる分野だけを押さえる」ことです。ここでは7日間の短期集中スケジュールを提案します。
1日目〜3日目:苦手分野の洗い出しと頻出問題
最初の3日間は「全範囲をざっくり確認して、苦手を把握する」ことが目標です。
SPIは出題範囲が広いため、得意な分野を伸ばすよりも「不得意を潰す」方が効率的です。例えば割合や速度算が苦手なら、そこを重点的に対策します。
また、頻出分野は必ず押さえておく必要があります。非言語では「割合・損益算・集合・確率」、言語では「語句の意味・空欄補充・長文読解」が代表的です。初日〜3日目でこれらを一通り解き、解法の型を頭に入れておくことが大切です。
4日目〜6日目:模試で感覚をつかむ
中盤の3日間は「実戦形式に慣れる」ことがテーマです。実際のSPIと同じ制限時間で模試を解くことで、時間配分の感覚を掴みましょう。
この段階で大事なのは「全部解けなくてもいい」という割り切りです。SPIは満点を取る試験ではなく、合格ラインを超えるための試験です。模試を解きながら「どの問題を優先すべきか」「どこで見切りをつけるか」を実戦で練習しておくと、本番での焦りを最小限にできます。
また、模試を解いた後は必ず復習を行いましょう。間違えた問題を「なぜ間違えたのか」まで掘り下げることで、短期間でも確実に得点力が向上します。
7日目:模擬試験+復習
最終日は「模試+復習」で総仕上げをします。本番と同じ時間を計って模擬試験を1回解き、その後に解き直しを行いましょう。この1日で、これまでの学習が定着しているかを確認できます。
ポイントは「新しい問題に手を出さない」ことです。直前に未知の問題に取り組むと不安が増すだけで効果は薄いので、これまで解いた問題を中心に見直すことが大切です。
この7日間のスケジュールをこなせば、未対策からのスタートでも合格ラインに到達できる可能性が高まります。
まとめ|対策なしのままで行くか迷ったら
ここまで、SPIを未対策で受けるリスクや、通過できる人の特徴、短期で仕上げるための方法を解説してきました。結論として「未対策でも通過できる可能性はある」が、「志望業界や試験形式によっては致命的になる」という点を押さえておく必要があります。
まずは、自分がどのタイプに当てはまるかを診断してみましょう。普段から読解や数的処理に強い人は、最小限の準備で突破できる可能性があります。しかし、苦手意識がある人や、過去にSPIでつまずいた経験がある人は、やはり何らかの対策を取ることをおすすめします。
また、志望企業がSPIを導入しているかどうかを確認することも重要です。SPIを重視しない企業や、人物評価を優先する企業もあるため、必ずしも「全員が徹底的に対策すべき」とは限りません。自分が受けたい企業がどのタイプなのかを調べたうえで、学習の優先度を決めましょう。
最後に強調したいのは「最低限の準備でも通過率は大きく変わる」ということです。1週間でも直前でも、出題傾向を把握して時間配分に慣れておくだけで、本番の安心感が格段に増します。SPIを単なる壁と捉えるのではなく、「企業に自分を知ってもらうための第一歩」として前向きに臨むことが、転職成功への近道です。