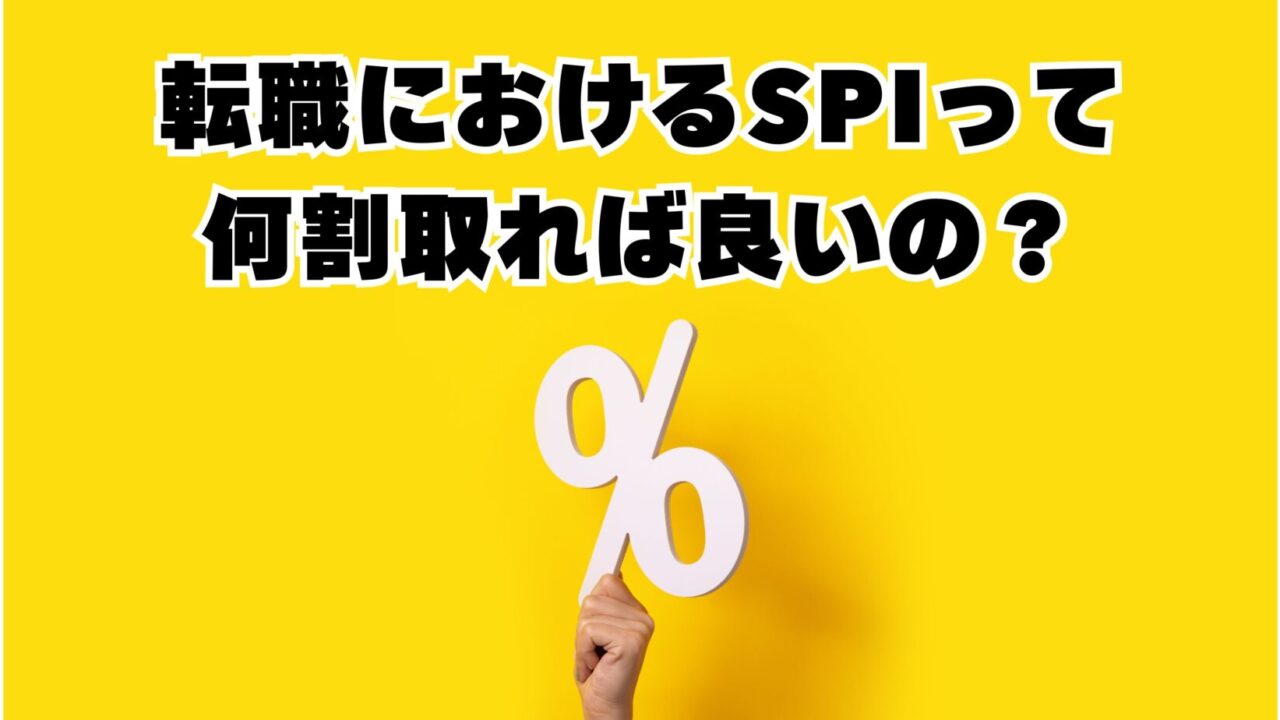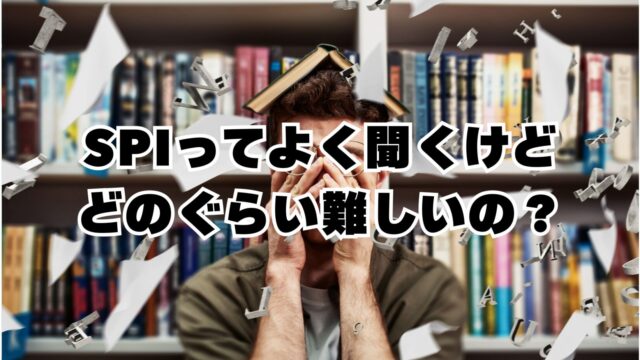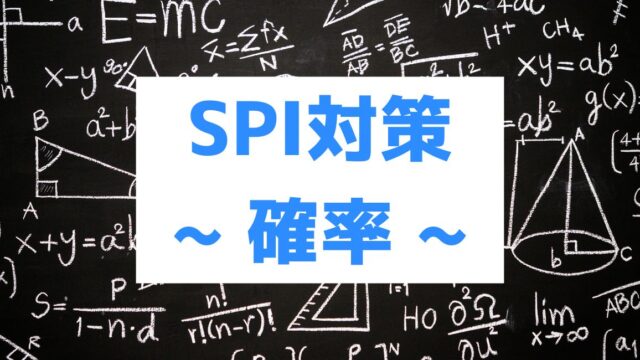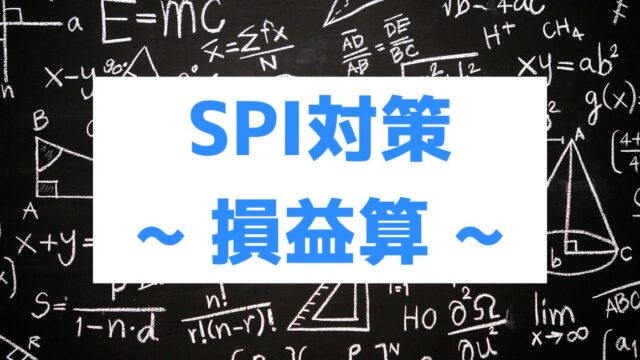【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
転職活動を進める中で、「SPIを受けてください」と案内されたとき、多くの人が最初に気になるのが「何割取れば通過できるのか?」という点です。特に新卒時代にSPIを経験していなかった方や、久しぶりに受ける方にとっては、不安や疑問が多いものです。
SPI(Synthetic Personality Inventory)は、リクルート社が提供する適性検査で、多くの企業が採用選考の一環として導入しています。転職においてもSPIは「応募者の基礎的な能力」や「職種との適性」を客観的に測る手段として活用されており、場合によっては書類選考と同じくらい重要視されることもあります。
しかし、SPIには明確な「合格点」が公表されていないため、自分がどれくらいの点数を目指せばいいのか分からず、不安を抱えたまま受検してしまう人も少なくありません。
本記事では、「転職におけるSPIは何割取れば良いのか?」という悩みを抱える方に向けて、SPIで求められる得点率の目安や、企業ごとの傾向、業界別の基準ライン、さらには対策法までを詳しく解説します。さらに、独自の「スコア×企業タイプ対照表」や「合格ライン自己診断チャート」などもご用意しており、あなたの転職活動にすぐに役立つ実践的な情報をまとめました。
転職市場でSPIを武器にするために、まずは自分が目指すべきスコアを把握し、効率的な対策を行うことが大切です。この記事を読み進めながら、あなたの現在地と目標地点をしっかり確認していきましょう。
目次
SPIとは?転職活動での役割と特徴
SPIを受けたことがない、あるいは新卒時代以来という方も多いかもしれません。ここでは、まずSPIの基本的な仕組みと、転職活動における位置づけについて解説します。どのような目的で導入されているのかを知ることで、対策の重要性や学習の方向性が明確になります。
SPIとは何か
SPIとは「Synthetic Personality Inventory(総合適性検査)」の略で、株式会社リクルートマネジメントソリューションズが提供している適性検査です。もともとは新卒採用向けに開発されたものですが、近年では中途採用でも広く使われるようになってきました。
SPIは大きく分けて二つの領域から構成されています。一つは「能力検査」、もう一つは「性格検査」です。
- 能力検査では、言語分野と非言語分野の問題が出題されます。言語では語彙力や読解力、非言語では計算力や論理的思考力が問われます。出題形式は四択問題で、解答時間に制限があるためスピードも求められます。
- 性格検査では、日常の考え方や行動パターンについての質問に対して、当てはまるかどうかを自己申告で回答します。結果は性格傾向として数値化され、職場での適応性や協調性、ストレス耐性などを測定されます。
SPIは、あくまでも「学力テスト」ではなく「ビジネスで通用する基礎力」を測ることが目的です。そのため、受験者の学歴や職歴に関係なく、結果に差が出るのが特徴です。
転職におけるSPIの位置づけ
中途採用の選考では、これまでの実務経験やスキルが最も重視される一方で、「地頭力」や「職場への適応力」など、書類では見えにくい要素を補完する目的でSPIが活用されています。特に応募者が多い企業や、若手のポテンシャル採用枠などではSPIの結果が選考通過に与える影響は決して小さくありません。
また、SPIは客観的な数値で結果が出るため、選考の一部として公平性を保ちやすく、「面接だけでは判断しにくい部分をSPIで見たい」という企業の意図もあります。
企業によってはSPIのスコアが一定水準に達していないと、次の面接に進めない「足切り基準」となる場合もあります。そのため、スコアが高ければ高いほど、選考上有利になると考えてよいでしょう。
特に大手企業や人気企業では、「実力のある人材」を効率よく見極めるために、SPIの得点を重視する傾向があります。逆に、中小企業やベンチャー企業ではSPIのウェイトが比較的軽く、面接や経歴のほうを重視するケースもあるため、企業ごとの使われ方も把握しておくと対策の精度が高まります。
SPIで何割取れば通過できる?
「SPIに合格点はあるの?」と疑問に思ったことはありませんか?SPIのスコアは基本的に非公開で、合格ラインも企業から明確には示されていないのが実情です。しかし、実際の体験談や傾向を集めることで、どの程度の得点率を目指すべきかはある程度見えてきます。この章では、転職におけるSPIの「通過ライン」の目安を業界や企業タイプ別に整理して紹介します。
一般的な合格ラインの目安
まず、SPIには正答率に応じて点数が算出されますが、企業ごとに「通過させたいスコアの目安」は異なります。以下に、大まかな得点率とそのスコア帯で通過しやすい企業のタイプを示します。
高得点層(8〜9割)
このスコア帯を求めるのは、総合商社、メガバンク、コンサルティングファーム、大手外資系企業など、いわゆる「超人気・難関企業」です。応募者が多く、スクリーニングを効率よく進めるため、SPIでの足切り基準が高く設定されている傾向があります。特に非言語(論理・数学)の正答率が高くないと通過できないケースもあるため、万全の対策が必要です。
標準層(6〜7割)
大手メーカー、インフラ系、SIer、IT企業、保険・証券など、しっかりとした選考フローを持つ企業では、6〜7割の得点が通過の目安とされています。ここではSPIの結果と書類、職務経験などを総合的に評価されるため、バランスよく得点できることが重要です。
緩めの基準(5割前後)
中小企業やスタートアップなどでは、SPIがそこまで重視されないこともあります。あくまで最低限の基礎力を確認する程度で、5割前後の得点でも通過できるケースが見られます。ただし、応募者数が多いポジションや、成長中の企業では徐々に基準が上がっていることもあるので注意が必要です。
このように、SPIで「何割取ればOKか」は、あなたが応募する企業のレベルや選考方針によって異なります。目指す業界や企業の選考傾向を踏まえて、自分が目指すべきスコアを見定めておくことが重要です。
SPIスコア×企業タイプ対照表(オリジナル要素)
下記の表は、企業タイプ別に求められるSPIスコアの目安と、それに応じた傾向や対策ポイントをまとめたものです。
| 業界カテゴリ | 合格ライン目安 | 傾向と対策ポイント |
| メガバンク・商社 | 8〜9割 | 非言語・論理思考力重視。時間配分・ケアレスミスに注意。 |
| 大手メーカー | 7〜8割 | 全体バランスが問われる。言語・非言語ともに安定感が必要。 |
| IT・通信企業 | 6〜7割 | 非言語寄りの評価。スピードと正確性が求められる。 |
| 中小・スタートアップ | 5〜6割 | 書類や面接重視。SPIは足切り用途。最低限の対策でOK。 |
| 外資・コンサル | 8〜9割 | 難問への対応力をチェック。参考書だけでなく模試や過去問が効果的。 |
この対照表を使えば、自分が目指す企業に合わせた戦略が立てやすくなります。スコアの目安と対策の方向性を具体的に把握することで、効率よく準備が進められるでしょう。
合格ライン自己診断チャート
「どれくらいのスコアが必要なのか、自分では判断しづらい…」という方のために、簡単なチャートをご用意しました。いくつかの質問に答えるだけで、自分が目指すべきスコア帯が見えてきます。
Q1:あなたの第一志望は大手企業ですか?
→ Yes → Q2へ進む
→ No → 【目安スコア:5〜6割】
Q2:営業・総合職など、論理的思考力が求められる職種ですか?
→ Yes → 【目安スコア:8〜9割】
→ No → 【目安スコア:7〜8割】
このように、志望企業と職種によって必要な得点ラインは変わります。まずはこのチャートで目安を確認し、自分の現状スコアとのギャップを意識したうえで、次の対策フェーズへ進んでいきましょう。
得点別:転職SPI通過戦略
SPIは「高得点を取ればいい」という単純な試験ではありません。自分が目指すべき企業レベルに応じたスコアを想定し、現状とのギャップを見極めたうえで、最短ルートでのスコアアップを目指すことが重要です。この章では、現在の得点状況に合わせた具体的な対策方法と学習ステップを解説します。
スコア別対策マッピング表
まずは、以下の表を見てください。これは、SPIの得点帯ごとに「どのような課題があり」「どこを強化すれば通過ラインに届くか」をまとめたものです。あなたの現在の実力に応じて、最適な対策方法を選んでください。
| 現状スコア | 目標スコア | 重点対策 | 推奨学習法 |
| 4割前後 | 7割 | 語彙力・基礎計算力の強化 | 入門問題集の反復+YouTube動画+アプリ演習 |
| 6割前後 | 8割 | 時間配分の見直し・弱点単元の補強 | 模試を活用した時間管理訓練+復習ノートの作成 |
| 7割以上 | 9割 | 実戦レベルの応用力と集中力強化 | 高難度問題集+テストセンター模試+本番シミュレーション |
以下、それぞれのスコア帯ごとに解説していきます。
① 現状スコア4割前後 → 目標スコア7割
この段階にある方は、SPIにおける基本的な知識や解答テクニックがまだ十分に身についていない状態です。まずは、言語なら語彙力・読解力、非言語なら四則演算や割合、表の読み取りなどの「基礎」にフォーカスすることが最優先です。
参考書は、いきなり分厚い問題集に手を出すのではなく、出題傾向に特化した「入門書」を1冊完走することを目指しましょう。あわせて、SPIを扱ったYouTubeチャンネルで解き方のコツを学んだり、スマホアプリで1問ずつ感覚的に解く練習を取り入れることで、徐々に苦手意識を払拭できます。
この段階では、まず「解ける問題を確実に正解できる力」を育てることがスコアアップの近道になります。
② 現状スコア6割前後 → 目標スコア8割
6割スコアは「基本は身についているが、ミスや時間不足で点が伸び悩んでいる」という方が多い層です。この段階では、「解けるのに時間が足りない」「ミスを繰り返してしまう」といった課題に向き合う必要があります。
この層の方におすすめなのは「模擬テストを時間内で解く練習」です。模試を使って本番と同じ時間制限で解き、どの問題でつまずいているかを明確にしましょう。間違えた問題は「復習ノート」に記録し、なぜ間違えたのか、次に同じパターンが出たらどうするかを自分の言葉でまとめておくと記憶に残りやすくなります。
また、演習量が増えると得点にムラが出がちですが、得意分野と苦手分野を分けて戦略的に時間を配分する意識も重要です。
③ 現状スコア7割以上 → 目標スコア9割
すでに7割を超えている方は、基礎力は十分あるため「実戦で差がつく応用力」が問われる段階に入っています。この層の方に求められるのは、応用問題や計算量の多い問題における正確性・スピード・集中力の三拍子を揃えることです。
おすすめの学習法は、高難度問題に特化した問題集を使った反復演習です。SPIに対応したハイレベル模擬テストや、テストセンター形式の練習サイトなどを活用すると、制限時間下での実力をさらに高めることができます。
また、時間を測りながら複数の問題を連続して解く「本番シミュレーション」を行うことで、試験当日の緊張感に慣れ、安定したスコアを出す力が身につきます。
このように、SPIの得点アップには「自分のスコア帯に合った対策」を選ぶことが何よりも大切です。逆に、今の自分の課題を無視して難しい問題ばかり解いていても、効果は薄れてしまいます。
まずは現状を冷静に分析し、自分に合った勉強法で効率よくスコアアップを目指していきましょう。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
SPIの形式と評価ポイント
SPIは「何をどのように測定しているのか」が企業にとって明確であるからこそ、多くの選考で取り入れられています。しかし、受験者側がその形式や評価基準をきちんと把握していないと、実力が正しく発揮できないこともあります。この章では、SPIの出題形式や評価のされ方について詳しく見ていきます。
検査形式の違いと特徴
SPIは、主に以下の3つの形式で実施されます。企業によって指定される形式は異なりますが、それぞれに特徴があるため、あらかじめ知っておくことで本番でも落ち着いて対応することができます。
テストセンター
SPIの代表的な形式で、リクルートが運営する専用会場(テストセンター)で受験します。会場は全国に点在しており、予約制で受けられます。
テストセンターでは、静かな環境で適切な試験設備が整っており、多くの受験者が集中して取り組みやすいため、高得点が出やすい傾向があります。問題は受験者ごとに異なる「適応型出題」がされるため、正答が続くと問題が難化し、スコアもより精密に測定される仕組みです。
Webテスティング
Webテスティングは、企業から送られてきたURLから自宅のPCやスマホを使って受験する形式です。自宅で受けられるためリラックスして取り組める反面、周囲の環境や通信状況によって集中力に差が出やすいというデメリットもあります。
また、不正防止の観点からカメラ起動が義務付けられるケースも増えており、「家だから簡単」とは限りません。操作性に慣れておくこともスコア安定のカギとなります。
インハウス(ペーパーテスト)
一部の企業では、会社の会議室などで紙のSPIを実施する場合もあります。こちらは事前に対策しにくいものの、出題傾向は他の形式と大きく変わりません。特に中小企業や地方企業ではこの方式が残っていることがあります。
形式によって問題傾向や時間配分、環境の影響が変わるため、志望企業がどの形式で実施しているかを早めに確認して、適切な準備を進めましょう。
評価におけるSPIの役割
SPIが評価において担う役割は、「採用合否を決める」ものではなく、「スクリーニング・補足情報」としての活用が主流です。つまり、SPIの点数だけで落とすのではなく、他の選考項目(職務経歴書、面接など)と合わせて総合的に判断されるケースが多くなっています。
ただし、以下のような場面ではSPIが非常に重要な意味を持つこともあります。
足切りの基準として使われる場合
人気企業や大手企業では、応募者数が非常に多いため、書類選考を経たうえでSPIでさらにふるいにかけることがあります。この場合、一定のスコア(例:非言語6割以上など)に達していないと、自動的に選考から外される「足切り」となるケースもあるため、注意が必要です。
書類や面接では見えない「地頭」を測る
SPIの能力検査では、論理的思考力や基礎学力、スピード感など、日々の業務でも必要となる“地頭”を測ることができます。特に、若手のポテンシャル採用や異職種への転職など、過去の実績だけでは測れない場面では、SPIの結果がそのまま適性の判断材料として使われることがあります。
性格検査との組み合わせによる総合評価
SPIの性格検査は、協調性・責任感・リーダーシップ・ストレス耐性などの数値が明確に示されます。企業はこれらの情報を元に「組織との相性」や「配属先に向いているかどうか」なども見極めているため、SPIが「入社後の活躍可能性」を測る指標として活用されているのです。
SPIは「落とすための試験」ではなく、「採用の確信を持つための試験」として使われる場面が多いのが特徴です。とはいえ、通過のためには最低限のスコアが求められるため、自分が目指す企業がSPIをどう活用しているかを事前に調べ、適切に対策を進めることが合格への第一歩となります。
SPIで高得点を取った転職者の体験談
SPI対策を進めるなかで、多くの方が感じるのが「この勉強法で本当に通過できるのか?」「他の人はどんなふうに対策しているの?」という不安です。ここでは、実際にSPIを受けて転職に成功した方々のリアルな体験談を紹介します。対策期間や使った教材、得点アップのコツなどを通して、実践的なヒントを得ることができるでしょう。
「最初は4割しか取れなかった。でも2週間で通過ラインに」
28歳・営業職希望の男性
志望企業:大手不動産系ベンチャー
最終スコア:約8割
「最初にSPI模試を受けたときは、本当にひどい結果で正答率4割あるかないかでした。特に非言語は苦手意識が強くて、問題を見ただけで諦めそうになることも…。でも、どうしても志望企業に行きたかったので、『これが本当のSPI3だ!』を1冊やり切ると決め、毎日15〜20分を朝の通勤時間にあてました。1週間で内容に慣れてきて、2週間目には模試で8割近く取れるように。無事に一次選考も通過でき、自信になりました。」
この方のように、たとえ最初は苦手でも、短期間で集中的に取り組めば大幅なスコアアップは可能です。時間がない中でも、効率よく取り組む工夫が鍵となります。
「毎朝の15分で、SPIが習慣に」
31歳・マーケティング職希望の女性
志望企業:大手IT企業
最終スコア:約8割
「社会人になってから数学なんて全く触れてこなかったので、SPIを受けると聞いたときはかなり不安でした。でも、いきなり長時間の勉強は無理だと思い、まずは朝の15分だけ問題集を開くことから始めました。『史上最強 SPI実戦問題集』を使って、1日3問だけでも確実に解く習慣を作りました。3週間くらい経つと、問題を見るスピードが速くなっているのを実感できて、本番でも落ち着いて解答できました。」
習慣化することの大切さが伝わってくる体験談です。SPIは短時間でもコツコツ積み上げることができるタイプのテストなので、継続することが高得点につながります。
「模試で苦手を見つけて、対策を集中」
26歳・事務職希望の女性
志望企業:大手保険会社
最終スコア:約7割
「勉強していたのに点数がなかなか上がらなくて、何が原因か分からず焦っていました。そこでSPIの無料模試を受けてみたところ、グラフの読み取りと割合の問題が壊滅的にできていないことが分かりました。それからは分野別の問題集で苦手分野だけを集中して繰り返し解くようにしました。本番では苦手だった分野で時間に余裕ができるほど解けるようになり、無事に通過。模試を使って自分の弱点を“見える化”したのがよかったと思います。」
このように、自己分析→戦略的な対策というステップを踏むことで、より確実なスコアアップが期待できます。模試を「現状確認のツール」として使うのは非常に効果的です。
SPIは「試験だからとりあえず勉強する」のではなく、「目的意識を持って戦略的に取り組む」ことで確実に結果が変わってきます。上記のような体験談を通して、自分なりのスタイルを見つけ、無理なく、でも確実に成果に結びつけられる勉強法を選んでください。
SPI対策におすすめの教材と学習法
SPIのスコアを上げるためには、自分に合った教材を使って、計画的に学習を進めることが非常に重要です。この章では、書籍やアプリなどのおすすめ教材と、それぞれに合った活用法を紹介します。初学者から高得点を目指す人まで、レベル別に取り組みやすい教材を厳選しました。
書籍ベスト3
まずは、SPI対策において定番とされている参考書の中から、特に人気の高い3冊を紹介します。どれも「問題の質が良い」「解説が丁寧」「スコアが伸びた」という口コミが多く、初学者から実戦派まで幅広く対応できる内容となっています。
『これが本当のSPI3だ!』
SPI参考書の中でも圧倒的な支持を集めるロングセラー。基礎から応用まで幅広いレベルの問題が収録されており、解説も丁寧でわかりやすいのが特徴です。出題傾向の分析も充実しており、「SPIとは何か」からしっかり学びたい人にぴったりです。
この本は、最初に1周読み切って、2周目で間違えた問題を重点的に復習するという方法が王道。付属の模試もタイムトライアルに最適です。
『史上最強 SPI&テストセンター実戦問題集』
より実践的な問題を多くこなしたい方向けの一冊です。近年の出題傾向に合わせて問題構成が工夫されており、難易度の高い問題に挑戦したい方や、テストセンター形式に慣れておきたい方におすすめです。
特に、時間を測って解く模試形式のページが充実しているため、「本番の緊張感を再現しながら勉強したい」という人に適しています。
『スピード攻略Webテスト』
Webテスティング対策に特化した一冊です。SPIと類似形式のWeb試験に対応しているため、IT系やベンチャー企業を志望している人には特に有効です。短時間で解ける問題が多く、隙間時間に取り組みやすいのも魅力の一つです。
テンポよく問題に触れたい人、短期集中で結果を出したい人にはこのシリーズが最適でしょう。
おすすめアプリ
LINEで受けられる無料SPI模試(らくらく就活)
弊社の「らくらく就活」が提供しているLINE公式アカウントから、SPI模試を無料で受けることができるサービスもおすすめです。LINE上で診断が完結するため、登録も簡単。テストセンターやWebテスティングを控えている方が本番前に“腕試し”するには最適なツールです。
また、模試終了後にスコアレポートが送られてくるため、自分の現状を客観的に把握できる点も魅力です。SPIの勉強に手をつけていない方でも気軽に取り組める入口として人気を集めています。
SPI対策は「書籍でじっくり理解する」「アプリでテンポよく演習する」「模試で実力をチェックする」という3ステップで進めるのが効果的です。それぞれの教材の特性を理解し、自分のライフスタイルや勉強ペースに合った方法で進めることで、より確実にスコアアップにつながるでしょう。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPIを課す企業一覧+合格ライン目安
SPIは非常に多くの企業で採用選考に活用されていますが、その位置づけやスコアの評価基準は企業ごとに異なります。ここでは、実際にSPIを課している代表的な企業と、求められるスコアの目安、またどのような観点でSPIを活用しているかについて、口コミや過去の選考体験談をもとにまとめました。
トヨタ自動車|8割〜(高得点者優遇)
日本を代表する自動車メーカーであるトヨタは、採用人数が多い一方で、応募者数も非常に多く、SPIを通じて応募者を絞り込む傾向があります。特に総合職採用では、非言語分野の得点が重視されるとの声が多く、「8割以上の得点がないと一次面接に進めない」という体験談も見られます。
SPI結果と職務経歴を合わせて、業務理解力や論理的な問題解決能力を評価していると考えられるため、高得点を目指す必要がある企業の代表格と言えるでしょう。
NTTデータ|7割前後(標準以上)
システムインテグレーター大手のNTTデータでは、SPIは「選考通過のための基礎評価」として機能しており、応募者の足切り基準として使われているケースが多いです。実際に選考を受けた人の中には、「SPIで6割台後半だったが通過できた」という声もあれば、「5割台前半で落ちた」といった報告もあり、目安として7割前後の得点が必要とされていると推察されます。
技術系・事務系ともにSPIが導入されており、形式はテストセンター型が主流です。
楽天グループ|6割程度(柔軟な評価)
楽天では、SPIは選考フローの中で比較的早い段階に実施されますが、スコアよりも性格検査や面接評価に重きを置く傾向があります。実際に「非言語は5割前後だったが面接で挽回できた」という報告もあり、あくまで「最低限の基礎力を確認するため」の位置づけのようです。
そのため、得点目安としては6割程度を確保できていれば、SPIがボトルネックになることは少ないと考えられます。
Web系スタートアップ|5割で通過も可能
スタートアップ企業では、SPI自体を導入していない場合も多く、導入されていてもそのウェイトは非常に軽めです。理由としては、職務経験やカルチャーフィット、スキルマッチングを重視する選考スタイルが主流であるためです。
実際にSPIを課されても「形式的なもの」「形式に慣れているかの確認レベル」として位置づけられることが多く、「5割でも十分通過できた」というケースも多く見られます。SPIが不安でもチャレンジしやすい業界と言えるでしょう。
その他SPI導入企業の一例(2025年口コミベース)
- 三井住友銀行(メガバンク)…8割以上必要との報告多数
- パーソルキャリア(人材業界)…Webテスティング、7割前後が目安
- 三菱電機(メーカー)…バランス型の評価、6.5〜7割が平均
- サイバーエージェント(IT・広告)…性格検査重視の傾向あり
このように、SPIの扱われ方や求められる得点ラインは企業によって大きく異なります。応募予定の企業がSPIをどのように使っているか、また自分の目指すポジションでどの形式が採用されているかを事前に調べておくことが、無駄のない対策につながります。
よくある質問(Q&A)
SPIは形式が特殊であり、選考フローの中でも独自の位置づけを持っているため、初めて受ける方や久しぶりに受験する方からはさまざまな疑問が寄せられます。ここでは、特に多くの人が気にする代表的な質問とその回答をまとめました。
SPIのスコアだけで落ちることはある?
結論から言うと、「あります」。特に応募者が多く、書類選考だけでは差がつきにくい企業では、SPIが“ふるい”の役割を果たしていることがあります。たとえば、「非言語で○割以上の正答率が必要」など、社内でスコア基準を設けている企業も存在します。
ただし、SPIのスコアだけですべてが決まるわけではなく、多くの場合は書類選考・職歴・面接と合わせて総合的に判断されます。SPIでやや得点が伸び悩んでも、他の評価項目でカバーできるケースもあるため、気負いすぎず、全体としてバランスの取れた選考対策を意識することが大切です。
性格検査は何を見ている?
性格検査では、あなたの「性格傾向」「行動特性」「価値観」などが数値化され、グラフやレポートとして出力されます。企業が注目するポイントは、職場での適応性、ストレス耐性、リーダーシップの傾向、協調性、責任感などです。
たとえば、顧客対応が中心の職種では「外向性」「共感性」などが重視されたり、開発職などでは「論理的思考」「独立志向」などが見られることもあります。また、企業風土と性格のミスマッチを避ける目的もあり、「地頭が良くても文化に合わない」という理由で選考を見送られるケースもあるため、正直に、かつ一貫性を持って回答することが重要です。
対策期間はどれくらい必要?
対策期間は個人の得意不得意や目指すスコアによって異なりますが、多くの人が口を揃えて言うのは「短期集中でも結果は出せる」ということです。
実際に、1日15〜20分の学習を2週間継続するだけでも、正答率を2〜3割アップさせた例は多くあります。特に非言語分野(計算や論理)に苦手意識がある人は、時間を多めに取りつつ、基本問題を繰り返すことが効果的です。
おすすめの勉強法は「模試で現状を測る → 苦手分野に絞って学習 → 再度模試で確認する」のサイクルを2〜3回繰り返すこと。短期間でもこの方法を取ることで、安定したスコアが出せるようになります。
書籍とアプリ、どっちを使えばいい?
結論としては、「両方を併用する」のが理想です。書籍は体系的に理解しやすく、問題の背景や解法をしっかり学べる一方、アプリはテンポよく繰り返し学習ができ、時間がない社会人にはぴったりです。
例えば、平日は通勤中にアプリで1問1答形式の問題を解き、休日にまとめて書籍で復習というように、使い分けると効果的です。また、模試などで実力を測りながら、バランス良く学習を進めることをおすすめします。
SPIに対して不安を感じるのは当然のことです。しかし、正しい知識と適切な対策を行えば、スコアは確実に伸ばせます。このQ&Aを参考に、あなたにとって最適な準備方法を見つけてください。
まとめ
転職活動において、SPIはもはや「新卒向けだけのテスト」ではありません。特に若手やポテンシャル採用を重視する企業においては、SPIが選考の重要な指標のひとつとなっており、対策の有無が合否を分けることもあります。
本記事では、「転職におけるSPIは何割取れば良いのか?」という疑問に対して、得点率の目安から企業別の傾向、対策方法まで幅広く解説してきました。
まず大前提として、SPIには明確な合格点が公表されていないため、企業ごとに必要なスコアは異なります。たとえば、メガバンクや商社などの人気企業では8〜9割、大手メーカーでは7〜8割、中小・スタートアップでは5〜6割程度が通過ラインとされることが多く、志望先に応じたスコア戦略が必要です。
また、自分の現状スコアや苦手分野に応じた「得点別対策マッピング表」や、企業タイプ別の「スコア×企業対照表」、さらに「合格ライン自己診断チャート」を使うことで、目標設定と戦略が立てやすくなります。
SPIの形式(テストセンター・Webテスティングなど)も理解しておくことで、実際の受験環境に応じた準備ができるようになります。評価においても、SPIは単なる足切りだけでなく、職場適応力や基礎力の可視化、性格適性などを測る手段として総合的に活用されていることを忘れてはいけません。
そして、何より伝えたいのは「SPIは努力次第で必ずスコアアップできる」ということです。実際に、短期間で4割から8割へ伸ばして通過した方や、朝の15分を活用して習慣化したことで安定的に高得点を取れるようになった方の体験談からもわかる通り、戦略的に取り組めば結果はついてきます。
おすすめの教材や無料模試も活用しながら、「今の自分に合ったSPI対策」を無理なく進めていきましょう。焦らず、でも着実に。SPI対策を通じて自信をつけ、転職成功への道を一歩ずつ前進してください。