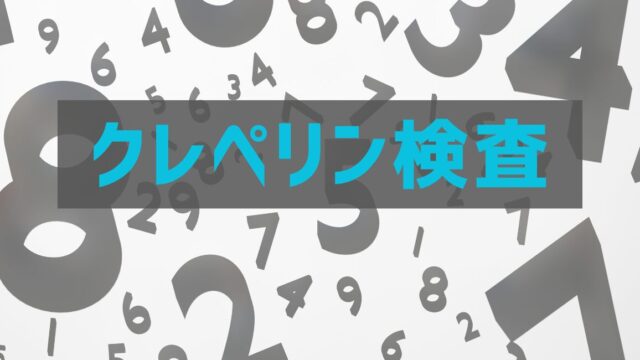【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
「第二新卒にもSPIってあるの?」
「中途採用だから筆記試験はないと思ってた…」
中途採用にもSPIが使われることを知らない人は多いです。たしかに中途採用では、書類と面接だけで内定が出るケースが多く、筆記試験がない企業も数多く存在します。しかし、第二新卒の場合は少し事情が異なります。
なぜなら、第二新卒は「社会人経験はあるものの、経験が浅く、ポテンシャル重視で採用される層」だからです。企業によっては新卒とほとんど同じフローで選考を行うため、SPI(Synthetic Personality Inventory:総合適性検査)を課すケースが増えています。特に大手企業や人気のある業界では、選考の効率化や能力のスクリーニングのためにSPIを活用する傾向が強くなっています。
実際、「SPIが出ると思っていなかった」「準備不足で時間切れだった」といった声は後を絶ちません。一方、しっかり対策をした人は、SPIを通過し、選考の序盤を有利に進めています。
本記事では、第二新卒がなぜSPIを課されやすいのかをはじめとして、SPIが出やすい企業の傾向、実際の出題内容、未対策で落ちた人の共通点、そして最短で結果を出すための対策法まで、網羅的に解説していきます。読み進めることで、「SPIが出るのか分からない」「どこまで対策すべきか不安」といった悩みがクリアになり、自信を持って選考に臨めるようになるはずです。
目次
第二新卒はなぜSPIを課されるのか?
社会人経験より将来性を見られるから
第二新卒とは、一般的に「卒業後1~3年以内で転職活動をしている若手社会人」を指します。この層は、すでに社会人としての経験があるとはいえ、十分な実績やスキルがあるとは限らず、まだまだ育てる前提で見られることが多いです。
企業側も、いわゆる即戦力の中途とは違った視点で採用を進めます。特に重視されるのが、将来に向けた伸びしろや地頭の良さです。ここで役立つのが、SPIなどの適性検査です。
SPIは、短時間で応募者の基礎学力や性格傾向、論理的思考力などを数値化して把握できるツールです。第二新卒は実務経験が浅いため、面接だけでは能力を判断しづらいという課題があります。そのため、SPIを通して「この人には成長のポテンシャルがあるか」「基本的な問題解決能力が備わっているか」といった点を客観的に見極めようとする企業が増えているのです。
つまり、第二新卒の選考では、「社会人経験をどう活かしてきたか」以上に、「これからの成長に期待できるか」が問われる場面が多く、その判断材料の一つとしてSPIが使われているというわけです。
中途採用と新卒採用の選考フローの違い
選考フローの観点からも、第二新卒がSPIを課されやすい理由が見えてきます。
中途採用の場合、多くの企業では以下のようなシンプルな選考フローを取ります。
- 書類選考 → 面接(1~2回) → 内定
これは即戦力を求めるからこそ、スピーディに進むスタイルです。しかし、第二新卒に対しては次のようなケースが増えています。
- 書類選考 → SPI(Webテスト) → 面接(2回程度) → 内定
つまり、新卒の選考フローとほとんど同じ形式です。
もちろん、すべての企業がこの形を取っているわけではありませんが、特に以下のような企業ではSPIの導入率が高い傾向にあります。
- 新卒採用を毎年行っている企業(=新卒フローが整備されている)
- 採用数が多く、選考を効率化する必要がある企業
- 若手育成前提で採用している企業(=教育投資を惜しまない)
このような企業は、第二新卒であっても新卒に近い存在として扱うため、筆記試験(=SPI)を導入するのが自然な流れになっているのです。
SPIが課される可能性診断チャート
あなたの応募先、SPIあるかも?
ここまでで「第二新卒でもSPIが出ることがある」という話は理解できたと思いますが、実際に自分の志望先でSPIが出るかどうかを判断するのは難しいですよね。
そこで、第二新卒の応募先にSPIが課される可能性を、簡単なチェック形式で診断できるチャートをご用意しました。以下の質問に「Yes」が多ければ多いほど、SPIが出題される確率は高くなります。
SPIが課される可能性診断チャート
- 応募企業は大手・有名企業ですか?
- 募集職種は「総合職」または「営業職」ですか?
- 求人に「ポテンシャル採用」「第二新卒歓迎」などの文言がありますか?
- 書類選考通過後、メールなどでWebテスト案内が届いていますか?
- 求人票に「適性検査あり」と記載がありますか?
いかがでしょうか?
「3つ以上Yesだった」という方は、SPIが課される可能性が高いと考えて準備しておいた方が安全です。
もちろん、これに当てはまらないからといって絶対に出ないというわけではありませんが、あらかじめ「SPIが出るかも」という前提で準備しておけば、万が一のときでも焦らず対応できます。
実際に、「SPIがあるなんて知らなかった」というだけで不合格になってしまうのは非常にもったいないことです。SPI対策において重要なのは、出る前提で準備するという姿勢です。
次の章では、実際にSPIを課している企業の傾向や事例について詳しく見ていきましょう。
SPIを課す企業の傾向と事例
大手や成長企業ではSPIは当たり前
「SPIって、特定の企業だけが使っているものじゃないの?」
そんな疑問を持つ方もいるかもしれませんが、実際にはかなり多くの企業で導入されています。特に大手企業や業界トップクラスの成長企業では、SPIは採用プロセスにおける「標準装備」ともいえる存在です。
なぜこれほど広く使われているのでしょうか?理由は大きく2つあります。
まず1つは、「応募者数が非常に多い」ことです。大手企業や人気企業は、求人を出すだけで膨大な数の応募が集まります。そこで、一定の水準に達していない人を事前にふるいにかける「足切り」のために、SPIが使われているのです。特にテストセンター方式などでは、受検データを基に比較的公平な判断ができるため、多くの企業が積極的に活用しています。
もう1つは、「新卒と同じフローを適用している」ことです。先述の通り、第二新卒はポテンシャル採用の意味合いが強く、新卒と同じ選考フローをそのまま転用しているケースも少なくありません。SPIを毎年のように使っている企業であれば、第二新卒にも同様の対応をするのは自然な流れです。
また、外資系企業や急成長スタートアップなどでも、独自の適性検査を導入しているケースが増えており、SPIに近い形式のWebテストが課されることもあります。
SPIを課す企業リスト(第二新卒可)
ここでは、実際に第二新卒枠での採用時にSPIを課している企業の一例を紹介します。あくまで代表的な事例ですが、これらの企業は特に「新卒フローに近い選考を行っている」「適性検査を重視している」といった特徴を持っています。
| 企業名 | 業界 | SPI実施形式 | 備考 |
| NTTデータ | IT | テストセンター | 技術職・総合職対象、難易度高め |
| パーソルキャリア | 人材 | Webテスティング | 書類通過後に受検案内が届く |
| 三井住友信託銀行 | 金融 | 自宅受検 | 性格検査も重視される傾向あり |
| 東京海上日動火災保険 | 保険 | テストセンター | 事前対策が必須のボリューム |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | IT | Webテスト | ロジカル思考問題も出題される |
| サントリーホールディングス | 食品・飲料 | テストセンター | SPIを含む適性検査が複数種存在 |
※上記は一例であり、出題形式や運用は変更されることがあります。
このように、いわゆるホワイト企業や有名企業、制度が整っている企業は、第二新卒でもSPIが出る前提で考えておくのが無難です。求人票で「適性検査あり」と明記されていなくても、選考が進んでから突然案内が届くことも珍しくありません。
次章では、実際に出題されるSPIの内容や難易度について、第二新卒向けに分かりやすく整理していきます。
第二新卒が受けるSPIの出題内容とは?
SPIの基本構成と新卒との共通点
SPIは「総合適性検査」と呼ばれ、リクルート社が開発した代表的な筆記試験です。基本的には新卒採用向けに設計されたテストですが、第二新卒の採用でも広く流用されています。そのため、出題内容や形式は新卒とほぼ同じです。
SPIは主に以下の3領域に分かれています。
1. 言語分野(語彙力・読解力)
語句の意味、空欄補充、長文読解、二語の関係など、日本語の運用能力や読解力を問う問題が中心です。特別な知識が求められるわけではありませんが、選択肢の引っかけが巧妙で、読解に時間がかかる問題もあります。
2. 非言語分野(計算・論理思考・図表)
表の読み取り、確率、割合、推論、集合、順列・組み合わせなどが出題されます。中学~高校レベルの数学がベースですが、限られた時間の中で処理するスピードと正確さが問われます。
3. 性格検査(価値観・行動傾向)
100問以上の設問に対し、自分の行動や考え方を選ぶ形式です。回答に「正解・不正解」はなく、価値観やストレス耐性、組織適応性などをチェックします。内容が被っているように見える設問が多く、矛盾のない一貫した回答が求められます。
このように、SPIでは知識ではなく「考える力」「判断力」「価値観の一貫性」が試されます。そのため、事前に出題形式に慣れておくことが対策のカギとなります。
第二新卒が受けるSPIでも、新卒と同じように時間制限が厳しく、初見だと難しく感じる問題が多い点には注意が必要です。「就活時代に経験しているから大丈夫」と思っていても、ブランクがあると苦戦するケースは珍しくありません。
SPI出題傾向マップ(第二新卒版)
では、第二新卒でよく出題される問題タイプにはどんな傾向があるのでしょうか?ここでは、頻出度や難易度の特徴をまとめた「SPI出題傾向マップ(第二新卒版)」を紹介します。
| 出題領域 | 頻出度 | 難易度の特徴 |
| 表の読み取り | ◎ | 情報量が多く、時間制限が厳しい |
| 推論(YES/NOなど) | ○ | 論理的な読み解きが必要。慣れがモノを言う |
| 言語:文の並び替え | △ | 文章理解力が必要。初見では迷いやすい |
| 確率・割合 | ○ | 一見単純でも、計算手順を工夫する必要あり |
| 性格検査 | ◎ | 対策不足で一貫性に欠けると悪印象に |
とくに表の読み取りと推論系の問題は、第二新卒のSPIでも頻出です。これらは慣れていないと時間切れになりやすいため、早めに問題形式に触れておくことをおすすめします。
また、意外と軽視されがちなのが性格検査です。回答の整合性が取れていなかったり、ネガティブな傾向が強く出てしまったりすると、「組織に馴染みにくい」と判断されるリスクもあります。こちらも慣れが対策のカギです。
今すぐ始められるSPI対策!完全無料のSPI対策早押しクイズ!
SPIの勉強って、なんだか面倒に感じてしまいますよね。
でも「SPI対策早押しクイズ」なら、LINEからすぐに始められるうえに、利用も完全無料!スマホがあれば、通学中でもベッドの中でも、いつでもサクッと対策できます。
まだ始めてないなら、今が始めるチャンスです!まずは今の自分の実力を測ってみましょう。
SPI未対策で落ちる人の共通点とは?
過信・準備不足・軽視が原因
「SPIが出るなんて知らなかった」
「新卒のときに受けたし、もう対策はいらないと思った」
「そもそも筆記で落ちるとは思わなかった」
こうした言葉は、第二新卒の選考でSPIに落ちた人からよく聞かれる声です。共通しているのは、SPIを軽視していたという点です。
中途採用の選考では筆記試験がないことが多いため、第二新卒の方もその感覚で応募してしまい、SPIをノーマークにしてしまうケースが少なくありません。しかし現実には、SPIが選考に含まれており、不合格の理由が「SPIの点数が基準を下回っていたから」という事例が非常に多くあります。
特に落ちる人にありがちなのが以下のパターンです。
- 面接対策にばかり時間をかけて、SPIの準備を後回しにした
- 新卒時代の記憶を頼りに、本番で何とかなると思い込んだ
- テストの案内が来てから慌てて対策を始めた
- 問題の難しさというよりも、時間内に解ききれず途中で終わった
SPIは「時間との戦い」です。問題自体は難解というより処理スピードを問われる設計になっているため、事前に練習していないと、本来の能力を発揮しきれずに終わってしまうことも。
また、性格検査でも「適当に答えたら、矛盾した回答になってしまい不採用になった」といった失敗例もあります。性格検査には嘘を見抜く質問も組み込まれており、一貫性のない回答はマイナス評価になることがあります。
SPIに落ちる人の多くは、「知識がないから落ちる」のではなく、準備していなかったことが最大の敗因になっています。
通過者は何をしている?
では、SPIに合格する人たちはどのような対策をしているのでしょうか?実はそれほど特別なことをしているわけではなく、基本的な対策をきちんと実行しているかどうかが分かれ目になります。
たとえば以下のような取り組みをしている人が多いです。
- SPI模試を最低2回は受けて、時間配分や出題傾向を把握
- スマホアプリを活用して、スキマ時間に頻出問題を繰り返し演習
- Webテスト・テストセンターの両方の形式に一通り触れておく
- 苦手分野を問題集などで集中対策し、「時間内に解く」練習を重視
- 性格検査にも一度は取り組み、設問のパターンに慣れておく
SPIに強い人は、「解けること」よりも「時間内に解き切ること」の重要性を理解しており、それに向けた演習を徹底しています。また、「どの問題にどれくらい時間をかけるか」「どこで見切りをつけるか」といった戦略も本番前に練習しています。
つまり、SPIは地頭の良さよりも、準備の質と量が結果を左右する試験です。
SPI対策チェックリスト
SPI対策を進める中で、よくある悩みが「どこまで対策すれば十分なのかが分からない」というものです。完璧を目指すあまり不安が消えず、何から手をつけるべきか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、SPI対策の進み具合を自己診断できるチェックリストをご用意しました。以下の項目を確認し、どれくらい準備が進んでいるかを把握しましょう。
SPI対策チェックリスト
- □ 出題形式(Webテスト/テストセンターなど)を事前に把握している
- □ スマホアプリまたはWeb模試を2回以上使って演習した
- □ 問題集を1冊以上はやり切って、苦手分野も理解できている
- □ 時間制限つきで演習しており、本番形式の感覚をつかんでいる
- □ 性格検査の設問構造に慣れ、矛盾なく一貫性ある回答ができる
いくつチェックがついたでしょうか?
3つ以上当てはまれば、SPI対策は合格レベルに近づいています。
一方で、1~2項目しかチェックできなかった方は、本番で焦るリスクがあるため、今すぐにでも対策を強化するのがおすすめです。
特に「時間制限つきでの演習」は、SPIの本質であるスピード感への対応に直結するため、軽視してはいけません。また、性格検査も適当に済ませず、事前に一度は取り組んでおくことで違和感のない回答を作ることができます。
SPIは「対策すればするほど点が伸びる」テストです。自信を持って選考に挑むためにも、上記のリストを使って、今の自分の対策レベルを見直してみてください。
第二新卒におすすめのSPI対策法
1冊の問題集+アプリで基本はOK
「SPI対策って、何から始めたらいいの?」「そんなに勉強時間が取れない…」という方も多いと思います。ですが、心配は無用です。SPIの対策は、**“やるべきことを絞って反復する”**ことが非常に効果的です。
まず基本になるのが、市販の問題集1冊をやり切ること。特に定番なのが、『これが本当のSPI3だ!』(洋泉社)や『最新SPI3完全版』(成美堂出版)などのシリーズです。これらは出題範囲を網羅しており、各分野の基礎と問題パターンに慣れるのに非常に適しています。
問題集を進める際は、「全問正解すること」よりも「出題パターンに慣れること」を意識しましょう。同じ問題を何度も解き直すことで、自然と処理スピードが上がっていきます。
さらに、通勤やスキマ時間を活用するにはSPI対策アプリの活用がおすすめです。弊社の「らくらく就活」のSPI対策アプリは、非言語分野(計算・推論など)を重点的に学べる構成になっており、第二新卒でも使いやすい設計になっています。
- 時間制限付きモードで、本番を想定した演習ができる
- ジャンル別演習機能で、苦手分野だけを重点的に練習できる
- 直感的なUI設計で、移動中やスキマ時間にもサクサク使える
- 解説付きの復習機能で、間違えた問題を何度でも学び直せる
「SPIが不安…でも勉強時間があまり取れない」という第二新卒の方にこそ、らくらく就活のSPIアプリは最適です。スマホ一つで始められる手軽さと、出題傾向をおさえた問題構成により、短期間でも実力を効率的に伸ばすことが可能です。

選考対策はやることがたくさん。そのせいでSPI対策は後回しになりがち、、だからこそ時間をかけずにSPI対策しませんか?
「SPI対策早押しクイズ」ならスキマ時間にゲーム感覚でSPIの勉強や模擬テストが可能です!
らくらく就活のLINEを追加するだけで完全無料でご利用いただけますので今すぐSPI対策を始めましょう!
模試→復習→時間制限つきの演習
SPI対策において「やりっぱなし」は最大の落とし穴です。問題を解いたら必ず復習し、間違えた問題を繰り返すことが重要です。
まず、Web上に公開されている無料のSPI模試やアプリの模擬試験機能を活用して、1回模試を受けてみましょう。その際、分野ごとの得点率や、時間内に解けなかった問題をチェックすることが大切です。
模試で見つけた苦手領域(たとえば推論・図表問題など)については、問題集で集中演習を行うのが効果的です。同じタイプの問題を複数解くことで、パターンを頭にインプットできます。
そして最後の仕上げは、本番形式での時間制限つき演習です。SPIは時間との勝負なので、必ずストップウォッチを使って、「この問題は1問につき何秒以内に解くべきか」を体で覚えましょう。
この流れ(模試→復習→時間制限つき演習)を1〜2周繰り返せば、多くの方が安定して7〜8割得点できる状態に到達できます。
「何となく勉強したつもり」では本番に通用しません。戦略的に、弱点をつぶしながら、試験形式に慣れていくことが合格への最短ルートです。
SPI対策スケジュール例(3段階)
SPI対策は「何を」「いつ」「どれくらいやるか」が明確になっていないと、気づけば本番直前になっていた…という事態に陥りがちです。そこで、第二新卒の方が最短2週間で結果を出すための3段階スケジュールをご紹介します。
これは、仕事や日常の予定がある中でも取り組みやすいように設計された、現実的なスケジュールです。目安の期間ごとにやるべきことと達成目標を設定しているので、計画的に対策を進めたい方はぜひ参考にしてください。
| 期間 | やること | 目標 |
| 3日 | ・SPIの全体構成を理解する | ・問題形式に慣れ、苦手分野の目星をつける |
| ・頻出問題をざっと解いてみる | ・1回目の模試を実施して、自分の得点傾向を知る | |
| 7日 | ・問題集を1日1〜2分野ずつ進める | ・分野ごとの特徴と攻略法を理解する |
| ・アプリで反復演習 | ・苦手分野に特化して演習できている状態に | |
| 14日 | ・模試2回目→間違えた問題の復習 | ・安定して7割以上取れる得点力を身につける |
| ・時間制限付きで本番形式の演習を実施 | ・制限時間内に最後まで到達できるようにする |
スケジュールのポイント
1〜3日目:全体把握フェーズ
SPIの出題形式・内容を把握し、「自分は何が苦手なのか?」を見つける時期です。模試を1回受けて傾向を知ることが最重要です。
4〜10日目:集中対策フェーズ
問題集で基礎を固め、アプリでスキマ時間に演習。とにかく手を動かすことが大切です。ここで1冊やり切れれば、自信につながります。
11〜14日目:仕上げフェーズ
2回目の模試を通じて本番力を測ります。苦手分野の最終復習と、時間制限付き演習を行い、本番に近い緊張感を体験しましょう。
このスケジュールはあくまで目安です。時間に余裕がある方は3週間以上かけても構いませんし、逆に「1週間しかない」という方でも、模試+重点復習だけでも効果はあります。
大切なのは、「対策しないまま挑まないこと」です。SPIは短期集中型の学習でも十分成果が出るので、自分のライフスタイルに合わせて柔軟にカスタマイズしてください。
第二新卒×SPIのよくある疑問
SPIについてある程度理解したつもりでも、細かい疑問や不安が残ることはよくあります。特に第二新卒の場合、「新卒とは違うのでは?」「そもそも企業ごとにルールが違いすぎて分からない」と感じる方も多いでしょう。
ここでは、実際に第二新卒からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。ひとつずつ丁寧に解説していくので、疑問の解消に役立ててください。
Q. SPIって何割取れば合格ラインですか?
A. 明確な「合格ライン」は公開されていませんが、7~8割得点できれば、安心ラインと言われています。
SPIは絶対評価ではなく、他の応募者との相対評価でふるい落としに使われることが多いため、目標としては全体の7割以上の得点を安定して出せる状態が理想です。
特にテストセンター方式では、企業によって通過基準が異なるため、「この点数なら絶対通る」というラインはありません。ただし、模試や演習で7~8割を安定して取れていれば、多くの企業で安心して臨めるでしょう。
Q. テストセンターの結果は他社と共有されるんですか?
A. はい。共有設定をすれば、他社にも送信されます。
テストセンターでのSPI受検結果は「スコア送信機能」によって、複数の企業に共有することができます。自分で共有する企業を選ぶ形式なので、「すべての企業に自動で送られる」わけではありません。
ただし、企業によっては独自の基準で扱っている場合もあるため、同じスコアを提出しても合否が分かれることがあります。
Q. 第二新卒でもSPIがない企業ってありますか?
A. あります。中小企業や即戦力重視の企業は、SPIなしで選考するケースも多いです。
たとえば以下のような企業では、SPIを実施しないケースが多く見られます。
- 従業員数が少なく、人物重視の面接を大切にしている企業
- 実務経験を重視していて、筆記試験よりも職歴を評価する企業
- ベンチャー企業やスタートアップなど、スピード採用を行う企業
ただし、「SPIなし=簡単に通る」ではなく、代わりに面接の比重が非常に高くなるので、企業ごとの選考方針をしっかりチェックすることが大切です。
SPIに関する疑問は、選考の過程で突然出てくることも多いです。事前に情報を集め、焦らず落ち着いて対応できるようにしておきましょう。
まとめ
第二新卒の転職活動において、「筆記試験はないだろう」と油断してしまうと、思わぬところでつまずいてしまう可能性があります。なぜなら、第二新卒は中途採用枠でありながら、企業からは新卒に近い存在として見られることが多いため、SPIなどの適性検査が導入されやすいからです。
特に、大手企業・人気企業・制度が整っている会社では、選考効率を高めるためにSPIを活用しており、書類通過後に突然Webテストの案内が届くこともあります。
また、実務経験の浅い第二新卒にとって、SPIは「地頭」や「将来性」を評価される重要なポイントとなり得るのです。
この記事では以下の内容を中心に、第二新卒のSPI対策を徹底解説してきました。
- 第二新卒がSPIを課されやすい理由と選考フローの違い
- SPIが出題される可能性診断チャート
- SPIを実施している代表的な企業リストと傾向
- 出題内容の特徴と第二新卒向け出題傾向マップ
- 対策不足で落ちる人の共通点と、通過者の行動
- 効果的な対策法と、短期集中型のスケジュール例
- よくある疑問へのQ&A
SPIは確かに厄介な選考ステップではありますが、出題傾向が明確で、練習すれば確実に点が伸びるという特徴もあります。つまり、「やるべきことをやれば誰でも通過できるチャンスがある」選考手段なのです。
SPI対策が不安な方も、まずはこの記事で紹介した診断チャートやチェックリストから、自分の状況を見直してみてください。そして、紹介した問題集やアプリを使って、できることから一つずつ取り組んでいきましょう。
しっかり準備をすれば、SPIでつまずくことなく、面接で自分らしさを存分に発揮できるはずです。
あなたの第二新卒転職が、納得のいく一歩となることを願っています。