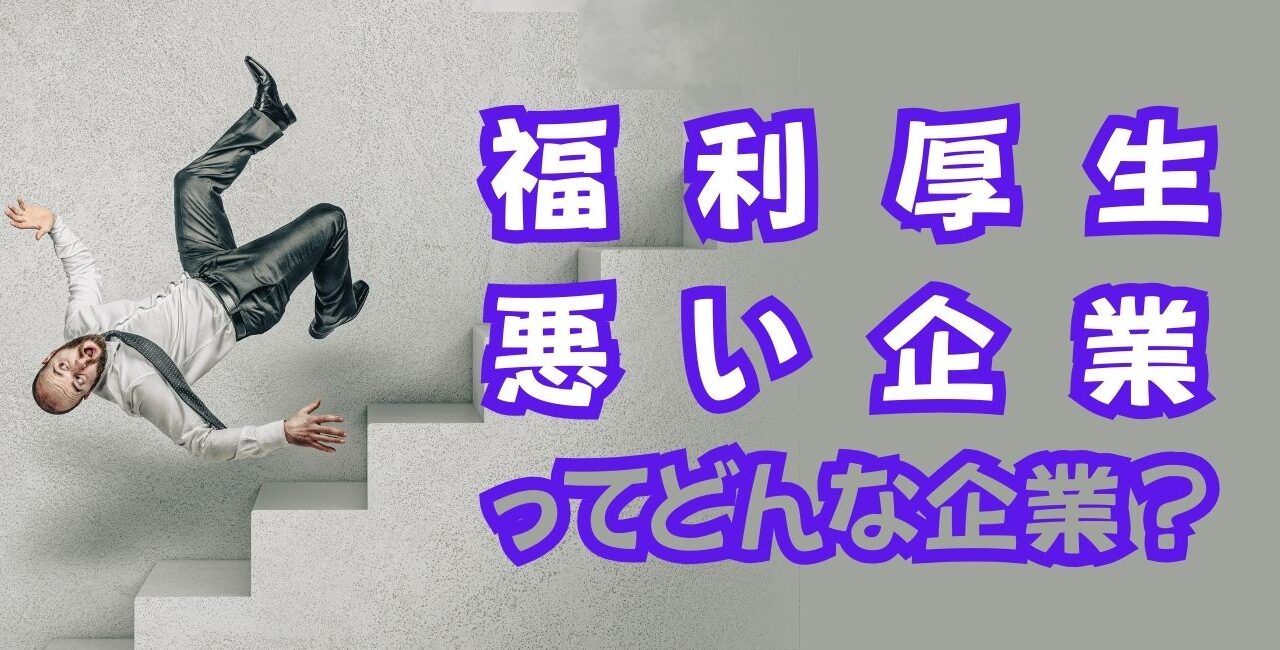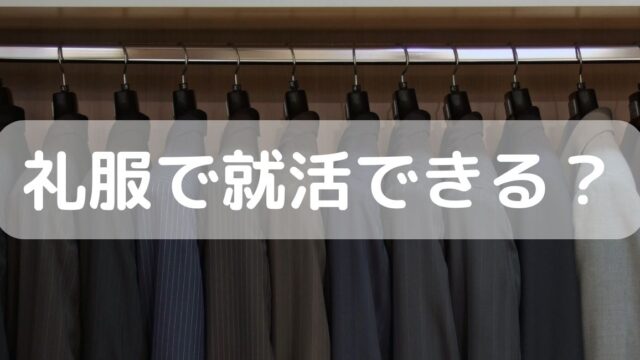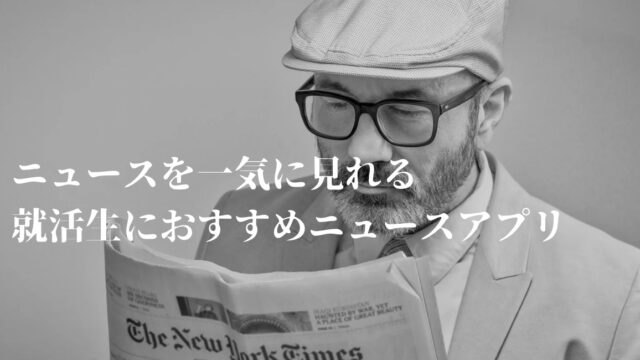【既卒・第二新卒の方もご利用いただけます】
①SPI対策早押しクイズ
絶対に対策しておきたいSPIの予想問題2000問を収録!
②ES自動作成ツール
質問に答えるだけで、誰でも受かるESが作れます!
③ES自動添削ツール
コピペした文章をAIが添削して、受かる文章に作り直します!
【27卒就活を始めたばかりの人におすすめ】
①AI自己分析ツール
準備不要!たったの3分3ステップで自己分析ができます!
②AI適職診断ツール
あなたにピッタリの職業が知れる診断です!
就活をしていると、企業選びの軸として「給与」「仕事内容」「勤務地」など、さまざまなポイントが出てきます。中でも「福利厚生」を気にする人は多いのではないでしょうか。
でも企業ごとに異なる福利厚生を見分けるのは意外と難しく、
「どうせどこも似たようなものでは?」
「福利厚生って、家賃補助とかジムの割引とかでしょ?」
などとふわっとした理解のまま就職先を選ぶ人も少なくありません。でも、実は福利厚生は働くうえでとても重要なポイントであり、企業によって差がとても大きい部分でもあります。特に、新卒で入社する企業の福利厚生がどうなっているかは、入社後の生活や将来のキャリアに大きな影響を与える可能性があります。
そこで本記事では、福利厚生の基本から、実際に福利厚生が悪い会社に入ってしまった場合のリスク、さらには就活中に見抜くためのポイントまで、学生目線でわかりやすく解説していきます。
そもそも福利厚生とは
まずは、そもそも「福利厚生」とは何かをしっかり理解しておきましょう。
福利厚生とは、企業が給与以外に提供する“従業員の生活を支える制度やサービス”のことを指します。たとえば、以下のようなものが代表的です。
- 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険など)
- 有給休暇制度
- 通勤手当や住宅手当
- 社宅や社員寮
- 食堂・昼食補助
- 産休・育休制度
- 健康診断やメンタルケア制度
- 退職金制度
法定福利厚生
これは法律で企業に義務づけられているものです。たとえば、健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険などが含まれます。企業はこれらを必ず用意しなければならず、最低限の生活保障に関わる重要な制度です。
法定外福利厚生
一方で、住宅手当や社員食堂、レジャー施設の利用補助などは企業が任意で提供するものです。これらは企業ごとの方針や経営状況により差が大きく、「働きやすさ」や「社員への思いやり」が表れる部分でもあります。
最近では「働き方改革」の流れもあり、柔軟な働き方やメンタルヘルスケアに関する福利厚生が重視されつつあります。また、ライフステージに合わせて選べる福利厚生を導入している企業も増えてきました。
とはいえ、すべての企業が手厚い制度を用意しているわけではありません。中には、法定福利厚生さえ不十分な会社や、制度が形だけになっている会社も存在します。
福利厚生が悪い会社に入社するとどうなる?
では、もし福利厚生が悪い会社に入ってしまったら、どんなことが起きるのでしょうか。ここでは、その具体的な影響を紹介します。
経済的・精神的な負担が増える
まず一番大きいのはお金の問題です。たとえば住宅手当や通勤手当がない会社に入ると、家賃や交通費がすべて自己負担になります。都市圏に住む場合は、それだけでひと月に使える金額に数万円の差が出ることもあるでしょう。
また、健康診断やメンタルケアの制度がないと、体調を崩したときの対応が遅れたり、精神的な不調を抱えても相談できなかったりします。そうした積み重ねがストレスや不安を増やし、結果的に「この会社にいて大丈夫かな…」という気持ちになってしまうことも考えられます。
仕事とプライベートのバランスが崩れる
福利厚生がしっかりしている会社では、有給休暇の取得が推奨されていたり、産休・育休の取得実績があったりします。反対に、福利厚生が悪い会社では休みを取りづらい空気が蔓延していることも。
例えば有給はあるけど誰も取ってないような職場では、旅行や家族との時間、自分の趣味の時間などを確保するのが難しいかもしれません。長期的に見ると、プライベートの充実度が下がり、仕事のパフォーマンスやモチベーションにも影響するでしょう。
キャリアにマイナスの影響が出ることも
また、産休・育休が取りにくかったり、退職金制度が整っていなかったりすると、将来のライフプランやキャリア形成にも支障が出てきます。例えば、将来子育てをしながら働きたいと考えている人にとって、育休後の復帰がスムーズにいかない職場は大きなリスクになります。
また、資格取得支援や書籍購入補助などスキルアップの環境が整っていないと、若手でたくさん経験を積むタイミングで十分に経験を積めず、昇進や転職のタイミングでもブレーキがかかってしまうこともあるかもしれません。
福利厚生が不十分な企業は、単に「ちょっと不便」なだけでなく、経済的な負担や精神的ストレス、キャリアへの悪影響など、多方面にリスクが及びます。入社前にしっかりと見極める力が求められる理由は、まさにここにあります。
こんな会社は要注意!福利厚生が悪い企業の例
ここからは、実際に「福利厚生が悪い」と言われる企業がどのような特徴を持っているのか、いくつかのパターンに分けて具体的に紹介していきます。ひとつひとつは小さなことに見えるかもしれませんが、これらが複数組み合わさると、働くうえで大きな問題に発展する可能性があります。
法定福利厚生すら不十分(社会保険・有給取得など)
最も危険なのが、法律で定められた「法定福利厚生」さえもきちんと整っていない会社です。
たとえば、
- 社会保険に加入していない
- 雇用保険・労災保険が未加入
- 有給休暇を与えていない、使わせない、自分で決められない
といったケースが当てはまります。
社会保険未加入だと、病気やけが、老後の保障が極端に不十分になります。さらに有給が取れない職場では、体調不良のときも無理して働くしかなく、働き続けるうちに体を壊してしまうことも。
こうした会社は法令違反の可能性も高いため、早い段階で見極めて避ける必要があります。
通勤手当がない・極端に低い
通勤手当についても、月に数千円から1万円以上の交通費がかかることもあり、全額支給かどうかで手取りに大きな差が出ます。
「通勤手当がまったくない」「一律で月5千円しか出ない」「自転車通勤は対象外」などとなっている企業は、生活面での負担が大きくなりがちです。
残業代が支払われないorみなし残業が常態化
「うちは固定残業代(みなし残業)制度だから」と言われた場合、その内容には要注意です。
本来、残業をした分は時間外労働としてきちんと支払われるべきですが、
- みなし残業時間を大幅に超えても超過分の残業代が支払われない
- 残業自体が常態化していて月60時間超え
といったケースもあります。
制度として存在していても、現場ではサービス残業が横行していることもあるため、実態に目を向けることが大切です。
産休・育休が取りにくいor制度が形骸化
男女問わず重要なのが、ライフイベントへのサポートです。結婚・出産・育児といった節目で仕事を続けやすい環境かどうかは、長く働くうえで見逃せないポイントです。
しかし中には、
- 育休はあるが取得実績ゼロ
- 上司が育休取得を嫌がる雰囲気
- 職場復帰後にキャリアダウンするケースが多い
といったように、「制度はあるけど使いづらい」「取得すると不利益を受ける」企業も存在します。
これでは、将来的に仕事と家庭の両立を目指すことが難しくなってしまいます。
退職金制度がない、または形だけの制度
退職金は将来の備えの一部です。多くの大手企業では、長く働いた人が安心して退職できるように、退職金制度を整えています。
しかし転職が普及した近年、退職金制度を整備していない企業が増加傾向にあります。
そのため、
- 退職金制度がまったく存在しない
- 勤続20年以上でないと受け取れない
- 会社の業績で変動し、確実にもらえない
といったケースもあるほどです。
短期間での転職を考えている人には影響が少ないかもしれませんが、1社で長く働きたいと考えている人にとっては非常に重要な要素のため、退職金の有無は要チェックです。
福利厚生をアピールするが、実際には使えない
最後に気をつけたいのが「見せかけだけの福利厚生」です。
たとえば、
- 有給はあるが忙しいから取れない空気
- ジムや映画の割引券があるが、対象施設が限られていて使いづらい
- 社員食堂があるが、使えるのは特定の部署だけ
など、表向き充実しているように見えても、実際には使えないものばかりというケースもあります。
こうした形だけの福利厚生がある企業には注意が必要です。
では、こうした会社を就活中にどうやって見抜けばよいのでしょうか?
次の章では、福利厚生の実態を事前に見極めるための具体的なポイントを解説します。
福利厚生が悪い会社を事前に見抜くポイント
「福利厚生が大事なのはわかったけど、就活中にそんな細かいところまで見抜けるの?」
そんな不安を持つ方も多いと思います。ですが、実はちょっとしたコツを知っていれば、求人票や企業説明会などから福利厚生が悪い会社をある程度見分けることが可能です。
ここでは、就活中にできる具体的なチェックポイントを3つ紹介します。
求人票・企業HPの福利厚生欄をチェック
まず注目したいのが、求人票や企業ホームページの福利厚生欄です。ここを見ると、最低限どんな制度があるかがわかります。
チェックするときのポイントは以下の通りです。
- 社会保険完備と明記されているか
→「完備」の表記がない場合、加入義務のある保険に未加入の可能性も - 住宅手当・通勤手当が記載されているか
→記載がなければ支給なしの可能性が高い - 制度の具体性があるかどうか
→「各種福利厚生あり」など抽象的な表現ばかりだと注意が必要 - 独自制度の有無
→「資格取得支援」や「育児支援」「時短勤務」など、働く人をサポートする姿勢がある企業は、制度の幅も広い
口コミサイトやSNSでの評判をチェック
求人票やHPだけでは見えてこない福利厚生の実態を知るには、口コミサイトやSNSの活用が有効です。
たとえば、
- ・OpenWork
- ・転職会議
- ・エンゲージ会社の評判(旧ライトハウス)
などの口コミサイトでは、実際に働いていた(いる)人のリアルな声が投稿されています。
また口コミサイトを確認する際は以下のような点に注目するとよいでしょう。
- 「有給は取りやすいか?」
- 「育休を取った人が復職できているか?」
- 「退職理由に“福利厚生が不満”があるか?」
もちろん、すべての口コミをうのみにするのはNGですが、一定の傾向が見えると判断材料になります。
また、TwitterやYouTubeなどで「会社名+ブラック」「会社名+福利厚生」で検索してみると、実際の社員のつぶやきや告白動画が出てくることもあります。中には誇張もありますが、参考情報として見ておく価値はあります。
面接や説明会で「福利厚生の実態」を質問するコツ
企業の本音を引き出す場として見逃せないのが、説明会や面接の質問タイムです。ここでは、「制度はあるけど、実際に使えるのか?」を確かめる質問が効果的です。
以下のような質問が参考になります。
「育休制度について伺いたいのですが、実際に取得された社員の方はいらっしゃいますか?」
「有給休暇の平均取得日数を教えていただけますか?」
「住宅手当はどのような条件で支給されていますか?」
「退職金制度はありますか?実際に退職された方への支給実績も知りたいです」
「福利厚生ありますか?」といった漠然とした質問ではなく、「実績」や「条件」を聞くことで、よりリアルな情報を引き出すことができます。
説明会の雰囲気や、社員の受け答えに違和感がある場合も、企業体質を見極める手がかりになります。制度について聞いたときに曖昧な回答しか返ってこなかったり、はぐらかされたりする場合は、注意した方がいいかもしれません。
「福利厚生が悪い」だけで判断するのは危険
ここまで、「福利厚生の重要性」や「福利厚生が悪い企業の見分け方」について解説してきましたが、最後に大切なことをお伝えします。それは、「福利厚生が悪い=絶対にNGな会社」とは限らないということです。
もちろん、最低限の法定福利厚生が整っていない企業は避けるべきですが、法定外の福利厚生が少ない、あるいは制度がシンプルだからといって、必ずしも「悪い会社」「入社する価値がない会社」とは限りません。
福利厚生以外の面が優れている場合がある
たとえば、住宅手当やジム補助などがない代わりに、下記のような魅力がある会社も存在します。
- 年収が高めに設定されている
- 圧倒的にスキルアップできる環境がある
- 自分の希望する業界や職種に特化したキャリアパスが描ける
- 風通しがよく、裁量が大きい社風
こうした企業は、福利厚生のコストを抑える代わりに、成長環境や給与など、別の形で社員に還元しているケースがあります。特にスタートアップ企業などではこの傾向が強く、福利厚生よりもスピード感や経験値を重視している場合も多いです。
理想のキャリアと相性ぴったりの可能性もある
就活は、「自分の理想のキャリア」にどれだけマッチしているかが非常に重要です。たとえば将来的に独立したいと考えている人にとっては、福利厚生よりもスキルが磨ける環境の方が価値が高いかもしれません。
また、若いうちは体力があるからこそ、少々ハードでも経験を積める職場を選びたいという人もいるでしょう。福利厚生に甘えるより、自分を鍛えたいという人にとっては、手厚さより内容の濃さを選ぶのも一つの戦略です。
ただし、それでも法定福利厚生が確保されていることは大前提です。そのラインを下回る企業を選んでしまうと、どんなに意欲があっても続かなくなってしまいます。
自分にとって何が「大事」かを考えることが大切
結局のところ、福利厚生をどう評価するかは「何を大切にして働きたいか」によって変わります。
- 家族との時間を大切にしたい人
- 健康面を気にしている人
- 金銭的な安定を求める人
- ワークライフバランス重視の人
それぞれにとって必要な福利厚生の中身は異なります。だからこそ、制度の数や豪華さではなく、自分の価値観や将来像に合っているかどうかで判断することが大切です。
まとめ
ここまで読んできたあなたは、「福利厚生=なんとなくあればラッキー」ではなく、「働く環境や人生に直結する重要な要素」だということがわかってきたはずです。
どんな福利厚生がいいかという正解はありません。
大切なのは、「どんな環境で働きたいのか」「どんな人生を送りたいのか」を自分自身で考え、その軸に合った企業を選ぶことです。
福利厚生は、その判断を助けてくれるヒントのひとつ。
制度の有無だけでなく、その背景にある企業の姿勢まで見抜けるようになれば、あなたの就活は確実に一歩前に進みます。
焦らず、自分に合った会社をじっくり見つけていきましょう。